風の学校の総括合宿に参加、若者たちの語り合いに、
昆吉則氏の「耕すは蒔(ま)く為に非ず」に関する考察を思い出した。
【「農業経営者編集長 昆 吉則 -profile 】
スガノ農機の総合カタログには、同社の企業理念である
「積年良土」ととともに
「耕すは種蒔(ま)く為に非ず」という禅問答ようなコピーが添えられてある。
僕は優れた経営者の生き様にふれる度に、この「耕すは種蒔く為に非ず」という句をいつも思い出す。
「広辞苑」で「耕す(たがやす)」の項をひくと(タガヘスの転)作物を植える準備として、
田畑を掘り返す」と解説がしてある。
漢和辞典で、漢字の「耕」の辞義をたどると「耕」の「すきへん」は「耒(ライ・すき)=鋤・耡・耜」に由来する。
そして、スキの作業目的である「土の反転」から「田返す(たがえす)」が「田返す」ことであるとされている。
ロータリ耕が一般化する以前の耕し方を思いおこせば、鍬であれ鋤であれ反転耕なのだから当然かもしれない。
しかし「がやす」という言葉に、次の様な意味を感じている、これは僕の「こじつけ」に過ぎないだろうか。
漢字の「耕」の意味はともかく、そもそも外国語である漢など知らぬはずの普通の人、
あるいは漢字伝来以前の日本人が「たがやす」あるいは「たがえす」の音を発していたのだとしたら、
それは「田を返す」ではなく「田へ返す」ことの意味ではないか。
「たがやす」は、
本来、田(土)から取り出したものは「田に返す」「土へ戻す」という
「農業の方法」を言い表した言葉なのであり、
「作業の方法」としての「田を返す」ではない。
言い換えれば「作業」や「技術」用語としての「田を返す」ではなく、
「喰い続ける方法」「き延びる方法」いうなれば「経営」の問題として「田へ返す」「土へ返せ」
そして「戻し続けよ」と語られてきたのではあるまいか。
農具の歴史からみても、スキやクワのレベまでに土壌の反転性が高い農具が使われる以前から、
人々が「たがやす」という言葉を使っていたのだとしたら、むしろそう考える方が自然だし矛盾も無い。
今ですら鋤を使っていた年配の人なら、土地それぞれの言葉があるが「スク」とか「起こす」とかいうのが普通であり、
「耕起」を意味する日常語として「耕す」なんて言葉は使わない。
昔から日本人にとって「たがやす」とは、「田を返す」ということでも、
ただ単に「作物を植える準備として、田畑を掘り返す」ことでもなく、
農業の基本原としての田から得たものを「田へ返す」「戻し続けよ」「循環を守れ」を意味る言葉であったのだと僕は思う。
人の思い通りにならない圧倒的な力をもつ自然。
その中で、継続的に安して生きる糧を得ていく農業という「自然を管理する方法」。
その基本原則が「循環を守る」ことあり「戻し続ける」ことであるからだ。
人が喰っていくことと同じ意味であったはずの「耕すこと」の本質として、
「田へ返せ」と語られていたのではないだろうか。
「喰うこと」とは「戻すこと」であったのだ。
話は変わるが、作ることに夢中になると、なぜ作るかを問わなくなり、
売ることに夢中にるとナゼ売るかを問わなくなる。
製造部長なら、営業部長なら、それで済むかもしれない。
しかし貴方は経営者なのだ。それでは足りないのだ。
いつの間に、我々は、春に始まり秋に終わる一連の作業の流れとしてしか農業が見えず、
そ作業消化に追われ様々に発生する障害への対症療法的な対策ばかりに気を取られ、
また当面の売上や利益の大小にばかり目を奪われてはいないだろうか。
「技術」や売上」あるいは「単なる帳簿面の利益や費用」や個々の作業という木にとらわれて
「経営」という森が見えなくなっているということはないだろうか。
「耕す」ということが、種まきや田植えの準備作業としてしか考えられなくなっているのではないだろうか。
むしろ、収穫に次の始まりを感じることができるだろうか。
我々はあらためて「耕す」を技術の問題として「田を返す」だけでなく、
経営の問題として「田へ返す」につながっているかを問うことが必要なのではないか。
そして、僕が行き会えた優れた経営者たちの践とは、
常に「戻し続け」「し続ける」という農業の原則を守ることであり、その「意志」を持ち続けることであった。
農業経営者だけでなく優れた仕事を成したあらゆる事業経営者たちもまた、
その規模の大小を問わず同じことを語る。
土を離れた事業者にとっての「土」とは顧客であり、市場であり、そして取引先であった。
それらの人々は、「田へ返す」「土へ戻」それも「取る前に戻す」ことを考えている。
「戻せなのは欲が足りないのだよ」という人もいた。もっとも、戻しても成功の保証などはない。
それでも戻す人が成功者たりえるのであり、戻せぬ者はやがて滅びるのだと僕は思う。
「耕すは種蒔く為に非ず」とカタログに謳うスガノという企業の経営と営業活動も、
この「へ返す」の精神なのあろう。
そして、この精神には、農業も他の産業も仕事の違いもなく、また人の一生もまた同じなのではないか。
 晴耕雨読人類往来記
晴耕雨読人類往来記




















































 1999年に立ち上げられた見沼田んぼ福祉農園は、間もなく開園10年を迎える。
1999年に立ち上げられた見沼田んぼ福祉農園は、間もなく開園10年を迎える。




























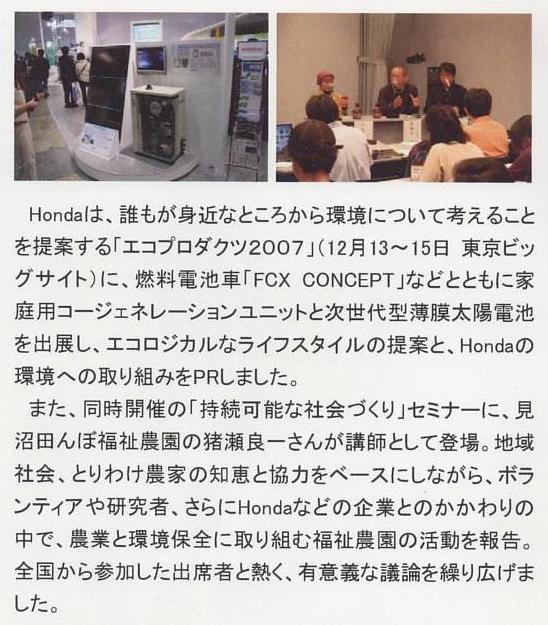













 見沼たんぼ
見沼たんぼ











































