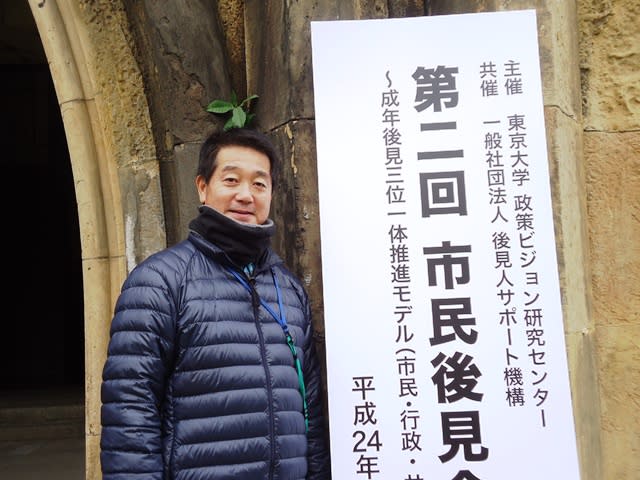2013年2月5日(火)
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェの更新研修が開催されました。
13時~15時は、「八王子市における高齢者支援の取組み」についてでした。
講師は、八王子市健康福祉部 高齢者支援課 相談担当主査の方と八王子市社会福祉協議会の方でした。
成年後見支援事業として、市長申立ての際の後見報酬の助成もされているとのことです。
平成21年に独自で市民後見人養成講座を実施。
平成22年度 登録者10名は、フォローアップ研修と地域福祉権利擁護事業の生活者支援員として活動。
平成24年2月1日 法人後見監督事業の実施要領を制定。
また、平成24年4月から市民後見人が認知症高齢者の成年後見として現在4名の方が受任し、社協が法人後見監督(弁護士がアドバーザー)をしているとのことです。
平成26年度からは、現在東京都が行っている市民後見人養成講座が、各区市町村で実施予定となっているとのことです。
ワンストップサービスとして、高齢者安心相談センターの立ち上げも考えておられるようです。
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェの更新研修が開催されました。
13時~15時は、「八王子市における高齢者支援の取組み」についてでした。
講師は、八王子市健康福祉部 高齢者支援課 相談担当主査の方と八王子市社会福祉協議会の方でした。
成年後見支援事業として、市長申立ての際の後見報酬の助成もされているとのことです。
平成21年に独自で市民後見人養成講座を実施。
平成22年度 登録者10名は、フォローアップ研修と地域福祉権利擁護事業の生活者支援員として活動。
平成24年2月1日 法人後見監督事業の実施要領を制定。
また、平成24年4月から市民後見人が認知症高齢者の成年後見として現在4名の方が受任し、社協が法人後見監督(弁護士がアドバーザー)をしているとのことです。
平成26年度からは、現在東京都が行っている市民後見人養成講座が、各区市町村で実施予定となっているとのことです。
ワンストップサービスとして、高齢者安心相談センターの立ち上げも考えておられるようです。