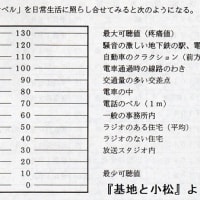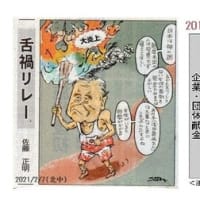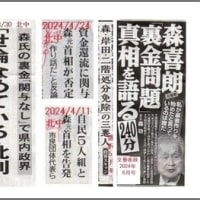福島原発事故と昆虫の被曝について
ヤマトシジミとは
私は、ここ数年住居地周辺の街路樹(アメリカ楓、ニワウルシなど)に大量発生しているアメリカシロヒトリの調査をおこなってきたが、福島原発事故後に原発周辺地域のアメシロの生態に何等かの変化があるのだろうかと思いつつ、インターネット検索で調べているなかで、大瀧研究室のヤマトシジミ研究を知ることとなった。
ヤマトシジミは沖縄から東北にかけて生息し、幼虫は都市部や農村部に広く繁殖するカタバミの葉を食べて成長する。幼虫は10ミリほどで、たっぷりとカタバミを食べて、サナギになり(蛹化)、成虫(蝶)になる。前翅は10~16ミリほどの小さなチョウである。
2011年3月12日に原発事故が起き、ヤマトシジミは幼虫の状態で、地表上で越冬しており、外部からはもちろん、食物により内部からも人工放射線に被曝した。
大瀧研究室は福島原発メルトダウン・爆発後の5月に現地に赴き、ヤマトシジミを採取して、放射能の昆虫に与える影響についての調査を始めた。
大瀧研究室のホームページにはこれまでに発表された研究論文(英文と日本語)が添付されている。第1、福島原発事故のヤマトシジミへの生態学的影響(2012.8.9)、第2、福島原発事故とヤマトシジミ:長期低線量被曝の生物学的影響評価(2013.8.12)、第3、ヤマトシジミにおける放射性物質摂取の生態学的影響(2014.5.15)、第4、原発事故の生物への影響をチョウで調査する(2014.8.30)、第5、ヤマトシジミにおける二世代にわたる放射能汚染食物の摂取(2014.9.23)、第6、ヤマトシジミにおける異常率の時空間的な動態:福島原発事故後3年間のモニタリング調査(2015.2.10日本語訳なし)の6論文である。その他に、『科学』(岩波書店)2014年9月号の大瀧丈二論文「原発事故の生物への影響をチョウで調査する」がある。
ここでは主として、第1論文、第2論文、『科学』誌論文を参考にして、原発事故による昆虫への影響についてレポートする。
第1論文の研究結果
2012年8月に発表した最初の第1論文では、次の8項目を結論している。
①福島現地で採取したヤマトシジミ(P世代)には、色模様、付属肢、触角、パルピ=鼻、複眼、腹部、胸部の形態異常が確認された。5月の採取地点では地面線量と相関関係はなかったが、9月は地面線量と成虫異常率には高い相関関係があった。
②雄の前翅サイズは他地域より小さく、地面線量と高い相関関係があった。
③採取したヤマトシジミ(P世代)の成虫異常率は5月よりも9月の方が高かった。
④現地で採取した雌の子世代(F1)にもさまざまな異常が観察され、原発に近いほど異常率は高かった。
⑤福島原発の近くで採取したヤマトシジミのF1世代には蛹化、羽化までの育成時間が遅延する傾向があった。
⑥F1世代には不妊化、生殖腺異常が見られ、F2世代(孫世代)に形態異常の遺伝が観察された。
⑦沖縄産のヤマトシジミにセシウム137を照射したところ、線量に応じて生存率が低下した。
⑧沖縄産ヤマトシジミに福島原発事故で汚染したカタバミを食べさせたら、生存率が低下した。
以上の結果と内部被曝実験により、大瀧研究室は福島原発から放出された人工放射線により個体の体細胞及び生殖細胞に生理的又は遺伝的損傷が生じたと結論している。
疑問と批判に反論
各界から第1論文にたいする批判があり、2013年8月に、11点について反論した第2論文が発表された。反論の中により深い内容があり、非常に難解な内容だが、誤解を恐れず要約する。
①「ヤマトシジミに環境指標生物及び実験動物としての適合性はあるか」という問いにたいして、大瀧研究室はヤマトシジミはカタバミだけを食べる昆虫で、沖縄から東北まで広範に生息し、成虫の寿命は1週間程度で、分散する距離は限定している。幼虫も成虫も地面に近いところで過ごすので、原発事故で拡散・降下した放射性物質の影響を受けやすいなどの理由を挙げて、環境指標生物として適当であると答えている。
②「緯度に依存した前翅サイズの縮小」ではないかという問いにたいして、大瀧研究室は福島より北方に位置する白石市のサンプル数が少なかったので、除外して統計を取ったことが誤解を招いた。あらためて白石市の結果を加えて結論を見ると、福島市の前翅サイズは北方、南方のヤマトシジミよりも小さかった。
③「環境温度の低下が幼虫期間を遅延させたのではないか」という問いにたいして、大瀧研究室は福島よりも北方にある白石市で採取したサンプルよりも、南方にある福島のサンプルの方が遅延傾向が強いこと、また福島原発のある緯度付近が最も高いピークを示していることから、環境温度の影響ではなく、放射性物質の影響の可能性が強いと結論づけている。
④「前翅の色模様の異常出現は気温変化によるのではないか」という問いにたいして、大瀧研究室は、ヤマトシジミの最北限青森県深浦町で、2000年から05年にかけて温度ショック型の色模様変化の報告があるが、他の異常を伴っていない。福島の場合は変化に多様性があり、他の異常を伴っており、病的である。遺伝子の変異による色模様変化の可能性が強いと反論している。
⑤「異常率や成長期間の違いは事故以前から存在する地域差に由来するのではないか」という問いにたいして、大瀧研究室は色模様異常以外の異常は生存上致命的な弱点となり、適応度が低くて、子孫を残せないだろう。福島でヤマトシジミがこのような弱点を抱えたまま何十年も生存してきたとは考えられない。福島のヤマトシジミは個体群レベルでの崩壊が起こりつつあるのではないか。2011年9月の福島の異常率は38.5%であり、地面線量と異常率には高い相関関係がある。1979年から2009年にかけて、福島県内で採取した9個のヤマトシジミの色模様はすべて正常であった。
⑥「バックグラウンドの数値が高いために放射線の影響を評価できない」という指摘にたいして、大瀧研究室は第1論文でこの点を議論しなかったことを率直に認めた上で、5月の異常率と9月の異常率を比較すると、有意な差が認められ、室内飼育による異常発生以外の要因が影響されていると考えられ、その要因として放射線による生殖細胞への損傷を想定するのが最も合理的であると答えている。
また、原発事故当時、ヤマトシジミの精子は成熟期にあり、生殖細胞は未分化の状態にあり、放射線感受性が強く、その精子と卵子が遺伝的な異常を生じたまま接合すれば、子孫世代においてさまざまな疾患を生じ、それはP(親世代)よりもF1(子世代)、F2(孫世代)の方が深刻な状態であったとも答えている。
⑦「放射線によりランダムに突然変異が生じた場合、異常が偏らないはず」という批判があるが、これにたいして大瀧研究室はランダムな突然変異作出実験でも、ランダムな異常形質を得ることは不可能であり、表現型が偏ることは一般的であると答えている。
⑧「サンプリング地点の津波の影響」の疑いについては、大瀧研究室はサンプリング地点は海岸よりはるか内陸にあり、津波による影響はないと答えている。
⑨「サンプル数やサンプリング地点が少ないから、結論を導くには不十分である」との主張にたいして、大瀧研究室は5月採取数は144個体、9月採取数は238個体、実験では5942個体を使っており、サンプル数としては十分である。さらなる研究のためには、サンプリング地点と数の増加、継続したモニタリングが必要である。
⑩「福島と沖縄の飼育環境の相違が幼虫の不健全な成育になったのではないか」との批判にたいして、大瀧研究室は実験群・対照群に標準環境(26±1℃)下で、飼育コンテナを清掃し、新鮮な食草を与えたとしている。福島と沖縄の気温の差はヤマトシジミに悪影響を与えるほどの差ではないと反論した。
⑪「昆虫は放射線に高い抵抗性をもつから、実験結果は信頼できない」という批判にたいして、大瀧研究室は従来の実験は短時間かつ高線量照射だが、長期間かつ低線量照射の結果であり、実験手法を無視した批判であると反論している。また、過去には、非汚染地域の生物に汚染地域産のエサを与えるという内部被曝実験はおこなわれていない。
『科学』に発表された大瀧論文
第1、第2論文は2011年秋までの調査結果の分析であり、2015年2月に発表された直近の第6論文の案内文と『科学』(岩波書店)2014年9月号に発表された大瀧論文「原発事故の生物への影響をチョウで調査する」によって、2013年までの調査結果を知ることができる。
大瀧研究室は福島市、本宮市、広野町、いわき市、高萩市、水戸市、つくば市で2011年から13年にかけて、3年間の春と秋、合計6回の調査をおこなっている。放射線汚染地域では、ヤマトシジミの総異常率は2011年秋から2012年春にピークに達した。ヤマトシジミの世代時間(卵→幼虫→蛹→蝶)は1カ月程度で、6世代後にピークを迎えたことになり、昆虫への影響をそのまま人間に当てはめることはできないにしても、人間の1世代を25年とすれば150年に相当する。
ヤマトシジミの異常率は2011年9月をピークにして減少し、15世代ほど経過した2013年7月時点で、放射線環境に適応できるようになったと考えられる。人間の15世代後といえば375年後であり、そんな遠い遠い先になってやっと原発事故による環境変化に適応できることになる。
全原発を廃炉に
「北海道新聞」(2012.8.16)によれば、同様の研究は北海道大学の秋元研究室でもおこなわれている。2012年6月に、福島原発から32キロ離れた計画的避難地区でおこなわれた調査で、ワタムシ(アブラムシの一種)の成育に異常がでているという。通常、奇形の発生率は1%未満であるが、原発周辺では約1割に達している。
昆虫は放射線だけではなく、いろいろなストレスに強い生き物である。だからこそ、地球上で最も繁栄しているのである。ある個体だけなら殺虫剤で殺すことはできるが、耐性をもつ個体が生まれるから、その種を根絶することは難しい。
私が観察しているアメリカシロヒトリも同様である。1945年にアメシロが日本に上陸し、70年後の今、北限の北海道南部にまで広がっている。街路樹や果樹に被害をもたらすので、各自治体は薬剤散布をくりかえしてきたが、どの地域でも、例外なく根絶に成功していない。このように昆虫は環境への適応能力が高いが、はたして福島原発由来の放射線にさらされた人間はどうであろうか。
原発事故由来の放射線によって、ヤマトシジミのある個体は死に、ある個体は生きのび、耐性を形成している。政治家や科学者もどきが「人への被曝量の安全基準」を一律に決めているが、各個人の放射線耐性度や健康度によって安全基準は異なるから、各個人の多様な耐性度や価値観を尊重して決めるべきであろう。
ふたたび原発事故を繰り返さないために、すべての原発の廃炉を決定し、廃炉作業に取りかからねばならない。
ヤマトシジミとは
私は、ここ数年住居地周辺の街路樹(アメリカ楓、ニワウルシなど)に大量発生しているアメリカシロヒトリの調査をおこなってきたが、福島原発事故後に原発周辺地域のアメシロの生態に何等かの変化があるのだろうかと思いつつ、インターネット検索で調べているなかで、大瀧研究室のヤマトシジミ研究を知ることとなった。
ヤマトシジミは沖縄から東北にかけて生息し、幼虫は都市部や農村部に広く繁殖するカタバミの葉を食べて成長する。幼虫は10ミリほどで、たっぷりとカタバミを食べて、サナギになり(蛹化)、成虫(蝶)になる。前翅は10~16ミリほどの小さなチョウである。
2011年3月12日に原発事故が起き、ヤマトシジミは幼虫の状態で、地表上で越冬しており、外部からはもちろん、食物により内部からも人工放射線に被曝した。
大瀧研究室は福島原発メルトダウン・爆発後の5月に現地に赴き、ヤマトシジミを採取して、放射能の昆虫に与える影響についての調査を始めた。
大瀧研究室のホームページにはこれまでに発表された研究論文(英文と日本語)が添付されている。第1、福島原発事故のヤマトシジミへの生態学的影響(2012.8.9)、第2、福島原発事故とヤマトシジミ:長期低線量被曝の生物学的影響評価(2013.8.12)、第3、ヤマトシジミにおける放射性物質摂取の生態学的影響(2014.5.15)、第4、原発事故の生物への影響をチョウで調査する(2014.8.30)、第5、ヤマトシジミにおける二世代にわたる放射能汚染食物の摂取(2014.9.23)、第6、ヤマトシジミにおける異常率の時空間的な動態:福島原発事故後3年間のモニタリング調査(2015.2.10日本語訳なし)の6論文である。その他に、『科学』(岩波書店)2014年9月号の大瀧丈二論文「原発事故の生物への影響をチョウで調査する」がある。
ここでは主として、第1論文、第2論文、『科学』誌論文を参考にして、原発事故による昆虫への影響についてレポートする。
第1論文の研究結果
2012年8月に発表した最初の第1論文では、次の8項目を結論している。
①福島現地で採取したヤマトシジミ(P世代)には、色模様、付属肢、触角、パルピ=鼻、複眼、腹部、胸部の形態異常が確認された。5月の採取地点では地面線量と相関関係はなかったが、9月は地面線量と成虫異常率には高い相関関係があった。
②雄の前翅サイズは他地域より小さく、地面線量と高い相関関係があった。
③採取したヤマトシジミ(P世代)の成虫異常率は5月よりも9月の方が高かった。
④現地で採取した雌の子世代(F1)にもさまざまな異常が観察され、原発に近いほど異常率は高かった。
⑤福島原発の近くで採取したヤマトシジミのF1世代には蛹化、羽化までの育成時間が遅延する傾向があった。
⑥F1世代には不妊化、生殖腺異常が見られ、F2世代(孫世代)に形態異常の遺伝が観察された。
⑦沖縄産のヤマトシジミにセシウム137を照射したところ、線量に応じて生存率が低下した。
⑧沖縄産ヤマトシジミに福島原発事故で汚染したカタバミを食べさせたら、生存率が低下した。
以上の結果と内部被曝実験により、大瀧研究室は福島原発から放出された人工放射線により個体の体細胞及び生殖細胞に生理的又は遺伝的損傷が生じたと結論している。
疑問と批判に反論
各界から第1論文にたいする批判があり、2013年8月に、11点について反論した第2論文が発表された。反論の中により深い内容があり、非常に難解な内容だが、誤解を恐れず要約する。
①「ヤマトシジミに環境指標生物及び実験動物としての適合性はあるか」という問いにたいして、大瀧研究室はヤマトシジミはカタバミだけを食べる昆虫で、沖縄から東北まで広範に生息し、成虫の寿命は1週間程度で、分散する距離は限定している。幼虫も成虫も地面に近いところで過ごすので、原発事故で拡散・降下した放射性物質の影響を受けやすいなどの理由を挙げて、環境指標生物として適当であると答えている。
②「緯度に依存した前翅サイズの縮小」ではないかという問いにたいして、大瀧研究室は福島より北方に位置する白石市のサンプル数が少なかったので、除外して統計を取ったことが誤解を招いた。あらためて白石市の結果を加えて結論を見ると、福島市の前翅サイズは北方、南方のヤマトシジミよりも小さかった。
③「環境温度の低下が幼虫期間を遅延させたのではないか」という問いにたいして、大瀧研究室は福島よりも北方にある白石市で採取したサンプルよりも、南方にある福島のサンプルの方が遅延傾向が強いこと、また福島原発のある緯度付近が最も高いピークを示していることから、環境温度の影響ではなく、放射性物質の影響の可能性が強いと結論づけている。
④「前翅の色模様の異常出現は気温変化によるのではないか」という問いにたいして、大瀧研究室は、ヤマトシジミの最北限青森県深浦町で、2000年から05年にかけて温度ショック型の色模様変化の報告があるが、他の異常を伴っていない。福島の場合は変化に多様性があり、他の異常を伴っており、病的である。遺伝子の変異による色模様変化の可能性が強いと反論している。
⑤「異常率や成長期間の違いは事故以前から存在する地域差に由来するのではないか」という問いにたいして、大瀧研究室は色模様異常以外の異常は生存上致命的な弱点となり、適応度が低くて、子孫を残せないだろう。福島でヤマトシジミがこのような弱点を抱えたまま何十年も生存してきたとは考えられない。福島のヤマトシジミは個体群レベルでの崩壊が起こりつつあるのではないか。2011年9月の福島の異常率は38.5%であり、地面線量と異常率には高い相関関係がある。1979年から2009年にかけて、福島県内で採取した9個のヤマトシジミの色模様はすべて正常であった。
⑥「バックグラウンドの数値が高いために放射線の影響を評価できない」という指摘にたいして、大瀧研究室は第1論文でこの点を議論しなかったことを率直に認めた上で、5月の異常率と9月の異常率を比較すると、有意な差が認められ、室内飼育による異常発生以外の要因が影響されていると考えられ、その要因として放射線による生殖細胞への損傷を想定するのが最も合理的であると答えている。
また、原発事故当時、ヤマトシジミの精子は成熟期にあり、生殖細胞は未分化の状態にあり、放射線感受性が強く、その精子と卵子が遺伝的な異常を生じたまま接合すれば、子孫世代においてさまざまな疾患を生じ、それはP(親世代)よりもF1(子世代)、F2(孫世代)の方が深刻な状態であったとも答えている。
⑦「放射線によりランダムに突然変異が生じた場合、異常が偏らないはず」という批判があるが、これにたいして大瀧研究室はランダムな突然変異作出実験でも、ランダムな異常形質を得ることは不可能であり、表現型が偏ることは一般的であると答えている。
⑧「サンプリング地点の津波の影響」の疑いについては、大瀧研究室はサンプリング地点は海岸よりはるか内陸にあり、津波による影響はないと答えている。
⑨「サンプル数やサンプリング地点が少ないから、結論を導くには不十分である」との主張にたいして、大瀧研究室は5月採取数は144個体、9月採取数は238個体、実験では5942個体を使っており、サンプル数としては十分である。さらなる研究のためには、サンプリング地点と数の増加、継続したモニタリングが必要である。
⑩「福島と沖縄の飼育環境の相違が幼虫の不健全な成育になったのではないか」との批判にたいして、大瀧研究室は実験群・対照群に標準環境(26±1℃)下で、飼育コンテナを清掃し、新鮮な食草を与えたとしている。福島と沖縄の気温の差はヤマトシジミに悪影響を与えるほどの差ではないと反論した。
⑪「昆虫は放射線に高い抵抗性をもつから、実験結果は信頼できない」という批判にたいして、大瀧研究室は従来の実験は短時間かつ高線量照射だが、長期間かつ低線量照射の結果であり、実験手法を無視した批判であると反論している。また、過去には、非汚染地域の生物に汚染地域産のエサを与えるという内部被曝実験はおこなわれていない。
『科学』に発表された大瀧論文
第1、第2論文は2011年秋までの調査結果の分析であり、2015年2月に発表された直近の第6論文の案内文と『科学』(岩波書店)2014年9月号に発表された大瀧論文「原発事故の生物への影響をチョウで調査する」によって、2013年までの調査結果を知ることができる。
大瀧研究室は福島市、本宮市、広野町、いわき市、高萩市、水戸市、つくば市で2011年から13年にかけて、3年間の春と秋、合計6回の調査をおこなっている。放射線汚染地域では、ヤマトシジミの総異常率は2011年秋から2012年春にピークに達した。ヤマトシジミの世代時間(卵→幼虫→蛹→蝶)は1カ月程度で、6世代後にピークを迎えたことになり、昆虫への影響をそのまま人間に当てはめることはできないにしても、人間の1世代を25年とすれば150年に相当する。
ヤマトシジミの異常率は2011年9月をピークにして減少し、15世代ほど経過した2013年7月時点で、放射線環境に適応できるようになったと考えられる。人間の15世代後といえば375年後であり、そんな遠い遠い先になってやっと原発事故による環境変化に適応できることになる。
全原発を廃炉に
「北海道新聞」(2012.8.16)によれば、同様の研究は北海道大学の秋元研究室でもおこなわれている。2012年6月に、福島原発から32キロ離れた計画的避難地区でおこなわれた調査で、ワタムシ(アブラムシの一種)の成育に異常がでているという。通常、奇形の発生率は1%未満であるが、原発周辺では約1割に達している。
昆虫は放射線だけではなく、いろいろなストレスに強い生き物である。だからこそ、地球上で最も繁栄しているのである。ある個体だけなら殺虫剤で殺すことはできるが、耐性をもつ個体が生まれるから、その種を根絶することは難しい。
私が観察しているアメリカシロヒトリも同様である。1945年にアメシロが日本に上陸し、70年後の今、北限の北海道南部にまで広がっている。街路樹や果樹に被害をもたらすので、各自治体は薬剤散布をくりかえしてきたが、どの地域でも、例外なく根絶に成功していない。このように昆虫は環境への適応能力が高いが、はたして福島原発由来の放射線にさらされた人間はどうであろうか。
原発事故由来の放射線によって、ヤマトシジミのある個体は死に、ある個体は生きのび、耐性を形成している。政治家や科学者もどきが「人への被曝量の安全基準」を一律に決めているが、各個人の放射線耐性度や健康度によって安全基準は異なるから、各個人の多様な耐性度や価値観を尊重して決めるべきであろう。
ふたたび原発事故を繰り返さないために、すべての原発の廃炉を決定し、廃炉作業に取りかからねばならない。