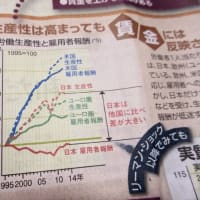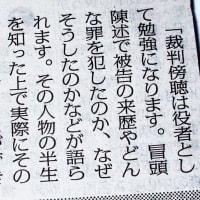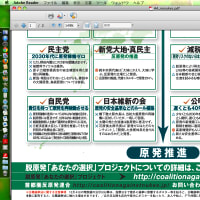★JANJANで石川雅之氏が
「サイモン&ガーファンクル、67歳の東京コンサート
東京ドームで再び見た「明日に架ける橋」の夢のかけら」
という一文を寄せている。
私も40数年前彼らの歌声に魅了されたファンの一人だった。あれからも年に数度家族に遠慮しながら深夜にヘッドホーンで聴いている。青春の歌である。
今回の石川氏の文章に共感し昨夜も久しぶりに彼らの曲に耳を傾けた。
同年代のファンに彼の感動の一文を紹介したい。(ネット虫)
==============================
4万人と公称された観衆の全員が固唾をのんでその瞬間を待ち構えた。アコースティックなギターの爪弾きが会場全体に響き、1曲目は今回で最後とされるワールドツアーの冠ともなっている「Old riends」。7月11日土曜日、サイモン&ガーファンクルの東京ドームコンサート(招聘:ウドー音楽事務所)は予定を15分遅れての開始だった。
周囲はほとんどが40代後半から団塊の世代とおぼしき男女、なかには杖をついて席に向かう姿もあった。あの方は、おいくつだったのだろう。東京ドームでの2日間のチケットはほぼ完売に近い捌け方で、15日には日本武道館での追加公演が行われる。
特筆すべきは、おそらくすべての会場に共通するそうした観客動員のありようである。自分自身は、直前に都合のつかなくなった知人から譲られてのライブだった。それほどの思い入れもなく席につき開演を待っていたせいか、ドーム全体のこれまでほとんど目にしたことのない雰囲気にただ戸惑うばかり。しかし、終わってみれば、実に懐かしい感覚に胸を揺すぶられる時間の重畳となり、大いに楽しむことができた。おそらく、この日参集したほとんどの聴衆がほぼ同様の満足感に浸ったのではなかったか。
終曲として演奏された「明日に架ける橋」が世界を席巻したのは40年前の1970年。日本は大阪万博一色の年だった。東大安田講堂事件に象徴される年長者たちの学生運動が終息し、彼等とともに世代を超えて共有しはじめた新たな虚無感を、国をあげての祭典騒ぎで紛らす中、アメリカから発せられた若い2人の歌声は、同世代や、それに続く中高生の心を慰撫し、励ました。
ビートルズが解散し、それを愛おしむように最後のアルバム「Let it be」の収録曲がそこかしこで聴こえ、同じ時期、気がつくとカーペンターズの甘い調べがヒットを重ねていた。それとは別の所で、ポール・サイモンの典雅な優しい歌声と、アート・ガーファンクルの「天使の歌声」とも評された清らかな高音とが、まだ希望はあるのだ、とそっと皆の背中を押して、特別な位置を獲得していたように思う。同時期の邦楽は、グループサウンズがすっかり鳴りを潜め、全盛をきわめていたフォークソングが、ニューミュージックと呼称されはじめる前夜だった。並行して、「あの素晴らしい愛をもう一度」が流れていた。
そうした時代の端の方で無聊をかこっていた1人にとって、サイモン&ガーファンクルの楽曲が愛聴盤の第1になったことは決してなかった。けれども振り返ってみれば、いくつもの曲が、自身の内なる部分の最も柔らかな場所に沁み入るものになっている。
「The Sound Of Silence」の「Hello darkness, my old friend」という、囁きかけるような歌い出しには、いつだって思春期はきっと共感する。いちいちは引用しないが、「冬の散歩道(A Hazy Shade Of Winter)」や「ボクサー」なども同様だ。ポール・サイモンの織りなす言葉の連なりは、アート・ガーファンクルとともに響かせる包み込むような調べにのって、ある意味、太宰治がいつの世でも若さを引き寄せつづけているものとよく似た共振をもたらすものだったのかも知れない。マイク・ニコルズ監督の「卒業」のダスティン・ホフマン、キャサリン・ロスとの切っても切れない関係性も大きく影響しているだろう。
だから、こんなにも切なく懐しいんだ。2時間に及ぶコンサートの最中、ずっとそんな風に考え、陶然とした気分で揺らいでいた。
あの頃から、40年。時代の姿は、予想だにしなったものに変貌した。希望とか夢とかの言葉が、いつからだったろう、表通りから退場して既に久しい。サイモン&ガーファンクルに激励され、誰もがそれぞれの場所を「卒業」し、洋々たる前途の中でアメリカが範を示してくれた幸福をみんなでこの手にしているはずだったのに。そう思いこんだあの頃は、はかなくも遠い彼方だ。
予想図通りの人生を駆け抜けた人も中にはいるだろう。振り返って、あぁいい人生だったと思う人の方が実は大多数なのかも知れない。しかし、だとしても、後悔のない人生などあり得ない。欠けているものが確かにある。サイモン&ガーファンクルの抱擁力溢れ深い懐かしさを湛えたデュオは、そのことを気づかせ、その上で、ふたたび慰め、励ます魅力に満ちていた。
コンサートを「70歳になった自分を思い描くことなど出来ない」(「Old riends」)という若い頃の歌詞でスタートさせた2人も、いまや67歳。老いてしまったことは、もはや隠しようもなかった。それでも、追加公演も含めて6回の公演で20万人を超える聴衆を集め、そのすべてに遠い夢のかけらを呼び戻させることになるであろう魅力の健在ぶりに、ブラボーの喝采を送らずにはいられなかった。
「サイモン&ガーファンクル、67歳の東京コンサート
東京ドームで再び見た「明日に架ける橋」の夢のかけら」
という一文を寄せている。
私も40数年前彼らの歌声に魅了されたファンの一人だった。あれからも年に数度家族に遠慮しながら深夜にヘッドホーンで聴いている。青春の歌である。
今回の石川氏の文章に共感し昨夜も久しぶりに彼らの曲に耳を傾けた。
同年代のファンに彼の感動の一文を紹介したい。(ネット虫)
==============================
4万人と公称された観衆の全員が固唾をのんでその瞬間を待ち構えた。アコースティックなギターの爪弾きが会場全体に響き、1曲目は今回で最後とされるワールドツアーの冠ともなっている「Old riends」。7月11日土曜日、サイモン&ガーファンクルの東京ドームコンサート(招聘:ウドー音楽事務所)は予定を15分遅れての開始だった。
周囲はほとんどが40代後半から団塊の世代とおぼしき男女、なかには杖をついて席に向かう姿もあった。あの方は、おいくつだったのだろう。東京ドームでの2日間のチケットはほぼ完売に近い捌け方で、15日には日本武道館での追加公演が行われる。
特筆すべきは、おそらくすべての会場に共通するそうした観客動員のありようである。自分自身は、直前に都合のつかなくなった知人から譲られてのライブだった。それほどの思い入れもなく席につき開演を待っていたせいか、ドーム全体のこれまでほとんど目にしたことのない雰囲気にただ戸惑うばかり。しかし、終わってみれば、実に懐かしい感覚に胸を揺すぶられる時間の重畳となり、大いに楽しむことができた。おそらく、この日参集したほとんどの聴衆がほぼ同様の満足感に浸ったのではなかったか。
終曲として演奏された「明日に架ける橋」が世界を席巻したのは40年前の1970年。日本は大阪万博一色の年だった。東大安田講堂事件に象徴される年長者たちの学生運動が終息し、彼等とともに世代を超えて共有しはじめた新たな虚無感を、国をあげての祭典騒ぎで紛らす中、アメリカから発せられた若い2人の歌声は、同世代や、それに続く中高生の心を慰撫し、励ました。
ビートルズが解散し、それを愛おしむように最後のアルバム「Let it be」の収録曲がそこかしこで聴こえ、同じ時期、気がつくとカーペンターズの甘い調べがヒットを重ねていた。それとは別の所で、ポール・サイモンの典雅な優しい歌声と、アート・ガーファンクルの「天使の歌声」とも評された清らかな高音とが、まだ希望はあるのだ、とそっと皆の背中を押して、特別な位置を獲得していたように思う。同時期の邦楽は、グループサウンズがすっかり鳴りを潜め、全盛をきわめていたフォークソングが、ニューミュージックと呼称されはじめる前夜だった。並行して、「あの素晴らしい愛をもう一度」が流れていた。
そうした時代の端の方で無聊をかこっていた1人にとって、サイモン&ガーファンクルの楽曲が愛聴盤の第1になったことは決してなかった。けれども振り返ってみれば、いくつもの曲が、自身の内なる部分の最も柔らかな場所に沁み入るものになっている。
「The Sound Of Silence」の「Hello darkness, my old friend」という、囁きかけるような歌い出しには、いつだって思春期はきっと共感する。いちいちは引用しないが、「冬の散歩道(A Hazy Shade Of Winter)」や「ボクサー」なども同様だ。ポール・サイモンの織りなす言葉の連なりは、アート・ガーファンクルとともに響かせる包み込むような調べにのって、ある意味、太宰治がいつの世でも若さを引き寄せつづけているものとよく似た共振をもたらすものだったのかも知れない。マイク・ニコルズ監督の「卒業」のダスティン・ホフマン、キャサリン・ロスとの切っても切れない関係性も大きく影響しているだろう。
だから、こんなにも切なく懐しいんだ。2時間に及ぶコンサートの最中、ずっとそんな風に考え、陶然とした気分で揺らいでいた。
あの頃から、40年。時代の姿は、予想だにしなったものに変貌した。希望とか夢とかの言葉が、いつからだったろう、表通りから退場して既に久しい。サイモン&ガーファンクルに激励され、誰もがそれぞれの場所を「卒業」し、洋々たる前途の中でアメリカが範を示してくれた幸福をみんなでこの手にしているはずだったのに。そう思いこんだあの頃は、はかなくも遠い彼方だ。
予想図通りの人生を駆け抜けた人も中にはいるだろう。振り返って、あぁいい人生だったと思う人の方が実は大多数なのかも知れない。しかし、だとしても、後悔のない人生などあり得ない。欠けているものが確かにある。サイモン&ガーファンクルの抱擁力溢れ深い懐かしさを湛えたデュオは、そのことを気づかせ、その上で、ふたたび慰め、励ます魅力に満ちていた。
コンサートを「70歳になった自分を思い描くことなど出来ない」(「Old riends」)という若い頃の歌詞でスタートさせた2人も、いまや67歳。老いてしまったことは、もはや隠しようもなかった。それでも、追加公演も含めて6回の公演で20万人を超える聴衆を集め、そのすべてに遠い夢のかけらを呼び戻させることになるであろう魅力の健在ぶりに、ブラボーの喝采を送らずにはいられなかった。