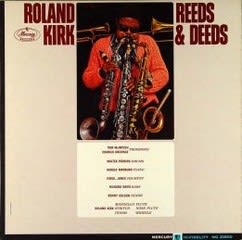最近、仕事でのテンションが高すぎて、家へ帰るとグッタリモードです。
いろいろ仕入れたネタのDVDやCDも楽しむ気力が無く……。
しかし車の中や仕事場では、鑑賞意欲が抑えられないというワガママ病になっています。
ということで、本日は――
■Frivolous Sal / Sal Salvador (Bethlehem)
モダンジャズギターの開祖=チャーリー・クリスチャンは黒人なのに、以降は何故か白人優位というのが、ジャズギター界の七不思議かもしれません。
そこで活躍したひとりが本日の主役、サル・サルヴァドールです。そのスタイルは正確無比なピッキングとストレートな歌心が強い印象を残します。
まあ、正直に言えば、タル・ファーロゥに近いものがありますが、あそこまでの豪快さよりは、逆に端正な様式美を追求した輝きに、私は大きな魅力を感じます。
その楽歴はスタン・ケントン楽団への参加が一番華やかなところですが、リーダー盤もシブイ名作が多く、いずれもジャズ者の心に支えになっているブツばかり♪ これもその中の1枚です。
録音は1955年、メンバーはサル・サルヴァドール(g)、エディ・コスタ(p,vib)、ジョージ・ルーマニス(b)、ジミー・キャンベル(ds) という面々で、なんと前述したタル・ファーロウの共演者が、そのまんま参加してきたような企画が興味深いところ――
A-1 Frivolous Sal
テンションの高いドラムスのイントロから、ややバロック調の端正なアンサンブルが、瞬間的にモダンジャズに転換するという素晴らしい名曲・名演です。
作曲は西海岸の名アレンジャーだったビル・ホールマンですから、さもありなん! とにくか間然することのない流麗なギターソロは、スピード感満点に歯切れが素晴らしいジミー・キャンベルのブラシと完全対決しながら、強烈な存在感を示してくれます。
もちろんエディ・コスタは十八番の低音打楽器奏法のピアノを披露してくれますよ♪
この1曲にアルバムの全てが凝縮されていると思います。
A-2 Tangerine
如何にもモダンジャズのスタンダード曲が、絶妙のアレンジを加えて名演化していく過程が楽しいです♪ あぁ、こんなにスピードがついていながら、全く乱れないサル・サルヴァドールのピッキングは驚異的です。
またエディ・コスタのストレートなピアノはパキパキしていて、気持ちが良いです。
A-3 Cover The Waterfront
これも有名スタンダードですが、重厚で幽玄なアレンジが効いています。全体にはスローな和み系の演奏になっており、メンバー全員の歌心優先モードが素晴らしい♪
ベースのジョージ・ルーマニスが大活躍しています。
A-4 You Stepped Out Of A Dream
一転してハードバップな演奏! スタンダード曲を素材にアップテンポの解釈は極めて爽快です。
全く淀みないサル・サルヴァドールのギターは、本人十八番のフレーズばかりですから、コピーするには最適かと思われますが、私には不可能です、難しすぎて……。
終盤のギター~ピアノ~ドラムスのソロチェンジはモダンジャズの醍醐味でしょうね。
A-5 You Could Swing For That
サル・サルヴァドールのオリジナル曲で、アグレッシブなイントロから、どっかで聞いたようなテーマメロディが楽しい限りです。アップテンポで一糸乱れぬバンドのノリも最高ですねぇ。
そしてエディ・コスタがお待ちかねの低音打楽器ピアノの真髄を披露! う~ん、これが出ると、失礼ながらタル・ファーロウのバンドみたいになっちゃいますねっ。いや、それでも良いんですが♪
B-1 All The Things You Are
これまたクラシック調のイントロからスピード感満点のテーマ演奏に入るという、最高の展開がたまりません。曲はモダンジャズでは避けて通れないスタンダードということで、数多い名演の中にあって、このバージョンもその仲間入りでしょう。
とにかく奔放なサル・サルヴァドールは、珍しく破綻寸前のところまで行っていますし、エディ・コスタは低音打楽器奏法のピアノに加えて、洒落たヴァイブラフォンも駆使して大活躍!
ジミー・キャンベルのヤケクソ気味のドラムスも良い感じで、このアルバムの中でも屈指の名演になっています。
B-2 Salaman
このアルバムにアレンジャーとして参画したマニー・アルパムとサル・サルヴァドールが共作した名曲で、そのテーマメロディには、ちょっと昭和歌謡曲の雰囲気がありますから、私は大好き♪
もちろんアドリブパートでもそれは横溢して止みません。エディ・コスタのヴァイブラフォンにも泣けてきます。あぁ、もうちょいとテンポを落としたら、松尾和子の世界ですよ♪
ここは各人のアドリブ云々よりも、演奏全体の良いムードを楽しんでしまうのでした。
B-3 Handful Of Star
美しいスタンダード曲を、さらに磨きをかけていくようなサル・サルヴァドールのギターが素晴らしいです。テーマメロディの歌わせ方なんて、絶品ですよ。
またエディ・コスタのヴァイブラフォンには緩やかなグルーヴがあって、これまたモダンジャズの楽しみになっています。
B-4 I Love You
コール・ポーターが書いた有名スタンダードですから、幾多の名演バージョンが残されていますが、こんなにシンプルで印象的なアレンジでの演奏は珍しいのではないでしょうか。
アドリブパートは安定感優先というか、このセッションの中では普通の出来ですが、凡百の演奏は足元にも及ばない完成度がありますし、バンドアンサンブルは流石! アレンジはベーシストのジョージ・ルーマニスが担当したと言われています。
B-5 I'll Remember April
オーラスは、これもモダンジャズでは大定番の歌物ですから、ここでのスピード感満点の演奏には安心して身をまかせ、そして痛快という仕上がりです。
とにかくサル・サルヴァドールのギターが凄すぎます! 若干の乱れがあるピッキングさえも、完全にジャズになっているという恐ろしさ!
エディ・コスタのヴァイブラフォン以下、共演者も熱演ですから、気持ち良くアルバムを聴き終えることが出来るのでした。
ということで、演奏はいずれも3~4分の短いものですが、内容は濃密で完成度の高さは驚異的です。如何にも白人ジャズらしいスマートでスピード感に満ちたノリは、実に爽快です。
ギターピックを持った指のアップというジャケ写も、自信の表れなんでしょうか。
ギター好きには宝典の1枚ですし、ジャズ者には避けて通れないアルバムだと、今日は断言させて下さいませ。