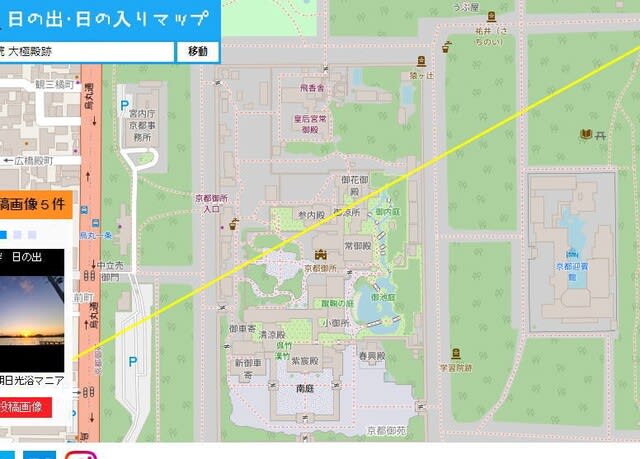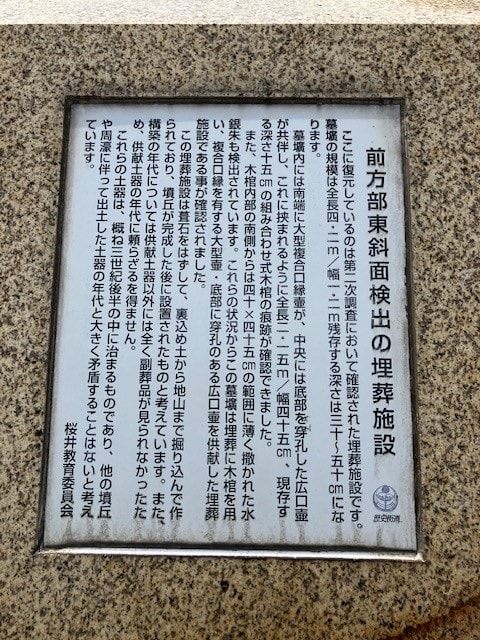犬山神社と、払い所のレイラインは後の、伊勢に向かう途中で出来たものでしょう。
推測の域を出ませんが、その時には、犬山神社には倭姫と、サタヒコとアメノウズメの子である
迦邇米雷王(かにめいかずちのみこ)が住んでいたと思います。
迦邇米雷王は、アメノウズメの死後ずっと倭姫に育てられていたのではないだろうか?
というより、それ以前の、丹波にいる時から、サタヒコとアメノウズメそして倭姫は、
おそらく比沼麻奈為神社に住んでいたと思います。
ですから、倭姫と、迦邇米雷王は強いつながりがあります。
サタヒコが、三種の神器を伊勢に運ぶ時には、犬山で船を作ったということはすでに書きました。
その時、サタヒコは、三種の神器の近く、つまり三光稲荷神社付近で、
尾張大印岐の娘である、眞敷刀俾命(マシキトベ)を妻にして住んでいたと考えます。
伊勢から帰ってきてから、彼女を妻にしたかもしれませんが、2~3年の違いです。
そうすると、眞敷刀俾命の夫とされている人物は、乎止与命(オトヨ)=サタヒコということになります
二人の間に出来た子は、建稲種命と宮簀媛 と言われていますが、建稲種命は架空の人物と思います。
しかし、迦邇米雷王(かにめいかずちのみこ)と、宮簀媛は異母兄弟なので彼が建稲種命の
モデルかもしれません。
以前にも書きましたが、氷上姉御神社は、本来は「火神姉御神社」だったそうです。
たしか、火事があったので、「火神」を「氷上」に代えたと記憶しています。
ですから、現在はスケートに関する人が参拝に来るそうです。
さて、迦邇米雷王は、後の「神大根王」つまり「金山神」なので、火の神様なのです。
そうすると、火神姉御神社の「火神」は、迦邇米雷王のことで、
「姉御」は、宮簀媛(玉姫)ということになります。
そして、その「火神姉御神社」は、伊勢から持ち帰った辰砂を陸揚げする港だったと思います。
彼は後に、伊久良河宮に移ります。そこは、元伊勢と言われます。
おいらは最初、どう考えても倭姫が、伊勢に行く途中滞在した場所とは思えなかったので
元伊勢ではないと考えてきました。
でも、倭姫は意外とエネルギッシュに伊勢から、あちこち移動しているようです。
よく考えれば不思議でもなんでもないですね。むしろ当たり前でしょう。
自分の育てた迦邇米雷王のいる伊久良河宮に行くのは当たり前です。
だから、伊久良河宮は元伊勢と言われているのでしょう。
そして、そのルートの途中にあるもう一つの、元伊勢といわれる「酒見神社」も、元伊勢と言われますけど、同じ理由で、伊久良河宮に行く途中に滞在した場所なのでしょう。
ちゃんとした理由がありました。