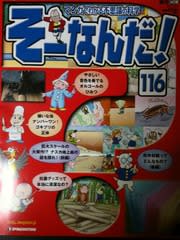
(【読書録】そーなんだ!科学編116)
最近、ほとんど目にすることはなくなったわら半紙。そもそも「わら半紙」という単語すらほとんど忘れていたのに、何故急に思い出したのかというと、「そーなんだ!科学編116」の「非木材紙」の特集に登場したから。
中国では今でも一般的に、麦や稲のわらを製紙に用いているという話に始まり、「日本でも20~30年前は、木の皮の繊維にわらを混ぜた『わら半紙』という紙がよく使われていたんだよ」という記述を見て驚愕した。
私が小学生の頃は、先生の作るプリントやテスト、クラスの文集などはみんなわら半紙だった。単純バカな私がなぜそれを文字通りわらの入っている紙だとは思わなかったのだろう。
おそらく理由は二つある。一つ目には、当時かなりマイナーではあったけど、やはり茶色い紙で、芯材などに用いられる黄土色の紙に「馬糞紙」というものがあった。これが文字通り馬糞から作られる紙ではなかったため、わら半紙もわらから作られるわけではないと勝手に思い込んでいたのである。
もう一つの理由は「半紙」という名称。書道で使う半紙とは似ても似つかぬ姿だったので、「わら半紙」という名称がニックネームのようなもの、つまり「わらのような色をした半紙みたいなもの」という意味だと思い込んでいたのだ。
ということで、「非木材紙」が注目されている今、昔のわら半紙というものは非木材紙の走りであるわけだ。ちなみに現在もわら半紙と呼ばれるものは存在するが、本当のわらを使ったものはまずなく、白色度の劣る中質紙をそのように呼んでいるケースが多いようである。
何か不思議ね。「わらが入っている」なんて思ってもいなかった紙にわらが入っていて、馬糞から作られる紙はなくても、象糞から作られる紙は存在するんだから。
▼(ご参考)ゾウのウンチで再生紙
http://blog.goo.ne.jp/y-saburin99/e/c6fd87859f3ccd60c5db0ef827886cd8
最近、ほとんど目にすることはなくなったわら半紙。そもそも「わら半紙」という単語すらほとんど忘れていたのに、何故急に思い出したのかというと、「そーなんだ!科学編116」の「非木材紙」の特集に登場したから。
中国では今でも一般的に、麦や稲のわらを製紙に用いているという話に始まり、「日本でも20~30年前は、木の皮の繊維にわらを混ぜた『わら半紙』という紙がよく使われていたんだよ」という記述を見て驚愕した。
私が小学生の頃は、先生の作るプリントやテスト、クラスの文集などはみんなわら半紙だった。単純バカな私がなぜそれを文字通りわらの入っている紙だとは思わなかったのだろう。
おそらく理由は二つある。一つ目には、当時かなりマイナーではあったけど、やはり茶色い紙で、芯材などに用いられる黄土色の紙に「馬糞紙」というものがあった。これが文字通り馬糞から作られる紙ではなかったため、わら半紙もわらから作られるわけではないと勝手に思い込んでいたのである。
もう一つの理由は「半紙」という名称。書道で使う半紙とは似ても似つかぬ姿だったので、「わら半紙」という名称がニックネームのようなもの、つまり「わらのような色をした半紙みたいなもの」という意味だと思い込んでいたのだ。
ということで、「非木材紙」が注目されている今、昔のわら半紙というものは非木材紙の走りであるわけだ。ちなみに現在もわら半紙と呼ばれるものは存在するが、本当のわらを使ったものはまずなく、白色度の劣る中質紙をそのように呼んでいるケースが多いようである。
何か不思議ね。「わらが入っている」なんて思ってもいなかった紙にわらが入っていて、馬糞から作られる紙はなくても、象糞から作られる紙は存在するんだから。
▼(ご参考)ゾウのウンチで再生紙
http://blog.goo.ne.jp/y-saburin99/e/c6fd87859f3ccd60c5db0ef827886cd8


























藁半紙はワラバンと呼んでいました。高校生の頃、広告の裏でも足りず、ワラバンを買って来て、計算用紙にしました。1枚を3回使うのです。初めは緑、二回目は赤、三回目は青か黒のボールペンで書くのです。
貧乏だった訳ではないのですが、折角紙として作られて、単に計算だけにサッと使われて捨てられてしまうのが不憫に思え、使い切ってあげたかったのです。
社会人になる頃には急速にOAが進み、無用なプリントアウトとコピーに、もっと上質な紙が浪費される一方で、世界にはまだまだノートすらも満足にない子供がいる世となりました。私に同調出来るのはそんな子供達しかいないのかも知れません。
わら半紙はシャープペンシルだと引っかかって書きづらいし、プリンターにセットすると詰まりやすく不向きなのだと思います。
考えるとシャープペンシルの普及やOA化が、紙の上質化を促進したのでしょうか。
私も広告の裏や青焼き図面の裏を計算用紙に使ったり、新聞を4つ切りにしたものを、お習字の練習によく使いました。でもいつからか、裏面が白い広告チラシ自体を目にしなくなったんですよね。
再生紙を作るのがかえってコスト高になる時代ですが、いかに電子機器が発達しようとも、紙の需要というものは容易に減らないものだと思います。再生紙に回す以前により有効活用する姿勢を、より習慣づけたいものですね。