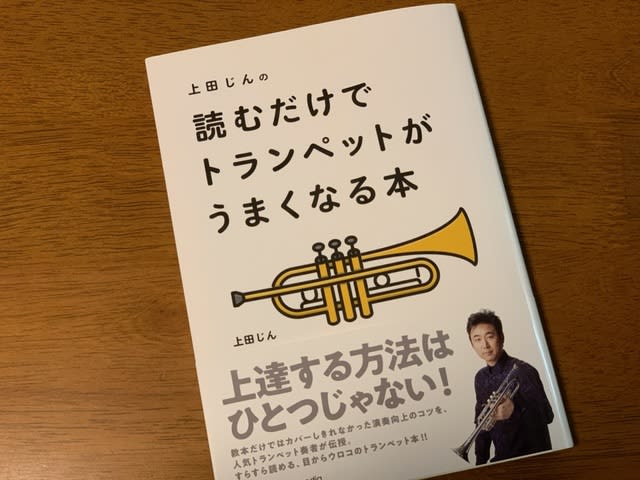
上田じん / ヤマハ
これは確か一昨年くらいに買って、ちょっと読んでそのままになってた本だ。つんどく本ストックから出してきて、ようやく読み切ることが出来た。で、読み切ったことで、トランペットが本当にうまくなったかというと、そう即効性のあるものではないと思うが、確かにいくつかの視点を与えられたことは事実である。
たとえば、その作曲家が本来話すことばのアーティキュレーションで演奏すべき・・という話。今、取り組んでいるゲディゲのコンサート・エチュードだが、ゲディゲはロシア人である。う、・・ロシア語知らない。
ちなみに同じ日本でも関東と関西で違うそうだ。東京で聴くトランペットは、関西のトランペットの発音よりはっきりしてるんだとか。へぇぇ~。
この、作曲家の国籍という話は、単に発音だけじゃなくて、フレージングにも影響するとか。歌うように吹くということは、フレージングを大切に・・ということにつながるのだが、作品の作曲家の国籍、言語、方言、時代などを考慮して、その作品にマッチしたフレージングをすべし・・と。・・・イタリアの作曲家の作品を探そうかなぁ。
あと、とても恥ずかしい話なのだが、誰でも知っている「トランペット吹きの休日」という曲。トランペット吹きは、仕事でさんざん吹いているくせに、休日もあんなにガンガン吹くなんて、なんてクレージーな仕事人間なんだ・・と、思っていたのだが、あの曲の原題は「Bugler’s Holiday」。トランペット吹きじゃなくてビューグル吹きなのである。ビューグルは信号ラッパのようなもので、ピストンがなかったり、あっても一つか二つしかないので、すべての音を吹くことができない。普段の仕事で単純なパッセージしか吹かせてもらえない信号ラッパ手が休日にトランペットを思う存分吹きまくるというのが、あの曲の真意だったのだ。別に働き方改革でエネルギーが有り余ってたから・・ってわけではなかったのね。
巻末にはソロのおすすめ曲が何曲か載っているが、今やってるゲディゲも載ってた! この本をもっとちゃんと読んでれば、この曲にもっと早く出会えたかもしれないのにね。
























