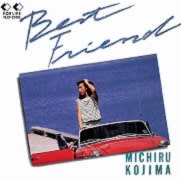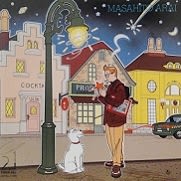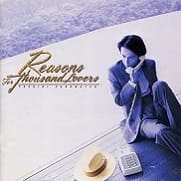秋の夜長にこんな作品を。シティポップスについて少しでも興味がある人なら、知らなければモグリと言っても過言ではない吉田美奈子の3rdシングルです。同日に発売された5thアルバムのTwilight Zoneからのいわゆるシングルカット作。何故だかPart.I・II共にLPヴァージョンとは別テイクと紹介されることが多いですが、聴き比べてみた雰囲気で判断する限り、Side-AのPart.Iは単にLPでのテイクから後半部分をオミットしたものかと。LPでの演奏は6分45秒もあり、そのうち後半の3分弱はサックス~トロンボーン~トランペットの各ソロが展開されているのみなので、このPart.Iではシングル用にその部分をばっさり削っただけという見方が正解だと思うのですがいかがでしょう。一方Side-BのPart.IIは完全に別テイク。基本的にはPart.Iでオミットされた三管ソロ部分の焼き直しなのですが、ボトムが元曲とは全く異なるファンキーなものに差し替えられているため受ける印象が随分変わります。いかにもヒップホップ畑の人が好みそうな骨太ビートの上で縦横無尽に展開されるソロ廻しは圧巻そのもの。当時7インチでしかリリースされなかった本作が他の追随を許さぬ人気高額盤たる所以です。ただ、個人的には正直そこまで高額を支払ってまで購入するべき作品かと問われると微妙。最近は1995年にVividからリリースされた再発盤にまでとんでもない値段が付いているようですが、今では人気のPart.IIのみならずPart.Iですら普通にCDで聴くことが出来るので、そこに高額を支払う価値があるかどうかはなかなかに判断が難しいところです。ちなみに件のPart.IIは数年前にクニモンド瀧口氏の流線形がカバーしており、そちらもなかなかに良い出来。まるで往年のスカイハイ・プロダクション(というかボビー・ハンフリー)を思わせるフルートがリードするソフィスティケイトされた仕上がりですが、これはこれでなかなかに悪くないと思います。こちらはitunesでもダウンロード出来るので気になる人は是非。これも今の時期にはぴったりの名演になっています。
「Light Mellow 和モノ669」誌掲載で一部好事家に知られる作品。文化放送のミスDJリクエストパレードがきっかけで芸能界入りした川口雅代が、1981年にリリースした1stアルバムです。大半の楽曲アレンジを鈴木茂と井上鑑のいずれかが務めていることもあり、全体的にシティポップス度が高い洗練された作品で、肝心の彼女自身のヴォーカル・ワークもなかなかのもの。いわゆる女子大生ブームの草分けとしてデビューした新人の作品とは思えぬ完成度を誇る一枚となっています。白眉はなんといってもB-4に収録されたMelty。間宮貴子~国分友里恵ラインのライトメロウなミディアムスロウナンバーで、都会的な雰囲気が絶妙な一曲です。井上鑑のアレンジの賜物であることは間違いないですが、これを当時大学生だった彼女自身が作詞作曲したというのだから信じられません。この手のアーベインな楽曲は趣味ど真ん中なため、安かったこともあり試聴一発で思わず即買いしてしまいました。ちなみにその他の収録曲ではA-1のFall In LoveやA-3の「さあもんぴんく」あたりが好み。高いレコードではないので、興味がある方は探してみてください。ちなみに作品自体のCD化はされていないものの、件のMeltyに関しては1998年にリリースされたmasshy@love.netというベスト盤に収録されているため、CD派の人はそちらがお勧め。なんでもこの人、ゲーム「ときめきメモリアル」で声優にも挑戦しているようで、このベスト盤もそちらの方面絡みで発売されたもののようですが、このMeltyに関しては本人も思い入れが強いらしくオリジナルの演奏のまま収録されています。中原めいこや二名敦子のような同時代の女性シンガー系ニューミュージックが好きな方ならハマるはず。タイミング的に今の季節にもぴったりのナンバーなので、まだ聴いたことないという方は是非チェックをお勧めします。
80年代歌謡曲界きっての問題作として、一部ではカルト的人気を誇るラ・ムーによる唯一のLP。当時清純派アイドルとして人気のあった菊池桃子が突如「ロック歌手」宣言をし、3枚のシングルの後にリリースされたのがこのアルバムです。もっとも「ロック」という文句はただの釣りで、実際の音楽スタイルがブラコン要素の強いテクノポップだというのは今となってはよく知られた話。当時はセールス的にまったく振るわなかったようですが、今の観点で聴くと捉え方によっては名作に聴こえるのだから不思議なものです。先行してシングルが切られたA-5の「少年は天使を殺す」やB-2の「Tokyo野蛮人」はさすがに電波過ぎて厳しいものがありますが、アルバムのみに収録された曲の完成度はなかなかのもので、特にA-3の「夏と秋のGood-Luck」はスタイル・カウンシルのThe Lodgersを上手に引用したJ-AOR屈指の名曲。中盤のサックスソロや黒人女性コーラスなど、この時代らしいクリスタルな魅力に満ちあふれた素晴らしいナンバーになっています。決して歌がうまいとは言えない菊池桃子のウィスパー・ヴォイスを最大限に活かす、思春期特有のノスタルジーを表現した歌詞も抜群。ほとんど奇跡みたいな化学反応が起きた突然変異のモンスター曲と言って良いでしょう。また、続くA-4のTwo Years Afterも雰囲気こそ違うもののなかなかの名曲。切ないハーモニカの音色が胸を打つ甘酸っぱさ全開の片思いソングで、秋の夜長にぴったりなナンバーです。アイドル声で歌われるJ-AORが好きな方ならばほぼ確実にハマるはず。1989年という微妙な時期のリリースのためアナログはなかなか珍しいですが、CDなら普通に手に入ると思うので気になる人は是非。これからの時期のBGMとしては最適な一枚と思います。
元二枚目俳優の宝田明とミス・ユニヴァースにおけるアジア人初の優勝者である児島明子を両親に持つ、いわゆる二世タレント的な女性シンガー児島未散が高校在学中の1985年にリリースした1st。あいにく世代が違うため彼女自身が当時メディアでどのように取り上げられていたのかは存じませんが、松本隆と林哲司というシティポップス~J-AOR界では非常に強力な二人が全曲に作詞作曲でクレジットされており、演奏メンバーもパーカッショニストの斉藤ノブをはじめ松原正樹(g)や新川博(key)らが参加と何やら豪華なため、なんとなく興味を惹かれて購入してみました。内容的には「オンショア・ウィンドに乗って、エンドレス・サマーの唄声がとどく。」と書かれた帯の文句そのままにオーシャン&メロウ。なんとなく先日紹介した二名敦子の3rdをもう少しアイドルポップス寄りにしたかのような雰囲気で、中には正直今聴くには少し厳しい楽曲もありますが、このあたりの産業系シティポップが好きな人ならば、まぁそれなりには満足頂ける一枚かと思います。当時シングルカットもされたB-1の「セプテンバー物語」を筆頭に、どこか懐かしくも都会的なナンバーが並ぶ作品ですが特筆すべきはA-4のタイトル曲。思い切り二名敦子路線なアーバンミディアムグルーヴに、まだ少女らしさの残るあどけなくも舌足らずな児島のヴォーカルが乗る絶品ナンバーに仕上がっています。J-AORというよりはシティポップスと表現したほうが適切かと思いますが、このあたりの音楽を好む30代以上の男性ならば独特のノスタルジックな雰囲気にやられること間違いなしでしょう。サノトモミがヴォーカルを務めていた時期の流線系に通じる絶妙な甘酸っぱさがツボです。なお僕が所有しているのはアナログ盤ですが、CDでも何度かリリースされているようなので入手は比較的容易かと。気になる人は是非聴いてみてください。ちなみに彼女はこの4年後VAPに移籍することになりますが、移籍後の作品もなかなかの出来なので興味のある人はそちらも合わせてどうぞ。
元パルのリード・ヴォーカル、新井正人による1987年のソロ・ファースト作品。一般的には(というか僕と同じような年齢層の男性にとっては)この前年にリリースされた、アニメ機動戦士ZZガンダムのOPテーマである「アニメじゃない〜夢を忘れた古い地球人よ〜」の方が遥かに知名度が高いと思われますが、彼本来の持ち味は実はこちらのJ-AOR路線だったりします。年代的にはやや新しめの作品ですが、イラストレーターの鴨沢祐仁が描いた素敵なジャケットワークに負けず劣らずのアーバンな楽曲が全編に渡り展開されており、この時期の作品としてはなかなかの好盤。後に彼自身がブランニュー・オメガトライブの中核となることからも察せられる通り、角松敏生や杉山清貴あたりの優男系ポップAORが好きな人にとっては堪らない内容かと思われます。中でも白眉はA-4の「モーニング・サブウェイ」。はっきり言ってしまうと単にマーヴィン・ゲイのMercy mercy Meをモロパクりしただけのナンバーなのですが、頼りなげな新井自身のヴォーカル・ワークや都会的な歌詞と相まり、これはこれで魅力的な一曲に仕上がっています。オメガトライブのDear Breeze(こちらはレイ・パーカーJr.のWoman Needs Loveがネタ)と並び、洋楽パクり系J-AORの二大巨頭と言ってしまって良いでしょう。日本人はなぜか昔からこの手のパクりやフォロワーに大して異常なまでに厳しく、そうと分かると途端に激しい嫌悪感を示す人が多いですが、個人的にはパクりであろうと何であろうと楽曲自体のクォリティが高ければまったく問題という考え方なので、正直そのあたりはあまり気にしていません。オリジナルを超えた贋作など世の中には山ほどあるし、それらを贋作だという点だけでバッサリ切り捨ててしまうのはもったいないというのが僕の基本スタンスです。ちなみに本作、87年という微妙な時期のリリースのためアナログは高額ですがCDならば簡単に手に入るので、特にこだわりがないという方はそちらで買うのが吉。気になる方は変な偏見にとらわれず是非耳を傾けてみてください。
嗄れ声の日本人ソウル・シンガー、円道一成が1983年にリリースした3rdアルバム。今となっては正直この円道氏自体の知名度はそれほどでもありませんが、山下達郎が全面サポートしたナンバーが2曲収録されており、未CD化ながらその筋では比較的人気の高い作品です。気になる達郎関連ナンバーはA-5のL.A.BabeとB-2の「酔いしれてDeja Vu」。このうち特にB-2の「酔いしれてDeja Vu」は山下氏自体も相当にお気に入りのようで、2年前にNHK-FMで放送された「今日は一日“山下達郎”三昧」で隠れ名曲として取り上げたり、昨年リリースされたベストアルバムでセルフカバーしてたりしていました。同時にピックアップされていたKinki Kidsや鈴木雅之らのネームバリューと比較すると、いずれも普通に考えれば有り得ない選曲なので、氏がいかにこの曲に愛着を感じているかが分かります。曲調としてはミディアムテンポのブルージーな和製AORナンバー。歌声にクセはありますが、そこさえ気にならなければおそらくわりと万人に受けるタイプの曲かと思います。個人的にはその他収録曲も含め、現クレイジーケンバンドの横山剣在籍時のクールス辺りに近い質感のアルバムとして比較的お気に入り。例の曲とは同名異曲ながらB-3に「シンデレラ・リバティー」なる曲が収録されていたりと、それなりに共通項も感じられるため親和性は高いと思います。昨日紹介した角松敏生らの優男路線とはまた少しベクトルが違いますが、これはこれで古き良き昭和を感じるシティポップスの一つの形。たとえば井田リエや当山マイラ恵子あたりのメロウながら多少やさぐれた雰囲気の曲が好きな人なら、きっと気に入るはずです。かっこいい不良の音楽という表現がぴったり。冒頭にも書いたように未CD化ですが、それほど極端にレアなアルバムと言うわけではないので、気になる人は探してみてください。
数ある彼の作品の中でも取り上げられることが比較的少ない1989年のアルバム。1981年のデビュー以来、ベスト盤や企画盤を含め80年代を通してやたらとリリースが多い彼ですが、本作は通算8枚目のオリジナル作品に当たるそうです。角松敏生と言えば、昨今のシティポップス・リバイバル・ブーム的には山下達郎ラインを踏襲したライトメロウな初期のリゾート路線がやはり人気で、個人的にも初期3作と「初恋」は捨てがたいのですが、実は最も良く聴いているのは本作。スピーディーな曲もなく全体的に地味な作品ではあるものの、80年代末期特有のバブル感が最も顕著に現れた一枚で、少しノスタルジックな気分に浸りたいときに重宝しています。この時期らしい打ち込みビートと生音が融合したA-1の「飴色の街」、イントロのシンセの音色がたまらなくライトメロウなA-5のPolar、それから変拍子のバラード・ナンバーであるB-4のMoonlight Tokyo Bayあたりを筆頭に、初期のリゾート路線と共に彼のもう一つの顔である「真夜中の大都会」路線の名曲がずらり。いずれも決して派手なナンバーではなく、当然のごとくフロアで使えるような類のものでもありませんが、深夜のラジオからふと流れてきたら何となく少し嬉しくなりそうなオトナ系のポップスで、個人的には非常にお気に入りです。そして何より本作最大の魅力はこのジャケット。数多あるシティポップス系の作品の中でも、ジャケの構図と色合いだけでここまで都会の洗練された空気感を出せるアルバムを他に知りません。ちょうどLPからCDへの移行がほぼ完了した時期の作品でLPのプレス数がCDと比べ極端に少なかったらしく、街のレコード屋でもなかなか遭遇する機会はないですが、これはアナログの大判ジャケットで持っていてこそ価値がある作品かと。当時オリコンでも最大4位になった作品とのことで、CDならば労せず手に入れることが出来ますが、だからこそ逆にマニアならばやはりここはアナログを探してみてほしいものです。
祝再発ということで紹介。昨年、幻の1stと呼ばれていた1983年の「Play Room~戯れ」が再発され一部で話題になった女性シンガーソングライター、二名敦子(にいなあつこ)の1985年作です。ハワイで録音した前作Loco Islandに続く3作目で、個人的に彼女のベストだと思っているのがこれ。エメラルドブルーのジャケットからして開放感満載なリゾート感覚に満ちた素晴らしい一枚です。前作ではKalapana Black Sand Beachなる曲が収録されていたりと若干やり過ぎ感がありましたが、本作では良い意味でこなれて来ているためか凄く自然体。とにかく全編にわたり洗練された極上のシティポップ作品となっており、歌が上手いアイドルみたいな二名嬢のヴォーカル含め、いわゆるライトメロウなJ-AOR好きには直球ど真ん中の作品なのではないでしょうか。特に初期の角松や先頃CDリイシューされた国分友里恵の1st辺りが好きな人は確実にツボ。アルバムにも演奏で参加しているパブロ・クルーズのカヴァーとなるA-1のTonight My Loveから最高です。続くA-2のSoldier Fishも同様のポップ路線。弾けるようなリズムとほろ苦いアレンジの好対照がたまらなくライトメロウ。80'sポップスの理想系です。アルバム中唯一のバラードとなるA-3の「雨のScenic Point」は皆大好きな間宮~国分ライン。まったくもって隙がありません。そしてなんと言っても名曲なのが、芳野藤丸節炸裂なB-1のIcebox & Movie。アーバンリゾート感満載なミディアム・ナンバーで、中盤のサックスソロ含め完璧な一曲です。ちなみに本作、LPだとどこの店でも二束三文なのですが、当時リリースされていたCDがその希少性からか異常な高額で取引されていたため今回の再発はCD派の人にとっては非常に嬉しいニュース。Japanese AOR~80's女性ヴォーカル好きの人は、今回のタイミングを逃さずチェックした方が良いかと思います。
間宮貴子、国分友里恵に続き次にCD化されるのはこの辺りでしょうか。中尾ミエ・園まりと共にスパーク3人娘として60年代中盤に一世を風靡した伊東ゆかりが、林哲司のプロデュースにより1982年にリリースしたLP。リリース当時はプロモーション不足もあり、ほとんど話題にならずセールス的にも振るわなかった作品のようですが、昨今のライトメロウ・ブームの中で再評価され、今ではそれなりに知名度を誇る作品となっています。内容的には完全にシティポップス。よく声質が似ていると指摘される竹内まりやの諸作と同じような感覚で聴ける極上の一枚に仕上がっています。井上鑑のペンによるミディアムテンポの冒頭A-1、「こんな優しい雨の日は」からシティポップス節全開。伊東ゆかりさん自体は本来、名実共に歌謡曲畑の人のはずなのですが、ここではシティポップスを完全に自分のものとして昇華しており、当時の新世代シンガーに少しも引けをとらない素晴らしい歌声を披露してくれます。そんな彼女の魅力が最も現れているのがアルバム中最も人気の高いB-2の「マリコ」。思い切り洋楽AORなアレンジと大人っぽい歌声が素晴らしいシティポップス屈指の一曲です。過ぎ去ってしまった青春時代に思いを馳せる歌詞も良い感じ。この雰囲気、30代以上の女性ならグッと来ること間違いなしでしょう。また個人的に気に入っているのはB-4の「再開レストラン」。別れた恋人同士が2年ぶりにレストランで再開するという大人のラブソングで、哀愁漂う展開が非常に魅力的なAORナンバーに仕上がっています。なおLP自体はそれほど極端にレアと言うわけではありませんが、近年の人気上昇の煽りを受け中古市場では比較的高めの相場で取引されているため、購入の際は慎重に。あまり売られているところを見たことはありませんが、もしかしたら専門店ではなく街の中古レコード屋で地道に探した方が幸せになれるかもしれません。
6年ほど前にLight Mellow's Choiceシリーズの一つとしてCDでもリイシューされたJ-AOR作品。楠木勇有行(ゆうこう)という別名義で、主にCM業界で活躍していたシンガーソングライターによる1985年のアルバムです。どうにも垢抜けないジャケットのせいもあってか、一部のJ-AOR愛好家を除けばほとんど知名度のないマニアックな作品ではありますが、完全に洋楽指向なその音作りのクォリティはなかなかに高く、日本人男性シンガーに抵抗がなければ無視するのは少しもったいない一枚。松下誠や芳野藤丸あたりのヴォーカルを違和感なく聴けるリスナーならば、トライしてみる価値のある作品かと思います。サウンド自体も松下誠の1stをもう少し都会寄りにシフトしたような雰囲気のフュージョン系AORなので、あの雰囲気が好きな人であればまず間違いないでしょう。冒頭から和製AORモード全開で都会の夜の雰囲気を醸し出すA-1のSugar Danceや、込み上げるメロディーがどことなくフリーソウル風なB-3のCome To Me Againなどは、この手のアーべインでライトメロウなJ-AORを好むファンなら確実に好きなはず。また個人的に気に入っているのはA-3のFor Our Love。LPに何曲か収録されている全英語詞ナンバーのうちの一つですが、メリッサ・マンチェスターのBad Weatherをもう少しディスコ寄りにシフトさせたような雰囲気で、非常に聴き易い一曲に仕上がっています。あいにくヴォーカル・ワーク自体は完全に日本人のそれなので、フリーソウル系のセットにさらっと組み込んでプレイするにはそれなりにハードルが高いかもしれませんが、自宅でまったりと聴く分には非常に魅力的なナンバーかと。ちなみにオリジナルのリリース元はKing。単に盤自体の知名度がないだけで、実はそれほど極端にレアな作品というわけではないので、気長に探していればそのうちひょっこり見つかるかと思います。実際、僕自身あまり労することなくオリジナルの帯付きLPを手に入れました。そんなわけで興味のある方は時々レコード屋の和モノ棚を探してみると幸せになれるかも。今ならCDもまだ探せば買えるようなので、まだ作品自体を知らないという方は良かったら是非聴いてみてください。