松江のシンボルでもある松江城内の一角に建つ洋風建築「興雲閣」は
建物が洋風、屋根が瓦葺きの疑似洋風建築で1903年(明治36)に完成した。
淡いグリーンがさわやかなこの建物は
「松江市工芸陳列所」として建設され、また明治天皇の行在所の目的として建てられたので
装飾が多く用いられ華やかな仕上げになっている。
しかし日露戦争により戦時色が濃くなったため明治天皇の巡行は実現せず
のち明治40年、皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)の山陰行啓のため改装し
嘉仁親王を迎えて迎賓館としての役目を果たした。
2階へと続く階段。

廊下(1階)

貴顕室(きけいしつ)(2階)

皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)が行啓の際に使用された部屋。
大広間(2階)

150人の収容が可能という広さ。コンサートなどにも使用される。
軒の周囲を飾る可愛いデザイン。

玄関の扉には松江市の徽章の文様。
円の輪郭は亀田山を、中は松葉が図案化されている。

1階には喫茶室が。

松江市工芸陳列所から興雲閣の名に改められたのは1909年(明治42)で
旧松江藩主・松平直亮氏により命名された。
現在は松江郷土館として一般公開されている。
1969年(昭和44)に島根県指定有形文化財に
2011年(平成23)に松江市歴史的風致形成建造物に指定された。
のち明治40年、皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)の山陰行啓のため改装し
嘉仁親王を迎えて迎賓館としての役目を果たした。
2階へと続く階段。

廊下(1階)

貴顕室(きけいしつ)(2階)

皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)が行啓の際に使用された部屋。
大広間(2階)

150人の収容が可能という広さ。コンサートなどにも使用される。
軒の周囲を飾る可愛いデザイン。

玄関の扉には松江市の徽章の文様。
円の輪郭は亀田山を、中は松葉が図案化されている。

1階には喫茶室が。

松江市工芸陳列所から興雲閣の名に改められたのは1909年(明治42)で
旧松江藩主・松平直亮氏により命名された。
現在は松江郷土館として一般公開されている。
1969年(昭和44)に島根県指定有形文化財に
2011年(平成23)に松江市歴史的風致形成建造物に指定された。

















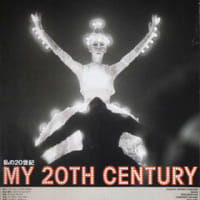


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます