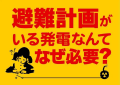乳牛はいつでも泌乳してくれるものではありません。ある一定の大きさになって、発情が来るようになり授精して妊娠して、臨月を迎えて分娩します。当たり前のことですが分娩しなければ泌乳しないのです。産まれてから初めての分娩まで、24~30カ月ほどかかります。母牛に受精するところから考えれば、さらに9カ月の時間がかかります。
他の農作物も計画しても一定の時間がかかりますが、乳牛は単純に考えるだけでも3年ほどの経過が必要になるのです。すぐに増産できないところに牛乳の大きな問題があります。
牛乳は鮮度が求められ、備蓄が基本的にできません。粉乳にしたりして乳飲料としての再生できる程度です。チーズやバターそれに、様々なものに転嫁するための粉乳などは、結果として備蓄ができる乳製品と言えます。
北海道の牛乳は、殆どが昨日記載しました一元集されて指定団体に集められ、目的別に加工されることになります。消費動向を見ながらできるという利点がありますが、農家側から見ると加工目的によって価格が異なるので、かなり複雑な構図になっています。
バター、チーズ、脱脂粉乳、生クリームそれに給食用と分けれれ多比率によって算出されたうえ、ここの酪農家の牛乳の成分と量によって、酪農家の受け取る牛乳価格が決められます。
乳牛は約13カ月間隔で分娩することになります。受胎しなければ、乳量は減ってきて淘汰されることになります。乳牛の病気はこのほぼ毎年繰り返される、分娩時にほとんどの病気の原因があると言われています。お産に係わるものだけではなく、乳房の炎症・乳房炎や繁殖に関する障害もこの時期に関係していると言われます。
搾乳は多くは一日2回行われます。この作業は欠かすことができません。牛を大事に扱う酪農家では、10産ほどはすることになります。酪農家は牛の個性や能力や、牛群内の力関係などを把握することになります。
大型でたくさんの乳牛を飼って、穀物を多給する高生産乳牛を抱える酪農家の乳牛は、平均で2.5回ほどで淘汰されます。牛に体がが生産に追い付かないので、受胎しなかったり乳房炎だったり、分娩時の障がいなどで淘汰されます。酪農家も個々の牛のことなど覚えていません。
酪農は現在、政府が推奨する大型農家が主流で多くの牛乳はこの環境で搾乳されています。つまり、コンクリートの床しか歩くことができない閉塞された空間で、大量の輸入穀物を給与された乳牛から搾った牛乳が主体なのです。乳牛を生命ある個体としてのアニマルフェアーの視点から牛を飼うべきと、私たちは提案しています。
酪農は忌避音的には手作業なのです。余りにもたくさんの牛を飼ったり、むやみに大量の穀物を給与して、乳牛に負担をかけるべきではないのです。有機農産物同様に、アニマルウエルフェアーに沿った使用環境には評価を与え、一定の価格帯になることは消費者の理解をいただきたいと思います。
他の農作物も計画しても一定の時間がかかりますが、乳牛は単純に考えるだけでも3年ほどの経過が必要になるのです。すぐに増産できないところに牛乳の大きな問題があります。
牛乳は鮮度が求められ、備蓄が基本的にできません。粉乳にしたりして乳飲料としての再生できる程度です。チーズやバターそれに、様々なものに転嫁するための粉乳などは、結果として備蓄ができる乳製品と言えます。
北海道の牛乳は、殆どが昨日記載しました一元集されて指定団体に集められ、目的別に加工されることになります。消費動向を見ながらできるという利点がありますが、農家側から見ると加工目的によって価格が異なるので、かなり複雑な構図になっています。
バター、チーズ、脱脂粉乳、生クリームそれに給食用と分けれれ多比率によって算出されたうえ、ここの酪農家の牛乳の成分と量によって、酪農家の受け取る牛乳価格が決められます。
乳牛は約13カ月間隔で分娩することになります。受胎しなければ、乳量は減ってきて淘汰されることになります。乳牛の病気はこのほぼ毎年繰り返される、分娩時にほとんどの病気の原因があると言われています。お産に係わるものだけではなく、乳房の炎症・乳房炎や繁殖に関する障害もこの時期に関係していると言われます。
搾乳は多くは一日2回行われます。この作業は欠かすことができません。牛を大事に扱う酪農家では、10産ほどはすることになります。酪農家は牛の個性や能力や、牛群内の力関係などを把握することになります。
大型でたくさんの乳牛を飼って、穀物を多給する高生産乳牛を抱える酪農家の乳牛は、平均で2.5回ほどで淘汰されます。牛に体がが生産に追い付かないので、受胎しなかったり乳房炎だったり、分娩時の障がいなどで淘汰されます。酪農家も個々の牛のことなど覚えていません。
酪農は現在、政府が推奨する大型農家が主流で多くの牛乳はこの環境で搾乳されています。つまり、コンクリートの床しか歩くことができない閉塞された空間で、大量の輸入穀物を給与された乳牛から搾った牛乳が主体なのです。乳牛を生命ある個体としてのアニマルフェアーの視点から牛を飼うべきと、私たちは提案しています。
酪農は忌避音的には手作業なのです。余りにもたくさんの牛を飼ったり、むやみに大量の穀物を給与して、乳牛に負担をかけるべきではないのです。有機農産物同様に、アニマルウエルフェアーに沿った使用環境には評価を与え、一定の価格帯になることは消費者の理解をいただきたいと思います。













 左の表はFAO(国連食糧機構)が発表した穀物生産量と価格動向である。
左の表はFAO(国連食糧機構)が発表した穀物生産量と価格動向である。 昨年一昨年と私たちの地域の酪農は、まるでバブルが起きたように好景気でした。政府の様々な財政支援もあるりますが、なんといっても世界的な牛肉不足が背景にあります。単純ではないが、大きな要因は中国です。裕になった中国が突如として牛肉を、世界各地で買い漁るようになったのである。世界的な牛肉の不足が起きている。それが牛肉価格を釣りあげる。結果日本の酪農家が潤うというのです。
昨年一昨年と私たちの地域の酪農は、まるでバブルが起きたように好景気でした。政府の様々な財政支援もあるりますが、なんといっても世界的な牛肉不足が背景にあります。単純ではないが、大きな要因は中国です。裕になった中国が突如として牛肉を、世界各地で買い漁るようになったのである。世界的な牛肉の不足が起きている。それが牛肉価格を釣りあげる。結果日本の酪農家が潤うというのです。 北海道では農民の減少が深刻です。限界集落があちこちにあります。私たちの町のように、乳量が増えることばかりを追求してきましたが、本当は人が増えることを求めなければならなかったのではないか。そうしたことが、若い人を都会へと後押しするようになった。酪農が順調であるからこそ離農者が増える現実に複雑な気持ちである。
北海道では農民の減少が深刻です。限界集落があちこちにあります。私たちの町のように、乳量が増えることばかりを追求してきましたが、本当は人が増えることを求めなければならなかったのではないか。そうしたことが、若い人を都会へと後押しするようになった。酪農が順調であるからこそ離農者が増える現実に複雑な気持ちである。

 列車で札幌往復する機会があって、一冊の本を読んだ「食料と人類」(飢餓を克服した大増産の文明史)ルース・ドフリーシ著 日本経済新聞社刊 2,400円である。著者はコロンビア大学教授で専門は生体・進化・環境生物学と訳者の小川敏子氏が紹介しているが、やや専門の内容が冗漫になるきらいはあるが、食料生産を人類の発展の基盤にした視点は正しいであろう。
列車で札幌往復する機会があって、一冊の本を読んだ「食料と人類」(飢餓を克服した大増産の文明史)ルース・ドフリーシ著 日本経済新聞社刊 2,400円である。著者はコロンビア大学教授で専門は生体・進化・環境生物学と訳者の小川敏子氏が紹介しているが、やや専門の内容が冗漫になるきらいはあるが、食料生産を人類の発展の基盤にした視点は正しいであろう。
 左のグラフは今月に発表された、国連のFAO(食糧機構)の発表したものである。
左のグラフは今月に発表された、国連のFAO(食糧機構)の発表したものである。 昨年5月フランスでスーパーマーケットの賞味期限切れ食品の廃棄が法的に禁止されたが、今月5日から実施されることになった。廃棄されるはずだった食品はフードバンク(品質に問題がない食品を生活困窮者などに配給するシステム)などの援助機関に回され、必要とする人々に配られる。これによって、毎年数百万人に無料の食事を提供できるようになるという。
昨年5月フランスでスーパーマーケットの賞味期限切れ食品の廃棄が法的に禁止されたが、今月5日から実施されることになった。廃棄されるはずだった食品はフードバンク(品質に問題がない食品を生活困窮者などに配給するシステム)などの援助機関に回され、必要とする人々に配られる。これによって、毎年数百万人に無料の食事を提供できるようになるという。