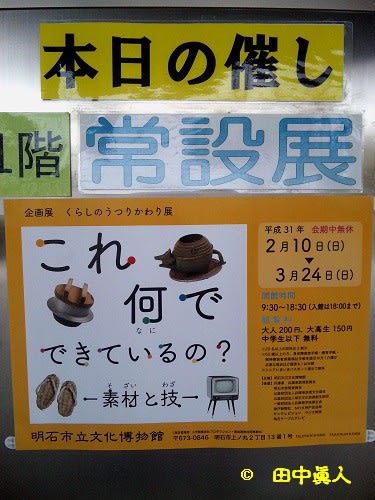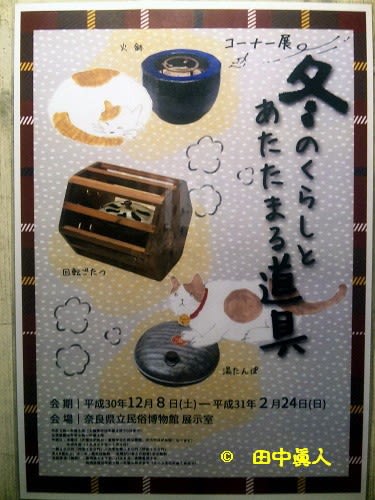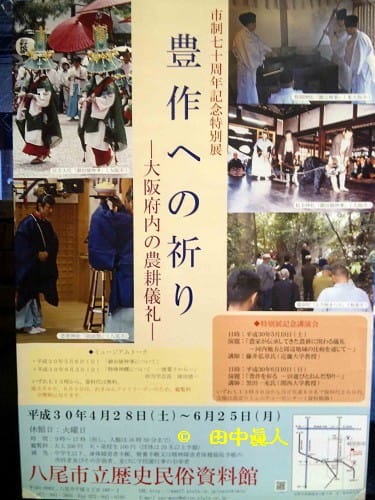昭和56年8月8日、大阪市内から奈良県大和郡山市に転居。
身近なところに自然が多く見られる大和郡山。
城下町から少し離れた地域に住んだ。
当時はまだ、コンクリート護岸をしていない富雄川から西に拡がる田園地。
どちらにお住まいですかと聞かれたら、高専に近いですと答えていた。
高専は奈良高専。
正式名称は、独立行政法人 国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校である。
その高専から少し歩けば、戦後しばらくまでは奈良県農業経営者伝習農場・特産種苗農場があった。
取材地先に尋ねた人生の先輩、先駆者の人たち。
そう、そこで学び、卒業し、地元で耕作している多くの人に出合うこと度々・・。
その伝習農場跡地にできたのが、奈良県立大和民俗公園である。
昭和50年、都市計画決定を受け、整備。
昭和49年11月10日、奈良県県立民俗博物館は、先に開館した。
公園内には、3棟の国重要文化財、10棟の県指定文化財を含む県内各地の特色をもった代表的民家を復元移築。
移築してから早や45年・・。
移築民家は、経年劣化的損傷もあるが、近年はアライグマなどに代表される動物による損壊が増えつつある。
今回、3年計画で実施された県内でも珍しい「杉皮葺き屋根」5棟の葺き替え工事を・・。
公園最奥に建つ「旧前坊住宅」を2年間にわたる葺き替え工事を終え、それを記念に、普段では見学もできなかった”渡り廊下”や”離れ座敷”に、続いて葺き替え工事を計画している「旧木村家住宅・主屋」も内部を公開された。
公開日は、令和3年3月6日、7日の両日。6日は都合つかず、本日いちばんの時間帯に見学させてもらった。
実は、「旧前坊家杉皮屋根葺き替え工事現場公開見学」は、今回が初めてではなく、令和2年2月15日(土)、17日(日)もあった。
工事初期の段階だけに、工事の足場利用の見学であった。
同年の11月21日(土)、22日(日)も、足場利用の見学会。
いずれも出かける日程が合わなかったが、今回こそ見逃さず、機会も失わず・・・いよいよ拝見できる建物内部にわくわくしていた。
県立民俗博物館に足しげく出入りするようになったのは、平成15年2月7日。
桜井市三輪で行われた恵比須神社の初えびす・御湯の神事の際に出合った現奈良民俗文化研究所代表の鹿谷勲氏がキッカケ。
当時の職場は、奈良県県立民俗博物館。
一度、職場訪問をしてほしいと願われたのが発端だった。
住まいする地域が大和郡山市内。
奈良県県立民俗博物館も同じく大和郡山市内。
その後、博物館が所在する大和郡山市内にある民俗行事を調査してほしい、というお願いである。
調査のすべてが終ったわけではないが、ごくごく一部の行事調査を終えて写真展を特別に開催する運びとなったのは、お願いされてから6年も経った平成21年10月に2度目開催の「大和郡山の祭りと行事」写真展だった。
それから1年後の平成22年8月。
大和民俗公園内施設の古民家を撮ってほしいというお願い。
総務課の依頼であるが、学芸課から伝えられた撮影指定の古民家は、宇陀・東山集落。
夏、真っ盛りの日に撮影は忍耐どころではない。
ほとばしる汗に難儀した。
撮影した古民家は、翌9月に発行された古民家ポスターに採用された。
その撮影依頼にすべての古民家を巡っていたが、屋内の風情を撮れる民家と、閉鎖され内部を観ることさえ不能だった民家がある。
それが、今回初の内部特別公開された「旧前坊家」。
実は、大和民俗公園は、それ以前から、大和郡山市少年自然の家主催事業の親子観察会に参加していたことから存じていた。
自然観察の場は、時季によって場を替えるが、主に矢田山丘陵地。
里山や矢田山を巡る自然観察会は、自然がいっぱいある大和民俗公園もフィールド地。
春は春に、秋は秋の自然形態が観察できる格好の公園に自然観察会。
蕨がいっぱい出ていた場所は、吉野建て住居が建つすぐ近くだった。
観察会から気持ちが離れ、手が勝手に動いた蕨取り。
その日の食卓に味わったこともある思い出の地。
そのことはともかく、何度も吉野建て住居をみているのだが、入室ができない状態だった。

春には真っ赤なボケの花がここに咲く。
また、しめ縄に欠かせないユズリハも観察対象にあったが、入室は不可の「旧前坊家」。
外観を眺めるしかできなかった。
この1年を待つどころか、おおかた20年以上も見ることができなかった「旧前坊家」の内部を見せていただける。
こんな機会は、もうないかもしれない。
県立民俗博物館の担当者に伝えていた見学希望である。
見学時間は、午前10時より。
その日、同じように拝見したく訪れると伝えていた写真家のSさんとともに拝見する内部公開に先客が1組のご夫婦。
愉しみにしてらしていたそうだ。
「旧前坊家」は、大和民俗公園の入り口ゲートから、最奥の場にある。
距離にしておよそ700メートルであろう。
この日と昨日の6日は、主催事業の「梅まつり」。・・・終了しました
ご家族、子どもたちにも楽しんでもらう盛りだくさんのイベントがある。
特に子供たちが競い合って、駆け付けるスタンプラリー。
9つのスタンプを集めても景品はない。
それでもスタンプを押してもらって、梅の花が満開になる達成感にご満悦だ。
古民家入口の扉は木製。
開園日に開く木製扉を抜けたそこは、町家集落エリア。
ちなみに博物館学芸課が作成した、見て、読み、学ぶ「古民家たんけんブック」が役立つ。
左側に大和高田市英和町にあった旧鹿沼家住宅が。

右手に茅葺民家の旧臼井家住宅が。
雨戸に障子は、いつも開けている高取町上土佐にあった旧臼井家住宅。
2月13日から本日まで展示していた古民家ひなまつり。

座敷にのぼって撮影する人多し。
お雛さんの被写体とともに映り込むイベントはいつも賑わっている。
さらに歩いたところに建っているのが国中集落エリア。
はじめに行きつく古民家が、橿原市中町にあった旧吉川家。

この時季に咲く白梅入れて撮ってしまう茅葺民家。
外観の佇まいがなんともいえない情感を醸し出す。
その向こう側にある茅葺民家が2棟。

手前が香芝市狐井にあった旧赤土家の離れ。
その向こうが、桜井市の大字・下(しも)にあった茅葺民家の旧萩原家。
平成29年、30年、31年に亘った工事。
およそ40年ぶりに、経年劣化していた茅葺屋根を全面的に修復、公開され、活用することになった令和元年の時代。
その先に建つ古民家は、宇陀・東山集落エリア。
国中集落エリアから歩くはじめの数十メートルは、なだらかな坂道。
カーブ道からは、やや高くなる急坂道。
県立民俗博物館の所在地。
奈良県大和郡山市矢田町545のアドレスをクリックしたマップファン地図では、その高低差は見えないが、古民家それぞれの位置が地図上に出現する。
まずは、八重川家住宅。

元の所在地は、旧都祁村の針。
現在は奈良市針町にあたる地にあった。
旧八重川家住宅からすぐ横に建つ。
かつては室生村の黒岩(※現在は宇陀市室生黒岩)にあった旧岩本家住宅が目に入る。
いずれも茅葺古民家。重厚な造りに圧倒されそうになる。
数十メートルも歩いたら、すぐわかる古民家は、同じく旧室生村の上笠間(※現在は宇陀市室生上笠間)にあった旧松井家住宅。
今回、目的地の吉野建て住宅は、もうすぐだ。

旧松井家住宅から向こう岸に見える2棟の建物。
下って、登る、まるで谷あいのような感覚に陥る道。
逆にいえば、カメラアイから、つい撮りたくなる構図がとれる3棟の位置である。
ようやく着いた吉野集落エリア。
右手に建つ古民家は、かつて十津川村旭の迫が所在地だった。
急斜面、山間地特有の建物構造。
山深い峡谷の地である。
その向かいに建つのが目的地の「旧前坊家」。
吉野山の門前町筋。
金峯山寺仁王門と銅鳥居の発心門の中ほど。
代々の当主は、吉野水分神社の神官を勤めたと伝わる「旧前坊家」は2階建て構造。
「旧前坊家」以外は、すべてが平屋構造であるが、「旧前坊家」だけが2階建て。
なぜに2階建てなのか・・。
それは後述する、として、参照していたマップファン地図には、「旧前坊家」が、プロットされていない。
不思議なことであるが、うすうす感じる公開のあり方が関係しているのだろうか。
と、いうのも大和郡山に転居し、県立民俗博物館・大和民俗公園に訪れるようになったが、未だに旧前坊家の扉が開いている状態を見たことがない。
窓も開いていないから、建物の外観を見るだけだ。
念のため調べてみたゼンリン住宅地図に、古民家表記はない。
ヤフー地図も、Goo地図もないが、マピオン地図にあった。
ところが、妙なことがわかった。
マップファン地図には、「旧前坊家」が、プロットされていないが、旧木村家はある。
逆に、マピオン地図では、「旧前坊家」はプロットされているが、旧木村家はない。
また、旧鹿沼家住宅も表記なし。
どっちもどっち、のような、いずれも精細に欠ける地図表記だとわかった。
(R3. 3. 7 SB805SH撮影)
身近なところに自然が多く見られる大和郡山。
城下町から少し離れた地域に住んだ。
当時はまだ、コンクリート護岸をしていない富雄川から西に拡がる田園地。
どちらにお住まいですかと聞かれたら、高専に近いですと答えていた。
高専は奈良高専。
正式名称は、独立行政法人 国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校である。
その高専から少し歩けば、戦後しばらくまでは奈良県農業経営者伝習農場・特産種苗農場があった。
取材地先に尋ねた人生の先輩、先駆者の人たち。
そう、そこで学び、卒業し、地元で耕作している多くの人に出合うこと度々・・。
その伝習農場跡地にできたのが、奈良県立大和民俗公園である。
昭和50年、都市計画決定を受け、整備。
昭和49年11月10日、奈良県県立民俗博物館は、先に開館した。
公園内には、3棟の国重要文化財、10棟の県指定文化財を含む県内各地の特色をもった代表的民家を復元移築。
移築してから早や45年・・。
移築民家は、経年劣化的損傷もあるが、近年はアライグマなどに代表される動物による損壊が増えつつある。
今回、3年計画で実施された県内でも珍しい「杉皮葺き屋根」5棟の葺き替え工事を・・。
公園最奥に建つ「旧前坊住宅」を2年間にわたる葺き替え工事を終え、それを記念に、普段では見学もできなかった”渡り廊下”や”離れ座敷”に、続いて葺き替え工事を計画している「旧木村家住宅・主屋」も内部を公開された。
公開日は、令和3年3月6日、7日の両日。6日は都合つかず、本日いちばんの時間帯に見学させてもらった。
実は、「旧前坊家杉皮屋根葺き替え工事現場公開見学」は、今回が初めてではなく、令和2年2月15日(土)、17日(日)もあった。
工事初期の段階だけに、工事の足場利用の見学であった。
同年の11月21日(土)、22日(日)も、足場利用の見学会。
いずれも出かける日程が合わなかったが、今回こそ見逃さず、機会も失わず・・・いよいよ拝見できる建物内部にわくわくしていた。
県立民俗博物館に足しげく出入りするようになったのは、平成15年2月7日。
桜井市三輪で行われた恵比須神社の初えびす・御湯の神事の際に出合った現奈良民俗文化研究所代表の鹿谷勲氏がキッカケ。
当時の職場は、奈良県県立民俗博物館。
一度、職場訪問をしてほしいと願われたのが発端だった。
住まいする地域が大和郡山市内。
奈良県県立民俗博物館も同じく大和郡山市内。
その後、博物館が所在する大和郡山市内にある民俗行事を調査してほしい、というお願いである。
調査のすべてが終ったわけではないが、ごくごく一部の行事調査を終えて写真展を特別に開催する運びとなったのは、お願いされてから6年も経った平成21年10月に2度目開催の「大和郡山の祭りと行事」写真展だった。
それから1年後の平成22年8月。
大和民俗公園内施設の古民家を撮ってほしいというお願い。
総務課の依頼であるが、学芸課から伝えられた撮影指定の古民家は、宇陀・東山集落。
夏、真っ盛りの日に撮影は忍耐どころではない。
ほとばしる汗に難儀した。
撮影した古民家は、翌9月に発行された古民家ポスターに採用された。
その撮影依頼にすべての古民家を巡っていたが、屋内の風情を撮れる民家と、閉鎖され内部を観ることさえ不能だった民家がある。
それが、今回初の内部特別公開された「旧前坊家」。
実は、大和民俗公園は、それ以前から、大和郡山市少年自然の家主催事業の親子観察会に参加していたことから存じていた。
自然観察の場は、時季によって場を替えるが、主に矢田山丘陵地。
里山や矢田山を巡る自然観察会は、自然がいっぱいある大和民俗公園もフィールド地。
春は春に、秋は秋の自然形態が観察できる格好の公園に自然観察会。
蕨がいっぱい出ていた場所は、吉野建て住居が建つすぐ近くだった。
観察会から気持ちが離れ、手が勝手に動いた蕨取り。
その日の食卓に味わったこともある思い出の地。
そのことはともかく、何度も吉野建て住居をみているのだが、入室ができない状態だった。

春には真っ赤なボケの花がここに咲く。
また、しめ縄に欠かせないユズリハも観察対象にあったが、入室は不可の「旧前坊家」。
外観を眺めるしかできなかった。
この1年を待つどころか、おおかた20年以上も見ることができなかった「旧前坊家」の内部を見せていただける。
こんな機会は、もうないかもしれない。
県立民俗博物館の担当者に伝えていた見学希望である。
見学時間は、午前10時より。
その日、同じように拝見したく訪れると伝えていた写真家のSさんとともに拝見する内部公開に先客が1組のご夫婦。
愉しみにしてらしていたそうだ。
「旧前坊家」は、大和民俗公園の入り口ゲートから、最奥の場にある。
距離にしておよそ700メートルであろう。
この日と昨日の6日は、主催事業の「梅まつり」。・・・終了しました
ご家族、子どもたちにも楽しんでもらう盛りだくさんのイベントがある。
特に子供たちが競い合って、駆け付けるスタンプラリー。
9つのスタンプを集めても景品はない。
それでもスタンプを押してもらって、梅の花が満開になる達成感にご満悦だ。
古民家入口の扉は木製。
開園日に開く木製扉を抜けたそこは、町家集落エリア。
ちなみに博物館学芸課が作成した、見て、読み、学ぶ「古民家たんけんブック」が役立つ。
左側に大和高田市英和町にあった旧鹿沼家住宅が。

右手に茅葺民家の旧臼井家住宅が。
雨戸に障子は、いつも開けている高取町上土佐にあった旧臼井家住宅。
2月13日から本日まで展示していた古民家ひなまつり。

座敷にのぼって撮影する人多し。
お雛さんの被写体とともに映り込むイベントはいつも賑わっている。
さらに歩いたところに建っているのが国中集落エリア。
はじめに行きつく古民家が、橿原市中町にあった旧吉川家。

この時季に咲く白梅入れて撮ってしまう茅葺民家。
外観の佇まいがなんともいえない情感を醸し出す。
その向こう側にある茅葺民家が2棟。

手前が香芝市狐井にあった旧赤土家の離れ。
その向こうが、桜井市の大字・下(しも)にあった茅葺民家の旧萩原家。
平成29年、30年、31年に亘った工事。
およそ40年ぶりに、経年劣化していた茅葺屋根を全面的に修復、公開され、活用することになった令和元年の時代。
その先に建つ古民家は、宇陀・東山集落エリア。
国中集落エリアから歩くはじめの数十メートルは、なだらかな坂道。
カーブ道からは、やや高くなる急坂道。
県立民俗博物館の所在地。
奈良県大和郡山市矢田町545のアドレスをクリックしたマップファン地図では、その高低差は見えないが、古民家それぞれの位置が地図上に出現する。
まずは、八重川家住宅。

元の所在地は、旧都祁村の針。
現在は奈良市針町にあたる地にあった。
旧八重川家住宅からすぐ横に建つ。
かつては室生村の黒岩(※現在は宇陀市室生黒岩)にあった旧岩本家住宅が目に入る。
いずれも茅葺古民家。重厚な造りに圧倒されそうになる。
数十メートルも歩いたら、すぐわかる古民家は、同じく旧室生村の上笠間(※現在は宇陀市室生上笠間)にあった旧松井家住宅。
今回、目的地の吉野建て住宅は、もうすぐだ。

旧松井家住宅から向こう岸に見える2棟の建物。
下って、登る、まるで谷あいのような感覚に陥る道。
逆にいえば、カメラアイから、つい撮りたくなる構図がとれる3棟の位置である。
ようやく着いた吉野集落エリア。
右手に建つ古民家は、かつて十津川村旭の迫が所在地だった。
急斜面、山間地特有の建物構造。
山深い峡谷の地である。
その向かいに建つのが目的地の「旧前坊家」。
吉野山の門前町筋。
金峯山寺仁王門と銅鳥居の発心門の中ほど。
代々の当主は、吉野水分神社の神官を勤めたと伝わる「旧前坊家」は2階建て構造。
「旧前坊家」以外は、すべてが平屋構造であるが、「旧前坊家」だけが2階建て。
なぜに2階建てなのか・・。
それは後述する、として、参照していたマップファン地図には、「旧前坊家」が、プロットされていない。
不思議なことであるが、うすうす感じる公開のあり方が関係しているのだろうか。
と、いうのも大和郡山に転居し、県立民俗博物館・大和民俗公園に訪れるようになったが、未だに旧前坊家の扉が開いている状態を見たことがない。
窓も開いていないから、建物の外観を見るだけだ。
念のため調べてみたゼンリン住宅地図に、古民家表記はない。
ヤフー地図も、Goo地図もないが、マピオン地図にあった。
ところが、妙なことがわかった。
マップファン地図には、「旧前坊家」が、プロットされていないが、旧木村家はある。
逆に、マピオン地図では、「旧前坊家」はプロットされているが、旧木村家はない。
また、旧鹿沼家住宅も表記なし。
どっちもどっち、のような、いずれも精細に欠ける地図表記だとわかった。
(R3. 3. 7 SB805SH撮影)