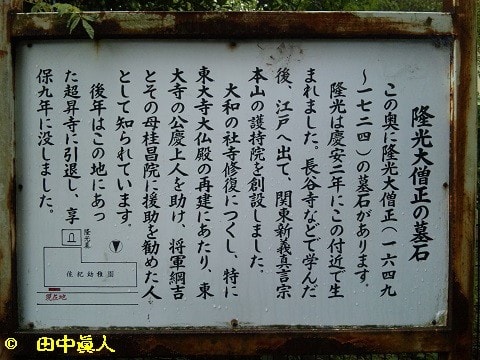この日はとにかくあちこちで地蔵盆がある。
どこへ行くかは選択肢が多すぎて迷いに迷う。
なんせ、在住地の大和郡山市内では7月にも8月にも地蔵盆がある。
7月は22地区で、8月は39地区にもおよぶ。
尤も大和郡山市内の地蔵尊は119地区にあるが・・・。
比率は大和郡山市内とは異なるが、7月、8月分かれの地蔵盆は天理市も奈良市もあるし、下市もそのような状況であることは認識している。
地域で行われる年中行事の中では最も多い行事が地蔵盆ではないだろうか。
それだけにどこを取材するか、実に悩まされる選択である。
大和郡山市内だけでも未だ40地区しか取材ができていない。
そこを振り切って出かけた目的地は奈良市の帯解地域。
かつて奈良市今市町帯解寺の子安地蔵会式や、そこより街道を南に下った奈良市柴屋町龍象寺の地蔵会式を拝見したことがある。
街道には夜店もたくさん並んで賑わいの地蔵盆に人々がごった返す。
その街道を東西に走る旧街道(五ケ谷街道)がある。
朱塗りの鳥居を挟んだ街道向こうに地蔵さんが目に入った。
鳥居がある神社は今市の春日神社。
今夕の子安地蔵会式の出発地である、その真ん前にあった地蔵さんを祀る祠の天井に提灯がぎっしり。
なんぼほど、あるんや、と声が出てしまうほどに多い吊り提灯に圧倒される。
奥には塔婆が数本ある地蔵尊は福徳延命地蔵尊。
野菜などのお供えがあった、その場に丸めたゴザがあった。
行事は終わったのか、それとも未だなのか。
尋ねてみる時間的余裕はないが、なんとなく念仏講の営みを想像してみた。
今市には「コネンブツ講」と呼ばれている講中がいる。
これまで公民館で行われる7月地蔵盆の数珠繰りやチバミ墓地内で行われる春彼岸の数珠繰りを取材したことがあるが、ここ福徳延命地蔵尊でもしているとは聞いていない。
別の講があるのか、それとも地区婦人会がされているのか、一度訪ねてみたい。
東西に抜ける街道を走る。
奈良市今市の一番西の集落外れに地蔵尊がある。
そこは通る度によく参拝者を目撃する。
高齢の婦人であるが、お顔は見る度に違うように思えてならない。
思わず車を停めて話しを聞いてみたいと思っては思うが、一瞬にして思いは消える。
そこから東へ、東へと行けば前回に紹介した福徳延命地蔵尊に巡りあえる。
そこよりもう少し行けば、JR桜井線を跨ぐ鉄橋越え。
最寄りの駅は右手にある帯解駅。無人駅である。
さらに東へ行けば古来は上ツ道と呼ばれていた南北に貫く旧街道(初瀬街道の名もある上街道)にでる。
さらに東に向けて走る。
それほど遠くない距離。
左手に地蔵尊がある。
そこもお供えをしているが、先を急ぐ。
もう一つは山町の八坂神社裏にある地蔵さんである。

お供えは採れたてと思われる野菜盛り。
白色のゴーヤに長茄子。
ピーマンに赤パプリカに、これまた赤いトマト。
仏花も飾って奉っていた。
それを拝見していたときのことだ。
南側にある道から一輪車を動かす男性の顔が見えた。
畑で収穫した帰り道に遭遇した男性は実に久しぶり。
長年において関わっている自然観察会でたいへんお世話になっていたY先生だった。
しばらくぶりに地蔵さんの前で立ち話。
お顔も喋りもお元気になられてはいるものの、見た目では気がつかない息苦しさを話してくださるのが辛い。
病いの状態は違うが、わが身もそうだけに辛さは共有できる。
愛鳥会も退いて、今は朝、夕の畑に孫の送迎だけの暮らしにしているそうだが、来年2月の馬見丘陵の観察会は一緒に行動できそうだといわれる。
「無理しやんといてください」と伝えて別れた。
(H29. 7.23 SB932SH撮影)
どこへ行くかは選択肢が多すぎて迷いに迷う。
なんせ、在住地の大和郡山市内では7月にも8月にも地蔵盆がある。
7月は22地区で、8月は39地区にもおよぶ。
尤も大和郡山市内の地蔵尊は119地区にあるが・・・。
比率は大和郡山市内とは異なるが、7月、8月分かれの地蔵盆は天理市も奈良市もあるし、下市もそのような状況であることは認識している。
地域で行われる年中行事の中では最も多い行事が地蔵盆ではないだろうか。
それだけにどこを取材するか、実に悩まされる選択である。
大和郡山市内だけでも未だ40地区しか取材ができていない。
そこを振り切って出かけた目的地は奈良市の帯解地域。
かつて奈良市今市町帯解寺の子安地蔵会式や、そこより街道を南に下った奈良市柴屋町龍象寺の地蔵会式を拝見したことがある。
街道には夜店もたくさん並んで賑わいの地蔵盆に人々がごった返す。
その街道を東西に走る旧街道(五ケ谷街道)がある。
朱塗りの鳥居を挟んだ街道向こうに地蔵さんが目に入った。
鳥居がある神社は今市の春日神社。
今夕の子安地蔵会式の出発地である、その真ん前にあった地蔵さんを祀る祠の天井に提灯がぎっしり。
なんぼほど、あるんや、と声が出てしまうほどに多い吊り提灯に圧倒される。
奥には塔婆が数本ある地蔵尊は福徳延命地蔵尊。
野菜などのお供えがあった、その場に丸めたゴザがあった。
行事は終わったのか、それとも未だなのか。
尋ねてみる時間的余裕はないが、なんとなく念仏講の営みを想像してみた。
今市には「コネンブツ講」と呼ばれている講中がいる。
これまで公民館で行われる7月地蔵盆の数珠繰りやチバミ墓地内で行われる春彼岸の数珠繰りを取材したことがあるが、ここ福徳延命地蔵尊でもしているとは聞いていない。
別の講があるのか、それとも地区婦人会がされているのか、一度訪ねてみたい。
東西に抜ける街道を走る。
奈良市今市の一番西の集落外れに地蔵尊がある。
そこは通る度によく参拝者を目撃する。
高齢の婦人であるが、お顔は見る度に違うように思えてならない。
思わず車を停めて話しを聞いてみたいと思っては思うが、一瞬にして思いは消える。
そこから東へ、東へと行けば前回に紹介した福徳延命地蔵尊に巡りあえる。
そこよりもう少し行けば、JR桜井線を跨ぐ鉄橋越え。
最寄りの駅は右手にある帯解駅。無人駅である。
さらに東へ行けば古来は上ツ道と呼ばれていた南北に貫く旧街道(初瀬街道の名もある上街道)にでる。
さらに東に向けて走る。
それほど遠くない距離。
左手に地蔵尊がある。
そこもお供えをしているが、先を急ぐ。
もう一つは山町の八坂神社裏にある地蔵さんである。

お供えは採れたてと思われる野菜盛り。
白色のゴーヤに長茄子。
ピーマンに赤パプリカに、これまた赤いトマト。
仏花も飾って奉っていた。
それを拝見していたときのことだ。
南側にある道から一輪車を動かす男性の顔が見えた。
畑で収穫した帰り道に遭遇した男性は実に久しぶり。
長年において関わっている自然観察会でたいへんお世話になっていたY先生だった。
しばらくぶりに地蔵さんの前で立ち話。
お顔も喋りもお元気になられてはいるものの、見た目では気がつかない息苦しさを話してくださるのが辛い。
病いの状態は違うが、わが身もそうだけに辛さは共有できる。
愛鳥会も退いて、今は朝、夕の畑に孫の送迎だけの暮らしにしているそうだが、来年2月の馬見丘陵の観察会は一緒に行動できそうだといわれる。
「無理しやんといてください」と伝えて別れた。
(H29. 7.23 SB932SH撮影)