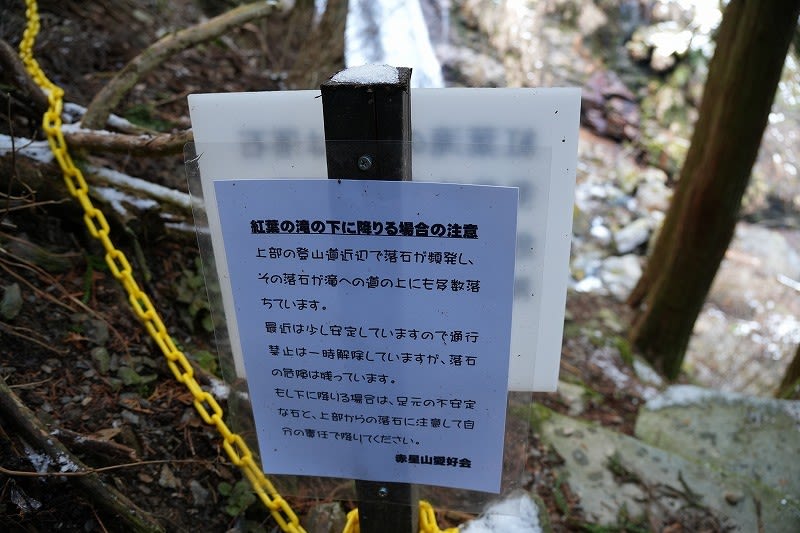今週は休みが水・木と取れそうなので奥様に相談したところ、残念なことに奥様の休みが取れる木曜日はどうも
天気が良くない。仕方がないので『水曜日に休んで、お山に行きます!』と宣言したもののあまりご機嫌が良く
ない。『それじゃ白鳥の河津桜が見頃のようなので、出勤前にささっと朝活する?』と聞いてみると、途端にご
機嫌がよくなった。私としては朝陽の当たった桜の花をきれいに撮ってみたいと思っていたので、しめしめ一石
二鳥で出かけてきた。ところが昨日からの大量の黄砂で、太陽も霞んでいる。桜の花に当たる光も薄くて弱い。


それでも奥様はスマホを持ってずっと熱心に写真や動画を撮って大満足のご様子。取りあえずこれで遠慮なくお
山に出かけられる。そう思いながら家まで奥様を送り届けた。


今日のお目当てはまんのう町の久保谷のユキワリイチゲとアワコバイモ。先日山友のお三人さんが出かけていた
し、YAMAPでも活動日記で目に付くようになった。国道438号線を南下する。朝活でいつもより早めに朝
ごはんを食べたせいか、途中で少し小腹が空いてきた。ちょうど9時前、あの三嶋製麺所が開く時間だ。
いつものように素っ気ない態度で注文を聞かれ、いつものように揚げたてのうどんを頂く。店主の態度は別にし
て、いつ食べても大満足の味だ。今朝は店の奥に座っているおばあちゃんにも会えた。

国道沿いの駐車場にはすでに5~6台の車が停まっていた。直ぐには数台また車が入ってきた。明神川を挟んで
橋を渡った大師堂の前が登山口になる。お目当ての花たちはお昼ごろから花を開かせるので、今日はのんびりゆ
っくり歩くことにしてスタートする。


この道沿いには峠越えの安全を祈願して三頭神社までに、西国三十三ケ寺の石仏を建てられている。ただ最初に
目についた落ち葉に埋もれかけたこの二番・三井寺というのが腑に落ちない。西国三十三ケ寺の二番は金剛宝寺
となっている。

先週の皇子渓谷に比べるとこの谷合をながれる水の量は少なく迫力に欠けるが、狭い谷の両岸には荒々しい柱状
節理が露出して、時には目の前にまで迫ってくる。


お目当ての花はどうやら朝が苦手なようだ。まるでどこかの奥様の様だ。所々で咲く花はまだ花弁を開かせてい
ない。


この谷筋は何度も何度も渡渉して右岸、左岸への移動を繰り返す。今日は水の量も少ないのでそれこそ10歩ほ
どで渡って行ける。すると前から声が聞こえてきた。しばらく歩くと女性が二人、スマホで熱心に写真を撮って
いた。片方の女性のザックのサイドポケットには見覚えのある可愛らしいぬいぐるみを入れていたが、YAMA
Pで見かけた人だったような気がしたが、はっきりとは思い出せない。



左岸を歩いていると落ち葉が積もった斜面で、今日のもう一つのお目当てが見つかった。周りの落ち葉とほぼ同
色のこの花は見つけるのに一苦労する。そこから右岸に移ると今度はユキワリイチゲの群生。といってもここの
子たちもまだまだお眠のようだ。



南東に向かって続いていた道がさらに東に向き始めると、いよいよこの谷も大詰めになってくる。昨年来た時は
最後の折れ曲がりの上部辺りが伐採されていたが、今日はずっと手前の左岸の上も伐採されていた。
谷の上部が伐採されて降雨の後に流れ出す水の量とか変われば、この谷の環境は変わってしまわないだろうか?



花を探しながらゆっくりと登ってきたが、1時間ほどで三頭越に着いた。峠には人の姿はなく、駐車場に停まっ
ていた車の人たちは、すでに三頭山に向かっているのだろう。徳島側からは金毘羅参りで、香川側からは金毘羅
の奥の院といわれる三頭神社の参道として賑わい、峠には当時は茶屋もあったという。そして昭和初期には80
00頭近くの借耕牛が行き来をして賑わっていた峠も、今は立派な鳥居と二体の石仏に見守られるだけの静かな
峠になっている。



いつものよう天細女命さんの胸にタッチすると、対面に鎮座する猿田彦さんは苦虫を嚙み潰したような顔をして
睨みつけていた。


峠からはヒノキの林の中を三頭山へと向かって行く。なだらかな坂道を下って行くとWOC登山部の女性メンバー
にバッタリ遭遇。二人ともお久しぶりで話が弾む。そして朝活で奥様サービスをした話をすると、『うんうん老
後の面倒見てもらわないかんのやから、奥様へのサービスは大事大事』と言われた。膝の具合も聞かれ『無理せ
ず自分のペースで歩いたらいい』と言ってもらった。
花粉症で鼻がぐじゅぐじゅという二人と分かれてしばらく歩くと舗装路に出た。


舗装路にでて直ぐに森の見晴らし台の広場になる。そこから少し歩くと下草の刈られたハンググライダー場。
少し小高い丘に向かって坂道を登って行くと360度の眺望。北には阿讃山脈の稜線と竜王山。麓には四国三郎
の吉野川が黄砂で霞んだ中でもその流れが見える。
それにしても風が強い。この強い風の中に黄色い砂が混じっていると思うとゾッとした。景色のいいこの場所で
お昼ご飯をと思っていたがとんでもなかった。



ハンググライダー場の南の端の木に三頭山の山頂標がある。その裏には三頭大明神の石碑が建っている。
さらにその奥の樹林帯の中に 四等三角点 三頭 734.16m



ここでのお昼は諦めて一旦三頭神社へと下って行く。舗装路を歩いて行くと神社の駐車場に着いた。真新しい狛
犬の間を通って石段を登って行くと三頭神社に着いた。剣霊、山王、清竜(青竜)の3社が祀られている事から三
頭と名付けられ、三頭大権現とも呼ばれる境内は、山頂近くにあっても荒れてもいなくきれいに清掃されていた。



神社からはもと来た道を戻って行く。ハンググライダー場を過ぎると東屋があるが、昨年ここで昼食を採ったの
で、今日はもう少し先の展望台でお昼にする。今日のお昼はインスタントの焼きそば。予定にはなかった朝うど
んを食べてしまったので、続けての炭水化物になってしまった。コンクリート製の東屋は暖かい日差しを遮って
くれて、日陰に吹き抜けていく風がちょうど心地よい。


展望台からは南側の山々を見渡せた。黄砂で霞んではいるものの、烏帽子山から矢筈山、そして剣山や一ノ森が
一望できる大展望だ。西から東に長く続く稜線にはまだ少し雪が残っているのが見える。麓には美馬から対岸の
半田の街並みが続いている。




お昼ご飯を食べ終え目の前の眺望を眺めて終わると、そろそろいい時間だ。今から下って行けばあのお花たちも
花びらを開いてくれている頃だろう。
三頭越まで戻ると寒風峠方面にあるベンチで女性が二人お昼を採っていた。そして峠を降りて行くと6名ほどの
クループが前を歩いていた。やはりお昼から開く花を目当てにみなさん登って来ている。


さらにその先には一組のご夫婦。みんなそれぞれ立ち止まっては花の写真を撮っているので場所によっては追い
抜きができない。昼からの温かい日差しを浴びて、予想通り気持ちよく花を広げてくれている。



そしてもう一つのお花もなるべく見つからないようにしているのか、落ち葉に混じってひっそりと咲いていた。




少しまとまった場所では、こちらに向かって愛想を振りまく子がいたりそっぽを向く子がいたりと様々。色も別
名ルリイチゲと云われるようなきれいな瑠璃色をしているのもあれば、少し色白の子もいる。
谷あいをやさしく吹き抜けていく風にゆらゆら揺れる姿が可愛らしい。



下って行く途中で次々と登ってくる人たちがいる。そんな中で写真を撮っていると若い女性から声をかけられた。
『ユキワリイチゲ、ほんと可愛いですね。アワコバイモは見つけられますか?』と聞かれたので、『落ち葉と区
別がつきにくいので、がんばって!』と答える。
駐車場まで戻ってくるとまだまだ結構な台数の車が停まっていた。帰りのラジオでは今日、香川で開花宣言が発
表されたと話をしている。これからしばらくは春の花めぐりでまた忙しくなりそうだ。

途中で会ったWOC登山部の女性陣に、早く降りるのでどこか行くところがないかと聞かれたので、昨年ここの帰
りに寄ったセリバオウレンの咲く場所を教えてあげたので、自分でも確認しに立ち寄ってみた。
稜線近くに続く林道沿いにも春の訪れを感じさせる花たちが咲いていた。




教えた場所に着くと昨年来た場所?とも見間違えるほどもう目当てのセリバオウレンは咲いていなかった。教え
た二人が遠回りのここまで来てなかったらいいのだけれど。(ひょっとしたら場所をまちがっていたのかもしれ
ない)寂しげに残る小さな花の写真を写して山を後にした。