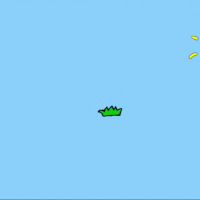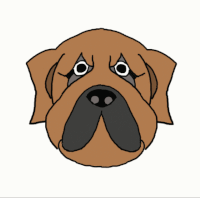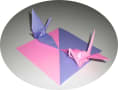『辰刻の雫 (ときのしずく) ~蒼い月~』 目次
『辰刻の雫 ~蒼い月~』 第1回から第120回までの目次は以下の 『辰刻の雫 ~蒼い月~』リンクページ からお願いいたします。
『辰刻の雫 ~蒼い月~』 リンクページ







辰刻の雫 (ときのしずく) ~蒼い月~ 第130回
「申し訳御座いません」
マツリを前にして杠が手をついて頭を下げている。
マツリの眉がピクリと動く。
「なにも杠から謝られるようなことはないはずだが? あれか? あの女人は杠が点々と置いているという女人の一人か?」
「はい」
「・・・杠があれ程の女人を置いているとは思わなかったな」
紫揺とは比べ物にならない程の超絶正反対だ。
懐かしく言うところの杢木誠也のボン・キュ・ボン。 あくまでもスレンダーな中に。 そして色香漂う容貌。
「己のことをよく分かってくれております」
「出過ぎず、訊かずか」
「はい」
「で? どうしてこのようなことになった?」
マツリに腰を取られていた女人が、道端に立っていた芯直の前まで案内してきた。 女人は芯直からマツリを連れてきてほしいと頼まれていた。
『どうしてもマツリ様にお願いしたいことがあるんだけど、文官さんが邪魔で話しができないんだ。 連れてきてくれない?』 と。
そしてその後、姿を消した女人から見えないように、マツリを少し先の店の中に入れたのだった。
そこで杠が姿を現したということである。
「巴央と享沙の同座をお許し願いたいのですが」
そういうことか。 杠一人ならばこんなことは要らなかったはず。 杠は巴央と享沙を同席させたくてこんなことをしたということか。
あの官吏がいるから宿を訪ねることも出来なければ、マツリが宿を出るとついて来るだろう、だからか。
「構わん」
杠がそう判断したのだから、それが必要なのだろう。
杠が合図らしきものを送ると、奥の襖が開き巴央と享沙が姿を現した。
(まだまだか・・・仕方がないか)
杠が出てくるまで、杠の気配は感じなかったが、杠が言う前から二人の気配は感じていた。
二人が座したままマツリに頭を下げると立ち上がり杠の後ろに移動しそこに座した。 享沙はいつものように端座していたが、意外にも巴央も胡坐ではなく正座をした。
杠が下三十都に巴央を連れて行ったことで、巴央の中で何かが変わったのかもしれない。 そうならば、あの灰汁の強い巴央をよくも短い間に手懐けたものだと感心する。
マツリが杠を見る。
杠が首肯する。
「分かったのか?」
「はい」
まずは以前目にしていた書簡のことを話した。
秀亜郡司が下三十都都司から、土地を広げると言われた。 早い話、この郡司の守る辺境の土地を吸収するという話であった。 それを断ると秀亜群の民の家が燃えた。 再度都司がやって来て同じ話をした。 断った。 また民の家が燃えた。
何度も繰り返すうち夜襲をかけられ民が死んだ。 燃え死んだ。 火をつけていたのは下三十都の官所(かんどころ)で働いている者であった。
「その話は父上から聞いておった。 大分してからだがな」
杠が首肯する。
「己も後になってのことですが、四方様にお付きして知ったことで御座いました」
「あの時か・・・」
官吏としての資格を得た後、四方に散々に使われていた時か。
「秀亜郡司から宮都に文が届きましたが、秀亜郡司の一方的な話だけを信じるわけにはいかず、四方様はすぐに早馬を走らされました。 共に武官も文官も動かされました。 秀亜群では家を焼かれ、民が亡くなったということを確認したと四方様は聞かれ、すぐに下三十都都司を宮都に呼ばれました。 都司は郡司に話したことを認めましたが、家を焼いたなどということは知らなかったと」
そして都司が己の責をもって、家を焼いたと言われる者を宮都に連れてくると言っていたが、都司が下三十都に戻るとその三人が自害していた。 その三人が秀亜群の家を焼いていたと秀亜群の民が証言をした。 そしてそれからは家を焼かれることがなくなった。
結局、家を焼いたのは自害した三人のやったことで、都司も大変なことになってしまったと、秀亜群を諦めたということになり、また都司は無罪放免となっていた。
だが杠たちはそれで終わらせる気などなかった。 調べに調べて証人を探し出した。
「自害した三人は都司の命令で家を焼いておりました。 下三十都に証人がおります」
「証人? 父上がお調べになられているときにその証人を見つけられなかったのか」
「武官殿相手では話し辛かったのではないかと」
屈強な武官を目の前にして知っていることを言えと言われても、なかなか言えるものではないだろう。
ついうっかりマツリが頷いた。 杠とだけであれば頷く必要さえないところだが、後ろにいる二人に聞かせる為に、その証人を抑えておるか、と聞くところだったのに。 杠がそれを見せるために二人・・・いや、巴央を呼んだというのに。
マツリの失敗に杠は気付いている。 マツリに敢えて受け答えしてほしいと思っていたのは杠なのだから。
「そして自害では御座いませんでしょう」
「宮都から戻った都司がやったと?」
「残念ながら証拠は御座いませんが、都司が宮都から戻った時には三人はまだ生きておりました」
「都司が毒でも盛ったか」
「官所の厨で三人とも血を吐いてこと切れていたということで御座います。 残っていたのは落ちて割れていた湯呑が三つ。 何を飲んだのかは分かりません」
「宮都で美味い茶の葉でも手に入れたとでも言ったのであろうな」
杠の眉が僅かに上がった。 マツリは話の間に言葉を挟むような人間ではない。 ましてや必要でない言葉を。 先の失敗を覆すように、後ろに控える二人を意識して言葉を挟んできている。 今マツリがどう考えたかということを分からせるために。 杠の考えが伝わっていたようだ。
「現段階で都司が三人に手を下したという証拠は一切ございません」
「ふむ」
「秀亜郡司は・・・許せなかったのでしょう」
己が守らなければならない民が殺された。 焼き殺された。
宮都に訴えた。 だが時遅しだった。 すでに民は焼き殺されていたのだから。
「宮都に訴えたあとに民には危険は及ばなかったものの、それまでに亡くなった民がおります」
「秀亜郡司が報復をしたとでも?」
「秀亜群では家を燃やしたのは都司が命令してやったことだと誰もが言っておりました、あくまでも民の憶測ですが。 ですがその根拠は亡くなった三人は家に火をつける前、都司から金を受け取っていたと話していたそうです。 割に合わないと不服を言っているのを聞いていた民がおりました」
多分、当時の武官か文官も同じ話を聞いただろう。 だが今の話では確たるものに欠ける。
「何をして金を受け取ったとは聞いておらんのだな」
杠が頷く。
「それではしかとした証言にはならんな」
郡司はその話を信じたのだろうか。 郡司が守るべき民が殺されたのだ。 感情的になれば確たる証拠証言が無くとも、その疑いが濃ければ行動に移すかもしれない。
もう一度杠が頷いて続ける。
「郡司は一度ひそかに下三十都に入りました。 その後に下三十都で流行り病が出ました。 ですが流行り病は大きくは広がらず、ある一定の場所でのみの発病でございます」
ひとつ間を置くと、ここからは己の推量で御座います、と言って続けた。
ある一定の場所と言うのは下三十都文官所とその周辺。 そして都司の住む家の周辺。 その二か所。 いずれも同じ井戸を使っている所で発病者が出ている。 考えられるのは井戸に何かがある。 郡司は下三十都に入ってこの二か所で使う井戸、早い話が都司が使う井戸に毒草の液を入れたと考えられる。
郡司はすぐに秀亜群に舞い戻り、まるで今の症状に苦しむに値する薬草を売る行商に来たという風に演じ、高値を付けて薬草を売ろうとした。 金が欲しいわけではなかった。 都司さえ苦しめばそれで良かった。 都司が毒草に苦しみ、そして都司が守らねばならない民が毒草に苦しんでいるのを見て、より苦しめばいいと。
だが都司は高値で薬草を買い求めたはいいが、それは都司自身と家族、働いてもらわなければ困る家で働く者たちの分しか買い求めなかった。
郡司が下三十都に身を置いて暫く待っていたが都司からの接触がない。 あの都司は己が守らねばならない民が苦しんでいるのを見ても何とも思わないのか、苦しむことがないのか。 それでは今の民のこの苦しみは何のためにある。
郡司が背にしょっている籠の中から薬草を出しそれを煎じると、苦しんでいる民に金を取ることなく配り始めた。
「薬草は解毒作用のあるものです。 苦しんでいる者は煎じることすら出来ない状態でございました」
「死人は」
「出ておりません」
「年寄りや赤子がいなかったということか」
「赤子はおりませんでした。 年寄もそれに近い歳の者はおりましたが、もし郡司があと二日でも民に配るのが遅くなっていれば死んでいたかもしれません」
「郡司はそこも見ていたということか」
「そう思われます」
「だがあの辺境・・・秀亜群はそこまで薬草、あ、いや、毒草に詳しいか?」
薬草はあるはずだが毒草がそんなにあっただろうか。 それに毒草が生ることは致し方ないが、その手に持つには許可が要る。 毒を以て毒を制す。 そういう意味で持つことを許される者がいるのだが、その者は宮都から許可が下ろされている者に限られている。
売る側の秀亜群では売る以上、秀亜群の代々郡司は毒草を持つ許可は宮都から得ているが、使いこなす知識があったのだろうか。
「秀亜群は薬草で知られておりますが、一部毒草も有るようで御座います。 ですが秀亜群自体は代々毒草のことは良く知らず、ただ生っているだけで宮都から許可が下りている者に売っていただけで、薬草だけを育てておりましたが、秀亜群から一人官吏になっている者がおります」
マツリの目の色が変わる。
辺境で暮らす者が官吏になるということは簡単なことではない。
「もともと頭が良かったのでしょう。 官吏になると言って秀亜群を出て五都で勉学に励んだようです。 秀亜群の出身です、元々薬草には詳しい。 そんな事もあって五都での勉学では毒草のことも学んだようです。 官吏になってからは能吏と呼ばれるほどに出来たようです」
「今も官吏をしておるのか」
「いいえ。 今は四方様に仕えていらっしゃいます」
「官吏から父上に?」
官吏から四方の従者になったのはマツリの知る限り一人しかいない。 今は他の従者のように四方に付くのではなく、遠目から堀を見て四方に危険が及ばないかをいつも見ている者。
「・・・朱禅」
唇を引いて杠が頷いた。
外堀であっても四方に付いている朱禅。 四方の抱える問題は全て目に通していた。 そんな時、秀亜郡司からの書簡を切っ掛けに秀亜で起きたことを知った。 すぐに郡司に文を送ると、事の真相を書いた文が返ってきた。
『・・・だが何の証拠もない。 これ以上、宮都も動けないという。 朱禅、都司に思い知らせてやりたい。 毒草のことを詳しく教えてくれ』
「朱禅殿のことです。 なんとか郡司を説き伏せようとされたはずで御座います」
宮を出て来た時のことを思い出す。 朱禅に引き留められた。 それは朱禅が言ったように僅かな時だった。
『マツリ様のこと、何事にも損じられる様なことは御座いませんでしょうが、マツリ様をお諫(いさ)めするのは杠殿のお役目でございます。 忌憚なく。 くれぐれもお忘れなきよう』
静かであり、心に残る言葉だった。
「結果として手を貸したのであれば問わねばならんだろう」
マツリの淡々とした言いように、巴央の下瞼がピクピクと動いている。 杠はマツリが都司を逃さない、許すはずが無いと言っていた。 それなのにマツリはそんな様子を見せることすらなく、杠と話している。
「我らが調べたのは以上で御座います」
ふむ、と言うと少しの間をおいて続けて言う。
「こと切れていた三人のことは都司を捕まえてからのことになるか。 家の中か官所のどこかを探せば毒草が出てこよう。 その毒草をどこから入手したのかも調べねばならんが、それは二の次として、下三十都の証人という者に都司が手を下すことはないのか?」
「無いとは言い切れませんが、口外すると身に危険が及ぶと言っておきました。 こちらに来るまで暫く金河が見ておりましたが、怪しい影を見ることは無かったということです」
「郡司は」
「かなり憔悴しておりましたが秀亜群に戻って来ました」
「憔悴か・・・。 己の罪の重さを感じたか」
「報復など、どうして考えたのか」
「朱禅が止められなかったほどだ。 その時は怒りに任せてしまったのだろう」
分からなくもない・・・。 ポツリと言った言葉が巴央の耳に届いた。
「承知した。 あとの事は我がする」
「マツリ様が? 六都のことでお忙しいのに、宮都に任せられれば如何ですか?」
「今のところ六都は順調にいっておる。 しばらく続くであろう。 この事はその間に片付ける。 郡司のしたことを見逃すわけにはいかんが、簡単に報復などということで終わらせるつもりはない。 下三十都都司は逃がさん」
巴央が目を大きく見開いた。 杠の言った通りだ。
「必ず捕らえる」
巴央と沙柊が大きく頷き、それに応えるようにマツリも頷いた。
「まずは宮に戻る。 俤は我と共に宮に戻ってくれ。 子細を問われた時に我では答えられないところがあっては困るのでな」
杠だけは官吏である。 他の者の目の前に堂々と出ることが出来る。
杠が頷く。
「下三十都の都司のことは宮都で動かす。 沙柊と金河は力山と共に六都に留まり、馬鹿者が何か動きを見せないか見ていてくれ」
マツリと杠が居ない間の見張ということである。
「はい」
二人が声を揃えた。
「オレ、今日すんごい女人を見たんだ。 マツリ様がその女人の腰に手をまわして・・・いひひぃ~」
杠からマツリのもとに女人が行く、マツリがその女人についていくよう仕向けるようにと柳技は言われていた。
「けー! どれだけすんごいか知んないけど、オレらが見た女人以上はいないって、なー、絨ら・・・淡月ぅ~」
淡月と呼ばれた絨礼が頷く。
「なんだよ、お母か姉ぇちゃんになって欲しいって言ってた女人かよ。 いや、絶対に今日オレが見た女人の方がすごいはず、いいはず。 お母や姉ぇちゃんってんじゃないんだ。 なんかこー・・・ああ、どう言ったらいいのかなぁ」
自分で自分を抱きしめて身悶えする柳技。 それを白い目で見ている絨礼と芯直だが、三人が言っているのが同一人物だとはこの中で誰一人として知らない。
翌朝、杠とマツリが六都を出て宮に戻っていった。
馬に揺られるマツリの肩にはキョウゲンが乗っている。 六都に来てキョウゲンの出番は一度しかなかった。 文官の言った杉の山を見にいっただけであった。
「それにしてもあの文官は何をあんなに呆然としてらしたんでしょうか?」
杠は六都文官所を既に退いている。 身を隠してマツリを見ていた時のことだ。
マツリがいったん宮に戻ると言った時だった。
『は?』
『宮で事が終わればまたこちらに来る。 それまで武官たちと諍いがないか見張りをしておいてくれ』
『あ・・・でも・・・。 今、晩』
『ああ、今晩どころか今から出る。 宿の方は当分使わぬから断っておいてくれ。 また来た時に頼む』
『・・・』
この官吏が夕べマツリが居なくなったあと、あちこち女のいる店をまわったことをマツリが知るはずもなかった。
『辰刻の雫 ~蒼い月~』 第1回から第120回までの目次は以下の 『辰刻の雫 ~蒼い月~』リンクページ からお願いいたします。
『辰刻の雫 ~蒼い月~』 リンクページ







辰刻の雫 (ときのしずく) ~蒼い月~ 第130回
「申し訳御座いません」
マツリを前にして杠が手をついて頭を下げている。
マツリの眉がピクリと動く。
「なにも杠から謝られるようなことはないはずだが? あれか? あの女人は杠が点々と置いているという女人の一人か?」
「はい」
「・・・杠があれ程の女人を置いているとは思わなかったな」
紫揺とは比べ物にならない程の超絶正反対だ。
懐かしく言うところの杢木誠也のボン・キュ・ボン。 あくまでもスレンダーな中に。 そして色香漂う容貌。
「己のことをよく分かってくれております」
「出過ぎず、訊かずか」
「はい」
「で? どうしてこのようなことになった?」
マツリに腰を取られていた女人が、道端に立っていた芯直の前まで案内してきた。 女人は芯直からマツリを連れてきてほしいと頼まれていた。
『どうしてもマツリ様にお願いしたいことがあるんだけど、文官さんが邪魔で話しができないんだ。 連れてきてくれない?』 と。
そしてその後、姿を消した女人から見えないように、マツリを少し先の店の中に入れたのだった。
そこで杠が姿を現したということである。
「巴央と享沙の同座をお許し願いたいのですが」
そういうことか。 杠一人ならばこんなことは要らなかったはず。 杠は巴央と享沙を同席させたくてこんなことをしたということか。
あの官吏がいるから宿を訪ねることも出来なければ、マツリが宿を出るとついて来るだろう、だからか。
「構わん」
杠がそう判断したのだから、それが必要なのだろう。
杠が合図らしきものを送ると、奥の襖が開き巴央と享沙が姿を現した。
(まだまだか・・・仕方がないか)
杠が出てくるまで、杠の気配は感じなかったが、杠が言う前から二人の気配は感じていた。
二人が座したままマツリに頭を下げると立ち上がり杠の後ろに移動しそこに座した。 享沙はいつものように端座していたが、意外にも巴央も胡坐ではなく正座をした。
杠が下三十都に巴央を連れて行ったことで、巴央の中で何かが変わったのかもしれない。 そうならば、あの灰汁の強い巴央をよくも短い間に手懐けたものだと感心する。
マツリが杠を見る。
杠が首肯する。
「分かったのか?」
「はい」
まずは以前目にしていた書簡のことを話した。
秀亜郡司が下三十都都司から、土地を広げると言われた。 早い話、この郡司の守る辺境の土地を吸収するという話であった。 それを断ると秀亜群の民の家が燃えた。 再度都司がやって来て同じ話をした。 断った。 また民の家が燃えた。
何度も繰り返すうち夜襲をかけられ民が死んだ。 燃え死んだ。 火をつけていたのは下三十都の官所(かんどころ)で働いている者であった。
「その話は父上から聞いておった。 大分してからだがな」
杠が首肯する。
「己も後になってのことですが、四方様にお付きして知ったことで御座いました」
「あの時か・・・」
官吏としての資格を得た後、四方に散々に使われていた時か。
「秀亜郡司から宮都に文が届きましたが、秀亜郡司の一方的な話だけを信じるわけにはいかず、四方様はすぐに早馬を走らされました。 共に武官も文官も動かされました。 秀亜群では家を焼かれ、民が亡くなったということを確認したと四方様は聞かれ、すぐに下三十都都司を宮都に呼ばれました。 都司は郡司に話したことを認めましたが、家を焼いたなどということは知らなかったと」
そして都司が己の責をもって、家を焼いたと言われる者を宮都に連れてくると言っていたが、都司が下三十都に戻るとその三人が自害していた。 その三人が秀亜群の家を焼いていたと秀亜群の民が証言をした。 そしてそれからは家を焼かれることがなくなった。
結局、家を焼いたのは自害した三人のやったことで、都司も大変なことになってしまったと、秀亜群を諦めたということになり、また都司は無罪放免となっていた。
だが杠たちはそれで終わらせる気などなかった。 調べに調べて証人を探し出した。
「自害した三人は都司の命令で家を焼いておりました。 下三十都に証人がおります」
「証人? 父上がお調べになられているときにその証人を見つけられなかったのか」
「武官殿相手では話し辛かったのではないかと」
屈強な武官を目の前にして知っていることを言えと言われても、なかなか言えるものではないだろう。
ついうっかりマツリが頷いた。 杠とだけであれば頷く必要さえないところだが、後ろにいる二人に聞かせる為に、その証人を抑えておるか、と聞くところだったのに。 杠がそれを見せるために二人・・・いや、巴央を呼んだというのに。
マツリの失敗に杠は気付いている。 マツリに敢えて受け答えしてほしいと思っていたのは杠なのだから。
「そして自害では御座いませんでしょう」
「宮都から戻った都司がやったと?」
「残念ながら証拠は御座いませんが、都司が宮都から戻った時には三人はまだ生きておりました」
「都司が毒でも盛ったか」
「官所の厨で三人とも血を吐いてこと切れていたということで御座います。 残っていたのは落ちて割れていた湯呑が三つ。 何を飲んだのかは分かりません」
「宮都で美味い茶の葉でも手に入れたとでも言ったのであろうな」
杠の眉が僅かに上がった。 マツリは話の間に言葉を挟むような人間ではない。 ましてや必要でない言葉を。 先の失敗を覆すように、後ろに控える二人を意識して言葉を挟んできている。 今マツリがどう考えたかということを分からせるために。 杠の考えが伝わっていたようだ。
「現段階で都司が三人に手を下したという証拠は一切ございません」
「ふむ」
「秀亜郡司は・・・許せなかったのでしょう」
己が守らなければならない民が殺された。 焼き殺された。
宮都に訴えた。 だが時遅しだった。 すでに民は焼き殺されていたのだから。
「宮都に訴えたあとに民には危険は及ばなかったものの、それまでに亡くなった民がおります」
「秀亜郡司が報復をしたとでも?」
「秀亜群では家を燃やしたのは都司が命令してやったことだと誰もが言っておりました、あくまでも民の憶測ですが。 ですがその根拠は亡くなった三人は家に火をつける前、都司から金を受け取っていたと話していたそうです。 割に合わないと不服を言っているのを聞いていた民がおりました」
多分、当時の武官か文官も同じ話を聞いただろう。 だが今の話では確たるものに欠ける。
「何をして金を受け取ったとは聞いておらんのだな」
杠が頷く。
「それではしかとした証言にはならんな」
郡司はその話を信じたのだろうか。 郡司が守るべき民が殺されたのだ。 感情的になれば確たる証拠証言が無くとも、その疑いが濃ければ行動に移すかもしれない。
もう一度杠が頷いて続ける。
「郡司は一度ひそかに下三十都に入りました。 その後に下三十都で流行り病が出ました。 ですが流行り病は大きくは広がらず、ある一定の場所でのみの発病でございます」
ひとつ間を置くと、ここからは己の推量で御座います、と言って続けた。
ある一定の場所と言うのは下三十都文官所とその周辺。 そして都司の住む家の周辺。 その二か所。 いずれも同じ井戸を使っている所で発病者が出ている。 考えられるのは井戸に何かがある。 郡司は下三十都に入ってこの二か所で使う井戸、早い話が都司が使う井戸に毒草の液を入れたと考えられる。
郡司はすぐに秀亜群に舞い戻り、まるで今の症状に苦しむに値する薬草を売る行商に来たという風に演じ、高値を付けて薬草を売ろうとした。 金が欲しいわけではなかった。 都司さえ苦しめばそれで良かった。 都司が毒草に苦しみ、そして都司が守らねばならない民が毒草に苦しんでいるのを見て、より苦しめばいいと。
だが都司は高値で薬草を買い求めたはいいが、それは都司自身と家族、働いてもらわなければ困る家で働く者たちの分しか買い求めなかった。
郡司が下三十都に身を置いて暫く待っていたが都司からの接触がない。 あの都司は己が守らねばならない民が苦しんでいるのを見ても何とも思わないのか、苦しむことがないのか。 それでは今の民のこの苦しみは何のためにある。
郡司が背にしょっている籠の中から薬草を出しそれを煎じると、苦しんでいる民に金を取ることなく配り始めた。
「薬草は解毒作用のあるものです。 苦しんでいる者は煎じることすら出来ない状態でございました」
「死人は」
「出ておりません」
「年寄りや赤子がいなかったということか」
「赤子はおりませんでした。 年寄もそれに近い歳の者はおりましたが、もし郡司があと二日でも民に配るのが遅くなっていれば死んでいたかもしれません」
「郡司はそこも見ていたということか」
「そう思われます」
「だがあの辺境・・・秀亜群はそこまで薬草、あ、いや、毒草に詳しいか?」
薬草はあるはずだが毒草がそんなにあっただろうか。 それに毒草が生ることは致し方ないが、その手に持つには許可が要る。 毒を以て毒を制す。 そういう意味で持つことを許される者がいるのだが、その者は宮都から許可が下ろされている者に限られている。
売る側の秀亜群では売る以上、秀亜群の代々郡司は毒草を持つ許可は宮都から得ているが、使いこなす知識があったのだろうか。
「秀亜群は薬草で知られておりますが、一部毒草も有るようで御座います。 ですが秀亜群自体は代々毒草のことは良く知らず、ただ生っているだけで宮都から許可が下りている者に売っていただけで、薬草だけを育てておりましたが、秀亜群から一人官吏になっている者がおります」
マツリの目の色が変わる。
辺境で暮らす者が官吏になるということは簡単なことではない。
「もともと頭が良かったのでしょう。 官吏になると言って秀亜群を出て五都で勉学に励んだようです。 秀亜群の出身です、元々薬草には詳しい。 そんな事もあって五都での勉学では毒草のことも学んだようです。 官吏になってからは能吏と呼ばれるほどに出来たようです」
「今も官吏をしておるのか」
「いいえ。 今は四方様に仕えていらっしゃいます」
「官吏から父上に?」
官吏から四方の従者になったのはマツリの知る限り一人しかいない。 今は他の従者のように四方に付くのではなく、遠目から堀を見て四方に危険が及ばないかをいつも見ている者。
「・・・朱禅」
唇を引いて杠が頷いた。
外堀であっても四方に付いている朱禅。 四方の抱える問題は全て目に通していた。 そんな時、秀亜郡司からの書簡を切っ掛けに秀亜で起きたことを知った。 すぐに郡司に文を送ると、事の真相を書いた文が返ってきた。
『・・・だが何の証拠もない。 これ以上、宮都も動けないという。 朱禅、都司に思い知らせてやりたい。 毒草のことを詳しく教えてくれ』
「朱禅殿のことです。 なんとか郡司を説き伏せようとされたはずで御座います」
宮を出て来た時のことを思い出す。 朱禅に引き留められた。 それは朱禅が言ったように僅かな時だった。
『マツリ様のこと、何事にも損じられる様なことは御座いませんでしょうが、マツリ様をお諫(いさ)めするのは杠殿のお役目でございます。 忌憚なく。 くれぐれもお忘れなきよう』
静かであり、心に残る言葉だった。
「結果として手を貸したのであれば問わねばならんだろう」
マツリの淡々とした言いように、巴央の下瞼がピクピクと動いている。 杠はマツリが都司を逃さない、許すはずが無いと言っていた。 それなのにマツリはそんな様子を見せることすらなく、杠と話している。
「我らが調べたのは以上で御座います」
ふむ、と言うと少しの間をおいて続けて言う。
「こと切れていた三人のことは都司を捕まえてからのことになるか。 家の中か官所のどこかを探せば毒草が出てこよう。 その毒草をどこから入手したのかも調べねばならんが、それは二の次として、下三十都の証人という者に都司が手を下すことはないのか?」
「無いとは言い切れませんが、口外すると身に危険が及ぶと言っておきました。 こちらに来るまで暫く金河が見ておりましたが、怪しい影を見ることは無かったということです」
「郡司は」
「かなり憔悴しておりましたが秀亜群に戻って来ました」
「憔悴か・・・。 己の罪の重さを感じたか」
「報復など、どうして考えたのか」
「朱禅が止められなかったほどだ。 その時は怒りに任せてしまったのだろう」
分からなくもない・・・。 ポツリと言った言葉が巴央の耳に届いた。
「承知した。 あとの事は我がする」
「マツリ様が? 六都のことでお忙しいのに、宮都に任せられれば如何ですか?」
「今のところ六都は順調にいっておる。 しばらく続くであろう。 この事はその間に片付ける。 郡司のしたことを見逃すわけにはいかんが、簡単に報復などということで終わらせるつもりはない。 下三十都都司は逃がさん」
巴央が目を大きく見開いた。 杠の言った通りだ。
「必ず捕らえる」
巴央と沙柊が大きく頷き、それに応えるようにマツリも頷いた。
「まずは宮に戻る。 俤は我と共に宮に戻ってくれ。 子細を問われた時に我では答えられないところがあっては困るのでな」
杠だけは官吏である。 他の者の目の前に堂々と出ることが出来る。
杠が頷く。
「下三十都の都司のことは宮都で動かす。 沙柊と金河は力山と共に六都に留まり、馬鹿者が何か動きを見せないか見ていてくれ」
マツリと杠が居ない間の見張ということである。
「はい」
二人が声を揃えた。
「オレ、今日すんごい女人を見たんだ。 マツリ様がその女人の腰に手をまわして・・・いひひぃ~」
杠からマツリのもとに女人が行く、マツリがその女人についていくよう仕向けるようにと柳技は言われていた。
「けー! どれだけすんごいか知んないけど、オレらが見た女人以上はいないって、なー、絨ら・・・淡月ぅ~」
淡月と呼ばれた絨礼が頷く。
「なんだよ、お母か姉ぇちゃんになって欲しいって言ってた女人かよ。 いや、絶対に今日オレが見た女人の方がすごいはず、いいはず。 お母や姉ぇちゃんってんじゃないんだ。 なんかこー・・・ああ、どう言ったらいいのかなぁ」
自分で自分を抱きしめて身悶えする柳技。 それを白い目で見ている絨礼と芯直だが、三人が言っているのが同一人物だとはこの中で誰一人として知らない。
翌朝、杠とマツリが六都を出て宮に戻っていった。
馬に揺られるマツリの肩にはキョウゲンが乗っている。 六都に来てキョウゲンの出番は一度しかなかった。 文官の言った杉の山を見にいっただけであった。
「それにしてもあの文官は何をあんなに呆然としてらしたんでしょうか?」
杠は六都文官所を既に退いている。 身を隠してマツリを見ていた時のことだ。
マツリがいったん宮に戻ると言った時だった。
『は?』
『宮で事が終わればまたこちらに来る。 それまで武官たちと諍いがないか見張りをしておいてくれ』
『あ・・・でも・・・。 今、晩』
『ああ、今晩どころか今から出る。 宿の方は当分使わぬから断っておいてくれ。 また来た時に頼む』
『・・・』
この官吏が夕べマツリが居なくなったあと、あちこち女のいる店をまわったことをマツリが知るはずもなかった。