関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14
Vol.-13からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第40番 福聚山 善應寺 普門院
(ふもんいん)
江東区亀戸3-43-3
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第40番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第30番、亀戸七福神(毘沙門天)
第40番札所は、下町・亀戸の普門院です。
第40番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに普門院なので、御府内霊場開創時から一貫して亀戸の普門院であったとみられます。
第40番の四ッ谷の真成院も御府内霊場開創時からの札所とみられるので、第39番の四ッ谷から第40番は亀戸へと、一気にエリアを変えることになります。
これは本四国八十八ヶ所霊場が第39番の延光寺(高知県(土佐國)宿毛市)から第40番の観自在寺(愛媛県(伊予國)愛南町)で国が変わることと関連があるのかもしれません。
本四国霊場は四国内の阿波國(1-23番)、土佐國(24-39番)、伊予國(40-65番)、讃岐國(66-88番)と国別に構成されており、それぞれ発心の道場、修行の道場、菩提の道場、涅槃の道場とされています。
御府内霊場をみると、23番(薬王寺/市ヶ谷)→24番(三光寺/内藤新宿)は比較的近いですが、39番(真成院/四ッ谷)→40番(普門院/亀戸)は大きくエリアを変え、65番(大聖院/芝三田寺町)→66番(東覚寺/田端)とこちらもエリアを移しています。
御府内の東端は亀戸辺とされ、亀戸天神御鎮座の参詣地でもあったため、御府内霊場札所の配置は自然な成り行きかも。
なお、これより東寄りは荒川辺八十八ヶ所霊場、荒綾八十八ヶ所霊場、新四国四箇領八十八ヵ所霊場、南葛八十八ヶ所霊場など、下町の弘法大師霊場の領域となり、現在巡拝するにはよりマニアックな踏み込みが必要となります。
亀戸あたりになると、『寺社書上』『御府内寺社書上』への記載はなくなりますが、『新編武蔵風土記稿』の収録エリアなのでこちらから追っていけます。
亀戸は江戸の名所のひとつなので『江戸名所図会』にも挿絵を添えてしっかり収録されています。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
普門院は大永二年(1522年)三股(隅田川・荒川・綾瀬川の合流点、現・足立区千住周辺)の城中に創建されました。
開山は長賢上人、開基は千葉中務大輔自胤と伝わります。
千葉自胤(1446-1494年)は室町時代の武将で、武蔵千葉氏第3代当主とされます。
千葉氏は桓武平氏の名族で、下総に勢力を張り坂東八平氏・関東八屋形のひとつに数えられました。
千葉(介)常胤は、頼朝公の旗揚げに呼応し、公の信任を得て、鎌倉時代には下総守護の家柄となりました。
千葉一族は繁栄した一方、同族間の確執が多く争いも絶えなかったといいます。
室町時代中期の千葉氏の嫡流は千葉胤賢でしたが、享徳の乱(1455-1483年)で古河公方・足利成氏方で同族の原胤房・馬加康胤に殺され、遺児となった実胤と自胤は下総八幡荘の市河城へ逃れました。
しかし、成氏方の簗田持助に敗れ、康正二年(1456年)市河城を失って武蔵へと逃れました。
実胤は石浜城(現・台東区橋場)、自胤は赤塚城(現・板橋区赤塚)に拠り、後に兄の実胤が隠遁したため、自胤が石浜城主となり千葉氏当主を嗣ぎました。
自胤は本領である房総への帰還を目指しましたが、分家の岩橋氏が勢力をふるい岩橋孝胤は千葉氏当主を自称、後に公認されました。
惣領筋の自胤はそれでも幾度か房総奪還を図りますが、岩橋孝胤は勢力を固めて下総千葉氏継承を確定しました。
自胤の子孫はよんどころなく武蔵に定着し、武蔵千葉氏とも呼ばれました。
普門院はこの千葉自胤が、自身が拠った城内に開基と伝わります。
『新編武蔵風土記稿』に「古ハ豊嶋郡橋場村ニアリシ」とあるのは、おそらく石浜城内を指すとみられます。
『江戸名所図会』には「三俣の城中に一宇の梵刹を開き(略)三俣といへるは、隅田川、綾瀬川、荒川の落合ひ、三俣になる所をいへり。昔千葉家在城の地なり。」とあります。
三俣はいまの千住周辺とされ、石浜城とはべつに三俣(三原)城という城があったのかも。
当初の普門院の御本尊は伝教大師の御作とも伝わる観世音菩薩で、自胤の信仰も篤く、自城内に一宇を建ててこの観世音菩薩を奉安したといいます。
また、千葉自胤の臣・佐田善次郎盛光が讒言を受け斬られそうになったとき、盛光が日頃信仰するこの観音像に祈ったところたちまち刀の刃がこぼれ、盛光は死を免れたとのこと。
天文三年(1534年)、この地に疫病が流行した際、この観音像を念ずる者はことごとく病が平癒し、患者と床を同じくしても感染しなかったといいます。
この観音様が衆生の身代りとなって疫病を引き受けられたという逸話もあり、以来「身代観世音」と尊称されて人々の信仰を集めました。
元和二年(1616年)荒川辺から現在地の亀戸に移転。
この時、誤って梵鐘を隅田川に沈めてしまい、鐘ヶ淵の地名の由来になったともいいます。
慶安二年(1649年)八月には大猷院殿(徳川家光公)の御渡りあって御休所も設けられましたが、いつしか取払われたとのこと。
「猫の足あと」様には『江東区の民俗城東編』の興味深い記事が紹介されているので、孫引きさせていただきます。
「『浅草区誌』によれば、鐘ヶ淵に沈んだ鐘は法元寺(『再校江戸砂子』註:保元寺)、普門院(『新編江戸志』)、長昌寺(『武蔵古蹟志』)と三説をあげている。『帝都郊外発展誌』によれば、安永年中(1772-1781年)に栄範上人が本尊を身代観音菩薩から大日如来に改め、観音堂を別に建立した。」
これによると安永年中(1772-1781年)までの普門院の御本尊は身代観世音菩薩で、栄範上人が御本尊を身代観音菩薩から大日如来に改めたということになります。
現在の御本尊も大日如来で、庶民の信仰を集めたとされる身代観世音菩薩の現況を辿ることはできませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十番
本所亀戸天神先
福聚山 善應寺 普門院
葛飾郡青戸村寶持院末 新義
本尊:大日如来 弘法大師 興教大師
■『新編武蔵風土記稿 巻之24 葛飾郡之5』(国立国会図書館)
(亀戸村)普門院
新義真言宗青戸村寶持院末 福聚山善應寺ト号ス 本尊大日 開山長賢大永七年(1527年)寂ス 開基ハ千葉中務大輔自胤ニテ 古ハ豊嶋郡橋場村ニアリシヲ 元和二年(1616年)今ノ処ニ移サル 慶安二年(1649年)八月大猷院殿(徳川家光公)当院ヘ御立寄アリテ 即日寺領五石ノ御朱印ヲ賜ハリ ツヒテ御小休ノ御門ヲ建サセラレシシカ 其後絶テ御渡モアラス 御殿モツヒニ取払ハセラレシナリ
観音堂
今ハ大破ニ及ヒテ再建ナラサレハ 観音ハ仮に本堂ニ置リ 縁起ニ云 当寺安置ノ聖観音ハ伝教大師ノ作ニテ 昔ハ下総國足立庄隅田川ノ邊ニアリシカ 大永ニ年(1522年)千葉中務大輔自胤ノ臣佐田善次郎盛光ト云モノ 讒者ノタメニ冤罪ヲ蒙リ 既ニ死刑ニ行レントセシトキ 盛光兼テ信スル処ナレハ カノ観音ニ祈誓セシニ 不思議ヤ奇瑞ノ奇特アリテ助命ニ逢シカハ 夫ヨリ身代ノ観音ト唱フ 斯テ盛光剃髪シテ観慧ト号シ 弥信心浅カラス 自胤モ深ク是ヲ感シテ乃城内ニ一宇ヲ建テ 普門院ト号シ 彼ノ観音ヲ安置スト云々 是ニ拠ハ初ハ寺ノ本尊トナセシト見ユ 其後別ニ堂ヲ建タル 年代等ハ詳ナラス
青龍権現社
■『江戸名所図会 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
福聚山普門院
善應寺と号す。真言宗にして、今大日如来を本尊とす。慶安二年(1649年)住持沙門栄賢●給の譽あるをもって、公命を得て寺産若干を賜り、永く香燭の料に充てしむとらん。
身代観世音菩薩
当寺に安置す。伝教大師の作にして、聖観音なり。
縁起に云ふ。大永二年(1522年)千葉介中務大夫自胤、兼胤の●にて季胤の二男なり。三俣の城中に一宇の梵刹を開き、此霊像を安置し、長賢上人をして始祖たらしむ。今の普門院これなり。三俣といへるは、隅田川、綾瀬川、荒川の落合ひ、三俣になる所をいへり。
昔千葉家在城の地なり。其頃普門院の郭と称しけるとなり。然れども、後兵火にかかり、堂塔ことごとく灰燼せり。此際にいたり、洪鐘一口隅田川に沈没す。其地を名づけて鐘ヶ潬と呼ぶ。元和ニ年(1616年)(或云六年)住持栄眞法印、公命によりて三俣の地を転じて、寺院を今の亀戸の邑に移すといふ。
往古千葉自胤の臣佐田善次盛光、後剃髪して観慧と号せり。虚名の罪により、誅に伏す時、日頃念ずる所の霊像の加護にて、其白刃段々に壊し、危難を免れたり。
此霊像により、自胤三俣の城中に当寺を創し、長賢上人を導師として且開祖とす。
又天文三年(1534年)、國中大に疫疾流行し、死に至る者少なからず。されど此霊像を念ずる輩は悉く病平癒し、将病に臨まざる者は、病者と床を等しうすといへども、敢て染延の患なし。
其後住持長栄上人、睡眠の中、一老翁の来るあり。吾は是施無畏大士なり、多くの人に代り、疫病を受く、故に病苦一身に逼れり。上人願くは我法一千坐を修して、予が救世の加彼力となるべしと。夢覚めて後、益々敬重を加へ、本尊を拝し奉るに、佛體に汗みちて蓮臺に滴る。感涙肝に銘じ、夫より昼夜不退に一千坐の観音供を修しけば、國中頓に疫疾の患を遁れけるとぞ。故に世俗身代観世音と唱へ奉るとなり。

「普門院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「普門院」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第4,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・東武亀戸線「亀戸」駅で徒歩約10分。
亀戸天神と亀戸香取神社の間に広大な山内を構えています。


【写真 上(左)】 山内入口-1
【写真 下(右)】 山内入口-2
山内入口からすでに鬱蒼とした樹木に覆われ、これが本堂までつづいています。
緑の少ない下町にはめずらしいくらいの緑濃い山内。
門柱脇に「伊藤左千夫の墓」の石碑。
伊藤左千夫は正岡子規の門人でアララギ派の歌人として知られ『野菊の墓』の作者としても有名で、普門院が墓所となります。
それにしても、この植物たちの繁茂ぶりはいったいどうしたことでしょう。マント群落のようにあたりを覆い尽くしています。
山内の各所には廃棄された?家具やブルーシートが掛けられ、これがまたなんとも雑然としたイメージを醸し出しています。
御府内霊場の札所としては異色の空気感があり、おそるおそる足を進めます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 観世音菩薩像
参道右手、台座のうえに端正な相貌の観世音菩薩坐像が御座します。
坐像で手に経巻を持たれているので、おそらく持経観世音菩薩かと思われます。
この観音様の奉持される経巻には、お如来さまの説法の内容がすべて収められているとのこと。
旧御本尊の身代観世音菩薩との関連を考えましたが、どうも身代観世音菩薩と持経観世音菩薩がストレートに結びつかず、別の系譜の観音様かもしれません。


【写真 上(左)】 毘沙門堂
【写真 下(右)】 毘沙門堂の扁額
その先左手の宝形造の堂宇が毘沙門堂。亀戸七福神(毘沙門天)の拝所です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
正面が近代建築の本堂。樹木に覆われて全貌はよくわかりませんでした。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股の意匠が凝らされています。
向拝正面鉄扉のうえに山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 院号標
9月と10月の2回参拝したのですが、いずれもものすごい数の蚊の襲撃に遭い、格闘しながらの読経となりました。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受。
山内の様子から、おそるおそるお伺いしたのですが、ご対応はいたって普通で亀戸七福神の御朱印も拝受できました。
ただし、原則書置授与のようです。
なお、身代観世音菩薩の現況については、参拝時、不勉強にも認識がなかったのでお伺いしておりません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 亀戸七福神の御朱印
■ 第41番 十善山 蓮花寺 密蔵院
(みつぞういん)
中野区沼袋2-33-4
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第41番、弘法大師二十一ヶ寺第17番
第41番札所は、中野・沼袋の密蔵院です。
御府内霊場では真言宗御室派の札所寺院は第32番圓満寺とこちらのふたつしかありません。
真言宗御室派の総本山、仁和寺は真言宗の流派「広沢流」の本拠で、仁和寺門跡として2世性信入道親王(大御室)が就任されて以来、江戸末期まで門跡には法親王(皇族)を迎えたというすこぶる格式の高い寺院です。
当山も『寺社書上』『御府内寺社備考』などに「京都御室御所仁和寺宮末」と記されています。
第41番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに密蔵院なので、御府内霊場開創時から一貫して密蔵院であったとみられます。
中野仏教会Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
密蔵院は北條氏直公(1562-1591年)の持仏・将軍(勝軍)地蔵菩薩を御本尊として、小田原城内に創建といいます。
開山は氏直公の帰依を受けた小田原蓮華寺の住持、慶誉法印(寛永十三年(1636年)寂)。
北條氏没落後、徳川家康公は慶誉法印を招聘し、その経歴知見から王子権現の別当・金輪寺の住職に誘いましたが、慶誉法印はこれを受けず弟子の宥雄を金輪寺住職に奉じ、みずからは慶長十六年(1611年)矢之倉に寺地30間を拝領、将軍(勝軍)地蔵菩薩を奉安して当山を結構したといいます。
また、北條家より伝わる愛宕権現を山内に安置して鎮守としたといいます。
こちらの愛宕権現の御神体は、のちに芝の愛宕社に安するとも。
正保元年(1644年)、浅草永住町(浅草寺町)に寺地を拝領して移転。
当時、御室法親王の隠室となり、代々仁和寺門跡に直属したと伝わります。
護摩堂は愛宕権現との合殿でしたがこれを失い、愛宕権現は本堂に奉安といいます。
護摩堂御本尊の不動明王は弘法大師の御作と伝わりますが、文化三年(1806年)に焼失したとも。
火災で寺伝類をことごとく焼失し、詳らかな由緒・沿革は伝わっていないようです。
明治45年に墓地を現在地(沼袋)に移し、昭和7年に寺院の移転を概ね終えました。
沼袋には寺院が多く集まっていますが、各寺院の沿革を追うと、関東大震災で被災した浅草寺町辺の寺院が東京府豊玉郡野方村沼袋(現在の中野区沼袋)に移転し、寺町を形成したようです。
当山は第二次大戦末期の空襲で浅草に残した堂宇を全焼、次いで沼袋の堂宇も戦禍に遭い、この時に多くの寺宝・寺什を失ったといいます。
昭和25年に現在地に本堂を再建。
幾多の変遷を辿りながらも、御府内霊場第41番の札所は堅持されて今日に至ります。
草創の縁起からすると、もともとの御本尊は勝軍地蔵菩薩。
現在の御本尊・御府内霊場札所本尊ともに大日如来ですが、『寺社書上』『御府内寺社備考』には「本堂 本尊 十一面観音座像」、江戸末期の『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:十一面観世音 勝軍地蔵尊 弘法大師」とあり、御本尊・札所本尊ともに変遷があった模様。
また、史料によると勝軍地蔵菩薩・愛宕権現を通じて芝の愛宕社とも関係があったようですが、寺伝類を焼失したため詳細は辿れないようです。
当山は「弘法大師二十一ヶ寺」第17番の札所でもあります。
この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。
これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。
「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。
「弘法大師二十一ヶ寺」の札所リストは↓『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)に記載されています。ご参考までにリストします。
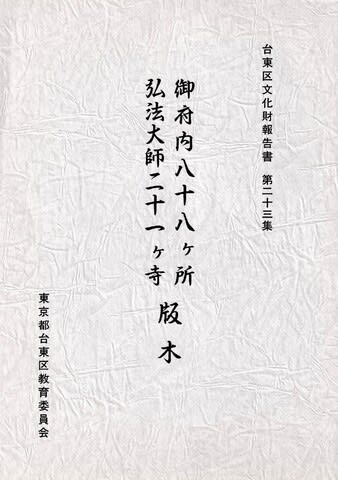
【弘法大師二十一ヶ寺】
1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺 真言宗御室派 文京区湯島1-6-2
2番 宝塔山 多寶院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35
3番 五剣山 普門寺 大乗院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16
4番 清光院 台東区下谷(廃寺)
5番 恵日山 延命寺 地蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8
6番 阿遮山 円満寺 不動院 真言宗智山派 台東区寿2-5-2
7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺 真言宗智山派 台東区寿2-8-15
8番 高野山 金剛閣 大徳院 高野山真言宗 墨田区両国2-7-13
9番 青林山 最勝寺 龍福院 真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2
10番 本覚山 宝光寺 自性院 新義真言宗 台東区谷中6-2-8
11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院 真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14
12番 神勝山 成就院 真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12
13番 広幡山 観蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5
14番 望月山 般若寺 正福院 真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21
15番 仏到山 無量寿院 西光寺 新義真言宗 台東区谷中6-2-20
16番 鶴亭山 隆全寺 威光院 真言宗智山派 台東区寿2-6-8
17番 十善山 蓮花寺 密蔵院 真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)
18番 象頭山 観音寺 本智院 真言宗智山派 北区滝野川1-58-2
19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16
20番 玉龍山 弘憲寺 延命院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2
21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺 真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6
このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。
●「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の札所ながら、「御府内八十八ヶ所」の札所ではない寺院の例

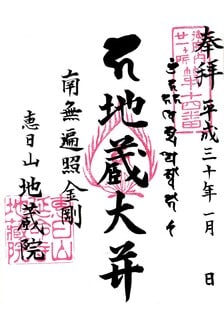
【写真 上(左)】 五剣山 普門寺 大乗院(元浅草)
【写真 下(右)】 恵日山 延命寺 地蔵院(元浅草)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十一番
浅草新寺町
勝軍山 蓮花寺 密蔵院
京都御室御所末 古義
本尊:十一面観世音 勝軍地蔵尊 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.1』
京都御室御所仁和寺宮末 浅草新寺町
勝軍山密蔵院
宗旨古義真言宗
当院小田原北条氏直公祈願所
開山 慶誉法印 寛永十三年寂
開基 不分明
本堂
本尊 十一面観音座像 丈一尺七寸作不詳
大師 十三仏 観音 不動尊 護諸童子経画像
当院十八世光照法印筆一巻 勝軍地蔵画像一幅
鎮守社
愛宕大権現 本地佛勝軍地蔵
当院開山慶誉ハ相州小田原蓮華寺住持シ 北條氏直公ニ親ミ深ク御祈祷等相●●
氏直没落之後 東照宮様慶誉を被(略)其由緒を●慶誉を王子権現別当金輪寺住職社例ヲ改可修神法旨蒙御上意候●共 極老たる●恐多も辞退申上 弟子宥雄ヲ金輪寺住職ニ奉●●(略)尚北條家より伝ル所之愛宕権現ヲ境内二安置シ可為鎮守●●
大猷院様御代正保元年(1644年)地所替●●付 於当浅草寺地三十間四方拝領仕候 もとハ護摩堂ありて愛宕と合殿なりし●再建ならす 愛宕ハ本堂に安す 護摩堂本尊不動ハ弘法大師作にて空海と志るし手判ありしと云 文化三年(1806年)焼失す 勝軍地蔵縁起もありしか 明暦火災に焼失せりと云伝ふ
北条氏より伝ふる愛宕神体ハ 今芝愛宕社ト安す所是なり ●本地仏ハ当寺に安す●と云伝ふ●と、古火災の時記録皆焼失して其由来詳ならすといふ
■『中野区史下巻1』(P.447)(中野区立図書館)
密蔵院
江古田四丁目一、四八九。本尊十一面観音。勝軍山密蔵院蓮花寺と号する。もと真言宗御室派の院室地であつたが、今は同宗東寺派に屬する。
はじめ北條氏直が相模小田原に創建し、勝軍地蔵を安置し祈願所としたのであつた。山号はこれに因由する。
北條氏没落後、慶長十六年(1611年)に至り、僧慶譽、勝軍地蔵の木像を背負うて江戸に来り、矢之倉に小庵を結んだが、正保元年(1644年)淺草永住町に移つた。
明治四十五年墓地を現在の地に移轉し、昭和七年に至り、寺をも同所に移した。

「密蔵院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
西武新宿線「沼袋」駅北側の寺院が集まるエリアの一画にあります。
駅から徒歩約10分ほどです。


【写真 上(左)】 冠木門
【写真 下(右)】 院号札
路地に面して冠木門で、門柱には院号が掲げられています。
こぢんまりとした山内は、よく手入れされ心落ち着く感じがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
正面の本堂は桟瓦葺で様式は不明。
堂宇というより民家を思わせるつくりで、向拝柱はありますが水引虹梁はありません。
参拝後、本堂向かって右の庫裡で御朱印をお願いすると、本堂に上げていただけ、たしか本堂内で揮毫いただいたと思います。
本堂内で参拝できる、貴重な札所のひとつです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第四十一番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第42番 蓮葉山 妙智院 観音寺
(かんのんじ)
公式Web
台東区谷中5-8-28
真言宗豊山派
御本尊:大日如来・阿弥陀如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第42番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番
第42番札所は、御府内霊場札所の集中エリア・谷中の観音寺です。
御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。
第42番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに観音寺なので、御府内霊場開創時から一貫して谷中の観音寺であったとみられます。
公式Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
観音寺は、慶長十六年(1611年)神田北寺町(現・千代田区神田錦町周辺)に、長福寺を号し尊雄和尚を開基に創建されました。
神田など、江戸城まわりにあった寺院は江戸城の拡張やこれにともなう武家屋敷地化もあって次々と移転を命ぜられましたが、当山もその例にもれず、慶安元年(1648年)御用地として召し上げられ、谷中清水坂(現・台東区池之端周辺)に移転したもののこちらもまた御用地となり、延宝八年(1680年)現在地に移転しています。
元禄十四年(1701年)三月十四日、浅野内匠頭長矩が江戸城内にて刃傷。即日切腹となり浅野家はお家断絶、領地を没収されました。
元禄十五年(1702年)二月、当山でしばしば密議を重ねた近松勘六行重、奥田貞右衛門行高(ともに当山6世朝山和尚(文良)の兄弟)は江戸を下り、十二月十四日赤穂義士討入り。
主君の仇の吉良上野介義央の首級をあげ本懐を遂げました。
元禄十六年(1703年)赤穂義士切腹。当山は義士の供養塔を建て、義士の菩提を弔うこととなりました。
これより、当山は「赤穂義士ゆかりの寺」としても知られています。
享保元年(1716年)8代将軍・徳川吉宗公の長子の長福丸(家重公)と寺号が重なるため、ときの住職朝海和尚はこれをはばかり寺号を長福寺から観音寺へと改めました。
『寺社書上』ではこの朝海和尚を中興開基とし、真言宗江戸四箇寺の本所弥勒寺末とされたと記され、公式Webでも朝海和尚の功績がとり上げられています。
谷中は江戸城周辺から寺院の移転が相次ぎ、元禄年中(1688-1703年)頃には御府内有数の寺町となりました。
御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1763年)とみられるので、御府内霊場に谷中の札所が多数定められる下地はすでに整っていました。
公式Webにも「宝暦年中(1751-1763年)江戸府内八十八所霊場巡拝が設けられ、観音寺は四十二番札所となる。」と明記されています。
明和九年(1772年)、行人坂の大火で諸堂宇を失い、寺伝類の多くも焼失しました。
しかし、谷中の中心にある御府内霊場札所で、観音堂安置の如意輪観音信者の助力もあってか、観音寺の復興ははやかったと伝わります。
安永年中(1772-1780年)には「三十三所観音参/上野より王子駒込辺西国の写し霊場」が開創。
観音寺は第32番札所に定められ、弘法大師(御府内霊場)、観音(上野王子駒込霊場)両霊場の札所となりました。
『江戸歳事記 4巻 付録1巻 [2]』(国立国会図書館)に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」の一覧があり、たしかに第32番として「谷中観音寺」がみられ、札所本尊は如意輪観世音菩薩となっています。
(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」)様)
この霊場は「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」とも呼ばれますが、筆者がまわった範囲では「西国霊場」の方が通りがよく、札所印つき御朱印授与の札所もあれば、廃寺や御朱印じたい不授与の札所も多く、御朱印拝受しにくい霊場となっています。
→ ■ 希少な札所印


↑ 第4番札所思惟山 正受院(北区滝野川)の札所御朱印。
「西國四番寫」の札所印が捺されています。
明治初頭の神仏分離・廃仏毀釈により寺地を官有地とされましたが、住職および檀信徒の寺運繁栄の努力により昭和18年現本堂が落慶しています。
このとき境内佛(濡佛)であった胡銅製大日如来像と阿弥陀如来像が本堂内に遷座され、御本尊となっています。
公式Webによると、当山創建当初の御本尊は五智如来木座像(金剛界五佛仏/大日如来(中心)、阿閦如来(東)、宝生如来(南)、阿弥陀如来(西)、不空成就如来(北))で開基・尊雄和尚が師子相承されていた尊佛でしたが、火災により失われました。
ついで観音堂本尊であった如意輪観世音菩薩と不空羂索観世音菩薩が御本尊となられ、昭和18年現本堂落慶とともに大日如来・阿弥陀如来両尊が御本尊となりました。
旧御本尊の観音菩薩像は、現在本堂内位牌堂に安置されています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
四十二番
谷中●●門前町
蓮葉山 妙智院 観音寺
本所彌勒寺末 新義
本尊:大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [112] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.104』
本所弥勒寺末 谷中不唱小名
蓮葉山妙智院観音寺
起立慶長年中
権現様御代 神田北寺町ニて拝領仕候
大猷院様御代 御用地ニ相成代地谷中清水坂ニ●右之●坪数程拝領仕候
厳有院様御代 御用地ニ相成 延寶八年只今之場所代地拝領仕候
開基 尊雄 寂年月不知
中興開基 当寺第六世朝快住職中 本所弥勒寺之末寺ニ●
右等之始末古記録等焼失仕候ニ付●●分不申候
本堂
本尊五智如来
四佛 阿閦 宝生 弥陀 釈迦 各木坐像
弘法大師 興教大師 各木坐像
護摩堂
本尊不動明王木坐像
観音堂
本尊如意輪観音木坐像
稲荷社
濡佛二体 大日如来 阿弥陀
■『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
観音寺(谷中上三崎北町七番地)
本所彌勒寺末、蓬莱山と号す。本尊大日如来。慶長十六年、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年谷中清水坂に移り、延寶八年現地に転じた。開山は僧尊雄。境内に観音堂(如意輪観音安置)、大師堂(弘法大師像安置)、駄枳尼天堂(駄枳尼天安置)がある。

「観音寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
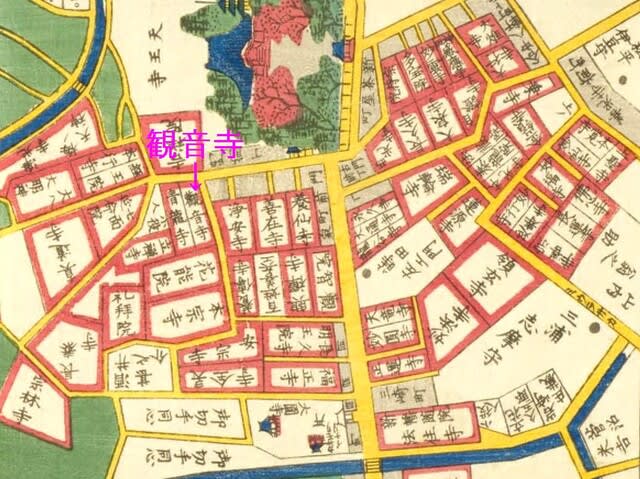
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約5分。メトロ千代田線「千駄木」駅からも歩けます。
谷中は都内有数の寺院の集積地で、複数の御府内霊場札所が立地します。
観音寺は日暮里駅から谷中銀座(夕やけだんだん)に至る御殿坂と千駄木から谷中にのぼる三崎坂を南北に結ぶ通り沿いにあります。
→ 谷中マップ
南側路地沿いの築地塀は国の国の登録有形文化財(建造物)に指定され、その趣きある風景は寺町・谷中のシンボルとしてしばしばメディアなどでとり上げられます
「観音寺の築地塀」は、幕末頃の築造で、南面のみ現存しています。


【写真 上(左)】 築地塀
【写真 下(右)】 山内入口
前面道路から少し引き込んで石畳。
右手石標は特徴ある字体の御寶号「南無大師遍照金剛」。


【写真 上(左)】 御寶号の石標
【写真 下(右)】 観音霊場札所碑


【写真 上(左)】 遠忌碑
【写真 下(右)】 山門
左手の「西国三十二番 近江観音寺うつし」とある石標は、「上野王子駒込辺三十三観音霊場」第32番の札所標。
そのとなりには弘法大師九百五十年と興教大師六百五十年の併記遠忌碑。
山門は切妻屋根本瓦葺で、おそらく薬医門と思われます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
参道正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、照り気味に秀麗に葺きおろす屋根が風格を感じさせます。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。
向拝正面の4連の桟唐戸が意匠的に効いています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂右手
本堂向かって右手には宝形造銅板葺の大師堂があり、こちらは御府内霊場の拝所となっています。


【写真 上(左)】 大師堂-1
【写真 下(右)】 大師堂-2
堂宇前には年季の入った御府内霊場の札所標。
堂宇前面には複数の御府内霊場の札所板、向拝見上げに御府内霊場の札所板と上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所板。
御府内二十一ヶ所第参番の札所札もみえます。
『江戸歳事記』では、「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」の第32番札所(観音寺)の札所本尊は如意輪観世音菩薩となっていますが、この札所板には千手観世音菩薩と刻されています。
また、札所板の霊場名は「西國三十三ヶ所寫」とみえ、やはり従前からこの霊場名で通っていたようです。
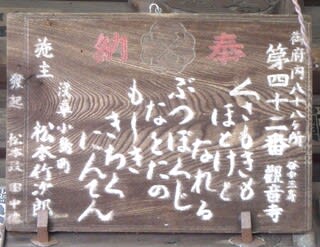

【写真 上(左)】 御府内霊場札所板-1
【写真 下(右)】 御府内霊場札所板-2
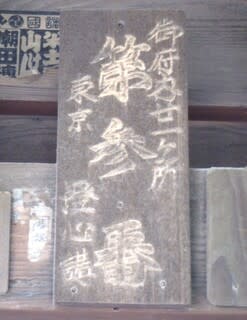

【写真 上(左)】 御府内廿一ヶ所札所板
【写真 下(右)】 観音霊場札所板と千社札
軒裏を埋める古びた千社札が、札所としての古い歴史を感じさせます。
(現在はほとんどの寺社で千社札の貼付は禁止されています。)
堂内中央に弘法大師坐像、向かって右手に不動明王立像、左に興教大師坐像を奉安。
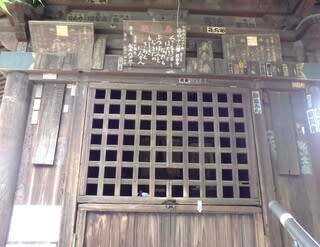

【写真 上(左)】 大師堂向拝
【写真 下(右)】 赤穂義士供養塔
本堂と大師堂の間には赤穂義士の供養塔と宝篋印塔。
その周辺には、聖観世音菩薩立像、如意輪観世音菩薩の石仏、救世菩薩地蔵尊などが安置されています。
『全国霊場大事典』(六月書房)によると、御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされています。
同書によると、信州・浅間山真楽寺の憲浄僧正と千葉県松戸の諦信によって四国八十八ヶ所霊場が写されたもの。
『全国霊場巡拝事典』(大法輪閣)では、宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』に「江戸にも此頃は信州浅間山の上人本願にて、四国の八十八箇所を移して立札など見えたり」とあり、文化十三年(1816年)の札所案内には「宝暦五乙亥三月下総葛飾松戸宿諦信の子、出家して信州浅間山真楽寺の住になりぬ。両人本願して江戸に霊場をうつす」とあることを紹介しています。
また、このことは「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」と刻まれた札所碑が第42番観音寺にあり、他の札所にも同様の石碑が残ることからも裏付けられるとされています。
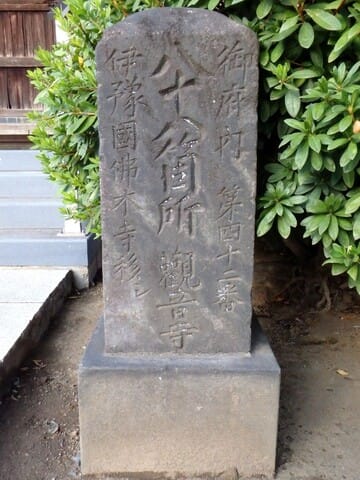
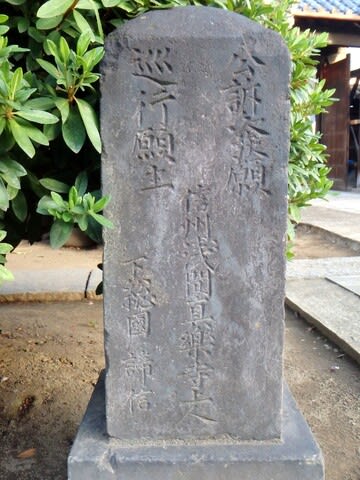
【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」とあります
本堂並びにある客殿も登録有形文化財(建造物)に指定されています。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 客殿からの本堂
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
こちらの御朱印拝受については、以前はいささか敷居が高い印象がありましたが、久しぶりにWebで観音寺の御朱印情報を検索してみたら、なんとスワロフスキー(クリスタルガラス)付御朱印や切り絵御朱印で有名になっている模様。(ぜんぜん知らなかった。)
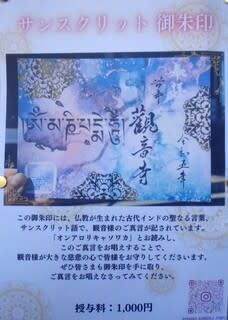

【写真 上(左)】 スワロフスキー付御朱印の案内
【写真 下(右)】 スワロフスキー付御朱印
大師堂前には↓のような掲示が依然としてあります。
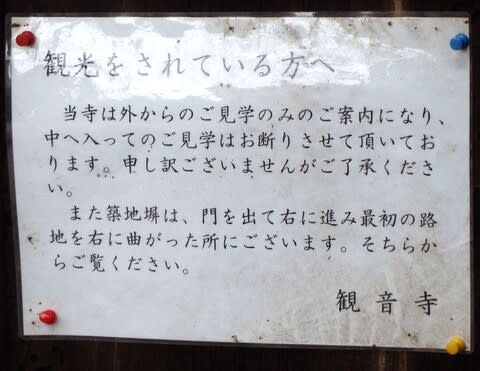
スワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印目当ての人も、いちおうは参拝しているのでしょうか・・・。
谷中の西光寺も以前は御朱印不授与でしたが、いまでは絵御朱印が人気となり、遙拝を条件とした御朱印郵送対応までされています。
→ ■ 谷中の御朱印・御首題
やはり絵御朱印の人気はかなりのものがありそうです。
個人的には絵御朱印や切り絵御朱印にさほど興味はありませんが、これをきっかけに仏教に興味をもつ人が増えるのは、意義あることなのかもしれません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
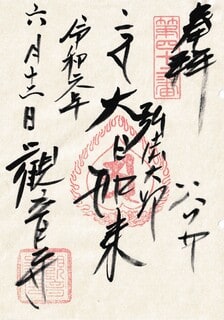
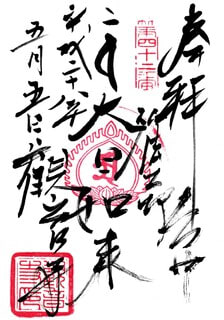
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に金剛界大日如来のお種子「バン」、「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫とお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
公式Web掲載の御本尊は智拳印を結ばれる金剛界大日如来、当山の当初の御本尊は五智如来で金剛界系です。
御寶印の「ア」は、胎蔵大日如来のお種子というより、通種子(すべての尊格をあらわす)として用いられているのかもしれません。
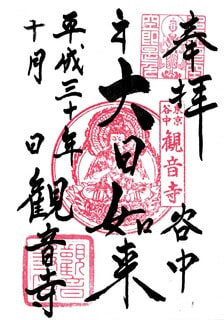

【写真 上(左)】 御本尊・大日如来の御朱印
【写真 下(右)】 お種子(ア)の御朱印
上記のとおり、現在観音寺の御朱印はスワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印がメインの模様で、無申告での墨朱御朱印は大日如来の揮毫御朱印か、お種子(ア)の揮毫御朱印が授与されている模様です。
御府内霊場御朱印の汎用御朱印帳への授与については不明です。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-15)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Ebb and Flow (凪のあすから) - LaLa(歌ってみた)
■ 思い出の向こうに - 小川範子
■ 空に近い週末 - 今井美樹
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第40番 福聚山 善應寺 普門院
(ふもんいん)
江東区亀戸3-43-3
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第40番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第30番、亀戸七福神(毘沙門天)
第40番札所は、下町・亀戸の普門院です。
第40番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに普門院なので、御府内霊場開創時から一貫して亀戸の普門院であったとみられます。
第40番の四ッ谷の真成院も御府内霊場開創時からの札所とみられるので、第39番の四ッ谷から第40番は亀戸へと、一気にエリアを変えることになります。
これは本四国八十八ヶ所霊場が第39番の延光寺(高知県(土佐國)宿毛市)から第40番の観自在寺(愛媛県(伊予國)愛南町)で国が変わることと関連があるのかもしれません。
本四国霊場は四国内の阿波國(1-23番)、土佐國(24-39番)、伊予國(40-65番)、讃岐國(66-88番)と国別に構成されており、それぞれ発心の道場、修行の道場、菩提の道場、涅槃の道場とされています。
御府内霊場をみると、23番(薬王寺/市ヶ谷)→24番(三光寺/内藤新宿)は比較的近いですが、39番(真成院/四ッ谷)→40番(普門院/亀戸)は大きくエリアを変え、65番(大聖院/芝三田寺町)→66番(東覚寺/田端)とこちらもエリアを移しています。
御府内の東端は亀戸辺とされ、亀戸天神御鎮座の参詣地でもあったため、御府内霊場札所の配置は自然な成り行きかも。
なお、これより東寄りは荒川辺八十八ヶ所霊場、荒綾八十八ヶ所霊場、新四国四箇領八十八ヵ所霊場、南葛八十八ヶ所霊場など、下町の弘法大師霊場の領域となり、現在巡拝するにはよりマニアックな踏み込みが必要となります。
亀戸あたりになると、『寺社書上』『御府内寺社書上』への記載はなくなりますが、『新編武蔵風土記稿』の収録エリアなのでこちらから追っていけます。
亀戸は江戸の名所のひとつなので『江戸名所図会』にも挿絵を添えてしっかり収録されています。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
普門院は大永二年(1522年)三股(隅田川・荒川・綾瀬川の合流点、現・足立区千住周辺)の城中に創建されました。
開山は長賢上人、開基は千葉中務大輔自胤と伝わります。
千葉自胤(1446-1494年)は室町時代の武将で、武蔵千葉氏第3代当主とされます。
千葉氏は桓武平氏の名族で、下総に勢力を張り坂東八平氏・関東八屋形のひとつに数えられました。
千葉(介)常胤は、頼朝公の旗揚げに呼応し、公の信任を得て、鎌倉時代には下総守護の家柄となりました。
千葉一族は繁栄した一方、同族間の確執が多く争いも絶えなかったといいます。
室町時代中期の千葉氏の嫡流は千葉胤賢でしたが、享徳の乱(1455-1483年)で古河公方・足利成氏方で同族の原胤房・馬加康胤に殺され、遺児となった実胤と自胤は下総八幡荘の市河城へ逃れました。
しかし、成氏方の簗田持助に敗れ、康正二年(1456年)市河城を失って武蔵へと逃れました。
実胤は石浜城(現・台東区橋場)、自胤は赤塚城(現・板橋区赤塚)に拠り、後に兄の実胤が隠遁したため、自胤が石浜城主となり千葉氏当主を嗣ぎました。
自胤は本領である房総への帰還を目指しましたが、分家の岩橋氏が勢力をふるい岩橋孝胤は千葉氏当主を自称、後に公認されました。
惣領筋の自胤はそれでも幾度か房総奪還を図りますが、岩橋孝胤は勢力を固めて下総千葉氏継承を確定しました。
自胤の子孫はよんどころなく武蔵に定着し、武蔵千葉氏とも呼ばれました。
普門院はこの千葉自胤が、自身が拠った城内に開基と伝わります。
『新編武蔵風土記稿』に「古ハ豊嶋郡橋場村ニアリシ」とあるのは、おそらく石浜城内を指すとみられます。
『江戸名所図会』には「三俣の城中に一宇の梵刹を開き(略)三俣といへるは、隅田川、綾瀬川、荒川の落合ひ、三俣になる所をいへり。昔千葉家在城の地なり。」とあります。
三俣はいまの千住周辺とされ、石浜城とはべつに三俣(三原)城という城があったのかも。
当初の普門院の御本尊は伝教大師の御作とも伝わる観世音菩薩で、自胤の信仰も篤く、自城内に一宇を建ててこの観世音菩薩を奉安したといいます。
また、千葉自胤の臣・佐田善次郎盛光が讒言を受け斬られそうになったとき、盛光が日頃信仰するこの観音像に祈ったところたちまち刀の刃がこぼれ、盛光は死を免れたとのこと。
天文三年(1534年)、この地に疫病が流行した際、この観音像を念ずる者はことごとく病が平癒し、患者と床を同じくしても感染しなかったといいます。
この観音様が衆生の身代りとなって疫病を引き受けられたという逸話もあり、以来「身代観世音」と尊称されて人々の信仰を集めました。
元和二年(1616年)荒川辺から現在地の亀戸に移転。
この時、誤って梵鐘を隅田川に沈めてしまい、鐘ヶ淵の地名の由来になったともいいます。
慶安二年(1649年)八月には大猷院殿(徳川家光公)の御渡りあって御休所も設けられましたが、いつしか取払われたとのこと。
「猫の足あと」様には『江東区の民俗城東編』の興味深い記事が紹介されているので、孫引きさせていただきます。
「『浅草区誌』によれば、鐘ヶ淵に沈んだ鐘は法元寺(『再校江戸砂子』註:保元寺)、普門院(『新編江戸志』)、長昌寺(『武蔵古蹟志』)と三説をあげている。『帝都郊外発展誌』によれば、安永年中(1772-1781年)に栄範上人が本尊を身代観音菩薩から大日如来に改め、観音堂を別に建立した。」
これによると安永年中(1772-1781年)までの普門院の御本尊は身代観世音菩薩で、栄範上人が御本尊を身代観音菩薩から大日如来に改めたということになります。
現在の御本尊も大日如来で、庶民の信仰を集めたとされる身代観世音菩薩の現況を辿ることはできませんでした。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十番
本所亀戸天神先
福聚山 善應寺 普門院
葛飾郡青戸村寶持院末 新義
本尊:大日如来 弘法大師 興教大師
■『新編武蔵風土記稿 巻之24 葛飾郡之5』(国立国会図書館)
(亀戸村)普門院
新義真言宗青戸村寶持院末 福聚山善應寺ト号ス 本尊大日 開山長賢大永七年(1527年)寂ス 開基ハ千葉中務大輔自胤ニテ 古ハ豊嶋郡橋場村ニアリシヲ 元和二年(1616年)今ノ処ニ移サル 慶安二年(1649年)八月大猷院殿(徳川家光公)当院ヘ御立寄アリテ 即日寺領五石ノ御朱印ヲ賜ハリ ツヒテ御小休ノ御門ヲ建サセラレシシカ 其後絶テ御渡モアラス 御殿モツヒニ取払ハセラレシナリ
観音堂
今ハ大破ニ及ヒテ再建ナラサレハ 観音ハ仮に本堂ニ置リ 縁起ニ云 当寺安置ノ聖観音ハ伝教大師ノ作ニテ 昔ハ下総國足立庄隅田川ノ邊ニアリシカ 大永ニ年(1522年)千葉中務大輔自胤ノ臣佐田善次郎盛光ト云モノ 讒者ノタメニ冤罪ヲ蒙リ 既ニ死刑ニ行レントセシトキ 盛光兼テ信スル処ナレハ カノ観音ニ祈誓セシニ 不思議ヤ奇瑞ノ奇特アリテ助命ニ逢シカハ 夫ヨリ身代ノ観音ト唱フ 斯テ盛光剃髪シテ観慧ト号シ 弥信心浅カラス 自胤モ深ク是ヲ感シテ乃城内ニ一宇ヲ建テ 普門院ト号シ 彼ノ観音ヲ安置スト云々 是ニ拠ハ初ハ寺ノ本尊トナセシト見ユ 其後別ニ堂ヲ建タル 年代等ハ詳ナラス
青龍権現社
■『江戸名所図会 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
福聚山普門院
善應寺と号す。真言宗にして、今大日如来を本尊とす。慶安二年(1649年)住持沙門栄賢●給の譽あるをもって、公命を得て寺産若干を賜り、永く香燭の料に充てしむとらん。
身代観世音菩薩
当寺に安置す。伝教大師の作にして、聖観音なり。
縁起に云ふ。大永二年(1522年)千葉介中務大夫自胤、兼胤の●にて季胤の二男なり。三俣の城中に一宇の梵刹を開き、此霊像を安置し、長賢上人をして始祖たらしむ。今の普門院これなり。三俣といへるは、隅田川、綾瀬川、荒川の落合ひ、三俣になる所をいへり。
昔千葉家在城の地なり。其頃普門院の郭と称しけるとなり。然れども、後兵火にかかり、堂塔ことごとく灰燼せり。此際にいたり、洪鐘一口隅田川に沈没す。其地を名づけて鐘ヶ潬と呼ぶ。元和ニ年(1616年)(或云六年)住持栄眞法印、公命によりて三俣の地を転じて、寺院を今の亀戸の邑に移すといふ。
往古千葉自胤の臣佐田善次盛光、後剃髪して観慧と号せり。虚名の罪により、誅に伏す時、日頃念ずる所の霊像の加護にて、其白刃段々に壊し、危難を免れたり。
此霊像により、自胤三俣の城中に当寺を創し、長賢上人を導師として且開祖とす。
又天文三年(1534年)、國中大に疫疾流行し、死に至る者少なからず。されど此霊像を念ずる輩は悉く病平癒し、将病に臨まざる者は、病者と床を等しうすといへども、敢て染延の患なし。
其後住持長栄上人、睡眠の中、一老翁の来るあり。吾は是施無畏大士なり、多くの人に代り、疫病を受く、故に病苦一身に逼れり。上人願くは我法一千坐を修して、予が救世の加彼力となるべしと。夢覚めて後、益々敬重を加へ、本尊を拝し奉るに、佛體に汗みちて蓮臺に滴る。感涙肝に銘じ、夫より昼夜不退に一千坐の観音供を修しけば、國中頓に疫疾の患を遁れけるとぞ。故に世俗身代観世音と唱へ奉るとなり。

「普門院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「普門院」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第4,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・東武亀戸線「亀戸」駅で徒歩約10分。
亀戸天神と亀戸香取神社の間に広大な山内を構えています。


【写真 上(左)】 山内入口-1
【写真 下(右)】 山内入口-2
山内入口からすでに鬱蒼とした樹木に覆われ、これが本堂までつづいています。
緑の少ない下町にはめずらしいくらいの緑濃い山内。
門柱脇に「伊藤左千夫の墓」の石碑。
伊藤左千夫は正岡子規の門人でアララギ派の歌人として知られ『野菊の墓』の作者としても有名で、普門院が墓所となります。
それにしても、この植物たちの繁茂ぶりはいったいどうしたことでしょう。マント群落のようにあたりを覆い尽くしています。
山内の各所には廃棄された?家具やブルーシートが掛けられ、これがまたなんとも雑然としたイメージを醸し出しています。
御府内霊場の札所としては異色の空気感があり、おそるおそる足を進めます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 観世音菩薩像
参道右手、台座のうえに端正な相貌の観世音菩薩坐像が御座します。
坐像で手に経巻を持たれているので、おそらく持経観世音菩薩かと思われます。
この観音様の奉持される経巻には、お如来さまの説法の内容がすべて収められているとのこと。
旧御本尊の身代観世音菩薩との関連を考えましたが、どうも身代観世音菩薩と持経観世音菩薩がストレートに結びつかず、別の系譜の観音様かもしれません。


【写真 上(左)】 毘沙門堂
【写真 下(右)】 毘沙門堂の扁額
その先左手の宝形造の堂宇が毘沙門堂。亀戸七福神(毘沙門天)の拝所です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
正面が近代建築の本堂。樹木に覆われて全貌はよくわかりませんでした。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股の意匠が凝らされています。
向拝正面鉄扉のうえに山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 院号標
9月と10月の2回参拝したのですが、いずれもものすごい数の蚊の襲撃に遭い、格闘しながらの読経となりました。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受。
山内の様子から、おそるおそるお伺いしたのですが、ご対応はいたって普通で亀戸七福神の御朱印も拝受できました。
ただし、原則書置授与のようです。
なお、身代観世音菩薩の現況については、参拝時、不勉強にも認識がなかったのでお伺いしておりません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 亀戸七福神の御朱印
■ 第41番 十善山 蓮花寺 密蔵院
(みつぞういん)
中野区沼袋2-33-4
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第41番、弘法大師二十一ヶ寺第17番
第41番札所は、中野・沼袋の密蔵院です。
御府内霊場では真言宗御室派の札所寺院は第32番圓満寺とこちらのふたつしかありません。
真言宗御室派の総本山、仁和寺は真言宗の流派「広沢流」の本拠で、仁和寺門跡として2世性信入道親王(大御室)が就任されて以来、江戸末期まで門跡には法親王(皇族)を迎えたというすこぶる格式の高い寺院です。
当山も『寺社書上』『御府内寺社備考』などに「京都御室御所仁和寺宮末」と記されています。
第41番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに密蔵院なので、御府内霊場開創時から一貫して密蔵院であったとみられます。
中野仏教会Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
密蔵院は北條氏直公(1562-1591年)の持仏・将軍(勝軍)地蔵菩薩を御本尊として、小田原城内に創建といいます。
開山は氏直公の帰依を受けた小田原蓮華寺の住持、慶誉法印(寛永十三年(1636年)寂)。
北條氏没落後、徳川家康公は慶誉法印を招聘し、その経歴知見から王子権現の別当・金輪寺の住職に誘いましたが、慶誉法印はこれを受けず弟子の宥雄を金輪寺住職に奉じ、みずからは慶長十六年(1611年)矢之倉に寺地30間を拝領、将軍(勝軍)地蔵菩薩を奉安して当山を結構したといいます。
また、北條家より伝わる愛宕権現を山内に安置して鎮守としたといいます。
こちらの愛宕権現の御神体は、のちに芝の愛宕社に安するとも。
正保元年(1644年)、浅草永住町(浅草寺町)に寺地を拝領して移転。
当時、御室法親王の隠室となり、代々仁和寺門跡に直属したと伝わります。
護摩堂は愛宕権現との合殿でしたがこれを失い、愛宕権現は本堂に奉安といいます。
護摩堂御本尊の不動明王は弘法大師の御作と伝わりますが、文化三年(1806年)に焼失したとも。
火災で寺伝類をことごとく焼失し、詳らかな由緒・沿革は伝わっていないようです。
明治45年に墓地を現在地(沼袋)に移し、昭和7年に寺院の移転を概ね終えました。
沼袋には寺院が多く集まっていますが、各寺院の沿革を追うと、関東大震災で被災した浅草寺町辺の寺院が東京府豊玉郡野方村沼袋(現在の中野区沼袋)に移転し、寺町を形成したようです。
当山は第二次大戦末期の空襲で浅草に残した堂宇を全焼、次いで沼袋の堂宇も戦禍に遭い、この時に多くの寺宝・寺什を失ったといいます。
昭和25年に現在地に本堂を再建。
幾多の変遷を辿りながらも、御府内霊場第41番の札所は堅持されて今日に至ります。
草創の縁起からすると、もともとの御本尊は勝軍地蔵菩薩。
現在の御本尊・御府内霊場札所本尊ともに大日如来ですが、『寺社書上』『御府内寺社備考』には「本堂 本尊 十一面観音座像」、江戸末期の『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:十一面観世音 勝軍地蔵尊 弘法大師」とあり、御本尊・札所本尊ともに変遷があった模様。
また、史料によると勝軍地蔵菩薩・愛宕権現を通じて芝の愛宕社とも関係があったようですが、寺伝類を焼失したため詳細は辿れないようです。
当山は「弘法大師二十一ヶ寺」第17番の札所でもあります。
この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。
これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。
「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。
二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。
「弘法大師二十一ヶ寺」の札所リストは↓『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)に記載されています。ご参考までにリストします。
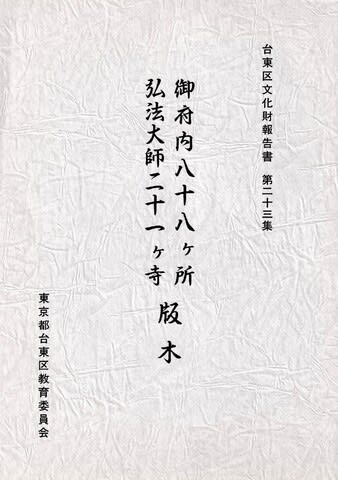
【弘法大師二十一ヶ寺】
1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺 真言宗御室派 文京区湯島1-6-2
2番 宝塔山 多寶院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35
3番 五剣山 普門寺 大乗院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16
4番 清光院 台東区下谷(廃寺)
5番 恵日山 延命寺 地蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8
6番 阿遮山 円満寺 不動院 真言宗智山派 台東区寿2-5-2
7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺 真言宗智山派 台東区寿2-8-15
8番 高野山 金剛閣 大徳院 高野山真言宗 墨田区両国2-7-13
9番 青林山 最勝寺 龍福院 真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2
10番 本覚山 宝光寺 自性院 新義真言宗 台東区谷中6-2-8
11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院 真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14
12番 神勝山 成就院 真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12
13番 広幡山 観蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5
14番 望月山 般若寺 正福院 真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21
15番 仏到山 無量寿院 西光寺 新義真言宗 台東区谷中6-2-20
16番 鶴亭山 隆全寺 威光院 真言宗智山派 台東区寿2-6-8
17番 十善山 蓮花寺 密蔵院 真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)
18番 象頭山 観音寺 本智院 真言宗智山派 北区滝野川1-58-2
19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16
20番 玉龍山 弘憲寺 延命院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2
21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺 真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6
このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。
●「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の札所ながら、「御府内八十八ヶ所」の札所ではない寺院の例

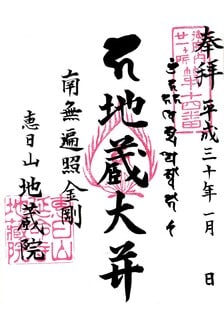
【写真 上(左)】 五剣山 普門寺 大乗院(元浅草)
【写真 下(右)】 恵日山 延命寺 地蔵院(元浅草)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
四十一番
浅草新寺町
勝軍山 蓮花寺 密蔵院
京都御室御所末 古義
本尊:十一面観世音 勝軍地蔵尊 弘法大師
■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.1』
京都御室御所仁和寺宮末 浅草新寺町
勝軍山密蔵院
宗旨古義真言宗
当院小田原北条氏直公祈願所
開山 慶誉法印 寛永十三年寂
開基 不分明
本堂
本尊 十一面観音座像 丈一尺七寸作不詳
大師 十三仏 観音 不動尊 護諸童子経画像
当院十八世光照法印筆一巻 勝軍地蔵画像一幅
鎮守社
愛宕大権現 本地佛勝軍地蔵
当院開山慶誉ハ相州小田原蓮華寺住持シ 北條氏直公ニ親ミ深ク御祈祷等相●●
氏直没落之後 東照宮様慶誉を被(略)其由緒を●慶誉を王子権現別当金輪寺住職社例ヲ改可修神法旨蒙御上意候●共 極老たる●恐多も辞退申上 弟子宥雄ヲ金輪寺住職ニ奉●●(略)尚北條家より伝ル所之愛宕権現ヲ境内二安置シ可為鎮守●●
大猷院様御代正保元年(1644年)地所替●●付 於当浅草寺地三十間四方拝領仕候 もとハ護摩堂ありて愛宕と合殿なりし●再建ならす 愛宕ハ本堂に安す 護摩堂本尊不動ハ弘法大師作にて空海と志るし手判ありしと云 文化三年(1806年)焼失す 勝軍地蔵縁起もありしか 明暦火災に焼失せりと云伝ふ
北条氏より伝ふる愛宕神体ハ 今芝愛宕社ト安す所是なり ●本地仏ハ当寺に安す●と云伝ふ●と、古火災の時記録皆焼失して其由来詳ならすといふ
■『中野区史下巻1』(P.447)(中野区立図書館)
密蔵院
江古田四丁目一、四八九。本尊十一面観音。勝軍山密蔵院蓮花寺と号する。もと真言宗御室派の院室地であつたが、今は同宗東寺派に屬する。
はじめ北條氏直が相模小田原に創建し、勝軍地蔵を安置し祈願所としたのであつた。山号はこれに因由する。
北條氏没落後、慶長十六年(1611年)に至り、僧慶譽、勝軍地蔵の木像を背負うて江戸に来り、矢之倉に小庵を結んだが、正保元年(1644年)淺草永住町に移つた。
明治四十五年墓地を現在の地に移轉し、昭和七年に至り、寺をも同所に移した。

「密蔵院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
西武新宿線「沼袋」駅北側の寺院が集まるエリアの一画にあります。
駅から徒歩約10分ほどです。


【写真 上(左)】 冠木門
【写真 下(右)】 院号札
路地に面して冠木門で、門柱には院号が掲げられています。
こぢんまりとした山内は、よく手入れされ心落ち着く感じがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
正面の本堂は桟瓦葺で様式は不明。
堂宇というより民家を思わせるつくりで、向拝柱はありますが水引虹梁はありません。
参拝後、本堂向かって右の庫裡で御朱印をお願いすると、本堂に上げていただけ、たしか本堂内で揮毫いただいたと思います。
本堂内で参拝できる、貴重な札所のひとつです。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第四十一番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第42番 蓮葉山 妙智院 観音寺
(かんのんじ)
公式Web
台東区谷中5-8-28
真言宗豊山派
御本尊:大日如来・阿弥陀如来
札所本尊:大日如来
司元別当:
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第42番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番
第42番札所は、御府内霊場札所の集中エリア・谷中の観音寺です。
御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。
第42番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに観音寺なので、御府内霊場開創時から一貫して谷中の観音寺であったとみられます。
公式Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
観音寺は、慶長十六年(1611年)神田北寺町(現・千代田区神田錦町周辺)に、長福寺を号し尊雄和尚を開基に創建されました。
神田など、江戸城まわりにあった寺院は江戸城の拡張やこれにともなう武家屋敷地化もあって次々と移転を命ぜられましたが、当山もその例にもれず、慶安元年(1648年)御用地として召し上げられ、谷中清水坂(現・台東区池之端周辺)に移転したもののこちらもまた御用地となり、延宝八年(1680年)現在地に移転しています。
元禄十四年(1701年)三月十四日、浅野内匠頭長矩が江戸城内にて刃傷。即日切腹となり浅野家はお家断絶、領地を没収されました。
元禄十五年(1702年)二月、当山でしばしば密議を重ねた近松勘六行重、奥田貞右衛門行高(ともに当山6世朝山和尚(文良)の兄弟)は江戸を下り、十二月十四日赤穂義士討入り。
主君の仇の吉良上野介義央の首級をあげ本懐を遂げました。
元禄十六年(1703年)赤穂義士切腹。当山は義士の供養塔を建て、義士の菩提を弔うこととなりました。
これより、当山は「赤穂義士ゆかりの寺」としても知られています。
享保元年(1716年)8代将軍・徳川吉宗公の長子の長福丸(家重公)と寺号が重なるため、ときの住職朝海和尚はこれをはばかり寺号を長福寺から観音寺へと改めました。
『寺社書上』ではこの朝海和尚を中興開基とし、真言宗江戸四箇寺の本所弥勒寺末とされたと記され、公式Webでも朝海和尚の功績がとり上げられています。
谷中は江戸城周辺から寺院の移転が相次ぎ、元禄年中(1688-1703年)頃には御府内有数の寺町となりました。
御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1763年)とみられるので、御府内霊場に谷中の札所が多数定められる下地はすでに整っていました。
公式Webにも「宝暦年中(1751-1763年)江戸府内八十八所霊場巡拝が設けられ、観音寺は四十二番札所となる。」と明記されています。
明和九年(1772年)、行人坂の大火で諸堂宇を失い、寺伝類の多くも焼失しました。
しかし、谷中の中心にある御府内霊場札所で、観音堂安置の如意輪観音信者の助力もあってか、観音寺の復興ははやかったと伝わります。
安永年中(1772-1780年)には「三十三所観音参/上野より王子駒込辺西国の写し霊場」が開創。
観音寺は第32番札所に定められ、弘法大師(御府内霊場)、観音(上野王子駒込霊場)両霊場の札所となりました。
『江戸歳事記 4巻 付録1巻 [2]』(国立国会図書館)に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」の一覧があり、たしかに第32番として「谷中観音寺」がみられ、札所本尊は如意輪観世音菩薩となっています。
(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」)様)
この霊場は「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」とも呼ばれますが、筆者がまわった範囲では「西国霊場」の方が通りがよく、札所印つき御朱印授与の札所もあれば、廃寺や御朱印じたい不授与の札所も多く、御朱印拝受しにくい霊場となっています。
→ ■ 希少な札所印


↑ 第4番札所思惟山 正受院(北区滝野川)の札所御朱印。
「西國四番寫」の札所印が捺されています。
明治初頭の神仏分離・廃仏毀釈により寺地を官有地とされましたが、住職および檀信徒の寺運繁栄の努力により昭和18年現本堂が落慶しています。
このとき境内佛(濡佛)であった胡銅製大日如来像と阿弥陀如来像が本堂内に遷座され、御本尊となっています。
公式Webによると、当山創建当初の御本尊は五智如来木座像(金剛界五佛仏/大日如来(中心)、阿閦如来(東)、宝生如来(南)、阿弥陀如来(西)、不空成就如来(北))で開基・尊雄和尚が師子相承されていた尊佛でしたが、火災により失われました。
ついで観音堂本尊であった如意輪観世音菩薩と不空羂索観世音菩薩が御本尊となられ、昭和18年現本堂落慶とともに大日如来・阿弥陀如来両尊が御本尊となりました。
旧御本尊の観音菩薩像は、現在本堂内位牌堂に安置されています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
四十二番
谷中●●門前町
蓮葉山 妙智院 観音寺
本所彌勒寺末 新義
本尊:大日如来 弘法大師 興教大師
■ 『寺社書上 [112] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.104』
本所弥勒寺末 谷中不唱小名
蓮葉山妙智院観音寺
起立慶長年中
権現様御代 神田北寺町ニて拝領仕候
大猷院様御代 御用地ニ相成代地谷中清水坂ニ●右之●坪数程拝領仕候
厳有院様御代 御用地ニ相成 延寶八年只今之場所代地拝領仕候
開基 尊雄 寂年月不知
中興開基 当寺第六世朝快住職中 本所弥勒寺之末寺ニ●
右等之始末古記録等焼失仕候ニ付●●分不申候
本堂
本尊五智如来
四佛 阿閦 宝生 弥陀 釈迦 各木坐像
弘法大師 興教大師 各木坐像
護摩堂
本尊不動明王木坐像
観音堂
本尊如意輪観音木坐像
稲荷社
濡佛二体 大日如来 阿弥陀
■『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)
観音寺(谷中上三崎北町七番地)
本所彌勒寺末、蓬莱山と号す。本尊大日如来。慶長十六年、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年谷中清水坂に移り、延寶八年現地に転じた。開山は僧尊雄。境内に観音堂(如意輪観音安置)、大師堂(弘法大師像安置)、駄枳尼天堂(駄枳尼天安置)がある。

「観音寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
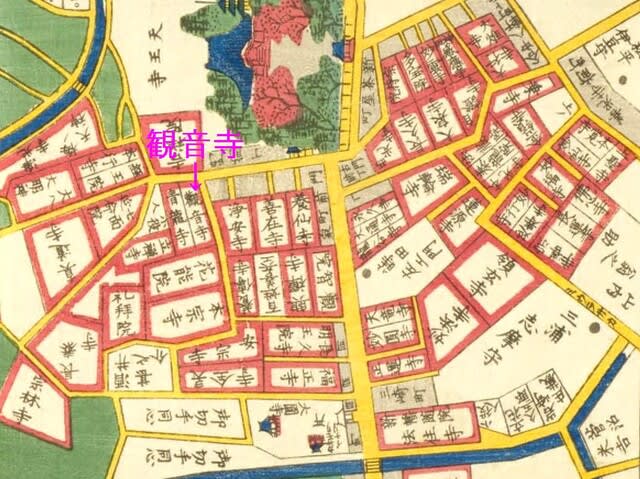
出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約5分。メトロ千代田線「千駄木」駅からも歩けます。
谷中は都内有数の寺院の集積地で、複数の御府内霊場札所が立地します。
観音寺は日暮里駅から谷中銀座(夕やけだんだん)に至る御殿坂と千駄木から谷中にのぼる三崎坂を南北に結ぶ通り沿いにあります。
→ 谷中マップ
南側路地沿いの築地塀は国の国の登録有形文化財(建造物)に指定され、その趣きある風景は寺町・谷中のシンボルとしてしばしばメディアなどでとり上げられます
「観音寺の築地塀」は、幕末頃の築造で、南面のみ現存しています。


【写真 上(左)】 築地塀
【写真 下(右)】 山内入口
前面道路から少し引き込んで石畳。
右手石標は特徴ある字体の御寶号「南無大師遍照金剛」。


【写真 上(左)】 御寶号の石標
【写真 下(右)】 観音霊場札所碑


【写真 上(左)】 遠忌碑
【写真 下(右)】 山門
左手の「西国三十二番 近江観音寺うつし」とある石標は、「上野王子駒込辺三十三観音霊場」第32番の札所標。
そのとなりには弘法大師九百五十年と興教大師六百五十年の併記遠忌碑。
山門は切妻屋根本瓦葺で、おそらく薬医門と思われます。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
参道正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、照り気味に秀麗に葺きおろす屋根が風格を感じさせます。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。
向拝正面の4連の桟唐戸が意匠的に効いています。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂右手
本堂向かって右手には宝形造銅板葺の大師堂があり、こちらは御府内霊場の拝所となっています。


【写真 上(左)】 大師堂-1
【写真 下(右)】 大師堂-2
堂宇前には年季の入った御府内霊場の札所標。
堂宇前面には複数の御府内霊場の札所板、向拝見上げに御府内霊場の札所板と上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所板。
御府内二十一ヶ所第参番の札所札もみえます。
『江戸歳事記』では、「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」の第32番札所(観音寺)の札所本尊は如意輪観世音菩薩となっていますが、この札所板には千手観世音菩薩と刻されています。
また、札所板の霊場名は「西國三十三ヶ所寫」とみえ、やはり従前からこの霊場名で通っていたようです。
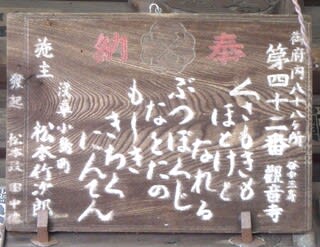

【写真 上(左)】 御府内霊場札所板-1
【写真 下(右)】 御府内霊場札所板-2
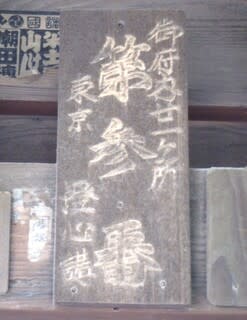

【写真 上(左)】 御府内廿一ヶ所札所板
【写真 下(右)】 観音霊場札所板と千社札
軒裏を埋める古びた千社札が、札所としての古い歴史を感じさせます。
(現在はほとんどの寺社で千社札の貼付は禁止されています。)
堂内中央に弘法大師坐像、向かって右手に不動明王立像、左に興教大師坐像を奉安。
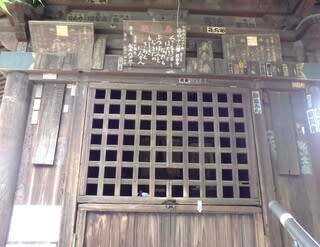

【写真 上(左)】 大師堂向拝
【写真 下(右)】 赤穂義士供養塔
本堂と大師堂の間には赤穂義士の供養塔と宝篋印塔。
その周辺には、聖観世音菩薩立像、如意輪観世音菩薩の石仏、救世菩薩地蔵尊などが安置されています。
『全国霊場大事典』(六月書房)によると、御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされています。
同書によると、信州・浅間山真楽寺の憲浄僧正と千葉県松戸の諦信によって四国八十八ヶ所霊場が写されたもの。
『全国霊場巡拝事典』(大法輪閣)では、宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』に「江戸にも此頃は信州浅間山の上人本願にて、四国の八十八箇所を移して立札など見えたり」とあり、文化十三年(1816年)の札所案内には「宝暦五乙亥三月下総葛飾松戸宿諦信の子、出家して信州浅間山真楽寺の住になりぬ。両人本願して江戸に霊場をうつす」とあることを紹介しています。
また、このことは「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」と刻まれた札所碑が第42番観音寺にあり、他の札所にも同様の石碑が残ることからも裏付けられるとされています。
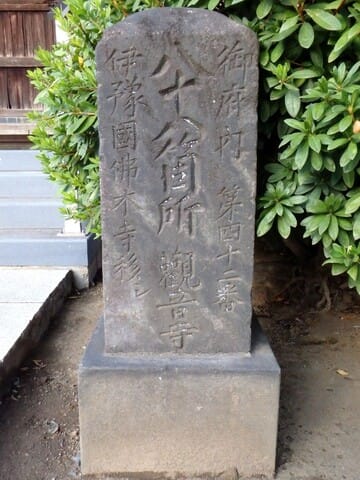
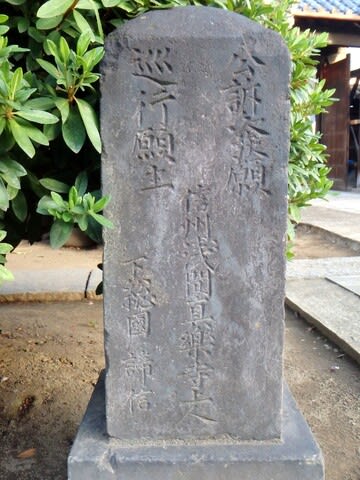
【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」とあります
本堂並びにある客殿も登録有形文化財(建造物)に指定されています。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 客殿からの本堂
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
こちらの御朱印拝受については、以前はいささか敷居が高い印象がありましたが、久しぶりにWebで観音寺の御朱印情報を検索してみたら、なんとスワロフスキー(クリスタルガラス)付御朱印や切り絵御朱印で有名になっている模様。(ぜんぜん知らなかった。)
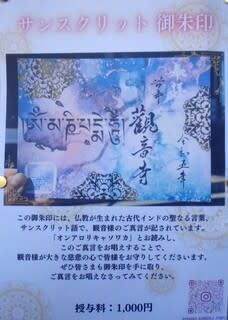

【写真 上(左)】 スワロフスキー付御朱印の案内
【写真 下(右)】 スワロフスキー付御朱印
大師堂前には↓のような掲示が依然としてあります。
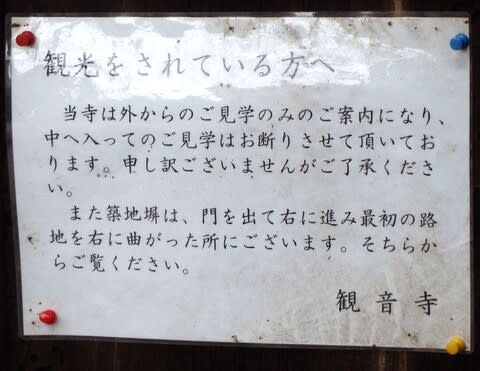
スワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印目当ての人も、いちおうは参拝しているのでしょうか・・・。
谷中の西光寺も以前は御朱印不授与でしたが、いまでは絵御朱印が人気となり、遙拝を条件とした御朱印郵送対応までされています。
→ ■ 谷中の御朱印・御首題
やはり絵御朱印の人気はかなりのものがありそうです。
個人的には絵御朱印や切り絵御朱印にさほど興味はありませんが、これをきっかけに仏教に興味をもつ人が増えるのは、意義あることなのかもしれません。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
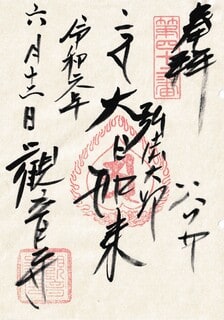
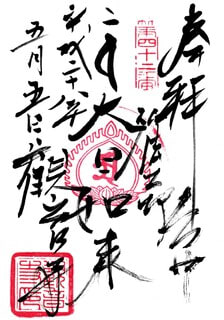
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に金剛界大日如来のお種子「バン」、「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫とお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
公式Web掲載の御本尊は智拳印を結ばれる金剛界大日如来、当山の当初の御本尊は五智如来で金剛界系です。
御寶印の「ア」は、胎蔵大日如来のお種子というより、通種子(すべての尊格をあらわす)として用いられているのかもしれません。
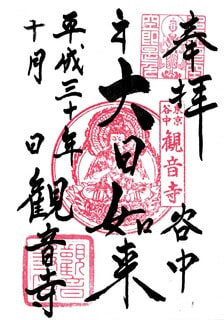

【写真 上(左)】 御本尊・大日如来の御朱印
【写真 下(右)】 お種子(ア)の御朱印
上記のとおり、現在観音寺の御朱印はスワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印がメインの模様で、無申告での墨朱御朱印は大日如来の揮毫御朱印か、お種子(ア)の揮毫御朱印が授与されている模様です。
御府内霊場御朱印の汎用御朱印帳への授与については不明です。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-15)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Ebb and Flow (凪のあすから) - LaLa(歌ってみた)
■ 思い出の向こうに - 小川範子
■ 空に近い週末 - 今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-13
Vol.-12からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第38番 神霊山 慈眼寺 金乗院
(こんじょういん)
豊島区高田2-12-39
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:
〔金乗院〕
江戸八十八ヶ所霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番、山の手三十三観音霊場第9番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第14番
〔新長谷寺〕
江戸八十八ヶ所霊場第54番、江戸五色不動(目白不動尊)、関東三十六不動霊場第14番、東京三十三観音霊場第23番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第16番
司元別当:此花咲耶姫社など
授与所:庫裡
第38番札所の金乗院は、第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)を合寺したので、現在、金乗院が第38番、第54番のふたつの札所の御朱印を授与されています。
この記事では第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)もとりあげ、第54番ではこの記事を再掲します。
(なお、本記事は「江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊」から転載・追記したものです。)
第38番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに金乗院なので、御府内霊場開創時から一貫して下高田砂り場の金乗院であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
金乗院は天正年間(1573-1592年)、開山永順が御本尊の聖観世音菩薩を勧請して観音堂を建立したのが草創といいます。
当初は蓮花山 金乗院と号し中野寶仙寺の末寺でしたが、のちに神霊山 金乗院 慈眼寺と号を改め、音羽護国寺の末寺となりました。
御本尊は正観世音菩薩(伝・眦首羯摩作、運慶の作とも)。
山内に荒神を合殿する観音堂、御嶽社、辨天社、三峯社などを置き、江戸時代には旧砂利場村の此花咲耶姫社をはじめ社地三、四ヶ所の別当でしたが、昭和20年4月の戦災で本堂などの伽藍、水戸光圀公揮毫とされる此花咲耶姫の額などの宝物を焼失しました。
戦災で全焼した関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)を合併し、新長谷寺の札所も金乗院に移動しています。
明治初期の神仏分離を乗り切ったふたつの札所のうち一方が戦災で全焼して、一方に合寺されたという比較的めずらしい例です。
-------------------------
第54番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに新長谷寺(目白不動尊)なので、御府内霊場開創時から一貫して関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)は、元和四年(1618年)大和長谷寺代世小池坊秀算が中興し、関口駒井町(現・文京区関口、金乗院から東に約1㎞)にありました。
『江戸切絵図(小日向絵図)』をみると、江戸川橋から目白台にのぼる目白坂沿い北側に永泉寺、養国寺、八幡宮(正八幡神社)と並び、その南側神田川寄りに目白不動尊があったことがわかります。
目白不動堂奉安の不動尊は高さ八寸、「断臂不動明王」といい、弘法大師の御作と伝わります。
縁起によると、弘法大師が唐より御帰朝の後、出羽羽黒山に参籠されたとき大日如来が現れてたちまち不動明王のお姿に変じました。
大師に告げるには「此の地は諸仏内証秘密の浄土なれば、有為の穢火をきらえり、故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏の浄火をあたうべし」と。
不動尊は利剣をもってみずから左の御臂を切られると、霊火が盛んに燃え出でて仏身に満ちあふれました。
大師はこの御影を二体謹刻され、一体は出羽国の荒沢に安置され、もう一体は大師みずから護持されたと伝わります。
後年、野州足利の沙門某が大師護持の不動尊を奉持していましたが、武蔵国関口の松村氏が霊夢を得て足利よりお遷しし、領主の渡辺岩見守より関口台の一画に土地の寄進を受けて一宇を建立したのが本寺の濫觴(らんしょう/はじまりのこと)とされます。
元和四年(1618年)、大和長谷寺小池坊秀算僧正が中興、徳川2代将軍秀忠公の命により堂塔伽藍を建立。
大和長谷寺から御本尊と同木同作の十一面観世音菩薩像を御遷ししてその直末となり、東叡山 浄滝院 新長谷寺と号しました。
寛永年間(1624-1644年)、3代将軍家光公は当山の断臂不動明王に「目白」の号を贈り、江戸守護の江戸五色不動(青・黄・赤・白・黒)のひとつとして、また、江戸三不動の代一位として名を高め、人々の篤い信仰を受けました。
ことに護身、厄除け眼病治癒の不動尊として霊験あらたかとされます。
元禄年間(1688-1704年)には、5代将軍綱吉公とその母桂昌院が深く帰依してさらに伽藍を整え、寺容は壮麗を極めたと伝わります。
境内は堰口の流れを見下ろす高台の景勝地で、付近には茶肆、割烹などの店が出て、ことに月雪景の名所であったようです。
その佳景は、『東京名所四十八景 関口目しろ不動』 (慶應義塾大学メディアセンターDC)からも偲ぶことができます。
昭和20年5月の戦災で焼失したため金乗院に合併、御本尊の目白不動明王像は関口から金乗院に遷られました。
ふたつの名刹が合併した金乗院は今日も複数のメジャー霊場の札所であり、多くの参拝客を集めています。
また、当寺住職の小野塚幾澄大僧正は、平成20年から平成24年まで真言宗豊山派管長・長谷寺化主に就任されています。
-------------------------
【史料】
【金乗院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十八番
砂り場
神霊山 金乗院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:千手観音 興教大師 弘法大師
■『新編武蔵風土記稿 巻之12 豊島郡之4』(国立国会図書館)
(下高田村)金乗院
新義真言宗多磨郡中野村寶仙寺末、神靈山観音院ト號ス 本尊正観音長一寸八分眦首羯摩作 開山永順文禄三年(1594念)六月四日寂 御嶽社 辨天社 三峯社 観音堂/荒神ヲ合殿トス 観音ハ木ノ立像長三尺運慶ノ作ト云

「金乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「宿坂関旧址 金乗院 観音堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
【新長谷寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十四番
関口駒井町
東豊山 海瀧院 新長谷寺
紀州初瀬小池坊末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 本社目白不動明王 弘法大師
■『江戸名所図会. 十二』(国立国会図書館)
目白不動堂 同所東の方にありて堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と号す
長谷小池坊の宿寺とす
本尊不動明王の霊像は長八寸弘法大師の作 総門の額東豊山の三大字ハ南岳悦山の筆
縁起云弘法大師唐より帰朝の後 羽州湯殿山に参籠ありし時 大日如来忽然と不動明王の姿に変現し滝の下に現ハれ●● 大師に告て云く此地ハ諸佛内證秘密の浄土なれハ有為の穢土をきらえり 故に凡夫登山することかたし 今汝に無漏の上火をあたふべしと宣ひ持ちし●●●の利劍をもって左の御臂を切●●ハ、霊火盛に燃出でて佛身に充てり 依て大使面前に出現の像二躯を模刻し一躰ハ同國荒澤に安置し 一躰ハ大師自ら護持なしたまふ
その後野州足利に住せる沙門某之を感得し●奉持せしに一年 霊感あるを以て此地の住人松村氏某に●かりつひに一宇を開きて此本尊を移し安置なし奉ると
当寺元和四年和州長谷小池坊秀算僧正中興ありし頃 大将軍台徳公の厳命により堂塔坊舎御建立あり
また和州長谷寺の本尊と同木同作の十一面観世音の像をうつし新長谷寺と改む
大将軍大猷公目白の号を賜ひ 元禄の始にハ桂昌一位尼公御帰依浅からす諸堂修理を加へたまひ丈余●地蔵尊等を安置なさしめられたり
此地麓●●堰口の流を帯ひ 水流そうそうとして日夜不絶 早稲田の村落高田の森林を望む風光の地なり 境内貸食亭多く何れも涯に臨めり
また、『寺社書上(御府内備考). [61] 関口寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.134』
新義真言宗
和州長谷小池坊末
目白不動尊別当
東豊山 新長谷寺 海瀧院
本堂
本尊不動尊 弘法大師御作 秘佛
開帳佛不動 木立像
前立不動 木座像 四大明王ニ童附各立像
不動堂本殿 桂昌院御建立別堂
地蔵尊木立像
不動木立像 良弁僧都作
聖徳大師木立像
七曜佛木立像 運慶作
庚申佛木立像
疱瘡神木立像
愛染明王木像
大日如来木像 聖徳太子作
毘沙門木像
弁財天木像 竹生嶋写し
観音堂
本尊十一面木立像 行基菩薩作 開山秀算僧正勧請
前立観音木立像
与森天神木座像
興教大師木像
弘法大師木像 伊豫國延命寺写しニテ五十四番札所
開山秀算僧正木像
子安地蔵尊金立像
如意輪観音木像
弥陀木座像
聖天金像
末社
稲荷社、秋葉社、人丸社
唐金地蔵尊 濡佛
■『東京名所図会』(国立国会図書館)
目白不動堂は同所東の方にあり堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と號す 本尊不動明王は弘法大師の作なり 当寺は元和年間(1615-1624年)和州長谷の小池坊秀算僧正中興ありしより将軍家の厳命にて堂塔伽藍建立あり 後ち桂昌院尼公諸堂に修理を加えられ頗る荘厳を極めたり 境内眺望佳絶にして茶肆割烹店等多し 冬月雪景最も宜しと云ふ

「新長谷寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「目白不動堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』小日向絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅か都電荒川線「学習院下」駅ですが、道行きの風情は「雑司ヶ谷」駅ルートの方があると思うので、こちらをご紹介。
メトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅3番出口から、目白通りを渡って宿坂通りに入ります。
目白通りは目白台の台地上を走り、ここから南側、神田川にかけては下り勾配となります。
宿坂(しゅくざか)もかなりの急坂ですが、この一本西側の「のぞき坂」は別名を「胸突(むなつき)坂」といい、「東京一急な坂」として知られています。
『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおり「宿坂」と「金乗院」が記されています。
「宿坂関之旧跡 同北の方金乗院といへる密寺の寺前を四谷町の方へ上る坂口をいふ 同じ寺の裏門の辺にさらちの平地あり(中略)昔の奥州街道●●其頃関門のありて跡ありといへり」
現地掲示によると、この辺りは中世に「宿坂の宿」と呼ばれた関所があり、「立丁場」と呼ばれた金乗院裏門辺の平地が関所跡との伝承があります。
宿坂は「江戸時代には竹木が生い茂り、昼なお暗く、くらやみ坂と呼ばれ、狐や狸が出て通行人を化かしたという話」が伝わっているそうです。


【写真 上(左)】 宿坂
【写真 下(右)】 山門
宿坂をほぼ下りきった右手が金乗院の山門です。
二軒の垂木を備えた銅板葺のどっしりとした二脚門で、「神霊山」の山号扁額を掲げています。
右の門柱には、関東三十六不動霊場、左には江戸三十三観音札所の札所板。


【写真 上(左)】 関東三十六不動霊場の札所板
【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の札所板
約200年前の建立ですが昭和20年4月の戦災で屋根を焼失、昭和63年に檀徒の寄進により復元されています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山門前の不動尊
山門周辺に御府内霊場第38番および第54番の札所標、「目白」と刻まれた台座の上に石造坐像のお不動さま、江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所標、「東豊山 新長谷寺」の寺号標などが建ち並び、当寺の歴史を物語っています。
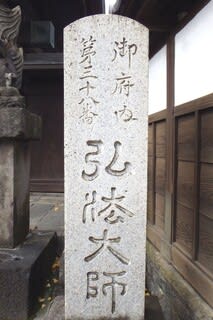

【写真 上(左)】 御府内霊場第38番の札所標
【写真 下(右)】 御府内霊場第54番の札所標
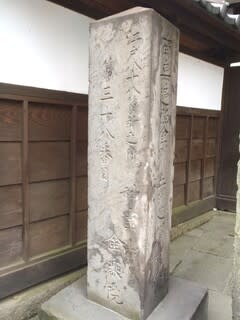

【写真 上(左)】 江戸八十八ヶ所の札所標
【写真 下(右)】 山の手三十三観音霊場の札所標
「江戸第拾六番 山之手第九番 本尊十一面観世音」の札所柱もありました。
「山之手第九番」は山の手三十三観音霊場第9番(新長谷寺)と思われますが、「江戸第拾六番」については霊場不明です。


【写真 上(左)】 金乗院の寺号標
【写真 下(右)】 新長谷寺の寺号標
石敷のすっきりとした境内。
山門正面が庫裡(納経所)、その左手に本堂、山門右手の高みが目白不動尊の不動堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂と不動堂
御府内霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番は本堂、御府内霊場第54番、関東三十六不動霊場第14番は不動堂のお参りとなります。(御府内霊場は修行大師像も参拝)
(「本堂に『断臂不動明王』を安置」とする資料もありますが、『関東三十六不動霊場ガイドブック』には不動堂が参拝堂とあり、不動堂への参道に「目白不動尊参道」の案内掲示、不動堂の扁額も「目白不動堂」です。)
ちなみに御府内霊場のうち、一寺二札所、ふたつの御朱印をいただけるのはこちらのみです。


【写真 上(左)】 本堂(斜めから)
【写真 下(右)】 本堂向拝露天
本堂は昭和46年再建、平成15年の改修。
木造ではありませんが、入母屋造本瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟ともにやや細身ですが、隅棟、稚児棟まわりの鳥衾・熨斗瓦、掛瓦などのつくりが精緻で、屋根の照りもほどよく風格ある堂宇です。
水引虹梁に禅宗様の木鼻、中備えに蟇股、向拝正面は格子戸、その上に「神霊山」の扁額を掲げています。
御本尊は眦首羯摩作と伝わる高さ7㎝の聖観世音菩薩。金剛仏で秘仏です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂向かって左に端正な修行大師像が御座。
金乗院は江戸五色不動唯一の真言宗寺院で、江戸五色不動巡拝中に修行大師像のお参りができるのはこちらだけです。
本堂向かって右には「倶梨伽羅不動庚申」。
不動明王の法形である倶梨(利)伽羅剣と「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた石像で、寛文六年(1660年)の建立です。
「人間を罪過から守る青面金剛の化身、三猿は天の神に人間の犯す罪を伝えない様子をあらわしている。」という現地掲示があります。


【写真 上(左)】 倶利伽羅不動庚申
【写真 下(右)】 不動堂参道
その横に宝塔。その後ろには立像の金仏(地蔵尊)。
その右横が墓地への参道で、その奥には慶安の変(由井正雪の乱、慶安四年7月(1651年))の首謀者の一人、丸橋忠弥の墓所があります。
さらに右手の山門寄りの高みのお堂が、目白不動尊の不動堂です。
確信はないですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、妻側に付向拝の構成かと思われます。
棟部に経の巻獅子口、猪の目懸魚が見えます。


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂向拝
水引虹梁部は向拝幕が張られているのでよくわかりませんが、身舎正面上部に「目白不動尊」の扁額。
格子戸越しに目白不動尊のおすがたが拝せます。
こちらの不動尊は御前立かと思われます。
整った面差しで、右手に剣、左臂に火焔を抱かれ、大盤石の上に御座される立像です。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 鐔塚
境内にはこの他、寛政十二年(1800年)に建立の刀剣の供養塔、鐔塚(つばづか)などの見どころがあります。
なお、江戸名所図会で宿坂のかなり上方に描かれている観音堂(運慶作の観音像が奉られていたと伝わる)の現況については不明です。
御朱印は境内寺務所にて快く授与いただけます。
こちらは江戸五色不動のほか、御府内霊場(2札所)、江戸三十三観音札所、関東三十六不動霊場の札所も兼ねられ、いずれも御朱印を授与されています。
札所無申告の場合、目白不動尊、聖観世音菩薩いずれの御朱印になるかは不明ですが、おそらく先方からお尋ねになるのかと思います。
〔 御府内霊場第38番(金乗院)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔御府内霊場第54番(新長谷寺)の御朱印〕
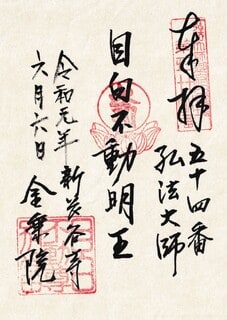
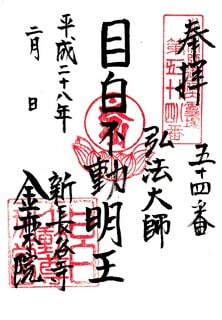
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「目白不動明王」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に寺号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 直書(筆書)
※ 関東三十六不動霊場の御朱印が授与されている模様です。
〔関東三十六不動尊霊場第14番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 筆書
〔江戸三十三観音札所第14番の御朱印〕
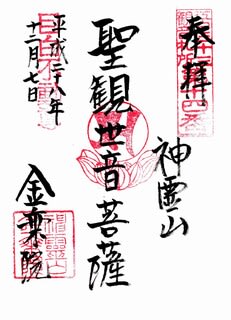
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第14番印判 目白不動尊の印判 直書(筆書)
■ 第39番 金鶏山 海繁寺 真成院
(しんじょういん)
公式Web
新宿区若葉2-7-8
高野山真言宗
御本尊:大日如来・薬師如来 他?
札所本尊:潮干十一面観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第39番、江戸三十三観音札所第18番、関東九十一薬師霊場第13番、大東京百観音霊場第14番、山の手三十三観音霊場第27番、江都三十三観音霊場第18番、東京市史稿撰四十四観音霊場(第15番)
司元別当:
授与所:寺務所
御府内霊場には札所の密集エリアが4つあります。
三田、元浅草・寿、谷中、四ッ谷で、第39番札所の真成院は四ッ谷エリアにあります。
第39番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真成院なので、御府内霊場開創時から一貫して真成院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』および『関東九十一薬師霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
真成院は慶長三年(1598年)、祈祷僧・清心法印によって開山され、江戸城外濠工事にともない幕府より替地として与えられた四ッ谷(現在地)に移転しました。
当山には「潮干観世音」と呼ばれる観音菩薩像が奉安され、江戸三十三観音札所第18番の札所本尊となっています。
潮干観世音菩薩像は天徳四年(960年)唐土より朝廷に奉納され、村上天皇はこの尊像を敬礼し給われたといいます。
また、信濃の戦国武将・村上義清の守り本尊とも伝わります。
Wikipediaには(村上氏の出自について)「村上天皇の第四皇子為平親王が村上姓を賜り、その子源憲定(村上憲定)の娘婿に源頼清がなったことが由来とされる。ただし、この説は十分な確証を得られていない。」とあり、村上天皇、村上氏双方とのゆかりはこの説から来ているのかもしれません。
村上氏は清和源氏頼清流とされる信濃源氏を代表する名族です。
源氏系図には清和天皇-貞純親王-源六孫王経基-源満仲-源頼信-源頼清-源仲宗-源盛清とあり、源仲宗とその子息が政変に巻き込まれて諸国に配流され、信濃国更級郡村上郷に配流された盛清が信濃(村上)源氏の実質的な祖となったという説がみられます。
(盛清の兄弟の顕清も村上郷に配流説あり)
『尊卑分脈』には村上姓初代は源仲宗とありますが、これは仲宗が子息の信濃配流以前に信濃国村上郷を領していたためとする説があります。
清和源氏の名族、村上氏は更級郡を本拠として信濃国内に勢力を張り、戦国期の当主・村上義清は室町幕府三管領家の斯波義寛の娘を母とし、正室を信濃守護・小笠原長棟の娘として北信濃の戦国大名として重きをなしました。
血筋だけでなく武勇にも優れ、上田原の戦い(天文十七年(1548年))、砥石崩れ(天文十九年(1550年))の二度に渡って武田信玄軍を撃退した猛将として名を馳せました。
しかし武田軍の猛攻は止まらず、天文二十二年(1553年)4月、村上義清はついに本拠の葛尾城を放棄して越後国の長尾景虎(上杉謙信)のもとへと身を寄せ客将となりました。
越後に追われたとはいえ、武田信玄を二度までも破った戦国武将は村上義清のみとも目され、その名将ぶりはいまも語り継がれています。
村上氏とその流れの山浦氏は上杉家臣となり、一時は旧領の海津城代となりましたが後にその地位を失い、子孫は上野国、下総国などに飛散したとみられています。
寺伝によると、村上義清の守護佛であった潮干観世音は孫の村上兵部道楽斎(覚玄齊)に伝わりました。
道楽斎は上杉家に従い大阪夏の陣に出陣のため奥州米沢から江戸に入った際、身を隠す必要にかられ、当山の祈祷僧・清心法印が迎え入れて匿ったといいます。
戦後そのお礼として家宝の潮干観世音像を当山に奉安と伝わります。
かつて真成院の近辺は海が迫り、潮干観世音の台石が潮の干満により常に濡れていたためその名を称されたといいます。(汐干(シホヒ)観世音、鹽踏(シホフミ)観世音とも)
潮干観世音は十一面観世音菩薩ですが、史料には「潮干観世音は聖観世音菩薩」という記載もあり、この尊格の錯綜についてはよくわかりません。
一時期本堂と観音堂が失われたものの天保八年(1837年)に再建。
御府内八十八ヶ所第39番札所、江戸三十三観音第18番札所で江戸時代から多くの参拝者を集めたといい、『江戸名所図会』では「四谷の四名所の一つ」に数えられています。
戦前までは境内も広く、四万六千日などの縁日には多くの信者で賑わったといいます。
兼務される観音霊場の多さをみても、江戸期から著名な観音霊場であったことがわかります。
昭和20年5月の東京大空襲によって焼失したものの戦後に再建。
昭和46年に当時としてはめずらしい室内墓地(四谷霊廟)を建立されています。
当山第19世の織田隆弘住職は青森県青森市の高野山青森別院・青龍寺を開山され、昭和59年青銅製の大日如来としては日本最大の「昭和大仏」を造立されたことで知られ、「正純密教」を唱えられ、在家のままであっても救われると説かれました。(Wikipediaより)
また、織田隆弘住職は楠造二尺三寸の薬師如来坐像を勧請され、加持によるお薬師様の御利益は難病平癒にことにあらたかといわれ、全国から信者が集まるといいます。
薬師如来は関東九十一薬師霊場第13番の札所本尊となっており、御朱印も授与されています。
観音堂に十一面観世音菩薩と大聖歓喜天尊を奉安し、什宝として太元明王画像、五大明王画像を蔵されていた(『寺社書上』)ことからも、往古から祈願寺、加持寺としての寺歴をもたれていたことが伺われます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十九番
四ッ谷南寺町
金鶏山 海繁寺 真成院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:薬師如来 潮干観世音 弘法大師
■『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.126』
新義真言宗
中野寶仙寺末
錦敬山 海繁寺 真成院
起立年代相分り不申候
開山 清心(正保四年(1647年)寂)
本堂
本尊薬師如来木坐像 運慶作
両脇 日光 月光 各運慶作
什宝
太元明王画像
五大明王画像
乾閻婆王画像
観音堂
十一面観音金銅立像*
歓喜天 木喰以空上人作
*)天徳四年(960年)唐土より朝廷に奉しと云 (村上)天皇此尊像を敬礼し給ふ(略) 村上義清殊に尊伝し給ひ堂宇を奉安(略)
太子堂
稲荷社
■『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
錦敬山海繁寺眞成院は四谷南寺町今の寺町にある新義眞言宗で、中野村寶仙寺の末寺である。(略)起立及び替地等の年代は詳でないが、開山清心は正保四年(1647年)に入寂(略)府内八十八箇所卅九番の札所で、鹽踏観音は一に汐干観音とも称して、村上天皇の守護佛と傳へている。又歓喜天があつて十六日を縁日とし、参詣者が多い。外に吉祥水がある。『武江披砂』に武州四谷潮干観音之説を載せて、「(略)眞成院の本尊観音也、潮干の観音といふ、其近邊の地を潮干といふ、亦潮ふみの観音共いふ(略)古代は足の下より潮出たりともいふ。(略)越後村上氏代々の守佛なり、村上義清の守本尊なり、一尺計の石の上に坐像の聖観音なり、此石潮のさし引に湿り乾くの変あり、村上信濃守成清(イに賴清)は上総國久留利の城主なり、北條氏康の為めに落城に及ぶ、成清自殺の期に其子二人あり、五歳と三歳の男子なり、是をも刺殺さむとす、折ふし城に信濃國の僧清心法印来りて曰、大将の跡絶へからすといひて、其二子を衣にかゝへ、城を出て寺に帰り育けり、後に兄をば村上左衛門信清といひ、弟をば勝長門守といふ、長門守は里見義弘の家臣となり、老職となる、兄村上左衛門は未だ浪人たりしに、三州より里見へ被仰談度事有しに、未だ其便を求させ給はず、村上左衛門は勝長門守が兄なるよしに付き、鈞命を蒙りて義弘へ使す、此時村上左衛門召出されしとぞ、先年落城の頃にや有らん、彼守本尊を彼僧携へて其寺にをく、一説に村上義清末流村上兵部入道楽斎は奥州米澤に在りしが、大坂御陣に立、其後江戸に帰る、当寺開山清心法印は祈の師たるにより、浪人の内当地に寓す、後水戸の御家に出勤す、其頃此本尊は当寺に納むともいふ、此観音の石座潮汐干満にしたがひ、乾湿の変有、此僧後に武州に来り、四ツ谷今の地に居す、此の佛をも安置す、此石に潮時のしるしを以て、諸人奇として尊み称して潮踏の観音と名づく、後になへて汐干の観音といふは、潮の満干の観音といふの略語なるべし(略)
■『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
汐干(しほひ)観世音菩薩
(四ッ谷)南寺町戒行寺の裏の坂口、眞言宗錦敬山眞成院にあり。此本尊は越後國村上義清が守佛にして、其末流村上兵部入道道楽齊大阪御陣の時、上杉景勝に従ひ、奥州米澤より彼地に赴く。後江戸に帰り、当寺に収むるといへり。(略)鹽踏(シホフミ)観世音とも号く、村上天皇護身の尊像なり。依て村上肥後守頼清常に崇信し、其後堂宇を造り安置す、大阪御陣のみぎり、村上覚玄齊当寺第三世●心に授興し当寺に安ずといふ。本尊聖観音 作者詳ならず、一尺斗の石の上に立せ給ふ。此台石潮のミチヒには必ず湿るヽとなり。

「真成院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「日宗寺 戒行寺 汐干観音」/出典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ丸ノ内線・南北線「四ッ谷」駅で徒歩約7分。
このあたりは山谷が複雑に入り組んだ地形で、真成院も「観音坂」の途中に位置します。


【写真 上(左)】 観音坂
【写真 下(右)】 山内入口
ビルタイプの寺院ながら、周囲には御宝号や尊格を記す幟がはためき、霊場札所の趣きがあります。


【写真 上(左)】 潮干観世音菩薩の幟
【写真 下(右)】 薬師如来の幟
門扉から左手方向が本堂・事務所、右手の階段上が観音堂です。
御朱印尊格からすると、御府内霊場の札所本尊には観音堂奉安の潮干十一面観世音菩薩も定められているとみられますが、観音堂は事務所で受付してからのお参りとなります。


【写真 上(左)】 延命地蔵尊
【写真 下(右)】 雨宝稲荷大明神
左手正面に延命地蔵尊坐像と雨宝稲荷大明神のお社。
延命地蔵尊は、先代織田隆弘和尚の傘寿を記念して平成5年に建立された尊像。
稲荷大明神は、「当山鎮守で潮干十一面観世音菩薩と関係の深い雨宝童子に因む神様(公式Web)とのことで、『寺社書上』に記載のある「稲荷社」の系譜かもしれません。


【写真 上(左)】 エントランスの手水鉢
【写真 下(右)】 札所板
ビルに入ると正面が事務所でこちらで参拝受付。
たしか御府内霊場では本堂(回向堂)と観音堂どちらも参拝したかと思います。
(公式Webには本堂(回向堂)の説明に「御府内八十八箇所の札所巡りの方は、ここでお参りいただきます。」とあります。)
本堂(回向堂)は事務所向かって左奥にあり、奉安されている御像は左から阿弥陀如来、金剛界大日如来、釈迦如来です。
弘法大師も本堂に御座されます。
寺務所の上階には加持殿があり、中央には薬師如来と胎蔵大日如来、右脇には不動明王、左脇には愛染明王が奉安されています。
関東九十一薬師霊場の札所本尊はこちらの薬師如来となります。
関東九十一薬師霊場の巡拝時にはちょうど加持がおこなわれており、手前からの黙拝としましたが、すこぶる厳粛な空気感で身が引き締まる思いでした。


【写真 上(左)】 観音堂入口
【写真 下(右)】 観音堂
一旦寺務所に戻りお断りをしてから観音堂に向かいます。
階段をのぼった風とおしのよい上階に観音堂があります。
入口は鉄扉で堅く閉ざされていますが、扉をあけると正面に潮干十一面観世音菩薩像、毘沙門天、弁財天もこちらに奉安されています。
江戸三十三観音札所の拝所はこちらになります。


【写真 上(左)】 観音堂向拝
【写真 下(右)】 真成院の外観
御内陣に護摩壇と天井には金色の天蓋。外陣の天井には格子の天井絵と絢爛たる設えですが、観音様の前に座ってみると不思議にきもちが落ち着きます。
先客がいた場合は、参拝を待った方がベターかと思います。
加持を本旨とされる寺院だけあって、いずれの堂宇も厳粛な空気が流れています。
御府内霊場はこのような雰囲気の札所も少なくないので、巡拝に当たっては少なくとも数珠と可能であれば勤行式の持参をおすすめします。


【写真 上(左)】 真言宗智山派の勤行式
【写真 下(右)】 真言宗豊山派の勤行式
このように書くと、敷居の高いお寺さまのように思われがちですが、建物壁面には御府内霊場、江戸三十三観音、関東九十一薬師の3つの札所板が掲げられ、巡拝者の受入体制は整い、ご対応も親切です。
御朱印は巡拝受付時に御朱印帳(集印帳)をお預けすると、参拝後に授与いただけます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
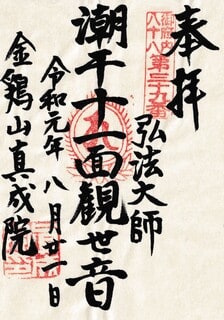

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「潮干十一面観世音」「弘法大師」の揮毫と十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八 第三十九番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 江戸三十三観音札所の御朱印
【写真 下(右)】 関東九十一薬師霊場の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Trust You + Endless Story - Yuna Ito (20 Mar 2010 LIVE @ SOTSUGYOU NO UTA '10)
■ far on the water - Kalafina
■ 千年の恋 - ANRI
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第38番 神霊山 慈眼寺 金乗院
(こんじょういん)
豊島区高田2-12-39
真言宗豊山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:
〔金乗院〕
江戸八十八ヶ所霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番、山の手三十三観音霊場第9番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第14番
〔新長谷寺〕
江戸八十八ヶ所霊場第54番、江戸五色不動(目白不動尊)、関東三十六不動霊場第14番、東京三十三観音霊場第23番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第16番
司元別当:此花咲耶姫社など
授与所:庫裡
第38番札所の金乗院は、第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)を合寺したので、現在、金乗院が第38番、第54番のふたつの札所の御朱印を授与されています。
この記事では第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)もとりあげ、第54番ではこの記事を再掲します。
(なお、本記事は「江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊」から転載・追記したものです。)
第38番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに金乗院なので、御府内霊場開創時から一貫して下高田砂り場の金乗院であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
金乗院は天正年間(1573-1592年)、開山永順が御本尊の聖観世音菩薩を勧請して観音堂を建立したのが草創といいます。
当初は蓮花山 金乗院と号し中野寶仙寺の末寺でしたが、のちに神霊山 金乗院 慈眼寺と号を改め、音羽護国寺の末寺となりました。
御本尊は正観世音菩薩(伝・眦首羯摩作、運慶の作とも)。
山内に荒神を合殿する観音堂、御嶽社、辨天社、三峯社などを置き、江戸時代には旧砂利場村の此花咲耶姫社をはじめ社地三、四ヶ所の別当でしたが、昭和20年4月の戦災で本堂などの伽藍、水戸光圀公揮毫とされる此花咲耶姫の額などの宝物を焼失しました。
戦災で全焼した関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)を合併し、新長谷寺の札所も金乗院に移動しています。
明治初期の神仏分離を乗り切ったふたつの札所のうち一方が戦災で全焼して、一方に合寺されたという比較的めずらしい例です。
-------------------------
第54番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに新長谷寺(目白不動尊)なので、御府内霊場開創時から一貫して関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)であったとみられます。
下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)は、元和四年(1618年)大和長谷寺代世小池坊秀算が中興し、関口駒井町(現・文京区関口、金乗院から東に約1㎞)にありました。
『江戸切絵図(小日向絵図)』をみると、江戸川橋から目白台にのぼる目白坂沿い北側に永泉寺、養国寺、八幡宮(正八幡神社)と並び、その南側神田川寄りに目白不動尊があったことがわかります。
目白不動堂奉安の不動尊は高さ八寸、「断臂不動明王」といい、弘法大師の御作と伝わります。
縁起によると、弘法大師が唐より御帰朝の後、出羽羽黒山に参籠されたとき大日如来が現れてたちまち不動明王のお姿に変じました。
大師に告げるには「此の地は諸仏内証秘密の浄土なれば、有為の穢火をきらえり、故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏の浄火をあたうべし」と。
不動尊は利剣をもってみずから左の御臂を切られると、霊火が盛んに燃え出でて仏身に満ちあふれました。
大師はこの御影を二体謹刻され、一体は出羽国の荒沢に安置され、もう一体は大師みずから護持されたと伝わります。
後年、野州足利の沙門某が大師護持の不動尊を奉持していましたが、武蔵国関口の松村氏が霊夢を得て足利よりお遷しし、領主の渡辺岩見守より関口台の一画に土地の寄進を受けて一宇を建立したのが本寺の濫觴(らんしょう/はじまりのこと)とされます。
元和四年(1618年)、大和長谷寺小池坊秀算僧正が中興、徳川2代将軍秀忠公の命により堂塔伽藍を建立。
大和長谷寺から御本尊と同木同作の十一面観世音菩薩像を御遷ししてその直末となり、東叡山 浄滝院 新長谷寺と号しました。
寛永年間(1624-1644年)、3代将軍家光公は当山の断臂不動明王に「目白」の号を贈り、江戸守護の江戸五色不動(青・黄・赤・白・黒)のひとつとして、また、江戸三不動の代一位として名を高め、人々の篤い信仰を受けました。
ことに護身、厄除け眼病治癒の不動尊として霊験あらたかとされます。
元禄年間(1688-1704年)には、5代将軍綱吉公とその母桂昌院が深く帰依してさらに伽藍を整え、寺容は壮麗を極めたと伝わります。
境内は堰口の流れを見下ろす高台の景勝地で、付近には茶肆、割烹などの店が出て、ことに月雪景の名所であったようです。
その佳景は、『東京名所四十八景 関口目しろ不動』 (慶應義塾大学メディアセンターDC)からも偲ぶことができます。
昭和20年5月の戦災で焼失したため金乗院に合併、御本尊の目白不動明王像は関口から金乗院に遷られました。
ふたつの名刹が合併した金乗院は今日も複数のメジャー霊場の札所であり、多くの参拝客を集めています。
また、当寺住職の小野塚幾澄大僧正は、平成20年から平成24年まで真言宗豊山派管長・長谷寺化主に就任されています。
-------------------------
【史料】
【金乗院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十八番
砂り場
神霊山 金乗院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:千手観音 興教大師 弘法大師
■『新編武蔵風土記稿 巻之12 豊島郡之4』(国立国会図書館)
(下高田村)金乗院
新義真言宗多磨郡中野村寶仙寺末、神靈山観音院ト號ス 本尊正観音長一寸八分眦首羯摩作 開山永順文禄三年(1594念)六月四日寂 御嶽社 辨天社 三峯社 観音堂/荒神ヲ合殿トス 観音ハ木ノ立像長三尺運慶ノ作ト云

「金乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「宿坂関旧址 金乗院 観音堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
【新長谷寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
五十四番
関口駒井町
東豊山 海瀧院 新長谷寺
紀州初瀬小池坊末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 本社目白不動明王 弘法大師
■『江戸名所図会. 十二』(国立国会図書館)
目白不動堂 同所東の方にありて堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と号す
長谷小池坊の宿寺とす
本尊不動明王の霊像は長八寸弘法大師の作 総門の額東豊山の三大字ハ南岳悦山の筆
縁起云弘法大師唐より帰朝の後 羽州湯殿山に参籠ありし時 大日如来忽然と不動明王の姿に変現し滝の下に現ハれ●● 大師に告て云く此地ハ諸佛内證秘密の浄土なれハ有為の穢土をきらえり 故に凡夫登山することかたし 今汝に無漏の上火をあたふべしと宣ひ持ちし●●●の利劍をもって左の御臂を切●●ハ、霊火盛に燃出でて佛身に充てり 依て大使面前に出現の像二躯を模刻し一躰ハ同國荒澤に安置し 一躰ハ大師自ら護持なしたまふ
その後野州足利に住せる沙門某之を感得し●奉持せしに一年 霊感あるを以て此地の住人松村氏某に●かりつひに一宇を開きて此本尊を移し安置なし奉ると
当寺元和四年和州長谷小池坊秀算僧正中興ありし頃 大将軍台徳公の厳命により堂塔坊舎御建立あり
また和州長谷寺の本尊と同木同作の十一面観世音の像をうつし新長谷寺と改む
大将軍大猷公目白の号を賜ひ 元禄の始にハ桂昌一位尼公御帰依浅からす諸堂修理を加へたまひ丈余●地蔵尊等を安置なさしめられたり
此地麓●●堰口の流を帯ひ 水流そうそうとして日夜不絶 早稲田の村落高田の森林を望む風光の地なり 境内貸食亭多く何れも涯に臨めり
また、『寺社書上(御府内備考). [61] 関口寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.134』
新義真言宗
和州長谷小池坊末
目白不動尊別当
東豊山 新長谷寺 海瀧院
本堂
本尊不動尊 弘法大師御作 秘佛
開帳佛不動 木立像
前立不動 木座像 四大明王ニ童附各立像
不動堂本殿 桂昌院御建立別堂
地蔵尊木立像
不動木立像 良弁僧都作
聖徳大師木立像
七曜佛木立像 運慶作
庚申佛木立像
疱瘡神木立像
愛染明王木像
大日如来木像 聖徳太子作
毘沙門木像
弁財天木像 竹生嶋写し
観音堂
本尊十一面木立像 行基菩薩作 開山秀算僧正勧請
前立観音木立像
与森天神木座像
興教大師木像
弘法大師木像 伊豫國延命寺写しニテ五十四番札所
開山秀算僧正木像
子安地蔵尊金立像
如意輪観音木像
弥陀木座像
聖天金像
末社
稲荷社、秋葉社、人丸社
唐金地蔵尊 濡佛
■『東京名所図会』(国立国会図書館)
目白不動堂は同所東の方にあり堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と號す 本尊不動明王は弘法大師の作なり 当寺は元和年間(1615-1624年)和州長谷の小池坊秀算僧正中興ありしより将軍家の厳命にて堂塔伽藍建立あり 後ち桂昌院尼公諸堂に修理を加えられ頗る荘厳を極めたり 境内眺望佳絶にして茶肆割烹店等多し 冬月雪景最も宜しと云ふ

「新長谷寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「目白不動堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』小日向絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはメトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅か都電荒川線「学習院下」駅ですが、道行きの風情は「雑司ヶ谷」駅ルートの方があると思うので、こちらをご紹介。
メトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅3番出口から、目白通りを渡って宿坂通りに入ります。
目白通りは目白台の台地上を走り、ここから南側、神田川にかけては下り勾配となります。
宿坂(しゅくざか)もかなりの急坂ですが、この一本西側の「のぞき坂」は別名を「胸突(むなつき)坂」といい、「東京一急な坂」として知られています。
『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおり「宿坂」と「金乗院」が記されています。
「宿坂関之旧跡 同北の方金乗院といへる密寺の寺前を四谷町の方へ上る坂口をいふ 同じ寺の裏門の辺にさらちの平地あり(中略)昔の奥州街道●●其頃関門のありて跡ありといへり」
現地掲示によると、この辺りは中世に「宿坂の宿」と呼ばれた関所があり、「立丁場」と呼ばれた金乗院裏門辺の平地が関所跡との伝承があります。
宿坂は「江戸時代には竹木が生い茂り、昼なお暗く、くらやみ坂と呼ばれ、狐や狸が出て通行人を化かしたという話」が伝わっているそうです。


【写真 上(左)】 宿坂
【写真 下(右)】 山門
宿坂をほぼ下りきった右手が金乗院の山門です。
二軒の垂木を備えた銅板葺のどっしりとした二脚門で、「神霊山」の山号扁額を掲げています。
右の門柱には、関東三十六不動霊場、左には江戸三十三観音札所の札所板。


【写真 上(左)】 関東三十六不動霊場の札所板
【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の札所板
約200年前の建立ですが昭和20年4月の戦災で屋根を焼失、昭和63年に檀徒の寄進により復元されています。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山門前の不動尊
山門周辺に御府内霊場第38番および第54番の札所標、「目白」と刻まれた台座の上に石造坐像のお不動さま、江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所標、「東豊山 新長谷寺」の寺号標などが建ち並び、当寺の歴史を物語っています。
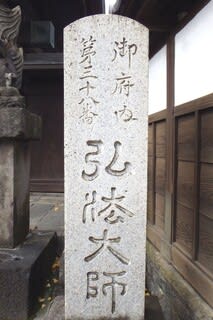

【写真 上(左)】 御府内霊場第38番の札所標
【写真 下(右)】 御府内霊場第54番の札所標
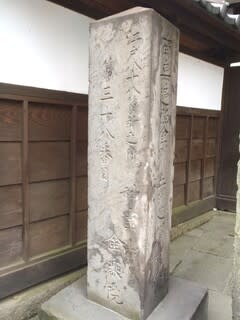

【写真 上(左)】 江戸八十八ヶ所の札所標
【写真 下(右)】 山の手三十三観音霊場の札所標
「江戸第拾六番 山之手第九番 本尊十一面観世音」の札所柱もありました。
「山之手第九番」は山の手三十三観音霊場第9番(新長谷寺)と思われますが、「江戸第拾六番」については霊場不明です。


【写真 上(左)】 金乗院の寺号標
【写真 下(右)】 新長谷寺の寺号標
石敷のすっきりとした境内。
山門正面が庫裡(納経所)、その左手に本堂、山門右手の高みが目白不動尊の不動堂です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂と不動堂
御府内霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番は本堂、御府内霊場第54番、関東三十六不動霊場第14番は不動堂のお参りとなります。(御府内霊場は修行大師像も参拝)
(「本堂に『断臂不動明王』を安置」とする資料もありますが、『関東三十六不動霊場ガイドブック』には不動堂が参拝堂とあり、不動堂への参道に「目白不動尊参道」の案内掲示、不動堂の扁額も「目白不動堂」です。)
ちなみに御府内霊場のうち、一寺二札所、ふたつの御朱印をいただけるのはこちらのみです。


【写真 上(左)】 本堂(斜めから)
【写真 下(右)】 本堂向拝露天
本堂は昭和46年再建、平成15年の改修。
木造ではありませんが、入母屋造本瓦葺流れ向拝。
大棟、降り棟ともにやや細身ですが、隅棟、稚児棟まわりの鳥衾・熨斗瓦、掛瓦などのつくりが精緻で、屋根の照りもほどよく風格ある堂宇です。
水引虹梁に禅宗様の木鼻、中備えに蟇股、向拝正面は格子戸、その上に「神霊山」の扁額を掲げています。
御本尊は眦首羯摩作と伝わる高さ7㎝の聖観世音菩薩。金剛仏で秘仏です。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 修行大師像
本堂向かって左に端正な修行大師像が御座。
金乗院は江戸五色不動唯一の真言宗寺院で、江戸五色不動巡拝中に修行大師像のお参りができるのはこちらだけです。
本堂向かって右には「倶梨伽羅不動庚申」。
不動明王の法形である倶梨(利)伽羅剣と「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた石像で、寛文六年(1660年)の建立です。
「人間を罪過から守る青面金剛の化身、三猿は天の神に人間の犯す罪を伝えない様子をあらわしている。」という現地掲示があります。


【写真 上(左)】 倶利伽羅不動庚申
【写真 下(右)】 不動堂参道
その横に宝塔。その後ろには立像の金仏(地蔵尊)。
その右横が墓地への参道で、その奥には慶安の変(由井正雪の乱、慶安四年7月(1651年))の首謀者の一人、丸橋忠弥の墓所があります。
さらに右手の山門寄りの高みのお堂が、目白不動尊の不動堂です。
確信はないですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、妻側に付向拝の構成かと思われます。
棟部に経の巻獅子口、猪の目懸魚が見えます。


【写真 上(左)】 不動堂
【写真 下(右)】 不動堂向拝
水引虹梁部は向拝幕が張られているのでよくわかりませんが、身舎正面上部に「目白不動尊」の扁額。
格子戸越しに目白不動尊のおすがたが拝せます。
こちらの不動尊は御前立かと思われます。
整った面差しで、右手に剣、左臂に火焔を抱かれ、大盤石の上に御座される立像です。


【写真 上(左)】 不動堂扁額
【写真 下(右)】 鐔塚
境内にはこの他、寛政十二年(1800年)に建立の刀剣の供養塔、鐔塚(つばづか)などの見どころがあります。
なお、江戸名所図会で宿坂のかなり上方に描かれている観音堂(運慶作の観音像が奉られていたと伝わる)の現況については不明です。
御朱印は境内寺務所にて快く授与いただけます。
こちらは江戸五色不動のほか、御府内霊場(2札所)、江戸三十三観音札所、関東三十六不動霊場の札所も兼ねられ、いずれも御朱印を授与されています。
札所無申告の場合、目白不動尊、聖観世音菩薩いずれの御朱印になるかは不明ですが、おそらく先方からお尋ねになるのかと思います。
〔 御府内霊場第38番(金乗院)の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔御府内霊場第54番(新長谷寺)の御朱印〕
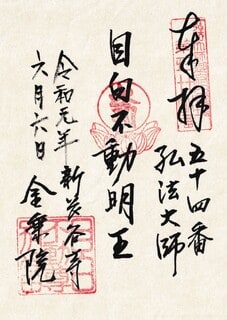
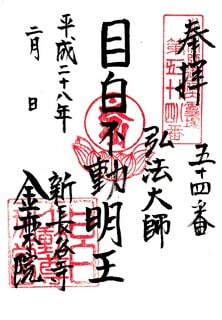
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「目白不動明王」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に寺号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 直書(筆書)
※ 関東三十六不動霊場の御朱印が授与されている模様です。
〔関東三十六不動尊霊場第14番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 筆書
〔江戸三十三観音札所第14番の御朱印〕
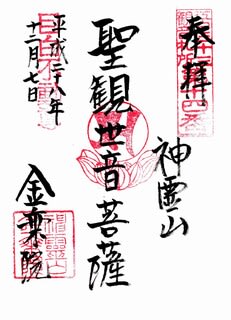
・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第14番印判 目白不動尊の印判 直書(筆書)
■ 第39番 金鶏山 海繁寺 真成院
(しんじょういん)
公式Web
新宿区若葉2-7-8
高野山真言宗
御本尊:大日如来・薬師如来 他?
札所本尊:潮干十一面観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第39番、江戸三十三観音札所第18番、関東九十一薬師霊場第13番、大東京百観音霊場第14番、山の手三十三観音霊場第27番、江都三十三観音霊場第18番、東京市史稿撰四十四観音霊場(第15番)
司元別当:
授与所:寺務所
御府内霊場には札所の密集エリアが4つあります。
三田、元浅草・寿、谷中、四ッ谷で、第39番札所の真成院は四ッ谷エリアにあります。
第39番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真成院なので、御府内霊場開創時から一貫して真成院であったとみられます。
公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』および『関東九十一薬師霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
真成院は慶長三年(1598年)、祈祷僧・清心法印によって開山され、江戸城外濠工事にともない幕府より替地として与えられた四ッ谷(現在地)に移転しました。
当山には「潮干観世音」と呼ばれる観音菩薩像が奉安され、江戸三十三観音札所第18番の札所本尊となっています。
潮干観世音菩薩像は天徳四年(960年)唐土より朝廷に奉納され、村上天皇はこの尊像を敬礼し給われたといいます。
また、信濃の戦国武将・村上義清の守り本尊とも伝わります。
Wikipediaには(村上氏の出自について)「村上天皇の第四皇子為平親王が村上姓を賜り、その子源憲定(村上憲定)の娘婿に源頼清がなったことが由来とされる。ただし、この説は十分な確証を得られていない。」とあり、村上天皇、村上氏双方とのゆかりはこの説から来ているのかもしれません。
村上氏は清和源氏頼清流とされる信濃源氏を代表する名族です。
源氏系図には清和天皇-貞純親王-源六孫王経基-源満仲-源頼信-源頼清-源仲宗-源盛清とあり、源仲宗とその子息が政変に巻き込まれて諸国に配流され、信濃国更級郡村上郷に配流された盛清が信濃(村上)源氏の実質的な祖となったという説がみられます。
(盛清の兄弟の顕清も村上郷に配流説あり)
『尊卑分脈』には村上姓初代は源仲宗とありますが、これは仲宗が子息の信濃配流以前に信濃国村上郷を領していたためとする説があります。
清和源氏の名族、村上氏は更級郡を本拠として信濃国内に勢力を張り、戦国期の当主・村上義清は室町幕府三管領家の斯波義寛の娘を母とし、正室を信濃守護・小笠原長棟の娘として北信濃の戦国大名として重きをなしました。
血筋だけでなく武勇にも優れ、上田原の戦い(天文十七年(1548年))、砥石崩れ(天文十九年(1550年))の二度に渡って武田信玄軍を撃退した猛将として名を馳せました。
しかし武田軍の猛攻は止まらず、天文二十二年(1553年)4月、村上義清はついに本拠の葛尾城を放棄して越後国の長尾景虎(上杉謙信)のもとへと身を寄せ客将となりました。
越後に追われたとはいえ、武田信玄を二度までも破った戦国武将は村上義清のみとも目され、その名将ぶりはいまも語り継がれています。
村上氏とその流れの山浦氏は上杉家臣となり、一時は旧領の海津城代となりましたが後にその地位を失い、子孫は上野国、下総国などに飛散したとみられています。
寺伝によると、村上義清の守護佛であった潮干観世音は孫の村上兵部道楽斎(覚玄齊)に伝わりました。
道楽斎は上杉家に従い大阪夏の陣に出陣のため奥州米沢から江戸に入った際、身を隠す必要にかられ、当山の祈祷僧・清心法印が迎え入れて匿ったといいます。
戦後そのお礼として家宝の潮干観世音像を当山に奉安と伝わります。
かつて真成院の近辺は海が迫り、潮干観世音の台石が潮の干満により常に濡れていたためその名を称されたといいます。(汐干(シホヒ)観世音、鹽踏(シホフミ)観世音とも)
潮干観世音は十一面観世音菩薩ですが、史料には「潮干観世音は聖観世音菩薩」という記載もあり、この尊格の錯綜についてはよくわかりません。
一時期本堂と観音堂が失われたものの天保八年(1837年)に再建。
御府内八十八ヶ所第39番札所、江戸三十三観音第18番札所で江戸時代から多くの参拝者を集めたといい、『江戸名所図会』では「四谷の四名所の一つ」に数えられています。
戦前までは境内も広く、四万六千日などの縁日には多くの信者で賑わったといいます。
兼務される観音霊場の多さをみても、江戸期から著名な観音霊場であったことがわかります。
昭和20年5月の東京大空襲によって焼失したものの戦後に再建。
昭和46年に当時としてはめずらしい室内墓地(四谷霊廟)を建立されています。
当山第19世の織田隆弘住職は青森県青森市の高野山青森別院・青龍寺を開山され、昭和59年青銅製の大日如来としては日本最大の「昭和大仏」を造立されたことで知られ、「正純密教」を唱えられ、在家のままであっても救われると説かれました。(Wikipediaより)
また、織田隆弘住職は楠造二尺三寸の薬師如来坐像を勧請され、加持によるお薬師様の御利益は難病平癒にことにあらたかといわれ、全国から信者が集まるといいます。
薬師如来は関東九十一薬師霊場第13番の札所本尊となっており、御朱印も授与されています。
観音堂に十一面観世音菩薩と大聖歓喜天尊を奉安し、什宝として太元明王画像、五大明王画像を蔵されていた(『寺社書上』)ことからも、往古から祈願寺、加持寺としての寺歴をもたれていたことが伺われます。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十九番
四ッ谷南寺町
金鶏山 海繁寺 真成院
中野村宝仙寺末 新義
本尊:薬師如来 潮干観世音 弘法大師
■『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.126』
新義真言宗
中野寶仙寺末
錦敬山 海繁寺 真成院
起立年代相分り不申候
開山 清心(正保四年(1647年)寂)
本堂
本尊薬師如来木坐像 運慶作
両脇 日光 月光 各運慶作
什宝
太元明王画像
五大明王画像
乾閻婆王画像
観音堂
十一面観音金銅立像*
歓喜天 木喰以空上人作
*)天徳四年(960年)唐土より朝廷に奉しと云 (村上)天皇此尊像を敬礼し給ふ(略) 村上義清殊に尊伝し給ひ堂宇を奉安(略)
太子堂
稲荷社
■『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
錦敬山海繁寺眞成院は四谷南寺町今の寺町にある新義眞言宗で、中野村寶仙寺の末寺である。(略)起立及び替地等の年代は詳でないが、開山清心は正保四年(1647年)に入寂(略)府内八十八箇所卅九番の札所で、鹽踏観音は一に汐干観音とも称して、村上天皇の守護佛と傳へている。又歓喜天があつて十六日を縁日とし、参詣者が多い。外に吉祥水がある。『武江披砂』に武州四谷潮干観音之説を載せて、「(略)眞成院の本尊観音也、潮干の観音といふ、其近邊の地を潮干といふ、亦潮ふみの観音共いふ(略)古代は足の下より潮出たりともいふ。(略)越後村上氏代々の守佛なり、村上義清の守本尊なり、一尺計の石の上に坐像の聖観音なり、此石潮のさし引に湿り乾くの変あり、村上信濃守成清(イに賴清)は上総國久留利の城主なり、北條氏康の為めに落城に及ぶ、成清自殺の期に其子二人あり、五歳と三歳の男子なり、是をも刺殺さむとす、折ふし城に信濃國の僧清心法印来りて曰、大将の跡絶へからすといひて、其二子を衣にかゝへ、城を出て寺に帰り育けり、後に兄をば村上左衛門信清といひ、弟をば勝長門守といふ、長門守は里見義弘の家臣となり、老職となる、兄村上左衛門は未だ浪人たりしに、三州より里見へ被仰談度事有しに、未だ其便を求させ給はず、村上左衛門は勝長門守が兄なるよしに付き、鈞命を蒙りて義弘へ使す、此時村上左衛門召出されしとぞ、先年落城の頃にや有らん、彼守本尊を彼僧携へて其寺にをく、一説に村上義清末流村上兵部入道楽斎は奥州米澤に在りしが、大坂御陣に立、其後江戸に帰る、当寺開山清心法印は祈の師たるにより、浪人の内当地に寓す、後水戸の御家に出勤す、其頃此本尊は当寺に納むともいふ、此観音の石座潮汐干満にしたがひ、乾湿の変有、此僧後に武州に来り、四ツ谷今の地に居す、此の佛をも安置す、此石に潮時のしるしを以て、諸人奇として尊み称して潮踏の観音と名づく、後になへて汐干の観音といふは、潮の満干の観音といふの略語なるべし(略)
■『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
汐干(しほひ)観世音菩薩
(四ッ谷)南寺町戒行寺の裏の坂口、眞言宗錦敬山眞成院にあり。此本尊は越後國村上義清が守佛にして、其末流村上兵部入道道楽齊大阪御陣の時、上杉景勝に従ひ、奥州米澤より彼地に赴く。後江戸に帰り、当寺に収むるといへり。(略)鹽踏(シホフミ)観世音とも号く、村上天皇護身の尊像なり。依て村上肥後守頼清常に崇信し、其後堂宇を造り安置す、大阪御陣のみぎり、村上覚玄齊当寺第三世●心に授興し当寺に安ずといふ。本尊聖観音 作者詳ならず、一尺斗の石の上に立せ給ふ。此台石潮のミチヒには必ず湿るヽとなり。

「真成院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「日宗寺 戒行寺 汐干観音」/出典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りはJR・メトロ丸ノ内線・南北線「四ッ谷」駅で徒歩約7分。
このあたりは山谷が複雑に入り組んだ地形で、真成院も「観音坂」の途中に位置します。


【写真 上(左)】 観音坂
【写真 下(右)】 山内入口
ビルタイプの寺院ながら、周囲には御宝号や尊格を記す幟がはためき、霊場札所の趣きがあります。


【写真 上(左)】 潮干観世音菩薩の幟
【写真 下(右)】 薬師如来の幟
門扉から左手方向が本堂・事務所、右手の階段上が観音堂です。
御朱印尊格からすると、御府内霊場の札所本尊には観音堂奉安の潮干十一面観世音菩薩も定められているとみられますが、観音堂は事務所で受付してからのお参りとなります。


【写真 上(左)】 延命地蔵尊
【写真 下(右)】 雨宝稲荷大明神
左手正面に延命地蔵尊坐像と雨宝稲荷大明神のお社。
延命地蔵尊は、先代織田隆弘和尚の傘寿を記念して平成5年に建立された尊像。
稲荷大明神は、「当山鎮守で潮干十一面観世音菩薩と関係の深い雨宝童子に因む神様(公式Web)とのことで、『寺社書上』に記載のある「稲荷社」の系譜かもしれません。


【写真 上(左)】 エントランスの手水鉢
【写真 下(右)】 札所板
ビルに入ると正面が事務所でこちらで参拝受付。
たしか御府内霊場では本堂(回向堂)と観音堂どちらも参拝したかと思います。
(公式Webには本堂(回向堂)の説明に「御府内八十八箇所の札所巡りの方は、ここでお参りいただきます。」とあります。)
本堂(回向堂)は事務所向かって左奥にあり、奉安されている御像は左から阿弥陀如来、金剛界大日如来、釈迦如来です。
弘法大師も本堂に御座されます。
寺務所の上階には加持殿があり、中央には薬師如来と胎蔵大日如来、右脇には不動明王、左脇には愛染明王が奉安されています。
関東九十一薬師霊場の札所本尊はこちらの薬師如来となります。
関東九十一薬師霊場の巡拝時にはちょうど加持がおこなわれており、手前からの黙拝としましたが、すこぶる厳粛な空気感で身が引き締まる思いでした。


【写真 上(左)】 観音堂入口
【写真 下(右)】 観音堂
一旦寺務所に戻りお断りをしてから観音堂に向かいます。
階段をのぼった風とおしのよい上階に観音堂があります。
入口は鉄扉で堅く閉ざされていますが、扉をあけると正面に潮干十一面観世音菩薩像、毘沙門天、弁財天もこちらに奉安されています。
江戸三十三観音札所の拝所はこちらになります。


【写真 上(左)】 観音堂向拝
【写真 下(右)】 真成院の外観
御内陣に護摩壇と天井には金色の天蓋。外陣の天井には格子の天井絵と絢爛たる設えですが、観音様の前に座ってみると不思議にきもちが落ち着きます。
先客がいた場合は、参拝を待った方がベターかと思います。
加持を本旨とされる寺院だけあって、いずれの堂宇も厳粛な空気が流れています。
御府内霊場はこのような雰囲気の札所も少なくないので、巡拝に当たっては少なくとも数珠と可能であれば勤行式の持参をおすすめします。


【写真 上(左)】 真言宗智山派の勤行式
【写真 下(右)】 真言宗豊山派の勤行式
このように書くと、敷居の高いお寺さまのように思われがちですが、建物壁面には御府内霊場、江戸三十三観音、関東九十一薬師の3つの札所板が掲げられ、巡拝者の受入体制は整い、ご対応も親切です。
御朱印は巡拝受付時に御朱印帳(集印帳)をお預けすると、参拝後に授与いただけます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
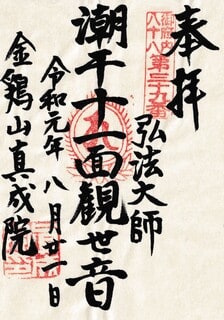

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「潮干十一面観世音」「弘法大師」の揮毫と十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八 第三十九番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 江戸三十三観音札所の御朱印
【写真 下(右)】 関東九十一薬師霊場の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ Trust You + Endless Story - Yuna Ito (20 Mar 2010 LIVE @ SOTSUGYOU NO UTA '10)
■ far on the water - Kalafina
■ 千年の恋 - ANRI
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
霊場の概要や記事リストは→ こちら(■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-0(導入編))です。
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
----------------------------------------
それでは、順にご紹介していきます。
■ 第0番 愛鷹山 三明寺(さんみょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
公式Web
沼津市大岡4051
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:静岡梅花観音霊場第65番
授与所:寺務所
当初、伊豆八十八ヶ所の専用御朱印帳頒布・ご不在札所の御朱印代理授与などは、修禅寺の「札所0番」で対応されていましたが、近年、沼津の三明寺がこの役割を担われています。
霊場公式Webの寺院一覧には第0番札所として掲載され、伊豆八十八ヶ所第0番の御朱印も授与されているので、正式な札所となっている模様です。
三明寺は沼津市北部の長泉町寄り、門池公園のすぐよこの高台にあります。
東名高速道路「長泉沼津IC」からもほど近く便利のよいところです。
伊豆八十八ヶ所の札所ではほぼ北端、伊豆の入口、沼津市内に手引き所があるのは戻り行程がなく便利です。
ただし、伊豆88遍路の紹介ページには「伊豆霊場振興会の関係者が常駐している訳ではありませんので、ご了承ください。」とあるので霊場会の事務局寺院ではなさそうです。
公式Webによると、沼津市本郷町にあった室町時代開創の瑞眼山光明院を、平成14年(2002年)の曹洞宗開祖道元禅師750回大遠忌を期して景勝地の門池に移転しました。
草創は平安時代、真言宗の愛鷹山 参明寺という名刹が存在し門池を含む公大な寺地を有していたことから、音が通じる「三明寺」に改称したようです。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 本堂
本堂は、千葉県茂原市の日蓮宗実相寺旧本堂を禅宗様式に改装・建立したもの。
入母屋造銅板葺で向拝上に大がかりな千鳥破風を興し、手前に附設した向拝屋根には軒唐破風を設えて、変化に富んだ意匠です。
水引虹梁両端に獅子・象の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。
向拝柱には「静岡梅花観音霊場第65番」の札所板、向拝見上げには寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 門池不動尊
本堂向かって右に御座の6メートルの不動明王立像(門池不動尊)は存在感を放たれ、密寺かと思うほどです。
御本尊の酒糟地藏菩薩は、室町時代足利尊氏公奉納と伝わり、沼津市の有形文化財に指定されています。
山内掲示には、村民の祈願を受けた地蔵菩薩が貴人に姿を変えて酒を搾って酒を売り、その家を富ませたという由来が記されています。
本堂向かって左手の階段うえには、南足柄の大雄山最乗寺道了大薩埵を勧請されたという道了堂があり、こちらは当山鎮守のようです。
その左手には、いいなり地蔵尊、地蔵尊坐像、銭洗弁天、魚籃観音、御印章供養塔などが整然とならびます。
尊像はいずれもおだやかでやさしいお顔です。


【写真 上(左)】 道了堂
【写真 下(右)】 寺務所
御朱印は本堂向かって左手よこの寺務所にて拝受できます。
専用納経帳など、伊豆八十八ヶ所霊場関連グッズもこちらで頒布されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院
〔 地蔵菩薩の絵御朱印 〕

〔 門池不動尊の御朱印 〕

〔 道了尊の御朱印 〕

※すみません、いろいろと忙しかったので「静岡梅花観音霊場第65番」の御朱印については聞きそびれました。
■ (旧)第1番 観富山 嶺松院(れいしょういん)
伊豆市田沢129
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆天城七福神(弁財天)、中伊豆観音札所第33番
授与所:本堂横、ないし第2番弘道寺
※現在、こちらの寺院は第1番札所を外れられ、第1番札所は伊豆の国市四日町の長徳寺に変更となっています。
記録の意味で記事は残します。


発願寺の嶺松院は、月ヶ瀬温泉にほど近い県道349号修善寺天城湯ヶ島線沿いにあります。
寺伝によると、大同年間(806-810年)(延暦年間(782-805年)とも)、弘法大師諸国巡錫の途次、この地で村民が病に苦しんでいる姿に接され草堂を建立、薬師三尊、十二神将を勧請、病気平癒・疫病退散の加持を修され村民を救われたのが開創といいます。
『豆州志稿』には「田澤村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス 永禄四年(1561年)寺トスト云」とあります。
『霊場めぐり』には、永禄四年(1561年)、僧真亮創建で旧は小庵。最勝院十一世僧仏山(慶長十年(1605年)寂)寺となす、とあります。
-------------------


湯ヶ島温泉から約3㎞。狩野川右岸の山腹、田沢集落にあり、対岸は月ヶ瀬。
本堂は寄棟造銅板葺平入りで桁行きがあります。向拝柱はなく正面桟格子戸。
扁額はないですが、門柱に院号と「伊豆國八十八ヶ所 第一番札所」の札所板が掲げられ発願所の雰囲気を盛り上げています。
現在の御本尊は聖観世音菩薩ですが、本堂には薬師三尊、十二神将、地蔵菩薩などが奉安されているそうです。
パワスポ感ある奥の院は伊豆天城七福神の弁財天霊場でもあり、弁財天(別名縁結び弁天)の御朱印も授与されています。
御朱印は嶺松院、第2番弘道寺いずれかで拝受できますが、三寶印のデザインが異なるようです。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
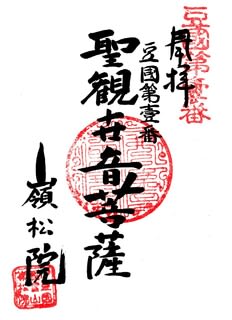

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院

御朱印帳/弘道寺
〔 伊豆天城七福神の御朱印 〕
● 弁財天 /主印は三寶印

御朱印帳
■ 第1番 瑞応山 長徳寺(ちょうとくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆詣Web
伊豆の国市四日町1027
臨済宗円覚寺派
御本尊:延命地蔵願王菩薩
札所本尊:延命地蔵願王菩薩
他札所:
授与所:庫裡
伊豆の国市仁田、原木、韮山、長岡あたりはふるくから伊豆國の中心で多くの寺院があり、伊豆中道三十三観音霊場、中伊豆観音札所など、ふるい霊場の中核エリアでした。
長徳寺は霊場札所ではなかった模様ですが、閻魔様・地蔵尊のお寺として知られているようです。
ご住職は気さくで話のお上手な方で、山内を案内していただけました。
現在は臨済宗円覚寺派ですが、往時は関東十刹に数えられた奈古谷の名刹・国清寺の影響が強かったようです。
伊豆詣Webによると、開創は延文年間(1356-1361年)とも伝わり、開祖は大拙祖能和尚。
大拙祖能和尚は足利義満公の駿河太守であった大江氏の帰依を受け、円融天皇より広円明鑑禅師のおくり名を与えられ、円覚寺の第四十世、建長寺の第四十九世などを歴任されたという高僧です。
『豆州志稿』には「四日市村 臨済宗円覚寺派 奈古谷國清寺末 本尊地蔵 慶安(1648-1652年)中ノ創立也 建長寺十三世廣圓和尚初祖タリ 島昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス(永和二年(1376年)唱滅ス) 本尊ヲ河越地蔵ト云 運慶ノ作ナリト傳フ」とあり、やはり開創は室町時代まで遡るようです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 本堂
山内は芝生メインで広々と明るいイメージ。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝で水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。
御朱印見上げには山号扁額を掲げています。
御本尊は延命地蔵願王菩薩で「河越地蔵」とも呼ばれたようです。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂向かって左手の十王堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端を設えています。
屋根勾配が急で、引き締まった印象の堂宇です。


【写真 上(左)】 十王堂
【写真 下(右)】 霊場の幟
十王堂には十王尊と地蔵菩薩・閻魔大王・奪衣婆が安置されています。
十王堂の主座は閻魔大王の例が多いですが、こちらでは主座に地蔵菩薩が御座されます。
『十王経』などでは地蔵菩薩と閻魔大王は同体、もしくは閻魔大王は地蔵菩薩の化身ともされ、奪衣婆さんは閻魔大王の妻とされるので、こちらの尊格構成は儀軌類にもっとも忠実なものなのかもしれません。
三途の川を渡り終えた亡者は、現世の罪過や善根功徳の軽重を問うため七日ごとに七回の裁判を受けることになりますが、三十五忌に閻魔大王の裁判があり、四十九日忌に判決によって六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天上道)に導かれるとされます。
日本の地蔵信仰では地蔵菩薩は六道(とくに地獄)の責め苦から衆生を救う役割を果たすといいます。
閻魔大王=地蔵菩薩ですから、地蔵菩薩は閻魔大王として六道(とくに地獄)に送られた衆生を、みずから救われるということになります。
伊豆八十八ヶ所には閻魔大王ゆかりの札所は比較的すくないので、第1番からいきなり閻魔大王・奪衣婆の洗礼を受け、現世の罪過や善根功徳、六道輪廻について考えさせられる札所構成は、なかなかのものかと思います。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受。閻魔大王の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

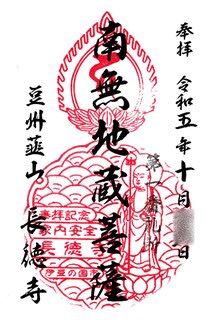
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 閻魔大王の御朱印 〕

■ 第2番 天城山 弘道寺(こうどうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市湯ケ島296
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆天城七福神(福禄寿)、中伊豆観音札所第35番
授与所:庫裡


第2番弘道寺は、第1番から天城街道を南下した、湯ヶ島温泉郷の東側の山ぎわにあります。
寺伝によると、弘治年間(1555-1558年)、最勝院七世笑山精眞禅師を開山とし、福寿庵と号して当町東原にありましたが、第二世気添龍意和尚が現寺地に遷され、天城山弘道寺と号を改めました。
『豆州志稿』には「湯ヶ島村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 此寺舊昔ハ龍若ノ祠ノ傍ニ在リ(其頃ハ福壽庵ト称ス) 龍若自屠スル所ト云神版アリ 龍若ハ上杉憲政ノ嫡男也 北条氏康当国修善寺ニ送リ誅戮セシムル事古戦録ニ見ユ 蓋此地ニテ屠腹セシナラン 其遺跡字東原ニアリ 最勝院七世精眞ヲ開山トス」とあります。
また、『霊場めぐり』には「創建として天文二十年(1551年)、上野国平井城主上杉憲政公の息竜若丸が北条氏に逐われこの地にて自刃せるを祀る」とあります。
関東管領上杉憲政公(1531-1561年)は、有名な河越夜戦で北条氏康に大敗を喫して上野国平井城に逃れ、長尾景虎(のちの上杉謙信)を養子とし、上杉家家督と関東管領職を譲りました。
天文二十一年(1552年)、憲政公が拠る平井城は西上野の諸衆に攻められ落城。吾妻から越後の長尾景虎(上杉謙信)のもとに退去しました。
平井落城の際に嫡男・龍若丸は置き去りとなり(安保泰広の御嶽城に待避という説もあり)、北条軍に捕らえられ、小田原ないし伊豆で自刃したと伝わります。
龍若丸の墓所は妙高山最勝禅院(宮上最勝院、第3番札所)にあり、最勝院は弘道寺の本寺です。
最勝院は宅間上杉家の上杉憲清公の再興ということもあり、末寺である弘道寺にこのような上杉氏御曹司の伝承が残っているのかもしれません。
『豆州志稿』の最勝院の項には「上杉安房守憲実鎌倉管領タル時 其弟兵庫頭清方ヲ越中ョリ招テ政ヲ摂セシム 永享十一年(1439年)年冬憲実豆州ニ遁レ 自称高岳長棟庵主 其の二子を携テ西遊セリ獨第三子龍若丸(龍若即憲忠也 憲政ノ子ニモ龍若アリ混ス可ラス)ハ豆州ノ邊鄙ニ棄置タリ(邊鄙トハ此ノアタリヲ云 憲実深ク罪ヲ成氏ニ得ン事ヲ恐ル 是故ニ伊豆ニ遁レ又僧トナリ 尚不安又西州ニ遠遊ス 此頃ハ大見邊ハ別シテ邊鄙也 故ニ玆(ここ)ニ匿シ置タル也 二子ヲ携ルニ対シテ棄置トハ●タルナラン 鎌倉大草紙ニ豆州ノ山家 北條五代記ニ伊豆ノ奥 北條九代後記ニ豆州奥山トアリ 共ニ此地ヲ云」とあり、憲政公の嫡男・龍若丸の逸話とは異なる内容を伝えています。
安政四年(1857年)、初代米国総領事のタウンゼント・ハリス、通訳のヒュースケン、下田奉行支配頭以下足軽等の一行36名が、通商条約締結のため江戸へ向かう途中に宿泊しました。当時門前に掲げられた「亜米理賀使節泊」の表札や床風脚などが今も残るそうです。
-------------------


本堂は寄棟造銅板葺で照り気味に曲線を描く降棟が端正な印象。
向拝柱はなく正面桟唐戸。上部に「弘道寺」の寺号扁額をおいています。
御本尊は行基作と伝わる聖観世音菩薩立像。伊豆天城七福神の福禄寿尊を奉安します。
御朱印は庫裡にて拝受。(旧)第1番嶺松院の御朱印も拝受しました。
伊豆天城七福神(福禄寿)の御朱印も授与されているようです。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
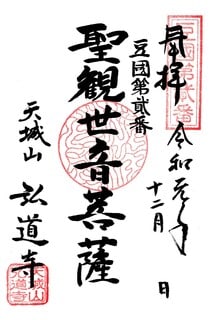
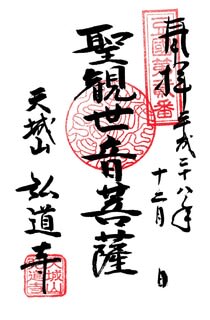
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 湯ヶ島温泉 「河鹿の湯」の入湯レポ
■ 第3番 妙高山 最勝院(さいしょういん)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市宮上48
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:庫裡


第2番弘道寺は天城街道の伊豆市側のいちばん南に位置し、ここから天城越えを経て札所密集エリアである河津・下田方面に抜けられます。
しかし、第3番最勝院は天城越えに背を向けて、狩野川筋から東側の大見川筋にルートを変えねばならず、早くもここでルート選択の岐路に立たされます。
伊豆観光のハイライトとして人気の高い「天城越え」ですが、伊豆八十八ヶ所で順打ち(札番通りに巡拝すること)をすると、東伊豆経由で南伊豆に至り、西伊豆まわりで中伊豆の結願所(修禅寺)に向かうので「天城越え」はしません。
ただし、この霊場はとくに「フリースタイル」の巡拝を推奨されているようなので、第2番からいきなり「天城越え」をして南伊豆に向かう、というコースどりもありかと思われます。
■ 天城越え - 石川さゆり(1986.12)
基本(札番)に忠実に大見川筋に向かえば、しばらくは第4番城富院や修善寺周辺の札所を巡ることになります。
また、大見川筋に向かう道筋も、いったん修善寺近くまで戻って大見川沿いを南下するルートと、湯ヶ島から県道59号伊東西伊豆線で国士峠を越え直接大見川上流に入るルートがあります。
県道59号は名うての険路(→情報)で、山道好きなら問題ないかと思いますが、運転に不慣れな方には荷が重いかもしれません。
伊豆の山道は隘路でカーブが多く、地図上では近くにみえても思いのほか時間を要します。
なので無理のない巡拝には、自身の運転の技量に合わせた行程づくりがポイントとなります。

地図(「伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅」より)
寺伝によると、永享五年(1433年)、管領上杉憲清公が祖父重兼公のために宮上村内の鎮守ヶ島という霊地にあった真言宗西勝寺の廃寺跡を再興し堂宇を建立。
妙高山と号し、金光明寺最勝院と号を改めて第一世吾寶宗璨禅師を招き開祖しました。
以降、優れた門下を輩出し、なかでも拈笑(ねんしょう)、雲岫(うんしゅう) 、南極(なんぎょく)、模菴(もあん)、洲菴(しゅうあん)は五哲と呼ばれ、それぞれに禅寺を開かれ、門下寺は実に1400余ヶ寺に及び、「曹洞宗吾宝五派の本山」と賞される伊豆屈指の名刹です。
その後、幾度の火災により堂宇を消失していますが、第四十八世玄道の代、昭和29年に再建、以降も境内整備が進められ、「最勝寺十景」という景勝を擁して山内はよく整っています。
『豆州志稿』には「宮上村 相州最乗寺末 本尊釋迦 金光明寺と称ス 管領藤(上杉)憲清欲追薦先考冥福 創院於豆州大見荘(略)文安元年(1444年)上杉氏ノ老長尾昌賢之ヲ鎌倉ニ迎ヘ管領ヲ継カシム 上杉右京亮憲忠ト称ス 乃叔父清方ノ為ニ大見ニ於テ寺を創ム 清方法名ハ道宣最勝院ト号ス因テ寺ニ名ク」とあります。
-------------------


端正な山門からまっすぐに延びる参道。背後には山、右手に唐破風の客殿を備えさすがに名刹の風格があります。
本堂は入母屋造平入りで大がかりな千鳥破風。その前面に流れ向拝で唐破風をおく変化のあるつくり。
水引虹梁端部の木鼻は正面獅子、側面貘ないし象。中備えに見事な龍の彫刻をおき、海老虹梁、手挟みの彫刻も見応えがあります。
正面格子の硝子戸で見上げに「妙高山」の山号扁額が掲げられ、名刹らしい格調を感じる本堂です。
御本尊の釈迦牟尼彿は約33cm昆首羯摩の正作と伝えられ、当院の体内釈迦牟尼佛として秘蔵されている霊佛とのことです。
火防大薩埵菩薩(秘仏)も奉安され、火防尊霊場としても知られています。
山内の弁財尊天は古来から当地の鎮守として祀られてきた、と御縁起にあります。
御朱印は庫裡にて拝受できますが、筆者の参拝時(2019年秋)には、「御朱印受付時間:9時~正午、午後1時~4時」の掲示がありました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 白岩温泉 「小川共同浴場」の入湯レポ
■ 第4番 泉首山 城富院(じょうふいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市城391
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡


第4番城富院は、第3番から県道12号伊東修善寺線を北上し、中伊豆(関野)の集落から城川沿いの枝道を遡った山あいにあります。
ちなみに、周辺の大見~白岩にかけては温泉が集中し、温泉マニアは素通りできないエリアです。
寺伝によると、天文十二年(1542年)、最勝院七世笑山精真和尚により開創され、北条氏五代の祈願所でもありました。
火災や山崩れにより幾度か被災しましたが、延宝九年(1681年)、相州の寿伝が来任して再興、今日に至っているとのこと。
春には境内の「北條氏康公手植えの梅(三代)」が開花します。
笑山和尚は氏康公と親交ふかく、和尚が氏康公に梅花に添えて贈ったという詩が残っています。
~ 武有りて文無きは隻翼に同じ 文有りて武無きは英雄ならず 此の梅遠く贈る君親しく見よ 紅白の花開く一樹のうちに ~
『豆州志稿』には「城村 宮上最勝院末 本尊観世音 天文中ノ創立也 開山笑山和尚 笑山贈梅花於北條氏康 係以詩曰(略・詩文)氏康大ニ悦ヒコレニ田園ヲ附ス」とあります。
-------------------


山内ふもとにがっしりとした切妻造桟瓦葺の四脚門を配し、北条氏五代祈願所としての寺格を感じさせます。
本堂は入母屋造桟瓦葺で、重厚なボリューム感があります。
向拝柱はありませんが、向拝両脇の格子入りの花頭窓が意匠的に効いています。
御朱印は本堂内に印が置かれているので自分で捺し、納経料は賽銭箱に納めます。
なので、山内では専用納経帳がないと、(揮毫なし)印判のみの御朱印となります。
公式Webに「代行納経所は永徳寺です。」とあるので、永徳寺(伊豆市徳永122)まで出向けば御朱印帳に拝受できるかもしれませんが、筆者はお伺いしていません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

専用納経帳
→ ■ 上白岩温泉 「希望園」の入湯レポ
→ ■ 上白岩温泉 「雨月庵」の入湯レポ
■ 第5番 吉原山 玉洞院(ぎょくとういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市牧之郷679
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第31番、駿豆両国横道三十三観音霊場第5番、中伊豆観音札所第29番
授与所:庫裡


第5番玉洞院は、修善寺と大仁のあいだに位置する牧之郷にあります。伊豆箱根鉄道駿豆線「牧之郷」駅にもほど近いところです。
由緒沿革は焼失のため詳細不明ですが、当初は真言宗で、天正十一年(1583年)最勝院十世香山宋清により曹洞宗に改宗と伝わります。
複数の霊場の札所となっていることからも、相応の歴史が感じられます。
『豆州志稿』には「牧之郷村 宮上最勝院末 本尊観世音 元密宗也 天正十一年(1583年)最勝院十世宗清留錫シテ改宗ス」とあります。
末寺であった大悲山 合掌寺を合併、伊豆中道三十三観音霊場第31番札所を務められており、こちらの御朱印も授与されています。
-------------------


山門は切妻屋根桟瓦葺柱4本のおそらく薬医門で、見上げに院号扁額を掲げています。
本堂は昭和51年総改築の近代建築ですが、入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配し、向拝左右に花頭窓、向拝見上げに「玉洞院」の院号扁額と整っています。
御本尊は十一面観世音菩薩。密寺に多い御本尊尊格で、真言宗寺院としての歴史が感じられます。
御朱印は、庫裡にて伊豆八十八ヶ所と伊豆中道観音霊場のものを拝受しました。
伊豆中道観音霊場の御朱印には、「駿豆両国第五番」の札所印も捺されていました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆中道観音霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳
■ 第6番 大澤山 金剛寺(こんごうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市大沢248
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:無住、別途連絡


第6番金剛寺は、大仁から山田川を西側に遡った奥にあります。
筆者参拝時は無住で、御朱印拝受の難易度はかなり高いと思います。
伊豆八十八ヶ所のうち、御朱印難易度のとくに高い札所は、第6番金剛寺、第8番益山寺、第15番高岩院、第70番金泉寺、第81番宝蔵院あたりかと思いますが、第6番金剛寺、第8番益山寺はいずれも山田川流域にあります。
沿革等は史料散逸で不明ですが、天文年間(1532-1555年)僧海真創立との由緒が伝わります。また明治22年、この札所で「豆州八十八ヶ所」の書入れのある版木が発見されています。
檀家を持ちませんが、本堂には貴重な仏像が安置されているそうです。
『豆州志稿』には「大澤村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊大日 天文元年(1532年)僧海眞創立ス」とあります。
-------------------

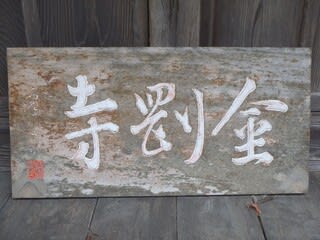
山田川の清流にほど近く、木立のなかにたたずむ本堂は寄棟造銅板葺で向拝柱をおかないシンプルな堂宇。「金剛寺」の寺号扁額は縁台のうえに置かれていました。
すぐお隣には子神社が鎮座し、急な階段のうえに端正な拝殿を構えています。
御朱印はご住職や霊場会に連絡をとり、なんとかゲットしました。
位置関係からすると、手前の第7番泉龍寺が納経を受けられてもいいような感じがしますが、金剛寺は高野山真言宗、泉龍寺は曹洞宗と宗派がことなるので、そういう訳にはいかないかと。
第8番益山寺は高野山真言宗ですがこちらも難易度が高く、第6番、第8番は初盤の難所といえるかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 大日如来


【写真 上(左)】 専用納経帳
・主印は御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。不動明王の種子「カーン」のような気もしますが、よくわかりません。
【写真 下(右)】 郵送の御朱印
・主印は三寶印
■ 第7番 東嶽山 泉龍寺(せんりゅうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市堀切343
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:中伊豆観音札所第28番
授与所:庫裡


第7番泉龍寺は、大仁から第6番金剛寺に向かう途中にあります。
こちらは2回参拝していますが1度目はご不在で、金剛寺の帰途に再度立ち寄ると戻っておられたので、可能性を高めるためまずは泉龍寺に参拝した方がいいかもしれません。
明應九年(1500年)伝覚泰心院主を開基とし、当初は真言宗で玉泉寺と号しました。
寛文七年(1667年)僧日山白により曹洞宗に改め、現寺号となりました。
寛延四年(1751年)、大洪水により被災、村中の下川戸の地より現寺地に移ったとされます。
『豆州志稿』には「洞岳山泉龍寺 堀切村 修善寺修禅寺末 本尊聖観世音 開基博覺天文元年(1544年)化ス 明應中創立玉泉寺ト称シ真言宗也 元禄十一年(1698年)修禅寺廿五世心了改宗シテ泉龍寺ト号ス」とあります。
-------------------


本堂は昭和33年改築。入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
向拝正面桟唐戸とその上に「東嶽山」の山号扁額を掲げています。
境内には立派な寝釈迦も奉安されています。
御朱印は庫裡にて拝受できます。牀座に結跏趺坐される真如親王様のお大師さまのおすがたの印が捺されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
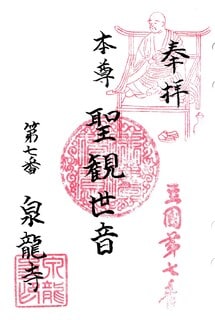

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第8番 養加山 益山寺(ましやまでら)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市観光情報サイト
伊豆市堀切760
高野山真言宗
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:駿豆両国横道三十三観音霊場第6番、中伊豆観音札所第27番
授与所:庫裡(ご不在気味?、要事前連絡)


第8番泉龍寺は、大仁から小山田川沿いの小道を延々と遡り、尾根に到達する直下にあります。
第81番の宝蔵院とならび、この霊場でもっとも山深いロケーションと思われます。
ご不在も多いようで要事前連絡とされますが、筆者はルート変更の急遽の参拝で事前連絡なしでお伺いしたにもかかわらず、ご住職がおられ御朱印を拝受できたのはラッキーでした。
この小山田川沿いの小道は、周辺にまったく人家がないためか相当に荒れており、山道の運転に慣れていないとかなり厳しいです。
霊場にはしばしば”難所”といわれる札所がありますが、このお寺もそうだと思います。
坂東三十三観音霊場第21番の八溝山日輪寺は”難所”として知られており、八溝山には登らず麓の遥拝所から遙拝する巡拝者も多かったことから「八溝知らずの偽坂東」という寸言が残っています。
道の険しさからすると日輪寺より益山寺の方が上で、同じく山道を長駆して到達する第81番宝蔵院よりも厳しく、「益山知らずの偽豆州」という例えがあってもいいほどです。
『豆州志稿』には「堀切村益山 紀州高野山高室院末 本尊千手観世音 益山ノ上に在リ古名千手院 本尊観世音ハ弘法大師自作(現今ノ本尊ハ弘法ノ作ニ非ス)(略)寺地延喜式内伊加麻志神社ノ旧跡ニシテ今佛殿(観音堂ト称ス)ノ地 往古ノ社域寺ハ庫裡ノ地ニ在テ別当ナリシヲ遂ニ社域ヲ略有セルナル可シ境内祠跡トアル 蓋其跡ナラム 今佛殿ノ後背僅ニ一小祠ヲ存スルノミ」とあります。
弘法大師の創建と伝わる名刹で、御本尊の千手観世音菩薩はお大師さまの御作と伝わります。
-------------------


参道、境内には百体の観音様が祀られ、深山の静謐なロケも加わり霊場の趣きゆたか。
参道の大楓と大銀杏は見事な古木で、ともに市の文化財に指定されています。
本堂は、おそらく寄棟造桟瓦葺で流れ向拝。水引虹梁は簡素で、正面の格子入りの硝子戸の上に「大悲殿」の扁額が掲げられています。
本堂右奥には延喜式内社に比定される伊加麻志神社(いかましじんじゃ)が御鎮座。
神仏ともに相い御座す、山上の聖域といえましょう。
御朱印拝受は上記のとおり要事前連絡です。
これほどの難路をたどって授与をのがすのは忍びないので、事前連絡をおすすめします。
専用納経帳の御朱印には「横道第六番」の札所印もいただき、駿豆両国横道三十三観音霊場第6番の御朱印を兼ねています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 千手観世音菩薩 /主印はいずれも御寶印(蓮華座+火焔宝珠)および三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第9番 引摂山 澄楽寺(ちょうらくじ)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市三福638
真言宗高野山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第27番
授与所:庫裡


第8番益山寺から平地に戻って、しばらくは中伊豆の里を巡るおだやかな道行きとなります。
第9番澄楽寺は大仁の北側の三福(みふく)にある、延暦十年(791年)、弘法大師の開創と伝えられる古刹です。
延暦十年は18歳の弘法大師が、修禅寺奥の院の正覚院で天魔地妖を岩谷に封じ込められたとされる年です。
弘法大師は15歳から18歳にかけて、母方の叔父阿刀大足について学問の時期で、延暦十一年(792年)、18歳で京の大学寮に入られています。
大学寮に入られる前ですが、巡拝ガイドには「たとえ出家前とはいえ庵を結ぶか何か縁があって、開創とされたものと考えられる。」と記されています。
公式Webなどでは宗派は「真言宗高野山派」となっています。
「高野山真言宗」の別称とも思いましたが、他の「高野山真言宗」寺院は「高野山真言宗」となっているので、この寺院が「真言宗高野山派」となっている理由はよくわかりません。
お大師さまとのゆかりが強いこともあって真言宗として残り、なにかの由緒があって「真言宗高野山派」となっているのかもしれません。
田京村深沢神社の供僧・覚乗による中興が伝わりますが、幾度かの祝融(火災)により旧記を失い、由緒変遷については不詳のようです
『豆州志稿』には「三福村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 元作長楽寺 延暦十年(791年)弘法大師創建 此寺最古刹ナレ共頻ニ回禄ノ災ニ罹リ流記古寶皆灰燼トナル 僧覺乗ヲ中興トス 田京深澤神社ノ供僧タリキ 慶安四年(1651年)ノ上梁文ニ供僧長楽寺ト見ユ 同社供僧六坊ノ一ナリキト伝フ 或者曰 当寺往昔定額ニ預リタル寺ニテ 定額ノ字長楽又澄楽ノ字ニ転セシナル可シ 延暦中ノ創建ト云古刹也ト伝フルヲ以テ証スベシト(略)小野の高村篁書ケルト云地蔵ノ像アリ」とあります。
伊豆88遍路の紹介ページには「桂谷二十一ヶ所巡礼の第9番」とあります。
修善寺には、桂谷八十八ヶ所巡礼という地域霊場があります。
昭和5年、修禅寺三十八世丘球学老師は、四国八十八ヶ所の霊場の土を、弘法大使が錫を留めたと伝わる修善寺・桂谷の地に移し、弘法大師の像と札所本尊の梵字・名号を刻んだ石碑を地元の協力を得て建立し「桂谷八十八ヶ所」を開創されました。
以降、霊場が開創された11月7日からの3日間に、各地から集まったお遍路さんが約28㎞の山道を歩いて巡拝する修善寺の晩秋の風物詩となりました。(2020年は新型コロナ禍により中止、2021年もこちらの記事に中止とあります。
「桂谷二十一ヶ所巡礼」については情報がほとんど得られていません。
ただし、ふつう、二十一ヶ所弘法大師霊場は八十八ヶ所の簡略版として開創されることが多いので、たとえば路傍ではなく、寺院内におかれた石碑を「桂谷二十一ヶ所」として再編したものかもしれません。
-------------------


本堂は入母屋造桟瓦葺で、正面屋根上に鐘楼をおく特徴あるつくり。
向拝柱はなく向拝正面はサッシュ扉で扁額もありませんが、本堂向かって右に御座す修行大師像が、お大師さまとのゆかりを語っています。
札所本尊は不動明王。この霊場初のお出ましです。
伊豆半島は意外にお不動さまを御本尊とする寺院が少なく、伊豆八十八ヶ所の札所本尊としても多くはないのでこちらは貴重な札所です。
御朱印は庫裡にて拝受。伊豆中道三十三観音霊場第27番の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 不動明王 /主印はいずれも不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆中道観音霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳
→ ■ 大仁温泉 「一二三荘」の入湯レポ
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2へつづく。
【 BGM 】
■ by your side - Wise feat. Nishino Kana
■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子
■ SWEET MEMORIES 松田 聖子
〔 参考文献 〕
『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)
『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)
を示します。
----------------------------------------
それでは、順にご紹介していきます。
■ 第0番 愛鷹山 三明寺(さんみょうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
公式Web
沼津市大岡4051
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:静岡梅花観音霊場第65番
授与所:寺務所
当初、伊豆八十八ヶ所の専用御朱印帳頒布・ご不在札所の御朱印代理授与などは、修禅寺の「札所0番」で対応されていましたが、近年、沼津の三明寺がこの役割を担われています。
霊場公式Webの寺院一覧には第0番札所として掲載され、伊豆八十八ヶ所第0番の御朱印も授与されているので、正式な札所となっている模様です。
三明寺は沼津市北部の長泉町寄り、門池公園のすぐよこの高台にあります。
東名高速道路「長泉沼津IC」からもほど近く便利のよいところです。
伊豆八十八ヶ所の札所ではほぼ北端、伊豆の入口、沼津市内に手引き所があるのは戻り行程がなく便利です。
ただし、伊豆88遍路の紹介ページには「伊豆霊場振興会の関係者が常駐している訳ではありませんので、ご了承ください。」とあるので霊場会の事務局寺院ではなさそうです。
公式Webによると、沼津市本郷町にあった室町時代開創の瑞眼山光明院を、平成14年(2002年)の曹洞宗開祖道元禅師750回大遠忌を期して景勝地の門池に移転しました。
草創は平安時代、真言宗の愛鷹山 参明寺という名刹が存在し門池を含む公大な寺地を有していたことから、音が通じる「三明寺」に改称したようです。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 本堂
本堂は、千葉県茂原市の日蓮宗実相寺旧本堂を禅宗様式に改装・建立したもの。
入母屋造銅板葺で向拝上に大がかりな千鳥破風を興し、手前に附設した向拝屋根には軒唐破風を設えて、変化に富んだ意匠です。
水引虹梁両端に獅子・象の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。
向拝柱には「静岡梅花観音霊場第65番」の札所板、向拝見上げには寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 門池不動尊
本堂向かって右に御座の6メートルの不動明王立像(門池不動尊)は存在感を放たれ、密寺かと思うほどです。
御本尊の酒糟地藏菩薩は、室町時代足利尊氏公奉納と伝わり、沼津市の有形文化財に指定されています。
山内掲示には、村民の祈願を受けた地蔵菩薩が貴人に姿を変えて酒を搾って酒を売り、その家を富ませたという由来が記されています。
本堂向かって左手の階段うえには、南足柄の大雄山最乗寺道了大薩埵を勧請されたという道了堂があり、こちらは当山鎮守のようです。
その左手には、いいなり地蔵尊、地蔵尊坐像、銭洗弁天、魚籃観音、御印章供養塔などが整然とならびます。
尊像はいずれもおだやかでやさしいお顔です。


【写真 上(左)】 道了堂
【写真 下(右)】 寺務所
御朱印は本堂向かって左手よこの寺務所にて拝受できます。
専用納経帳など、伊豆八十八ヶ所霊場関連グッズもこちらで頒布されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院
〔 地蔵菩薩の絵御朱印 〕

〔 門池不動尊の御朱印 〕

〔 道了尊の御朱印 〕

※すみません、いろいろと忙しかったので「静岡梅花観音霊場第65番」の御朱印については聞きそびれました。
■ (旧)第1番 観富山 嶺松院(れいしょういん)
伊豆市田沢129
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆天城七福神(弁財天)、中伊豆観音札所第33番
授与所:本堂横、ないし第2番弘道寺
※現在、こちらの寺院は第1番札所を外れられ、第1番札所は伊豆の国市四日町の長徳寺に変更となっています。
記録の意味で記事は残します。


発願寺の嶺松院は、月ヶ瀬温泉にほど近い県道349号修善寺天城湯ヶ島線沿いにあります。
寺伝によると、大同年間(806-810年)(延暦年間(782-805年)とも)、弘法大師諸国巡錫の途次、この地で村民が病に苦しんでいる姿に接され草堂を建立、薬師三尊、十二神将を勧請、病気平癒・疫病退散の加持を修され村民を救われたのが開創といいます。
『豆州志稿』には「田澤村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス 永禄四年(1561年)寺トスト云」とあります。
『霊場めぐり』には、永禄四年(1561年)、僧真亮創建で旧は小庵。最勝院十一世僧仏山(慶長十年(1605年)寂)寺となす、とあります。
-------------------


湯ヶ島温泉から約3㎞。狩野川右岸の山腹、田沢集落にあり、対岸は月ヶ瀬。
本堂は寄棟造銅板葺平入りで桁行きがあります。向拝柱はなく正面桟格子戸。
扁額はないですが、門柱に院号と「伊豆國八十八ヶ所 第一番札所」の札所板が掲げられ発願所の雰囲気を盛り上げています。
現在の御本尊は聖観世音菩薩ですが、本堂には薬師三尊、十二神将、地蔵菩薩などが奉安されているそうです。
パワスポ感ある奥の院は伊豆天城七福神の弁財天霊場でもあり、弁財天(別名縁結び弁天)の御朱印も授与されています。
御朱印は嶺松院、第2番弘道寺いずれかで拝受できますが、三寶印のデザインが異なるようです。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
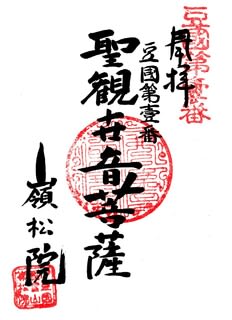

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院

御朱印帳/弘道寺
〔 伊豆天城七福神の御朱印 〕
● 弁財天 /主印は三寶印

御朱印帳
■ 第1番 瑞応山 長徳寺(ちょうとくじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆詣Web
伊豆の国市四日町1027
臨済宗円覚寺派
御本尊:延命地蔵願王菩薩
札所本尊:延命地蔵願王菩薩
他札所:
授与所:庫裡
伊豆の国市仁田、原木、韮山、長岡あたりはふるくから伊豆國の中心で多くの寺院があり、伊豆中道三十三観音霊場、中伊豆観音札所など、ふるい霊場の中核エリアでした。
長徳寺は霊場札所ではなかった模様ですが、閻魔様・地蔵尊のお寺として知られているようです。
ご住職は気さくで話のお上手な方で、山内を案内していただけました。
現在は臨済宗円覚寺派ですが、往時は関東十刹に数えられた奈古谷の名刹・国清寺の影響が強かったようです。
伊豆詣Webによると、開創は延文年間(1356-1361年)とも伝わり、開祖は大拙祖能和尚。
大拙祖能和尚は足利義満公の駿河太守であった大江氏の帰依を受け、円融天皇より広円明鑑禅師のおくり名を与えられ、円覚寺の第四十世、建長寺の第四十九世などを歴任されたという高僧です。
『豆州志稿』には「四日市村 臨済宗円覚寺派 奈古谷國清寺末 本尊地蔵 慶安(1648-1652年)中ノ創立也 建長寺十三世廣圓和尚初祖タリ 島昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス(永和二年(1376年)唱滅ス) 本尊ヲ河越地蔵ト云 運慶ノ作ナリト傳フ」とあり、やはり開創は室町時代まで遡るようです。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 本堂
山内は芝生メインで広々と明るいイメージ。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝で水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。
御朱印見上げには山号扁額を掲げています。
御本尊は延命地蔵願王菩薩で「河越地蔵」とも呼ばれたようです。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂向かって左手の十王堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端を設えています。
屋根勾配が急で、引き締まった印象の堂宇です。


【写真 上(左)】 十王堂
【写真 下(右)】 霊場の幟
十王堂には十王尊と地蔵菩薩・閻魔大王・奪衣婆が安置されています。
十王堂の主座は閻魔大王の例が多いですが、こちらでは主座に地蔵菩薩が御座されます。
『十王経』などでは地蔵菩薩と閻魔大王は同体、もしくは閻魔大王は地蔵菩薩の化身ともされ、奪衣婆さんは閻魔大王の妻とされるので、こちらの尊格構成は儀軌類にもっとも忠実なものなのかもしれません。
三途の川を渡り終えた亡者は、現世の罪過や善根功徳の軽重を問うため七日ごとに七回の裁判を受けることになりますが、三十五忌に閻魔大王の裁判があり、四十九日忌に判決によって六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天上道)に導かれるとされます。
日本の地蔵信仰では地蔵菩薩は六道(とくに地獄)の責め苦から衆生を救う役割を果たすといいます。
閻魔大王=地蔵菩薩ですから、地蔵菩薩は閻魔大王として六道(とくに地獄)に送られた衆生を、みずから救われるということになります。
伊豆八十八ヶ所には閻魔大王ゆかりの札所は比較的すくないので、第1番からいきなり閻魔大王・奪衣婆の洗礼を受け、現世の罪過や善根功徳、六道輪廻について考えさせられる札所構成は、なかなかのものかと思います。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受。閻魔大王の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

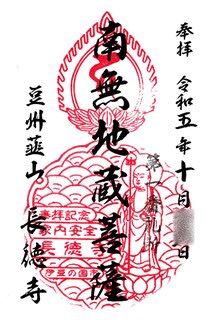
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 閻魔大王の御朱印 〕

■ 第2番 天城山 弘道寺(こうどうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市湯ケ島296
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:伊豆天城七福神(福禄寿)、中伊豆観音札所第35番
授与所:庫裡


第2番弘道寺は、第1番から天城街道を南下した、湯ヶ島温泉郷の東側の山ぎわにあります。
寺伝によると、弘治年間(1555-1558年)、最勝院七世笑山精眞禅師を開山とし、福寿庵と号して当町東原にありましたが、第二世気添龍意和尚が現寺地に遷され、天城山弘道寺と号を改めました。
『豆州志稿』には「湯ヶ島村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 此寺舊昔ハ龍若ノ祠ノ傍ニ在リ(其頃ハ福壽庵ト称ス) 龍若自屠スル所ト云神版アリ 龍若ハ上杉憲政ノ嫡男也 北条氏康当国修善寺ニ送リ誅戮セシムル事古戦録ニ見ユ 蓋此地ニテ屠腹セシナラン 其遺跡字東原ニアリ 最勝院七世精眞ヲ開山トス」とあります。
また、『霊場めぐり』には「創建として天文二十年(1551年)、上野国平井城主上杉憲政公の息竜若丸が北条氏に逐われこの地にて自刃せるを祀る」とあります。
関東管領上杉憲政公(1531-1561年)は、有名な河越夜戦で北条氏康に大敗を喫して上野国平井城に逃れ、長尾景虎(のちの上杉謙信)を養子とし、上杉家家督と関東管領職を譲りました。
天文二十一年(1552年)、憲政公が拠る平井城は西上野の諸衆に攻められ落城。吾妻から越後の長尾景虎(上杉謙信)のもとに退去しました。
平井落城の際に嫡男・龍若丸は置き去りとなり(安保泰広の御嶽城に待避という説もあり)、北条軍に捕らえられ、小田原ないし伊豆で自刃したと伝わります。
龍若丸の墓所は妙高山最勝禅院(宮上最勝院、第3番札所)にあり、最勝院は弘道寺の本寺です。
最勝院は宅間上杉家の上杉憲清公の再興ということもあり、末寺である弘道寺にこのような上杉氏御曹司の伝承が残っているのかもしれません。
『豆州志稿』の最勝院の項には「上杉安房守憲実鎌倉管領タル時 其弟兵庫頭清方ヲ越中ョリ招テ政ヲ摂セシム 永享十一年(1439年)年冬憲実豆州ニ遁レ 自称高岳長棟庵主 其の二子を携テ西遊セリ獨第三子龍若丸(龍若即憲忠也 憲政ノ子ニモ龍若アリ混ス可ラス)ハ豆州ノ邊鄙ニ棄置タリ(邊鄙トハ此ノアタリヲ云 憲実深ク罪ヲ成氏ニ得ン事ヲ恐ル 是故ニ伊豆ニ遁レ又僧トナリ 尚不安又西州ニ遠遊ス 此頃ハ大見邊ハ別シテ邊鄙也 故ニ玆(ここ)ニ匿シ置タル也 二子ヲ携ルニ対シテ棄置トハ●タルナラン 鎌倉大草紙ニ豆州ノ山家 北條五代記ニ伊豆ノ奥 北條九代後記ニ豆州奥山トアリ 共ニ此地ヲ云」とあり、憲政公の嫡男・龍若丸の逸話とは異なる内容を伝えています。
安政四年(1857年)、初代米国総領事のタウンゼント・ハリス、通訳のヒュースケン、下田奉行支配頭以下足軽等の一行36名が、通商条約締結のため江戸へ向かう途中に宿泊しました。当時門前に掲げられた「亜米理賀使節泊」の表札や床風脚などが今も残るそうです。
-------------------


本堂は寄棟造銅板葺で照り気味に曲線を描く降棟が端正な印象。
向拝柱はなく正面桟唐戸。上部に「弘道寺」の寺号扁額をおいています。
御本尊は行基作と伝わる聖観世音菩薩立像。伊豆天城七福神の福禄寿尊を奉安します。
御朱印は庫裡にて拝受。(旧)第1番嶺松院の御朱印も拝受しました。
伊豆天城七福神(福禄寿)の御朱印も授与されているようです。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
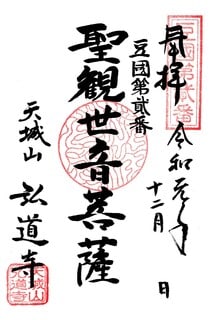
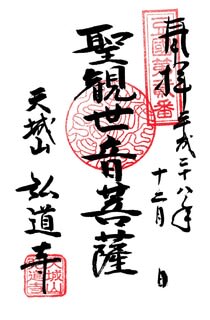
【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 湯ヶ島温泉 「河鹿の湯」の入湯レポ
■ 第3番 妙高山 最勝院(さいしょういん)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市宮上48
曹洞宗
御本尊:釈迦牟尼佛
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:-
授与所:庫裡


第2番弘道寺は天城街道の伊豆市側のいちばん南に位置し、ここから天城越えを経て札所密集エリアである河津・下田方面に抜けられます。
しかし、第3番最勝院は天城越えに背を向けて、狩野川筋から東側の大見川筋にルートを変えねばならず、早くもここでルート選択の岐路に立たされます。
伊豆観光のハイライトとして人気の高い「天城越え」ですが、伊豆八十八ヶ所で順打ち(札番通りに巡拝すること)をすると、東伊豆経由で南伊豆に至り、西伊豆まわりで中伊豆の結願所(修禅寺)に向かうので「天城越え」はしません。
ただし、この霊場はとくに「フリースタイル」の巡拝を推奨されているようなので、第2番からいきなり「天城越え」をして南伊豆に向かう、というコースどりもありかと思われます。
■ 天城越え - 石川さゆり(1986.12)
基本(札番)に忠実に大見川筋に向かえば、しばらくは第4番城富院や修善寺周辺の札所を巡ることになります。
また、大見川筋に向かう道筋も、いったん修善寺近くまで戻って大見川沿いを南下するルートと、湯ヶ島から県道59号伊東西伊豆線で国士峠を越え直接大見川上流に入るルートがあります。
県道59号は名うての険路(→情報)で、山道好きなら問題ないかと思いますが、運転に不慣れな方には荷が重いかもしれません。
伊豆の山道は隘路でカーブが多く、地図上では近くにみえても思いのほか時間を要します。
なので無理のない巡拝には、自身の運転の技量に合わせた行程づくりがポイントとなります。

地図(「伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅」より)
寺伝によると、永享五年(1433年)、管領上杉憲清公が祖父重兼公のために宮上村内の鎮守ヶ島という霊地にあった真言宗西勝寺の廃寺跡を再興し堂宇を建立。
妙高山と号し、金光明寺最勝院と号を改めて第一世吾寶宗璨禅師を招き開祖しました。
以降、優れた門下を輩出し、なかでも拈笑(ねんしょう)、雲岫(うんしゅう) 、南極(なんぎょく)、模菴(もあん)、洲菴(しゅうあん)は五哲と呼ばれ、それぞれに禅寺を開かれ、門下寺は実に1400余ヶ寺に及び、「曹洞宗吾宝五派の本山」と賞される伊豆屈指の名刹です。
その後、幾度の火災により堂宇を消失していますが、第四十八世玄道の代、昭和29年に再建、以降も境内整備が進められ、「最勝寺十景」という景勝を擁して山内はよく整っています。
『豆州志稿』には「宮上村 相州最乗寺末 本尊釋迦 金光明寺と称ス 管領藤(上杉)憲清欲追薦先考冥福 創院於豆州大見荘(略)文安元年(1444年)上杉氏ノ老長尾昌賢之ヲ鎌倉ニ迎ヘ管領ヲ継カシム 上杉右京亮憲忠ト称ス 乃叔父清方ノ為ニ大見ニ於テ寺を創ム 清方法名ハ道宣最勝院ト号ス因テ寺ニ名ク」とあります。
-------------------


端正な山門からまっすぐに延びる参道。背後には山、右手に唐破風の客殿を備えさすがに名刹の風格があります。
本堂は入母屋造平入りで大がかりな千鳥破風。その前面に流れ向拝で唐破風をおく変化のあるつくり。
水引虹梁端部の木鼻は正面獅子、側面貘ないし象。中備えに見事な龍の彫刻をおき、海老虹梁、手挟みの彫刻も見応えがあります。
正面格子の硝子戸で見上げに「妙高山」の山号扁額が掲げられ、名刹らしい格調を感じる本堂です。
御本尊の釈迦牟尼彿は約33cm昆首羯摩の正作と伝えられ、当院の体内釈迦牟尼佛として秘蔵されている霊佛とのことです。
火防大薩埵菩薩(秘仏)も奉安され、火防尊霊場としても知られています。
山内の弁財尊天は古来から当地の鎮守として祀られてきた、と御縁起にあります。
御朱印は庫裡にて拝受できますが、筆者の参拝時(2019年秋)には、「御朱印受付時間:9時~正午、午後1時~4時」の掲示がありました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
→ ■ 白岩温泉 「小川共同浴場」の入湯レポ
■ 第4番 泉首山 城富院(じょうふいん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市城391
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:-
授与所:庫裡


第4番城富院は、第3番から県道12号伊東修善寺線を北上し、中伊豆(関野)の集落から城川沿いの枝道を遡った山あいにあります。
ちなみに、周辺の大見~白岩にかけては温泉が集中し、温泉マニアは素通りできないエリアです。
寺伝によると、天文十二年(1542年)、最勝院七世笑山精真和尚により開創され、北条氏五代の祈願所でもありました。
火災や山崩れにより幾度か被災しましたが、延宝九年(1681年)、相州の寿伝が来任して再興、今日に至っているとのこと。
春には境内の「北條氏康公手植えの梅(三代)」が開花します。
笑山和尚は氏康公と親交ふかく、和尚が氏康公に梅花に添えて贈ったという詩が残っています。
~ 武有りて文無きは隻翼に同じ 文有りて武無きは英雄ならず 此の梅遠く贈る君親しく見よ 紅白の花開く一樹のうちに ~
『豆州志稿』には「城村 宮上最勝院末 本尊観世音 天文中ノ創立也 開山笑山和尚 笑山贈梅花於北條氏康 係以詩曰(略・詩文)氏康大ニ悦ヒコレニ田園ヲ附ス」とあります。
-------------------


山内ふもとにがっしりとした切妻造桟瓦葺の四脚門を配し、北条氏五代祈願所としての寺格を感じさせます。
本堂は入母屋造桟瓦葺で、重厚なボリューム感があります。
向拝柱はありませんが、向拝両脇の格子入りの花頭窓が意匠的に効いています。
御朱印は本堂内に印が置かれているので自分で捺し、納経料は賽銭箱に納めます。
なので、山内では専用納経帳がないと、(揮毫なし)印判のみの御朱印となります。
公式Webに「代行納経所は永徳寺です。」とあるので、永徳寺(伊豆市徳永122)まで出向けば御朱印帳に拝受できるかもしれませんが、筆者はお伺いしていません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

専用納経帳
→ ■ 上白岩温泉 「希望園」の入湯レポ
→ ■ 上白岩温泉 「雨月庵」の入湯レポ
■ 第5番 吉原山 玉洞院(ぎょくとういん)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市牧之郷679
曹洞宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第31番、駿豆両国横道三十三観音霊場第5番、中伊豆観音札所第29番
授与所:庫裡


第5番玉洞院は、修善寺と大仁のあいだに位置する牧之郷にあります。伊豆箱根鉄道駿豆線「牧之郷」駅にもほど近いところです。
由緒沿革は焼失のため詳細不明ですが、当初は真言宗で、天正十一年(1583年)最勝院十世香山宋清により曹洞宗に改宗と伝わります。
複数の霊場の札所となっていることからも、相応の歴史が感じられます。
『豆州志稿』には「牧之郷村 宮上最勝院末 本尊観世音 元密宗也 天正十一年(1583年)最勝院十世宗清留錫シテ改宗ス」とあります。
末寺であった大悲山 合掌寺を合併、伊豆中道三十三観音霊場第31番札所を務められており、こちらの御朱印も授与されています。
-------------------


山門は切妻屋根桟瓦葺柱4本のおそらく薬医門で、見上げに院号扁額を掲げています。
本堂は昭和51年総改築の近代建築ですが、入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配し、向拝左右に花頭窓、向拝見上げに「玉洞院」の院号扁額と整っています。
御本尊は十一面観世音菩薩。密寺に多い御本尊尊格で、真言宗寺院としての歴史が感じられます。
御朱印は、庫裡にて伊豆八十八ヶ所と伊豆中道観音霊場のものを拝受しました。
伊豆中道観音霊場の御朱印には、「駿豆両国第五番」の札所印も捺されていました。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆中道観音霊場の御朱印 〕
● 十一面観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳
■ 第6番 大澤山 金剛寺(こんごうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市大沢248
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:-
授与所:無住、別途連絡


第6番金剛寺は、大仁から山田川を西側に遡った奥にあります。
筆者参拝時は無住で、御朱印拝受の難易度はかなり高いと思います。
伊豆八十八ヶ所のうち、御朱印難易度のとくに高い札所は、第6番金剛寺、第8番益山寺、第15番高岩院、第70番金泉寺、第81番宝蔵院あたりかと思いますが、第6番金剛寺、第8番益山寺はいずれも山田川流域にあります。
沿革等は史料散逸で不明ですが、天文年間(1532-1555年)僧海真創立との由緒が伝わります。また明治22年、この札所で「豆州八十八ヶ所」の書入れのある版木が発見されています。
檀家を持ちませんが、本堂には貴重な仏像が安置されているそうです。
『豆州志稿』には「大澤村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊大日 天文元年(1532年)僧海眞創立ス」とあります。
-------------------

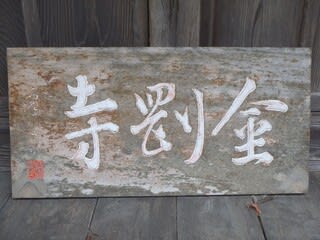
山田川の清流にほど近く、木立のなかにたたずむ本堂は寄棟造銅板葺で向拝柱をおかないシンプルな堂宇。「金剛寺」の寺号扁額は縁台のうえに置かれていました。
すぐお隣には子神社が鎮座し、急な階段のうえに端正な拝殿を構えています。
御朱印はご住職や霊場会に連絡をとり、なんとかゲットしました。
位置関係からすると、手前の第7番泉龍寺が納経を受けられてもいいような感じがしますが、金剛寺は高野山真言宗、泉龍寺は曹洞宗と宗派がことなるので、そういう訳にはいかないかと。
第8番益山寺は高野山真言宗ですがこちらも難易度が高く、第6番、第8番は初盤の難所といえるかもしれません。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 大日如来


【写真 上(左)】 専用納経帳
・主印は御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。不動明王の種子「カーン」のような気もしますが、よくわかりません。
【写真 下(右)】 郵送の御朱印
・主印は三寶印
■ 第7番 東嶽山 泉龍寺(せんりゅうじ)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市堀切343
曹洞宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:中伊豆観音札所第28番
授与所:庫裡


第7番泉龍寺は、大仁から第6番金剛寺に向かう途中にあります。
こちらは2回参拝していますが1度目はご不在で、金剛寺の帰途に再度立ち寄ると戻っておられたので、可能性を高めるためまずは泉龍寺に参拝した方がいいかもしれません。
明應九年(1500年)伝覚泰心院主を開基とし、当初は真言宗で玉泉寺と号しました。
寛文七年(1667年)僧日山白により曹洞宗に改め、現寺号となりました。
寛延四年(1751年)、大洪水により被災、村中の下川戸の地より現寺地に移ったとされます。
『豆州志稿』には「洞岳山泉龍寺 堀切村 修善寺修禅寺末 本尊聖観世音 開基博覺天文元年(1544年)化ス 明應中創立玉泉寺ト称シ真言宗也 元禄十一年(1698年)修禅寺廿五世心了改宗シテ泉龍寺ト号ス」とあります。
-------------------


本堂は昭和33年改築。入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
向拝正面桟唐戸とその上に「東嶽山」の山号扁額を掲げています。
境内には立派な寝釈迦も奉安されています。
御朱印は庫裡にて拝受できます。牀座に結跏趺坐される真如親王様のお大師さまのおすがたの印が捺されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印
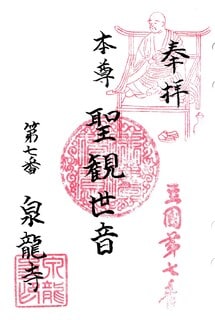

【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第8番 養加山 益山寺(ましやまでら)
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆市観光情報サイト
伊豆市堀切760
高野山真言宗
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:駿豆両国横道三十三観音霊場第6番、中伊豆観音札所第27番
授与所:庫裡(ご不在気味?、要事前連絡)


第8番泉龍寺は、大仁から小山田川沿いの小道を延々と遡り、尾根に到達する直下にあります。
第81番の宝蔵院とならび、この霊場でもっとも山深いロケーションと思われます。
ご不在も多いようで要事前連絡とされますが、筆者はルート変更の急遽の参拝で事前連絡なしでお伺いしたにもかかわらず、ご住職がおられ御朱印を拝受できたのはラッキーでした。
この小山田川沿いの小道は、周辺にまったく人家がないためか相当に荒れており、山道の運転に慣れていないとかなり厳しいです。
霊場にはしばしば”難所”といわれる札所がありますが、このお寺もそうだと思います。
坂東三十三観音霊場第21番の八溝山日輪寺は”難所”として知られており、八溝山には登らず麓の遥拝所から遙拝する巡拝者も多かったことから「八溝知らずの偽坂東」という寸言が残っています。
道の険しさからすると日輪寺より益山寺の方が上で、同じく山道を長駆して到達する第81番宝蔵院よりも厳しく、「益山知らずの偽豆州」という例えがあってもいいほどです。
『豆州志稿』には「堀切村益山 紀州高野山高室院末 本尊千手観世音 益山ノ上に在リ古名千手院 本尊観世音ハ弘法大師自作(現今ノ本尊ハ弘法ノ作ニ非ス)(略)寺地延喜式内伊加麻志神社ノ旧跡ニシテ今佛殿(観音堂ト称ス)ノ地 往古ノ社域寺ハ庫裡ノ地ニ在テ別当ナリシヲ遂ニ社域ヲ略有セルナル可シ境内祠跡トアル 蓋其跡ナラム 今佛殿ノ後背僅ニ一小祠ヲ存スルノミ」とあります。
弘法大師の創建と伝わる名刹で、御本尊の千手観世音菩薩はお大師さまの御作と伝わります。
-------------------


参道、境内には百体の観音様が祀られ、深山の静謐なロケも加わり霊場の趣きゆたか。
参道の大楓と大銀杏は見事な古木で、ともに市の文化財に指定されています。
本堂は、おそらく寄棟造桟瓦葺で流れ向拝。水引虹梁は簡素で、正面の格子入りの硝子戸の上に「大悲殿」の扁額が掲げられています。
本堂右奥には延喜式内社に比定される伊加麻志神社(いかましじんじゃ)が御鎮座。
神仏ともに相い御座す、山上の聖域といえましょう。
御朱印拝受は上記のとおり要事前連絡です。
これほどの難路をたどって授与をのがすのは忍びないので、事前連絡をおすすめします。
専用納経帳の御朱印には「横道第六番」の札所印もいただき、駿豆両国横道三十三観音霊場第6番の御朱印を兼ねています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 千手観世音菩薩 /主印はいずれも御寶印(蓮華座+火焔宝珠)および三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
■ 第9番 引摂山 澄楽寺(ちょうらくじ)
公式Web
伊豆88遍路の紹介ページ
伊豆の国市三福638
真言宗高野山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:伊豆中道三十三観音霊場第27番
授与所:庫裡


第8番益山寺から平地に戻って、しばらくは中伊豆の里を巡るおだやかな道行きとなります。
第9番澄楽寺は大仁の北側の三福(みふく)にある、延暦十年(791年)、弘法大師の開創と伝えられる古刹です。
延暦十年は18歳の弘法大師が、修禅寺奥の院の正覚院で天魔地妖を岩谷に封じ込められたとされる年です。
弘法大師は15歳から18歳にかけて、母方の叔父阿刀大足について学問の時期で、延暦十一年(792年)、18歳で京の大学寮に入られています。
大学寮に入られる前ですが、巡拝ガイドには「たとえ出家前とはいえ庵を結ぶか何か縁があって、開創とされたものと考えられる。」と記されています。
公式Webなどでは宗派は「真言宗高野山派」となっています。
「高野山真言宗」の別称とも思いましたが、他の「高野山真言宗」寺院は「高野山真言宗」となっているので、この寺院が「真言宗高野山派」となっている理由はよくわかりません。
お大師さまとのゆかりが強いこともあって真言宗として残り、なにかの由緒があって「真言宗高野山派」となっているのかもしれません。
田京村深沢神社の供僧・覚乗による中興が伝わりますが、幾度かの祝融(火災)により旧記を失い、由緒変遷については不詳のようです
『豆州志稿』には「三福村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 元作長楽寺 延暦十年(791年)弘法大師創建 此寺最古刹ナレ共頻ニ回禄ノ災ニ罹リ流記古寶皆灰燼トナル 僧覺乗ヲ中興トス 田京深澤神社ノ供僧タリキ 慶安四年(1651年)ノ上梁文ニ供僧長楽寺ト見ユ 同社供僧六坊ノ一ナリキト伝フ 或者曰 当寺往昔定額ニ預リタル寺ニテ 定額ノ字長楽又澄楽ノ字ニ転セシナル可シ 延暦中ノ創建ト云古刹也ト伝フルヲ以テ証スベシト(略)小野の高村篁書ケルト云地蔵ノ像アリ」とあります。
伊豆88遍路の紹介ページには「桂谷二十一ヶ所巡礼の第9番」とあります。
修善寺には、桂谷八十八ヶ所巡礼という地域霊場があります。
昭和5年、修禅寺三十八世丘球学老師は、四国八十八ヶ所の霊場の土を、弘法大使が錫を留めたと伝わる修善寺・桂谷の地に移し、弘法大師の像と札所本尊の梵字・名号を刻んだ石碑を地元の協力を得て建立し「桂谷八十八ヶ所」を開創されました。
以降、霊場が開創された11月7日からの3日間に、各地から集まったお遍路さんが約28㎞の山道を歩いて巡拝する修善寺の晩秋の風物詩となりました。(2020年は新型コロナ禍により中止、2021年もこちらの記事に中止とあります。
「桂谷二十一ヶ所巡礼」については情報がほとんど得られていません。
ただし、ふつう、二十一ヶ所弘法大師霊場は八十八ヶ所の簡略版として開創されることが多いので、たとえば路傍ではなく、寺院内におかれた石碑を「桂谷二十一ヶ所」として再編したものかもしれません。
-------------------


本堂は入母屋造桟瓦葺で、正面屋根上に鐘楼をおく特徴あるつくり。
向拝柱はなく向拝正面はサッシュ扉で扁額もありませんが、本堂向かって右に御座す修行大師像が、お大師さまとのゆかりを語っています。
札所本尊は不動明王。この霊場初のお出ましです。
伊豆半島は意外にお不動さまを御本尊とする寺院が少なく、伊豆八十八ヶ所の札所本尊としても多くはないのでこちらは貴重な札所です。
御朱印は庫裡にて拝受。伊豆中道三十三観音霊場第27番の御朱印も授与されています。
〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
● 不動明王 /主印はいずれも不動明王の種子「カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 御朱印帳
〔 伊豆中道観音霊場の御朱印 〕
● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳
→ ■ 大仁温泉 「一二三荘」の入湯レポ
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2へつづく。
【 BGM 】
■ by your side - Wise feat. Nishino Kana
■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子
■ SWEET MEMORIES 松田 聖子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 多摩新四国八十八ヶ所霊場/多摩百八ヶ所霊場の御朱印
多摩新四国八十八ヶ所霊場とは、1934年(昭和9年)弘法大師ご入定1100年ご遠忌を記念して、1936年(昭和11年)に多摩地域の真言宗寺院八十八ヶ寺で再編成された弘法大師霊場です。(霊場公式ガイドブック『多摩八十八ヶ所巡拝のしおり』より)
(札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様))
”再編成”とあるのは、Wikipediaに「1823年(文政6年)、弘法大師御入定1000年を記念して、多摩郡の霊場を巡るために武玉新四国88ヶ所が作られた」とあるとおり、武玉新四国八十八ヶ所霊場を再編したものとみられます。
多摩新四国八十八ヶ所霊場は2019年2月に結願しているのですが、じつはこの霊場に20箇寺の札所を加えた多摩百八ヶ所霊場というものが存在します。
この情報は「ニッポンの霊場」様からのもので、当Webには「多摩88霊場に、20札所が追加された構成」「本霊場としての開創は1984年(昭和59年)で、宗祖弘法大師の御遠忌1,150年にあたる。」とあります。
つまり多摩百八ヶ所霊場は、1936年(昭和11年)に開創(再編)された多摩新四国八十八ヶ所霊場に、1984年(昭和59年)、20の札所を加えて成立した108箇寺からなる弘法大師霊場とみることができます。
札所範囲はすべて東京都下の主に多摩川流域で、範囲は以下のとおり。
東端:岸光山 安養寺(第1番、武蔵野市吉祥寺東町)
西端:金剛山 寶蔵寺(第50番、檜原村)
北端:成木山 安楽寺(第45番、青梅市成木)
南端:河上山 福寿院(第96番、町田市つくし野)
東端は杉並区、西端は山梨県上野原市、北端は埼玉県飯能市、南端は横浜市瀬谷区に接し、ほぼ東京都下全域に広がりをみせる広域霊場となっています。
札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様)、多摩新四国八十八ヶ所霊場に限ると→こちらの地図がわかりやすいです。
すべての札所が真言宗寺院の、保守本流ともいえる札所構成です。
札所本尊は多彩ですが、とくに大日如来と不動明王が多くなっています。
ガイドブックは霊場会公式の『多摩八十八ヶ所巡拝のしおり』が、高幡山 金剛寺(高幡不動尊)の納経所で頒布されていましたが現況は不明です。


■ 巡拝のしおり
専用納経帳は、御詠歌つきの規定用紙御朱印授与の札所があるので存在するのかもしれませんが、筆者は未確認です。

■ 規定用紙の御朱印(第100番 梅香山 大聖院)
現況、参拝者はさほど多くない模様で書入揮毫率は高めですが、それだけにご不在時の対応がむずかしく、比較的拝受難易度の高い霊場かと思います。
この傾向はとくに89番~108番で顕著です。
今般、ようやく多摩百八ヶ所霊場を結願しましたので、これから順次御朱印を紹介していきます。
なお、108の札所のうち御朱印を拝受できたのは106。
じつに98.1%の札所が御朱印を授与されています。
(新型コロナ禍前の拝受分もあるので、現況は変わっているかもしれません。)
まずは、一部のみ御朱印UPしてみます。


【写真 上(左)】 第1番発願寺・東端札所:岸光山 安養寺
【写真 下(右)】 第88番結願寺:高幡山 金剛寺


【写真 上(左)】 第89番:清浄光山 圓通寺(清瀬市下宿)
【写真 下(右)】 第108番結願寺:独峰山 高楽寺(御朱印不授与です)


【写真 上(左)】 西端:金剛山 寶蔵寺(第50番、檜原村)
【写真 下(右)】 高尾山 薬王院(第68番)もほぼ西端です


【写真 上(左)】 北端:成木山 安楽寺(第45番、青梅市成木)
【写真 下(右)】 南端:河上山 福寿院(第96番、町田市つくし野)
【 BGM 】 梶浦由記さん特集
■ 夢の大地 - Kalafina
■ far on the water - Kalafina
■「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」
梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」
(札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様))
”再編成”とあるのは、Wikipediaに「1823年(文政6年)、弘法大師御入定1000年を記念して、多摩郡の霊場を巡るために武玉新四国88ヶ所が作られた」とあるとおり、武玉新四国八十八ヶ所霊場を再編したものとみられます。
多摩新四国八十八ヶ所霊場は2019年2月に結願しているのですが、じつはこの霊場に20箇寺の札所を加えた多摩百八ヶ所霊場というものが存在します。
この情報は「ニッポンの霊場」様からのもので、当Webには「多摩88霊場に、20札所が追加された構成」「本霊場としての開創は1984年(昭和59年)で、宗祖弘法大師の御遠忌1,150年にあたる。」とあります。
つまり多摩百八ヶ所霊場は、1936年(昭和11年)に開創(再編)された多摩新四国八十八ヶ所霊場に、1984年(昭和59年)、20の札所を加えて成立した108箇寺からなる弘法大師霊場とみることができます。
札所範囲はすべて東京都下の主に多摩川流域で、範囲は以下のとおり。
東端:岸光山 安養寺(第1番、武蔵野市吉祥寺東町)
西端:金剛山 寶蔵寺(第50番、檜原村)
北端:成木山 安楽寺(第45番、青梅市成木)
南端:河上山 福寿院(第96番、町田市つくし野)
東端は杉並区、西端は山梨県上野原市、北端は埼玉県飯能市、南端は横浜市瀬谷区に接し、ほぼ東京都下全域に広がりをみせる広域霊場となっています。
札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様)、多摩新四国八十八ヶ所霊場に限ると→こちらの地図がわかりやすいです。
すべての札所が真言宗寺院の、保守本流ともいえる札所構成です。
札所本尊は多彩ですが、とくに大日如来と不動明王が多くなっています。
ガイドブックは霊場会公式の『多摩八十八ヶ所巡拝のしおり』が、高幡山 金剛寺(高幡不動尊)の納経所で頒布されていましたが現況は不明です。


■ 巡拝のしおり
専用納経帳は、御詠歌つきの規定用紙御朱印授与の札所があるので存在するのかもしれませんが、筆者は未確認です。

■ 規定用紙の御朱印(第100番 梅香山 大聖院)
現況、参拝者はさほど多くない模様で書入揮毫率は高めですが、それだけにご不在時の対応がむずかしく、比較的拝受難易度の高い霊場かと思います。
この傾向はとくに89番~108番で顕著です。
今般、ようやく多摩百八ヶ所霊場を結願しましたので、これから順次御朱印を紹介していきます。
なお、108の札所のうち御朱印を拝受できたのは106。
じつに98.1%の札所が御朱印を授与されています。
(新型コロナ禍前の拝受分もあるので、現況は変わっているかもしれません。)
まずは、一部のみ御朱印UPしてみます。


【写真 上(左)】 第1番発願寺・東端札所:岸光山 安養寺
【写真 下(右)】 第88番結願寺:高幡山 金剛寺


【写真 上(左)】 第89番:清浄光山 圓通寺(清瀬市下宿)
【写真 下(右)】 第108番結願寺:独峰山 高楽寺(御朱印不授与です)


【写真 上(左)】 西端:金剛山 寶蔵寺(第50番、檜原村)
【写真 下(右)】 高尾山 薬王院(第68番)もほぼ西端です


【写真 上(左)】 北端:成木山 安楽寺(第45番、青梅市成木)
【写真 下(右)】 南端:河上山 福寿院(第96番、町田市つくし野)
【 BGM 】 梶浦由記さん特集
■ 夢の大地 - Kalafina
■ far on the water - Kalafina
■「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」
梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 開運三社巡り【10月31日まで】
現在、磐井神社、大塚天祖神社、上目黒氷川神社の三社で「開運三社巡り」が企画され、特別御朱印が授与されています。
御鎮座1450年の磐井神社、御鎮座700年の大塚天祖神社、御鎮座450年の上目黒氷川神社を記念しての特別企画とのことです。
■ 磐井神社 大田区大森北2-20-8
■ 大塚天祖神社 豊島区南大塚3-49-1
■ 上目黒氷川神社 目黒区大橋2-16-21
当初は令和5年8月1日から9月30日まででしたが、好評につき10月31日まで延長されています。
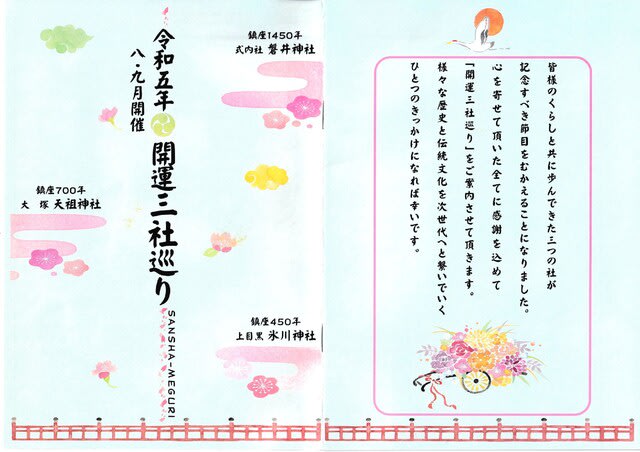


いずれも見開きの美しい限定カラー御朱印(書置)で、初穂料はいずれも500円。
無料の専用リーフレットがあり、参拝するとこちらにシールをいただけ、3社のシールが揃うと満願です。
満願で満願御朱印と記念品(オリジナル手拭い)がいただけます。(ともに数量限定)
筆者は月替わりなどの限定御朱印にはあまり興味はありませんが、御鎮座周年記念御朱印となると話は別でトライしました。(気づいたのが10月上旬だった。)
筆者は今週(10/16~の週)前半に満願しましたが、満願御朱印・記念品ともにいただけました。



参拝順はとくに設定されておりません。
三社間の距離はかなりありますが、下記のとおりいずれも駅から近いので、1日満願できるかと思います。
磐井神社:京浜急行線「大森海岸」駅徒歩3分
大塚天祖神社:JR山手線「大塚」駅・都電荒川線「大塚駅前」駅徒歩3分
上目黒氷川神社:東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩5分
御朱印受付時間は、リーフレットに下記のとおり記載されています。
磐井神社:9:30~16:30
大塚天祖神社:9:00~17:00
上目黒氷川神社:9:00~16:30
上目黒氷川神社は、先日ご紹介した「東急線 花御朱印巡り 第2弾」にも参画されているので、そちらと併せての参拝もできます。

■ 東急線 花御朱印
秋晴れの一日、御鎮座奉祝の神社巡拝はいかがでしょうか。
御鎮座1450年の磐井神社、御鎮座700年の大塚天祖神社、御鎮座450年の上目黒氷川神社を記念しての特別企画とのことです。
■ 磐井神社 大田区大森北2-20-8
■ 大塚天祖神社 豊島区南大塚3-49-1
■ 上目黒氷川神社 目黒区大橋2-16-21
当初は令和5年8月1日から9月30日まででしたが、好評につき10月31日まで延長されています。
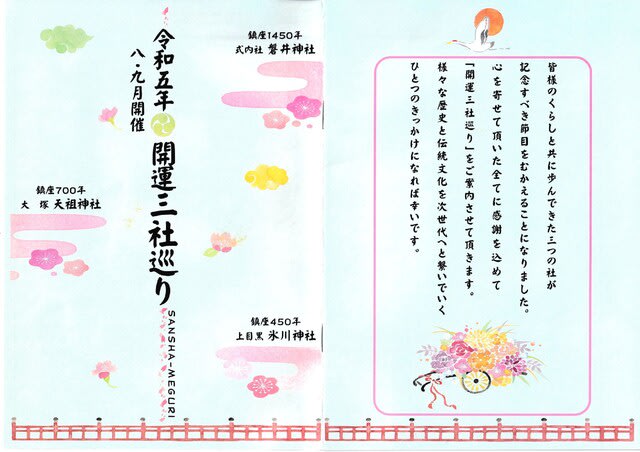


いずれも見開きの美しい限定カラー御朱印(書置)で、初穂料はいずれも500円。
無料の専用リーフレットがあり、参拝するとこちらにシールをいただけ、3社のシールが揃うと満願です。
満願で満願御朱印と記念品(オリジナル手拭い)がいただけます。(ともに数量限定)
筆者は月替わりなどの限定御朱印にはあまり興味はありませんが、御鎮座周年記念御朱印となると話は別でトライしました。(気づいたのが10月上旬だった。)
筆者は今週(10/16~の週)前半に満願しましたが、満願御朱印・記念品ともにいただけました。



参拝順はとくに設定されておりません。
三社間の距離はかなりありますが、下記のとおりいずれも駅から近いので、1日満願できるかと思います。
磐井神社:京浜急行線「大森海岸」駅徒歩3分
大塚天祖神社:JR山手線「大塚」駅・都電荒川線「大塚駅前」駅徒歩3分
上目黒氷川神社:東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩5分
御朱印受付時間は、リーフレットに下記のとおり記載されています。
磐井神社:9:30~16:30
大塚天祖神社:9:00~17:00
上目黒氷川神社:9:00~16:30
上目黒氷川神社は、先日ご紹介した「東急線 花御朱印巡り 第2弾」にも参画されているので、そちらと併せての参拝もできます。

■ 東急線 花御朱印
秋晴れの一日、御鎮座奉祝の神社巡拝はいかがでしょうか。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-12
Vol.-11からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第36番 瑠璃山 醫王寺 薬王院
(やくおういん)
新宿区観光振興協会Web
新宿区下落合4-8-2
真言宗豊山派
御本尊:薬師瑠璃光如来
札所本尊:薬師瑠璃光如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第33番、豊島八十八ヶ所霊場第36番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第2番
司元別当:(下落合)氷川神社
授与所:庫裡
第36番札所も変遷をたどっています。
現在の第36番札所は下落合の薬王院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では牛込根来町の根来山 東光院 報恩寺となっています。
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第36番の(牛込原町)報恩寺は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第36番札所は下落合の薬王院に承継されたとみられます。
下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。
薬王院は新宿区下落合にあり「ぼたん寺」「東長谷寺」とも呼ばれて庭園や舞台造の本堂が美しい真言密寺です。
相州大山寺中興の願行上人が鎌倉時代に創建と伝わります。
中世、兵火に罹り荒廃したところ、延寶年中(1673-1681年)寶壽上人が中興。
元文年中(1736-1741年)再び火災に遭い記録を失って寺伝詳細は不明ですが、江戸期に近隣の(下落合)氷川神社の別当を務めているので、途切れることなく寺歴は継続しているようです。


【写真 上(左)】 (下落合)氷川神社
【写真 下(右)】 (下落合)氷川神社の御朱印
本格的な再興は明治時代に入ってから(Wikipedia)といい、御府内霊場札所承継はその頃とみられます。
明治40年開創の豊島八十八ヶ所霊場の札所でもあるので、その頃には御府内霊場札所になっていたのでは。
真言宗豊山派総本山長谷寺から昭和41年に移植されたぼたんが有名で、40種1,000株を数え4月中~下旬の開花時には多くの見物客を迎えます。
しだれ桜やツバキも植えられた花の寺として知られ、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第2番の札所となっています。
長谷寺とゆかりふかく、本堂の造りもあってか東長谷寺とも呼ばれます。
江戸時代、落合は江戸近郊の風光明媚の地だったらしく、『江戸名所図会』に「落合惣図」が収録され、山裾には薬王院や氷川神社がみえます。

「落合惣図」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
つぎに旧36番札所とみられる報恩寺について、下記史料から追ってみます。
報恩寺は牛込根来町にあり、京都御室御所仁和寺末の新義真言宗寺院でした。
開山は覚鑁上人(興教大師)で、尾張様(不明)市ヶ谷御殿内に結ばれた御庵を覚鑁寺と号したのが草創といいます。
興教大師覚鑁上人(嘉保二年(1095年)-康治二年(1144年)は真言宗中興の祖、新義真言宗始祖とされる高僧です。
興教大師は御府内霊場ともふかいゆかりをもたれるので、主に根来寺公式Web、智積院公式Web、真言宗豊山派公式Webおよび『日本仏教 思想のあゆみ』(竹村牧男氏著)を参考にそのご生涯について辿ってみます。
覚鑁上人は嘉保二年(1095年)、肥前国藤津庄(現・佐賀県鹿島市)に生誕されました。
父は仁和寺の荘園藤津庄の総追補使伊佐平治兼元、母は橘氏の娘といい、幼名は弥千歳(みちとせ)と伝わります。
幼くして仏道を志し、十歳の時に父が亡くなると仁和寺との縁を頼って十三歳で仁和寺成就院に入られ、寛助僧正に師事して十六歳で出家得度し、正覚房覚鑁(しょうがくぼうかくばん)と号されました。
二十歳で修行を成満され東大寺戒壇院で受戒。
同年の暮れに高野山へ入り、修行を続けられました。
保安二年(1121年)、二十七歳の時に仁和寺に戻られ、師匠の寛助大僧正から伝法灌頂を受けられたといいます。
『日本仏教 思想のあゆみ』によると、覚鑁上人は奈良仏教や真言宗小野流も相承され、のちに高野山別当の念仏聖とも交流したとのことです。
三十五歳で古義真言宗の伝法の悉くを一身に受けられて、「弘法大師空海以来の才」と賞されたといいます。
法統は「真言教学」で定尊、教尋の両師、「坐禅観法」で青蓮、明寂の両師と伝わります。
大治五年(1130年)、高野山内に伝法院を建立。
修法により鳥羽上皇の病を癒して篤い帰依・外護を受け、上皇建立の北向山不動院を開山されています。
平為里による岩手荘(根来を含む)の寄進も覚鑁上人の経済的基盤となりました。
覚鑁上人は春秋二会の伝法会(学問研鑽の法要)さえ止絶していた当時の高野山の状況を憂い、真言宗の建て直しに着手。
長承元年(1132年)、鳥羽上皇の院宣を得て山内に大伝法院、密厳院を建立
長承三年(1134年)には金剛峯寺座主をも兼ねられて山内の主導権を制したといいます。
しかし、これに反発する守旧派の一部は覚鑁上人の密厳院を急襲。
このとき、密厳院の不動堂に乱入した僧徒が須弥壇上に二体の不動明王をみつけ、どちらか一方が覚鑁上人と疑うも、不動尊の霊威を受けて恐懼退散したという逸話が残ります。
この逸話からこの乱を「錐もみの乱」、上人を守護された密厳院不動尊を「錐鑽(きりもみ)不動尊」といいます。
不動尊のご加護により一命をとりとめた覚鑁上人は僧徒の非道を嘆き密厳院に籠居、1446日にも及ぶ無言三昧行を修され、この直後に代表著作である『密厳院発露懺悔文』を書き上げたともいわれます。(公式には著者不詳)
保延六年(1140年)ついに覚鑁上人は高野山を下り、弟子一派とともに根来(和歌山県岩出市)の豊福寺(ぶふくじ)に入られ、のちの根来寺を成立させていきます。
覚鑁上人の命を救われた「錐鑽不動尊」も一緒に下山して覚鑁一派を守護され、いまも根来寺不動堂に手篤く奉安されています。
以降覚鑁上人は根来を拠点とされ、学問所として「円明寺」、お住まいとして「密厳院」を創られて教学深化、弟子の教化に勤められました。
康治二年(1143年)12月根来にて四十八歳で入滅され、根来寺奥之院の霊廟に埋葬されました。
なお、覚鑁上人に興教大師の謚号が贈られたのは 元禄三年(1690年)ときの東山天皇からと伝わります。
覚鑁上人門下「大伝法院流」の弟子たちは一旦高野山へ戻りましたが守旧勢力「金剛峯方」僧徒との確執はふかく、正応元年(1288年)高野山大伝法院の学頭頼瑜は大伝法院の寺籍を根来寺に移し、覚鑁上人の教学・解釈を基礎とした「新義真言宗」を展開・発展させていくこととなります。
なお、根来寺公式Webによると、根来寺の呼称は元久二年(1205年)頃までに成立とのことで、正応元年(1288年)の頼瑜による大伝法院の寺籍異動時には「根来寺」はすでに存在していました。
宗祖・弘法大師空海以来の正統密教の復興を目指したとされる覚鑁上人ですが、結果として新義真言宗を打ち立てられたのは、ある意味歴史の必然だったのかもしれません。
根来寺は新義真言宗の本拠として繁栄し、僧兵集団「根来衆」も擁して勢力を張りましたが、豊臣秀吉との確執の末に天正十三年(1585年)討伐を受けて壊滅しました。
生き延びた門徒の僧たちは奈良や京都へ逃れ、長谷寺(のちの豊山派)や智積院(のちの智山派)において新義真言宗の教義を広めました。
真言宗では宗祖の弘法大師空海があまりに完成された仏教哲学を打ち立てられたので、後進の僧はとりつく隙がなく、新たな教学が発展しにくかったという見方もあります。
しかし覚鑁上人は平安時代後期に勃興した浄土教思想を、真言教学から捉えて包摂する「密厳浄土」思想を唱えたことで高く評価され、真言宗中興の祖としていまに至るまで崇敬されています。
(『日本仏教 思想のあゆみ』に、「(覚鑁上人は)浄土教を密教にとりこむような教義を展開」「阿弥陀仏の観察行において、阿弥陀大日であるがゆえ」とあり、念仏三昧による極楽往生を願う者を迷いなく密教に導く教義が革新的であったような気もしますが、詳細についてはよくわかりません。)
浄土教では、法然上人(浄土宗の宗祖)が有力鎌倉武士に複数の信者をもち、親鸞上人(浄土真宗の宗祖)が東国布教をされ、一遍上人(時宗の開祖)が東国経巡されるなど、「専修念仏」の教えは東国でも大きく広まりました。
浄土教の教義も包摂する新義真言宗が東国で広まったのは、このような背景もあったのかもしれません。
江戸時代に徳川頼宣公の外護もあって根来寺も復興したため、覚鑁上人の教学を受け継ぐ新義真言宗の主力は以下の三派とされ、覚鑁上人(興教大師)は(広義の)新義真言宗の派祖とされます。
■ (狭義の)新義真言宗
総本山:一乗山 大伝法院 根来寺(和歌山県岩出市)
■ 真言宗智山派
総本山:五百佛山 根来寺 智積院(京都市東山区)
■ 真言宗豊山派
総本山:豊山 神楽院 長谷寺(奈良県桜井市初瀬)
※真言宗室生寺派も新義真言宗とされる。
なお、古義真言宗と新義真言宗の違いについては、前者が「本地身説法(本地法身説)」(大日如来が自ら説法するとする説)、後者が「加持身説法(加持身説)」(大日如来が説法のため加持身となって教えを説くとする説)を説くともされますが、根本思想や所依経典類に大差はないという見方もあるようです。
新義真言宗3派の違いに至っては、素人目からはほぼわかりません。
あるいは事相(修法の作法など)の違いなのかもしれませんが、事相は密教にとってきわめて大切な事柄なので、これにより派を分ける理由は成り立つのかもしれません。
小池坊専誉僧正(長谷寺、豊山派の派祖)、玄宥僧正(智積院、智山派の派祖)以来の法統堅持の意味合いも考えられます。
『近世初期の長谷寺と智積院』(宇高良哲氏、PDF)によると、(「新義真言宗」を確立した)頼喩の法統を「中性院流」といい、その「中性院流」の承継を巡って両派それぞれの結束が高まったという見方もあるのかもしれません。
また、江戸時代の本末制度の流れで派を分ける必要があったのかも。
この点についてすこしく触れてみます。
徳川政権と新義真言宗各派の関係はそれぞれ密接でした。
〔豊山派系〕
筑波山神社の別当・知足院 中禅寺は当初天台宗でしたがのちに新義真言宗の教学下に入り、慶長七年(1602年)徳川家康公より朱印五百石を賜わって外護されました。
2世光誉は江戸別院として建立されていた湯島の護摩堂(江戸知足院)に入られ、以降江戸知足院は幕府・将軍家の祈祷を担ったといいます。
元禄元年(1688年)、江戸知足院は幕府から神田の地を与えられ伽藍を整え、隆光を開山として護持院と号しました。
大僧正隆光は、長谷寺で修学した新義真言宗の僧で5代将軍徳川綱吉公の帰依を受けました。
享保二年(1717年)、護持院が火災で焼失すると吉宗公は同地での再建を許さず、跡地は火除地(護持院ヶ原)となり、護持院は音羽護国寺の境内に移されて護持院住職が護国寺住職を兼任することとなりました。
一方、音羽護国寺の前身は上野国高崎の大聖護国寺で、ときの住職は大和長谷寺で新義真言宗を修学した亮賢(貞享四年(1687年)寂)でした。
亮賢は卜筮(ぼくぜい)の名声高く、3代将軍家光公の側室となるお玉の方(後の桂昌院)を占って5代将軍綱吉公の出産を予言し、桂昌院の篤い帰依を受けたといいます。
音羽護国寺は天和元年(1681年)、亮賢が綱吉公から桂昌院の祈願寺としての開山を命じられて開いたものです。
護持院は幕府・将軍家の祈祷寺で新義真言宗僧録(人事を統括した高い格式の寺院・僧)、
音羽護国寺は桂昌院の祈願寺で、両寺が統合した音羽護国寺は江戸時代を通じて高い格式を誇り多数の末寺を擁しました。
〔智山派系〕
根来山内の寺院の一つであった智積院の能化であった玄宥僧正は、天正十三年(1585年)の豊臣秀吉による根来山焼き討ちの際、弟子とともに難を逃れたものの各地を流転されました。
慶長六年(1601年)、玄宥僧正は徳川家康公より京都東山に寺院を寄進され、智積院の再興がなりました。
智山派の名刹、成田山 新勝寺には水戸光圀公も参詣され、江戸では10回もの出開帳が催行、最初の出開帳では5代将軍綱吉公の生母桂昌院の礼拝を受けています。
同じく智山派の川崎大師(金剛山 平間寺)では11代将軍家斉公が厄除け祈願を行っています。
府下の名刹、高尾山 薬王院には紀州徳川家から寄せられた書状が相当数存在し、江戸でも出開帳が催行されています。
〔新義真言宗/根来寺系〕
紀州徳川家の祖・徳川頼宣公は根来寺を外護され、根来寺は再興されました。
宝暦元年(1751年)には紀州藩が寺内に学頭を設置し、根来寺の立場は強まりました。
紀州徳川家の根来寺への外護は、江戸時代を通じて続いたといいます。
Wikipediaによると、明治政府の宗教政策により真言宗各宗派が合同したのが明治12年。
明治33年新義真言宗として独立するものの、昭和16年政府の政策によって真言宗宗派はふたたび合同し大真言宗が成立。
智山派・豊山派ともに戦後独立し、昭和27年に法人登記を行っています。
なので、江戸時代の史料には智山派、豊山派という表記はなく、京智積院末、大和國初瀬長谷寺末、あるいは紀州根来寺末などと書かれています。
いわゆる本末制度からの記載で、京智積院末→智山派、大和國初瀬小池坊長谷寺末→豊山派、紀州根来寺末→(狭義)新義真言宗という系譜を辿っていったことは容易に想像されます。
御府内霊場の札所は(広義の)新義真言宗寺院(とくに智山派と豊山派)がすこぶる多くなっています。
(→ こちらの札所リストをご覧ください。)
札所本尊として興教大師が定められている例も少なくありません。
この場合、中央に寺院御本尊、向かって右に弘法大師坐像、左に興教大師坐像となるのが一般的で、御朱印にもこのような構成の揮毫がみられます。
話が逸れつつ、しかも長くなりました(笑)
つぎに報恩寺から薬王院への札所承継をみてみます。
薬王院は『新編武蔵風土記稿』によれば新義真言宗大塚護持院末。
ところが、縁起は相州大山寺(真言宗大覚寺派/古義真言宗)中興の願行上人創建と伝えています。
鎌倉時代の願行上人はナゾが多い高僧ですが、こちらの記事(■ 鎌倉市の御朱印-7(24.安養院))で辿ったところでは、法統は真言宗醍醐派三宝院流(古義)および北京律です。
薬王院は古義真言宗系の願行上人創建ですが、江戸期の宗派は新義真言宗大塚護持院末(現・真言宗豊山派)。
一方、報恩寺は『寺社書上』『御府内寺社備考』には「京都御室御所仁和寺末 新義真言宗」とあり、長谷寺との関係がふかそうです。
(京都御室御所仁和寺は、現在真言宗御室派で古義真言宗)
どちらも古義、新義が錯綜していますが、江戸末期の状況をみると薬王院は大塚護持院末で真言宗豊山派系、報恩寺も長谷寺と関係がふかく真言宗豊山派系。
よって、報恩寺廃寺の際に豊山派内で御府内霊場札所の承継がなされたのでは。
報恩寺は覚鑁上人開山で「紀州長谷寺のうつし」ともいわれ、御本尊の不動明王は弘法大師の一刀三礼の御作とも伝わる新義真言宗の名刹。
大社の神宮寺でもなく、明治の神仏分離で廃止されてしまった事情はよくわかりません。
-------------------------
【史料】
【薬王院関連】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(下落合村)薬王院
新義真言宗大塚護持院末 瑠璃山醫王寺ト号ス 本尊薬師行基ノ作坐像長九寸許 外ニ観音ノ立像アリ長一尺余運慶ノ作 開山ハ願行上人ナリト云 其後兵火ニ逢テ荒廃セシカ 延寶年中(1673-1681年)寶壽ト云僧中興シ 元文年中(1736-1741年)再ヒ火災ニ罹リ記録ヲ失ヒテ詳ナルコトヲ傳ヘス
神田明神社 八幡社 稲荷社 三峯社
釋迦堂 本尊ハ眦首羯摩ノ作立像長三尺二寸 堂中ニ愛染ノ像ヲ置
金蔵院 妙楽寺 以上二ヶ寺ハ薬王院門徒ニテ 慶安(1648-1652年)以後廃トナリ 余地ハ本山ニテ預レリ
【報恩寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十六番
牛込根来町
根来山 東光院 報恩寺
御室御所末 新義
本尊:不動明王 歓喜天 弘法大師
紀州根来山のうつしなり 本尊不動明王ハ弘法大師の一刀三礼の御作なり
開山興教大師 中興信州佐久●郡浅間山志楽寺儀員上人
宝暦年中(1751-1764年)御府内八十八ヶ所之●●なり
■ 『寺社書上 [34] 牛込寺社書上 七』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.8』
京都御室御所仁和寺末 新義真言宗
牛籠根来組屋舗
根来山 東光院 報恩寺
当寺開闢起立之儀は紀伊國一乗山 僧法院 根来寺開山興教大師覚鑁上人関来下向之● 今之尾張様市ヶ谷御殿御園中ニ大師御庵室●之寺号を覚鑁寺ト唱ヘ 坂を覚鑁坂と称しは御舊跡●し今もおおく僧承り
東照宮様小牧長久手御陣之時 泉州之城々ニ流浪仕乃根来山法師拾六人御味方申上御家人ニ移(略)右拾六人市ヶ谷御殿御園中大師乃庵室●覚鑁寺●●●菩提
開山覚鑁上人康治二年(1143年)十二月寂右上人を肥前州●津郡代乃人なり 本姓は平氏 桓武天皇御代の孫平将門之裔、父ハ伊佐平兼元 母ハ橘氏の女
中興開山秀雄 寛永十九年(1642年)寂 中野宝仙寺一代ころ当寺に移御座候
本堂
本尊 不動明王 木座像 弘法大師作
嵯峨天皇の御宇大和州●寺において弘仁三年(812年)一刀三礼して開眼供養(略)承應三年(1654年)当院中興第三世遍阿仁和寺宮令●を蒙●当院に●移●
千手観音 金鋳佛立像 弘法大師作
疱瘡神 木立像 弘法大師作
什物
興教大師画像
龍の玉 雷の玉
聖天堂
歓喜天
伏見稲荷社
忍岡稲荷社
疱瘡神社
聖天堂

「報恩寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
西武新宿線「下落合」駅から徒歩約6分。新目白通りから1本北側に入ったところで、Pも広くアクセスは楽です。
南側は神田川、妙正寺川が東西に流れる低地、北側は武蔵野台地が目白台に張り出す高台の傾斜地にあります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 院号標
参道は始まりからすでに階段で、階段脇には立派な石づくりの院号標。
少しのぼると切妻屋根本から和瓦葺の豪壮な四脚門で、すでに名刹の風格をただよわせています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 緑濃い山内


【写真 上(左)】 札所標-1
【写真 下(右)】 札所標-2
山門をくぐると右手に2基の札所標。
山内は緑濃く、新宿区内の寺院とはとても思えません。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 風格ある客殿?
参道右手に修行大師像、庫裡、唐破風を構えた客殿?とつづき、正面の高みが本堂です。
本堂は大規模な懸造(舞台造とも、斜面の上に長い束柱を立て、その上に堂宇を築く普請様式、総本山長谷寺の本堂が有名)で、山内の急傾斜を巧みに活かした造りです。


【写真 上(左)】 ぼたん
【写真 下(右)】 ぼたんと本堂


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め下からの本堂
参道~舞台下はぼたん園で、開花期には堂下の斜面がぼたんの花で埋め尽くされます。
こちらの本堂は鉄筋コンクリートの入母屋造瓦葺で、参道側が妻側。
左から回り込むように階段をのぼった右手が平入りの向拝となっています。


【写真 上(左)】 舞台造
【写真 下(右)】 本堂向拝
向拝柱や扁額はなく、比較的シンプルな向拝です。


【写真 上(左)】 階段途中の六地蔵
【写真 下(右)】 観音堂
さらに階段をのぼると墓域で、手前には観音堂があります。
名刹だけに文化財も多く、鎌倉時代から室町時代の板碑が8点保存されています。(非公開)
都心のお寺が多い御府内霊場札所ではもっとも緑の多い寺院のひとつで、巡拝のいいアクセントとなっています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三十六番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印
■ 第37番 瑠璃光山 萬徳院
(まんとくいん)
江東区永代2-37-23
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:東方三十三観音霊場第32番、坂東写東都三十三観音霊場第33番、大東京百観音霊場第36番
司元別当:
授与所:社務所
第37番札所も変遷があります。
現在の第37番札所は江東区永代の萬徳院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では市ヶ谷八幡町の稲嶺山 無量壽院 東圓寺となっています。
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第37番の(市谷八幡町)東円寺は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第37番札所は永代の萬徳院に承継されたとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
江東区永代にある萬徳院は寛永六年(1629年)八丁堀材木町に創建、寛永二十年(1643年)現在地(深川奥川町)へ移転したといいます。
本寺は深川永代寺の古義真言宗で本堂には御本尊薬師如来銅立像、弘法大師木座像、如意輪観音木座像、山内に石地蔵尊などを奉安しました。
江戸時代、周囲には相撲部屋が多かったため墓地には初代から九代の伊勢の海親方、初代若松、佐渡ヶ嶽の代々、さらには行司の六代目式守伊之助などの墓があり「相撲寺」とも呼ばれます。
明治初期の神仏分離により廃寺となった市ヶ谷亀岡八幡宮の別当・東圓寺から札所を承継しています。
-------------------------
御府内霊場旧37番の東圓寺は、市ヶ谷亀岡八幡宮の別当でした。
亀岡八幡宮の縁起・沿革と切り離せないので、こちらを下記史料、市谷亀岡八幡宮の公式Webなどから追ってみます。
当宮は太田道灌が文明十一年(1479年)の江戸城築城の際、市谷御門内に西方の守護神として鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を勧請したのが創祀とされます。
鎌倉の「鶴岡」に対して「亀岡」八幡宮と号したといいます。
『江戸名所図会』には、太田道灌による創祀時に、すでに別当・東圓寺が創立とあります。
御祭神は誉田別命(応神天皇)、気長足姫尊(神功皇后)、与登比売神です。
当初は市谷御門の中(現在の千代田区内)にありましたが戦火で荒廃していたところ、江戸時代の寛永十三年(1636年)頃に江戸城の外堀ができたのを機に現在地に移転したといいます。
徳川三代将軍、桂昌院などの尊崇を得て再興され、ことに例祭は江戸市中でも華やかなものとして有名でした。
旗本に奉公若衆やいなせな町奴(まちやっこ)が多く集まる ”伊達をつくした祭” といわれ、これを見物する腰元や武家、町人の娘たちもそれぞれに着飾ったあで姿を競い、たいへんな賑わいだったそうです。
茶屋の類も競って出され、そのなかには江戸の侠客、幡随院長兵衛が見染めた茶屋女がいたといいます。
境内には江戸八所の一つとされる”時の鐘”があり、江戸ッ子に時刻を知らせていました。
明治の神仏分離令により別当・東圓寺が廃寺となり、昭和20年5月の空襲による戦火で社殿を焼失したものの、昭和37年に現在の社殿が再建され、市ヶ谷を代表する名社としていまも人々の尊崇を集めています。


【写真 上(左)】 亀岡八幡宮の社頭
【写真 下(右)】 同 拝殿


【写真 上(左)】 亀岡八幡宮の御朱印-1
【写真 下(右)】 同-2
境内に御鎮座の茶ノ木稲荷神社は、亀岡八幡宮とは別の縁起をもたれます。
創祀はふるく、弘法大師空海によると伝わります。
当社はこの地の地主神で、古来この地を稲荷山と呼んだのもそのいわれによるものといいます。
弘法大師空海開山については、御朱印にも揮毫されています。
御祭神は保食神(稲荷大神)で、商売繁昌、衣食住安泰、芸事向上、ことに眼病平癒の御利益は全国的に有名とのこと。
眼病平癒については以下のような伝説があります。
昔この山に稲荷大神の御神使の白狐がいましたが、ある時あやまって茶の木で目をつき、それ以来当社の崇敬者は茶を忌み、正月の三ヶ日は茶を呑まない習俗がありました。
とくに眼病の人は一七日、あるいは三七日二十一日の間茶をたって願えば霊験あらたかであったといわれています。
茶ノ木稲荷神社は大名・旗本、遠近の士民の崇敬が篤く、境内の奉納物にはいまも多くの崇敬者の名が刻まれています。


【写真 上(左)】 茶ノ木稲荷神社の社頭
【写真 下(右)】 同 拝殿


【写真 上(左)】 茶ノ木稲荷神社の御朱印-1
【写真 下(右)】 同-2
気になるのは茶ノ木稲荷神社が弘法大師空海ゆかりということで、このゆかりにより創始時から東圓寺が置かれたのかもしれず、またこのゆかりがあったため御府内霊場札所に定められたのかもしれません。
東圓寺の廃寺については、亀岡八幡宮が鎌倉鶴岡八幡宮からの勧請であり、明治初期の神仏分離時に鶴岡八幡宮寺(鶴岡二十五坊)が廃された流れかと推測されます。
東圓寺から萬徳院への御府内霊場札所の承継については、両山ともに古義真言宗という共通項がありますが、市ヶ谷から深川に飛んだ経緯についてはよくわかりません。
なお、江戸時代開創の霊場、山の手三十三観音霊場第33番と弁財天百社参り番外14の札所は市谷(亀岡)八幡ですが、前者については別当・東圓寺が札所という説があります。
御本尊の如意輪観世音菩薩が札所本尊かとも思いましたが、「ニッポンの霊場」様によると札所本尊は正観世音菩薩なので、べつに正観世音菩薩を奉安する観音堂があったのかもしれません。
『御府内八十八ケ所道しるべ 』によると、別当・東圓寺はいまの外堀通り沿いにあり、そこから左内坂の南側の急坂をのぼる階段が参道で、亀岡八幡宮は高台にありました。
いまも高台に御鎮座の亀岡八幡宮の参道はかなりの急階段です。
亀岡八幡宮社頭から市谷見附(南北線市ヶ谷駅付近)にかけては紅葉谷川とも長延寺谷とも呼ばれた江戸城外堀に沿った低地、亀岡八幡宮の社殿あたりは北側の市谷本村町の台地がこの低地に向かって岬状に突き出した台地のランドマーク的な地形です。
低地の社頭と台地の社殿地の高低差は大きく、いきおい参道階段は急となります。
かつての弘法大師堂は亀岡八幡宮本殿の向かって右手にあり、弘法大師堂は坂下の別当・東圓寺とは離れた高台に置かれていたことがわかります。
開山堂が最も高い、あるいは奥まった場所に置かれる例は珍しくなく、地主神であった茶ノ木稲荷神社を開山された弘法大師のゆかりをあらわす配置なのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【萬徳院関連】
■ 『寺社書上 [95] 深川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.9』
本寺深川永代寺末
深川奥川町
古義真言宗 瑠璃光山 萬徳院
当時●●寛永六年(1629年)八丁堀材木町に起立
開山 法印 慶安二年(1649年)九月寂
本堂
本尊 薬師如来銅立像
前立 同木坐像
脇立 弘法大師木座像
同 如意輪観音木座像
石地蔵尊

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
【東圓寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十七番
市ヶ谷八幡宮 門前町にあり
稲嶺山 無量壽院 東圓寺
高野山金剛院末 古義
本尊:如意輪観世音 阿弥陀如来 弘法大師
■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
市ヶ谷八幡宮
市ヶ谷御門の外にあり。別当は東圓寺と号す。南紀高野山金剛峯寺に属して、古義の真言宗なり。
本社祭神 應神天皇
甲冑の神体なり。相伝ふ、多田満仲崇信ありし霊体にして、往古攝州多田の廟にありしを。太田持資こゝにうつし奉るといへり。本地佛は愛染明王なり。
東は紳功皇后 應神天皇の御母君なり。
西は妃大神 天皇の御姉君 寶萬菩薩なり。
三神鎮座。
稲荷祠
当社地主の神なり。石階の中段左の方にあり。世俗茶の木稲荷と称す。其由来信ずるにたらず、故にこゝに略せり。此神の産子は、毎歳正月三の間茶を飲まず、眼疾を患ふる者は、一七日又三七日と日数を定めて茶を絶ち祈願する時は、霊験いちじるしく、もろもろの願ひ成就せざる事なしといへり。
社記に曰く、文明年間(1469-1487年)太田持資(道灌)、江戸城擁護のために、相州鶴ヶ岡の八幡大神を勧請し、山林及び神田等若干を附して、東園寺を創立す。山号を稲荷といふは、此地もとより稲荷のやしろありて、地主の神とする故なり。鶴ヶ岡もいにしへ稲荷の社地なり。蓋し此例に本づくと云ふ。(略)
慶長年間(1596-1615年)、別当源空少僧都、此頽基を憤激し、一宇を再営し、神殿に擬儀し、絶えたるを継ぎ、廃れたるを興す。(略)
大神君関東御入城の時、当社の来由を問はしめ給い其後御三代大将軍家、社領を附せられ(略)元禄十五年(1702年)従一位桂昌院黄金数枚を寄捨して、新たに是を奉造なし給へり。
■ 『牛込区史』(国立国会図書館)
市谷八幡神社
文明年中(『東京通誌』には文明十一年(1479年)とある)太田道灌が江戸城を築いた時、それを守護する目的で社殿を建立し、相州鶴岡八幡宮を勸請し、山林、神田を寄進した(別当東圓寺)。
後天正年中(1573-1592年)兵燹に罹って破壊したので、慶長年中(1596-1615年)別当源空が再興した。別に頼朝鶴岡八幡造営の時の余材を以て、淺草の大工が建造したとか、北氏某が多田満仲の守護神である八幡を享保(1716-1736年)頃奉納した為め、多田満仲守護紳といふとか、舊地は市谷門内にあり、寛永年中(1624-1644年)今の地に遷したとか、色々の傳説がある。本社の主祭神は應神天皇で、東には紳功皇后、西には妃大神が鎮座まします。江戸時代の隆盛は主として、元禄年中(1688-1704年)、桂昌院が帰依して、多くの寄進をしたのに因ると考へられている。

「東圓寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「市谷八幡宮」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
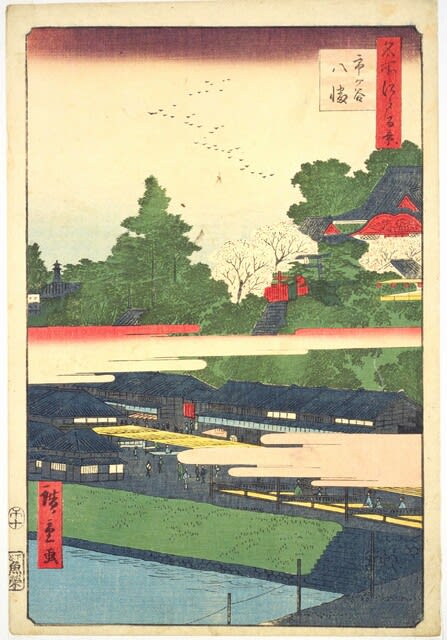
「市ヶ谷八幡」/原典:広重『名所江戸百景 市ケ谷八幡』,魚栄,安政5. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは東京メトロ東西線・都営大江戸線西武新宿線「門前仲町」駅から徒歩約6分。
「門前仲町」駅周辺には第68番・永代寺、第74番・法乗院があるので一気にまわるのが効率的です。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 院号表札
職住混在する下町のビル街に土塀を巡らした寺院建築を見せています。
山内は広くはないですが、奉拝に必要な十分な空間は確保されています。
門柱に「高野山真言宗」と「萬徳院」の院号表札。
正面が2階建ての本堂で、向かって右手の階段をのぼり向拝に向かいます。


【写真 上(左)】 門柱と本堂
【写真 下(右)】 1階


【写真 上(左)】 宗紋
【写真 下(右)】 階段からの向拝
1階正面軒には高野山真言宗宗紋「五三の桐」「三頭右巴(さんとうみぎどもえ)」が燦然と輝いています。


【写真 上(左)】 2階向拝
【写真 下(右)】 扁額
2階はコンクリ造ながら寺院建築で、おそらく入母屋造本瓦葺の妻入りとみられます。
妻部千鳥破風の下に本瓦葺の向拝屋根を置き、その下に山号扁額を掲げています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
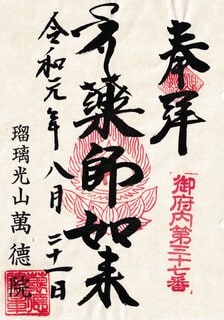

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「薬師如来」と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内第三十七番」の札所印。左下に山号院号の印判と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-13)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 君って - 西野カナ
コメント「流石実力派 もっとこういう人がテレビに出るべき」
御意。いつか復帰して、また名唱をとどけてほしい。
■ LOVE BRACE - 華原朋美 / 2013/11/25 LIVE @NHKホール
圧倒的なオリジナリティ。
この人も、もっとメジャーに活躍してほしい。
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 / Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO
上位互換カバー不可のオリジナリティ。
いまの時代には稀少なフェミニンでたおやかな歌声。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第36番 瑠璃山 醫王寺 薬王院
(やくおういん)
新宿区観光振興協会Web
新宿区下落合4-8-2
真言宗豊山派
御本尊:薬師瑠璃光如来
札所本尊:薬師瑠璃光如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第33番、豊島八十八ヶ所霊場第36番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第2番
司元別当:(下落合)氷川神社
授与所:庫裡
第36番札所も変遷をたどっています。
現在の第36番札所は下落合の薬王院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では牛込根来町の根来山 東光院 報恩寺となっています。
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第36番の(牛込原町)報恩寺は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第36番札所は下落合の薬王院に承継されたとみられます。
下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。
薬王院は新宿区下落合にあり「ぼたん寺」「東長谷寺」とも呼ばれて庭園や舞台造の本堂が美しい真言密寺です。
相州大山寺中興の願行上人が鎌倉時代に創建と伝わります。
中世、兵火に罹り荒廃したところ、延寶年中(1673-1681年)寶壽上人が中興。
元文年中(1736-1741年)再び火災に遭い記録を失って寺伝詳細は不明ですが、江戸期に近隣の(下落合)氷川神社の別当を務めているので、途切れることなく寺歴は継続しているようです。


【写真 上(左)】 (下落合)氷川神社
【写真 下(右)】 (下落合)氷川神社の御朱印
本格的な再興は明治時代に入ってから(Wikipedia)といい、御府内霊場札所承継はその頃とみられます。
明治40年開創の豊島八十八ヶ所霊場の札所でもあるので、その頃には御府内霊場札所になっていたのでは。
真言宗豊山派総本山長谷寺から昭和41年に移植されたぼたんが有名で、40種1,000株を数え4月中~下旬の開花時には多くの見物客を迎えます。
しだれ桜やツバキも植えられた花の寺として知られ、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第2番の札所となっています。
長谷寺とゆかりふかく、本堂の造りもあってか東長谷寺とも呼ばれます。
江戸時代、落合は江戸近郊の風光明媚の地だったらしく、『江戸名所図会』に「落合惣図」が収録され、山裾には薬王院や氷川神社がみえます。

「落合惣図」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
つぎに旧36番札所とみられる報恩寺について、下記史料から追ってみます。
報恩寺は牛込根来町にあり、京都御室御所仁和寺末の新義真言宗寺院でした。
開山は覚鑁上人(興教大師)で、尾張様(不明)市ヶ谷御殿内に結ばれた御庵を覚鑁寺と号したのが草創といいます。
興教大師覚鑁上人(嘉保二年(1095年)-康治二年(1144年)は真言宗中興の祖、新義真言宗始祖とされる高僧です。
興教大師は御府内霊場ともふかいゆかりをもたれるので、主に根来寺公式Web、智積院公式Web、真言宗豊山派公式Webおよび『日本仏教 思想のあゆみ』(竹村牧男氏著)を参考にそのご生涯について辿ってみます。
覚鑁上人は嘉保二年(1095年)、肥前国藤津庄(現・佐賀県鹿島市)に生誕されました。
父は仁和寺の荘園藤津庄の総追補使伊佐平治兼元、母は橘氏の娘といい、幼名は弥千歳(みちとせ)と伝わります。
幼くして仏道を志し、十歳の時に父が亡くなると仁和寺との縁を頼って十三歳で仁和寺成就院に入られ、寛助僧正に師事して十六歳で出家得度し、正覚房覚鑁(しょうがくぼうかくばん)と号されました。
二十歳で修行を成満され東大寺戒壇院で受戒。
同年の暮れに高野山へ入り、修行を続けられました。
保安二年(1121年)、二十七歳の時に仁和寺に戻られ、師匠の寛助大僧正から伝法灌頂を受けられたといいます。
『日本仏教 思想のあゆみ』によると、覚鑁上人は奈良仏教や真言宗小野流も相承され、のちに高野山別当の念仏聖とも交流したとのことです。
三十五歳で古義真言宗の伝法の悉くを一身に受けられて、「弘法大師空海以来の才」と賞されたといいます。
法統は「真言教学」で定尊、教尋の両師、「坐禅観法」で青蓮、明寂の両師と伝わります。
大治五年(1130年)、高野山内に伝法院を建立。
修法により鳥羽上皇の病を癒して篤い帰依・外護を受け、上皇建立の北向山不動院を開山されています。
平為里による岩手荘(根来を含む)の寄進も覚鑁上人の経済的基盤となりました。
覚鑁上人は春秋二会の伝法会(学問研鑽の法要)さえ止絶していた当時の高野山の状況を憂い、真言宗の建て直しに着手。
長承元年(1132年)、鳥羽上皇の院宣を得て山内に大伝法院、密厳院を建立
長承三年(1134年)には金剛峯寺座主をも兼ねられて山内の主導権を制したといいます。
しかし、これに反発する守旧派の一部は覚鑁上人の密厳院を急襲。
このとき、密厳院の不動堂に乱入した僧徒が須弥壇上に二体の不動明王をみつけ、どちらか一方が覚鑁上人と疑うも、不動尊の霊威を受けて恐懼退散したという逸話が残ります。
この逸話からこの乱を「錐もみの乱」、上人を守護された密厳院不動尊を「錐鑽(きりもみ)不動尊」といいます。
不動尊のご加護により一命をとりとめた覚鑁上人は僧徒の非道を嘆き密厳院に籠居、1446日にも及ぶ無言三昧行を修され、この直後に代表著作である『密厳院発露懺悔文』を書き上げたともいわれます。(公式には著者不詳)
保延六年(1140年)ついに覚鑁上人は高野山を下り、弟子一派とともに根来(和歌山県岩出市)の豊福寺(ぶふくじ)に入られ、のちの根来寺を成立させていきます。
覚鑁上人の命を救われた「錐鑽不動尊」も一緒に下山して覚鑁一派を守護され、いまも根来寺不動堂に手篤く奉安されています。
以降覚鑁上人は根来を拠点とされ、学問所として「円明寺」、お住まいとして「密厳院」を創られて教学深化、弟子の教化に勤められました。
康治二年(1143年)12月根来にて四十八歳で入滅され、根来寺奥之院の霊廟に埋葬されました。
なお、覚鑁上人に興教大師の謚号が贈られたのは 元禄三年(1690年)ときの東山天皇からと伝わります。
覚鑁上人門下「大伝法院流」の弟子たちは一旦高野山へ戻りましたが守旧勢力「金剛峯方」僧徒との確執はふかく、正応元年(1288年)高野山大伝法院の学頭頼瑜は大伝法院の寺籍を根来寺に移し、覚鑁上人の教学・解釈を基礎とした「新義真言宗」を展開・発展させていくこととなります。
なお、根来寺公式Webによると、根来寺の呼称は元久二年(1205年)頃までに成立とのことで、正応元年(1288年)の頼瑜による大伝法院の寺籍異動時には「根来寺」はすでに存在していました。
宗祖・弘法大師空海以来の正統密教の復興を目指したとされる覚鑁上人ですが、結果として新義真言宗を打ち立てられたのは、ある意味歴史の必然だったのかもしれません。
根来寺は新義真言宗の本拠として繁栄し、僧兵集団「根来衆」も擁して勢力を張りましたが、豊臣秀吉との確執の末に天正十三年(1585年)討伐を受けて壊滅しました。
生き延びた門徒の僧たちは奈良や京都へ逃れ、長谷寺(のちの豊山派)や智積院(のちの智山派)において新義真言宗の教義を広めました。
真言宗では宗祖の弘法大師空海があまりに完成された仏教哲学を打ち立てられたので、後進の僧はとりつく隙がなく、新たな教学が発展しにくかったという見方もあります。
しかし覚鑁上人は平安時代後期に勃興した浄土教思想を、真言教学から捉えて包摂する「密厳浄土」思想を唱えたことで高く評価され、真言宗中興の祖としていまに至るまで崇敬されています。
(『日本仏教 思想のあゆみ』に、「(覚鑁上人は)浄土教を密教にとりこむような教義を展開」「阿弥陀仏の観察行において、阿弥陀大日であるがゆえ」とあり、念仏三昧による極楽往生を願う者を迷いなく密教に導く教義が革新的であったような気もしますが、詳細についてはよくわかりません。)
浄土教では、法然上人(浄土宗の宗祖)が有力鎌倉武士に複数の信者をもち、親鸞上人(浄土真宗の宗祖)が東国布教をされ、一遍上人(時宗の開祖)が東国経巡されるなど、「専修念仏」の教えは東国でも大きく広まりました。
浄土教の教義も包摂する新義真言宗が東国で広まったのは、このような背景もあったのかもしれません。
江戸時代に徳川頼宣公の外護もあって根来寺も復興したため、覚鑁上人の教学を受け継ぐ新義真言宗の主力は以下の三派とされ、覚鑁上人(興教大師)は(広義の)新義真言宗の派祖とされます。
■ (狭義の)新義真言宗
総本山:一乗山 大伝法院 根来寺(和歌山県岩出市)
■ 真言宗智山派
総本山:五百佛山 根来寺 智積院(京都市東山区)
■ 真言宗豊山派
総本山:豊山 神楽院 長谷寺(奈良県桜井市初瀬)
※真言宗室生寺派も新義真言宗とされる。
なお、古義真言宗と新義真言宗の違いについては、前者が「本地身説法(本地法身説)」(大日如来が自ら説法するとする説)、後者が「加持身説法(加持身説)」(大日如来が説法のため加持身となって教えを説くとする説)を説くともされますが、根本思想や所依経典類に大差はないという見方もあるようです。
新義真言宗3派の違いに至っては、素人目からはほぼわかりません。
あるいは事相(修法の作法など)の違いなのかもしれませんが、事相は密教にとってきわめて大切な事柄なので、これにより派を分ける理由は成り立つのかもしれません。
小池坊専誉僧正(長谷寺、豊山派の派祖)、玄宥僧正(智積院、智山派の派祖)以来の法統堅持の意味合いも考えられます。
『近世初期の長谷寺と智積院』(宇高良哲氏、PDF)によると、(「新義真言宗」を確立した)頼喩の法統を「中性院流」といい、その「中性院流」の承継を巡って両派それぞれの結束が高まったという見方もあるのかもしれません。
また、江戸時代の本末制度の流れで派を分ける必要があったのかも。
この点についてすこしく触れてみます。
徳川政権と新義真言宗各派の関係はそれぞれ密接でした。
〔豊山派系〕
筑波山神社の別当・知足院 中禅寺は当初天台宗でしたがのちに新義真言宗の教学下に入り、慶長七年(1602年)徳川家康公より朱印五百石を賜わって外護されました。
2世光誉は江戸別院として建立されていた湯島の護摩堂(江戸知足院)に入られ、以降江戸知足院は幕府・将軍家の祈祷を担ったといいます。
元禄元年(1688年)、江戸知足院は幕府から神田の地を与えられ伽藍を整え、隆光を開山として護持院と号しました。
大僧正隆光は、長谷寺で修学した新義真言宗の僧で5代将軍徳川綱吉公の帰依を受けました。
享保二年(1717年)、護持院が火災で焼失すると吉宗公は同地での再建を許さず、跡地は火除地(護持院ヶ原)となり、護持院は音羽護国寺の境内に移されて護持院住職が護国寺住職を兼任することとなりました。
一方、音羽護国寺の前身は上野国高崎の大聖護国寺で、ときの住職は大和長谷寺で新義真言宗を修学した亮賢(貞享四年(1687年)寂)でした。
亮賢は卜筮(ぼくぜい)の名声高く、3代将軍家光公の側室となるお玉の方(後の桂昌院)を占って5代将軍綱吉公の出産を予言し、桂昌院の篤い帰依を受けたといいます。
音羽護国寺は天和元年(1681年)、亮賢が綱吉公から桂昌院の祈願寺としての開山を命じられて開いたものです。
護持院は幕府・将軍家の祈祷寺で新義真言宗僧録(人事を統括した高い格式の寺院・僧)、
音羽護国寺は桂昌院の祈願寺で、両寺が統合した音羽護国寺は江戸時代を通じて高い格式を誇り多数の末寺を擁しました。
〔智山派系〕
根来山内の寺院の一つであった智積院の能化であった玄宥僧正は、天正十三年(1585年)の豊臣秀吉による根来山焼き討ちの際、弟子とともに難を逃れたものの各地を流転されました。
慶長六年(1601年)、玄宥僧正は徳川家康公より京都東山に寺院を寄進され、智積院の再興がなりました。
智山派の名刹、成田山 新勝寺には水戸光圀公も参詣され、江戸では10回もの出開帳が催行、最初の出開帳では5代将軍綱吉公の生母桂昌院の礼拝を受けています。
同じく智山派の川崎大師(金剛山 平間寺)では11代将軍家斉公が厄除け祈願を行っています。
府下の名刹、高尾山 薬王院には紀州徳川家から寄せられた書状が相当数存在し、江戸でも出開帳が催行されています。
〔新義真言宗/根来寺系〕
紀州徳川家の祖・徳川頼宣公は根来寺を外護され、根来寺は再興されました。
宝暦元年(1751年)には紀州藩が寺内に学頭を設置し、根来寺の立場は強まりました。
紀州徳川家の根来寺への外護は、江戸時代を通じて続いたといいます。
Wikipediaによると、明治政府の宗教政策により真言宗各宗派が合同したのが明治12年。
明治33年新義真言宗として独立するものの、昭和16年政府の政策によって真言宗宗派はふたたび合同し大真言宗が成立。
智山派・豊山派ともに戦後独立し、昭和27年に法人登記を行っています。
なので、江戸時代の史料には智山派、豊山派という表記はなく、京智積院末、大和國初瀬長谷寺末、あるいは紀州根来寺末などと書かれています。
いわゆる本末制度からの記載で、京智積院末→智山派、大和國初瀬小池坊長谷寺末→豊山派、紀州根来寺末→(狭義)新義真言宗という系譜を辿っていったことは容易に想像されます。
御府内霊場の札所は(広義の)新義真言宗寺院(とくに智山派と豊山派)がすこぶる多くなっています。
(→ こちらの札所リストをご覧ください。)
札所本尊として興教大師が定められている例も少なくありません。
この場合、中央に寺院御本尊、向かって右に弘法大師坐像、左に興教大師坐像となるのが一般的で、御朱印にもこのような構成の揮毫がみられます。
話が逸れつつ、しかも長くなりました(笑)
つぎに報恩寺から薬王院への札所承継をみてみます。
薬王院は『新編武蔵風土記稿』によれば新義真言宗大塚護持院末。
ところが、縁起は相州大山寺(真言宗大覚寺派/古義真言宗)中興の願行上人創建と伝えています。
鎌倉時代の願行上人はナゾが多い高僧ですが、こちらの記事(■ 鎌倉市の御朱印-7(24.安養院))で辿ったところでは、法統は真言宗醍醐派三宝院流(古義)および北京律です。
薬王院は古義真言宗系の願行上人創建ですが、江戸期の宗派は新義真言宗大塚護持院末(現・真言宗豊山派)。
一方、報恩寺は『寺社書上』『御府内寺社備考』には「京都御室御所仁和寺末 新義真言宗」とあり、長谷寺との関係がふかそうです。
(京都御室御所仁和寺は、現在真言宗御室派で古義真言宗)
どちらも古義、新義が錯綜していますが、江戸末期の状況をみると薬王院は大塚護持院末で真言宗豊山派系、報恩寺も長谷寺と関係がふかく真言宗豊山派系。
よって、報恩寺廃寺の際に豊山派内で御府内霊場札所の承継がなされたのでは。
報恩寺は覚鑁上人開山で「紀州長谷寺のうつし」ともいわれ、御本尊の不動明王は弘法大師の一刀三礼の御作とも伝わる新義真言宗の名刹。
大社の神宮寺でもなく、明治の神仏分離で廃止されてしまった事情はよくわかりません。
-------------------------
【史料】
【薬王院関連】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(下落合村)薬王院
新義真言宗大塚護持院末 瑠璃山醫王寺ト号ス 本尊薬師行基ノ作坐像長九寸許 外ニ観音ノ立像アリ長一尺余運慶ノ作 開山ハ願行上人ナリト云 其後兵火ニ逢テ荒廃セシカ 延寶年中(1673-1681年)寶壽ト云僧中興シ 元文年中(1736-1741年)再ヒ火災ニ罹リ記録ヲ失ヒテ詳ナルコトヲ傳ヘス
神田明神社 八幡社 稲荷社 三峯社
釋迦堂 本尊ハ眦首羯摩ノ作立像長三尺二寸 堂中ニ愛染ノ像ヲ置
金蔵院 妙楽寺 以上二ヶ寺ハ薬王院門徒ニテ 慶安(1648-1652年)以後廃トナリ 余地ハ本山ニテ預レリ
【報恩寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十六番
牛込根来町
根来山 東光院 報恩寺
御室御所末 新義
本尊:不動明王 歓喜天 弘法大師
紀州根来山のうつしなり 本尊不動明王ハ弘法大師の一刀三礼の御作なり
開山興教大師 中興信州佐久●郡浅間山志楽寺儀員上人
宝暦年中(1751-1764年)御府内八十八ヶ所之●●なり
■ 『寺社書上 [34] 牛込寺社書上 七』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.8』
京都御室御所仁和寺末 新義真言宗
牛籠根来組屋舗
根来山 東光院 報恩寺
当寺開闢起立之儀は紀伊國一乗山 僧法院 根来寺開山興教大師覚鑁上人関来下向之● 今之尾張様市ヶ谷御殿御園中ニ大師御庵室●之寺号を覚鑁寺ト唱ヘ 坂を覚鑁坂と称しは御舊跡●し今もおおく僧承り
東照宮様小牧長久手御陣之時 泉州之城々ニ流浪仕乃根来山法師拾六人御味方申上御家人ニ移(略)右拾六人市ヶ谷御殿御園中大師乃庵室●覚鑁寺●●●菩提
開山覚鑁上人康治二年(1143年)十二月寂右上人を肥前州●津郡代乃人なり 本姓は平氏 桓武天皇御代の孫平将門之裔、父ハ伊佐平兼元 母ハ橘氏の女
中興開山秀雄 寛永十九年(1642年)寂 中野宝仙寺一代ころ当寺に移御座候
本堂
本尊 不動明王 木座像 弘法大師作
嵯峨天皇の御宇大和州●寺において弘仁三年(812年)一刀三礼して開眼供養(略)承應三年(1654年)当院中興第三世遍阿仁和寺宮令●を蒙●当院に●移●
千手観音 金鋳佛立像 弘法大師作
疱瘡神 木立像 弘法大師作
什物
興教大師画像
龍の玉 雷の玉
聖天堂
歓喜天
伏見稲荷社
忍岡稲荷社
疱瘡神社
聖天堂

「報恩寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
西武新宿線「下落合」駅から徒歩約6分。新目白通りから1本北側に入ったところで、Pも広くアクセスは楽です。
南側は神田川、妙正寺川が東西に流れる低地、北側は武蔵野台地が目白台に張り出す高台の傾斜地にあります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 院号標
参道は始まりからすでに階段で、階段脇には立派な石づくりの院号標。
少しのぼると切妻屋根本から和瓦葺の豪壮な四脚門で、すでに名刹の風格をただよわせています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 緑濃い山内


【写真 上(左)】 札所標-1
【写真 下(右)】 札所標-2
山門をくぐると右手に2基の札所標。
山内は緑濃く、新宿区内の寺院とはとても思えません。


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 風格ある客殿?
参道右手に修行大師像、庫裡、唐破風を構えた客殿?とつづき、正面の高みが本堂です。
本堂は大規模な懸造(舞台造とも、斜面の上に長い束柱を立て、その上に堂宇を築く普請様式、総本山長谷寺の本堂が有名)で、山内の急傾斜を巧みに活かした造りです。


【写真 上(左)】 ぼたん
【写真 下(右)】 ぼたんと本堂


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜め下からの本堂
参道~舞台下はぼたん園で、開花期には堂下の斜面がぼたんの花で埋め尽くされます。
こちらの本堂は鉄筋コンクリートの入母屋造瓦葺で、参道側が妻側。
左から回り込むように階段をのぼった右手が平入りの向拝となっています。


【写真 上(左)】 舞台造
【写真 下(右)】 本堂向拝
向拝柱や扁額はなく、比較的シンプルな向拝です。


【写真 上(左)】 階段途中の六地蔵
【写真 下(右)】 観音堂
さらに階段をのぼると墓域で、手前には観音堂があります。
名刹だけに文化財も多く、鎌倉時代から室町時代の板碑が8点保存されています。(非公開)
都心のお寺が多い御府内霊場札所ではもっとも緑の多い寺院のひとつで、巡拝のいいアクセントとなっています。
御朱印は庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三十六番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印
■ 第37番 瑠璃光山 萬徳院
(まんとくいん)
江東区永代2-37-23
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:東方三十三観音霊場第32番、坂東写東都三十三観音霊場第33番、大東京百観音霊場第36番
司元別当:
授与所:社務所
第37番札所も変遷があります。
現在の第37番札所は江東区永代の萬徳院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では市ヶ谷八幡町の稲嶺山 無量壽院 東圓寺となっています。
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第37番の(市谷八幡町)東円寺は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第37番札所は永代の萬徳院に承継されたとみられます。
下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
江東区永代にある萬徳院は寛永六年(1629年)八丁堀材木町に創建、寛永二十年(1643年)現在地(深川奥川町)へ移転したといいます。
本寺は深川永代寺の古義真言宗で本堂には御本尊薬師如来銅立像、弘法大師木座像、如意輪観音木座像、山内に石地蔵尊などを奉安しました。
江戸時代、周囲には相撲部屋が多かったため墓地には初代から九代の伊勢の海親方、初代若松、佐渡ヶ嶽の代々、さらには行司の六代目式守伊之助などの墓があり「相撲寺」とも呼ばれます。
明治初期の神仏分離により廃寺となった市ヶ谷亀岡八幡宮の別当・東圓寺から札所を承継しています。
-------------------------
御府内霊場旧37番の東圓寺は、市ヶ谷亀岡八幡宮の別当でした。
亀岡八幡宮の縁起・沿革と切り離せないので、こちらを下記史料、市谷亀岡八幡宮の公式Webなどから追ってみます。
当宮は太田道灌が文明十一年(1479年)の江戸城築城の際、市谷御門内に西方の守護神として鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を勧請したのが創祀とされます。
鎌倉の「鶴岡」に対して「亀岡」八幡宮と号したといいます。
『江戸名所図会』には、太田道灌による創祀時に、すでに別当・東圓寺が創立とあります。
御祭神は誉田別命(応神天皇)、気長足姫尊(神功皇后)、与登比売神です。
当初は市谷御門の中(現在の千代田区内)にありましたが戦火で荒廃していたところ、江戸時代の寛永十三年(1636年)頃に江戸城の外堀ができたのを機に現在地に移転したといいます。
徳川三代将軍、桂昌院などの尊崇を得て再興され、ことに例祭は江戸市中でも華やかなものとして有名でした。
旗本に奉公若衆やいなせな町奴(まちやっこ)が多く集まる ”伊達をつくした祭” といわれ、これを見物する腰元や武家、町人の娘たちもそれぞれに着飾ったあで姿を競い、たいへんな賑わいだったそうです。
茶屋の類も競って出され、そのなかには江戸の侠客、幡随院長兵衛が見染めた茶屋女がいたといいます。
境内には江戸八所の一つとされる”時の鐘”があり、江戸ッ子に時刻を知らせていました。
明治の神仏分離令により別当・東圓寺が廃寺となり、昭和20年5月の空襲による戦火で社殿を焼失したものの、昭和37年に現在の社殿が再建され、市ヶ谷を代表する名社としていまも人々の尊崇を集めています。


【写真 上(左)】 亀岡八幡宮の社頭
【写真 下(右)】 同 拝殿


【写真 上(左)】 亀岡八幡宮の御朱印-1
【写真 下(右)】 同-2
境内に御鎮座の茶ノ木稲荷神社は、亀岡八幡宮とは別の縁起をもたれます。
創祀はふるく、弘法大師空海によると伝わります。
当社はこの地の地主神で、古来この地を稲荷山と呼んだのもそのいわれによるものといいます。
弘法大師空海開山については、御朱印にも揮毫されています。
御祭神は保食神(稲荷大神)で、商売繁昌、衣食住安泰、芸事向上、ことに眼病平癒の御利益は全国的に有名とのこと。
眼病平癒については以下のような伝説があります。
昔この山に稲荷大神の御神使の白狐がいましたが、ある時あやまって茶の木で目をつき、それ以来当社の崇敬者は茶を忌み、正月の三ヶ日は茶を呑まない習俗がありました。
とくに眼病の人は一七日、あるいは三七日二十一日の間茶をたって願えば霊験あらたかであったといわれています。
茶ノ木稲荷神社は大名・旗本、遠近の士民の崇敬が篤く、境内の奉納物にはいまも多くの崇敬者の名が刻まれています。


【写真 上(左)】 茶ノ木稲荷神社の社頭
【写真 下(右)】 同 拝殿


【写真 上(左)】 茶ノ木稲荷神社の御朱印-1
【写真 下(右)】 同-2
気になるのは茶ノ木稲荷神社が弘法大師空海ゆかりということで、このゆかりにより創始時から東圓寺が置かれたのかもしれず、またこのゆかりがあったため御府内霊場札所に定められたのかもしれません。
東圓寺の廃寺については、亀岡八幡宮が鎌倉鶴岡八幡宮からの勧請であり、明治初期の神仏分離時に鶴岡八幡宮寺(鶴岡二十五坊)が廃された流れかと推測されます。
東圓寺から萬徳院への御府内霊場札所の承継については、両山ともに古義真言宗という共通項がありますが、市ヶ谷から深川に飛んだ経緯についてはよくわかりません。
なお、江戸時代開創の霊場、山の手三十三観音霊場第33番と弁財天百社参り番外14の札所は市谷(亀岡)八幡ですが、前者については別当・東圓寺が札所という説があります。
御本尊の如意輪観世音菩薩が札所本尊かとも思いましたが、「ニッポンの霊場」様によると札所本尊は正観世音菩薩なので、べつに正観世音菩薩を奉安する観音堂があったのかもしれません。
『御府内八十八ケ所道しるべ 』によると、別当・東圓寺はいまの外堀通り沿いにあり、そこから左内坂の南側の急坂をのぼる階段が参道で、亀岡八幡宮は高台にありました。
いまも高台に御鎮座の亀岡八幡宮の参道はかなりの急階段です。
亀岡八幡宮社頭から市谷見附(南北線市ヶ谷駅付近)にかけては紅葉谷川とも長延寺谷とも呼ばれた江戸城外堀に沿った低地、亀岡八幡宮の社殿あたりは北側の市谷本村町の台地がこの低地に向かって岬状に突き出した台地のランドマーク的な地形です。
低地の社頭と台地の社殿地の高低差は大きく、いきおい参道階段は急となります。
かつての弘法大師堂は亀岡八幡宮本殿の向かって右手にあり、弘法大師堂は坂下の別当・東圓寺とは離れた高台に置かれていたことがわかります。
開山堂が最も高い、あるいは奥まった場所に置かれる例は珍しくなく、地主神であった茶ノ木稲荷神社を開山された弘法大師のゆかりをあらわす配置なのかもしれません。
-------------------------
【史料】
【萬徳院関連】
■ 『寺社書上 [95] 深川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.9』
本寺深川永代寺末
深川奥川町
古義真言宗 瑠璃光山 萬徳院
当時●●寛永六年(1629年)八丁堀材木町に起立
開山 法印 慶安二年(1649年)九月寂
本堂
本尊 薬師如来銅立像
前立 同木坐像
脇立 弘法大師木座像
同 如意輪観音木座像
石地蔵尊

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
【東圓寺関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十七番
市ヶ谷八幡宮 門前町にあり
稲嶺山 無量壽院 東圓寺
高野山金剛院末 古義
本尊:如意輪観世音 阿弥陀如来 弘法大師
■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
市ヶ谷八幡宮
市ヶ谷御門の外にあり。別当は東圓寺と号す。南紀高野山金剛峯寺に属して、古義の真言宗なり。
本社祭神 應神天皇
甲冑の神体なり。相伝ふ、多田満仲崇信ありし霊体にして、往古攝州多田の廟にありしを。太田持資こゝにうつし奉るといへり。本地佛は愛染明王なり。
東は紳功皇后 應神天皇の御母君なり。
西は妃大神 天皇の御姉君 寶萬菩薩なり。
三神鎮座。
稲荷祠
当社地主の神なり。石階の中段左の方にあり。世俗茶の木稲荷と称す。其由来信ずるにたらず、故にこゝに略せり。此神の産子は、毎歳正月三の間茶を飲まず、眼疾を患ふる者は、一七日又三七日と日数を定めて茶を絶ち祈願する時は、霊験いちじるしく、もろもろの願ひ成就せざる事なしといへり。
社記に曰く、文明年間(1469-1487年)太田持資(道灌)、江戸城擁護のために、相州鶴ヶ岡の八幡大神を勧請し、山林及び神田等若干を附して、東園寺を創立す。山号を稲荷といふは、此地もとより稲荷のやしろありて、地主の神とする故なり。鶴ヶ岡もいにしへ稲荷の社地なり。蓋し此例に本づくと云ふ。(略)
慶長年間(1596-1615年)、別当源空少僧都、此頽基を憤激し、一宇を再営し、神殿に擬儀し、絶えたるを継ぎ、廃れたるを興す。(略)
大神君関東御入城の時、当社の来由を問はしめ給い其後御三代大将軍家、社領を附せられ(略)元禄十五年(1702年)従一位桂昌院黄金数枚を寄捨して、新たに是を奉造なし給へり。
■ 『牛込区史』(国立国会図書館)
市谷八幡神社
文明年中(『東京通誌』には文明十一年(1479年)とある)太田道灌が江戸城を築いた時、それを守護する目的で社殿を建立し、相州鶴岡八幡宮を勸請し、山林、神田を寄進した(別当東圓寺)。
後天正年中(1573-1592年)兵燹に罹って破壊したので、慶長年中(1596-1615年)別当源空が再興した。別に頼朝鶴岡八幡造営の時の余材を以て、淺草の大工が建造したとか、北氏某が多田満仲の守護神である八幡を享保(1716-1736年)頃奉納した為め、多田満仲守護紳といふとか、舊地は市谷門内にあり、寛永年中(1624-1644年)今の地に遷したとか、色々の傳説がある。本社の主祭神は應神天皇で、東には紳功皇后、西には妃大神が鎮座まします。江戸時代の隆盛は主として、元禄年中(1688-1704年)、桂昌院が帰依して、多くの寄進をしたのに因ると考へられている。

「東圓寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「市谷八幡宮」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
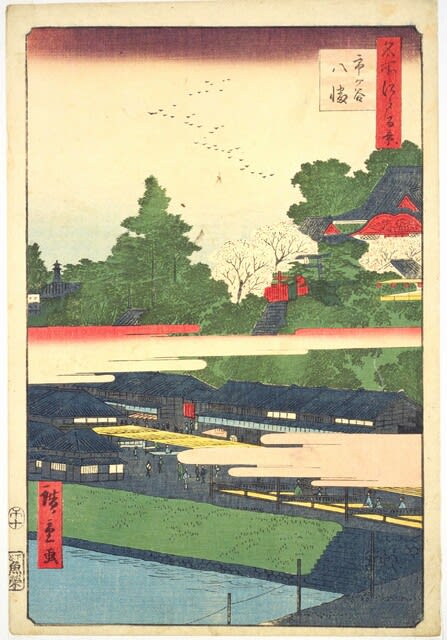
「市ヶ谷八幡」/原典:広重『名所江戸百景 市ケ谷八幡』,魚栄,安政5. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは東京メトロ東西線・都営大江戸線西武新宿線「門前仲町」駅から徒歩約6分。
「門前仲町」駅周辺には第68番・永代寺、第74番・法乗院があるので一気にまわるのが効率的です。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 院号表札
職住混在する下町のビル街に土塀を巡らした寺院建築を見せています。
山内は広くはないですが、奉拝に必要な十分な空間は確保されています。
門柱に「高野山真言宗」と「萬徳院」の院号表札。
正面が2階建ての本堂で、向かって右手の階段をのぼり向拝に向かいます。


【写真 上(左)】 門柱と本堂
【写真 下(右)】 1階


【写真 上(左)】 宗紋
【写真 下(右)】 階段からの向拝
1階正面軒には高野山真言宗宗紋「五三の桐」「三頭右巴(さんとうみぎどもえ)」が燦然と輝いています。


【写真 上(左)】 2階向拝
【写真 下(右)】 扁額
2階はコンクリ造ながら寺院建築で、おそらく入母屋造本瓦葺の妻入りとみられます。
妻部千鳥破風の下に本瓦葺の向拝屋根を置き、その下に山号扁額を掲げています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
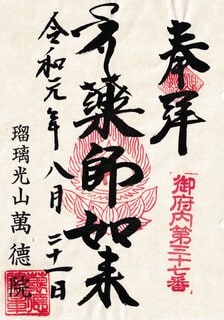

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「薬師如来」と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右に「御府内第三十七番」の札所印。左下に山号院号の印判と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-13)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 君って - 西野カナ
コメント「流石実力派 もっとこういう人がテレビに出るべき」
御意。いつか復帰して、また名唱をとどけてほしい。
■ LOVE BRACE - 華原朋美 / 2013/11/25 LIVE @NHKホール
圧倒的なオリジナリティ。
この人も、もっとメジャーに活躍してほしい。
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 / Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO
上位互換カバー不可のオリジナリティ。
いまの時代には稀少なフェミニンでたおやかな歌声。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-11
Vol.-10からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第33番 醫王山 東光院 眞性寺
(しんしょうじ)
巣鴨地蔵通り商店街Web
豊島区巣鴨3-21-21
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第33番、豊島八十八ヶ所霊場第33番、江戸六地蔵第3番、北豊島三十三観音霊場第20番、九品佛霊場第1番、弁財天百社参り番外16、江戸・東京四十四閻魔参り第29番
司元別当:
授与所:寺務所
第33番は「おばあちゃんの原宿」とも呼ばれる巣鴨の名刹、眞性寺です。
第33番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに眞性寺なので、御府内霊場開創時から一貫して巣鴨の眞性寺であったとみられます。
下記史料、巣鴨地蔵通り商店街Web、現地掲示類を参照して縁起・沿革を追ってみます。
眞性寺の開創は不詳ながら、聖武天皇の勅願による行基菩薩の開基と伝わります。
中興開基は元和元年(1615年)祐遍法印によります。
元禄年中(1688-1704年)に田端村東覚寺末となり、盛辨法印が入院。
正徳元年(1711年)に東覚寺末を離れ、京御室御所(仁和寺)直末となっています。
御本尊は秘佛の薬師如来。
江戸時代より御府内霊場第33番札所・江戸六地蔵参り第3番として参詣者で賑わったといいます。
巣鴨は中山道の江戸への入口に当たる要衝で、ふるくから賑わいました。
眞性寺山内には芭蕉句碑も残っています。
~ 白露も こぼさぬ萩の うねりかな ~
また、徳川8代将軍吉宗公が放鷹の折に当寺を御膳所とされたなど、華々しい歴史が伝わります。
なにより江戸六地蔵の札所のひとつとして、参詣者を集めたといいます。
江戸六地蔵は、江戸市中の6箇所に造立された地蔵菩薩坐像を廻る地蔵尊霊場です。
江戸深川の地蔵坊正元が宝永三年(1706年)に発願し、江戸市中から寄進者を集めて江戸の出入口6箇所に丈六の銅造地蔵菩薩坐像を造立して開創されました。
地蔵坊正元とその両親が正元の病気平癒を地蔵菩薩に祈願したところ有り難くも快癒したため、京都六地蔵に倣っての開創と伝わります。
〔江戸六地蔵〕
第1番目(巡拝札第1番)
品川寺 旧東海道 品川区南品川
第2番目(巡拝札第4番)
東禅寺 奥州街道 台東区東浅草
第3番目(巡拝札第2番)
太宗寺 甲州街道 新宿区新宿
第4番目(巡拝札第3番)
眞性寺 旧中山道 豊島区巣鴨
第5番目(巡拝札第5番)
霊巌寺 水戸街道 江東区白河
第6番目(巡拝札第6番)
永代寺 千葉街道 江東区富岡
第6番目(代仏)
浄名院 江東区上野桜木
※永代寺以外は現存。浄名院の代仏については諸説あり
鋳造は神田鍋町の鋳物師・太田駿河守藤原正儀で、造立時には鍍金が施されたといいます。
金色に輝く大きな地蔵尊(おおむね像高2.5m以上)は、いずれも交通の要衝に置かれたこともあって多くの参詣者で賑わい、Wikipediaによると六体の像や蓮台に刻まれた寄進者の数は72,000名を超えるとのこと。
江戸期の多くの絵図に当山が描かれていることからも、城北の名所として広く親しまれたことがわかります。
元禄の頃から田端東覚寺の末寺でしたが、正徳元年(1711年)に京都御室御所仁和寺の末になったといいます。
明治33年には仁和寺末を離れ、真言宗豊山派総本山長谷寺の末寺となっていまに至ります。
〔関連記事〕
■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~
「江戸六地蔵」については、まだまとめておりません。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十三番
すがも中下町
醫王山 東光院 眞性寺
御直末
本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師
■『御府内寺社備考 P.6』
京都仁和寺末
巣鴨町増上寺領
醫王山 東光院 眞性寺
起立之儀相知不●-●元禄年中(1688-1704年)に本寺田端村東覚寺末ニ ●●十二年四月盛辨法印当寺に入院 正徳元年(1711年)に至り東覚寺離末 同年二月上京●時御室御所直末に御成(略)
中興開基 祐遍法印元和元年(1615年)当寺住職仕
本堂
本尊 薬師如来木坐像 行基菩薩作
鐘楼堂 大鐘
神明社
八幡宮社 八幡宮 愛宕 稲荷 相殿
阿弥陀堂 阿弥陀如来木座像 九品佛壱番目ニ御座候
閻魔堂 閻魔王坐像尺四尺
銅地蔵尊坐像壱丈六尺石壇 江戸六地蔵第三番目ニ御座候
御成門跡
■ 當國六地蔵造立之意趣(略記)(眞性寺山内掲示資料より)
抑 予十二歳のころ古郷を出で 十六歳にして剃髪受戒す 其後廿四歳の秋乃ころより重病を請け(略)醫術の叶難く死既に極まれり(略)父母是を悲 偏に地蔵菩薩に延命を祷奉る 自らも親の嘆骨髄に通 一心に地蔵菩薩に請願すへく我若菩薩の慈恩を蒙って父母存生の内命を延る事を得 尽未来に至まで衆生の為に菩薩の御利益を勧め多くの尊像を造立して衆生に帰依せしめ 共に安楽を得せしめんと誓 其夜不思議の霊験を得て重病速に本復す(略)帝都の六地蔵に周く御当地の入口毎に 一躰づつ金銅壱丈六尺の地蔵菩薩を六所に都合六躰造立して天下安全武運長久御城下繁栄を祝願し 兼而又諸国往来の一切衆生へ遍く縁を結ばしめんと誓(略)諸人往来の街に立てれば一切衆生皆悉く縁結び奉る 抑願し神明仏陀の加護を蒙りて六躰の尊像恙なく像立して万代の一切衆生と共に同じく善道に至らん事を
勧化沙門 深川 地蔵坊正元 謹言

「眞性寺」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「眞性寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
JR巣鴨駅北口界隈は、いつも年配者を中心に賑わいをみせています。
巣鴨にはふるくからとげぬき地蔵尊・高岩寺、江戸六地蔵第3番の眞性寺がありました。
高岩寺のとげぬき地蔵尊・洗い観音ともに病気平癒・延命に霊験あらたか、眞性寺の御本尊はお薬師様で、江戸六地蔵のお地蔵様も病気平癒のご利益で知られています。
健康・延命を願う年配者の参詣スポットとなり、その参詣客を狙って年配者向けのお店が増えていったというのが、巣鴨にお年寄りが多い理由とされます。


【写真 上(左)】 眞性寺前から商店街
【写真 下(右)】 巣鴨地蔵通り商店街


【写真 上(左)】 高岩寺
【写真 下(右)】 高岩寺の御朱印
中心の「巣鴨地蔵通り商店街」は坂道がなくバリアフリー完備で、お年寄りも安心して買い物やグルメを楽しめることも人気の理由とされています。
眞性寺はJR山手線「巣鴨」駅北口から徒歩約3分、都営三田線「巣鴨」駅からだと至近で便利がいいです。
巣鴨駅前を北上する国道17号(中仙道)から分岐する「巣鴨地蔵通り商店街」は旧中山道なので、「巣鴨地蔵通り商店街」の入口にある眞性寺はちょうど新旧中山道の分岐に面していることになります。
中山道側からは奥行きのある参道を構え、参道脇に並ぶ提灯が人々の篤い信仰を物語っています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
参道正面に江戸六地蔵の地蔵尊坐像とそのおくに本堂がみえます。
参道右手の建物は阿弥陀堂で、九品佛霊場第1番の拝所。
江戸・東京四十四閻魔参り第29番の閻魔大王もこちらに御座します。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂と本堂
【写真 下(右)】 芭蕉句碑
江戸六地蔵尊の向かって左手に山門があり、山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の扁額


【写真 上(左)】 江戸六地蔵札所標
【写真 下(右)】 地蔵尊と本堂
江戸六地蔵の地蔵尊は蓮座に趺座され像高さ2.68m、蓮花台を含めると3.45mにも及ぶ大きな坐像で、東京都指定有形文化財に指定されています。
日々多くの参詣者を集め、あたりは線香のけむりがたなびいています。


【写真 上(左)】 地蔵尊
【写真 下(右)】 陰光地蔵尊碑
毎年6月24日夕刻に行われる百万遍大念珠供養は、全長16m、541の桜材の珠からなる大念珠を念仏を唱えつつ500~600名で廻して供養するもので、巣鴨の梅雨の風物詩として知られています。
地蔵尊前には「江戸六地蔵三番目」の札所碑と「陰光地蔵尊」の碑が建っています。
この「陰光地蔵尊」の碑文には、百万遍大念珠供養の音頭取りを父子併せて実に八十年間務めた繪馬屋 征矢父子の功徳を賞して「陰光地蔵尊」と尊号し、御信心を新たにすることが刻されています。


【写真 上(左)】 地蔵尊立像
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
六地蔵の地蔵尊の向かって左手堂宇内には地蔵尊立像が御座します。
子供を抱えられているので子安地蔵尊かもしれません。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂扁額
【写真 下(右)】 阿弥陀如来像
参道向かって右手には近代建築の阿弥陀堂。
眞性寺は『江戸砂子拾遺』『拾遺続江戸砂子』などに収録されている「九品佛霊場」の第1番札所(上品上生)です。
上品上生の阿弥陀如来の印相はふつうは来迎印ですが、こちらの阿弥陀様は施無畏印・与願印です。


【写真 上(左)】 九体の阿弥陀佛
【写真 下(右)】 初閻魔の阿弥陀堂
こちらの堂宇本尊の阿弥陀様が「九品佛霊場」(→札所リスト(「ニッポンの霊場」様))の第1番の御像とも思われますが、印相は施無畏印・与願印。
阿弥陀如来の印相は施無畏印・与願印、転法輪印(説法印)、阿弥陀定印、来迎印と多彩かつ複雑なので、印相からみてこちらが九品佛霊場の札所本尊かどうかはよくわかりません。
堂内に来迎印(上品上生印)を結ばれた九体の阿弥陀木坐像が御座し、『御府内寺社備考』には「阿弥陀堂 阿弥陀如来木座像 九品佛壱番目ニ御座候」とあるので、こちらが九品佛霊場の札所本尊とみるのが自然かもしれません。


【写真 上(左)】 閻魔大王と奪衣婆
【写真 下(右)】 初閻魔の閻魔大王
堂内向かって右手に御座す閻魔大王はおそらく江戸・東京四十四閻魔参り第29番の札所本尊で、常時間近でお参りできます。
閻魔様の御朱印も拝受していますが、こちらはご縁日限定かもしれません。
令和5年秋時点で阿弥陀堂改築の予定で、すでに普請工事に入っています。
閻魔様も新堂にご遷座の予定で、閻魔様の前には新たに奪衣婆がお出ましになっていました。


【写真 上(左)】 地蔵尊と本堂
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
階段上の本堂は重層屋根のうえに相輪を備えた堂々たる構えですが、様式はよくわかりません。
下層屋根の唐破風が向拝雨よけとなっていますが、向拝柱はなく比較的シンプル。
本堂内陣見上げにも山号扁額が掲げられ、向かって右手には百万遍大念珠が安置されています。
御本尊のお薬師様は絶対秘仏なので、正面お厨子前に御座す薬師如来坐像は御前立ちかと思われます。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 観世音菩薩立像
本堂向かって右手が寺務所で、その前には修行大師像と石仏の観世音菩薩立像が御座します。
眞性寺は北豊島三十三観音霊場第20番の札所(→ 札所一覧(「ニッポンの霊場」様))ですが、この霊場はすこぶる情報が少なく、この観世音菩薩像が札所本尊であるかは定かではありません。
御朱印は寺務所で拝受。
ご対応はいつお伺いしてもたいへんにご親切で、頭が下がります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
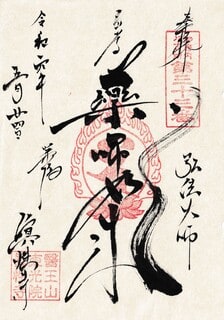

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八所第三十三番」の札所印。寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 江戸六地蔵の御朱印


【写真 上(左)】 閻魔大王のご縁日の御朱印
【写真 下(右)】 九品佛霊場
閻魔様の御朱印授与は、ご縁日限定かもしれません。
九品佛霊場の御朱印については、巡拝者もきわめて少なく通常は授与されていないとのことでしたが、ご厚意で授与いただけました。
「九品佛第壱番」「上品上生」の揮毫をいただいた稀少な御朱印です。
■ 第34番 薬王山 遍照院 三念寺
(さんねんじ)
文京区本郷2-15-6
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第34番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所
司元別当:
授与所:寺務所
第34番は本郷にある真言宗の古刹です。
第34番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに三念寺なので、御府内霊場開創時から一貫して本郷の三念寺であったとみられます。
下記史料から縁起・沿革を追ってみます。
開創・開基は不明ですが、文明年中(1469-1487年)一人の修行者が一宇の草堂を結び遍照院と号したといいます。
慈覺大師真作の大日如来を安置し恭敬されたとも。
御本尊の薬師如来は、恵心僧都の母公が病に罹ったときに恵心僧都みずからが彫刻されたといいます。
一時期三州の鳳来寺に移り、慶長年中(1596-1615年)に当山に奉安、堂舎を整えて醫王山 三念寺と号したともいいます。
中興開山は法印品隆(文禄二年(1593年)卒)と伝わります。
往古は土手四番町にありましたが、元禄(1688-1704年)の頃当地へ移転ともいいます。
「千代田区観光協会Web」の千代田区五番町の三年坂の説明に「『新撰東京名所図会』に「三年坂は現今通称する所なるも、三念寺坂といふを正しとす。むかし三念寺といへる寺地なりしに因り此名あり。」とあります。」とあるので、土手四番町は現在の千代田区五番町あたりと推測されます。
『江戸砂子』に掲載されているらしい「江戸薬師如来霊場三十二ヶ所」(出所:「ニッポンの霊場」様)の札所なので、江戸期から著名なお薬師様だったとみられます。
なお、『寺社書上』『御府内寺社備考』には、本堂御本尊は大日如来、薬師堂に薬師如来とあり、寺院としては両尊御本尊だったのかもしれませんが、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所本尊として薬師如来 弘法大師 興教大師が記されているので、お薬師さまのお寺のイメージが強かったのではないでしょうか。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十四番
本郷元町
薬王山 遍照院 三念寺
本所彌勒寺末 新義
本尊:薬師如来 弘法大師 興教大師
本尊薬師如来恵心僧都の御作なり
■ 『寺社書上 [71] 本郷寺社書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.105』
本所彌勒寺末
本郷御弓町
薬王山 遍照院 三念寺
開闢・開基 未分明
中興開山 法印品隆(文禄二年(1593年)卒)
本堂
本尊 大日如来木座像
阿弥陀如来 地蔵菩薩 弘法大師 興教大師
薬師堂
薬師如来木像 恵心僧都作之由
十二神将木像 同
日光菩薩木像 月光菩薩 同
各像 前立
■ 『本郷区史』(文京区立図書館Web)
元町二丁目に在り、本所弥勒寺末、薬王山遍照院と号す。『江砂餘礫』には当寺古く土手四番町に在り、元禄(1688-1704年)の比元町へ移さるとあるが、文政書上には慶長八年(1603年)当地拝領と記して居る。

「三念寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本郷湯島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC
-------------------------
メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅の南(徒歩約5分)、東京都水道歴史館のすぐ北側で、都内に住んでいてもなかなか訪れないところです。
壱岐坂通りから一本南の路地に面したビル内の寺院です。
このあたりの江戸期の地名は御弓町(のちに本郷元町)。
「坂学会Web」に「この坂(本郷の新坂)の一帯は,もと御弓町(おゆみちょう),その後,弓町と呼ばれ,慶長・元和の頃(1600年ごろ) 御弓町の与力同心六組の屋敷がおかれ,的場で弓の稽古が行われた。」とあります。
『江戸切絵図』をみても、三念寺周辺には区画の狭い武家屋敷や「御中間」が多く、この地が与力同心や中間(武家の奉公人)層の居住エリアであったことがわかります。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 エントランス
2016年春に初参拝したときの写真が行方不明になってしまい、2019年夏(建物改装中でメッシュシートで覆われていた)の写真しかなく詳細不明です。


【写真 上(左)】 六地蔵尊とエントランス
【写真 下(右)】 六地蔵尊
Web検索してみると、白い外壁のなかなか瀟洒なビルで2階が本堂とみられ、2階正面に山号扁額が掲げられています。
ビル前面に六地蔵尊を奉安し、寺号標もあるので寺院であることはすぐにわかります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 扉を開けると正面が拝所
本堂は2階ですが、御府内霊場の奉拝は1階正面の拝所にておこないます。
正面が坐像の薬師如来とおくに釈迦三尊の掛け軸。
薬師如来の左右に弘法大師と興教大師の坐像が御座します。
ベルを押さないとビル内に入れないので、ベルでお呼びして御府内霊場巡拝を申告、御朱印をご準備いただくあいだに勤行という流れになります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「薬師如来」「弘法大師」と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫、主印は「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八所」「第三十四番」の札所印。寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第35番 金剛寶山 延壽寺 根生院
(こんしょういん)
豊島区高田1-34-6
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第35番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所
司元別当:
授与所:庫裡
第35番は豊島区高田にある真言宗の名刹です。
第35番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに根生院なので、御府内霊場開創時から一貫して根生院であったとみられます。
ただし、『御府内八十八ケ所道しるべ』での所在は「湯嶋切通し上」となっています。
下記史料、「豊島区Web資料」、現地掲示類から縁起・沿革を追ってみます。
創建は寛永十三年(1636年)、徳川3代将軍家光公の乳母・春日局の発願により、大和国長谷寺(初瀬)小池坊より栄誉法印を招聘して開山しました。
栄誉法印は春日局の親族で、局は栄誉法印を猶子にしたといいます。
神田白壁町に堂宇を建立して薬師瑠璃光如来像を本尊に奉じ、金剛寶山 延壽寺 根生院を号しました。
春日局発願による徳川将軍家の祈願寺の創建につき、檀家のない寺院でした。
以降、徳川将軍家代々の祈願寺となり、正保二年(1645年)、下谷二長町に移転の際には江戸城西の丸祈願所として寺領250石を賜りました。
貞享四年(1687年)には、新義真言宗江戸四ヶ寺の一ヶ寺(触頭)となったといいます。
Wikipediaには触頭(ふれがしら)とは、「江戸時代に江戸幕府や藩の寺社奉行の下で各宗派ごとに任命された特定の寺院のこと。本山及びその他寺院との上申下達などの連絡を行い、地域内の寺院の統制を行った。」とあります。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏、PDF)によると、新義真言宗触頭江戸四箇寺は知足院(湯島~一ツ橋→大塚護持院)、真福寺(愛宕)、円福寺(愛宕)、彌勒寺(本所)で、元和八年(1622年)夏以前に成立の可能性が高いとしています。
「港区Web資料」には「新義真言宗の江戸触頭は江戸四箇寺と呼ばれ、本所弥勒寺・湯島知足院(後に湯島根生院)・円福寺・真福寺からなる。」とあり、『寺社書上』にも「根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候」とあるので、根生院は触頭の地位を貞享四年(1687年)に湯島知足院から承継したとみられます。
後に仁和寺光明院の院室を兼務して院家となり、歴代住職は代々幕命により任ぜられるなど、高い格式を有する名刹です。
根生院の歴史は移転の歴史といえるほど、移転をくり返しています。
その内容は山内掲示に詳しいので抜粋引用してみます。
-------------------------
寛永十二年(1636年)徳川幕府西の丸祈願所として、神田白壁町に建立
正保二年(1645年)下谷長者町へ移転
元禄元年(1688年)本郷切通坂知足院跡へ移転
明治22年(1889年)上野池端七軒町へ移転
明治36年(1903年)豊島郡高田、田安候旧邸(現在地)へ移転
-------------------------
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十五番
湯嶋切通し上
金剛宝山 延壽寺 根生院
新義 境内二千坪
本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [68] 湯嶋寺院書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.112』
本寺 山城国宇治郡報恩院
新義真言宗触頭
湯嶋 不唱小名
金剛寶山 延壽寺 根生院
寛永年中(1624-1644年)春日局吹挙にて下谷長者町御徒士組屋補割残し地三百六拾坪 開山栄誉寺地を拝領仕 当院御●主御祈願所に相成
大猷院様(徳川3代将軍家光公)
厳有院様(徳川4代将軍家綱公)
常憲院様(徳川5代将軍綱吉公)
清揚院様(徳川綱重公、徳川6代将軍家宣公の父、甲府宰相)
霊仙院様(徳川3代将軍家光公の長女、千代姫)
御祈願● 御座候
開山栄誉土州幡多縣の人なり 春日局御親族にて字文秀房● 父ハ秋葉(?)氏某なり 同縣石見の栄雅法印を師とし出家して和州初瀬山にて勤学● 然ルに春日局日頃栄誉●密に尋結(?)ふといへとも(略)或日知足院(今大塚護持院)第三世栄増法印に尋結(?)ふに栄誉●今大和國初瀬に勤学●●も 法類なりと云ふ 時に(春日)局密●栄増に託して栄誉●初瀬山より呼●して猶子と成し ●より大猷院様に願ひ奉り一寺造立仕御祈願所と● 抑●年月は不知
根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候
本堂俄建
本尊 薬師如来木像 立像秘佛 春日作
不動明王木像(此尊往昔常州筑波山の●水戸殿御領内に●真言宗の古寺の本尊を谷川に流し給ふ所 不思議なる哉(略)奇特に依て黄門公より本所彌勒寺乗應の方に送り納給ふ 依て●流不動と号し候由 然る所根性院第二世栄専代元禄十六年(1703年)十一月殿堂不残類焼の砌 護摩堂本尊不動明王焼失せり ●に依て此霊像●当院に●●安置す)
東照宮様御座像
文殊画像
本堂内に安置
弘法大師座像 御府内八十八ヶ所之内代三十五番ニ相定
鎮守稲荷社
享保十年(1725年)正月勧請 由来不知
根生院末寺七ヶ寺御座候
明王院(江府巣鴨) 西光院(江府中丸) 多宝院(江府谷中) 蓮乗院(四ッ谷南寺町) 玉藏院(武州二郷半領彦川戸村) 全性寺(上州新田郡大原村) 十方院(野州那須郡星之井村))
■ 『江戸名所図会 第3』(国立国会図書館)
延壽寺と号す。真言宗新義江戸四箇寺の一にして、寛永の始、御祈願所に命ぜらる。
本尊薬師如来は、佛工春日の作、脇壇に十二神将の像を置く。栄譽法印(春日局の猶子なり)をもって開山とす。

「根生院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「根生院」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2..国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
豊島区高田周辺には御府内霊場札所が4箇寺あり(29番南蔵院、35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺)、ふつうは4箇寺まとめての巡拝となります。
このあたりは土地の起伏が激しく、東京メトロ「雑司ヶ谷」駅からだと急な下り坂となります。
35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺は坂の途中にあり、南蔵院は神田川にもほど近い坂下に位置します。
カラフルな月替わり御朱印で有名な(高田)氷川神社にもほど近く、54番新長谷寺(目白不動尊)は江戸五色不動尊の一尊なので、一帯は御朱印エリアとなっています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
根生院は奥まった路地に面し、路地から少しく引いて山門を置き、路地側に板塀を巡らしてコの字状の門前となっています。
こういったさりげない配置にも寺格の高さが感じられます。
山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門(確証なし)。
門まわりは古色を帯びた朱塗りで趣きがあります。
門柱に年季の入った院号板。


【写真 上(左)】 門柱の院号札
【写真 下(右)】 御府内霊場札所標(門前)
門前に銀杏の古木と御府内霊場の札所碑。
右手に建つ青面金剛庚申塔と奉供養庚申天子の石碑は(旧)大榎一里塚から移転したものとみられ、ともに豊島区有形文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 庚申塔
【写真 下(右)】 山内
山門をくぐった山内は広くはないものの、名刹特有の落ち着きが感じられます。
「豊島区Web資料」には、「この地はもと尾張候の下屋敷であったものを田安家に譲り渡され(略)樹木あり、また清泉涌き出た幽境の地であり、宿坂より山門までの参道は欅の並木があり、山門の奥には満々たる水を湛えた池があり、四季折々を楽しませた。殊に菖蒲の頃は散策と参詣の人で賑わったと伝えられている。」とあります。
いまでは住宅街の一画となっていますが、往年は散策の名所としても知られ『江戸名所図会』にも挿絵が載せられています。
細い路地奥なので車通りがほとんどなく、あたりは日中でも静寂につつまれています。


【写真 上(左)】 手水鉢
【写真 下(右)】 本堂
参道右手の手水鉢に満たされた水は茶褐色の濁りを帯び、金気とギシギシとした手ざわりがありました。
温泉マニアの直感からすると(笑)、分析したら鉄分の項で温泉規定に乗るかもしれません。
参道正面階段上に本堂。
身舎ガラス面のシャープな近代建築で、屋根は寄棟、軒下向拝で見上げには院号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
昭和20年に戦火を受け山門を除いて焼失したものの、昭和28年境内地の一部に再建され、平成14年現在の堂宇に改築されています。
御本尊は薬師如来。
こちらも『江戸砂子』に掲載されているらしい「江戸薬師如来霊場三十二ヶ所」(出所:「ニッポンの霊場」様)の札所なので、江戸期から著名なお薬師様だったとみられます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 稲荷大明神
参道の片隅に祀られている稲荷大明神は、『寺社書上』に「鎮守稲荷社」とあるお社の系譜かもしれません。
山内には数体の露仏・石仏が御座します。


【写真 上(左)】 胎蔵(界)大日如来
【写真 下(右)】 薬師瑠璃光如来石仏
蓮座に結跏趺坐される石像の胎蔵(界)大日如来は、螺髪で法界定印を結ばれているため、説明書がなければ釈迦如来かと思われるお姿です。
金剛界大日如来は智挙印(ちけんいん/左手人差し指を立てその人差し指を右手で包み込む印相)なのですぐにわかりますが、胎蔵(界)大日如来は法界定印(左手手のひらに右手手のひらを重ね合わせ両親指先をつける印相)で、これは釈迦如来の禅定印と酷似しています。

■ 金剛界大日如来(常光院/埼玉県熊谷市)
ふつう胎蔵(界)大日如来は宝冠、瓔珞(ようらく)などの装身具を身に着けられていますが、如来様(薄衣の姿)の場合もあり、この場合の識別はなかなか困難です。
自然石に「所願成就 薬師瑠璃光如来」と刻まれた石仏は元禄十一年建立のもの。
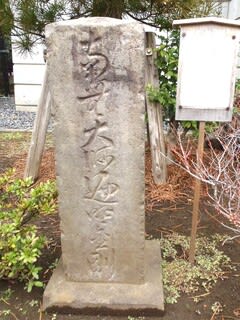

【写真 上(左)】 御府内霊場札所標(山内)
【写真 下(右)】 歌碑
「南無大師遍照金剛」の御宝号が刻まれた石碑は御府内霊場の札所碑でもあり、現地掲示によると願主・諦信は御府内霊場の開創、維持発展に寄与されたとのことです。
江戸時代の連歌歌人・無相の歌碑もあります。
山内の各所でみられる葵紋が、徳川将軍家とのゆかりをさりげに物語っています。


【写真 上(左)】 葵紋-1
【写真 下(右)】 葵紋-2
こぢんまりとした山内ながら新義真言宗触頭を担った格式が感じられ、名刹の矜持を感じとれる好ましいお寺さまでした。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内三十五番」の札所印。院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-12)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 君って - 西野カナ
コメント「流石実力派 もっとこういう人がテレビに出るべき」
御意。いつか復帰して、また名唱をとどけてほしい。
■ LOVE BRACE - 華原朋美 / 2013/11/25 LIVE @NHKホール
唯一無二のビブラート。圧倒的なオリジナリティ。
この人も、もっとメジャーに活躍してほしい。
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 / Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO
上位互換カバー不可の卓越したオリジナリティ。
いまの時代には稀少なフェミニンでたおやかな歌声。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第33番 醫王山 東光院 眞性寺
(しんしょうじ)
巣鴨地蔵通り商店街Web
豊島区巣鴨3-21-21
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第33番、豊島八十八ヶ所霊場第33番、江戸六地蔵第3番、北豊島三十三観音霊場第20番、九品佛霊場第1番、弁財天百社参り番外16、江戸・東京四十四閻魔参り第29番
司元別当:
授与所:寺務所
第33番は「おばあちゃんの原宿」とも呼ばれる巣鴨の名刹、眞性寺です。
第33番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに眞性寺なので、御府内霊場開創時から一貫して巣鴨の眞性寺であったとみられます。
下記史料、巣鴨地蔵通り商店街Web、現地掲示類を参照して縁起・沿革を追ってみます。
眞性寺の開創は不詳ながら、聖武天皇の勅願による行基菩薩の開基と伝わります。
中興開基は元和元年(1615年)祐遍法印によります。
元禄年中(1688-1704年)に田端村東覚寺末となり、盛辨法印が入院。
正徳元年(1711年)に東覚寺末を離れ、京御室御所(仁和寺)直末となっています。
御本尊は秘佛の薬師如来。
江戸時代より御府内霊場第33番札所・江戸六地蔵参り第3番として参詣者で賑わったといいます。
巣鴨は中山道の江戸への入口に当たる要衝で、ふるくから賑わいました。
眞性寺山内には芭蕉句碑も残っています。
~ 白露も こぼさぬ萩の うねりかな ~
また、徳川8代将軍吉宗公が放鷹の折に当寺を御膳所とされたなど、華々しい歴史が伝わります。
なにより江戸六地蔵の札所のひとつとして、参詣者を集めたといいます。
江戸六地蔵は、江戸市中の6箇所に造立された地蔵菩薩坐像を廻る地蔵尊霊場です。
江戸深川の地蔵坊正元が宝永三年(1706年)に発願し、江戸市中から寄進者を集めて江戸の出入口6箇所に丈六の銅造地蔵菩薩坐像を造立して開創されました。
地蔵坊正元とその両親が正元の病気平癒を地蔵菩薩に祈願したところ有り難くも快癒したため、京都六地蔵に倣っての開創と伝わります。
〔江戸六地蔵〕
第1番目(巡拝札第1番)
品川寺 旧東海道 品川区南品川
第2番目(巡拝札第4番)
東禅寺 奥州街道 台東区東浅草
第3番目(巡拝札第2番)
太宗寺 甲州街道 新宿区新宿
第4番目(巡拝札第3番)
眞性寺 旧中山道 豊島区巣鴨
第5番目(巡拝札第5番)
霊巌寺 水戸街道 江東区白河
第6番目(巡拝札第6番)
永代寺 千葉街道 江東区富岡
第6番目(代仏)
浄名院 江東区上野桜木
※永代寺以外は現存。浄名院の代仏については諸説あり
鋳造は神田鍋町の鋳物師・太田駿河守藤原正儀で、造立時には鍍金が施されたといいます。
金色に輝く大きな地蔵尊(おおむね像高2.5m以上)は、いずれも交通の要衝に置かれたこともあって多くの参詣者で賑わい、Wikipediaによると六体の像や蓮台に刻まれた寄進者の数は72,000名を超えるとのこと。
江戸期の多くの絵図に当山が描かれていることからも、城北の名所として広く親しまれたことがわかります。
元禄の頃から田端東覚寺の末寺でしたが、正徳元年(1711年)に京都御室御所仁和寺の末になったといいます。
明治33年には仁和寺末を離れ、真言宗豊山派総本山長谷寺の末寺となっていまに至ります。
〔関連記事〕
■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~
■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~
「江戸六地蔵」については、まだまとめておりません。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十三番
すがも中下町
醫王山 東光院 眞性寺
御直末
本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師
■『御府内寺社備考 P.6』
京都仁和寺末
巣鴨町増上寺領
醫王山 東光院 眞性寺
起立之儀相知不●-●元禄年中(1688-1704年)に本寺田端村東覚寺末ニ ●●十二年四月盛辨法印当寺に入院 正徳元年(1711年)に至り東覚寺離末 同年二月上京●時御室御所直末に御成(略)
中興開基 祐遍法印元和元年(1615年)当寺住職仕
本堂
本尊 薬師如来木坐像 行基菩薩作
鐘楼堂 大鐘
神明社
八幡宮社 八幡宮 愛宕 稲荷 相殿
阿弥陀堂 阿弥陀如来木座像 九品佛壱番目ニ御座候
閻魔堂 閻魔王坐像尺四尺
銅地蔵尊坐像壱丈六尺石壇 江戸六地蔵第三番目ニ御座候
御成門跡
■ 當國六地蔵造立之意趣(略記)(眞性寺山内掲示資料より)
抑 予十二歳のころ古郷を出で 十六歳にして剃髪受戒す 其後廿四歳の秋乃ころより重病を請け(略)醫術の叶難く死既に極まれり(略)父母是を悲 偏に地蔵菩薩に延命を祷奉る 自らも親の嘆骨髄に通 一心に地蔵菩薩に請願すへく我若菩薩の慈恩を蒙って父母存生の内命を延る事を得 尽未来に至まで衆生の為に菩薩の御利益を勧め多くの尊像を造立して衆生に帰依せしめ 共に安楽を得せしめんと誓 其夜不思議の霊験を得て重病速に本復す(略)帝都の六地蔵に周く御当地の入口毎に 一躰づつ金銅壱丈六尺の地蔵菩薩を六所に都合六躰造立して天下安全武運長久御城下繁栄を祝願し 兼而又諸国往来の一切衆生へ遍く縁を結ばしめんと誓(略)諸人往来の街に立てれば一切衆生皆悉く縁結び奉る 抑願し神明仏陀の加護を蒙りて六躰の尊像恙なく像立して万代の一切衆生と共に同じく善道に至らん事を
勧化沙門 深川 地蔵坊正元 謹言

「眞性寺」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「眞性寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
JR巣鴨駅北口界隈は、いつも年配者を中心に賑わいをみせています。
巣鴨にはふるくからとげぬき地蔵尊・高岩寺、江戸六地蔵第3番の眞性寺がありました。
高岩寺のとげぬき地蔵尊・洗い観音ともに病気平癒・延命に霊験あらたか、眞性寺の御本尊はお薬師様で、江戸六地蔵のお地蔵様も病気平癒のご利益で知られています。
健康・延命を願う年配者の参詣スポットとなり、その参詣客を狙って年配者向けのお店が増えていったというのが、巣鴨にお年寄りが多い理由とされます。


【写真 上(左)】 眞性寺前から商店街
【写真 下(右)】 巣鴨地蔵通り商店街


【写真 上(左)】 高岩寺
【写真 下(右)】 高岩寺の御朱印
中心の「巣鴨地蔵通り商店街」は坂道がなくバリアフリー完備で、お年寄りも安心して買い物やグルメを楽しめることも人気の理由とされています。
眞性寺はJR山手線「巣鴨」駅北口から徒歩約3分、都営三田線「巣鴨」駅からだと至近で便利がいいです。
巣鴨駅前を北上する国道17号(中仙道)から分岐する「巣鴨地蔵通り商店街」は旧中山道なので、「巣鴨地蔵通り商店街」の入口にある眞性寺はちょうど新旧中山道の分岐に面していることになります。
中山道側からは奥行きのある参道を構え、参道脇に並ぶ提灯が人々の篤い信仰を物語っています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
参道正面に江戸六地蔵の地蔵尊坐像とそのおくに本堂がみえます。
参道右手の建物は阿弥陀堂で、九品佛霊場第1番の拝所。
江戸・東京四十四閻魔参り第29番の閻魔大王もこちらに御座します。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂と本堂
【写真 下(右)】 芭蕉句碑
江戸六地蔵尊の向かって左手に山門があり、山号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の扁額


【写真 上(左)】 江戸六地蔵札所標
【写真 下(右)】 地蔵尊と本堂
江戸六地蔵の地蔵尊は蓮座に趺座され像高さ2.68m、蓮花台を含めると3.45mにも及ぶ大きな坐像で、東京都指定有形文化財に指定されています。
日々多くの参詣者を集め、あたりは線香のけむりがたなびいています。


【写真 上(左)】 地蔵尊
【写真 下(右)】 陰光地蔵尊碑
毎年6月24日夕刻に行われる百万遍大念珠供養は、全長16m、541の桜材の珠からなる大念珠を念仏を唱えつつ500~600名で廻して供養するもので、巣鴨の梅雨の風物詩として知られています。
地蔵尊前には「江戸六地蔵三番目」の札所碑と「陰光地蔵尊」の碑が建っています。
この「陰光地蔵尊」の碑文には、百万遍大念珠供養の音頭取りを父子併せて実に八十年間務めた繪馬屋 征矢父子の功徳を賞して「陰光地蔵尊」と尊号し、御信心を新たにすることが刻されています。


【写真 上(左)】 地蔵尊立像
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
六地蔵の地蔵尊の向かって左手堂宇内には地蔵尊立像が御座します。
子供を抱えられているので子安地蔵尊かもしれません。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂扁額
【写真 下(右)】 阿弥陀如来像
参道向かって右手には近代建築の阿弥陀堂。
眞性寺は『江戸砂子拾遺』『拾遺続江戸砂子』などに収録されている「九品佛霊場」の第1番札所(上品上生)です。
上品上生の阿弥陀如来の印相はふつうは来迎印ですが、こちらの阿弥陀様は施無畏印・与願印です。


【写真 上(左)】 九体の阿弥陀佛
【写真 下(右)】 初閻魔の阿弥陀堂
こちらの堂宇本尊の阿弥陀様が「九品佛霊場」(→札所リスト(「ニッポンの霊場」様))の第1番の御像とも思われますが、印相は施無畏印・与願印。
阿弥陀如来の印相は施無畏印・与願印、転法輪印(説法印)、阿弥陀定印、来迎印と多彩かつ複雑なので、印相からみてこちらが九品佛霊場の札所本尊かどうかはよくわかりません。
堂内に来迎印(上品上生印)を結ばれた九体の阿弥陀木坐像が御座し、『御府内寺社備考』には「阿弥陀堂 阿弥陀如来木座像 九品佛壱番目ニ御座候」とあるので、こちらが九品佛霊場の札所本尊とみるのが自然かもしれません。


【写真 上(左)】 閻魔大王と奪衣婆
【写真 下(右)】 初閻魔の閻魔大王
堂内向かって右手に御座す閻魔大王はおそらく江戸・東京四十四閻魔参り第29番の札所本尊で、常時間近でお参りできます。
閻魔様の御朱印も拝受していますが、こちらはご縁日限定かもしれません。
令和5年秋時点で阿弥陀堂改築の予定で、すでに普請工事に入っています。
閻魔様も新堂にご遷座の予定で、閻魔様の前には新たに奪衣婆がお出ましになっていました。


【写真 上(左)】 地蔵尊と本堂
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
階段上の本堂は重層屋根のうえに相輪を備えた堂々たる構えですが、様式はよくわかりません。
下層屋根の唐破風が向拝雨よけとなっていますが、向拝柱はなく比較的シンプル。
本堂内陣見上げにも山号扁額が掲げられ、向かって右手には百万遍大念珠が安置されています。
御本尊のお薬師様は絶対秘仏なので、正面お厨子前に御座す薬師如来坐像は御前立ちかと思われます。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所標
【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑


【写真 上(左)】 修行大師像
【写真 下(右)】 観世音菩薩立像
本堂向かって右手が寺務所で、その前には修行大師像と石仏の観世音菩薩立像が御座します。
眞性寺は北豊島三十三観音霊場第20番の札所(→ 札所一覧(「ニッポンの霊場」様))ですが、この霊場はすこぶる情報が少なく、この観世音菩薩像が札所本尊であるかは定かではありません。
御朱印は寺務所で拝受。
ご対応はいつお伺いしてもたいへんにご親切で、頭が下がります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
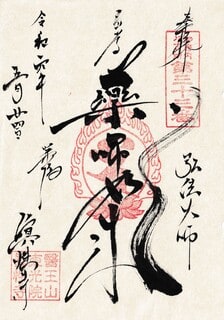

【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八所第三十三番」の札所印。寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 江戸六地蔵の御朱印


【写真 上(左)】 閻魔大王のご縁日の御朱印
【写真 下(右)】 九品佛霊場
閻魔様の御朱印授与は、ご縁日限定かもしれません。
九品佛霊場の御朱印については、巡拝者もきわめて少なく通常は授与されていないとのことでしたが、ご厚意で授与いただけました。
「九品佛第壱番」「上品上生」の揮毫をいただいた稀少な御朱印です。
■ 第34番 薬王山 遍照院 三念寺
(さんねんじ)
文京区本郷2-15-6
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第34番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所
司元別当:
授与所:寺務所
第34番は本郷にある真言宗の古刹です。
第34番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに三念寺なので、御府内霊場開創時から一貫して本郷の三念寺であったとみられます。
下記史料から縁起・沿革を追ってみます。
開創・開基は不明ですが、文明年中(1469-1487年)一人の修行者が一宇の草堂を結び遍照院と号したといいます。
慈覺大師真作の大日如来を安置し恭敬されたとも。
御本尊の薬師如来は、恵心僧都の母公が病に罹ったときに恵心僧都みずからが彫刻されたといいます。
一時期三州の鳳来寺に移り、慶長年中(1596-1615年)に当山に奉安、堂舎を整えて醫王山 三念寺と号したともいいます。
中興開山は法印品隆(文禄二年(1593年)卒)と伝わります。
往古は土手四番町にありましたが、元禄(1688-1704年)の頃当地へ移転ともいいます。
「千代田区観光協会Web」の千代田区五番町の三年坂の説明に「『新撰東京名所図会』に「三年坂は現今通称する所なるも、三念寺坂といふを正しとす。むかし三念寺といへる寺地なりしに因り此名あり。」とあります。」とあるので、土手四番町は現在の千代田区五番町あたりと推測されます。
『江戸砂子』に掲載されているらしい「江戸薬師如来霊場三十二ヶ所」(出所:「ニッポンの霊場」様)の札所なので、江戸期から著名なお薬師様だったとみられます。
なお、『寺社書上』『御府内寺社備考』には、本堂御本尊は大日如来、薬師堂に薬師如来とあり、寺院としては両尊御本尊だったのかもしれませんが、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所本尊として薬師如来 弘法大師 興教大師が記されているので、お薬師さまのお寺のイメージが強かったのではないでしょうか。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十四番
本郷元町
薬王山 遍照院 三念寺
本所彌勒寺末 新義
本尊:薬師如来 弘法大師 興教大師
本尊薬師如来恵心僧都の御作なり
■ 『寺社書上 [71] 本郷寺社書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.105』
本所彌勒寺末
本郷御弓町
薬王山 遍照院 三念寺
開闢・開基 未分明
中興開山 法印品隆(文禄二年(1593年)卒)
本堂
本尊 大日如来木座像
阿弥陀如来 地蔵菩薩 弘法大師 興教大師
薬師堂
薬師如来木像 恵心僧都作之由
十二神将木像 同
日光菩薩木像 月光菩薩 同
各像 前立
■ 『本郷区史』(文京区立図書館Web)
元町二丁目に在り、本所弥勒寺末、薬王山遍照院と号す。『江砂餘礫』には当寺古く土手四番町に在り、元禄(1688-1704年)の比元町へ移さるとあるが、文政書上には慶長八年(1603年)当地拝領と記して居る。

「三念寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本郷湯島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC
-------------------------
メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅の南(徒歩約5分)、東京都水道歴史館のすぐ北側で、都内に住んでいてもなかなか訪れないところです。
壱岐坂通りから一本南の路地に面したビル内の寺院です。
このあたりの江戸期の地名は御弓町(のちに本郷元町)。
「坂学会Web」に「この坂(本郷の新坂)の一帯は,もと御弓町(おゆみちょう),その後,弓町と呼ばれ,慶長・元和の頃(1600年ごろ) 御弓町の与力同心六組の屋敷がおかれ,的場で弓の稽古が行われた。」とあります。
『江戸切絵図』をみても、三念寺周辺には区画の狭い武家屋敷や「御中間」が多く、この地が与力同心や中間(武家の奉公人)層の居住エリアであったことがわかります。


【写真 上(左)】 外観
【写真 下(右)】 エントランス
2016年春に初参拝したときの写真が行方不明になってしまい、2019年夏(建物改装中でメッシュシートで覆われていた)の写真しかなく詳細不明です。


【写真 上(左)】 六地蔵尊とエントランス
【写真 下(右)】 六地蔵尊
Web検索してみると、白い外壁のなかなか瀟洒なビルで2階が本堂とみられ、2階正面に山号扁額が掲げられています。
ビル前面に六地蔵尊を奉安し、寺号標もあるので寺院であることはすぐにわかります。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 扉を開けると正面が拝所
本堂は2階ですが、御府内霊場の奉拝は1階正面の拝所にておこないます。
正面が坐像の薬師如来とおくに釈迦三尊の掛け軸。
薬師如来の左右に弘法大師と興教大師の坐像が御座します。
ベルを押さないとビル内に入れないので、ベルでお呼びして御府内霊場巡拝を申告、御朱印をご準備いただくあいだに勤行という流れになります。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「薬師如来」「弘法大師」と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫、主印は「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八所」「第三十四番」の札所印。寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第35番 金剛寶山 延壽寺 根生院
(こんしょういん)
豊島区高田1-34-6
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第35番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所
司元別当:
授与所:庫裡
第35番は豊島区高田にある真言宗の名刹です。
第35番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに根生院なので、御府内霊場開創時から一貫して根生院であったとみられます。
ただし、『御府内八十八ケ所道しるべ』での所在は「湯嶋切通し上」となっています。
下記史料、「豊島区Web資料」、現地掲示類から縁起・沿革を追ってみます。
創建は寛永十三年(1636年)、徳川3代将軍家光公の乳母・春日局の発願により、大和国長谷寺(初瀬)小池坊より栄誉法印を招聘して開山しました。
栄誉法印は春日局の親族で、局は栄誉法印を猶子にしたといいます。
神田白壁町に堂宇を建立して薬師瑠璃光如来像を本尊に奉じ、金剛寶山 延壽寺 根生院を号しました。
春日局発願による徳川将軍家の祈願寺の創建につき、檀家のない寺院でした。
以降、徳川将軍家代々の祈願寺となり、正保二年(1645年)、下谷二長町に移転の際には江戸城西の丸祈願所として寺領250石を賜りました。
貞享四年(1687年)には、新義真言宗江戸四ヶ寺の一ヶ寺(触頭)となったといいます。
Wikipediaには触頭(ふれがしら)とは、「江戸時代に江戸幕府や藩の寺社奉行の下で各宗派ごとに任命された特定の寺院のこと。本山及びその他寺院との上申下達などの連絡を行い、地域内の寺院の統制を行った。」とあります。
『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏、PDF)によると、新義真言宗触頭江戸四箇寺は知足院(湯島~一ツ橋→大塚護持院)、真福寺(愛宕)、円福寺(愛宕)、彌勒寺(本所)で、元和八年(1622年)夏以前に成立の可能性が高いとしています。
「港区Web資料」には「新義真言宗の江戸触頭は江戸四箇寺と呼ばれ、本所弥勒寺・湯島知足院(後に湯島根生院)・円福寺・真福寺からなる。」とあり、『寺社書上』にも「根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候」とあるので、根生院は触頭の地位を貞享四年(1687年)に湯島知足院から承継したとみられます。
後に仁和寺光明院の院室を兼務して院家となり、歴代住職は代々幕命により任ぜられるなど、高い格式を有する名刹です。
根生院の歴史は移転の歴史といえるほど、移転をくり返しています。
その内容は山内掲示に詳しいので抜粋引用してみます。
-------------------------
寛永十二年(1636年)徳川幕府西の丸祈願所として、神田白壁町に建立
正保二年(1645年)下谷長者町へ移転
元禄元年(1688年)本郷切通坂知足院跡へ移転
明治22年(1889年)上野池端七軒町へ移転
明治36年(1903年)豊島郡高田、田安候旧邸(現在地)へ移転
-------------------------
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十五番
湯嶋切通し上
金剛宝山 延壽寺 根生院
新義 境内二千坪
本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [68] 湯嶋寺院書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.112』
本寺 山城国宇治郡報恩院
新義真言宗触頭
湯嶋 不唱小名
金剛寶山 延壽寺 根生院
寛永年中(1624-1644年)春日局吹挙にて下谷長者町御徒士組屋補割残し地三百六拾坪 開山栄誉寺地を拝領仕 当院御●主御祈願所に相成
大猷院様(徳川3代将軍家光公)
厳有院様(徳川4代将軍家綱公)
常憲院様(徳川5代将軍綱吉公)
清揚院様(徳川綱重公、徳川6代将軍家宣公の父、甲府宰相)
霊仙院様(徳川3代将軍家光公の長女、千代姫)
御祈願● 御座候
開山栄誉土州幡多縣の人なり 春日局御親族にて字文秀房● 父ハ秋葉(?)氏某なり 同縣石見の栄雅法印を師とし出家して和州初瀬山にて勤学● 然ルに春日局日頃栄誉●密に尋結(?)ふといへとも(略)或日知足院(今大塚護持院)第三世栄増法印に尋結(?)ふに栄誉●今大和國初瀬に勤学●●も 法類なりと云ふ 時に(春日)局密●栄増に託して栄誉●初瀬山より呼●して猶子と成し ●より大猷院様に願ひ奉り一寺造立仕御祈願所と● 抑●年月は不知
根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候
本堂俄建
本尊 薬師如来木像 立像秘佛 春日作
不動明王木像(此尊往昔常州筑波山の●水戸殿御領内に●真言宗の古寺の本尊を谷川に流し給ふ所 不思議なる哉(略)奇特に依て黄門公より本所彌勒寺乗應の方に送り納給ふ 依て●流不動と号し候由 然る所根性院第二世栄専代元禄十六年(1703年)十一月殿堂不残類焼の砌 護摩堂本尊不動明王焼失せり ●に依て此霊像●当院に●●安置す)
東照宮様御座像
文殊画像
本堂内に安置
弘法大師座像 御府内八十八ヶ所之内代三十五番ニ相定
鎮守稲荷社
享保十年(1725年)正月勧請 由来不知
根生院末寺七ヶ寺御座候
明王院(江府巣鴨) 西光院(江府中丸) 多宝院(江府谷中) 蓮乗院(四ッ谷南寺町) 玉藏院(武州二郷半領彦川戸村) 全性寺(上州新田郡大原村) 十方院(野州那須郡星之井村))
■ 『江戸名所図会 第3』(国立国会図書館)
延壽寺と号す。真言宗新義江戸四箇寺の一にして、寛永の始、御祈願所に命ぜらる。
本尊薬師如来は、佛工春日の作、脇壇に十二神将の像を置く。栄譽法印(春日局の猶子なり)をもって開山とす。

「根生院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「根生院」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2..国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
豊島区高田周辺には御府内霊場札所が4箇寺あり(29番南蔵院、35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺)、ふつうは4箇寺まとめての巡拝となります。
このあたりは土地の起伏が激しく、東京メトロ「雑司ヶ谷」駅からだと急な下り坂となります。
35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺は坂の途中にあり、南蔵院は神田川にもほど近い坂下に位置します。
カラフルな月替わり御朱印で有名な(高田)氷川神社にもほど近く、54番新長谷寺(目白不動尊)は江戸五色不動尊の一尊なので、一帯は御朱印エリアとなっています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 山門
根生院は奥まった路地に面し、路地から少しく引いて山門を置き、路地側に板塀を巡らしてコの字状の門前となっています。
こういったさりげない配置にも寺格の高さが感じられます。
山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門(確証なし)。
門まわりは古色を帯びた朱塗りで趣きがあります。
門柱に年季の入った院号板。


【写真 上(左)】 門柱の院号札
【写真 下(右)】 御府内霊場札所標(門前)
門前に銀杏の古木と御府内霊場の札所碑。
右手に建つ青面金剛庚申塔と奉供養庚申天子の石碑は(旧)大榎一里塚から移転したものとみられ、ともに豊島区有形文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 庚申塔
【写真 下(右)】 山内
山門をくぐった山内は広くはないものの、名刹特有の落ち着きが感じられます。
「豊島区Web資料」には、「この地はもと尾張候の下屋敷であったものを田安家に譲り渡され(略)樹木あり、また清泉涌き出た幽境の地であり、宿坂より山門までの参道は欅の並木があり、山門の奥には満々たる水を湛えた池があり、四季折々を楽しませた。殊に菖蒲の頃は散策と参詣の人で賑わったと伝えられている。」とあります。
いまでは住宅街の一画となっていますが、往年は散策の名所としても知られ『江戸名所図会』にも挿絵が載せられています。
細い路地奥なので車通りがほとんどなく、あたりは日中でも静寂につつまれています。


【写真 上(左)】 手水鉢
【写真 下(右)】 本堂
参道右手の手水鉢に満たされた水は茶褐色の濁りを帯び、金気とギシギシとした手ざわりがありました。
温泉マニアの直感からすると(笑)、分析したら鉄分の項で温泉規定に乗るかもしれません。
参道正面階段上に本堂。
身舎ガラス面のシャープな近代建築で、屋根は寄棟、軒下向拝で見上げには院号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 向拝
昭和20年に戦火を受け山門を除いて焼失したものの、昭和28年境内地の一部に再建され、平成14年現在の堂宇に改築されています。
御本尊は薬師如来。
こちらも『江戸砂子』に掲載されているらしい「江戸薬師如来霊場三十二ヶ所」(出所:「ニッポンの霊場」様)の札所なので、江戸期から著名なお薬師様だったとみられます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 稲荷大明神
参道の片隅に祀られている稲荷大明神は、『寺社書上』に「鎮守稲荷社」とあるお社の系譜かもしれません。
山内には数体の露仏・石仏が御座します。


【写真 上(左)】 胎蔵(界)大日如来
【写真 下(右)】 薬師瑠璃光如来石仏
蓮座に結跏趺坐される石像の胎蔵(界)大日如来は、螺髪で法界定印を結ばれているため、説明書がなければ釈迦如来かと思われるお姿です。
金剛界大日如来は智挙印(ちけんいん/左手人差し指を立てその人差し指を右手で包み込む印相)なのですぐにわかりますが、胎蔵(界)大日如来は法界定印(左手手のひらに右手手のひらを重ね合わせ両親指先をつける印相)で、これは釈迦如来の禅定印と酷似しています。

■ 金剛界大日如来(常光院/埼玉県熊谷市)
ふつう胎蔵(界)大日如来は宝冠、瓔珞(ようらく)などの装身具を身に着けられていますが、如来様(薄衣の姿)の場合もあり、この場合の識別はなかなか困難です。
自然石に「所願成就 薬師瑠璃光如来」と刻まれた石仏は元禄十一年建立のもの。
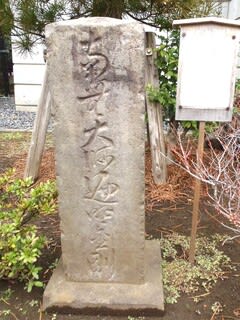

【写真 上(左)】 御府内霊場札所標(山内)
【写真 下(右)】 歌碑
「南無大師遍照金剛」の御宝号が刻まれた石碑は御府内霊場の札所碑でもあり、現地掲示によると願主・諦信は御府内霊場の開創、維持発展に寄与されたとのことです。
江戸時代の連歌歌人・無相の歌碑もあります。
山内の各所でみられる葵紋が、徳川将軍家とのゆかりをさりげに物語っています。


【写真 上(左)】 葵紋-1
【写真 下(右)】 葵紋-2
こぢんまりとした山内ながら新義真言宗触頭を担った格式が感じられ、名刹の矜持を感じとれる好ましいお寺さまでした。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内三十五番」の札所印。院号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-12)
■ 札所リスト・目次など
→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1
【 BGM 】
■ 君って - 西野カナ
コメント「流石実力派 もっとこういう人がテレビに出るべき」
御意。いつか復帰して、また名唱をとどけてほしい。
■ LOVE BRACE - 華原朋美 / 2013/11/25 LIVE @NHKホール
唯一無二のビブラート。圧倒的なオリジナリティ。
この人も、もっとメジャーに活躍してほしい。
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 / Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO
上位互換カバー不可の卓越したオリジナリティ。
いまの時代には稀少なフェミニンでたおやかな歌声。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-10
Vol.-9からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第30番 光松山 威盛院 放生寺
(ほうじょうじ)
公式Web
新宿区西早稲田2-1-14
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第30番、江戸三十三観音札所第15番、大東京百観音霊場第19番、山の手三十三観音霊場第16番、九品仏霊場第7番
司元別当:高田穴八幡宮
授与所:寺務所ないし本堂内
第30番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ 』、江戸八十八ヶ所霊場ともに放生寺なので、御府内霊場開創時から一貫して早稲田の放生寺であったとみられます。
縁起・沿革は公式Web、現地掲示に詳しいので、こちらと下記史料を参照してまとめてみます。
放生寺は寛永十八年(1641年)、威盛院権大僧都法印良昌上人が高田八幡(穴八幡宮)の造営に尽力され、その別当寺として開創されました。
良昌上人は周防國の生まれで十九歳の年遁世して高野山に登り、寶性院の法印春山の弟子となり修行をとげられ、三十一歳の頃より諸國修行されて様々な奇特をあらわされたといいます。
寛永十六年(1639年)二月、陸奥国尾上八幡に参籠の夜、霊夢に老翁があらわれ「将軍家の若君が辛巳の年の夏頃御降誕あり、汝祈念せよ」と告げられました。
上人は直ちに堂宇に籠もり、無事御生誕の大願成就行を厳修されました。
寛永十八年(1641年)当地に止錫の折、御弓組の長松平新五左衛門尉源直次の組の者の請を受け、穴八幡宮の別当職に就かれました。
同年の八月三日、草庵を結ぶため山裾を切り闢くと霊窟があり(現在の穴八幡宮出現殿付近)、窟の中には金銅の下品上生阿彌陀如来が立たれていました。
この阿彌陀如来像は八幡宮の御本地で、良昌上人はこの尊像を手篤く奉安。
「穴八幡宮」の号はこの霊窟に由来といいます。
おりしも、この日に将軍家御令嗣・厳有公(竹千代君、4代将軍家綱公)の御誕生があったため、以前から「将軍家若君、辛巳の年の夏頃無事御降誕の行厳修」の譚を聞いていた人々は、その霊威を新たにしたとのことです。
良昌上人が霊夢でみられた「将軍家の若君」は家光公とする資料もありますが、霊夢は寛永十六年(1639年)、家光公の御生誕は慶長九年(1604年)ですから年代が合いません。
家光公嫡男の竹千代君(4代将軍家綱公)は寛永十八年(1641年)八月の御生誕で、この年は辛巳ですから、おそらく良昌上人は竹千代君御生誕の成就祈願行を2年前に厳修したことになります。
『江戸名所図会』にも、「厳有公 御誕生」と明記されています。
なお、穴八幡宮の公式Webによると、高田八幡(穴八幡宮)は「康平五年(1062年)、奥州の乱を鎮圧した八幡太郎源義家公が凱旋の折、日本武尊命の先蹤に習ってこの地に兜と太刀を納めて氏神八幡宮を勧請」とあるので、良昌上人来所以前の創祀とみられます。
『江戸名所図会』には、寛永十三年(1636年)、御弓組の長松平新五左衛門尉源直次の与力の輩が、射術練習のためこの地に的山を築立てた際、弓箭の守護神である八幡神を勧請とあります。
以上から、八幡宮は良昌上人来所(寛永十八年(1641年))以前に当地に勧請されており、良昌上人は同年、霊窟から金銅の御神像(あるいは阿彌陀佛)を得て穴八幡宮と号したことなどでの貢献とみるべきでしょうか。
当地に古松があって山鳩が遊ぶ神木とされ、あるいは暗夜に瑞光を放つことから霊松ともされて、光松山の号はこの松に由来といいます。
慶安二年(1649年)、大猶院殿(徳川家光公)が御放鷹の折に穴八幡宮を訪れ、良昌上人より件の霊夢や大願成就の厳修について聞き及ぶと、「威盛院光松山放生會寺」の号を賜り、以降、別当・放生寺を御放鷹の御膳所とするなど篤く外護しました。
厳有院(4代将軍・家綱公)生誕の霊夢譚、そして家綱公生誕の当日に高田八幡の御本地・金銅阿彌陀佛の降臨とあっては、将軍家としてもなおざりにはできなかったと思われます。
歴代の徳川将軍家の尊崇は、『江戸名所図会』に穴八幡宮の什寶としてつぎのとおり記されていることからもうかがえます。
・台徳院(2代将軍・秀忠公) 御筆、御自賛の和歌
・大猶院(3代将軍・家光公) 賜物の扇子 一握
・常憲院(5代将軍・綱吉公) 御筆の福禄壽御画 一幅
元禄年間(1688-1704年)には宮居の造営あって結構を整えたといい、とくに元禄十六年(1703年)の造営は江戸権現造り社殿として壮麗を極めたといいます。
爾来、将軍家の尊崇篤く、徳川家代々の祈願寺として葵の紋を寺紋に、また江戸城登城の際には寺格から独礼登城三色(緋色、紫色、鳶色)衣の着用を許されたとも。
穴八幡宮の祭礼の八月十五日には放生會で賑わいをみせたといい、現在の放生寺の放生会はその系譜にあるとみられます。
「放生會(ほうじょうえ)」とは、捕らえられた魚介、鳥、動物などを殺生せずに池、川や山林に放す法事で、養老四年(720年)宇佐八幡宮で行われた放生會が発祥ともされることから、八幡宮社・八幡社で多く催されます。
江戸期の放生寺は穴八幡宮別当としてその地位を固め、一帯は神仏習合の一大霊場として栄えたことは、『江戸名所図会』の挿絵からもうかがえます。
しかし、穴八幡宮とこれだけ強固な神仏習合関係を築きながら、明治初期の神仏分離で放生寺が廃されなかったのはある意味おどろきです。
そのカギはひょっとして別当寺と神宮寺の別にあるのかもしれません。
放生寺の公式Webに唐突ともいえるかたちで、以下の説明が記載されています。
-------------------------
別当寺 べっとうじ
神宮寺の一種。神社境内に建てられ、別当が止住し、読経・祭祀・加持祈祷とともに神社の経営管理を行なった寺。
神宮寺 じんぐうじ
神社に付属して建てられた寺院。神仏習合思想の現れで、社僧(別当)が神社の祭祀を仏式で挙行した。1868年(明治1)の神仏分離令により廃絶または分離。宮寺。別当寺。神護寺。神宮院。神願寺。
-------------------------
明治の神仏分離で廃絶されたのは「神宮寺」で、「別当寺」は神宮寺の一種ながら廃絶を免れたと読めなくもありません。
(別当寺の説明で「神仏習合」ということばを用いていない。)
神宮寺と別当寺の別は、わが国の神仏習合を語るうえで避けてとおれない重要な事柄ですが、すこぶるデリケートかつ複雑な内容を含むので、ここではこれ以上触れません。
ひとつ気になるのは、『御府内八十八ケ所道しるべ 』では放生寺の御本尊は阿弥陀如来(穴八幡宮の御本地)となっているのに、現在の御本尊は聖観世音菩薩(融通虫封観世音菩薩)であることです。
この点について、現地掲示には「代々の(放生寺)住職が社僧として寺社一山の法務を司っておりましたが、明治二年、当山十六世実行上人の代、廃仏毀釈の布告に依り、境内を分割し現今の地に本尊聖観世音菩薩が遷されました。」とあります。
放生寺は明治二年に現在地に伽藍を遷し、そのときに聖観世音菩薩を御本尊とされたのでは。
以前の御本尊?の阿弥陀如来は、江戸時代に九品仏霊場第7番(下品上生)に定められた著名な阿弥陀様です。
(九品仏霊場の札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様))
一方、放生寺は江戸期から複数の観音霊場の札所で、観音様(おそらく融通虫封観世音菩薩)の信仰の場でもありました。
あるいは八幡宮との習合関係のうすい聖観世音菩薩を御本尊とすることで、神宮寺の性格(御本地が御本尊)をよわめたのかもしれません。
ともあれ御府内霊場第30番札所の放生寺は、明治初期の廃仏毀釈の波を乗り切って存続しました。
現在も高野山真言宗準別格本山の高い格式を保ち、複数の霊場札所を兼務されて多くの参拝客を迎えています。
放生寺と穴八幡宮は現在はそれぞれ独立した寺社ですが、いずれも「一陽来福」「一陽来復」ゆかりの寺社として知られています。
「一陽来福」(「一陽来復」)とは冬至をあらわす中国の易経の言葉で、「陰極まって一陽を生ずる」の意とされます。
「一陽と共に福もかえり来る」、来る年も福がまた訪れますように、との祈念を込めて参詣し、「一陽来福」(「一陽来復」)のお札をいただいて、冬至、大晦日、節分の深夜に恵方(「明の方」、歳徳神のおわす方角)に向けて貼るといいます。
放生寺の「一陽来福」は、御本尊・聖観世音菩薩ゆかりの「観音経の結びの「福聚海無量」=福聚(あつ)むること海の如く無量なり と言う偈文より「福」の字を取り「一陽来福」と名付けられました。」とのこと。(当山Webより)
御本尊・聖観世音菩薩は古来より融通・虫封観世音と呼ばれ、「融通=滞りなく通じる」から商家はもとより円満な人間関係(融通円満)の祈願本尊として信仰を集めており、冬至、大晦日、節分には「一陽来福」「融通」「虫封」を祈念する参詣者でことに賑わいをみせます。
一方、穴八幡宮の「一陽来復」は公式Webによると「福神(打出小槌)」に由来するものです。
『新編武蔵風土記稿』には、聖武天皇の御代に公家の水無瀬家の息女が感得されたもので、祈願の趣を掌に書き、この小槌でその掌を打てば所願成就とあります。
穴八幡宮公式Webには「公家の水無瀬家が山城国国宝寺より感得したものを当社に納めたもので、聖武天皇が養老七年の冬至の日に龍神により授けられた宝器」とあります。
穴八幡宮の「一陽来復御守」は江戸中期から冬至の福神祭に授与された歴史あるもので、「金銀融通の御守」とも呼ばれて、授与時には多くの参詣客で賑わいます。
なお、穴八幡宮の御朱印は「一陽来復」が揮毫される貴重なものですが、冬至から節分にかけては授与されておりません。

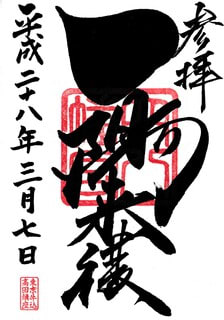
【写真 上(左)】 穴八幡宮の社頭
【写真 下(右)】 穴八幡宮の御朱印
-------------------------
【史料】 ※なぜか『寺社書上』『御府内寺社備考』には記載がありません。
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十番
高田穴八まん
光松山 威盛院 放生會寺
高野山宝性院末 古義
本尊:阿弥陀如来 本社八幡宮 弘法大師
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(下戸塚村(穴)八幡社)別当放生會寺
古義真言宗、高野山寶性院末、光松山威盛院ト号ス 本尊不動を安ス 開山良昌ハ周防國ノ産ニテ 俗称ハ榎本氏 高野山寶性院青山ニ投ジテ薙染シ 諸國ヲ経歴シテ 寛永十六年(1616年)陸奥國尾上八幡ニ参籠ノ夜 将軍家若君辛巳年夏ノ頃御降誕アルヘキ由霊夢ヲ得タリ 其後当國ニ来リ シルヘノ僧室ニ暫ク錫ヲ止メシニ 同十八年(1618年)松平新五左衛門カ組ノ者ノ請ニ任セ当社((穴)八幡社)ノ別当職トナレリ 此年(寛永十八年(1641年))厳有院殿御降誕マシ々々 カノ霊堂ニ符合セリ 此事イツトナク上聞くニ達セシカハ 大猶院殿御放鷹ノ時当山ニ御立寄アリテ 良昌ヲ召サセラレ社ノ由緒ヲ聞シメサレ 光松山放生會寺ノ号ヲ賜ハレリト云 是ヨリ以来此邊御遊猟ノ時ハ 当寺ヲ御膳所ニ命セラレテ今ニ然リ
什寶
柳ニ竹ノ御書一幅 台徳院殿ノ御筆ト云 御自賛ノ和歌アリ
柳チル カタ岡ノヘノ秋風ニ 一ツフタツノ家ニカクルヽ
扇子一握 大猶院殿ノ賜物ニテ開山良昌拝領す、便面ス便面ニ御筆ノ詩歌アリ
飛鳥去邊山侶眉 空低水潤影遅遅 上林雖好非栖處 一任千枝與萬枝
雁カヘル常世ノ花ノイカナレヤ 月ハイヅクモ霞ム春ノヨ
福禄壽御画一幅 常憲院殿ノ御筆ナリ 落款ニ御諱アリ
楊柳観音画像一幅
百體大黒天画像一幅
(略)
不動愛染ノ画像各幅 弘法大師筆
心経一巻 同筆。
十六善神画像一幅
(略)
打出小槌 由来記一巻アリ其略ニ
此槌●紳家水無瀬家ノ女感得セシ所也 昔聖武天皇ノ此ノ如キ寶物ヲ山城國●原ノ一宇ニ御寄納アリシカハ 彼寺ヲ寶寺ト号ス 信心ノ男女祈願ノ意趣ヲ掌ニ書シテ 此槌モテソノ掌ヲ打テハ所願成就スト云
(略)
寺中 松済院 光済院 是ハ廃院トナリテ末再建ニ及ハス
■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)〔要旨抜粋〕
高田八幡宮 穴八幡
牛込の総鎮守 別当は真言宗光松山 放生會寺
祭礼は八月十五日にて、放生會あり
寛永十三年(1636年)御弓組の長松平新五左衛門尉源直次に与力の輩、射術練習の為、其地に的山を築立てらる。
八幡宮は源家の宗廟にして而も弓箭の守護神なればとて、此地に勧請せん事を謀る。
此山に素より古松二株あり。其頃山鳩来つて、日々に此松の枝上に遊ぶを以て、霊瑞とし、仮に八幡大神の小祠を営みて、件の松樹を神木とす。此地昔は阿彌陀山と呼び来りしとなり。
(略)
寛永十八年(1641年)の夏、中野寶仙寺秀雄法印の會下に、威盛院良昌といえる沙門あり。周防國の産にして、山口八幡の氏人なり。十九歳の年遁世して、高野山に登り、寶性院の法印春山の弟子となり、一紀の行法をとげて、三十一の時より、諸國修行の志をおこし、其聞さまざまの奇特をあらはせりといふ。依てこの沙門を迎へて、社僧たらしむ。
同年の秋八月三日、草庵を結ばんとして、山の腰を切り闢く時に、ひとつの霊窟を得たり。
その窟の中石上に、金銅の阿彌陀の霊像一軀たたせ給へり。八幡宮の本地にて、しかも山の号に相応するを以て奇なりとす。穴八幡の号ここに起れり。又此日将軍御令嗣 厳有公 御誕生ありしかば、衆益ますその霊威をしる。
其後元禄年間(1688-1704年)、今の如く宮居を御造営ありて、結構備れり。
若宮八幡宮 本社の前右
東照大権現 同所
氷室大明神 本社に相対す
光松 別当寺と本社との間、坂の支路にあり。暗夜には折として瑞光を現ず。
放生池 本社の左
出現所 坂の半腹、絶壁にそひてあり 往古の霊窟の舊址なり。近頃迄其地に出現堂となづけて、九品佛の中、下品上生の阿彌陀如来の像を安置せし堂宇ありしが。今は見えず。
そもそも当社の別当寺を光松山と号くるも、神木の奇特によそへてなり。

「放生會寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
放生寺は高田・西早稲田方面から東に向かって早稲田の低地に突き出す台地の突端に、穴八幡宮と並ぶようにしてあります。
江戸期は低地から仰ぎ見る台地の寺社として、ことにランドマーク的な偉容を誇ったと思われます。
東京メトロ東西線「早稲田駅」徒歩2分と交通至便です。
周辺には絵御朱印(御首題)で有名な法輪寺、豊島八十八ヶ所霊場第3番の龍泉院、御府内霊場第52番の観音寺、早稲田大学合格祈願で知られる宝泉寺、そして穴八幡宮など都内有数の御朱印エリアとなっています。
放生寺はその縁起・沿革から穴八幡宮とのゆかりがふかいので、一部穴八幡宮の社殿等も併せてご紹介します。
早稲田通り、諏訪通り、早大南門通りが交差する「馬場下町」交差点。
早稲田大学のキャンパスに近く活気ある街なかに、穴八幡宮の朱色の明神鳥居と背後の流鏑馬の銅像が存在感を放っています。
この流鏑馬造は、享保十三年(1726年)、徳川8代将軍吉宗公が御世嗣の疱瘡平癒祈願の為に催した流鏑馬を起源とする「高田馬場の流鏑馬」が、昭和9年皇太子殿下御誕生奉祝のため、穴八幡宮境内にて再興されたことに因むものです。(現在は戸山公園内で開催)


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道
放生寺の参道は、ここから左手の諏訪通りに入ってすぐのところにあります。
おのおの入口はことなりますが、両社寺の敷地は重なるように隣接しています。
諏訪通りから伸びる急な登り参道で、放生寺が台地の山裾に位置していることがわかります。
山内は南西向きで明るい雰囲気。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 札所標
参道のぼり口に寺号標と「一陽来福の寺」の碑、そして御府内霊場、江戸三十三観音霊場の札所標。
参道途中には「光松山 観世音菩薩 虫封霊場 放生寺」の碑もあります。
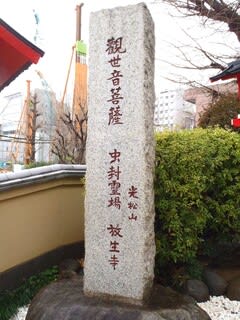

【写真 上(左)】 虫封の碑
【写真 下(右)】 寺務所
参道右手上方の朱塗りの建物はおそらく穴八幡宮の出現殿(平成18年再建)で、往年の神仏習合のたたずまいを彷彿とさせます。
坂の正面に見えるのは唐破風軒の寺務所(客殿?)、その手前に本堂。
山内入口手前左手に手水舎と、その奥にある朱塗りの堂宇は神変大菩薩のお堂です。
神変大菩薩(役の行者)は、主に修験系寺院や神仏習合の色あいの強い寺院で祀られます。
当尊のご縁起は定かでないですが、かつての神仏習合の流れを汲む尊格かもしれません。


【写真 上(左)】 神変大菩薩堂
【写真 下(右)】 本堂
階段のうえにおそらく入母屋造瓦葺流れ向拝の本堂。
朱塗りの身舎に五色の向拝幕を巡らせて、観音霊場らしい華々しい雰囲気。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 大提灯
おそらくコンクリート造の近代建築ながら、向拝まわりは水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股など伝統的な寺社建築の特徴を備えています。
向拝見上げに「聖観世音」と徳川家ゆかりの葵紋を掲げた大提灯。
さらにその奥に「聖観自在尊」の扁額。


【写真 上(左)】 扁額と葵紋
【写真 下(右)】 修行大師像
身舎柱には御府内霊場・観音札所の札所板と「高野山真言宗準別格本山」を示す寺号板が掲げられています。
向拝左右は授与所となっていて、こちらで御朱印をいただいたこともあれば、寺務所で拝受したこともあります。


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 寺号板
本堂向かって左には端正な修行大師像が御座します。
本堂向かって右には放生供養碑と馬頭観世音菩薩立像。
整った像容で、忿怒尊である馬頭尊の特徴がよく出ています。
掲示によると、馬頭尊は畜生道を救うことから、放生会を厳修する当山でお祀りされているそうです。

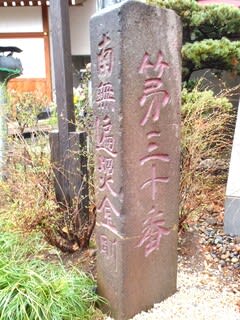
【写真 上(左)】 放生供養碑と馬頭観世音菩薩
【写真 下(右)】 御府内霊場札所標
このあたりからは、上方に穴八幡宮の鼓楼(以前は鐘楼)がよく見えます。
鼓楼は平成27年の再建。名刹の山門を思わせる楼門の建立は平成10年。
穴八幡宮が次第にかつての神仏習合の姿を取り戻しているかのようです。
とくにある意味「本地堂」ともいえる「出現殿」を再建されるとは、往時の姿の復興に対する明確な意思が感じられます。

「放生會寺」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
また、『江戸名所図会』と見比べてみると、出現殿といい、鼓楼といい、往時に忠実に場所を選んで再建されていることがわかります。
関東の八幡宮の神仏習合例として、明治初頭までは鎌倉・鶴岡八幡宮(鶴岡八幡宮寺)が代表格でしたが、廃仏毀釈で多くの伽藍堂宇を失い神宮寺も現存していません。
なので、穴八幡宮と放生寺が現存している(というか復興が進む)この界隈は、往年の八幡宮の神仏習合の姿を味わえる貴重な空間だと思います。
御朱印は寺務所ないし本堂内で拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「聖観世音」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の揮毫と三寶印。
右上に「弘法大師御府内三十番」の札所印。左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
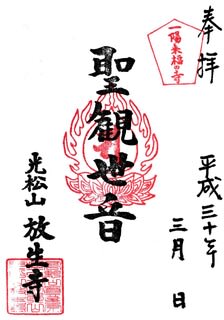
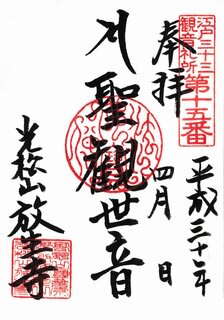
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の御朱印
※御本尊御影印の御朱印も授与されている模様です。
■ 第31番 照林山 吉祥寺 多聞院
(たもんいん)
新宿区弁天町100
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第31番、大東京百観音霊場第60番、秩父写山の手三十四観音霊場第26番
司元別当:
授与所:庫裡
新宿区弁天町にある真言宗豊山派で、烏山の多聞院(第3番札所)との区別の意味合いもあって、牛込多聞院と呼ばれます。
第31番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに多聞院なので、御府内霊場開創時から一貫して多聞院であったとみられます。
縁起・沿革について、下記史料、現地掲示、「ルートガイド」を参照に追ってみます。
多聞院は天正年間(1573-1592年)に平河口(現在の千代田区平河町)に起立し、慶長十二年(1607年)江戸城造営のため牛込門外外濠通りに移転、寛永十二年(1635年)、境内がお堀用地となったため現在地の辨天町に移転したといいます。
法流開山は覺祐上人(天正年中(1573-1592年)遷化)、中興開山は覺彦律師と伝わります。
※現地掲示には、寛永年間(1624-1629年)に法印覚賢により開創とあります。
『寺社書上』、『御府内寺社備考』ともに、御本尊は三身毘沙門天となっていますが、『御府内八十八ケ所道しるべ天』には本尊:大日如来 三身毘沙門天王 弘法大師とあります。
弘法大師はもとより、本堂御本尊の三身毘沙門天王、位牌堂御本尊の金剛界大日如来が拝所となっていた可能性があります。
『寺社書上』には、御本尊尊三身毘沙門天王は「楠正成之守本尊」とありますが、詳細については不明。
現在の御本尊は大日如来ですが、院号に多聞院とあるとおり、毘沙門天とゆかりのふかい寺院と思われます。
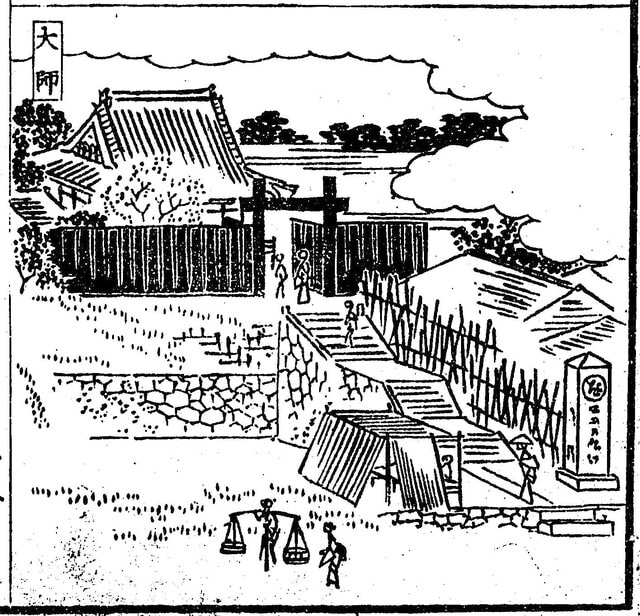
「多聞院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十一番
牛込七軒寺町門前町あり
照林山 吉祥寺 多聞院
西新井村惣持寺末 新義
本尊:大日如来 三身毘沙門天王 弘法大師
■ 『寺社書上 [33] 牛込寺社書上 六』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.122』
武州足立郡西新井村 惣持寺末
牛込七軒寺町
林山 吉祥寺 多聞院
新義真言宗
開山不分名
法流開山 覺祐上人 遷化年代●不詳
中興開山(寛永年中) 覚彦律師● 湯島霊雲寺開山
本堂
本尊 三身毘沙門天 大黒毘沙門 弁財天之三身一体之木像
●教大師之作 楠正成之守本尊 楠正成之末孫に沙門●●と申者当寺●●来案す●る事
唐●双身毘沙門天立像 弘法大師作
聖天堂
●金観喜天王立像
唐金地蔵尊
稲荷大明神
天満宮社
位牌堂
本尊 金剛界大日如来木立像 運●作
毘沙門天画像 弘法大師筆
(付記)
開山ハ覚●法印といふ 寛永十六年七月寂
■ 『牛込区史』(国立国会図書館)
昭林山吉祥寺多聞院
新井總持寺末
年代不詳、平河口に起立、慶長十二年(1607年)牛込門外外濠通りに移転、寛永十二年(1635年)辨天町に移つた。法流開山覺祐上人、天正年中(1573-1592年)遷化。中興開山覺彦律師。舊境内拝領地千九百廿五坪。
-------------------------
外苑東通り(都道319号)は、江戸川橋そばの鶴巻町から弁天町~牛込柳町と南下して青山、六本木を経て麻布台に至ります。
弁天町~牛込柳町あたりは南北の谷筋を走り、とくに東側は坂が多くみられます。
『江戸切絵図』と現代の地図を見比べてみると、かつての七軒寺町の通りがほぼ現在の外苑東通りとなっていることがわかります。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
最寄りは都営大江戸線「牛込柳町」駅。徒歩5分ほどです。
「牛込柳町」周辺は、日蓮宗江戸十大祖師の幸國寺、新宿山之手七福神の経王寺、曹洞宗の法身寺、顕本法華宗の常楽寺、日蓮宗の瑞光寺など、多彩な宗派の御朱印・御首題が拝受できるエリアとなっています。
多聞院のお隣の浄輪寺には江戸時代の和算家で算聖とあがめられた関孝和の墓があり、御首題も授与されています。

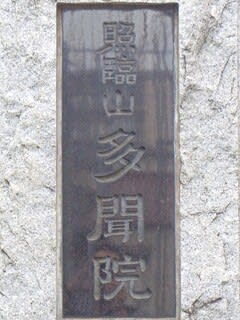
【写真 上(左)】 参道入口(工事中)
【写真 下(右)】 山院号表札


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 鐘楼
多聞院の入口は外苑東通りに面し、やはり坂道の参道となっています。
入口にはコンクリ造の山門がありその上部の鐘楼もスクエアなコンクリ造でモダンなイメージ。
左手には真新しい「牛込四恩の杜」(公園墓地?)があり、よく整備された印象です。


【写真 上(左)】 整備された山内
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
少し参道をのぼると、いきなり寺院づくりの本堂があらわれます。
本堂向かって左手の庫裡もモダンなイメージですが、本堂まわりだけは伝統的な寺院のイメージを保ち、独特のコントラスト。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝と整った意匠で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股を備え、向拝見上げに山号扁額を掲げています。
勢いのある降り棟と留蓋上の獅子飾りがいい味を出しています。

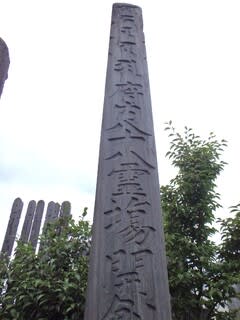
【写真 上(左)】 正等大阿闍梨供養塔
【写真 下(右)】 御府内霊場開創記念碑
山内には、御府内霊場の開基とも伝わる正等和尚の墓?(供養塔)、御府内霊場開創記念碑があります。
供養塔には「御府内八十八ヶ所開基 (通種子・ア)正等大阿闍梨百五十年供養塔 大正十二年六月十二日 大僧正●●●」とあります。
また、別の碑(祈念碑?)には「(梵字)府内八十八霊場開創」とあります。


【写真 上(左)】 吉川湊一の墓
【写真 下(右)】 庫裡
平家琵琶の奥義を極め、検校にまで昇進した吉川湊一(1748-1829年)、大正時代の女優・松井須麿子、大正時代の詩人・生田春月の墓所もあります。
御朱印は本堂向かって左のモダンな庫裡で拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

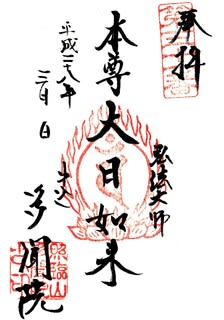
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三十一番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています
■ 第32番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺
(えんまんじ)
文京区湯島1-6-2
真言宗御室派
御本尊:不動明王・十一面観世音菩薩
札所本尊:不動明王・十一面観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第32番、弘法大師二十一ヶ寺第1番、御府内二十八不動霊場第25番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第1番、弁財天百社参り番外27
司元別当:
授与所:ビル内寺務所
第32番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに圓満寺なので、御府内霊場開創時から一貫して湯島の圓満寺であったとみられます。
下記史料を参照して縁起・沿革を追ってみます。
圓満寺は、寶永七年(1710年)、木食覺海義高上人が湯島の地に梵刹を建て、萬昌山圓満寺と号したのが開山といいます。
開山の「木食義高」に因んで「木食寺」とも呼ばれます。
義高上人は、足利13代将軍義輝公の孫義辰の子とも(義輝公の孫とも)伝わります。
幼くして出家、日向國佐土原の福禅寺に入り木食となりました。
寛文八年(1668年)から東国に下り各地に堂宇を建立、大いに奇特をあらわされて伝燈大阿闍梨権僧都法印に任ぜられました。
元禄四年(1691年)江戸に赴かれ本郷三組町に住むと、常憲公(5代将軍徳川綱吉公)や浄光院殿(綱吉公の正室・鷹司信子)の帰依を受け御祈祷を申しつけられています。
文昭公(6代将軍家宣公)の帰依も受け、家宣公は上人を以て当寺の(公的な?)開山とされたとのこと。
当山は開創時から真言宗御室派(当時は仁和寺御室御所)と所縁があったとみられます。
義高上人と御室御所について、『江戸名所図会』に「延寶七年(1679年)御室宮へ参るに、高野山光臺院の住持職に任ぜらる。」とあります。
「御室宮」はおそらく「仁和寺御室御所」で、上人は「御室御所」に参内された後、高野山光臺院の住持職に任ぜられています。
高野山光臺院は現存し、その公式Webには「当院は白河天皇の第四皇子覚法親王の開基で(約900年前)以来27代にわたり法親王方が参籠されている。それによって当院は「高野御室」と称され、非常に由緒ある名刹」とあります。
さらに「御室御所」についてたどってみます。
仁和寺の公式Webには「仁和2年(886年)第58代光孝天皇によって「西山御願寺」と称する一寺の建立を発願されたことに始まります。しかし翌年、光孝天皇は志半ばにして崩御されたため、第59代宇多天皇が先帝の遺志を継がれ、仁和4年(888年)に完成。寺号も元号から仁和寺となりました。」「宇多天皇は寛平9年(897年)に譲位、後に出家し仁和寺第1世 宇多(寛平)法皇となります。以降、皇室出身者が仁和寺の代々住職(門跡)を務め、平安〜鎌倉期には門跡寺院として最高の格式を保ちました。」とあります。
高野山光臺院は高野山内の門跡寺院で、その由緒から仁和寺御室御所と関係があり「高野御室」と称されていたのでは。
義高上人は仁和寺御室御所に参内してその才を認められ、時をおかずに御室御所所縁の高野山光臺院の住持職に任ぜらたのではないでしょうか。
むろん氏素性の明らかでない者が門跡寺院に参内できる筈はなく、おそらく義高上人が足利13代将軍義輝公の曽孫(ないし孫)という出自が効いたものと思われます。
中世の東密(真言宗)は小野六流・広沢六流の十二流に分化し、そこからさらに法脈を広げたといいます。
このうち広沢流の中心となったのが仁和寺御室御所です。
いささか長くなりますが、その経緯について『呪術宗教の世界』(速水侑氏著)を参照してたどってみます。
第52代嵯峨天皇は弘法大師空海の理解者で、東寺を賜った帝として知られています。
第59代の宇多天皇も仏教、ことに密教への帰依篤く、寛平九年(897年)の突然の譲位は、仏道に専心するためという説があるほどです。
宇多天皇は東寺長者の益信僧正(本覚大師)に帰依されたといいます。
益信僧正は弘法大師空海から第4世の直系で、東密広沢流の祖とされる高僧です。
昌泰二年(899年)、33歳の宇多上皇が仁和寺で出家する際に、益信僧正は受戒の師となり寛平法皇(法号は空理)と号されました。
延喜元年(901年)12月、益信僧正は東寺灌頂院にて法皇に伝法灌頂を授け継承者とされたといいます。
延喜四年(904年)、法皇は仁和寺に「御室御所」を構えられ、以降、仁和寺は東密の門跡寺院として寺勢大いに振いました。
法皇の弟子の寛空は嵯峨の大覚寺に入られ、寛空の弟子の寛朝は広沢に遍照寺を開かれました。
この寛平法皇(宇多天皇)所縁の法流が、後に「広沢流」と呼ばれることとなります。
一方、醍醐寺を開かれた聖宝(理源大師)ないしその弟子筋の仁海(小野僧正)も法流を興され、こちらは「小野流」と呼ばれます。
洛東の小野、洛西の広沢は東密の二大潮流となり、さらに分化していきました。
広沢流:仁和御流、西院流、保寿院流、華蔵院流、忍辱山流、伝法院流の六流
小野流:勧修寺(小野)三流(安祥寺流、勧修寺流、随心院流)
醍醐三流(三宝院流、理性院流、金剛王院流)の六流
これらを総じて「野沢(やたく)十二流」といいます。
広沢流と小野流の違いについては、
・広沢流は儀軌を重視、小野流は口伝口訣を重視
・広沢流は「初胎後金」、小野流は「初金後胎」(両部灌頂を行うときに胎蔵界、金剛界いずれを先にするかの流儀)
などが論じられるようです。
東密が分化したのは事相(修法の作法など)の研究が進んだため、というほど修法の存在は大きく、たとえば雨乞いの修法を修するときに
・広沢流は孔雀経法、小野流は請雨経法
という説もみられたようです。
『呪術宗教の世界』では、例外もみられるとして修法における差異については慎重に扱われていますが、それだけ東密に対する「秘法」の要請が強かったとしています。
(「他の流派にない霊験ある秘法を相承することで、貴族たちの呪術的欲求にこたえ、流派独自の秘法として主張喧伝された。」(同書より抜粋引用))
話が長くなりました。
ともあれ、仁和御流は高い格式をもつ門跡寺院・仁和寺を中心に東密「広沢流」の中核をなしました。
なお、Wikipediaには「仁和寺の仁和御流(真言宗御室派)」と記され、仁和御流が真言宗御室派に承継されていることを示唆しています。
仁和御流(真言宗御室派)は西日本中心の流派で、現在の総本山は仁和寺(京都市右京区)、大本山は金剛寺(大阪府河内長野市)と大聖院(広島県廿日市市)、準大本山は屋島寺(香川県高松市)です。
別格本山もほとんどが西日本で、これは仁和寺は江戸時代末期まで法親王(皇族)を迎えた門跡寺院で、京の皇室との所縁が深いということがあるのでは。
しかし、江戸時代の江戸にも仁和寺末を名乗る寺院はいくつかありました。
そのひとつが湯島の圓満寺です。
寶永七年(1710年)、義高上人が湯島の地に圓満寺を開山された以前に、上人は「御室御所」と所縁をもち、おそらく「御室御所」から高野山光臺院(「高野御室」)の住持職を託されています。
その義高上人が江戸に開山された圓満寺が「京仁和寺末」となるのは、自然な流れかと思われます。
(『御府内寺社備考』に「御室御所より院室御影●之節 圓満寺の寺号(以下不詳)」とあり。)
御府内霊場では当山のほか、第41番密蔵院が真言宗御室派です。
義高上人は日暮里の補陀落山 養福寺(豊島霊場第73番ほか)を中興開山と伝わりますが、養福寺は真言宗豊山派(新義真言宗)となっています。
Wikipediaによると、明治初期の火災で伽藍を焼失し、明治20年に相模の大山寺の協力の下で再建されたものの関東大震災、東京大空襲で焼失しています。
昭和38年木造の本堂が再建、昭和53年にはRC造の「おむろビル」に改築され、ビル内の寺院となっています。
なお、Wikipediaには「御室派総本山仁和寺の東京事務所」とあり、おむろビルの袖看板にも「総本山 仁和寺 東京事務所」とあります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十二番
ゆしま四丁目
萬昌山 金剛幢院 圓満寺
御直末
本尊:十一面観世音菩薩 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [68] 湯嶋寺院書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.2』
本寺 御室御所仁和寺宮 (御室御所院室)
湯島 不唱小名
萬昌山 金剛幢院 圓満寺
開山 開山木食覺海義高僧正者 将軍光源院(足利)義輝公の御子
本堂
本尊 七観音尊木立像 紀伊殿●御寄附
十一面観世音尊 秘佛 如意法尼内親王之御作
歓喜天尊 秘佛
多聞天木立像 開山義高僧正作
両部大日如来木座像
不空羅索尊木座像
千手観音尊木座像
薬師如来木座像 日光月光立像 十二神将立像
愛染明王木座像
孔雀明王尊影
五大虚空蔵尊影
常倶梨天尊影
位牌所
地蔵菩薩木立像(ほか)
鐘楼堂
阿弥陀如来天竺佛座像 等持院殿守本尊
当寺開山義高権僧正御影
弘法大師●筆 楷書心経巻物
六観音 弘法大師之作
辨財天木座像 弘法大師之作
胎蔵界大日如来木座像 弘法大師之作
御香宮明神木像
三尊来迎
天満宮渡唐神像
十六善神
地蔵尊 二童子有
刀八毘沙門天神像 尊氏公軍中守本尊
大師目引之尊影 真如親王之御筆 高野山御影堂に有し●
十六羅漢御影
阿育王塔石
多寶塔
護摩堂
不動明王 二童子附 秘封 弘法大師作
前立五大尊明王
閻魔天木座像
金佛地蔵尊座像
秋葉社
鐘楼堂
辨財天社
辨財天女木立像
稲荷大明神 秘封
大黒天木立像
恵比須神木座像
千手観音木座像
青面金剛木立像
地蔵堂 石地蔵尊立像
七観音堂 本堂の左にあり
十一面観音
■ 『江戸名所図会 第3 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)〔要旨抜粋〕
萬昌山圓満寺
湯島六丁目にあり。真言宗にして、開山は木食義高上人なり。本尊十一面観世音、如意法尼の御作なり。法尼は淳和帝の妃にして弘法大師の御弟子なり。左右に六観音を安置す。当寺を世に木食寺と称す。
寺伝に曰く、開山木食義高上人は覺海と号す。足利十三代将軍義輝公の孫義辰の息なり。
日向國に産る。幼より瑞相あるに仍て出家し、肥後國(日向國?)佐土原の福禅寺に入りて、覺深師に随従し、木食となれり。寛文八年(1668年)、衆生化益のために東奥に下り、あまねく霊地を拝しこゝかしこに堂宇を建立す。(略)伝燈大阿闍梨権僧都法印に任ぜらる。其後西國に赴くの頃も、大に奇特を顕す。延寶三年(1675年)都に上り堀河姉小路多聞寺に止宿(略)延宝五年(1677年)江城湯島の地に至り、大に霊験をあらはす。延寶七年(1679年)御室宮へ参るに、高野山光臺院の住持職に任ぜらる。元禄四年(1691年)志願によって光臺院を辞して江戸に赴き、本郷三組町に住せらる。常憲公(5代将軍徳川綱吉公)および浄光院殿(綱吉公の正室・鷹司信子)、須山女を以て御祈祷を仰附けらる。寶永六年(1709年)上京(略)寶永七年(1710年)江戸湯島の地に梵刹を建てゝ、萬昌山圓満寺と号す。文昭公(6代将軍家宣公)の御志願に仍て、則ち上人を以て当寺の開山とす。

「圓満寺」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
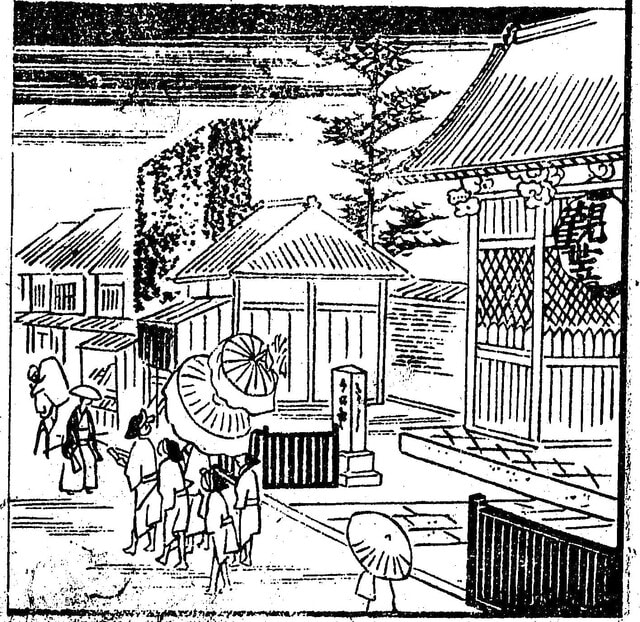
「圓満寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本郷湯島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
JR・メトロ丸ノ内線「お茶ノ水」駅から徒歩約5分、オフィス街に建つ「おむろビル」のなかにあります。
現在、土祝日はビルのセキュリティの関係上入館不可につき平日のみ参拝可のようです。
ごくふつうのオフィスビルのエントランスですが、袖看板に「圓満寺」とあり、かろうじて館内に寺院があることがわかります。

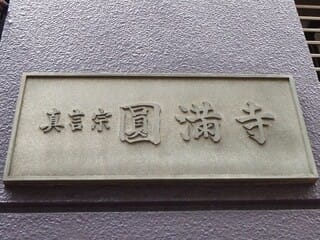
【写真 上(左)】 おむろビル全景
【写真 下(右)】 寺号標

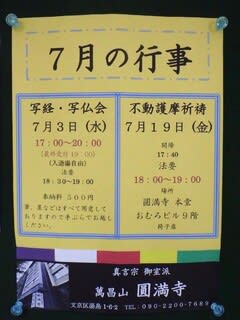
【写真 上(左)】 寺号の袖看板
【写真 下(右)】 行事予定
貼り出されていた行事予定によると、不動護摩祈祷や写経会が開催されているようです。


【写真 上(左)】 エントランス
【写真 下(右)】 8階エレベーターホールの「授与所」
受付は8階、本堂は9階でエレベーターでのぼりますが、通常9階は不停止となっているようです。
8階にどなたかおられるときは、申し入れれば本堂参拝可能な模様ですが、筆者参拝時(2回)はいずれもご不在で、8階からの遙拝となりました。
8階にはエレベーターホールに書置御朱印が置かれているので、ここから遙拝しました。
上層階の御本尊に向かって、階下のエレベーターホールからの参拝ははじめてで、不思議な感じですが、これはこれで「都心のお遍路」ならではの雰囲気は味わえるかと思います。
史料によると、当山は数多くの尊像を奉安されていたようですが、そのお像は現在本堂に安置されているのでしょうか。
『寺社書上』(文政年間(1818-1831年))では、御本尊は七観音木像。
『御府内寺社備考』(同)では本堂本尊は七観音木像、十一面観世音(秘佛、如意法尼内親王御作)。
『江戸名所図会』(天保年間(1831-1845年))では、御本尊は十一面観世音(如意法尼の御作)。
『御府内八十八ケ所道しるべ』(幕末-明治)では、札所本尊は十一面観世音菩薩、不動明王、弘法大師とあります。
さらにWikipediaには「明治初期の火災までは、以下の寺宝があった。 七観音(旧本尊)」とあります。
また『御府内寺社備考』には「七観音堂 本堂の左にあり 十一面観音」「護摩堂 不動明王 二童子付秘封 弘法大師作」とあります。
以上から、江戸時代の御本尊は七観音木像、ないし十一面観世音(如意法尼内親王御作)とみられます。
七観音木像は明治初期の火災で焼失?し、御本尊は十一面観世音菩薩(如意法尼内親王御作)となり、明治20年に「関東三大不動」で不動尊とのゆかり深い相模・大山寺の協力で再建された際に、十一面観世音菩薩・不動明王の両尊御本尊となったのでは。
こちらの不動明王は、護摩堂本尊の不動明王(弘法大師御作)、ないしは大山寺から奉安された尊像と考えられます。
明治初期来、数度の火災に遭い古文書など焼失されているようなので詳細は不明です。
御朱印は8階エレベーターホールに置かれていたものを拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(規定用紙貼付)
中央に「本尊不動明王」「十一面観世音菩薩」「弘法大師」の印判と十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の印判と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第三十二番」の札所印。山号の印判と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-11)
【 BGM 】
■ 名もない花 - 遥海
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
■ Parade - FictionJunction
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第30番 光松山 威盛院 放生寺
(ほうじょうじ)
公式Web
新宿区西早稲田2-1-14
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第30番、江戸三十三観音札所第15番、大東京百観音霊場第19番、山の手三十三観音霊場第16番、九品仏霊場第7番
司元別当:高田穴八幡宮
授与所:寺務所ないし本堂内
第30番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ 』、江戸八十八ヶ所霊場ともに放生寺なので、御府内霊場開創時から一貫して早稲田の放生寺であったとみられます。
縁起・沿革は公式Web、現地掲示に詳しいので、こちらと下記史料を参照してまとめてみます。
放生寺は寛永十八年(1641年)、威盛院権大僧都法印良昌上人が高田八幡(穴八幡宮)の造営に尽力され、その別当寺として開創されました。
良昌上人は周防國の生まれで十九歳の年遁世して高野山に登り、寶性院の法印春山の弟子となり修行をとげられ、三十一歳の頃より諸國修行されて様々な奇特をあらわされたといいます。
寛永十六年(1639年)二月、陸奥国尾上八幡に参籠の夜、霊夢に老翁があらわれ「将軍家の若君が辛巳の年の夏頃御降誕あり、汝祈念せよ」と告げられました。
上人は直ちに堂宇に籠もり、無事御生誕の大願成就行を厳修されました。
寛永十八年(1641年)当地に止錫の折、御弓組の長松平新五左衛門尉源直次の組の者の請を受け、穴八幡宮の別当職に就かれました。
同年の八月三日、草庵を結ぶため山裾を切り闢くと霊窟があり(現在の穴八幡宮出現殿付近)、窟の中には金銅の下品上生阿彌陀如来が立たれていました。
この阿彌陀如来像は八幡宮の御本地で、良昌上人はこの尊像を手篤く奉安。
「穴八幡宮」の号はこの霊窟に由来といいます。
おりしも、この日に将軍家御令嗣・厳有公(竹千代君、4代将軍家綱公)の御誕生があったため、以前から「将軍家若君、辛巳の年の夏頃無事御降誕の行厳修」の譚を聞いていた人々は、その霊威を新たにしたとのことです。
良昌上人が霊夢でみられた「将軍家の若君」は家光公とする資料もありますが、霊夢は寛永十六年(1639年)、家光公の御生誕は慶長九年(1604年)ですから年代が合いません。
家光公嫡男の竹千代君(4代将軍家綱公)は寛永十八年(1641年)八月の御生誕で、この年は辛巳ですから、おそらく良昌上人は竹千代君御生誕の成就祈願行を2年前に厳修したことになります。
『江戸名所図会』にも、「厳有公 御誕生」と明記されています。
なお、穴八幡宮の公式Webによると、高田八幡(穴八幡宮)は「康平五年(1062年)、奥州の乱を鎮圧した八幡太郎源義家公が凱旋の折、日本武尊命の先蹤に習ってこの地に兜と太刀を納めて氏神八幡宮を勧請」とあるので、良昌上人来所以前の創祀とみられます。
『江戸名所図会』には、寛永十三年(1636年)、御弓組の長松平新五左衛門尉源直次の与力の輩が、射術練習のためこの地に的山を築立てた際、弓箭の守護神である八幡神を勧請とあります。
以上から、八幡宮は良昌上人来所(寛永十八年(1641年))以前に当地に勧請されており、良昌上人は同年、霊窟から金銅の御神像(あるいは阿彌陀佛)を得て穴八幡宮と号したことなどでの貢献とみるべきでしょうか。
当地に古松があって山鳩が遊ぶ神木とされ、あるいは暗夜に瑞光を放つことから霊松ともされて、光松山の号はこの松に由来といいます。
慶安二年(1649年)、大猶院殿(徳川家光公)が御放鷹の折に穴八幡宮を訪れ、良昌上人より件の霊夢や大願成就の厳修について聞き及ぶと、「威盛院光松山放生會寺」の号を賜り、以降、別当・放生寺を御放鷹の御膳所とするなど篤く外護しました。
厳有院(4代将軍・家綱公)生誕の霊夢譚、そして家綱公生誕の当日に高田八幡の御本地・金銅阿彌陀佛の降臨とあっては、将軍家としてもなおざりにはできなかったと思われます。
歴代の徳川将軍家の尊崇は、『江戸名所図会』に穴八幡宮の什寶としてつぎのとおり記されていることからもうかがえます。
・台徳院(2代将軍・秀忠公) 御筆、御自賛の和歌
・大猶院(3代将軍・家光公) 賜物の扇子 一握
・常憲院(5代将軍・綱吉公) 御筆の福禄壽御画 一幅
元禄年間(1688-1704年)には宮居の造営あって結構を整えたといい、とくに元禄十六年(1703年)の造営は江戸権現造り社殿として壮麗を極めたといいます。
爾来、将軍家の尊崇篤く、徳川家代々の祈願寺として葵の紋を寺紋に、また江戸城登城の際には寺格から独礼登城三色(緋色、紫色、鳶色)衣の着用を許されたとも。
穴八幡宮の祭礼の八月十五日には放生會で賑わいをみせたといい、現在の放生寺の放生会はその系譜にあるとみられます。
「放生會(ほうじょうえ)」とは、捕らえられた魚介、鳥、動物などを殺生せずに池、川や山林に放す法事で、養老四年(720年)宇佐八幡宮で行われた放生會が発祥ともされることから、八幡宮社・八幡社で多く催されます。
江戸期の放生寺は穴八幡宮別当としてその地位を固め、一帯は神仏習合の一大霊場として栄えたことは、『江戸名所図会』の挿絵からもうかがえます。
しかし、穴八幡宮とこれだけ強固な神仏習合関係を築きながら、明治初期の神仏分離で放生寺が廃されなかったのはある意味おどろきです。
そのカギはひょっとして別当寺と神宮寺の別にあるのかもしれません。
放生寺の公式Webに唐突ともいえるかたちで、以下の説明が記載されています。
-------------------------
別当寺 べっとうじ
神宮寺の一種。神社境内に建てられ、別当が止住し、読経・祭祀・加持祈祷とともに神社の経営管理を行なった寺。
神宮寺 じんぐうじ
神社に付属して建てられた寺院。神仏習合思想の現れで、社僧(別当)が神社の祭祀を仏式で挙行した。1868年(明治1)の神仏分離令により廃絶または分離。宮寺。別当寺。神護寺。神宮院。神願寺。
-------------------------
明治の神仏分離で廃絶されたのは「神宮寺」で、「別当寺」は神宮寺の一種ながら廃絶を免れたと読めなくもありません。
(別当寺の説明で「神仏習合」ということばを用いていない。)
神宮寺と別当寺の別は、わが国の神仏習合を語るうえで避けてとおれない重要な事柄ですが、すこぶるデリケートかつ複雑な内容を含むので、ここではこれ以上触れません。
ひとつ気になるのは、『御府内八十八ケ所道しるべ 』では放生寺の御本尊は阿弥陀如来(穴八幡宮の御本地)となっているのに、現在の御本尊は聖観世音菩薩(融通虫封観世音菩薩)であることです。
この点について、現地掲示には「代々の(放生寺)住職が社僧として寺社一山の法務を司っておりましたが、明治二年、当山十六世実行上人の代、廃仏毀釈の布告に依り、境内を分割し現今の地に本尊聖観世音菩薩が遷されました。」とあります。
放生寺は明治二年に現在地に伽藍を遷し、そのときに聖観世音菩薩を御本尊とされたのでは。
以前の御本尊?の阿弥陀如来は、江戸時代に九品仏霊場第7番(下品上生)に定められた著名な阿弥陀様です。
(九品仏霊場の札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様))
一方、放生寺は江戸期から複数の観音霊場の札所で、観音様(おそらく融通虫封観世音菩薩)の信仰の場でもありました。
あるいは八幡宮との習合関係のうすい聖観世音菩薩を御本尊とすることで、神宮寺の性格(御本地が御本尊)をよわめたのかもしれません。
ともあれ御府内霊場第30番札所の放生寺は、明治初期の廃仏毀釈の波を乗り切って存続しました。
現在も高野山真言宗準別格本山の高い格式を保ち、複数の霊場札所を兼務されて多くの参拝客を迎えています。
放生寺と穴八幡宮は現在はそれぞれ独立した寺社ですが、いずれも「一陽来福」「一陽来復」ゆかりの寺社として知られています。
「一陽来福」(「一陽来復」)とは冬至をあらわす中国の易経の言葉で、「陰極まって一陽を生ずる」の意とされます。
「一陽と共に福もかえり来る」、来る年も福がまた訪れますように、との祈念を込めて参詣し、「一陽来福」(「一陽来復」)のお札をいただいて、冬至、大晦日、節分の深夜に恵方(「明の方」、歳徳神のおわす方角)に向けて貼るといいます。
放生寺の「一陽来福」は、御本尊・聖観世音菩薩ゆかりの「観音経の結びの「福聚海無量」=福聚(あつ)むること海の如く無量なり と言う偈文より「福」の字を取り「一陽来福」と名付けられました。」とのこと。(当山Webより)
御本尊・聖観世音菩薩は古来より融通・虫封観世音と呼ばれ、「融通=滞りなく通じる」から商家はもとより円満な人間関係(融通円満)の祈願本尊として信仰を集めており、冬至、大晦日、節分には「一陽来福」「融通」「虫封」を祈念する参詣者でことに賑わいをみせます。
一方、穴八幡宮の「一陽来復」は公式Webによると「福神(打出小槌)」に由来するものです。
『新編武蔵風土記稿』には、聖武天皇の御代に公家の水無瀬家の息女が感得されたもので、祈願の趣を掌に書き、この小槌でその掌を打てば所願成就とあります。
穴八幡宮公式Webには「公家の水無瀬家が山城国国宝寺より感得したものを当社に納めたもので、聖武天皇が養老七年の冬至の日に龍神により授けられた宝器」とあります。
穴八幡宮の「一陽来復御守」は江戸中期から冬至の福神祭に授与された歴史あるもので、「金銀融通の御守」とも呼ばれて、授与時には多くの参詣客で賑わいます。
なお、穴八幡宮の御朱印は「一陽来復」が揮毫される貴重なものですが、冬至から節分にかけては授与されておりません。

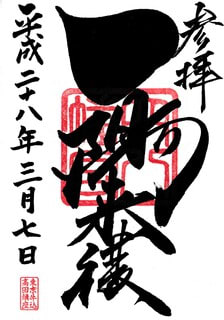
【写真 上(左)】 穴八幡宮の社頭
【写真 下(右)】 穴八幡宮の御朱印
-------------------------
【史料】 ※なぜか『寺社書上』『御府内寺社備考』には記載がありません。
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十番
高田穴八まん
光松山 威盛院 放生會寺
高野山宝性院末 古義
本尊:阿弥陀如来 本社八幡宮 弘法大師
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(下戸塚村(穴)八幡社)別当放生會寺
古義真言宗、高野山寶性院末、光松山威盛院ト号ス 本尊不動を安ス 開山良昌ハ周防國ノ産ニテ 俗称ハ榎本氏 高野山寶性院青山ニ投ジテ薙染シ 諸國ヲ経歴シテ 寛永十六年(1616年)陸奥國尾上八幡ニ参籠ノ夜 将軍家若君辛巳年夏ノ頃御降誕アルヘキ由霊夢ヲ得タリ 其後当國ニ来リ シルヘノ僧室ニ暫ク錫ヲ止メシニ 同十八年(1618年)松平新五左衛門カ組ノ者ノ請ニ任セ当社((穴)八幡社)ノ別当職トナレリ 此年(寛永十八年(1641年))厳有院殿御降誕マシ々々 カノ霊堂ニ符合セリ 此事イツトナク上聞くニ達セシカハ 大猶院殿御放鷹ノ時当山ニ御立寄アリテ 良昌ヲ召サセラレ社ノ由緒ヲ聞シメサレ 光松山放生會寺ノ号ヲ賜ハレリト云 是ヨリ以来此邊御遊猟ノ時ハ 当寺ヲ御膳所ニ命セラレテ今ニ然リ
什寶
柳ニ竹ノ御書一幅 台徳院殿ノ御筆ト云 御自賛ノ和歌アリ
柳チル カタ岡ノヘノ秋風ニ 一ツフタツノ家ニカクルヽ
扇子一握 大猶院殿ノ賜物ニテ開山良昌拝領す、便面ス便面ニ御筆ノ詩歌アリ
飛鳥去邊山侶眉 空低水潤影遅遅 上林雖好非栖處 一任千枝與萬枝
雁カヘル常世ノ花ノイカナレヤ 月ハイヅクモ霞ム春ノヨ
福禄壽御画一幅 常憲院殿ノ御筆ナリ 落款ニ御諱アリ
楊柳観音画像一幅
百體大黒天画像一幅
(略)
不動愛染ノ画像各幅 弘法大師筆
心経一巻 同筆。
十六善神画像一幅
(略)
打出小槌 由来記一巻アリ其略ニ
此槌●紳家水無瀬家ノ女感得セシ所也 昔聖武天皇ノ此ノ如キ寶物ヲ山城國●原ノ一宇ニ御寄納アリシカハ 彼寺ヲ寶寺ト号ス 信心ノ男女祈願ノ意趣ヲ掌ニ書シテ 此槌モテソノ掌ヲ打テハ所願成就スト云
(略)
寺中 松済院 光済院 是ハ廃院トナリテ末再建ニ及ハス
■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)〔要旨抜粋〕
高田八幡宮 穴八幡
牛込の総鎮守 別当は真言宗光松山 放生會寺
祭礼は八月十五日にて、放生會あり
寛永十三年(1636年)御弓組の長松平新五左衛門尉源直次に与力の輩、射術練習の為、其地に的山を築立てらる。
八幡宮は源家の宗廟にして而も弓箭の守護神なればとて、此地に勧請せん事を謀る。
此山に素より古松二株あり。其頃山鳩来つて、日々に此松の枝上に遊ぶを以て、霊瑞とし、仮に八幡大神の小祠を営みて、件の松樹を神木とす。此地昔は阿彌陀山と呼び来りしとなり。
(略)
寛永十八年(1641年)の夏、中野寶仙寺秀雄法印の會下に、威盛院良昌といえる沙門あり。周防國の産にして、山口八幡の氏人なり。十九歳の年遁世して、高野山に登り、寶性院の法印春山の弟子となり、一紀の行法をとげて、三十一の時より、諸國修行の志をおこし、其聞さまざまの奇特をあらはせりといふ。依てこの沙門を迎へて、社僧たらしむ。
同年の秋八月三日、草庵を結ばんとして、山の腰を切り闢く時に、ひとつの霊窟を得たり。
その窟の中石上に、金銅の阿彌陀の霊像一軀たたせ給へり。八幡宮の本地にて、しかも山の号に相応するを以て奇なりとす。穴八幡の号ここに起れり。又此日将軍御令嗣 厳有公 御誕生ありしかば、衆益ますその霊威をしる。
其後元禄年間(1688-1704年)、今の如く宮居を御造営ありて、結構備れり。
若宮八幡宮 本社の前右
東照大権現 同所
氷室大明神 本社に相対す
光松 別当寺と本社との間、坂の支路にあり。暗夜には折として瑞光を現ず。
放生池 本社の左
出現所 坂の半腹、絶壁にそひてあり 往古の霊窟の舊址なり。近頃迄其地に出現堂となづけて、九品佛の中、下品上生の阿彌陀如来の像を安置せし堂宇ありしが。今は見えず。
そもそも当社の別当寺を光松山と号くるも、神木の奇特によそへてなり。

「放生會寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
放生寺は高田・西早稲田方面から東に向かって早稲田の低地に突き出す台地の突端に、穴八幡宮と並ぶようにしてあります。
江戸期は低地から仰ぎ見る台地の寺社として、ことにランドマーク的な偉容を誇ったと思われます。
東京メトロ東西線「早稲田駅」徒歩2分と交通至便です。
周辺には絵御朱印(御首題)で有名な法輪寺、豊島八十八ヶ所霊場第3番の龍泉院、御府内霊場第52番の観音寺、早稲田大学合格祈願で知られる宝泉寺、そして穴八幡宮など都内有数の御朱印エリアとなっています。
放生寺はその縁起・沿革から穴八幡宮とのゆかりがふかいので、一部穴八幡宮の社殿等も併せてご紹介します。
早稲田通り、諏訪通り、早大南門通りが交差する「馬場下町」交差点。
早稲田大学のキャンパスに近く活気ある街なかに、穴八幡宮の朱色の明神鳥居と背後の流鏑馬の銅像が存在感を放っています。
この流鏑馬造は、享保十三年(1726年)、徳川8代将軍吉宗公が御世嗣の疱瘡平癒祈願の為に催した流鏑馬を起源とする「高田馬場の流鏑馬」が、昭和9年皇太子殿下御誕生奉祝のため、穴八幡宮境内にて再興されたことに因むものです。(現在は戸山公園内で開催)


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 参道
放生寺の参道は、ここから左手の諏訪通りに入ってすぐのところにあります。
おのおの入口はことなりますが、両社寺の敷地は重なるように隣接しています。
諏訪通りから伸びる急な登り参道で、放生寺が台地の山裾に位置していることがわかります。
山内は南西向きで明るい雰囲気。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 札所標
参道のぼり口に寺号標と「一陽来福の寺」の碑、そして御府内霊場、江戸三十三観音霊場の札所標。
参道途中には「光松山 観世音菩薩 虫封霊場 放生寺」の碑もあります。
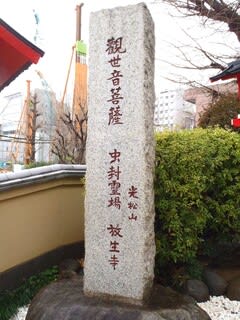

【写真 上(左)】 虫封の碑
【写真 下(右)】 寺務所
参道右手上方の朱塗りの建物はおそらく穴八幡宮の出現殿(平成18年再建)で、往年の神仏習合のたたずまいを彷彿とさせます。
坂の正面に見えるのは唐破風軒の寺務所(客殿?)、その手前に本堂。
山内入口手前左手に手水舎と、その奥にある朱塗りの堂宇は神変大菩薩のお堂です。
神変大菩薩(役の行者)は、主に修験系寺院や神仏習合の色あいの強い寺院で祀られます。
当尊のご縁起は定かでないですが、かつての神仏習合の流れを汲む尊格かもしれません。


【写真 上(左)】 神変大菩薩堂
【写真 下(右)】 本堂
階段のうえにおそらく入母屋造瓦葺流れ向拝の本堂。
朱塗りの身舎に五色の向拝幕を巡らせて、観音霊場らしい華々しい雰囲気。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 大提灯
おそらくコンクリート造の近代建築ながら、向拝まわりは水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股など伝統的な寺社建築の特徴を備えています。
向拝見上げに「聖観世音」と徳川家ゆかりの葵紋を掲げた大提灯。
さらにその奥に「聖観自在尊」の扁額。


【写真 上(左)】 扁額と葵紋
【写真 下(右)】 修行大師像
身舎柱には御府内霊場・観音札所の札所板と「高野山真言宗準別格本山」を示す寺号板が掲げられています。
向拝左右は授与所となっていて、こちらで御朱印をいただいたこともあれば、寺務所で拝受したこともあります。


【写真 上(左)】 札所板
【写真 下(右)】 寺号板
本堂向かって左には端正な修行大師像が御座します。
本堂向かって右には放生供養碑と馬頭観世音菩薩立像。
整った像容で、忿怒尊である馬頭尊の特徴がよく出ています。
掲示によると、馬頭尊は畜生道を救うことから、放生会を厳修する当山でお祀りされているそうです。

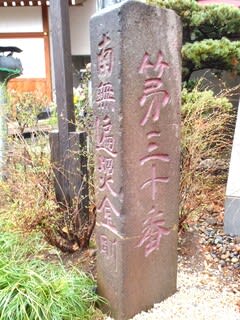
【写真 上(左)】 放生供養碑と馬頭観世音菩薩
【写真 下(右)】 御府内霊場札所標
このあたりからは、上方に穴八幡宮の鼓楼(以前は鐘楼)がよく見えます。
鼓楼は平成27年の再建。名刹の山門を思わせる楼門の建立は平成10年。
穴八幡宮が次第にかつての神仏習合の姿を取り戻しているかのようです。
とくにある意味「本地堂」ともいえる「出現殿」を再建されるとは、往時の姿の復興に対する明確な意思が感じられます。

「放生會寺」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
また、『江戸名所図会』と見比べてみると、出現殿といい、鼓楼といい、往時に忠実に場所を選んで再建されていることがわかります。
関東の八幡宮の神仏習合例として、明治初頭までは鎌倉・鶴岡八幡宮(鶴岡八幡宮寺)が代表格でしたが、廃仏毀釈で多くの伽藍堂宇を失い神宮寺も現存していません。
なので、穴八幡宮と放生寺が現存している(というか復興が進む)この界隈は、往年の八幡宮の神仏習合の姿を味わえる貴重な空間だと思います。
御朱印は寺務所ないし本堂内で拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「聖観世音」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の揮毫と三寶印。
右上に「弘法大師御府内三十番」の札所印。左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
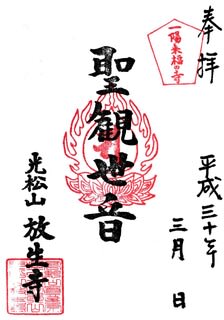
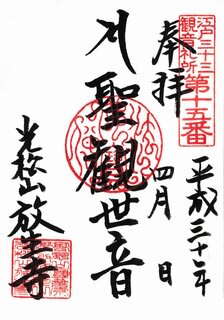
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の御朱印
※御本尊御影印の御朱印も授与されている模様です。
■ 第31番 照林山 吉祥寺 多聞院
(たもんいん)
新宿区弁天町100
真言宗豊山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第31番、大東京百観音霊場第60番、秩父写山の手三十四観音霊場第26番
司元別当:
授与所:庫裡
新宿区弁天町にある真言宗豊山派で、烏山の多聞院(第3番札所)との区別の意味合いもあって、牛込多聞院と呼ばれます。
第31番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに多聞院なので、御府内霊場開創時から一貫して多聞院であったとみられます。
縁起・沿革について、下記史料、現地掲示、「ルートガイド」を参照に追ってみます。
多聞院は天正年間(1573-1592年)に平河口(現在の千代田区平河町)に起立し、慶長十二年(1607年)江戸城造営のため牛込門外外濠通りに移転、寛永十二年(1635年)、境内がお堀用地となったため現在地の辨天町に移転したといいます。
法流開山は覺祐上人(天正年中(1573-1592年)遷化)、中興開山は覺彦律師と伝わります。
※現地掲示には、寛永年間(1624-1629年)に法印覚賢により開創とあります。
『寺社書上』、『御府内寺社備考』ともに、御本尊は三身毘沙門天となっていますが、『御府内八十八ケ所道しるべ天』には本尊:大日如来 三身毘沙門天王 弘法大師とあります。
弘法大師はもとより、本堂御本尊の三身毘沙門天王、位牌堂御本尊の金剛界大日如来が拝所となっていた可能性があります。
『寺社書上』には、御本尊尊三身毘沙門天王は「楠正成之守本尊」とありますが、詳細については不明。
現在の御本尊は大日如来ですが、院号に多聞院とあるとおり、毘沙門天とゆかりのふかい寺院と思われます。
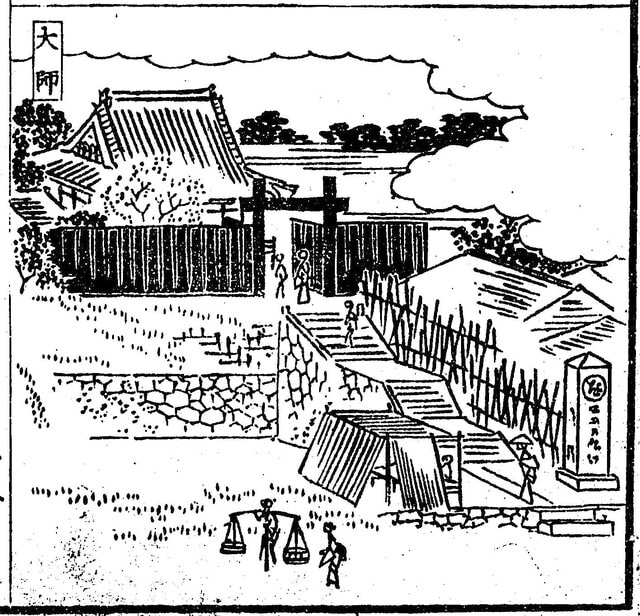
「多聞院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
三十一番
牛込七軒寺町門前町あり
照林山 吉祥寺 多聞院
西新井村惣持寺末 新義
本尊:大日如来 三身毘沙門天王 弘法大師
■ 『寺社書上 [33] 牛込寺社書上 六』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.122』
武州足立郡西新井村 惣持寺末
牛込七軒寺町
林山 吉祥寺 多聞院
新義真言宗
開山不分名
法流開山 覺祐上人 遷化年代●不詳
中興開山(寛永年中) 覚彦律師● 湯島霊雲寺開山
本堂
本尊 三身毘沙門天 大黒毘沙門 弁財天之三身一体之木像
●教大師之作 楠正成之守本尊 楠正成之末孫に沙門●●と申者当寺●●来案す●る事
唐●双身毘沙門天立像 弘法大師作
聖天堂
●金観喜天王立像
唐金地蔵尊
稲荷大明神
天満宮社
位牌堂
本尊 金剛界大日如来木立像 運●作
毘沙門天画像 弘法大師筆
(付記)
開山ハ覚●法印といふ 寛永十六年七月寂
■ 『牛込区史』(国立国会図書館)
昭林山吉祥寺多聞院
新井總持寺末
年代不詳、平河口に起立、慶長十二年(1607年)牛込門外外濠通りに移転、寛永十二年(1635年)辨天町に移つた。法流開山覺祐上人、天正年中(1573-1592年)遷化。中興開山覺彦律師。舊境内拝領地千九百廿五坪。
-------------------------
外苑東通り(都道319号)は、江戸川橋そばの鶴巻町から弁天町~牛込柳町と南下して青山、六本木を経て麻布台に至ります。
弁天町~牛込柳町あたりは南北の谷筋を走り、とくに東側は坂が多くみられます。
『江戸切絵図』と現代の地図を見比べてみると、かつての七軒寺町の通りがほぼ現在の外苑東通りとなっていることがわかります。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
最寄りは都営大江戸線「牛込柳町」駅。徒歩5分ほどです。
「牛込柳町」周辺は、日蓮宗江戸十大祖師の幸國寺、新宿山之手七福神の経王寺、曹洞宗の法身寺、顕本法華宗の常楽寺、日蓮宗の瑞光寺など、多彩な宗派の御朱印・御首題が拝受できるエリアとなっています。
多聞院のお隣の浄輪寺には江戸時代の和算家で算聖とあがめられた関孝和の墓があり、御首題も授与されています。

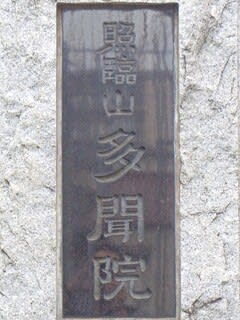
【写真 上(左)】 参道入口(工事中)
【写真 下(右)】 山院号表札


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 鐘楼
多聞院の入口は外苑東通りに面し、やはり坂道の参道となっています。
入口にはコンクリ造の山門がありその上部の鐘楼もスクエアなコンクリ造でモダンなイメージ。
左手には真新しい「牛込四恩の杜」(公園墓地?)があり、よく整備された印象です。


【写真 上(左)】 整備された山内
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
少し参道をのぼると、いきなり寺院づくりの本堂があらわれます。
本堂向かって左手の庫裡もモダンなイメージですが、本堂まわりだけは伝統的な寺院のイメージを保ち、独特のコントラスト。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝と整った意匠で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股を備え、向拝見上げに山号扁額を掲げています。
勢いのある降り棟と留蓋上の獅子飾りがいい味を出しています。

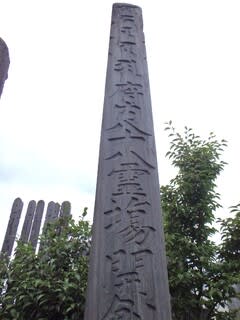
【写真 上(左)】 正等大阿闍梨供養塔
【写真 下(右)】 御府内霊場開創記念碑
山内には、御府内霊場の開基とも伝わる正等和尚の墓?(供養塔)、御府内霊場開創記念碑があります。
供養塔には「御府内八十八ヶ所開基 (通種子・ア)正等大阿闍梨百五十年供養塔 大正十二年六月十二日 大僧正●●●」とあります。
また、別の碑(祈念碑?)には「(梵字)府内八十八霊場開創」とあります。


【写真 上(左)】 吉川湊一の墓
【写真 下(右)】 庫裡
平家琵琶の奥義を極め、検校にまで昇進した吉川湊一(1748-1829年)、大正時代の女優・松井須麿子、大正時代の詩人・生田春月の墓所もあります。
御朱印は本堂向かって左のモダンな庫裡で拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

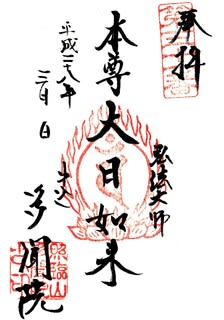
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三十一番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています
■ 第32番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺
(えんまんじ)
文京区湯島1-6-2
真言宗御室派
御本尊:不動明王・十一面観世音菩薩
札所本尊:不動明王・十一面観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第32番、弘法大師二十一ヶ寺第1番、御府内二十八不動霊場第25番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第1番、弁財天百社参り番外27
司元別当:
授与所:ビル内寺務所
第32番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに圓満寺なので、御府内霊場開創時から一貫して湯島の圓満寺であったとみられます。
下記史料を参照して縁起・沿革を追ってみます。
圓満寺は、寶永七年(1710年)、木食覺海義高上人が湯島の地に梵刹を建て、萬昌山圓満寺と号したのが開山といいます。
開山の「木食義高」に因んで「木食寺」とも呼ばれます。
義高上人は、足利13代将軍義輝公の孫義辰の子とも(義輝公の孫とも)伝わります。
幼くして出家、日向國佐土原の福禅寺に入り木食となりました。
寛文八年(1668年)から東国に下り各地に堂宇を建立、大いに奇特をあらわされて伝燈大阿闍梨権僧都法印に任ぜられました。
元禄四年(1691年)江戸に赴かれ本郷三組町に住むと、常憲公(5代将軍徳川綱吉公)や浄光院殿(綱吉公の正室・鷹司信子)の帰依を受け御祈祷を申しつけられています。
文昭公(6代将軍家宣公)の帰依も受け、家宣公は上人を以て当寺の(公的な?)開山とされたとのこと。
当山は開創時から真言宗御室派(当時は仁和寺御室御所)と所縁があったとみられます。
義高上人と御室御所について、『江戸名所図会』に「延寶七年(1679年)御室宮へ参るに、高野山光臺院の住持職に任ぜらる。」とあります。
「御室宮」はおそらく「仁和寺御室御所」で、上人は「御室御所」に参内された後、高野山光臺院の住持職に任ぜられています。
高野山光臺院は現存し、その公式Webには「当院は白河天皇の第四皇子覚法親王の開基で(約900年前)以来27代にわたり法親王方が参籠されている。それによって当院は「高野御室」と称され、非常に由緒ある名刹」とあります。
さらに「御室御所」についてたどってみます。
仁和寺の公式Webには「仁和2年(886年)第58代光孝天皇によって「西山御願寺」と称する一寺の建立を発願されたことに始まります。しかし翌年、光孝天皇は志半ばにして崩御されたため、第59代宇多天皇が先帝の遺志を継がれ、仁和4年(888年)に完成。寺号も元号から仁和寺となりました。」「宇多天皇は寛平9年(897年)に譲位、後に出家し仁和寺第1世 宇多(寛平)法皇となります。以降、皇室出身者が仁和寺の代々住職(門跡)を務め、平安〜鎌倉期には門跡寺院として最高の格式を保ちました。」とあります。
高野山光臺院は高野山内の門跡寺院で、その由緒から仁和寺御室御所と関係があり「高野御室」と称されていたのでは。
義高上人は仁和寺御室御所に参内してその才を認められ、時をおかずに御室御所所縁の高野山光臺院の住持職に任ぜらたのではないでしょうか。
むろん氏素性の明らかでない者が門跡寺院に参内できる筈はなく、おそらく義高上人が足利13代将軍義輝公の曽孫(ないし孫)という出自が効いたものと思われます。
中世の東密(真言宗)は小野六流・広沢六流の十二流に分化し、そこからさらに法脈を広げたといいます。
このうち広沢流の中心となったのが仁和寺御室御所です。
いささか長くなりますが、その経緯について『呪術宗教の世界』(速水侑氏著)を参照してたどってみます。
第52代嵯峨天皇は弘法大師空海の理解者で、東寺を賜った帝として知られています。
第59代の宇多天皇も仏教、ことに密教への帰依篤く、寛平九年(897年)の突然の譲位は、仏道に専心するためという説があるほどです。
宇多天皇は東寺長者の益信僧正(本覚大師)に帰依されたといいます。
益信僧正は弘法大師空海から第4世の直系で、東密広沢流の祖とされる高僧です。
昌泰二年(899年)、33歳の宇多上皇が仁和寺で出家する際に、益信僧正は受戒の師となり寛平法皇(法号は空理)と号されました。
延喜元年(901年)12月、益信僧正は東寺灌頂院にて法皇に伝法灌頂を授け継承者とされたといいます。
延喜四年(904年)、法皇は仁和寺に「御室御所」を構えられ、以降、仁和寺は東密の門跡寺院として寺勢大いに振いました。
法皇の弟子の寛空は嵯峨の大覚寺に入られ、寛空の弟子の寛朝は広沢に遍照寺を開かれました。
この寛平法皇(宇多天皇)所縁の法流が、後に「広沢流」と呼ばれることとなります。
一方、醍醐寺を開かれた聖宝(理源大師)ないしその弟子筋の仁海(小野僧正)も法流を興され、こちらは「小野流」と呼ばれます。
洛東の小野、洛西の広沢は東密の二大潮流となり、さらに分化していきました。
広沢流:仁和御流、西院流、保寿院流、華蔵院流、忍辱山流、伝法院流の六流
小野流:勧修寺(小野)三流(安祥寺流、勧修寺流、随心院流)
醍醐三流(三宝院流、理性院流、金剛王院流)の六流
これらを総じて「野沢(やたく)十二流」といいます。
広沢流と小野流の違いについては、
・広沢流は儀軌を重視、小野流は口伝口訣を重視
・広沢流は「初胎後金」、小野流は「初金後胎」(両部灌頂を行うときに胎蔵界、金剛界いずれを先にするかの流儀)
などが論じられるようです。
東密が分化したのは事相(修法の作法など)の研究が進んだため、というほど修法の存在は大きく、たとえば雨乞いの修法を修するときに
・広沢流は孔雀経法、小野流は請雨経法
という説もみられたようです。
『呪術宗教の世界』では、例外もみられるとして修法における差異については慎重に扱われていますが、それだけ東密に対する「秘法」の要請が強かったとしています。
(「他の流派にない霊験ある秘法を相承することで、貴族たちの呪術的欲求にこたえ、流派独自の秘法として主張喧伝された。」(同書より抜粋引用))
話が長くなりました。
ともあれ、仁和御流は高い格式をもつ門跡寺院・仁和寺を中心に東密「広沢流」の中核をなしました。
なお、Wikipediaには「仁和寺の仁和御流(真言宗御室派)」と記され、仁和御流が真言宗御室派に承継されていることを示唆しています。
仁和御流(真言宗御室派)は西日本中心の流派で、現在の総本山は仁和寺(京都市右京区)、大本山は金剛寺(大阪府河内長野市)と大聖院(広島県廿日市市)、準大本山は屋島寺(香川県高松市)です。
別格本山もほとんどが西日本で、これは仁和寺は江戸時代末期まで法親王(皇族)を迎えた門跡寺院で、京の皇室との所縁が深いということがあるのでは。
しかし、江戸時代の江戸にも仁和寺末を名乗る寺院はいくつかありました。
そのひとつが湯島の圓満寺です。
寶永七年(1710年)、義高上人が湯島の地に圓満寺を開山された以前に、上人は「御室御所」と所縁をもち、おそらく「御室御所」から高野山光臺院(「高野御室」)の住持職を託されています。
その義高上人が江戸に開山された圓満寺が「京仁和寺末」となるのは、自然な流れかと思われます。
(『御府内寺社備考』に「御室御所より院室御影●之節 圓満寺の寺号(以下不詳)」とあり。)
御府内霊場では当山のほか、第41番密蔵院が真言宗御室派です。
義高上人は日暮里の補陀落山 養福寺(豊島霊場第73番ほか)を中興開山と伝わりますが、養福寺は真言宗豊山派(新義真言宗)となっています。
Wikipediaによると、明治初期の火災で伽藍を焼失し、明治20年に相模の大山寺の協力の下で再建されたものの関東大震災、東京大空襲で焼失しています。
昭和38年木造の本堂が再建、昭和53年にはRC造の「おむろビル」に改築され、ビル内の寺院となっています。
なお、Wikipediaには「御室派総本山仁和寺の東京事務所」とあり、おむろビルの袖看板にも「総本山 仁和寺 東京事務所」とあります。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)
三十二番
ゆしま四丁目
萬昌山 金剛幢院 圓満寺
御直末
本尊:十一面観世音菩薩 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [68] 湯嶋寺院書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.2』
本寺 御室御所仁和寺宮 (御室御所院室)
湯島 不唱小名
萬昌山 金剛幢院 圓満寺
開山 開山木食覺海義高僧正者 将軍光源院(足利)義輝公の御子
本堂
本尊 七観音尊木立像 紀伊殿●御寄附
十一面観世音尊 秘佛 如意法尼内親王之御作
歓喜天尊 秘佛
多聞天木立像 開山義高僧正作
両部大日如来木座像
不空羅索尊木座像
千手観音尊木座像
薬師如来木座像 日光月光立像 十二神将立像
愛染明王木座像
孔雀明王尊影
五大虚空蔵尊影
常倶梨天尊影
位牌所
地蔵菩薩木立像(ほか)
鐘楼堂
阿弥陀如来天竺佛座像 等持院殿守本尊
当寺開山義高権僧正御影
弘法大師●筆 楷書心経巻物
六観音 弘法大師之作
辨財天木座像 弘法大師之作
胎蔵界大日如来木座像 弘法大師之作
御香宮明神木像
三尊来迎
天満宮渡唐神像
十六善神
地蔵尊 二童子有
刀八毘沙門天神像 尊氏公軍中守本尊
大師目引之尊影 真如親王之御筆 高野山御影堂に有し●
十六羅漢御影
阿育王塔石
多寶塔
護摩堂
不動明王 二童子附 秘封 弘法大師作
前立五大尊明王
閻魔天木座像
金佛地蔵尊座像
秋葉社
鐘楼堂
辨財天社
辨財天女木立像
稲荷大明神 秘封
大黒天木立像
恵比須神木座像
千手観音木座像
青面金剛木立像
地蔵堂 石地蔵尊立像
七観音堂 本堂の左にあり
十一面観音
■ 『江戸名所図会 第3 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)〔要旨抜粋〕
萬昌山圓満寺
湯島六丁目にあり。真言宗にして、開山は木食義高上人なり。本尊十一面観世音、如意法尼の御作なり。法尼は淳和帝の妃にして弘法大師の御弟子なり。左右に六観音を安置す。当寺を世に木食寺と称す。
寺伝に曰く、開山木食義高上人は覺海と号す。足利十三代将軍義輝公の孫義辰の息なり。
日向國に産る。幼より瑞相あるに仍て出家し、肥後國(日向國?)佐土原の福禅寺に入りて、覺深師に随従し、木食となれり。寛文八年(1668年)、衆生化益のために東奥に下り、あまねく霊地を拝しこゝかしこに堂宇を建立す。(略)伝燈大阿闍梨権僧都法印に任ぜらる。其後西國に赴くの頃も、大に奇特を顕す。延寶三年(1675年)都に上り堀河姉小路多聞寺に止宿(略)延宝五年(1677年)江城湯島の地に至り、大に霊験をあらはす。延寶七年(1679年)御室宮へ参るに、高野山光臺院の住持職に任ぜらる。元禄四年(1691年)志願によって光臺院を辞して江戸に赴き、本郷三組町に住せらる。常憲公(5代将軍徳川綱吉公)および浄光院殿(綱吉公の正室・鷹司信子)、須山女を以て御祈祷を仰附けらる。寶永六年(1709年)上京(略)寶永七年(1710年)江戸湯島の地に梵刹を建てゝ、萬昌山圓満寺と号す。文昭公(6代将軍家宣公)の御志願に仍て、則ち上人を以て当寺の開山とす。

「圓満寺」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
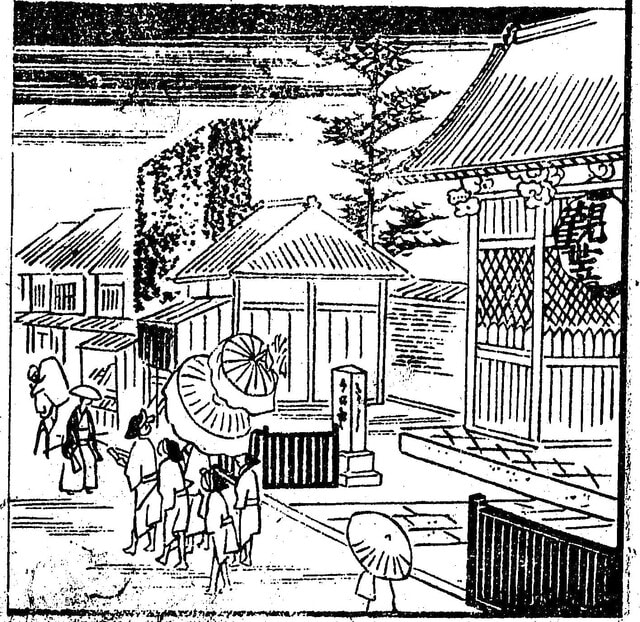
「圓満寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本郷湯島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
JR・メトロ丸ノ内線「お茶ノ水」駅から徒歩約5分、オフィス街に建つ「おむろビル」のなかにあります。
現在、土祝日はビルのセキュリティの関係上入館不可につき平日のみ参拝可のようです。
ごくふつうのオフィスビルのエントランスですが、袖看板に「圓満寺」とあり、かろうじて館内に寺院があることがわかります。

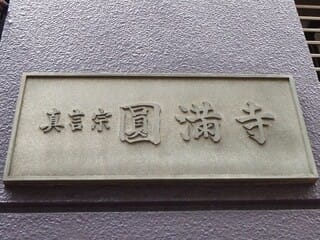
【写真 上(左)】 おむろビル全景
【写真 下(右)】 寺号標

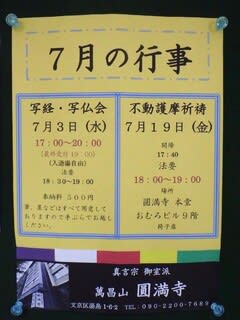
【写真 上(左)】 寺号の袖看板
【写真 下(右)】 行事予定
貼り出されていた行事予定によると、不動護摩祈祷や写経会が開催されているようです。


【写真 上(左)】 エントランス
【写真 下(右)】 8階エレベーターホールの「授与所」
受付は8階、本堂は9階でエレベーターでのぼりますが、通常9階は不停止となっているようです。
8階にどなたかおられるときは、申し入れれば本堂参拝可能な模様ですが、筆者参拝時(2回)はいずれもご不在で、8階からの遙拝となりました。
8階にはエレベーターホールに書置御朱印が置かれているので、ここから遙拝しました。
上層階の御本尊に向かって、階下のエレベーターホールからの参拝ははじめてで、不思議な感じですが、これはこれで「都心のお遍路」ならではの雰囲気は味わえるかと思います。
史料によると、当山は数多くの尊像を奉安されていたようですが、そのお像は現在本堂に安置されているのでしょうか。
『寺社書上』(文政年間(1818-1831年))では、御本尊は七観音木像。
『御府内寺社備考』(同)では本堂本尊は七観音木像、十一面観世音(秘佛、如意法尼内親王御作)。
『江戸名所図会』(天保年間(1831-1845年))では、御本尊は十一面観世音(如意法尼の御作)。
『御府内八十八ケ所道しるべ』(幕末-明治)では、札所本尊は十一面観世音菩薩、不動明王、弘法大師とあります。
さらにWikipediaには「明治初期の火災までは、以下の寺宝があった。 七観音(旧本尊)」とあります。
また『御府内寺社備考』には「七観音堂 本堂の左にあり 十一面観音」「護摩堂 不動明王 二童子付秘封 弘法大師作」とあります。
以上から、江戸時代の御本尊は七観音木像、ないし十一面観世音(如意法尼内親王御作)とみられます。
七観音木像は明治初期の火災で焼失?し、御本尊は十一面観世音菩薩(如意法尼内親王御作)となり、明治20年に「関東三大不動」で不動尊とのゆかり深い相模・大山寺の協力で再建された際に、十一面観世音菩薩・不動明王の両尊御本尊となったのでは。
こちらの不動明王は、護摩堂本尊の不動明王(弘法大師御作)、ないしは大山寺から奉安された尊像と考えられます。
明治初期来、数度の火災に遭い古文書など焼失されているようなので詳細は不明です。
御朱印は8階エレベーターホールに置かれていたものを拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(規定用紙貼付)
中央に「本尊不動明王」「十一面観世音菩薩」「弘法大師」の印判と十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の印判と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第三十二番」の札所印。山号の印判と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-11)
【 BGM 】
■ 名もない花 - 遥海
■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん
■ Parade - FictionJunction
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】
アクセスが急に増えたと思ったら、たしかにお彼岸のイベントですね。
アゲてみます。
-------------------------
2021/06/22 UP
江戸時代、江戸の庶民、とくに女性に広く信仰を広めた札所詣がありました。
「武州江戸六阿弥陀詣」です。
江戸名所図会など江戸期の絵図にも多くとりあげられ、逸話も多いので時間をかけてじっくり構成してみたいと思いますが、まずは初稿としてUPしてみます。
なお、「 滝野川寺院めぐり」の記事と重複する内容があります。
ボリュームがあるので、前編と後編に分けます。
■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】
■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 後編 】
--------------------------------------------

『江戸名所図会』(常光寺境内説明板より)


【写真 上(左)】 第1番目 西福寺
【写真 下(右)】 第2番目 恵明寺
武州江戸六阿弥陀霊場(江戸六阿弥陀)は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木で刻した阿弥陀仏、残り木(末木)で刻した聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、女人成仏の阿弥陀仏として崇められ、江戸中期から大正時代にかけて、とくに春秋の彼岸の頃に女性を中心として盛んに巡拝されたといわれます。
開創年代については諸説あり錯綜していますが、札所は確定しています。
第1番目 三縁山 無量壽院 西福寺
北区豊島2-14-1 真言宗豊山派
第2番目 宮城山 円明院 恵明寺(旧小台村延命院)
足立区江北2-4-3 真言宗系単立
第3番目 佛寶山 西光院 無量寺
北区西ケ原1-34-8 真言宗豊山派
第4番目 宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1 真言宗豊山派
第5番目 福増山 常楽院
調布市西つつじヶ丘4-9-1(旧下谷(上野)広小路) 天台宗
第6番目 西帰山 常光寺
江東区亀戸4-48-3 曹洞宗
木余の弥陀 龍燈山 貞香院 性翁寺
足立区扇2-19-3 浄土宗
木残(末木)の観音 補陀山 昌林寺
北区西ケ原3-12-6 曹洞宗

※国土地理院ウェブサイト掲載の「地理院地図」を筆者にて加工作成。
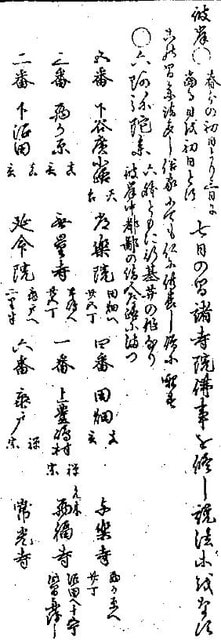
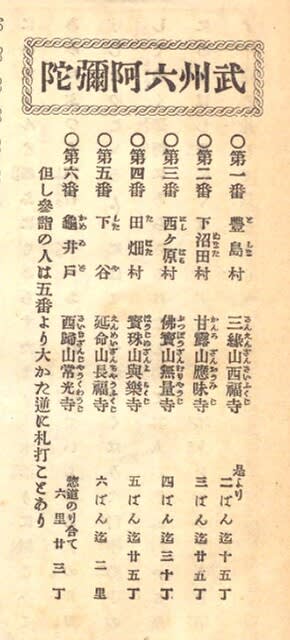
【写真 上(左)】 『東都歳時記』の札所一覧(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載・原データ)
【写真 下(右)】 『滑稽名作集. 上/六あみだ詣 上編・十返舎一九題』の札所一覧 (国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載・原データ)
■常光寺「六阿弥陀道道標」説明板より
「江戸六阿弥陀詣とは、江戸時代、春秋の彼岸に六ヶ寺の阿弥陀仏を巡拝するもので、その巡拝地は順に上豊島村西福寺(北区)、下沼田村延命院(足立区)、西ヶ原無量寺(北区)、田端村与楽寺(北区)、下谷広小路常楽院(調布市に移転)、亀戸村常光寺となっていました。江戸六阿弥陀には奈良時代を発祥とする伝承がありますが、文献上の初見は明暦年間(1655-58年)であることから、六阿弥陀詣は明暦大火後の江戸市中拡大、江戸町方住民の定着にともなう江戸町人の行楽行動を示すものといえます。」
江戸六阿弥陀についてまとめた文献は多数ありますが、ここでは下記2資料を主に参考とし、適宜引用させていただきました。
1.「江戸の3 つの『六阿弥陀参』における『武州六阿弥陀参』の特徴」/古田悦造氏(リンク、以下「資料1」とします。)
2.「『篤信』の『商売人』 - 東天紅上野本店裏手の常楽院別院に関する調査報告 -」/徳田安津樹氏(リンク、以下「資料2」とします。)
順路については、『東都歳時記』によると札番どおりではなく、第5番目 常楽院 → 第4番目 與楽寺 → 第3番目 無量寺・木残(末木) 昌林寺 → 第1番目 西福寺 → 第2番目 延命院 (現・恵明寺)・木余 性翁寺 → 第6番目 常光寺〔結願〕という時計回りのコースが多くとられたようです。
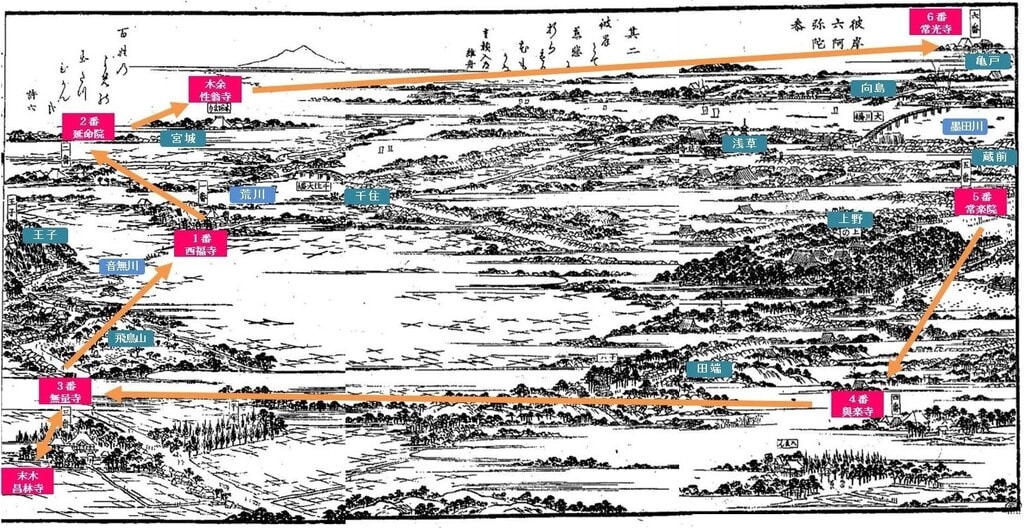
※ 『東都歳事記. 春之部 下』(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載・加工)
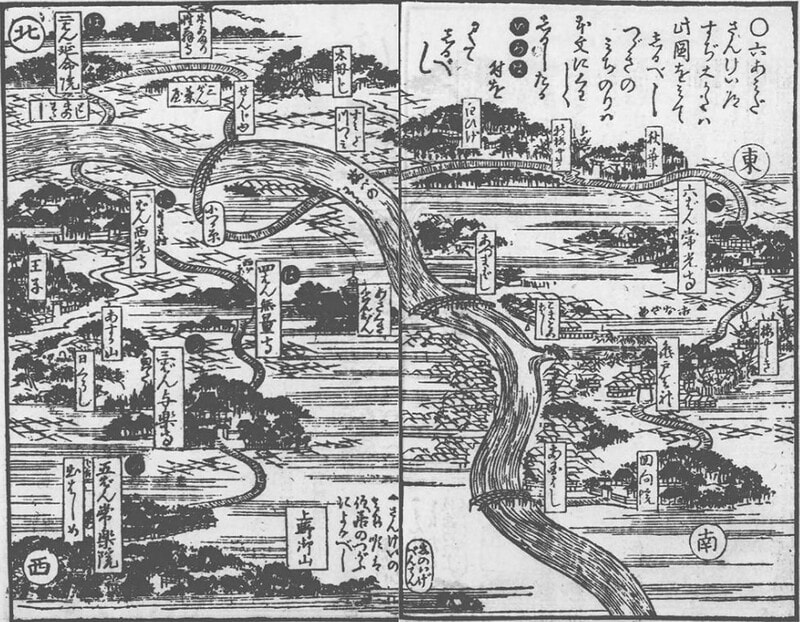
※ 『東都遊覧年中行事』(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
各寺院の縁起や由緒、足立区資料、および「資料1」「資料2」などから江戸六阿弥陀の創祀を辿ってみます。
**********************
〔 足立姫伝説 〕
その昔この地に「足立の長者」(足立庄司宮城宰相とも)という人がおり、年老いて子がないことを憂いて、日頃から尊崇している熊野権現に一途に祈ると女の子を授かりました。
「足立姫」と呼ばれたこの子は容顔すこぶる麗しく、見るものはみな心を奪われたといいます。
生来仏を崇うことが篤く、聡明に成長した姫は「豊嶋の長者」(豊島左衛門尉清光とも)に嫁いだものの、嫁ぎ先で誹りを受け、12人(5人とも)の侍女とともに荒川に身を投げ命を絶ってしまいました。
足立の長者はこれを悲しみ、娘や侍女の菩提のために諸国の霊場巡りに出立しました。
紀州牟宴の郡熊野権現に参籠した際、霊夢を蒙り1本の霊木を得て、これを熊野灘に流すと、やがてこの霊木は国元の熊野木(沼田の浦とも)というところに流れ着きました。
この霊木は不思議にも夜ごと光を放ちましたが、折しもこの地を巡られた行基菩薩は(この霊木は)浄土に導かんがための仏菩薩の化身なるべしと云われ、南無阿弥陀仏の六字の御名号数にあわせて霊木から六体の阿弥陀如来像を刻し、余り木からもう一体の阿弥陀仏、さらに残った木から一体の観音菩薩像を刻まれそれを姫の遺影として与えました。
後にこれら七体の阿弥陀仏と一体の観音像は近隣の寺院に祀られ、以降、女人成仏の阿弥陀詣でとしてとくに江戸期に信仰を集めました。
※なお、資料によっては、足立姫は豊嶋左衛門清光の娘、嫁ぎ先を足立少輔家にしているものがあります。
この哀しい逸話は「足立姫伝説」とも呼ばれ、このエリアに広く伝わるものです。
『滝野川寺院めぐり案内』の無量寺の頁に「江戸近郊を歩くこのミニ巡礼は、表向きは信心とはいうものの、実際は世代家族の同居が当たり前だった時代の、年に2回のストレス解消とレクリエーションの一石二鳥の効果を狙ったものであった。まさに庶民が、日常生活の中から考えた知恵だったのであろう。」と記載されていますが、江戸の年中行事を描いた『東都歳時記』や『江戸名所図絵』でも複数取り上げられていることからも、そのような側面が大きかったと思われます。
「足立姫伝説」の経緯からは娵姑の確執がうかがわれ、このような背景もあってか、第6番目の常光寺のWebでは「六番は嫁の小言の言いじまい」「六阿弥陀嫁の小言(噂)の捨て処」の川柳が紹介されています。
気候のよい春秋の彼岸の一日、気の合ったお仲間と連れだって、日頃の鬱憤の発散をはかる庶民の姿がうかがわれます。

※ 『江戸名所図会』7巻[17](国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
「資料2」では柳沢吉保の孫・信鴻作の『宴遊日記』からつぎの描写が紹介されています。(安永六年(1777年)2月の項)
「今日彼岸の終り阿弥陀参り往来甚賑し、天色大に晴、西南白雲如刷、平塚明神鳥居前より坂道を下り、利島郡へ行、行人にて塗甚込合、五歩六歩に路上仏を居へ、村姥数人念仏を唱へ、或ハ太鼓・鐘をうち建立の法施を請者夥く、疥癬の乞僧路上に満ち、辻博突有、畝中路上皆貝売雪の如し」

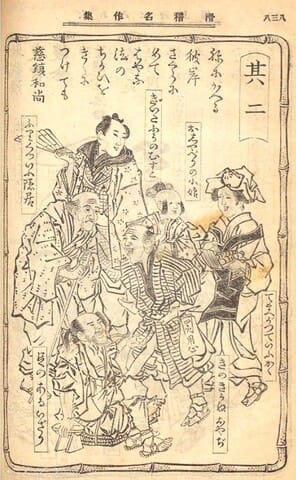
※ 『滑稽名作集. 上/六あみだ詣 上編・十返舎一九題』(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
また、十返舎一九の『六あみだ詣 上編』には下記の描写があります。(国会図書館DC)
「彼岸功徳経に曰。二八月七日の間無数萬億のぼさつ。法を説て衆生楽をあたへ給うなりと。其外諸経にも見へて。春秋二度の彼岸には。人間の罪障消滅の縁ふかく。佛に法施し。僧に供養するの時なりとて。六阿彌陀詣といふ事。いつの頃にやはじまり。六ヶ所の霊地に貴きも賤しきも。あみだの光も地獄のさたも。銭次第とてはやみちに。臍くりをとりこみ。巾着のひもながき麗なるに。打ちむれつヽ一乗無外の色のよの中。とぢぶたとつれだつ破鍋(われなべ)あれば。餅をつく桃灯は。ぬれたる祖母の腰つきを思ひやり。佛性常住の吸筒をかたげ。一色一香のにぎりめしをふところにして。ぬらりくらりの牛は牛づれ。馬は馬づれ。はなしつれてゆく中にも。(以下略)」
「資料2」によると、六阿弥陀伝説が最初に記されたのは江戸時代前期成立の『六阿弥陀伝説』とみられ、すべての札所(寺院所在)が明確にされたのは貞享四年(1987年)の『江戸鹿子』とのことです。
なお、京都今熊野の新熊野神社の公式Webによると、熊野本宮大社の本地は阿弥陀如来で「この当時(平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて)の当時の熊野信仰を一言でいうと、本地垂迹説に基づく神仏習合信仰と浄土信仰が一体化した信仰ということになろう。」とあるので、江戸六阿弥陀が熊野とつながりをもつのは自然な成り行きであったともみられます。
それでは第1番目から順にご紹介していきます。
なお、御朱印については8箇寺すべてで授与されておられますが、多くが授与所ではなく庫裡での授与で、タイミングや状況によっては拝受できない可能性もあるかもしれません。
ある程度御朱印拝受に慣れた方向けの札所詣のような感じがしています。
■ 第1番目 三縁山 無量壽院 西福寺
北区豊島2-14-1
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:豊島八十八ヶ所霊場第67番、荒川辺八十八ヶ所霊場第20番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.江戸六阿弥陀霊場第1番目
朱印尊格:阿弥陀如来
2.豊島八十八ヶ所霊場第67番
朱印尊格:阿弥陀如来
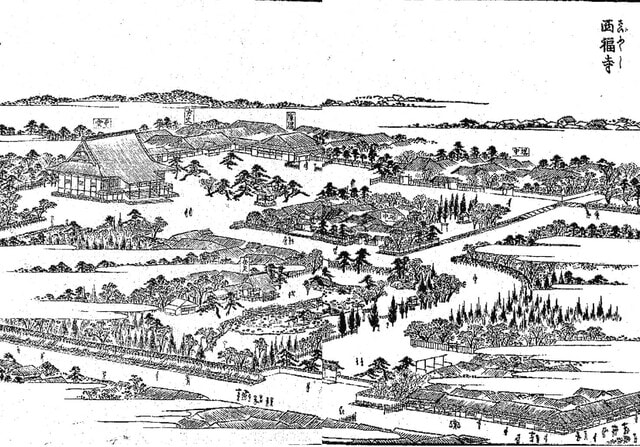
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
「足立姫伝説」の登場人物、豊嶋左衛門清光の創建(開基)と伝わる古刹で、六阿弥陀第1番目の阿弥陀如来をご本尊としています。
「是世に所謂六阿彌陀の一なり、縁起を閲するに、聖武帝御宇當國の住人豊嶋左衛門清光、紀伊國熊野権現を信し、其霊夢に因て一社を王子村に建立し、王子権現と崇め祀れり、然るに清光子なきを憂ひ彼社に祈願せしに、一人の女子を産す、成長の後足立少輔某に嫁せしか、奩具の備はらさるを以少輔に辱しめられしかは、彼女私に逃れ荒川に身を投て死す、父清光悲に堪す是より佛教に心を委ねしか、或夜霊夢に因て異木を得だり、折しも行基當國に来りし故、清光其事を告しに行基即ちかの異木を以て六體の阿弥陀を彫刻し、近郷六ヶ所に安置して彼女の追福とせり、故に是を女人成佛の本尊と稱す、當寺の本尊は其第一なり、次は足立郡小臺村、第三は當郡西ヶ原村、第四は田畑村、第五は江戸下谷、第六は葛飾郡亀戸村なりと云、此説もとより妄誕にして信用すへきにあらされと、當寺のみにあらす残る五ヶ所とともに、少の異同はあれと皆縁起なとありて世人の口碑に傳る所なれは、其略を記しおきぬ、且清光は権頭と稱し、治承の頃の人なれは行基とは時代遥に後れたり」
(『新編武蔵風土記稿』 → 国会図書館DCより)
「此説もとより妄誕にして信用すへきにあらされと、當寺のみにあらす残る五ヶ所とともに、少の異同はあれと皆縁起なとありて世人の口碑に傳る所なれは、其略を記しおきぬ」とあり、江戸六阿弥陀の創祀伝承については疑義をはさんでいます。
ただし文面からは、六阿弥陀の伝承は人口に膾炙し、信仰も広がっていたことがうかがわれます。
江戸六阿弥陀の寺院の縁起や由緒をみると、
A.足立姫の父は足立(沼田)庄司(従二位宰相藤原正成)、嫁ぎ先は豊島左衛門尉清光
B.足立姫の父は豊島左衛門尉清光、嫁ぎ先は足立の沼田治部少輔
の2パターンあることがわかります。
当寺の縁起は、B.足立姫の父は豊島左衛門尉清光のパターンです。
足立氏(藤原氏流)も豊島氏も中世には豊島郡・足立郡に勢力を張った有力氏族です。
足立氏と豊島氏の関係については未だ調べていませんが、対抗関係にあったとすると、その関係が「足立姫伝説」を介して伝わった可能性もあるかもしれません。
豊島清光は中世に豊島郡を領した武将で、史料から正式名は”清元”とされています。
治承四年(1180年)、石橋山の戦いで敗れ、安房国から再挙を図った源頼朝軍に合流し、鎌倉に入って幕府御家人に列しました。
清光・清重父子は奥州合戦の遠征軍に加わり、清重は戦功を挙げて戦後に奥州総奉行に任ぜられています。
豊島清光の館は当寺からもほど近い清光寺とされ、清光寺には豊島清光の木像が祀られています。(清光寺も豊島霊場の札所なので、御朱印を拝受できます。)
飛鳥山から流れ下る石神井川(滝野川・音無川)が荒川に合流するすぐそばにあり、王子駅前からだと徒歩15分弱です。
境内は広く、多くの見どころがあります。


【写真 上(左)】 石柱門
【写真 下(右)】 身代地蔵菩薩
通りに面した石柱門の右手には「身代地蔵菩薩」が御座します。
美貌で高慢な双六好きの藤原氏のお姫様の危機を救われ、改心したお姫様の信仰を受けたという逸話をもつお地蔵さまです。


【写真 上(左)】 境内参道
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 奉石橋の碑
【写真 下(右)】 六地蔵
参道正面が山門。三間一戸の八脚門で屋根は本瓦葺、唐破風の下に天井絵をはじめ艶やかな彩色の意匠が施されています。
手前は仁王尊二体。本堂側には風神、雷神が御座す見どころの多い山門です。
山門の手前右手の六地蔵は、「逆さ卍の六地蔵」として知られる石仏です。


【写真 上(左)】 風神
【写真 下(右)】 雷神


【写真 上(左)】 中門前
【写真 下(右)】 中門
さらに参道を進むと正面が中門。おそらく三間一戸の八脚門ですが山門よりはシックなつくで、山門と中門のふたつの門がいいコントラストを見せています。
手前に「関東六阿彌陀元木第壱番霊場」の札所標。
江戸六阿弥陀は「関東六阿弥陀」とも呼ばれたと伝わりますが、これを裏付けるものです。
中門手前左右の獅子はともに阿形で、ちよっと変わった表情をしています。
左手に御座す端正なお顔立ちのお地蔵様と正面上手の「六阿弥陀第壱番」の赤い提灯が、女人霊場らしい華やぎを醸しています。


【写真 上(左)】 札所標と中門
【写真 下(右)】 本堂前
中門は閉ざされているので脇から回り込みます。
中門から本堂までは回廊形式で朱塗りの柱梁の屋根がかかっています。
正面は左右にたくさんの絵馬がかかった、信仰の篤さを伝える本堂です。
本堂の全容は明らかでないですが、近代建築かと思われます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 阿弥陀如来と本堂


【写真 上(左)】 阿弥陀如来
【写真 下(右)】 岩清水六阿弥陀
本堂向かって右に、御本尊のお前立ちとみられる阿弥陀如来が御座します。
蓮華座に結跏趺坐され、光背に化仏を配し、来迎印(上品下生印)を組まれる存在感あるおすがたで、さすがに阿弥陀霊場発願札所です。
境内にはほかにもさまざまな見どころがあります。
・お馬塚
「よさこい節」の一節 ”土佐の高知のはりまや橋で坊さんかんざし買うを見た”の逸話の主人公「お馬」の墓所が当寺であることが確認されたため、昭和47年に建立されたものです。
土佐の2人のイケメンの僧と、美しい鋳掛屋の娘「お馬」の間で繰り広げられた波瀾万丈の恋物語で、メインの舞台は土佐ですが、「お馬」は2人の僧いずれとも結ばれず、土佐の大工・寺崎氏と結婚し、明治中期に東京に移り、没後西福寺に入りました。
→「お馬」の恋物語の概要
物見高い江戸っ子のことゆえ、この色恋沙汰の物語が知られていれば「お馬」とこのお寺は一大観光?スポットとなった筈ですが、このお話しは幕末が舞台で、しかも当寺との関係が確認されたのは昭和も後期。
さすがの江戸っ子も、これでは駆けつけるすべもありません。
・奉石橋の碑
石神井川に架かる現在の豊石橋は、以前は氾濫のたびに流され、かつてこの地を訪れた夫婦の六部(巡礼者)が川を渡れずに困っていたところ、村人たちが助力してこの六部を安全に渡しました。
その後、「秩父のある方から頼まれて来た」という石屋が立派な橋を架け、一体の石のお地蔵さまを納めて帰っていきました。村人たちは「秩父のある方」がかの六部であると悟り、感謝の意を込めて「奉石橋」と名付けたと伝わります。
・岩清水六阿弥陀
境内の一角にあります。
中央に当山の施無畏印・与願印の立像の阿弥陀如来。左右に定印を結ばれる五体の阿弥陀如来坐像が御座し、六阿弥陀各寺の寺号が刻まれています。
江戸六阿弥陀発願寺としての矜持が感じられる六阿弥陀です。


【写真 上(左)】 当山(壱番目)
【写真 下(右)】 弐番目 恵明寺


【写真 上(左)】 参番目 無量寺
【写真 下(右)】 四番目 與楽寺


【写真 上(左)】 五番目 常楽院
【写真 下(右)】 六番目 常光寺
御朱印は庫裡にて拝受しました。
豊島八十八ヶ所霊場第67番の札所でもあり、そちらの御朱印も授与されています。
● 江戸六阿弥陀如来第1番目の御朱印
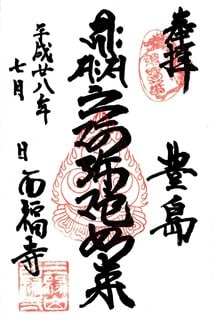
中央に宝珠印(蓮華座+火焔宝珠)、「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と右上に「第壱番」の札所印。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
なお、中央上部に阿弥陀如来の種子(キリーク)、右に聖観世音菩薩の種子(サ)、左に勢至菩薩の種子(サク)が揮毫された阿弥陀三尊様式は、江戸六阿弥陀の御朱印で複数みられるものです。
〔 豊島霊場の御朱印 〕
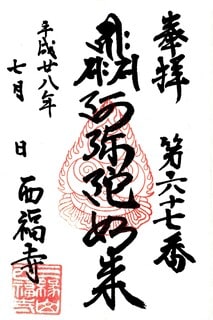
基本的な構成は江戸六阿弥陀と同様ですが、こちらは尊格揮毫が「阿弥陀如来」。
右に豊島霊場の札番「第六十七番」の揮毫があります。
■ 第2番目 宮城山 円明院 恵明寺
足立区江北2-4-3
真言宗系単立
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:荒綾八十八ヶ所霊場第54番、荒川辺八十八ヶ所霊場第21番(旧小台村延命寺)、第23番、第24番(旧沼田村能満寺)、第25番(旧宮城村円満寺)、第26番(旧小台村正覚寺)、第27番(旧小台村観性寺)
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.江戸六阿弥陀霊場第2番目
朱印尊格:阿弥陀如来
御本尊の阿弥陀如来は六阿弥陀第2番目で、明治9年(1876年)小台の延命寺を合併の際、延命寺から移られたものと伝わります。(よって、江戸期の第2番目は延命寺)
新編武蔵風土記稿巻之百三十六 足立郡之二 小臺村の「阿彌陀堂」が小台の延命寺を指すものとみられます。
「六阿彌陀堂と称する其第二番なり、沼田村の接地にあるを以て、人多く沼田の六阿彌陀といへり、其濫觴を尋るに、人王四十五代聖武帝の御宇、豊嶋郡沼田村に庄司と云もの一人の女子あり、隣村に嫁す、いかなる故にや其家の婢女と沼田川に身を投じて死せり、父の庄司悲の餘彼等追福の為にとて、所々の霊場を順拝し、紀州熊野山に詣でし時、山下にて一株の霊木を得たりしかば、則仏像を彫刻して、かの冥福を祈らんと、本國に帰りて後僧行基に託して、六軆の彌陀を刻し、分て此邊六ヶ寺に安置せし其一なるよし縁起に載す、尤うけがたき説なり、聖武帝の頃庄司と云ものあるべき名にあらず、且沼田村は豊嶋郡にはあらで本郡の地なり、かゝる杜撰の寺傳取べきにあらず、また隣村宮城村性翁寺の傳には、足立の庄司宮城宰相の女子、豊嶋左衛門尉に嫁せしが、故ありて神亀二年六月朔日侍女と共に荒川に投じて死す、其追福の為にかの熊野山の霊木を以て、行基に託し彫刻して此邊の寺院六ヶ寺に安すと云、神亀は聖武帝の年号にて、少しくたがひあれど同じ傳へなり(中略)されど此六阿弥陀のことは、世の人信ずることにて、其造立さまで近き頃のことゝも思はれず。」
(『新編武蔵風土記稿』 → 国会図書館DCより)
ここでも『風土記稿』は「かゝる杜撰の寺傳取べきにあらず」としながらも「されど此六阿弥陀のことは、世の人信ずることにて」と受け、創祀伝承に疑問を呈しながらも人々のあいだに「六阿弥陀」の信仰が広がっていることを記しています。
荒川辺八十八ヶ所霊場の札所であり、沼田村、宮城村、小台村の数寺の札所が恵明寺に移動していることから、3村の寺院が合併された可能性があります。
「猫のあしあと」様の情報によると、荒川辺霊場第21番の小台村延命寺)、第25番の宮城村円満寺、第26番の小台村正覚寺、第27番の小台村観性寺が荒川河川改修工事に伴い廃寺(第24番の沼田村能満寺は明治維新前に廃寺)となり、札所は本寺の恵明寺に移動したようです。
この影響か、現在の宮城、小台は隅田川と荒川に挟まれた島状のエリアで、寺院の数は少なくなっています。
創建年代等は不詳ですが、複数の末寺を抱えていたことからも想像されるとおり、山城国醍醐三宝院の直末で(足立風土記資料)、慶安元年(1648年)寺領二十石の御朱印状拝領の記録が残るこのエリア有数の古刹(中本寺格の寺院)です。
以前は鉄道駅から遠く陸の孤島的な立地でしたが、日暮里舎人ライナーが開通して交通の便がよくなりました。「扇大橋」駅から徒歩約9分で到着です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標と山門
荒川沿い、首都高江北JCTのそばにあります。
山門は本瓦葺の重厚な薬医門で、門前に大ぶりな寺号標、枝ぶりのいい青松と六阿弥陀・荒綾霊場併記の札所標を置く構えは、さすがに名刹の風格があります。
山門は常閉のようなので、脇の通用門から参内します。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 通用門


【写真 上(左)】 境内1
【写真 下(右)】 境内2
境内も手入れが行き届き、清々しい空気が流れています。
覆堂内に子育地蔵と数体のお地蔵さま。


【写真 上(左)】 子育地蔵
【写真 下(右)】 本堂への参道


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。身舎の材質は木造ではありませんが、色調がシックで落ち着いたたたずまい。
海老虹梁もしっかり造作され、向拝手前の青銅色の天水受がいいアクセントになっています。


【写真 上(左)】 向拝側面
【写真 下(右)】 天水受
恵明寺のもともとの御本尊は不動明王と伝わりますが、延命寺合併時に六阿弥陀の阿弥陀如来坐像(等身大の寄木造り)が御本尊となられたようです。
御朱印は庫裡にて授与いただきました。
荒綾八十八ヶ所霊場や荒川辺八十八ヶ所霊場の御朱印の授与については不明です。
● 江戸六阿弥陀第2番目の御朱印

中央に阿弥陀如来の種子キリークの御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と右に「第弐番」の札所印と「沼田」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第3番目 佛寶山 西光院 無量寺
北区西ヶ原1-34-8
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
他の札所:御府内八十八箇所第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第59番、大東京百観音霊場第81番、、滝野川寺院めぐり第9番
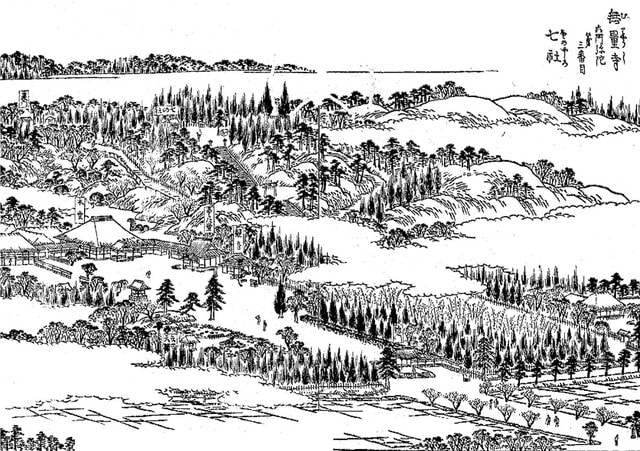
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
メジャー霊場、御府内八十八箇所第59番の札所なので、認知度は比較的高いと思います。
また、こちらは江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺(第3番目)で、もともと参詣者の多かった寺院とみられます。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル、古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ、常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ」
「寺寶 紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅」
「七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス 末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社」
「阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛 寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス」
創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。
また、北区設置の説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。
江戸時代には広大な寺域を有していたといわれ、当寺が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。
『江戸名所図会』には無量寺境内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」が表され、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったことがうかがわれます。
大正三年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。
なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現社地)に遷座されています。

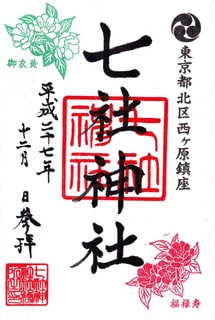
【写真 上(左)】 七社神社
【写真 下(右)】 七社神社の御朱印(旧)
西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。
旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅であり、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。
現在でも、落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。
内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)
このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に台地上を辿ります。
第七番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅方面からだと本郷通りを越えての道順となるので、本郷通りからかなりの急坂を下ってのアブローチとなります。
旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。
坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。
入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。
ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊
【写真 下(右)】 山門
参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。
そのおくに山門。この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門だと思います。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑


【写真 上(左)】 中門
【写真 下(右)】 秋の山内


【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道
【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼
さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある参道です。
緑ゆたかな境内は手入れも行き届き、枯淡な風情があります。
御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院だと思います。
左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。


【写真 上(左)】 見事な紅葉
【写真 上(左)】 冬の山内


【写真 上(左)】 早春の本堂
【写真 下(右)】 秋の本堂


【写真 上(左)】 右斜め前から本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。
本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 まどろむネコ
本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。
落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。
本堂には阿弥陀如来坐像と、御本尊である不動明王像が御座します。
この阿弥陀如来像は、江戸時代に、江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第3番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。
御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 上(左)】 大師堂の堂号板
本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。
大師堂の中には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置されており、「雷除けの本尊」として知られています。
本堂のそばには、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標も建っており、札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるので、この「雷除けの本尊」が札所本尊かもしれません。
御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。
原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。
なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。
● 江戸六阿弥陀如来第3番目の御朱印

中央に「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三番」の札所印。右に「西ヶ原」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

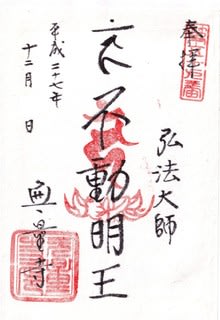
【上(左)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第59番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
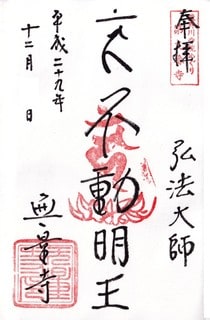
● 滝野川寺院めぐり第9番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「滝野川寺院めぐり 第九番寺」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第4番目 宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:御府内八十八箇所第56番、豊島八十八ヶ所第56番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、江戸八十八ヶ所霊場第56番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番、、滝野川寺院めぐり第1番
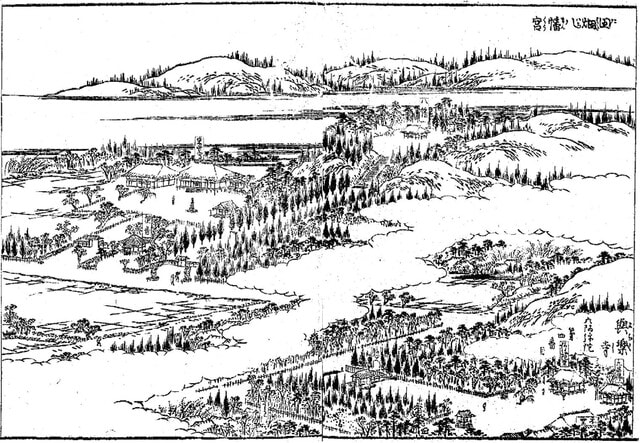
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像と札所標
弘法大師の建立とも伝わり、慶安元年(1648年)に寺領20石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。
『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、寺歴は相当に古そうです。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔當寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ、翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ、是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト伝フ 開山ヲ秀榮ト云」「鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク」「阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ」「九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云」
複数の霊場の札所を兼ねておられ、とくに御府内八十八箇所と武州江戸六阿弥陀で参拝される方が多いのでは。
こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。
豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。
山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。
山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 霊堂
参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。
その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。
境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
参道正面に本堂。
入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。
水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。
正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。
向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ
本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。
本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。
本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。
第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番目の札所です。
「江戸六阿弥陀」と「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。
シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。
札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額
【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂
阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。
お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。
● 江戸六阿弥陀第4番目の御朱印
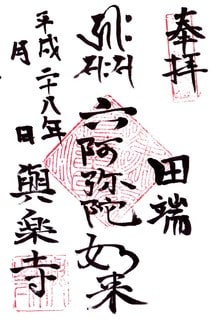
中央に三寶印と「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫。右に「第四番」の札所印と「田端」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
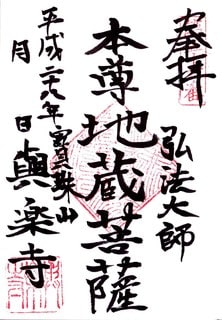

【上(左)】 御府内八十八箇所第56番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所第56番の御朱印
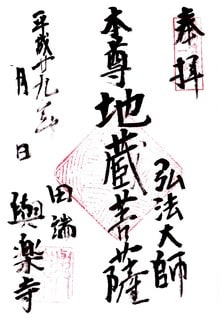
滝野川寺院めぐり第1番の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 地蔵菩薩」の揮毫と三寶印の捺印、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、右上に各霊場の札所印。
尊格構成は御府内霊場、豊島霊場、滝野川寺院めぐりともに同様です。
→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 御編 】へつづく
【 BGM 】
■ ひらひら ひらら - ClariS
■ 夢の途中 - KOKIA
■ 潮見表 - 遊佐未森
アゲてみます。
-------------------------
2021/06/22 UP
江戸時代、江戸の庶民、とくに女性に広く信仰を広めた札所詣がありました。
「武州江戸六阿弥陀詣」です。
江戸名所図会など江戸期の絵図にも多くとりあげられ、逸話も多いので時間をかけてじっくり構成してみたいと思いますが、まずは初稿としてUPしてみます。
なお、「 滝野川寺院めぐり」の記事と重複する内容があります。
ボリュームがあるので、前編と後編に分けます。
■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】
■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 後編 】
--------------------------------------------

『江戸名所図会』(常光寺境内説明板より)


【写真 上(左)】 第1番目 西福寺
【写真 下(右)】 第2番目 恵明寺
武州江戸六阿弥陀霊場(江戸六阿弥陀)は、行基菩薩が一夜の内に一本の木から刻み上げた六体の阿弥陀仏と、余り木で刻した阿弥陀仏、残り木(末木)で刻した聖観世音菩薩を巡拝する八箇寺からなる阿弥陀霊場で、女人成仏の阿弥陀仏として崇められ、江戸中期から大正時代にかけて、とくに春秋の彼岸の頃に女性を中心として盛んに巡拝されたといわれます。
開創年代については諸説あり錯綜していますが、札所は確定しています。
第1番目 三縁山 無量壽院 西福寺
北区豊島2-14-1 真言宗豊山派
第2番目 宮城山 円明院 恵明寺(旧小台村延命院)
足立区江北2-4-3 真言宗系単立
第3番目 佛寶山 西光院 無量寺
北区西ケ原1-34-8 真言宗豊山派
第4番目 宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1 真言宗豊山派
第5番目 福増山 常楽院
調布市西つつじヶ丘4-9-1(旧下谷(上野)広小路) 天台宗
第6番目 西帰山 常光寺
江東区亀戸4-48-3 曹洞宗
木余の弥陀 龍燈山 貞香院 性翁寺
足立区扇2-19-3 浄土宗
木残(末木)の観音 補陀山 昌林寺
北区西ケ原3-12-6 曹洞宗

※国土地理院ウェブサイト掲載の「地理院地図」を筆者にて加工作成。
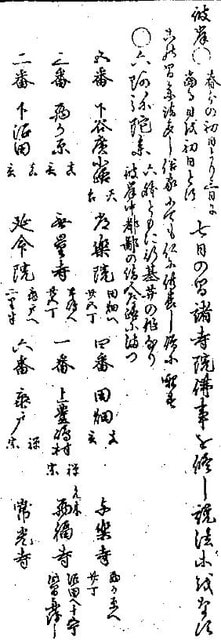
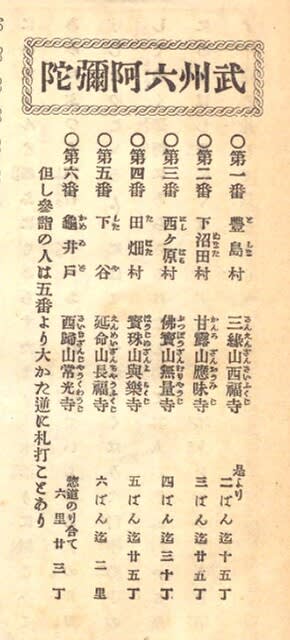
【写真 上(左)】 『東都歳時記』の札所一覧(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載・原データ)
【写真 下(右)】 『滑稽名作集. 上/六あみだ詣 上編・十返舎一九題』の札所一覧 (国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載・原データ)
■常光寺「六阿弥陀道道標」説明板より
「江戸六阿弥陀詣とは、江戸時代、春秋の彼岸に六ヶ寺の阿弥陀仏を巡拝するもので、その巡拝地は順に上豊島村西福寺(北区)、下沼田村延命院(足立区)、西ヶ原無量寺(北区)、田端村与楽寺(北区)、下谷広小路常楽院(調布市に移転)、亀戸村常光寺となっていました。江戸六阿弥陀には奈良時代を発祥とする伝承がありますが、文献上の初見は明暦年間(1655-58年)であることから、六阿弥陀詣は明暦大火後の江戸市中拡大、江戸町方住民の定着にともなう江戸町人の行楽行動を示すものといえます。」
江戸六阿弥陀についてまとめた文献は多数ありますが、ここでは下記2資料を主に参考とし、適宜引用させていただきました。
1.「江戸の3 つの『六阿弥陀参』における『武州六阿弥陀参』の特徴」/古田悦造氏(リンク、以下「資料1」とします。)
2.「『篤信』の『商売人』 - 東天紅上野本店裏手の常楽院別院に関する調査報告 -」/徳田安津樹氏(リンク、以下「資料2」とします。)
順路については、『東都歳時記』によると札番どおりではなく、第5番目 常楽院 → 第4番目 與楽寺 → 第3番目 無量寺・木残(末木) 昌林寺 → 第1番目 西福寺 → 第2番目 延命院 (現・恵明寺)・木余 性翁寺 → 第6番目 常光寺〔結願〕という時計回りのコースが多くとられたようです。
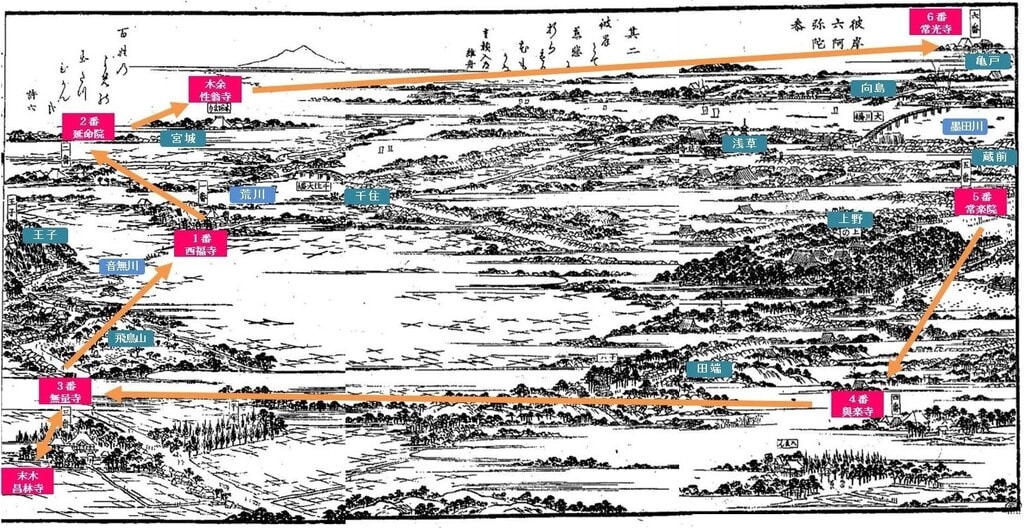
※ 『東都歳事記. 春之部 下』(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載・加工)
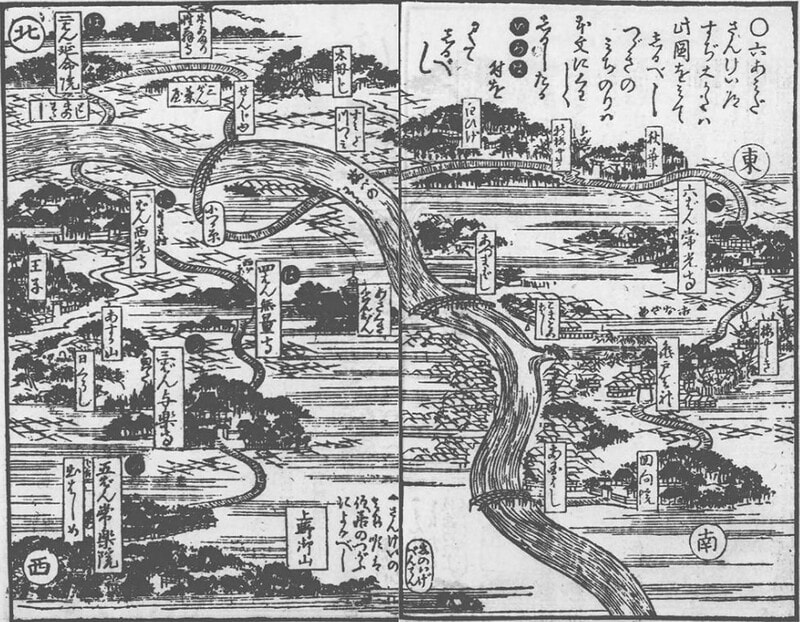
※ 『東都遊覧年中行事』(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
各寺院の縁起や由緒、足立区資料、および「資料1」「資料2」などから江戸六阿弥陀の創祀を辿ってみます。
**********************
〔 足立姫伝説 〕
その昔この地に「足立の長者」(足立庄司宮城宰相とも)という人がおり、年老いて子がないことを憂いて、日頃から尊崇している熊野権現に一途に祈ると女の子を授かりました。
「足立姫」と呼ばれたこの子は容顔すこぶる麗しく、見るものはみな心を奪われたといいます。
生来仏を崇うことが篤く、聡明に成長した姫は「豊嶋の長者」(豊島左衛門尉清光とも)に嫁いだものの、嫁ぎ先で誹りを受け、12人(5人とも)の侍女とともに荒川に身を投げ命を絶ってしまいました。
足立の長者はこれを悲しみ、娘や侍女の菩提のために諸国の霊場巡りに出立しました。
紀州牟宴の郡熊野権現に参籠した際、霊夢を蒙り1本の霊木を得て、これを熊野灘に流すと、やがてこの霊木は国元の熊野木(沼田の浦とも)というところに流れ着きました。
この霊木は不思議にも夜ごと光を放ちましたが、折しもこの地を巡られた行基菩薩は(この霊木は)浄土に導かんがための仏菩薩の化身なるべしと云われ、南無阿弥陀仏の六字の御名号数にあわせて霊木から六体の阿弥陀如来像を刻し、余り木からもう一体の阿弥陀仏、さらに残った木から一体の観音菩薩像を刻まれそれを姫の遺影として与えました。
後にこれら七体の阿弥陀仏と一体の観音像は近隣の寺院に祀られ、以降、女人成仏の阿弥陀詣でとしてとくに江戸期に信仰を集めました。
※なお、資料によっては、足立姫は豊嶋左衛門清光の娘、嫁ぎ先を足立少輔家にしているものがあります。
この哀しい逸話は「足立姫伝説」とも呼ばれ、このエリアに広く伝わるものです。
『滝野川寺院めぐり案内』の無量寺の頁に「江戸近郊を歩くこのミニ巡礼は、表向きは信心とはいうものの、実際は世代家族の同居が当たり前だった時代の、年に2回のストレス解消とレクリエーションの一石二鳥の効果を狙ったものであった。まさに庶民が、日常生活の中から考えた知恵だったのであろう。」と記載されていますが、江戸の年中行事を描いた『東都歳時記』や『江戸名所図絵』でも複数取り上げられていることからも、そのような側面が大きかったと思われます。
「足立姫伝説」の経緯からは娵姑の確執がうかがわれ、このような背景もあってか、第6番目の常光寺のWebでは「六番は嫁の小言の言いじまい」「六阿弥陀嫁の小言(噂)の捨て処」の川柳が紹介されています。
気候のよい春秋の彼岸の一日、気の合ったお仲間と連れだって、日頃の鬱憤の発散をはかる庶民の姿がうかがわれます。

※ 『江戸名所図会』7巻[17](国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
「資料2」では柳沢吉保の孫・信鴻作の『宴遊日記』からつぎの描写が紹介されています。(安永六年(1777年)2月の項)
「今日彼岸の終り阿弥陀参り往来甚賑し、天色大に晴、西南白雲如刷、平塚明神鳥居前より坂道を下り、利島郡へ行、行人にて塗甚込合、五歩六歩に路上仏を居へ、村姥数人念仏を唱へ、或ハ太鼓・鐘をうち建立の法施を請者夥く、疥癬の乞僧路上に満ち、辻博突有、畝中路上皆貝売雪の如し」

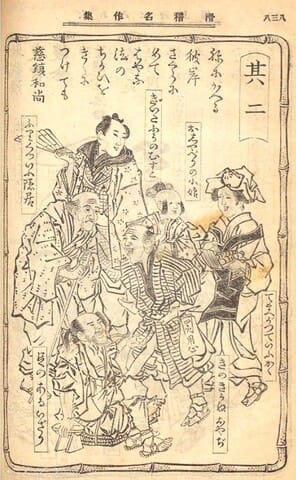
※ 『滑稽名作集. 上/六あみだ詣 上編・十返舎一九題』(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
また、十返舎一九の『六あみだ詣 上編』には下記の描写があります。(国会図書館DC)
「彼岸功徳経に曰。二八月七日の間無数萬億のぼさつ。法を説て衆生楽をあたへ給うなりと。其外諸経にも見へて。春秋二度の彼岸には。人間の罪障消滅の縁ふかく。佛に法施し。僧に供養するの時なりとて。六阿彌陀詣といふ事。いつの頃にやはじまり。六ヶ所の霊地に貴きも賤しきも。あみだの光も地獄のさたも。銭次第とてはやみちに。臍くりをとりこみ。巾着のひもながき麗なるに。打ちむれつヽ一乗無外の色のよの中。とぢぶたとつれだつ破鍋(われなべ)あれば。餅をつく桃灯は。ぬれたる祖母の腰つきを思ひやり。佛性常住の吸筒をかたげ。一色一香のにぎりめしをふところにして。ぬらりくらりの牛は牛づれ。馬は馬づれ。はなしつれてゆく中にも。(以下略)」
「資料2」によると、六阿弥陀伝説が最初に記されたのは江戸時代前期成立の『六阿弥陀伝説』とみられ、すべての札所(寺院所在)が明確にされたのは貞享四年(1987年)の『江戸鹿子』とのことです。
なお、京都今熊野の新熊野神社の公式Webによると、熊野本宮大社の本地は阿弥陀如来で「この当時(平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて)の当時の熊野信仰を一言でいうと、本地垂迹説に基づく神仏習合信仰と浄土信仰が一体化した信仰ということになろう。」とあるので、江戸六阿弥陀が熊野とつながりをもつのは自然な成り行きであったともみられます。
それでは第1番目から順にご紹介していきます。
なお、御朱印については8箇寺すべてで授与されておられますが、多くが授与所ではなく庫裡での授与で、タイミングや状況によっては拝受できない可能性もあるかもしれません。
ある程度御朱印拝受に慣れた方向けの札所詣のような感じがしています。
■ 第1番目 三縁山 無量壽院 西福寺
北区豊島2-14-1
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:豊島八十八ヶ所霊場第67番、荒川辺八十八ヶ所霊場第20番
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.江戸六阿弥陀霊場第1番目
朱印尊格:阿弥陀如来
2.豊島八十八ヶ所霊場第67番
朱印尊格:阿弥陀如来
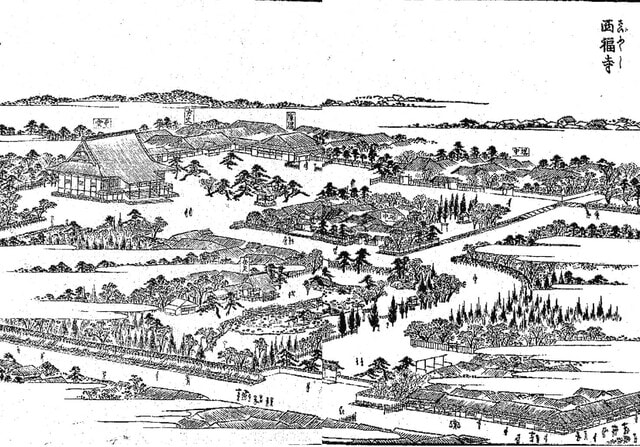
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
「足立姫伝説」の登場人物、豊嶋左衛門清光の創建(開基)と伝わる古刹で、六阿弥陀第1番目の阿弥陀如来をご本尊としています。
「是世に所謂六阿彌陀の一なり、縁起を閲するに、聖武帝御宇當國の住人豊嶋左衛門清光、紀伊國熊野権現を信し、其霊夢に因て一社を王子村に建立し、王子権現と崇め祀れり、然るに清光子なきを憂ひ彼社に祈願せしに、一人の女子を産す、成長の後足立少輔某に嫁せしか、奩具の備はらさるを以少輔に辱しめられしかは、彼女私に逃れ荒川に身を投て死す、父清光悲に堪す是より佛教に心を委ねしか、或夜霊夢に因て異木を得だり、折しも行基當國に来りし故、清光其事を告しに行基即ちかの異木を以て六體の阿弥陀を彫刻し、近郷六ヶ所に安置して彼女の追福とせり、故に是を女人成佛の本尊と稱す、當寺の本尊は其第一なり、次は足立郡小臺村、第三は當郡西ヶ原村、第四は田畑村、第五は江戸下谷、第六は葛飾郡亀戸村なりと云、此説もとより妄誕にして信用すへきにあらされと、當寺のみにあらす残る五ヶ所とともに、少の異同はあれと皆縁起なとありて世人の口碑に傳る所なれは、其略を記しおきぬ、且清光は権頭と稱し、治承の頃の人なれは行基とは時代遥に後れたり」
(『新編武蔵風土記稿』 → 国会図書館DCより)
「此説もとより妄誕にして信用すへきにあらされと、當寺のみにあらす残る五ヶ所とともに、少の異同はあれと皆縁起なとありて世人の口碑に傳る所なれは、其略を記しおきぬ」とあり、江戸六阿弥陀の創祀伝承については疑義をはさんでいます。
ただし文面からは、六阿弥陀の伝承は人口に膾炙し、信仰も広がっていたことがうかがわれます。
江戸六阿弥陀の寺院の縁起や由緒をみると、
A.足立姫の父は足立(沼田)庄司(従二位宰相藤原正成)、嫁ぎ先は豊島左衛門尉清光
B.足立姫の父は豊島左衛門尉清光、嫁ぎ先は足立の沼田治部少輔
の2パターンあることがわかります。
当寺の縁起は、B.足立姫の父は豊島左衛門尉清光のパターンです。
足立氏(藤原氏流)も豊島氏も中世には豊島郡・足立郡に勢力を張った有力氏族です。
足立氏と豊島氏の関係については未だ調べていませんが、対抗関係にあったとすると、その関係が「足立姫伝説」を介して伝わった可能性もあるかもしれません。
豊島清光は中世に豊島郡を領した武将で、史料から正式名は”清元”とされています。
治承四年(1180年)、石橋山の戦いで敗れ、安房国から再挙を図った源頼朝軍に合流し、鎌倉に入って幕府御家人に列しました。
清光・清重父子は奥州合戦の遠征軍に加わり、清重は戦功を挙げて戦後に奥州総奉行に任ぜられています。
豊島清光の館は当寺からもほど近い清光寺とされ、清光寺には豊島清光の木像が祀られています。(清光寺も豊島霊場の札所なので、御朱印を拝受できます。)
飛鳥山から流れ下る石神井川(滝野川・音無川)が荒川に合流するすぐそばにあり、王子駅前からだと徒歩15分弱です。
境内は広く、多くの見どころがあります。


【写真 上(左)】 石柱門
【写真 下(右)】 身代地蔵菩薩
通りに面した石柱門の右手には「身代地蔵菩薩」が御座します。
美貌で高慢な双六好きの藤原氏のお姫様の危機を救われ、改心したお姫様の信仰を受けたという逸話をもつお地蔵さまです。


【写真 上(左)】 境内参道
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 奉石橋の碑
【写真 下(右)】 六地蔵
参道正面が山門。三間一戸の八脚門で屋根は本瓦葺、唐破風の下に天井絵をはじめ艶やかな彩色の意匠が施されています。
手前は仁王尊二体。本堂側には風神、雷神が御座す見どころの多い山門です。
山門の手前右手の六地蔵は、「逆さ卍の六地蔵」として知られる石仏です。


【写真 上(左)】 風神
【写真 下(右)】 雷神


【写真 上(左)】 中門前
【写真 下(右)】 中門
さらに参道を進むと正面が中門。おそらく三間一戸の八脚門ですが山門よりはシックなつくで、山門と中門のふたつの門がいいコントラストを見せています。
手前に「関東六阿彌陀元木第壱番霊場」の札所標。
江戸六阿弥陀は「関東六阿弥陀」とも呼ばれたと伝わりますが、これを裏付けるものです。
中門手前左右の獅子はともに阿形で、ちよっと変わった表情をしています。
左手に御座す端正なお顔立ちのお地蔵様と正面上手の「六阿弥陀第壱番」の赤い提灯が、女人霊場らしい華やぎを醸しています。


【写真 上(左)】 札所標と中門
【写真 下(右)】 本堂前
中門は閉ざされているので脇から回り込みます。
中門から本堂までは回廊形式で朱塗りの柱梁の屋根がかかっています。
正面は左右にたくさんの絵馬がかかった、信仰の篤さを伝える本堂です。
本堂の全容は明らかでないですが、近代建築かと思われます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 阿弥陀如来と本堂


【写真 上(左)】 阿弥陀如来
【写真 下(右)】 岩清水六阿弥陀
本堂向かって右に、御本尊のお前立ちとみられる阿弥陀如来が御座します。
蓮華座に結跏趺坐され、光背に化仏を配し、来迎印(上品下生印)を組まれる存在感あるおすがたで、さすがに阿弥陀霊場発願札所です。
境内にはほかにもさまざまな見どころがあります。
・お馬塚
「よさこい節」の一節 ”土佐の高知のはりまや橋で坊さんかんざし買うを見た”の逸話の主人公「お馬」の墓所が当寺であることが確認されたため、昭和47年に建立されたものです。
土佐の2人のイケメンの僧と、美しい鋳掛屋の娘「お馬」の間で繰り広げられた波瀾万丈の恋物語で、メインの舞台は土佐ですが、「お馬」は2人の僧いずれとも結ばれず、土佐の大工・寺崎氏と結婚し、明治中期に東京に移り、没後西福寺に入りました。
→「お馬」の恋物語の概要
物見高い江戸っ子のことゆえ、この色恋沙汰の物語が知られていれば「お馬」とこのお寺は一大観光?スポットとなった筈ですが、このお話しは幕末が舞台で、しかも当寺との関係が確認されたのは昭和も後期。
さすがの江戸っ子も、これでは駆けつけるすべもありません。
・奉石橋の碑
石神井川に架かる現在の豊石橋は、以前は氾濫のたびに流され、かつてこの地を訪れた夫婦の六部(巡礼者)が川を渡れずに困っていたところ、村人たちが助力してこの六部を安全に渡しました。
その後、「秩父のある方から頼まれて来た」という石屋が立派な橋を架け、一体の石のお地蔵さまを納めて帰っていきました。村人たちは「秩父のある方」がかの六部であると悟り、感謝の意を込めて「奉石橋」と名付けたと伝わります。
・岩清水六阿弥陀
境内の一角にあります。
中央に当山の施無畏印・与願印の立像の阿弥陀如来。左右に定印を結ばれる五体の阿弥陀如来坐像が御座し、六阿弥陀各寺の寺号が刻まれています。
江戸六阿弥陀発願寺としての矜持が感じられる六阿弥陀です。


【写真 上(左)】 当山(壱番目)
【写真 下(右)】 弐番目 恵明寺


【写真 上(左)】 参番目 無量寺
【写真 下(右)】 四番目 與楽寺


【写真 上(左)】 五番目 常楽院
【写真 下(右)】 六番目 常光寺
御朱印は庫裡にて拝受しました。
豊島八十八ヶ所霊場第67番の札所でもあり、そちらの御朱印も授与されています。
● 江戸六阿弥陀如来第1番目の御朱印
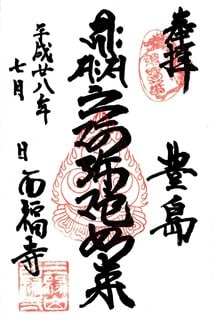
中央に宝珠印(蓮華座+火焔宝珠)、「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と右上に「第壱番」の札所印。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
なお、中央上部に阿弥陀如来の種子(キリーク)、右に聖観世音菩薩の種子(サ)、左に勢至菩薩の種子(サク)が揮毫された阿弥陀三尊様式は、江戸六阿弥陀の御朱印で複数みられるものです。
〔 豊島霊場の御朱印 〕
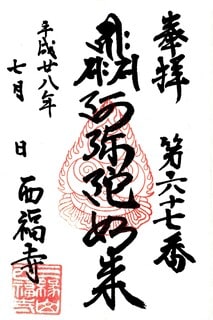
基本的な構成は江戸六阿弥陀と同様ですが、こちらは尊格揮毫が「阿弥陀如来」。
右に豊島霊場の札番「第六十七番」の揮毫があります。
■ 第2番目 宮城山 円明院 恵明寺
足立区江北2-4-3
真言宗系単立
御本尊:阿弥陀如来
他の札所:荒綾八十八ヶ所霊場第54番、荒川辺八十八ヶ所霊場第21番(旧小台村延命寺)、第23番、第24番(旧沼田村能満寺)、第25番(旧宮城村円満寺)、第26番(旧小台村正覚寺)、第27番(旧小台村観性寺)
〔拝受御朱印〕 ・庫裡にて拝受
1.江戸六阿弥陀霊場第2番目
朱印尊格:阿弥陀如来
御本尊の阿弥陀如来は六阿弥陀第2番目で、明治9年(1876年)小台の延命寺を合併の際、延命寺から移られたものと伝わります。(よって、江戸期の第2番目は延命寺)
新編武蔵風土記稿巻之百三十六 足立郡之二 小臺村の「阿彌陀堂」が小台の延命寺を指すものとみられます。
「六阿彌陀堂と称する其第二番なり、沼田村の接地にあるを以て、人多く沼田の六阿彌陀といへり、其濫觴を尋るに、人王四十五代聖武帝の御宇、豊嶋郡沼田村に庄司と云もの一人の女子あり、隣村に嫁す、いかなる故にや其家の婢女と沼田川に身を投じて死せり、父の庄司悲の餘彼等追福の為にとて、所々の霊場を順拝し、紀州熊野山に詣でし時、山下にて一株の霊木を得たりしかば、則仏像を彫刻して、かの冥福を祈らんと、本國に帰りて後僧行基に託して、六軆の彌陀を刻し、分て此邊六ヶ寺に安置せし其一なるよし縁起に載す、尤うけがたき説なり、聖武帝の頃庄司と云ものあるべき名にあらず、且沼田村は豊嶋郡にはあらで本郡の地なり、かゝる杜撰の寺傳取べきにあらず、また隣村宮城村性翁寺の傳には、足立の庄司宮城宰相の女子、豊嶋左衛門尉に嫁せしが、故ありて神亀二年六月朔日侍女と共に荒川に投じて死す、其追福の為にかの熊野山の霊木を以て、行基に託し彫刻して此邊の寺院六ヶ寺に安すと云、神亀は聖武帝の年号にて、少しくたがひあれど同じ傳へなり(中略)されど此六阿弥陀のことは、世の人信ずることにて、其造立さまで近き頃のことゝも思はれず。」
(『新編武蔵風土記稿』 → 国会図書館DCより)
ここでも『風土記稿』は「かゝる杜撰の寺傳取べきにあらず」としながらも「されど此六阿弥陀のことは、世の人信ずることにて」と受け、創祀伝承に疑問を呈しながらも人々のあいだに「六阿弥陀」の信仰が広がっていることを記しています。
荒川辺八十八ヶ所霊場の札所であり、沼田村、宮城村、小台村の数寺の札所が恵明寺に移動していることから、3村の寺院が合併された可能性があります。
「猫のあしあと」様の情報によると、荒川辺霊場第21番の小台村延命寺)、第25番の宮城村円満寺、第26番の小台村正覚寺、第27番の小台村観性寺が荒川河川改修工事に伴い廃寺(第24番の沼田村能満寺は明治維新前に廃寺)となり、札所は本寺の恵明寺に移動したようです。
この影響か、現在の宮城、小台は隅田川と荒川に挟まれた島状のエリアで、寺院の数は少なくなっています。
創建年代等は不詳ですが、複数の末寺を抱えていたことからも想像されるとおり、山城国醍醐三宝院の直末で(足立風土記資料)、慶安元年(1648年)寺領二十石の御朱印状拝領の記録が残るこのエリア有数の古刹(中本寺格の寺院)です。
以前は鉄道駅から遠く陸の孤島的な立地でしたが、日暮里舎人ライナーが開通して交通の便がよくなりました。「扇大橋」駅から徒歩約9分で到着です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標と山門
荒川沿い、首都高江北JCTのそばにあります。
山門は本瓦葺の重厚な薬医門で、門前に大ぶりな寺号標、枝ぶりのいい青松と六阿弥陀・荒綾霊場併記の札所標を置く構えは、さすがに名刹の風格があります。
山門は常閉のようなので、脇の通用門から参内します。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 通用門


【写真 上(左)】 境内1
【写真 下(右)】 境内2
境内も手入れが行き届き、清々しい空気が流れています。
覆堂内に子育地蔵と数体のお地蔵さま。


【写真 上(左)】 子育地蔵
【写真 下(右)】 本堂への参道


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。身舎の材質は木造ではありませんが、色調がシックで落ち着いたたたずまい。
海老虹梁もしっかり造作され、向拝手前の青銅色の天水受がいいアクセントになっています。


【写真 上(左)】 向拝側面
【写真 下(右)】 天水受
恵明寺のもともとの御本尊は不動明王と伝わりますが、延命寺合併時に六阿弥陀の阿弥陀如来坐像(等身大の寄木造り)が御本尊となられたようです。
御朱印は庫裡にて授与いただきました。
荒綾八十八ヶ所霊場や荒川辺八十八ヶ所霊場の御朱印の授与については不明です。
● 江戸六阿弥陀第2番目の御朱印

中央に阿弥陀如来の種子キリークの御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と右に「第弐番」の札所印と「沼田」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第3番目 佛寶山 西光院 無量寺
北区西ヶ原1-34-8
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
他の札所:御府内八十八箇所第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第59番、大東京百観音霊場第81番、、滝野川寺院めぐり第9番
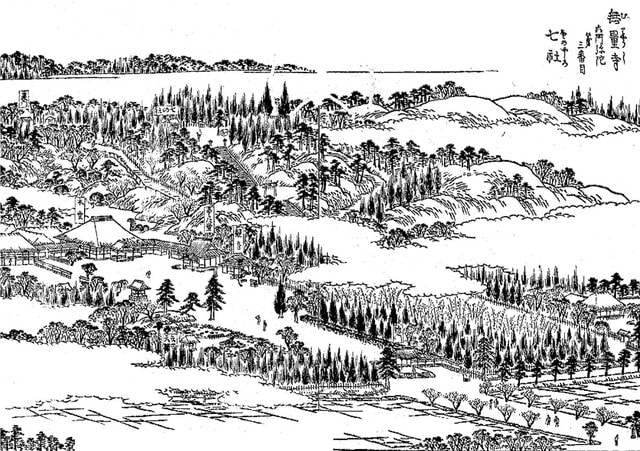
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)
メジャー霊場、御府内八十八箇所第59番の札所なので、認知度は比較的高いと思います。
また、こちらは江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺(第3番目)で、もともと参詣者の多かった寺院とみられます。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号20/114)に以下の記述があります。
「新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル、古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ、常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ」
「寺寶 紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅」
「七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス 末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社」
「阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛 寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス」
創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。
また、北区設置の説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。
江戸時代には広大な寺域を有していたといわれ、当寺が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。
『江戸名所図会』には無量寺境内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」が表され、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったことがうかがわれます。
大正三年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。
なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現社地)に遷座されています。

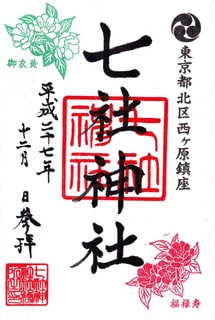
【写真 上(左)】 七社神社
【写真 下(右)】 七社神社の御朱印(旧)
西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。
旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅であり、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。
現在でも、落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。
内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)
このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に台地上を辿ります。
第七番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅方面からだと本郷通りを越えての道順となるので、本郷通りからかなりの急坂を下ってのアブローチとなります。
旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。
坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。
入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。
ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊
【写真 下(右)】 山門
参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。
そのおくに山門。この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門だと思います。


【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑
【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑


【写真 上(左)】 中門
【写真 下(右)】 秋の山内


【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道
【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼
さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある参道です。
緑ゆたかな境内は手入れも行き届き、枯淡な風情があります。
御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院だと思います。
左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。


【写真 上(左)】 見事な紅葉
【写真 上(左)】 冬の山内


【写真 上(左)】 早春の本堂
【写真 下(右)】 秋の本堂


【写真 上(左)】 右斜め前から本堂
【写真 下(右)】 向拝
正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。
本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 まどろむネコ
本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。
扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。
落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。
本堂には阿弥陀如来坐像と、御本尊である不動明王像が御座します。
この阿弥陀如来像は、江戸時代に、江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第3番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。
御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 上(左)】 大師堂の堂号板
本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。
大師堂の中には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置されており、「雷除けの本尊」として知られています。
本堂のそばには、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標も建っており、札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるので、この「雷除けの本尊」が札所本尊かもしれません。
御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。
原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。
なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。
● 江戸六阿弥陀如来第3番目の御朱印

中央に「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫と阿弥陀如来の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第三番」の札所印。右に「西ヶ原」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

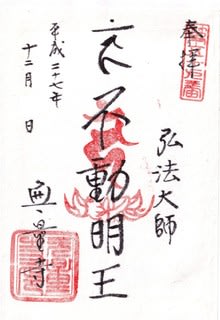
【上(左)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(専用納経帳)
【下(右)】 御府内八十八箇所第59番の御朱印(御朱印帳揮毫)
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

● 豊島八十八ヶ所霊場第59番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「第五十九番」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
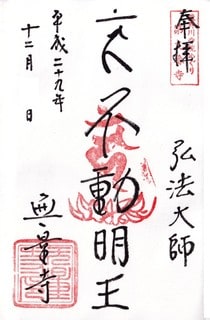
● 滝野川寺院めぐり第9番の御朱印
中央に「不動明王」と不動明王の種子「カン」の揮毫と御寶印(蓮華座)。
右上に「滝野川寺院めぐり 第九番寺」の札所印。右に弘法大師の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第4番目 宝珠山 地蔵院 與楽寺
北区田端1-25-1
真言宗豊山派
御本尊:地蔵菩薩
他の札所:御府内八十八箇所第56番、豊島八十八ヶ所第56番、大東京百観音霊場第82番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第21番、江戸八十八ヶ所霊場第56番、九品仏霊場第3番(上品下生)、豊島六地蔵霊場第1番、、滝野川寺院めぐり第1番
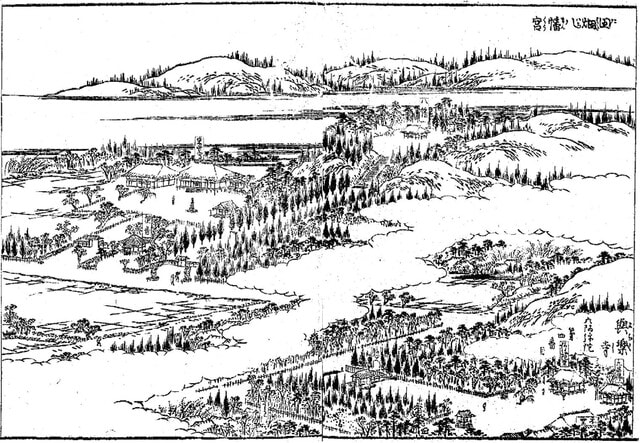
※ 『江戸名所図会』十五(国会図書館DC(保護期間満了資料)より転載)


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 修行大師像と札所標
弘法大師の建立とも伝わり、慶安元年(1648年)に寺領20石の御朱印状を拝領、京都仁和寺の関東末寺の取締役寺を務められ末寺20余を擁したとされる名刹です。
『滝野川寺院めぐり案内』には康歴三年(1381年)銘の石塔の存在が記され、寺歴は相当に古そうです。
『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国会図書館DCコマ番号21/114)には以下の記述があります。
「新義真言宗京都仁和寺末 寶珠山地蔵院ト号ス 慶安元年八月二十四日寺領二十石ノ御朱印を賜フ 本尊地蔵ハ弘法大師ノ作ナリ 昔當寺へ或夜賊押入シ時 イツク●ナク数多ノ僧出テ賊ヲ防キ遂ニ追退タリ、翌朝本尊ノ足泥ニ汚レアリシカハ、是ヨリ賊除ノ地蔵ト号スト伝フ 開山ヲ秀榮ト云」「鐘樓 寶暦元年鑄造ノ鐘ヲカク」「阿彌陀堂 本尊ハ行基ノ作ニテ六阿彌陀ノ第四番ナリ」「九品佛堂 是モ近郷九品阿彌陀佛ノ内第三番ナリト云」
複数の霊場の札所を兼ねておられ、とくに御府内八十八箇所と武州江戸六阿弥陀で参拝される方が多いのでは。
こちらのご住職は滝野川寺院めぐり開創当時の滝野川仏教会の会長で、そのことから札所1番発願寺を務められているものと思われます。
豊島郡有数の名刹の歴史を語るように、ゆったりとした間口を構えます。
山門は平成29年(2017年)建立で、切妻造本瓦葺の立派な四脚門。
山門左手には修行大師像と、御府内霊場第五十六番、六阿弥陀第四番の両札所標、それに上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標「西國廿一番 丹波國阿のう寺写」があります。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 霊堂
参道を進むと左手に霊堂。宝形造唐破風向拝の少し変わった雰囲気のお堂です。
その先には鐘楼。さらに進んだ右手にも宝形造のお堂があって、伽藍は整っています。
境内はよく整備され、名刹特有の荘厳な空気がただよっています。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 右手のお堂と客殿


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
参道正面に本堂。
入母屋造本瓦葺流れ向拝。降り棟、隅棟、稚児棟をきっちり備える堂々たる仏殿です。
水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に出三ツ斗、身舎側に海老虹梁と雲形の手挟を伸ばし、中備に板蟇股を置いています。
正面桟唐戸の上に「與楽寺」の扁額。
向拝両脇の花頭窓と身舎欄間の菱格子が、引き締まった印象を与えます。


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂向拝見上げ
本堂に御座す御本尊の地蔵菩薩は弘法大師の御作と伝わり、盗賊の侵入を追い返された「賊除地蔵」としても知られる秘仏です。
本堂右手が客殿。切妻造桟瓦葺唐破風付きの整った意匠は、本瓦葺の本堂とバランスのよい対比を見せています。
本堂右手脇にも上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所標がありますが、こちらは「西國弐拾九番」となっています。
第29番は東覚寺で、標中に「是」「道」の文字があるので、札所導標かもしれません。


【写真 上(左)】 客殿
【写真 下(右)】 阿弥陀堂
本堂向かって右手が阿弥陀堂で、こちらは武州江戸六阿弥陀第4番目の札所です。
「江戸六阿弥陀」と「滝野川寺院めぐり」とは複数の札所(第1番與楽寺、第9番無量寺、第10番昌林寺)が重複しています。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝。水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。
正面板戸の上に「六阿弥陀 第四番」の扁額。
シンプルな虹梁と両脇の連子が効いて、シャープな印象の向拝です。
札所本尊の阿弥陀如来は行基作と伝わります。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂の扁額
【写真 下(右)】 本堂と阿弥陀堂のあいだのナゾのお堂
阿弥陀堂の右手、本堂とのあいだにもうひとつ宝形造のナゾのお堂がありますが詳細不明。
お堂の手前に観音様の線刻碑があるので、観音堂かもしれません。
御朱印は本堂向かって右手の客殿で拝受します。ここは5回以上参拝していますが、いずれも揮毫御朱印をいただけました。
● 江戸六阿弥陀第4番目の御朱印
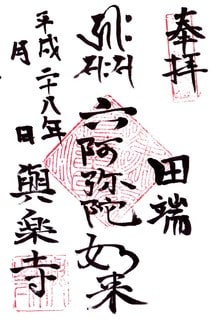
中央に三寶印と「六阿弥陀如来」と阿弥陀三尊の種子「キリーク、サ、サク」の揮毫。右に「第四番」の札所印と「田端」の揮毫。
左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
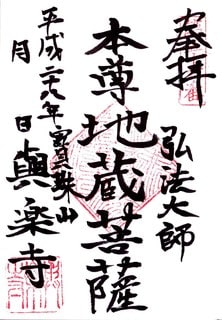

【上(左)】 御府内八十八箇所第56番の御朱印
【下(右)】 豊島八十八ヶ所第56番の御朱印
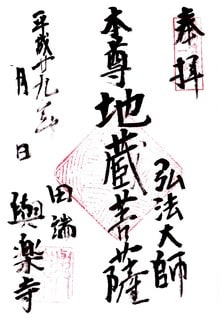
滝野川寺院めぐり第1番の御朱印
御朱印は、中央に「本尊 地蔵菩薩」の揮毫と三寶印の捺印、右に「弘法大師」の揮毫。
左下に寺号と寺院印、右上に各霊場の札所印。
尊格構成は御府内霊場、豊島霊場、滝野川寺院めぐりともに同様です。
→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 御編 】へつづく
【 BGM 】
■ ひらひら ひらら - ClariS
■ 夢の途中 - KOKIA
■ 潮見表 - 遊佐未森
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 初期サザンの名ライブ3曲
どうしようもなく、桑田さんの世界。
途中離脱不可の名テイクたち・・・。
■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド
■ Oh!クラウディア
■ 旅姿六人衆
・「学生の洋楽好きなバンドのサザンオールスターズが終わったのが『KAMAKURA』」。
・「メガサザン」は「国民を相手にしてスタンドアリーナ(の世界)」。
・「初期サザン」だけが別のにおいを発している。
-------------------------
■ 蒼氓 - 山下達郎
『僕の中の少年』(1988年)収録。
コーラス:竹内まりや、桑田圭祐、原由子。
→山下達郎|珠玉の名曲「蒼氓」の魅力とは!?
Wikipediaより
「YMOを取り巻く文化人的なものが、日本のポピュラー音楽をダメにするんじゃないかって、真剣に思ってたの。YMOの音楽的背景ではなく、主として文化人的な側面によって、日本の音楽が変えられるんじゃないかという恐怖感があった。」
↑ いい音楽を生み出すのに、+αの要素は要らないということか・・・。
いまは、+αがなければデビューさえできない時代。
「自分の音楽を思わせぶりに語る」アーティスト、やたらに多いもんね。
だからこそ、(じつは)音楽一本勝負だった初期サザンの曲が心を打つのかも。
音楽だけですベてを語り尽くした名テイク ↓
■ 佐野元春 - HEART BEAT(小さなカサノバと街のナイチンゲールのバラッド) LIVE 1983
映像もあるか・・・。でも、それもすこぶるシンプル。
〔 関連記事 〕
■ 初期サザンとメガサザン(サザンオールスターズ、名曲の変遷)
途中離脱不可の名テイクたち・・・。
■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド
■ Oh!クラウディア
■ 旅姿六人衆
・「学生の洋楽好きなバンドのサザンオールスターズが終わったのが『KAMAKURA』」。
・「メガサザン」は「国民を相手にしてスタンドアリーナ(の世界)」。
・「初期サザン」だけが別のにおいを発している。
-------------------------
■ 蒼氓 - 山下達郎
『僕の中の少年』(1988年)収録。
コーラス:竹内まりや、桑田圭祐、原由子。
→山下達郎|珠玉の名曲「蒼氓」の魅力とは!?
Wikipediaより
「YMOを取り巻く文化人的なものが、日本のポピュラー音楽をダメにするんじゃないかって、真剣に思ってたの。YMOの音楽的背景ではなく、主として文化人的な側面によって、日本の音楽が変えられるんじゃないかという恐怖感があった。」
↑ いい音楽を生み出すのに、+αの要素は要らないということか・・・。
いまは、+αがなければデビューさえできない時代。
「自分の音楽を思わせぶりに語る」アーティスト、やたらに多いもんね。
だからこそ、(じつは)音楽一本勝負だった初期サザンの曲が心を打つのかも。
音楽だけですベてを語り尽くした名テイク ↓
■ 佐野元春 - HEART BEAT(小さなカサノバと街のナイチンゲールのバラッド) LIVE 1983
映像もあるか・・・。でも、それもすこぶるシンプル。
〔 関連記事 〕
■ 初期サザンとメガサザン(サザンオールスターズ、名曲の変遷)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-9
Vol.-8からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第28番 宝林山 大悲心院 霊雲寺
(れいうんじ)
文京区湯島2-21-6
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部(界)大日如来
札所本尊:両部(界)大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第28番、御府内二十一ヶ所霊場第21番、大東京百観音霊場第22番、御府内二十八不動霊場第27番、秩父写山の手三十四観音霊場第1番、弁財天百社参り番外28、御府内十三仏霊場第12番
司元別当:
授与所:寺務所
第28番は真言宗霊雲寺派総本山の霊雲寺です。
『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに第28番札所は霊雲寺となっており、御府内霊場開創時からの札所であったとみられます。
現地掲示、下記史料、文京区Web資料、東京国立博物館Web資料などから、縁起・沿革を追ってみます。
霊雲寺は、元禄四年(1691年)浄厳覚彦和尚による開山と伝わります。
浄厳和尚は河内国出身の真言律僧で新安祥寺流の祖。
霊雲寺を語るうえで法系は欠かせないので、『呪術宗教の世界』(速水侑氏著)およびWikipediaを参照してまとめてみます。
真言密教は多くの流派に分かれ、「東密三十六流」とも称されました。
その主流は広沢流(派祖:益信)・小野流(派祖:聖宝)とされ、「野沢十二流・根本十二流」と称されました。
小野流は安祥寺流、勧修寺流、随心院流、三宝院流、理性院流、金剛王院流の六流で、とくに安祥寺流、勧修寺流、随心院流を「小野三流」といいます。
浄厳和尚はこのうち「安祥寺流」を承継、「新安祥寺流(新安流)」を興されたといいます。
浄厳和尚は慶安元年(1648年)高野山で出家され、万治元年(1658年)南院良意から安祥寺流の許可を受けて以降、畿内で戒律護持等の講筵を盛んに開かれました。
元禄四年(1691年)、徳川五代将軍綱吉公に謁見して公の帰依を受け、側近・柳沢吉保の援助もあって徳川将軍家(幕府)の祈願所として湯島に霊雲寺を建立。
『悉曇三密鈔』(悉曇学書)、『別行次第秘記』(修行に関する解説書)、『通用字輪口訣』(意密(字輪観)の解説書)などの重要な著作を遺され、近世の真言(律)宗屈指の学徳兼備の傑僧と評されます。
浄厳和尚は霊雲寺で入寂されましたが、霊雲寺は将軍家祈願所であるため、みずから開山された塔頭の池之端・妙極院が墓所となっています。
浄厳和尚、そして霊雲寺を語るとき、「真言律宗」は外せないのでこれについてもまとめてみます。(主にWikipediaを参照)
真言律宗とは、真言密教の出家戒・「具足戒」と、金剛乗の戒律・「三昧耶戒」を修学する一派とされ、南都六宗の律宗の精神を受け継ぐ法系ともいわれます。
弘法大師空海を高祖とし、西大寺の叡尊(興正菩薩)を中興の祖とします。
叡尊は出家戒の授戒を自らの手で行い(自誓授戒)、独自の戒壇を設置したとされます。
「自誓授戒」は当時としては期を画すイベントで、新宗派の要件を備えるとして「鎌倉新仏教」のひとつとみる説さえあります。
→ ■ 日本仏教13宗派と御朱印(首都圏版)
真言律(宗)は当時律宗の新派とする説もあったとされますが、叡尊自身は既存の律宗が依る『四分律』よりも、弘法大師空海が重視された『十誦律』を重んじたため、真言宗の一派である「西大寺流」と規定して行動していた(Wikipedia)という説もあるようです。
以降、律宗は衰微した古義律、唐招提寺派の「南都律」、泉涌寺・俊芿系の「北京律」、そして西大寺系の「真言律(宗)」に分化することとなります。
叡尊の法流は弟子の忍性が承継し、忍性はとくに民衆への布教や社会的弱者の救済に才覚を顕したといいます。
鎌倉に極楽寺を建立したのは忍性です。
叡尊・忍性は朝廷の信任篤く、諸国の国分寺再建(勧進)を命じられたとされ、元寇における元軍の撃退も叡尊・忍性の呪法によるものという説があります。
江戸初期、西大寺系の律宗は真言僧・明忍により中興され、この流れを浄厳が引き継いで公に「真言律(宗)」を名乗ったといいます。
霊雲寺は「将軍家祈願所」であるとともに、関八州真言律宗総本寺を命じられ、御府内屈指の名刹の地位を保ちました。
明治5年、明治政府による仏教宗派の整理により、律宗系寺院の多くは真言宗に組み入れられましたが、その後独立の動きがおこり、西大寺は明治28年に真言律宗として独立しています。
真言律(宗)であった霊雲寺が真言宗霊雲寺総本山となった経緯はオフィシャルな資料が入手できず詳細不明ですが、Wikipediaには「昭和22年(1947年)に真言宗霊雲寺派を公称して真言律宗から独立した。」とあるので、戦後、江戸期に47を数えた末寺とともに独立したとみられます。
霊雲寺を「将軍家祈願寺」としてみるとき、興味ぶかい事柄があります。
真言律(宗)は、もともと民衆への布教・救済と国家鎮護という二面性をもった宗派でした。
とくに、元寇の戦捷祈願に叡尊・忍性が関与したとされることは国家鎮護の面での注目ポイントです。
元寇の戦捷祈願には、大元帥明王を御本尊とする大元帥法が修されたとも伝わります。
もともと大元帥法は国家鎮護・敵国降伏を祈って修される法で、毎年正月8日から17日間宮中の治部省内で修されたといいます。
のちに修法の場は醍醐寺理性院に遷された(江戸期に宮中の小御所に復活)ともいいますが、国家、朝廷のみが修することのできる大法とされています。
一方、霊雲寺の大元帥明王画像について、『御府内寺社備考』には「御祈祷本尊大元帥明王之画像 常憲院様(綱吉公)御自画と(中略)鎮護国家之御祈祷」とあります。
大元帥明王の画像を綱吉公みずからが描かれ、こちらを御本尊として鎮護国家を祈祷したというのです。
しかも大元帥明王が御座される御祈祷殿には、東照大権現も祀られています。
つまり、霊雲寺の御祈祷殿では大元帥明王と東照大権現に鎮護国家が祈祷されていたことになります。
しかも『御府内八十八ケ所道しるべ』には御府内霊場の拝所として「太元堂 灌順堂 本尊太元明王」と明記されています。
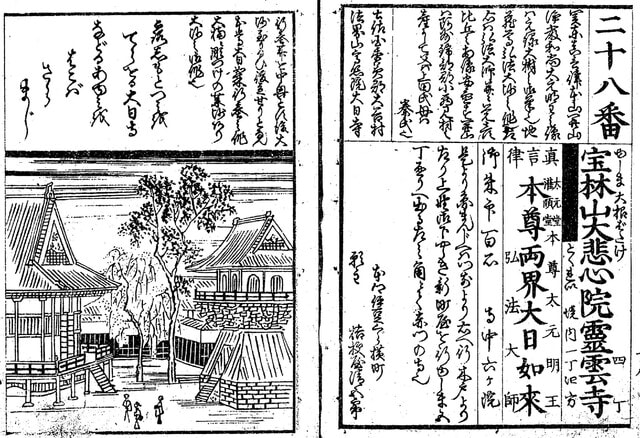
出典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
旧来、国家鎮護の大法・大元帥法の御本尊である大元帥明王は厳重に秘すべき存在でしたが、江戸時代になると、そこまでの厳格さは失われていたのでしょうか。
あるいは日の本の為政者としての徳川将軍家の存在を際立たせる、政治的な狙いもあったのやもしれません。
また、当山は「絹本着色大威徳明王像」(文京区指定文化財)を所蔵されます。
大威徳明王は単独で奉安されることは希で、通常、五大明王(不動明王(中心)、降三世明王(東)、軍荼利明王(南)、大威徳明王(西)、金剛夜叉明王(北))として奉安・供養されますから、当山で五大明王を御本尊とする五壇法が修せられていた可能性があります。
五壇法も国家安穏を祈願する修法として知られているので、やはり当山は祈願寺としての性格が強かったとみられます。
御本尊は両部(両界)大日如来。
「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」(東京国立博物館)には「独自の解釈による両界曼荼羅」とあり、大進美術㈱のWebに「新安祥寺流曼荼羅」として見事な両界曼荼羅が紹介されていることからみても、新安祥寺流(真言宗霊雲寺派)にとって両界曼荼羅、あるいは両界大日如来がとりわけ重要な存在であることがうかがわれます。
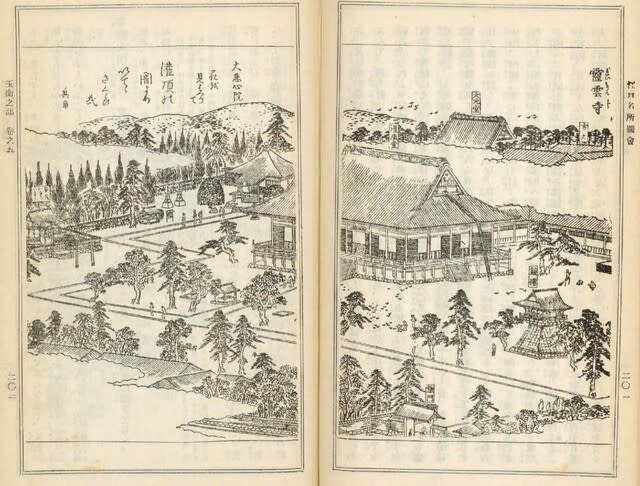
出典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
二十八番
ゆしま
宝林山 大悲心院 霊雲寺
真言律
本尊:両界大日如来 太元堂 灌順堂 本尊太元明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [68] 湯嶋寺院書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.142.』
江戸湯嶋(不唱小名)
(関東)真言律宗惣本寺
寶林山 佛日院 霊雲寺
開基 元禄四年(1691年) 浄厳和尚(浄厳律師覚彦)
本堂
本尊 両部大日如来木像
右 不動明王木像
左 愛染明王木像
四天王立像
御祈祷殿
本尊 大元帥明王画像
同 木像秘佛
東照大権現
寶幢閣
本尊 地蔵菩薩木像
右(左) 弘法大師木像
左(右) 開祖浄厳和尚木像
鎮守社
神体八幡大菩薩 賀茂大明神 稲荷大明神 三神合殿
右 冨士権現社
左 恵寶稲荷社
寺中六ヶ院
智厳院 本尊 地蔵菩薩
五大院 本尊 愛染明王
蓮光院 本尊 辨財天
寶光院 本尊 十一面観音
五智院 本尊 愛染明王
福厳院 本尊 釈迦如来
※ 妙極院(下谷七軒町、本尊 大日如来)を含めて塔頭七院
※ 末寺四拾七ヶ寺を記載
■ 『江戸名所図会 第3 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
寶林山 靈雲寺
大悲心院と号す。圓満寺の北の方にあり。関東眞言律の惣本寺にして、覺彦(かくげん)比丘の開基なり。
灌頂堂 両界の大日如来を安置す。
大元堂 灌頂堂のうしろ方丈の中にあり。本尊大元明王の像は元禄大樹の御筆なり。(以下略(大元法について記す))
鐘楼 本堂の右にあり。開山覺彦和尚自ら銘を作る。
地蔵堂 本堂の左の方艮の隅にあり。本尊地蔵菩薩 弘法大師の作なり。左右の脇壇に弘法大師、ならびに覺彦比丘の両像を安置す。
開山 諱は浄厳、字は覺彦、河州錦部郡小西見村の産なり。父は上田氏、母は秦氏なり。
寛永十六年(1639年)に生る。凡そ耳目の歴る所終に遺忘する事なし。衆人是を神童と称す。(中略)
慶安元年(1648年)高野山検校法雲を禮して薙染す。時に年十歳。朝参暮詣倦む事なし。(中略)元禄四年(1691年)、大将軍(常憲公=綱吉公)召見し給ひ、普門品を講ぜしむ。(中略)遂に城北にして地を賜ひ、梵刹を経始す。ここにおいて佛殿、僧房、香厨、門郭甍を連ね、巍然として一精藍となる。号(なづ)けて霊雲寺という。遂に密壇を建て秘法を行し(中略)元禄五年(1692年)六月、大元帥の大法を修し、國家昇平を祈る。これより以後、毎歳三神通月七日、修法することを永規とす。翌年関東眞言律の僧統となしたまふ。又乙亥の夏、大将軍(常憲公=綱吉公)みづから斎戒し給ひ、大元帥金剛の像を画き、本尊に下し賜ふ。今大元堂に安置し奉る。元禄十年(1697年)、僧俗の請に依って曼荼羅を開く。壇場に入る者九萬人に幾し。隔年灌頂を行ふこと今に至てたえず。(中略)徳化洋々として天下に彌布し。王公より下愚夫に至る迄敬仰せずといふことなし。
■ 『本郷区史 P.1232』(文京区立図書館デジタル文庫)
靈雲寺
湯島新花町に在り、眞言宗高野派の別格本山で寶林山佛日院と称する。元禄四年(1691年)将軍綱吉の建立する所で浄厳和尚を開基とし寺領百石を有した。本堂の外境内に地蔵堂、大元堂、観音堂、鐘楼、経蔵、内佛殿、庫裡、土蔵、学寮等を有したが、何れも大正十二年の震火災に焼失し其後は假建築を以て今日に及んで居る。寺寶の中には十六羅漢十六幅(顔輝筆) 吉野曼荼羅一幅、諸尊集會圖一幅等国寶に指定せられたるものゝ外尊重すべきもの多数を蔵したが何れも大正震火災に焼失した。(國寶は現存)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本郷湯島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
湯島といってもメイン通りから外れており、東京で生まれ育った人間でもあまり訪れることのない立地です。
このような場所に突如としてあらわれる大伽藍は、ある意味おどろきです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 戒壇石
山門脇の石標に「不許葷辛酒肉入山内」とあります。
よく禅宗の寺院の山門脇に「不許葷酒入山門」(くんしゅさんもんにいるをゆるさず)と刻まれた標石が立っていますが、これは「戒壇石」といいます。
修行の妨げになるので、「葷」と「酒」は山内に持ち込んではいけない。あるいは「葷」と「酒」を口にしたものは山内に入ってはいけないという戒めです。
「葷」とはニンニク、韮、ラッキョウなどのにおいが強くて辛い野菜、あるいは生臭い肉料理などをさします。
なので、「葷」には「辛」も「肉」も含むはずですが、あえて「葷」「辛」「酒」「肉」すべて列挙して戒めているあたり、戒律を重んじる律宗系の流れの寺院であることが伝わってきます。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内
山門は薬医門か高麗門。
うかつにも内側からの写真を撮り忘れたので断言できませんが、正面からのたたずまいからすると高麗門のような感じもします。
屋根は本瓦葺でさすがに名刹の風格。見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 寺号標と大本堂
【写真 下(右)】 大本堂
山門をくぐると空間が広がり、正面階段のうえに昭和51年落成の鉄筋コンクリート造2階建ての大本堂(灌頂堂)。
築浅ながら名刹にふさわしい堂々たる大伽藍です。
上層は入母屋造本瓦葺葺、下層も本瓦葺で流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。


【写真 上(左)】 大本堂向拝
【写真 下(右)】 大本堂扁額
向拝見上げに院号扁額をおき、「西大寺 長老」の揮毫がみえます。
霊雲寺は真言律宗から分離独立して真言宗霊雲寺派総本山となりましたが、西大寺(真言律宗総本山)との関係は依然として深いのかもしれません。
大本堂(灌頂堂)には御本尊として両部(金剛界・胎蔵(界))の大日如来像を奉安。
大本堂の下は寺務所・書院となっています。


【写真 上(左)】 地蔵尊と寶幢閣
【写真 下(右)】 寶幢閣
大本堂向かって左手奥に堂宇があり、「寶幢閣」の扁額があります。
■ 『寺社書上 [68] 湯嶋寺院書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.142.』には、「寶幢閣」として、「本尊 地蔵菩薩木像、弘法大師木像、開祖浄厳和尚木像」とあり、『江戸名所図会』にはこの位置に「開山堂」とあるので、「大師堂」と「開山堂」の性格を併せ持つ堂宇であったとみられ、いまもこの系譜を受け継ぐ堂宇かもしれません。
なお、「寶幢閣」は「寶幢如来」ゆかりの堂号とも思われます。


【写真 上(左)】 寶幢閣の扁額
【写真 下(右)】 弘法大師記念供養塔
寶幢如来は胎蔵曼荼羅の中央の区画「中台八葉院」に御座される如来で、胎蔵大日如来(中央)、寶幢如来(東)、開敷華王如来(南)、無量寿如来(西)、天鼓雷音如来(北)とともに「胎蔵(界)五仏」と呼ばれます。
寶幢如来は「発心」(悟りを開こうとする心を起こすこと)を表す尊格とされます。
開山の浄厳覚彦和尚は啓蒙のためにかな書きの教学書を著わされ、多くの庶民に灌頂・受戒を行うなど衆生を仏道に導かれたとされるので、そのゆかりで「発心」(あるいは発菩提心)を表す寶幢如来の号をいただいているのかもしれません。
『江戸名所図会』には
「大悲心院 花を見はべりて 灌頂の闇よりいでてさくら哉 其角」
の句が載せられ、「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」(東京国立博物館)には「霊雲寺では目隠しをして敷曼荼羅に華を投げ、落ちた仏と結縁する結縁灌頂が盛んに行なわれた(中略)霊雲寺で結縁灌頂を受けた後、目隠しの闇と心の闇が同時に晴れる喜びを詠った宝井其角(1661~1707)の句が紹介されています。」とあって、霊雲寺の結縁灌頂が広く知られていたことがわかります。
「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」(東京国立博物館)には「多くの庶民に灌頂、授戒を行ない、啓蒙のためにかな書きの教学書を著すなど、浄厳と霊雲寺は民衆にも寄り添い親しまれる存在となりました。」とあり、江戸名所図会にも記されていることから、「将軍家祈願所」という厳めしい存在ながら案外庶民に親しまれ、御府内霊場の札所としても違和感なくとけこんでいたのでは。
↑ でも触れましたが、将軍家護持の御本尊・大元帥明王が御府内霊場の拝尊であったこと、「将軍家祈願所」という立ち位置ながら、庶民の結縁灌頂の場としての機能していたことなど、やはり霊雲寺は二面性をもつ寺院であったことがうかがわれます。
江戸期にあった大本堂裏手の太元堂もいまはなく、山内の伽藍構成はシンプルですが、寶幢閣前の百度石のうえに地蔵尊、立像の厄除大師像(記念供養塔)、梵字碑の前にも地蔵尊が御座します。
ふつう「祈願所」というと、密寺特有の濃密な空気をまとった寺院を想像しますが、こちらは徹底して明るい空間。
これは律宗の流れ、奈良仏教の平明さを受け継いでいるためかもしれません。


【写真 上(左)】 地蔵尊と梵字碑
【写真 下(右)】 御朱印授与案内
御朱印は寺務所にて拝受しました。
Web情報によると、お昼前後は授与を休止との情報あり要注意です。
なお、霊雲寺は歴史ある名刹だけあって多くの霊場札所となっていますが、現在、御朱印を授与されているのは御府内霊場のみの模様です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
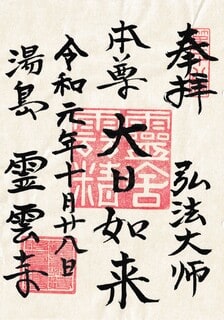
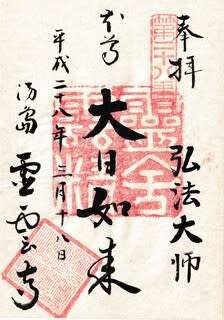
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と「霊雲精舎」の御印。
右上に「第二十八番」の札所印。左下には「湯島 霊雲寺」の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 「御本尊」申告にて拝受の御朱印
【写真 下(右)】 ご縁日の御朱印
「御本尊」申告にて拝受の御朱印には胎蔵大日如来のお種子「ア」の揮毫、ご縁日の御朱印には金剛界大日如来のお種子「バン」と胎蔵大日如来のお種子「ア」の揮毫があります。
「ア」は大元帥明王、寶幢如来のお種子でもあり、当山とは格別のゆかりのあるお種子ではないでしょうか。
なお、申告や日によってお種子の種類が定まっているかは不明です。
■ 第29番 大鏡山 薬師寺 南蔵院
(なんぞういん)
豊島区高田1-19-16
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第41番、東京三十三観音霊場第21番、大東京百観音霊場第71番、弁財天百社参り第44番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所
司元別当:(下高田村)氷川社
授与所:庫裡
御府内霊場には南蔵院と号する札所が練馬(第15番)、牛込(第22番)と高田(第29番)の3箇寺あり、それぞれ練馬南蔵院、牛込南蔵院、高田南蔵院と呼んで区別されます。
第29番札所も複雑な変遷をたどっています。
現在の第29番札所は高田南蔵院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では牛込七軒寺町の三明山 清谷寺 千手院となっています。
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第29番の(牛込七軒寺町)千手院は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第29番札所は高田南蔵院に承継されたとみられます。
下記資料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。
開山は圓成比丘(永和二年(1376年)寂)と伝わります。
御本尊の薬師如来は、奥州藤原秀衡の念持仏といわれ、圓成比丘が諸国遊化のみぎり、夢告によって彼の地の農家で入手し、当地(高田)を通りかかったところにわかに薬師如来像が重くなり、ここが薬師如来有縁の地として草庵を建て奉安したのが開創と伝わります。
御本尊の薬師如来は聖徳太子の御作ともいいます。
寛永(1624-1644年)の頃は、大猷院殿(徳川三代将軍家光公)が狩猟の折にしばしば訪れたと伝わり、仮御殿も建てられたといいます。
三遊亭円朝作の「怪談乳房榎」ゆかりの寺ともいわれます。
『江戸名所図会』の(高田)「氷川明神社」の項に「『南蔵院』の奉祀なり」とあるので、江戸期は(高田)「氷川明神社」の別当であった可能性があります。
つぎに旧29番札所とみられる千手院について、下記史料から追ってみます。
千手院は牛込七軒寺町にあり、足立郡西新井村惣持寺末の新義真言宗寺院でした。
開山 法印舜●(慶安三年(1650年)八月遷化)
慶長十二年(1607年)、手川口(場所不明)に創立され、寛永四年(1627年)御用地召上のため牛込橋場に遷ったようです。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
本堂には御本尊地蔵菩薩、阿弥陀如来、辨財天、愛染明王(弘法大師作)、弘法大師木坐像、興教大師木坐像を奉安。
観音堂には千手観世音菩薩、持國天、不動明王、弁財天、観喜天(秘佛)を奉安し、山内に稲荷社を祀っていたようです。
『御府内寺社備考』によると、観音堂の千手観世音菩薩は、もともと越後国に御座され、柴田勝家、蒲生氏郷、佐倉城主堀田家とゆかりをもたれた後、千手院に奉安されたようですが、達筆すぎて読解不明箇所が多く詳細はわかりません。
千手院は幕末~明治編纂の『御府内八十八ケ所道しるべ』に掲載されているので、明治に入ってから廃されたとみられます。
千手院の廃寺から御府内霊場第29番札所が高田南蔵院に承継された経緯は史料がみつからず不明ですが、千手院は西新井の惣持寺(西新井大師)末、南蔵院は大塚護國寺末で、ともに真言宗豊山派系なので豊山派の法系内で札所が承継されたのではないでしょうか。
また、牛込と高田は比較的近いということもあったかもしれません。
-------------------------
【史料】
【南蔵院関連】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(下高田村)南蔵院
新義真言宗大塚護國寺末 大鏡山醫王寺ト号ス 開山圓成比丘ト云 本尊薬師ハ聖徳太子ノ作長三尺 或云此像ハ奥州秀衡ノ持佛タリシカ 圓成比丘回國ノヲリ 夢ノ告アリテ笈ニウツシテ 此高田ノ里ニ至ルニ 笈俄ニ重リテ盤石ノ如シ 此地有縁ノ地ナレハトテ 草堂ヲイトナミ安置スト云 其後大橋龍慶佛道歸依ノ餘リシハラク 當寺ニ奇寓シケレハ 大猷院殿此邊御遊猟ノ時シハ々々ナラセラレ 御殿ナト御造營アリシトナリ 其頃中根壱岐守ヨリ龍慶に与ヘシ書状アリ 文後ニ出ス 當寺ヘ御成ノ時四方ヘ出入セル門アリ 八ヶ所門ト名付シト云 昔寺内ニ池アリ鏡カ池ト呼シトナリ 當時ノ山号モ是ヨリ起レリ 今境内ヲ流ルヽ小溝ヲ根川ト云
■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
大鏡山南蔵院
砂利場村にあり。真言宗にして、大塚の護國寺に属す。開山は圓成比丘と号す。本尊薬師佛は聖徳太子の作にして、立像三尺四寸あり。此霊像は秀衡の念持佛なりとて、養和年間の頃迄は、奥州平泉にありしを、圓成比丘、諸国遊化の時、霊夢を感じ、彼地の農家にして是を得て、此地に安置すといへり。(中略)寛永の頃は、大将軍家度々此に入らせ給ひしとて、仮の御殿なども構へ置れしとなり。
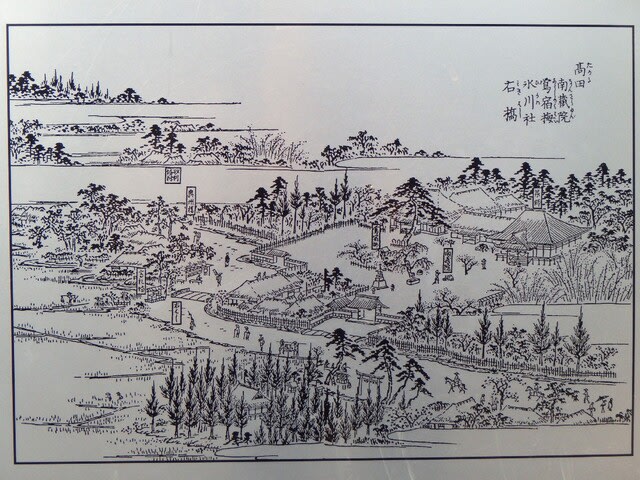
「高田」/出典:『江戸名所図会』(山内掲示より)
【千手院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
二十九番
牛込七軒寺町
三明山 清谷寺 千手院
西新井村惣持寺末 新義
本尊:千手観世音王 多聞天 持国天 弘法大師
■ 『寺社書上 [33] 牛込寺社書上 六』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.124』
牛込七軒寺町
武州足立郡西新井村惣持寺末真言宗豊山派
三明山 清谷寺 千手院
新義真言宗
開山 法印舜● 慶安三年(1650年)八月遷化
当寺起立之儀●慶長十二年手川口に造立
寛永四年御用地に●召上 牛込橋場
本堂
本尊 地蔵菩薩木坐像
阿弥陀如来木立像
辨財天木坐像
愛染明王木坐像 弘法大師作
弘法大師木坐像
興教大師木坐像
観音堂
千手観音立像
持國天立像
不動明王木立像 附二童子
弁財天木坐像
観喜天 秘佛
千手尊像脇士多聞持国の二天ともに赤梅壇毘首羯磨●也●●ハ越後国安臣山にあり 天正年中(1573-1592年)太閤秀吉●柴田勝家を討 柴田の一族安臣山●古もる 会津の城を蒲生氏郷に命じて●さしむ ●●の時●●三尊を守りて(以下解読不明)元和年中(1615-1624年)蒲生家●壊の後 殿地ハ下総佐倉城主堀田家の(以下解読不明)
稲荷社
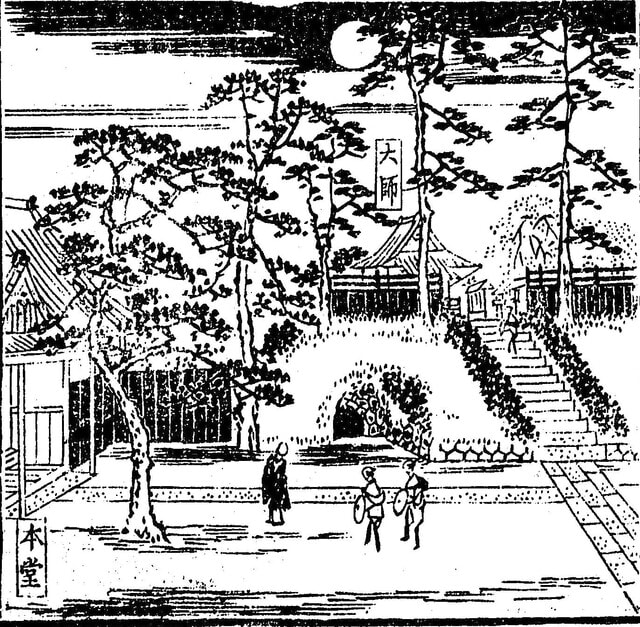
「千手院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
豊島区高田周辺は御府内霊場札所が4箇寺あり(29番南蔵院、35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺)、ふつうは4箇寺まとめての巡拝となります。
このあたりは土地の起伏が激しく、東京メトロ「雑司ヶ谷」駅からだと急な下り坂となります。
35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺は坂の途中にあり、南蔵院は神田川にもほど近い坂下に位置します。
カラフルな月替わり御朱印で有名な高田氷川神社にもほど近く、54番新長谷寺(目白不動尊)は江戸五色不動尊の一尊なので、一帯は御朱印エリアとなっています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山内

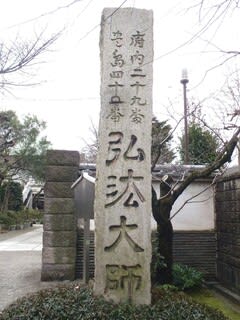
【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 札所標
山門はないですが、山内入口両脇に院号標と札所標(御府内霊場、豊島霊場兼用)を備え、門柱と築地を巡らして風格ある構え。


【写真 上(左)】 辨財天
【写真 下(右)】 馬頭観世音碑
門柱を抜けると、多くの石仏群。
うち、弁財天の石碑は元禄九年(1696年)に神保長賢により寄進された山吹の里弁財天で、そばには弁財天像も御座されます。
南蔵院は弁財天百社参り第44番の札所ですが、こちらが札所本尊かもしれません。
端正な馬頭観世音碑も建っています。
『江戸名所図会』には参道脇に「鶯宿梅」が描かれ、これは徳川家光公お手植えの銘木といいますが現在はありません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は参道階段の上にありますが、参道や階段には植木鉢がところ狭しと並べられ、階段はシャッターで閉ざされているのでシャッター前からのお参りとなります。


【写真 上(左)】 本堂前階段
【写真 下(右)】 向拝
本堂は宝形造銅板葺と思われますが、定かではありません。
向かって右には銅板葺屋根の鐘楼を配しています。
向拝柱はなく、見上げに御本尊・薬師如来をあらわす「瑠璃光」の扁額。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 庫裡への道
御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。
豊島八十八ヶ所霊場第41番を兼務され、こちらの御朱印も授与されています。
また、東京三十三観音霊場第21番の御朱印(札所本尊:千手観世音菩薩)も拝受しています。
東京三十三観音霊場は、関東大震災の犠牲者の慰霊を目的として開創された観音霊場で、初番・発願は南品川の海晏寺、第33番・結願は墨田区横網の東京都慰霊堂。
札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様)
初番海晏寺、第12番雲照寺(代々木上原)、第15番心法寺(麹町)、 第17番天龍寺(新宿)など、現況御朱印不授与とみられる寺院を含み、授与寺院でもおおむね他霊場の御朱印となるため、こちらの霊場の御朱印は貴重です。
札所本尊の千手観世音菩薩が、旧千手院観音堂の堂宇本尊であった千手観世音菩薩であるかどうかはよくわかりません。
また、これまたナゾの多い大東京百観音霊場第71番の札所でもありますが、こちらの御朱印は授与されていない模様です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
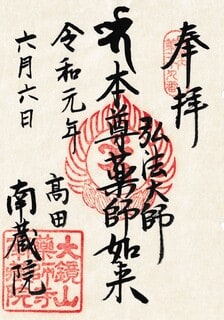
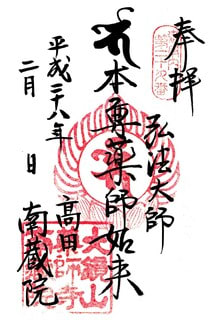
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第二十九番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

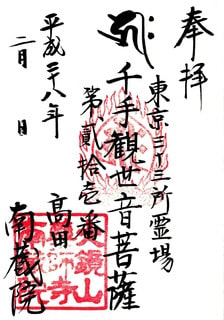
【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東京三十三観音霊場の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-10)
【 BGM 】
■ December - milet
■ Flavor Of Life - 宇多田ヒカル
■ Parade - FictionJunction
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第28番 宝林山 大悲心院 霊雲寺
(れいうんじ)
文京区湯島2-21-6
真言宗霊雲寺派
御本尊:両部(界)大日如来
札所本尊:両部(界)大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第28番、御府内二十一ヶ所霊場第21番、大東京百観音霊場第22番、御府内二十八不動霊場第27番、秩父写山の手三十四観音霊場第1番、弁財天百社参り番外28、御府内十三仏霊場第12番
司元別当:
授与所:寺務所
第28番は真言宗霊雲寺派総本山の霊雲寺です。
『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに第28番札所は霊雲寺となっており、御府内霊場開創時からの札所であったとみられます。
現地掲示、下記史料、文京区Web資料、東京国立博物館Web資料などから、縁起・沿革を追ってみます。
霊雲寺は、元禄四年(1691年)浄厳覚彦和尚による開山と伝わります。
浄厳和尚は河内国出身の真言律僧で新安祥寺流の祖。
霊雲寺を語るうえで法系は欠かせないので、『呪術宗教の世界』(速水侑氏著)およびWikipediaを参照してまとめてみます。
真言密教は多くの流派に分かれ、「東密三十六流」とも称されました。
その主流は広沢流(派祖:益信)・小野流(派祖:聖宝)とされ、「野沢十二流・根本十二流」と称されました。
小野流は安祥寺流、勧修寺流、随心院流、三宝院流、理性院流、金剛王院流の六流で、とくに安祥寺流、勧修寺流、随心院流を「小野三流」といいます。
浄厳和尚はこのうち「安祥寺流」を承継、「新安祥寺流(新安流)」を興されたといいます。
浄厳和尚は慶安元年(1648年)高野山で出家され、万治元年(1658年)南院良意から安祥寺流の許可を受けて以降、畿内で戒律護持等の講筵を盛んに開かれました。
元禄四年(1691年)、徳川五代将軍綱吉公に謁見して公の帰依を受け、側近・柳沢吉保の援助もあって徳川将軍家(幕府)の祈願所として湯島に霊雲寺を建立。
『悉曇三密鈔』(悉曇学書)、『別行次第秘記』(修行に関する解説書)、『通用字輪口訣』(意密(字輪観)の解説書)などの重要な著作を遺され、近世の真言(律)宗屈指の学徳兼備の傑僧と評されます。
浄厳和尚は霊雲寺で入寂されましたが、霊雲寺は将軍家祈願所であるため、みずから開山された塔頭の池之端・妙極院が墓所となっています。
浄厳和尚、そして霊雲寺を語るとき、「真言律宗」は外せないのでこれについてもまとめてみます。(主にWikipediaを参照)
真言律宗とは、真言密教の出家戒・「具足戒」と、金剛乗の戒律・「三昧耶戒」を修学する一派とされ、南都六宗の律宗の精神を受け継ぐ法系ともいわれます。
弘法大師空海を高祖とし、西大寺の叡尊(興正菩薩)を中興の祖とします。
叡尊は出家戒の授戒を自らの手で行い(自誓授戒)、独自の戒壇を設置したとされます。
「自誓授戒」は当時としては期を画すイベントで、新宗派の要件を備えるとして「鎌倉新仏教」のひとつとみる説さえあります。
→ ■ 日本仏教13宗派と御朱印(首都圏版)
真言律(宗)は当時律宗の新派とする説もあったとされますが、叡尊自身は既存の律宗が依る『四分律』よりも、弘法大師空海が重視された『十誦律』を重んじたため、真言宗の一派である「西大寺流」と規定して行動していた(Wikipedia)という説もあるようです。
以降、律宗は衰微した古義律、唐招提寺派の「南都律」、泉涌寺・俊芿系の「北京律」、そして西大寺系の「真言律(宗)」に分化することとなります。
叡尊の法流は弟子の忍性が承継し、忍性はとくに民衆への布教や社会的弱者の救済に才覚を顕したといいます。
鎌倉に極楽寺を建立したのは忍性です。
叡尊・忍性は朝廷の信任篤く、諸国の国分寺再建(勧進)を命じられたとされ、元寇における元軍の撃退も叡尊・忍性の呪法によるものという説があります。
江戸初期、西大寺系の律宗は真言僧・明忍により中興され、この流れを浄厳が引き継いで公に「真言律(宗)」を名乗ったといいます。
霊雲寺は「将軍家祈願所」であるとともに、関八州真言律宗総本寺を命じられ、御府内屈指の名刹の地位を保ちました。
明治5年、明治政府による仏教宗派の整理により、律宗系寺院の多くは真言宗に組み入れられましたが、その後独立の動きがおこり、西大寺は明治28年に真言律宗として独立しています。
真言律(宗)であった霊雲寺が真言宗霊雲寺総本山となった経緯はオフィシャルな資料が入手できず詳細不明ですが、Wikipediaには「昭和22年(1947年)に真言宗霊雲寺派を公称して真言律宗から独立した。」とあるので、戦後、江戸期に47を数えた末寺とともに独立したとみられます。
霊雲寺を「将軍家祈願寺」としてみるとき、興味ぶかい事柄があります。
真言律(宗)は、もともと民衆への布教・救済と国家鎮護という二面性をもった宗派でした。
とくに、元寇の戦捷祈願に叡尊・忍性が関与したとされることは国家鎮護の面での注目ポイントです。
元寇の戦捷祈願には、大元帥明王を御本尊とする大元帥法が修されたとも伝わります。
もともと大元帥法は国家鎮護・敵国降伏を祈って修される法で、毎年正月8日から17日間宮中の治部省内で修されたといいます。
のちに修法の場は醍醐寺理性院に遷された(江戸期に宮中の小御所に復活)ともいいますが、国家、朝廷のみが修することのできる大法とされています。
一方、霊雲寺の大元帥明王画像について、『御府内寺社備考』には「御祈祷本尊大元帥明王之画像 常憲院様(綱吉公)御自画と(中略)鎮護国家之御祈祷」とあります。
大元帥明王の画像を綱吉公みずからが描かれ、こちらを御本尊として鎮護国家を祈祷したというのです。
しかも大元帥明王が御座される御祈祷殿には、東照大権現も祀られています。
つまり、霊雲寺の御祈祷殿では大元帥明王と東照大権現に鎮護国家が祈祷されていたことになります。
しかも『御府内八十八ケ所道しるべ』には御府内霊場の拝所として「太元堂 灌順堂 本尊太元明王」と明記されています。
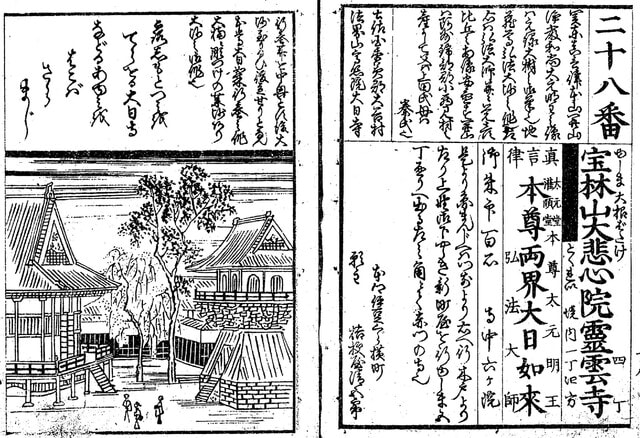
出典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
旧来、国家鎮護の大法・大元帥法の御本尊である大元帥明王は厳重に秘すべき存在でしたが、江戸時代になると、そこまでの厳格さは失われていたのでしょうか。
あるいは日の本の為政者としての徳川将軍家の存在を際立たせる、政治的な狙いもあったのやもしれません。
また、当山は「絹本着色大威徳明王像」(文京区指定文化財)を所蔵されます。
大威徳明王は単独で奉安されることは希で、通常、五大明王(不動明王(中心)、降三世明王(東)、軍荼利明王(南)、大威徳明王(西)、金剛夜叉明王(北))として奉安・供養されますから、当山で五大明王を御本尊とする五壇法が修せられていた可能性があります。
五壇法も国家安穏を祈願する修法として知られているので、やはり当山は祈願寺としての性格が強かったとみられます。
御本尊は両部(両界)大日如来。
「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」(東京国立博物館)には「独自の解釈による両界曼荼羅」とあり、大進美術㈱のWebに「新安祥寺流曼荼羅」として見事な両界曼荼羅が紹介されていることからみても、新安祥寺流(真言宗霊雲寺派)にとって両界曼荼羅、あるいは両界大日如来がとりわけ重要な存在であることがうかがわれます。
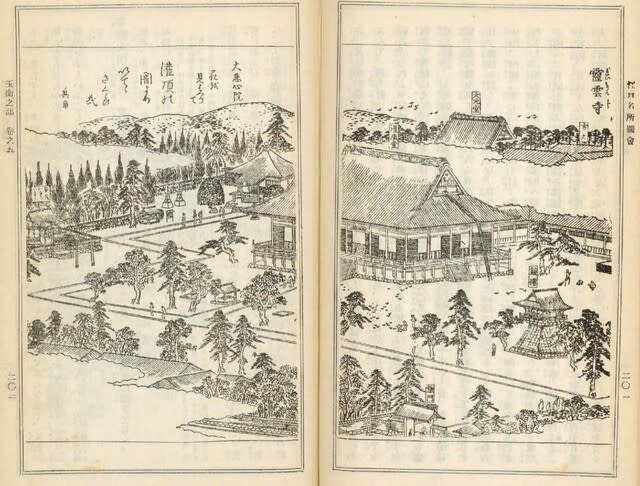
出典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
二十八番
ゆしま
宝林山 大悲心院 霊雲寺
真言律
本尊:両界大日如来 太元堂 灌順堂 本尊太元明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [68] 湯嶋寺院書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.142.』
江戸湯嶋(不唱小名)
(関東)真言律宗惣本寺
寶林山 佛日院 霊雲寺
開基 元禄四年(1691年) 浄厳和尚(浄厳律師覚彦)
本堂
本尊 両部大日如来木像
右 不動明王木像
左 愛染明王木像
四天王立像
御祈祷殿
本尊 大元帥明王画像
同 木像秘佛
東照大権現
寶幢閣
本尊 地蔵菩薩木像
右(左) 弘法大師木像
左(右) 開祖浄厳和尚木像
鎮守社
神体八幡大菩薩 賀茂大明神 稲荷大明神 三神合殿
右 冨士権現社
左 恵寶稲荷社
寺中六ヶ院
智厳院 本尊 地蔵菩薩
五大院 本尊 愛染明王
蓮光院 本尊 辨財天
寶光院 本尊 十一面観音
五智院 本尊 愛染明王
福厳院 本尊 釈迦如来
※ 妙極院(下谷七軒町、本尊 大日如来)を含めて塔頭七院
※ 末寺四拾七ヶ寺を記載
■ 『江戸名所図会 第3 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
寶林山 靈雲寺
大悲心院と号す。圓満寺の北の方にあり。関東眞言律の惣本寺にして、覺彦(かくげん)比丘の開基なり。
灌頂堂 両界の大日如来を安置す。
大元堂 灌頂堂のうしろ方丈の中にあり。本尊大元明王の像は元禄大樹の御筆なり。(以下略(大元法について記す))
鐘楼 本堂の右にあり。開山覺彦和尚自ら銘を作る。
地蔵堂 本堂の左の方艮の隅にあり。本尊地蔵菩薩 弘法大師の作なり。左右の脇壇に弘法大師、ならびに覺彦比丘の両像を安置す。
開山 諱は浄厳、字は覺彦、河州錦部郡小西見村の産なり。父は上田氏、母は秦氏なり。
寛永十六年(1639年)に生る。凡そ耳目の歴る所終に遺忘する事なし。衆人是を神童と称す。(中略)
慶安元年(1648年)高野山検校法雲を禮して薙染す。時に年十歳。朝参暮詣倦む事なし。(中略)元禄四年(1691年)、大将軍(常憲公=綱吉公)召見し給ひ、普門品を講ぜしむ。(中略)遂に城北にして地を賜ひ、梵刹を経始す。ここにおいて佛殿、僧房、香厨、門郭甍を連ね、巍然として一精藍となる。号(なづ)けて霊雲寺という。遂に密壇を建て秘法を行し(中略)元禄五年(1692年)六月、大元帥の大法を修し、國家昇平を祈る。これより以後、毎歳三神通月七日、修法することを永規とす。翌年関東眞言律の僧統となしたまふ。又乙亥の夏、大将軍(常憲公=綱吉公)みづから斎戒し給ひ、大元帥金剛の像を画き、本尊に下し賜ふ。今大元堂に安置し奉る。元禄十年(1697年)、僧俗の請に依って曼荼羅を開く。壇場に入る者九萬人に幾し。隔年灌頂を行ふこと今に至てたえず。(中略)徳化洋々として天下に彌布し。王公より下愚夫に至る迄敬仰せずといふことなし。
■ 『本郷区史 P.1232』(文京区立図書館デジタル文庫)
靈雲寺
湯島新花町に在り、眞言宗高野派の別格本山で寶林山佛日院と称する。元禄四年(1691年)将軍綱吉の建立する所で浄厳和尚を開基とし寺領百石を有した。本堂の外境内に地蔵堂、大元堂、観音堂、鐘楼、経蔵、内佛殿、庫裡、土蔵、学寮等を有したが、何れも大正十二年の震火災に焼失し其後は假建築を以て今日に及んで居る。寺寶の中には十六羅漢十六幅(顔輝筆) 吉野曼荼羅一幅、諸尊集會圖一幅等国寶に指定せられたるものゝ外尊重すべきもの多数を蔵したが何れも大正震火災に焼失した。(國寶は現存)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本郷湯島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
湯島といってもメイン通りから外れており、東京で生まれ育った人間でもあまり訪れることのない立地です。
このような場所に突如としてあらわれる大伽藍は、ある意味おどろきです。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 戒壇石
山門脇の石標に「不許葷辛酒肉入山内」とあります。
よく禅宗の寺院の山門脇に「不許葷酒入山門」(くんしゅさんもんにいるをゆるさず)と刻まれた標石が立っていますが、これは「戒壇石」といいます。
修行の妨げになるので、「葷」と「酒」は山内に持ち込んではいけない。あるいは「葷」と「酒」を口にしたものは山内に入ってはいけないという戒めです。
「葷」とはニンニク、韮、ラッキョウなどのにおいが強くて辛い野菜、あるいは生臭い肉料理などをさします。
なので、「葷」には「辛」も「肉」も含むはずですが、あえて「葷」「辛」「酒」「肉」すべて列挙して戒めているあたり、戒律を重んじる律宗系の流れの寺院であることが伝わってきます。


【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 山内
山門は薬医門か高麗門。
うかつにも内側からの写真を撮り忘れたので断言できませんが、正面からのたたずまいからすると高麗門のような感じもします。
屋根は本瓦葺でさすがに名刹の風格。見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 寺号標と大本堂
【写真 下(右)】 大本堂
山門をくぐると空間が広がり、正面階段のうえに昭和51年落成の鉄筋コンクリート造2階建ての大本堂(灌頂堂)。
築浅ながら名刹にふさわしい堂々たる大伽藍です。
上層は入母屋造本瓦葺葺、下層も本瓦葺で流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。


【写真 上(左)】 大本堂向拝
【写真 下(右)】 大本堂扁額
向拝見上げに院号扁額をおき、「西大寺 長老」の揮毫がみえます。
霊雲寺は真言律宗から分離独立して真言宗霊雲寺派総本山となりましたが、西大寺(真言律宗総本山)との関係は依然として深いのかもしれません。
大本堂(灌頂堂)には御本尊として両部(金剛界・胎蔵(界))の大日如来像を奉安。
大本堂の下は寺務所・書院となっています。


【写真 上(左)】 地蔵尊と寶幢閣
【写真 下(右)】 寶幢閣
大本堂向かって左手奥に堂宇があり、「寶幢閣」の扁額があります。
■ 『寺社書上 [68] 湯嶋寺院書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.142.』には、「寶幢閣」として、「本尊 地蔵菩薩木像、弘法大師木像、開祖浄厳和尚木像」とあり、『江戸名所図会』にはこの位置に「開山堂」とあるので、「大師堂」と「開山堂」の性格を併せ持つ堂宇であったとみられ、いまもこの系譜を受け継ぐ堂宇かもしれません。
なお、「寶幢閣」は「寶幢如来」ゆかりの堂号とも思われます。


【写真 上(左)】 寶幢閣の扁額
【写真 下(右)】 弘法大師記念供養塔
寶幢如来は胎蔵曼荼羅の中央の区画「中台八葉院」に御座される如来で、胎蔵大日如来(中央)、寶幢如来(東)、開敷華王如来(南)、無量寿如来(西)、天鼓雷音如来(北)とともに「胎蔵(界)五仏」と呼ばれます。
寶幢如来は「発心」(悟りを開こうとする心を起こすこと)を表す尊格とされます。
開山の浄厳覚彦和尚は啓蒙のためにかな書きの教学書を著わされ、多くの庶民に灌頂・受戒を行うなど衆生を仏道に導かれたとされるので、そのゆかりで「発心」(あるいは発菩提心)を表す寶幢如来の号をいただいているのかもしれません。
『江戸名所図会』には
「大悲心院 花を見はべりて 灌頂の闇よりいでてさくら哉 其角」
の句が載せられ、「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」(東京国立博物館)には「霊雲寺では目隠しをして敷曼荼羅に華を投げ、落ちた仏と結縁する結縁灌頂が盛んに行なわれた(中略)霊雲寺で結縁灌頂を受けた後、目隠しの闇と心の闇が同時に晴れる喜びを詠った宝井其角(1661~1707)の句が紹介されています。」とあって、霊雲寺の結縁灌頂が広く知られていたことがわかります。
「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」(東京国立博物館)には「多くの庶民に灌頂、授戒を行ない、啓蒙のためにかな書きの教学書を著すなど、浄厳と霊雲寺は民衆にも寄り添い親しまれる存在となりました。」とあり、江戸名所図会にも記されていることから、「将軍家祈願所」という厳めしい存在ながら案外庶民に親しまれ、御府内霊場の札所としても違和感なくとけこんでいたのでは。
↑ でも触れましたが、将軍家護持の御本尊・大元帥明王が御府内霊場の拝尊であったこと、「将軍家祈願所」という立ち位置ながら、庶民の結縁灌頂の場としての機能していたことなど、やはり霊雲寺は二面性をもつ寺院であったことがうかがわれます。
江戸期にあった大本堂裏手の太元堂もいまはなく、山内の伽藍構成はシンプルですが、寶幢閣前の百度石のうえに地蔵尊、立像の厄除大師像(記念供養塔)、梵字碑の前にも地蔵尊が御座します。
ふつう「祈願所」というと、密寺特有の濃密な空気をまとった寺院を想像しますが、こちらは徹底して明るい空間。
これは律宗の流れ、奈良仏教の平明さを受け継いでいるためかもしれません。


【写真 上(左)】 地蔵尊と梵字碑
【写真 下(右)】 御朱印授与案内
御朱印は寺務所にて拝受しました。
Web情報によると、お昼前後は授与を休止との情報あり要注意です。
なお、霊雲寺は歴史ある名刹だけあって多くの霊場札所となっていますが、現在、御朱印を授与されているのは御府内霊場のみの模様です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
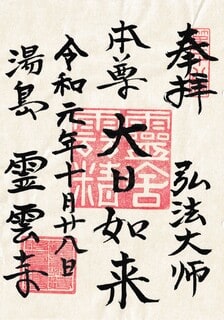
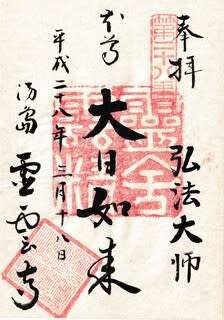
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と「霊雲精舎」の御印。
右上に「第二十八番」の札所印。左下には「湯島 霊雲寺」の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 「御本尊」申告にて拝受の御朱印
【写真 下(右)】 ご縁日の御朱印
「御本尊」申告にて拝受の御朱印には胎蔵大日如来のお種子「ア」の揮毫、ご縁日の御朱印には金剛界大日如来のお種子「バン」と胎蔵大日如来のお種子「ア」の揮毫があります。
「ア」は大元帥明王、寶幢如来のお種子でもあり、当山とは格別のゆかりのあるお種子ではないでしょうか。
なお、申告や日によってお種子の種類が定まっているかは不明です。
■ 第29番 大鏡山 薬師寺 南蔵院
(なんぞういん)
豊島区高田1-19-16
真言宗豊山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:豊島八十八ヶ所霊場第41番、東京三十三観音霊場第21番、大東京百観音霊場第71番、弁財天百社参り第44番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所
司元別当:(下高田村)氷川社
授与所:庫裡
御府内霊場には南蔵院と号する札所が練馬(第15番)、牛込(第22番)と高田(第29番)の3箇寺あり、それぞれ練馬南蔵院、牛込南蔵院、高田南蔵院と呼んで区別されます。
第29番札所も複雑な変遷をたどっています。
現在の第29番札所は高田南蔵院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では牛込七軒寺町の三明山 清谷寺 千手院となっています。
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第29番の(牛込七軒寺町)千手院は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第29番札所は高田南蔵院に承継されたとみられます。
下記資料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。
開山は圓成比丘(永和二年(1376年)寂)と伝わります。
御本尊の薬師如来は、奥州藤原秀衡の念持仏といわれ、圓成比丘が諸国遊化のみぎり、夢告によって彼の地の農家で入手し、当地(高田)を通りかかったところにわかに薬師如来像が重くなり、ここが薬師如来有縁の地として草庵を建て奉安したのが開創と伝わります。
御本尊の薬師如来は聖徳太子の御作ともいいます。
寛永(1624-1644年)の頃は、大猷院殿(徳川三代将軍家光公)が狩猟の折にしばしば訪れたと伝わり、仮御殿も建てられたといいます。
三遊亭円朝作の「怪談乳房榎」ゆかりの寺ともいわれます。
『江戸名所図会』の(高田)「氷川明神社」の項に「『南蔵院』の奉祀なり」とあるので、江戸期は(高田)「氷川明神社」の別当であった可能性があります。
つぎに旧29番札所とみられる千手院について、下記史料から追ってみます。
千手院は牛込七軒寺町にあり、足立郡西新井村惣持寺末の新義真言宗寺院でした。
開山 法印舜●(慶安三年(1650年)八月遷化)
慶長十二年(1607年)、手川口(場所不明)に創立され、寛永四年(1627年)御用地召上のため牛込橋場に遷ったようです。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
本堂には御本尊地蔵菩薩、阿弥陀如来、辨財天、愛染明王(弘法大師作)、弘法大師木坐像、興教大師木坐像を奉安。
観音堂には千手観世音菩薩、持國天、不動明王、弁財天、観喜天(秘佛)を奉安し、山内に稲荷社を祀っていたようです。
『御府内寺社備考』によると、観音堂の千手観世音菩薩は、もともと越後国に御座され、柴田勝家、蒲生氏郷、佐倉城主堀田家とゆかりをもたれた後、千手院に奉安されたようですが、達筆すぎて読解不明箇所が多く詳細はわかりません。
千手院は幕末~明治編纂の『御府内八十八ケ所道しるべ』に掲載されているので、明治に入ってから廃されたとみられます。
千手院の廃寺から御府内霊場第29番札所が高田南蔵院に承継された経緯は史料がみつからず不明ですが、千手院は西新井の惣持寺(西新井大師)末、南蔵院は大塚護國寺末で、ともに真言宗豊山派系なので豊山派の法系内で札所が承継されたのではないでしょうか。
また、牛込と高田は比較的近いということもあったかもしれません。
-------------------------
【史料】
【南蔵院関連】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(下高田村)南蔵院
新義真言宗大塚護國寺末 大鏡山醫王寺ト号ス 開山圓成比丘ト云 本尊薬師ハ聖徳太子ノ作長三尺 或云此像ハ奥州秀衡ノ持佛タリシカ 圓成比丘回國ノヲリ 夢ノ告アリテ笈ニウツシテ 此高田ノ里ニ至ルニ 笈俄ニ重リテ盤石ノ如シ 此地有縁ノ地ナレハトテ 草堂ヲイトナミ安置スト云 其後大橋龍慶佛道歸依ノ餘リシハラク 當寺ニ奇寓シケレハ 大猷院殿此邊御遊猟ノ時シハ々々ナラセラレ 御殿ナト御造營アリシトナリ 其頃中根壱岐守ヨリ龍慶に与ヘシ書状アリ 文後ニ出ス 當寺ヘ御成ノ時四方ヘ出入セル門アリ 八ヶ所門ト名付シト云 昔寺内ニ池アリ鏡カ池ト呼シトナリ 當時ノ山号モ是ヨリ起レリ 今境内ヲ流ルヽ小溝ヲ根川ト云
■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
大鏡山南蔵院
砂利場村にあり。真言宗にして、大塚の護國寺に属す。開山は圓成比丘と号す。本尊薬師佛は聖徳太子の作にして、立像三尺四寸あり。此霊像は秀衡の念持佛なりとて、養和年間の頃迄は、奥州平泉にありしを、圓成比丘、諸国遊化の時、霊夢を感じ、彼地の農家にして是を得て、此地に安置すといへり。(中略)寛永の頃は、大将軍家度々此に入らせ給ひしとて、仮の御殿なども構へ置れしとなり。
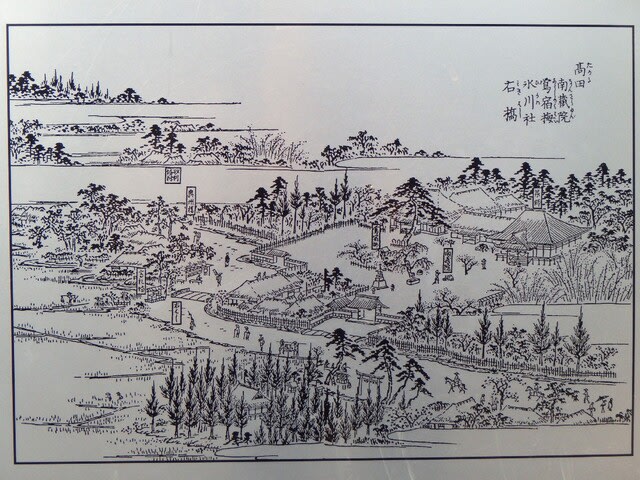
「高田」/出典:『江戸名所図会』(山内掲示より)
【千手院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
二十九番
牛込七軒寺町
三明山 清谷寺 千手院
西新井村惣持寺末 新義
本尊:千手観世音王 多聞天 持国天 弘法大師
■ 『寺社書上 [33] 牛込寺社書上 六』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.124』
牛込七軒寺町
武州足立郡西新井村惣持寺末真言宗豊山派
三明山 清谷寺 千手院
新義真言宗
開山 法印舜● 慶安三年(1650年)八月遷化
当寺起立之儀●慶長十二年手川口に造立
寛永四年御用地に●召上 牛込橋場
本堂
本尊 地蔵菩薩木坐像
阿弥陀如来木立像
辨財天木坐像
愛染明王木坐像 弘法大師作
弘法大師木坐像
興教大師木坐像
観音堂
千手観音立像
持國天立像
不動明王木立像 附二童子
弁財天木坐像
観喜天 秘佛
千手尊像脇士多聞持国の二天ともに赤梅壇毘首羯磨●也●●ハ越後国安臣山にあり 天正年中(1573-1592年)太閤秀吉●柴田勝家を討 柴田の一族安臣山●古もる 会津の城を蒲生氏郷に命じて●さしむ ●●の時●●三尊を守りて(以下解読不明)元和年中(1615-1624年)蒲生家●壊の後 殿地ハ下総佐倉城主堀田家の(以下解読不明)
稲荷社
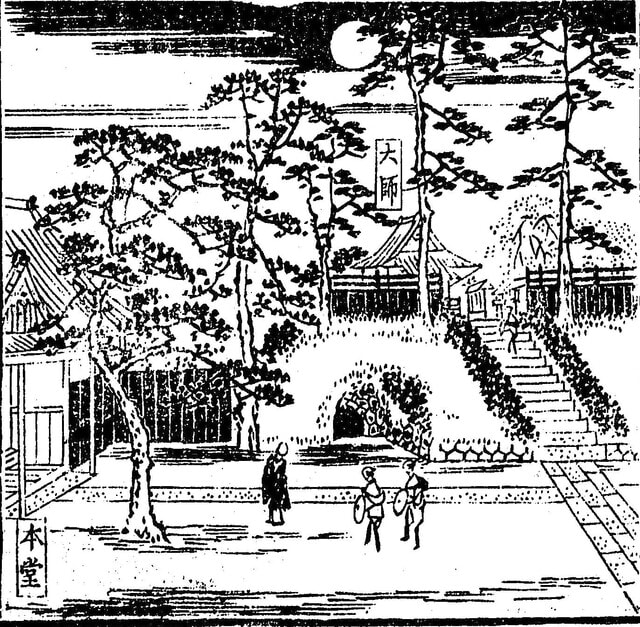
「千手院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
豊島区高田周辺は御府内霊場札所が4箇寺あり(29番南蔵院、35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺)、ふつうは4箇寺まとめての巡拝となります。
このあたりは土地の起伏が激しく、東京メトロ「雑司ヶ谷」駅からだと急な下り坂となります。
35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺は坂の途中にあり、南蔵院は神田川にもほど近い坂下に位置します。
カラフルな月替わり御朱印で有名な高田氷川神社にもほど近く、54番新長谷寺(目白不動尊)は江戸五色不動尊の一尊なので、一帯は御朱印エリアとなっています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 山内

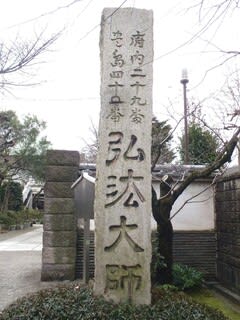
【写真 上(左)】 院号標
【写真 下(右)】 札所標
山門はないですが、山内入口両脇に院号標と札所標(御府内霊場、豊島霊場兼用)を備え、門柱と築地を巡らして風格ある構え。


【写真 上(左)】 辨財天
【写真 下(右)】 馬頭観世音碑
門柱を抜けると、多くの石仏群。
うち、弁財天の石碑は元禄九年(1696年)に神保長賢により寄進された山吹の里弁財天で、そばには弁財天像も御座されます。
南蔵院は弁財天百社参り第44番の札所ですが、こちらが札所本尊かもしれません。
端正な馬頭観世音碑も建っています。
『江戸名所図会』には参道脇に「鶯宿梅」が描かれ、これは徳川家光公お手植えの銘木といいますが現在はありません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は参道階段の上にありますが、参道や階段には植木鉢がところ狭しと並べられ、階段はシャッターで閉ざされているのでシャッター前からのお参りとなります。


【写真 上(左)】 本堂前階段
【写真 下(右)】 向拝
本堂は宝形造銅板葺と思われますが、定かではありません。
向かって右には銅板葺屋根の鐘楼を配しています。
向拝柱はなく、見上げに御本尊・薬師如来をあらわす「瑠璃光」の扁額。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 庫裡への道
御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。
豊島八十八ヶ所霊場第41番を兼務され、こちらの御朱印も授与されています。
また、東京三十三観音霊場第21番の御朱印(札所本尊:千手観世音菩薩)も拝受しています。
東京三十三観音霊場は、関東大震災の犠牲者の慰霊を目的として開創された観音霊場で、初番・発願は南品川の海晏寺、第33番・結願は墨田区横網の東京都慰霊堂。
札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様)
初番海晏寺、第12番雲照寺(代々木上原)、第15番心法寺(麹町)、 第17番天龍寺(新宿)など、現況御朱印不授与とみられる寺院を含み、授与寺院でもおおむね他霊場の御朱印となるため、こちらの霊場の御朱印は貴重です。
札所本尊の千手観世音菩薩が、旧千手院観音堂の堂宇本尊であった千手観世音菩薩であるかどうかはよくわかりません。
また、これまたナゾの多い大東京百観音霊場第71番の札所でもありますが、こちらの御朱印は授与されていない模様です。
〔 御府内霊場の御朱印 〕
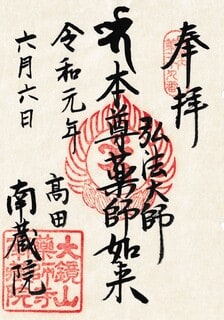
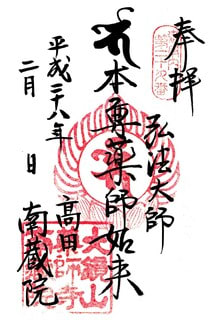
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第二十九番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

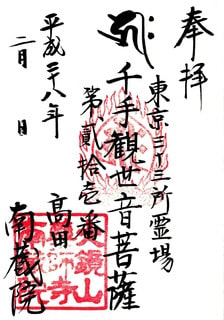
【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東京三十三観音霊場の御朱印
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-10)
【 BGM 】
■ December - milet
■ Flavor Of Life - 宇多田ヒカル
■ Parade - FictionJunction
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印-2
■ 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印-1からのつづきです。
第51番 泉久山 海照寺
横浜市磯子区坂下4-19
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第25番、横浜市内二十一ヶ所霊場第14番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第52番 明王山 不動院 寶積寺
横浜市磯子区上町7-13
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第26番、横浜市内二十一ヶ所霊場第13番、横浜磯子七福神(恵比寿)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


横浜市内二十一ヶ所霊場・横浜市内三十三観音霊場の御朱印
第53番 青龍山 宝金剛院 寶生寺
横浜市南区堀ノ内町1-68
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:
他札所:横浜市内三十三観音霊場第31番、横浜磯子七福神(寿老人)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
※不授与の模様です。

横浜磯子七福神(寿老人)のスタンプ
第54番 妙法山 観世音寺 弘誓院
横浜市南区睦町2-221
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第30番、横浜市内二十一ヶ所霊場第10番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


横浜市内三十三観音霊場の御朱印
第55番 南龍山 不動院 無量寺
横浜市南区蒔田町174
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第33番、武相二十八不動尊霊場第番16番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第7番
司元別当:(蒔田)杉山神社(南区宮元町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


武相二十八不動尊霊場の御朱印
第56番 松峯山 宝杉院 大光寺
横浜市南区南太田町2-167
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第6番、横浜市内二十一ヶ所霊場第9番
司元別当:(太田)杉山神社(南区南太田)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第57番 十輪山 延命寺 西光院
横浜市南区永田東1-22-3
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩?
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:
司元別当:(永田)春日神社(南区永田東)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第58番 西向山 妙觀院 乗蓮寺
横浜市南区井土ヶ谷上町33-1
高野山真言宗
御本尊:阿彌陀三尊・不動明王
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:
司元別当:住吉神社(南区井土ヶ谷上町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第59番 引越山 福壽院 定光寺
横浜市南区六ッ川町1-270
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:薬師如来
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


御本尊の御朱印
第60番 瑞應山 蓮華院 弘明寺
横浜市南区弘明寺町267
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:大日如来
他札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第14番、横浜市内三十三観音霊場第33番、武相二十八不動尊霊場第18番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第2番、七観音霊場第2番
司元別当:
授与所:山内授与所
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
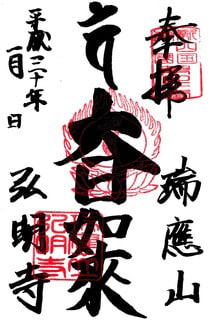


【写真 上(左)】 弘法大師の御朱印
【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印


【写真 上(左)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 七観音霊場の御朱印
※他にも多種の御朱印を授与されています。
第61番 慈雲山 如意珠院 吉祥寺
横浜市南区大岡1-6-1
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:大日如来
他札所:
司元別当:(下大岡村)若宮社
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第62番 雨寶山 瑠璃院 萬福寺
横浜市南区大岡5-39-17
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:
司元別当:(下大岡村)神明社・諏訪社
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第63番 大岡山 蓮上院 眞光寺
横浜市港南区上大岡東3-1-1
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:毘沙門天王
他札所:武相四十八ヶ所不動尊霊場第32番
司元別当:上大岡鹿嶋神社(港南区上大岡西)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第64番 瑠璃山 金剛院
横浜市磯子区岡村5-3-1
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:横浜磯子七福神(大黒天)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


横浜磯子七福神(大黒天)の御朱印
第65番 西岸山 蓮華寺 千手院
横浜市港南区最戸2-21-1
真言宗大覚寺派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:一光三尊
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第66番 大久保山 地蔵寺 自性院
横浜市港南区大久保2-34-15
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:
司元別当:青木神社(港南区大久保)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


御本尊の御朱印
第67番 南光山 慈眼寺 福聚院
横浜市港南区港南1-3-2
高野山真言宗
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:薬師如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第27番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


武州金沢三十四観音霊場の御朱印
第68番 福聚山 光明寺
横浜市港南区日野7-19-19
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第25番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第33番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


武州金沢三十四観音霊場の御朱印
第69番 日野山 徳恩寺
横浜市港南区日野中央2-10-14
高野山真言宗
御本尊:延命地蔵菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:武州金沢三十四観音霊場第24番
司元別当:(日野)春日神社(港南区日野中央)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
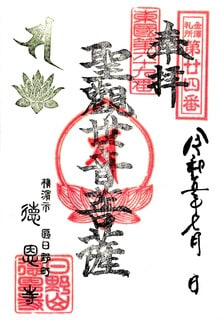

御本尊の御朱印
第70番 鬨宮山 東樹院
横浜市港南区笹下2-24-17
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:馬頭明王
他札所:武州金沢三十四観音霊場第28番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第71番 花翁山 慶珊寺
横浜市金沢区富岡東4-1-8
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第32番、金沢八景三十三札所第2番、第32番、かなざわの霊場めぐり第2番
司元別当:富岡八幡宮(金沢区富岡東)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第72番 地福山 宝珠院
横浜市金沢区富岡東5-8-19
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:金沢八景三十三札所第3番、かなざわの霊場めぐり第3番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第73番 海照山 持明院
横浜市金沢区富岡東5-8-34
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第33番、第34番、金沢八景三十三札所第4番、第33番、かなざわの霊場めぐり第4番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第74番 三療山 医王院 薬王寺
横浜市金沢区寺前2-23-52
真言宗御室派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第4番、金沢八景三十三札所第24番、かなざわの霊場めぐり第24番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
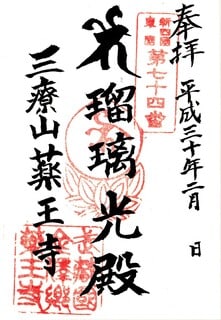
第75番 金澤山 彌勒院 稱名寺
横浜市金沢区金沢町212-1
真言律宗
御本尊:弥勒菩薩
札所本尊:弥勒菩薩
他札所:武州金沢三十四観音霊場第1番、第2番、第3番、金沢八景三十三札所第26番、かなざわの霊場めぐり第26番
司元別当:
授与所:授与所
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕



【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 ぼさつの寺めぐりの御朱印
第76番 此木山 西方寺 寶蔵院
横浜市金沢区柴町214
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:薬師如来
他札所:金沢八景三十三札所第25番、横浜金澤七福神(寿老人)、かなざわの霊場めぐり第25番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


御本尊の御朱印
第77番 野鳥山 染王寺
横浜市金沢区野島町5-1
真言宗御室派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:金沢八景三十三札所第8番、金沢八景三十三札所第19番、かなざわの霊場めぐり第19番
司元別当:野島稲荷神社(金沢区野島町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
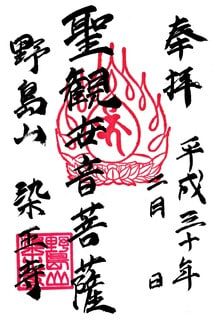
第78番 知足山 彌勒院 龍華寺
横浜市金沢区洲崎9-31
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:金沢八景三十三札所第6番、第7番、金沢八景三十三札所第20番、横浜金澤七福神(大黒天)、富士見楽寿(ぼけ封じ)観音霊場第2番、かなざわの霊場めぐり第20番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
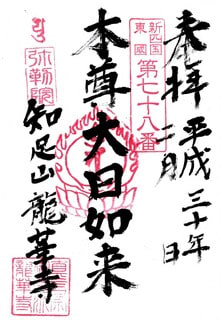

横浜金澤七福神(大黒天)の御朱印
第79番 青龍山 東昌寺
逗子市池子2-8-33
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:三浦半島七阿弥陀霊場第1番、三浦半島四十八阿弥陀霊場第1番、湘南七福神(福禄寿)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


弘法大師の御朱印
第80番 黄雲山 地蔵密院 延命寺
逗子市逗子3-1-17
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所本尊:金剛界大日如来
他札所:三浦三十八地蔵尊霊場第24番、三浦二十八不動尊霊場第28番、三浦半島観音三十三札所第1番、三浦干支守り本尊八佛霊場第8番、湘南七福神(弁財天)
司元別当:亀岡八幡宮(逗子市逗子)
授与所:寺務所
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕



【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 三浦三十八地蔵尊霊場の御朱印


【写真 上(左)】 三浦二十八不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 三浦干支守り本尊八佛霊場の御朱印
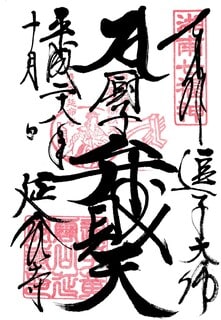
湘南七福神(弁財天)の御朱印
第81番 南向山 帰命院 補陀洛寺
鎌倉市材木座6-7-31
真言宗大覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:鎌倉三十三観音霊場第17番、相州二十一ヶ所霊場第10番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
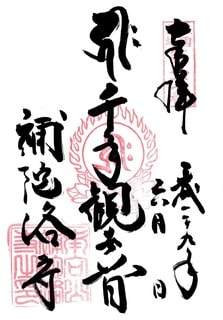


【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
第82番 泉谷山 浄光明寺
鎌倉市扇ガ谷2-12-1
真言宗泉涌寺派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:鎌倉三十三観音霊場第25番、鎌倉二十四地蔵霊場第16番、第17番、相州二十一ヶ所霊場第6番、鎌倉十三仏霊場第9番、鎌倉六阿弥陀霊場第4番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
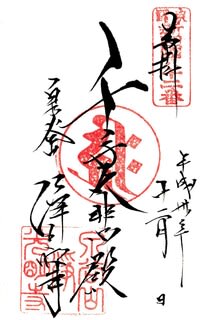
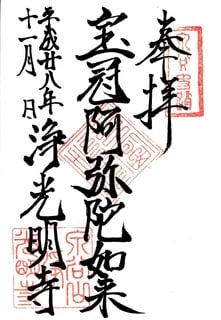

【写真 上(左)】 御本尊(鎌倉六阿弥陀霊場)の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印


【写真 上(左)】 鎌倉二十四地蔵霊場第16番の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場第17番の御朱印


【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉十三仏霊場の御朱印
第83番 普明山 法立寺 成就院
鎌倉市極楽寺1-1-5
真言宗大覚寺派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、鎌倉十三仏霊場第13番(星井寺)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕



【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印

鎌倉十三仏霊場(星井寺)の御朱印
第84番 龍護山 満福寺
鎌倉市腰越2-4-8
真言宗大覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:相州二十一ヶ所霊場第15番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第50番、小田急武相三十三観音霊場第33番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


相州二十一ヶ所霊場の御朱印
第85番 小動山 浄泉寺
鎌倉市腰越2-10-7
真言宗大覚寺派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:相州二十一ヶ所霊場第16番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第29番
司元別当:小動神社(鎌倉市腰越)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


相州二十一ヶ所霊場の御朱印
第86番 加持山 宝善院
鎌倉市腰越5-13-17
真言宗大覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:相模国準四国八十八ヶ所霊場第40番、小田急武相三十三観音霊場第32番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第87番 寶盛山 薬師院 密蔵寺
藤沢市片瀬3-3-44
真言宗大覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:観世音菩薩
他札所:相州二十一ヶ所霊場第17番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第17番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

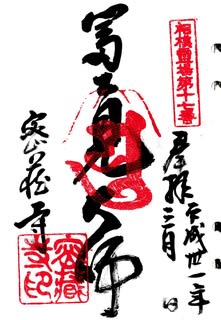
相州二十一ヶ所霊場の御朱印
第88番 飯盛山 仁王院 青蓮寺
鎌倉市手広5-1-8
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:薬師如来
他札所:相州二十一ヶ所霊場第19番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第27番、関東八十八箇所霊場第59番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
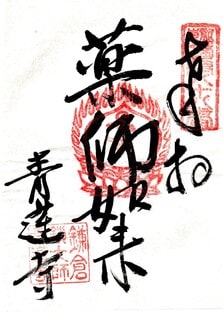


【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(鎖大師)
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(愛染明王)

関東八十八箇所霊場の御朱印
【 BGM 】
■ On My Own - Patti LaBelle feat. Michael McDonald
■ Never Too Far to Fall - George Benson
■ Has It Come To This - Amy Keys
第51番 泉久山 海照寺
横浜市磯子区坂下4-19
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第25番、横浜市内二十一ヶ所霊場第14番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第52番 明王山 不動院 寶積寺
横浜市磯子区上町7-13
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第26番、横浜市内二十一ヶ所霊場第13番、横浜磯子七福神(恵比寿)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


横浜市内二十一ヶ所霊場・横浜市内三十三観音霊場の御朱印
第53番 青龍山 宝金剛院 寶生寺
横浜市南区堀ノ内町1-68
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:
他札所:横浜市内三十三観音霊場第31番、横浜磯子七福神(寿老人)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
※不授与の模様です。

横浜磯子七福神(寿老人)のスタンプ
第54番 妙法山 観世音寺 弘誓院
横浜市南区睦町2-221
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第30番、横浜市内二十一ヶ所霊場第10番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


横浜市内三十三観音霊場の御朱印
第55番 南龍山 不動院 無量寺
横浜市南区蒔田町174
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第33番、武相二十八不動尊霊場第番16番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第7番
司元別当:(蒔田)杉山神社(南区宮元町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


武相二十八不動尊霊場の御朱印
第56番 松峯山 宝杉院 大光寺
横浜市南区南太田町2-167
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第6番、横浜市内二十一ヶ所霊場第9番
司元別当:(太田)杉山神社(南区南太田)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第57番 十輪山 延命寺 西光院
横浜市南区永田東1-22-3
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩?
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:
司元別当:(永田)春日神社(南区永田東)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第58番 西向山 妙觀院 乗蓮寺
横浜市南区井土ヶ谷上町33-1
高野山真言宗
御本尊:阿彌陀三尊・不動明王
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:
司元別当:住吉神社(南区井土ヶ谷上町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第59番 引越山 福壽院 定光寺
横浜市南区六ッ川町1-270
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:薬師如来
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


御本尊の御朱印
第60番 瑞應山 蓮華院 弘明寺
横浜市南区弘明寺町267
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:大日如来
他札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第14番、横浜市内三十三観音霊場第33番、武相二十八不動尊霊場第18番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第2番、七観音霊場第2番
司元別当:
授与所:山内授与所
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
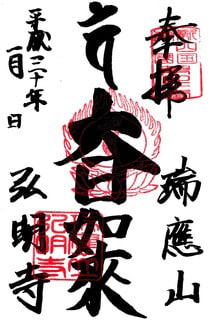


【写真 上(左)】 弘法大師の御朱印
【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印


【写真 上(左)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 七観音霊場の御朱印
※他にも多種の御朱印を授与されています。
第61番 慈雲山 如意珠院 吉祥寺
横浜市南区大岡1-6-1
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:大日如来
他札所:
司元別当:(下大岡村)若宮社
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第62番 雨寶山 瑠璃院 萬福寺
横浜市南区大岡5-39-17
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:
司元別当:(下大岡村)神明社・諏訪社
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第63番 大岡山 蓮上院 眞光寺
横浜市港南区上大岡東3-1-1
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:毘沙門天王
他札所:武相四十八ヶ所不動尊霊場第32番
司元別当:上大岡鹿嶋神社(港南区上大岡西)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第64番 瑠璃山 金剛院
横浜市磯子区岡村5-3-1
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:横浜磯子七福神(大黒天)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


横浜磯子七福神(大黒天)の御朱印
第65番 西岸山 蓮華寺 千手院
横浜市港南区最戸2-21-1
真言宗大覚寺派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:一光三尊
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第66番 大久保山 地蔵寺 自性院
横浜市港南区大久保2-34-15
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:
司元別当:青木神社(港南区大久保)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


御本尊の御朱印
第67番 南光山 慈眼寺 福聚院
横浜市港南区港南1-3-2
高野山真言宗
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:薬師如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第27番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


武州金沢三十四観音霊場の御朱印
第68番 福聚山 光明寺
横浜市港南区日野7-19-19
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第25番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第33番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


武州金沢三十四観音霊場の御朱印
第69番 日野山 徳恩寺
横浜市港南区日野中央2-10-14
高野山真言宗
御本尊:延命地蔵菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:武州金沢三十四観音霊場第24番
司元別当:(日野)春日神社(港南区日野中央)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
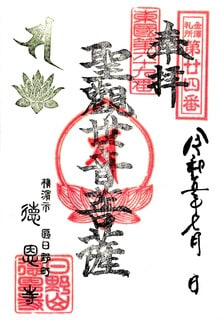

御本尊の御朱印
第70番 鬨宮山 東樹院
横浜市港南区笹下2-24-17
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:馬頭明王
他札所:武州金沢三十四観音霊場第28番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第71番 花翁山 慶珊寺
横浜市金沢区富岡東4-1-8
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第32番、金沢八景三十三札所第2番、第32番、かなざわの霊場めぐり第2番
司元別当:富岡八幡宮(金沢区富岡東)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第72番 地福山 宝珠院
横浜市金沢区富岡東5-8-19
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:金沢八景三十三札所第3番、かなざわの霊場めぐり第3番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第73番 海照山 持明院
横浜市金沢区富岡東5-8-34
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第33番、第34番、金沢八景三十三札所第4番、第33番、かなざわの霊場めぐり第4番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第74番 三療山 医王院 薬王寺
横浜市金沢区寺前2-23-52
真言宗御室派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:武州金沢三十四観音霊場第4番、金沢八景三十三札所第24番、かなざわの霊場めぐり第24番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
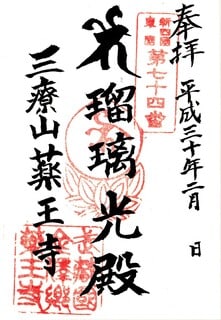
第75番 金澤山 彌勒院 稱名寺
横浜市金沢区金沢町212-1
真言律宗
御本尊:弥勒菩薩
札所本尊:弥勒菩薩
他札所:武州金沢三十四観音霊場第1番、第2番、第3番、金沢八景三十三札所第26番、かなざわの霊場めぐり第26番
司元別当:
授与所:授与所
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕



【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 ぼさつの寺めぐりの御朱印
第76番 此木山 西方寺 寶蔵院
横浜市金沢区柴町214
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:薬師如来
他札所:金沢八景三十三札所第25番、横浜金澤七福神(寿老人)、かなざわの霊場めぐり第25番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


御本尊の御朱印
第77番 野鳥山 染王寺
横浜市金沢区野島町5-1
真言宗御室派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:金沢八景三十三札所第8番、金沢八景三十三札所第19番、かなざわの霊場めぐり第19番
司元別当:野島稲荷神社(金沢区野島町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
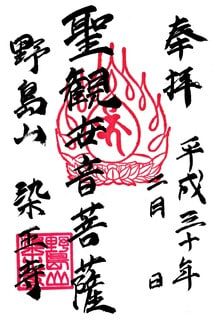
第78番 知足山 彌勒院 龍華寺
横浜市金沢区洲崎9-31
真言宗御室派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:金沢八景三十三札所第6番、第7番、金沢八景三十三札所第20番、横浜金澤七福神(大黒天)、富士見楽寿(ぼけ封じ)観音霊場第2番、かなざわの霊場めぐり第20番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
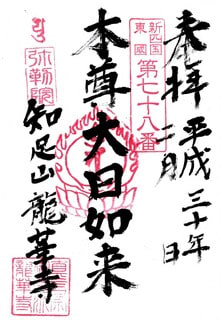

横浜金澤七福神(大黒天)の御朱印
第79番 青龍山 東昌寺
逗子市池子2-8-33
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:三浦半島七阿弥陀霊場第1番、三浦半島四十八阿弥陀霊場第1番、湘南七福神(福禄寿)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


弘法大師の御朱印
第80番 黄雲山 地蔵密院 延命寺
逗子市逗子3-1-17
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所本尊:金剛界大日如来
他札所:三浦三十八地蔵尊霊場第24番、三浦二十八不動尊霊場第28番、三浦半島観音三十三札所第1番、三浦干支守り本尊八佛霊場第8番、湘南七福神(弁財天)
司元別当:亀岡八幡宮(逗子市逗子)
授与所:寺務所
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕



【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 三浦三十八地蔵尊霊場の御朱印


【写真 上(左)】 三浦二十八不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 三浦干支守り本尊八佛霊場の御朱印
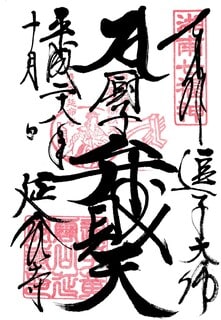
湘南七福神(弁財天)の御朱印
第81番 南向山 帰命院 補陀洛寺
鎌倉市材木座6-7-31
真言宗大覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:鎌倉三十三観音霊場第17番、相州二十一ヶ所霊場第10番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
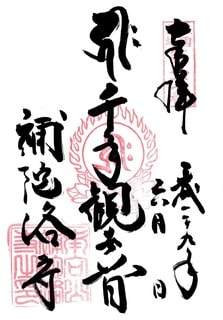


【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
第82番 泉谷山 浄光明寺
鎌倉市扇ガ谷2-12-1
真言宗泉涌寺派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:鎌倉三十三観音霊場第25番、鎌倉二十四地蔵霊場第16番、第17番、相州二十一ヶ所霊場第6番、鎌倉十三仏霊場第9番、鎌倉六阿弥陀霊場第4番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
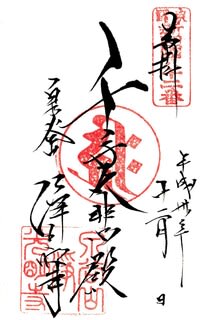
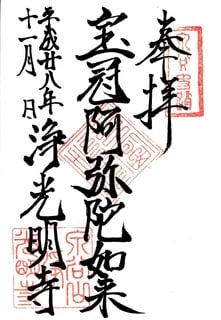

【写真 上(左)】 御本尊(鎌倉六阿弥陀霊場)の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印


【写真 上(左)】 鎌倉二十四地蔵霊場第16番の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場第17番の御朱印


【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉十三仏霊場の御朱印
第83番 普明山 法立寺 成就院
鎌倉市極楽寺1-1-5
真言宗大覚寺派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:鎌倉三十三観音霊場第21番、相州二十一ヶ所霊場第13番、鎌倉十三仏霊場第13番(星井寺)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕



【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印

鎌倉十三仏霊場(星井寺)の御朱印
第84番 龍護山 満福寺
鎌倉市腰越2-4-8
真言宗大覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:相州二十一ヶ所霊場第15番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第50番、小田急武相三十三観音霊場第33番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


相州二十一ヶ所霊場の御朱印
第85番 小動山 浄泉寺
鎌倉市腰越2-10-7
真言宗大覚寺派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:相州二十一ヶ所霊場第16番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第29番
司元別当:小動神社(鎌倉市腰越)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


相州二十一ヶ所霊場の御朱印
第86番 加持山 宝善院
鎌倉市腰越5-13-17
真言宗大覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:相模国準四国八十八ヶ所霊場第40番、小田急武相三十三観音霊場第32番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第87番 寶盛山 薬師院 密蔵寺
藤沢市片瀬3-3-44
真言宗大覚寺派
御本尊:薬師如来
札所本尊:観世音菩薩
他札所:相州二十一ヶ所霊場第17番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第17番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

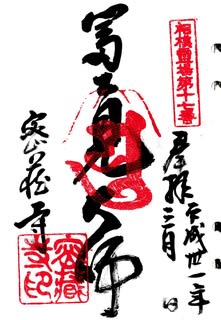
相州二十一ヶ所霊場の御朱印
第88番 飯盛山 仁王院 青蓮寺
鎌倉市手広5-1-8
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:薬師如来
他札所:相州二十一ヶ所霊場第19番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第27番、関東八十八箇所霊場第59番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
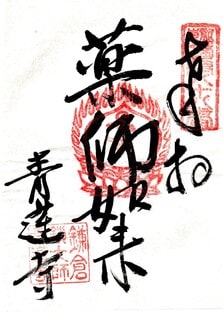


【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(鎖大師)
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(愛染明王)

関東八十八箇所霊場の御朱印
【 BGM 】
■ On My Own - Patti LaBelle feat. Michael McDonald
■ Never Too Far to Fall - George Benson
■ Has It Come To This - Amy Keys
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印-1
鎌倉、材木座の南向山 補陀落寺。
こちらは鎌倉三十三観音霊場第16番の札所で、鎌倉観音霊場巡拝で訪れる人は少なくありません。
こちらは相州二十一ヶ所霊場第10番の札所でもあって、かなりマニアック(?)な霊場ですが、それでもある程度の巡拝者はいるかと思われます。
鎌倉三十三観音霊場の御朱印尊格は御本尊の十一面観世音菩薩。
相州二十一ヶ所霊場の御朱印尊格は「秘鍵大師」です。
ところがWeb検索でごく希に「千手観世音」の御朱印がヒットすることがあります。
これが新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印です。


【写真 上(左)】 補陀落寺の鎌倉観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 補陀落寺の相州二十一ヶ所の御朱印
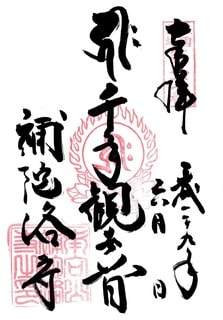
■ 補陀落寺の新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印
新四国東国八十八ヶ所霊場は川崎から横浜、そして逗子、鎌倉、藤沢と巡拝する神奈川県の弘法大師霊場(八十八ヶ所)です。
初番・発願は川崎大師(平間寺)、第88番の結願は鎌倉・手広の青蓮寺。
番外や掛所はなく、八十八の札所はすべて真言宗寺院です。
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
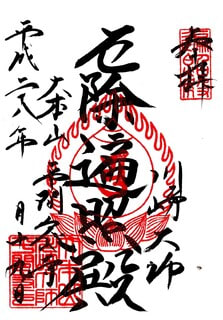
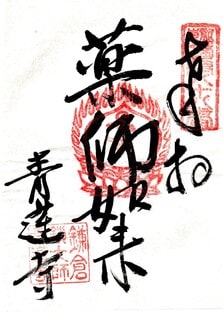
【写真 上(左)】 初番・発願の川崎大師(平間寺)の御朱印
【写真 下(右)】 第88番・結願の青蓮寺の御朱印
川崎エリアの札所は玉川八十八ヶ所との重複札所が多く、どうしても情報が多く専用納経帳も用意されている玉川八十八ヶ所霊場から巡拝することになります。
玉川八十八ヶ所霊場の初番・発願も川崎大師(平間寺)で、こちらは平間寺様がとりまとめを担われている模様。
一方、新四国東国霊場は現在、平間寺様はとりまとめにノータッチとみられ、新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印は授与されていません。
そんなこともあって新四国東国霊場の御朱印コンプリートは困難とあきらめていましたが、こつこつとまわっているうちに、意外に札所印つきの御朱印をいただけることに気づき、弘法大師御生誕1250年の今年の結願をもくろみ、数年がかりでようやく結願に漕ぎ着けました。
新四国東国霊場はすこぶる情報が少なく、ガイドブックはおろかリーフレットさえみたことがありません。
そのわりにしっかりとした札所標が設置されていたりして、どうもナゾの多い霊場です。
88の札所のうち御朱印を拝受できたのは87(残る1寺は七福神スタンプ)。その多くは札所印つきです。
お納めは概ね300円。専用納経帳がないので揮毫(書入れ)、印判捺、書置と授与形態は多彩です。
新四国東国霊場で面白いのは、ふつう弘法大師霊場では御本尊ないし弘法大師が札所本尊となりますが、新四国東国霊場では別尊や境内仏が札所本尊となる例がみられることです。
玉川八十八ヶ所霊場の札所本尊はおおむね御本尊なので、玉川、東国両札所兼任のお寺様ではそれぞれ異なる尊格の御朱印を拝受できる場合があります。
■ 上記の例/龍宿山 西明寺(川崎市中原区小杉御殿町/第9番)


【写真 上(左)】 玉川霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東国霊場の御朱印
↑ 玉川霊場は御本尊の金剛界大日如来、東国霊場は釈迦如来。
■ 坂東霊場と御朱印尊格が異なる例/瑞応山 弘明寺(横浜市南区弘明寺町/第60番)

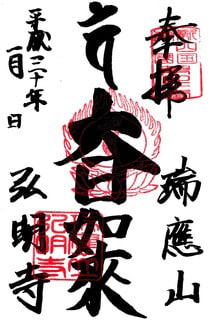
【写真 上(左)】 坂東霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東国霊場の御朱印
↑ 坂東霊場は御本尊の十一面観世音菩薩、東国霊場は金剛界大日如来。
実際、新四国東国霊場の札所本尊については情報が少ないため、拝所がよくわからず、先に御朱印をお願いすると同時に札所本尊についてお伺いするというかたちをとりました。(拝所が本堂ではない場合がある。)
札所の多くは他霊場との兼務で、新四国東国霊場は巡拝者が少ないため御朱印申告時は要注意です。
「八十八ヶ所」で申告すると玉川霊場、「弘法大師霊場」で申告すると相州二十一ヶ所と間違われる可能性があります。
実際、申告時に「東国霊場の御朱印ですね」と念を押されたケースが何度もありました。
しっかり「新四国東国霊場第●番でお願いします。」とお伝えすると間違いがないかと思います。
また、筆者は新四国東国霊場専用の御朱印帳をつくって巡拝したのですが、この場合はすべての御朱印がこの霊場なので間違いが少なくなると思います。
重複霊場としては、
川崎エリアで玉川八十八ヶ所霊場、東海三十三観音霊場、准秩父三十四観音霊場、准四国稲毛三十三観音霊場、武相二十八不動、川崎七福神。
横浜東部エリアで玉川八十八ヶ所霊場、准秩父三十四観音霊場、武相卯歳四十八観音霊場、旧小机領三十三観音霊場、横浜七福神。
横浜西南部エリアで坂東霊場、武州金沢三十四観音霊場、横浜磯子七福神、横浜金澤七福神。
逗子・鎌倉エリアで鎌倉三十三観音霊場、鎌倉二十四地蔵霊場、相州二十一ヶ所霊場、鎌倉十三仏霊場、相模国準四国八十八ヶ所霊場、小田急武相三十三観音霊場、関東八十八箇所霊場などがあります。
札所寺院は駅から離れたところがあり、札所範囲も広いため車での巡拝が有効です。
おおむね駐車場はありますが、入り組んだ路地や高低差のあるアプローチが多く、運転にはかなり気を使います。
見どころが多い札所もあるので、時間に余裕をもった巡拝をおすすめします。
それでは、順に御朱印をご紹介していきます。
新四国東国霊場の札所本尊は御本尊と異なるケースがあること、またエリア毎に兼務霊場が変わっていく様子もわかるので、拝受した御朱印はすべて掲載します。
第1番 金剛山 金乗院 平間寺(川崎大師)
川崎市川崎区大師町4-48
真言宗智山派
御本尊:弘法大師
札所本尊:
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第1番、関東八十八箇所霊場特別霊場、関東三十六不動尊霊場第7番、武相二十八不動尊霊場第1番、東海三十三観音霊場第33番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第1番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第15番
司元別当:大師稲荷神社(川崎区中瀬)
授与所:授与所
※平間寺様では、新四国東国霊場の御朱印は授与されていません。
〔 御本尊の御朱印 〕
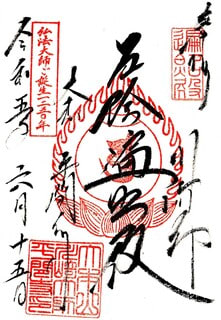
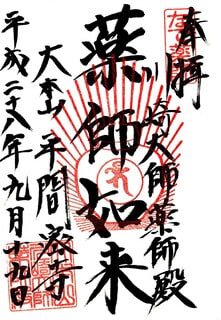
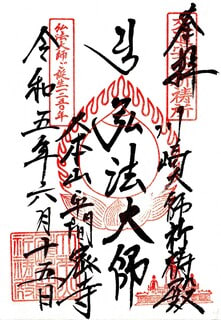
【写真 上(左)】 薬師殿の御朱印
【写真 下(右)】 自動車交通安全祈祷殿の御朱印
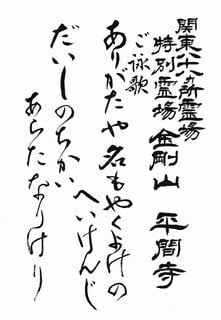
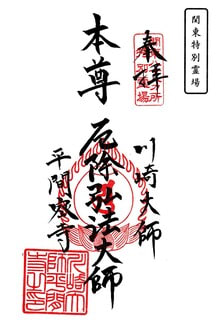
関東八十八箇所霊場の御朱印
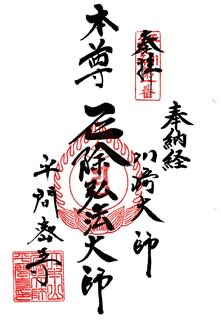
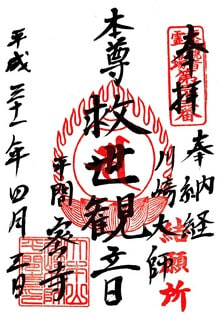
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
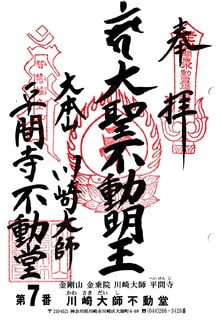
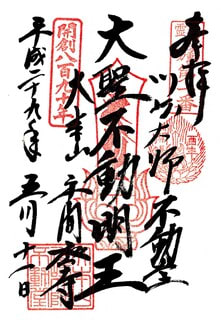
【写真 上(左)】 関東三十六不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
第2番 瑠璃光山 金剛院 真福寺
川崎市川崎区堀之内町11-7
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第13番、東海三十三観音霊場番外、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第11番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
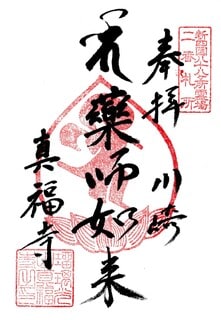

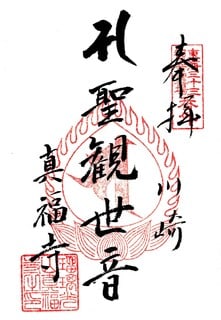
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第3番 大島山 般若院 真観寺
川崎市川崎区大島2-10-16
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第2番、東海三十三観音霊場第4番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第2番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

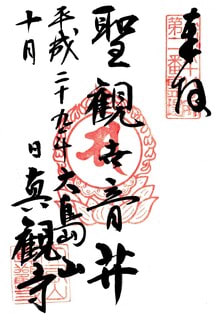
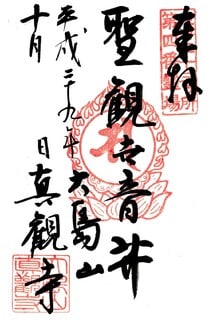
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第4番 明王山 聖無動寺 成就院
川崎市川崎区渡田3-8-1
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:大日如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第4番、東海三十三観音霊場第5番、武相二十八不動尊霊場第27番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第4番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕



【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
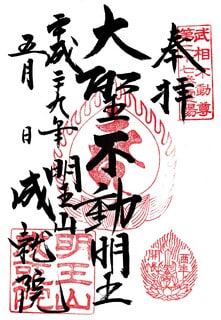
武相二十八不動尊霊場の御朱印
第5番 金澤山 福泉寺 圓能院
川崎市川崎区小田1-25-12
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:延命地蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第6番、東海三十三観音霊場第6番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第5番
司元別当:日枝大神社(川崎区小田)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
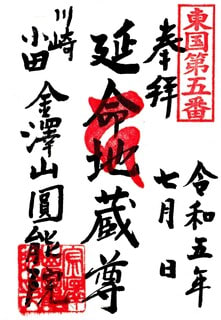
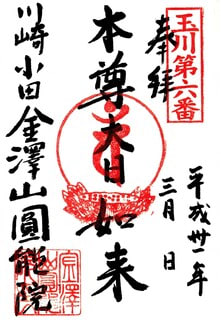
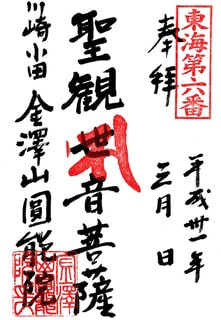
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第6番 圓明山 宝蔵院 延命寺
川崎市幸区都町4-2
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:薬師如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第14番、東海三十三観音霊場第15番
司元別当:女躰大神(幸区幸町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
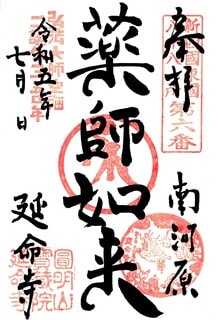
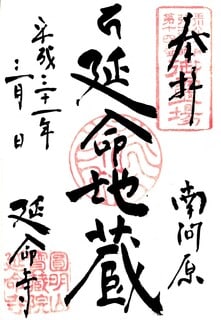
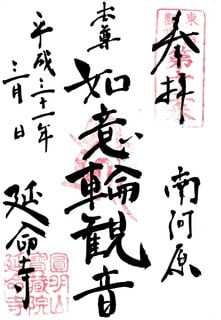
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第7番 瑠璃光山 長壽院 無量寺
川崎市中原区中丸子498
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第17番、川崎七福神(寿老神)、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第30番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

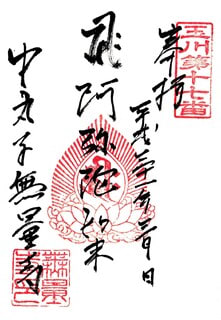
玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
第8番 西光山 東福寺
川崎市中原区市ノ坪45
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第21番、准秩父三十四観音霊場第10番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第32番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
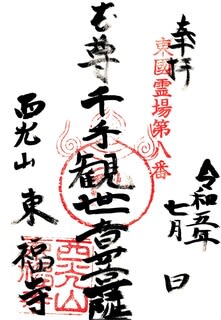

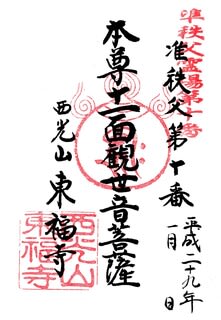
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 准秩父三十四観音霊場の御朱印
第9番 龍宿山 金剛院 西明寺
川崎市中原区小杉御殿町1-906
真言宗智山派
御本尊:金剛界大日如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第20番、准四国稲毛三十三観音霊場第18番、川崎七福神(大黒天)、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第36番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


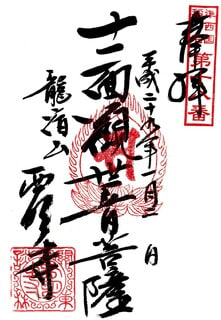
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 准四国稲毛三十三観音霊場の御朱印
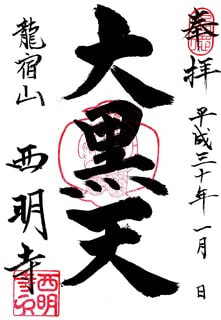
川崎七福神(大黒天)の御朱印
第10番 光明山 遍照院 金剛寺
横浜市鶴見区市場下町6-33
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第11番、東海三十三観音霊場第9番
司元別当:(鶴見)熊野神社
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
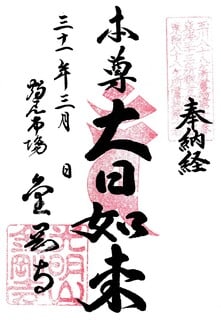
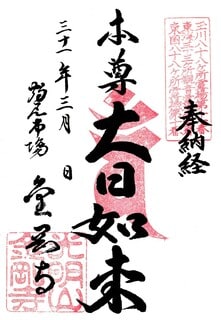
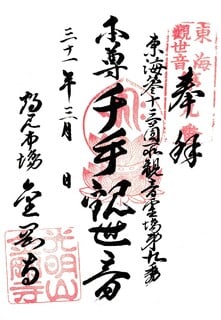
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第11番 金胎山 東住院 東漸寺
横浜市鶴見区潮田町3-144-2
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:薬師如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第7番、東海三十三観音霊場第30番
司元別当:潮田神社(鶴見区潮田町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
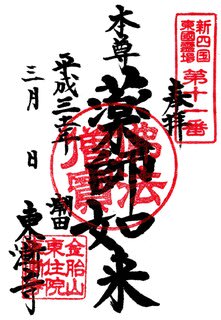
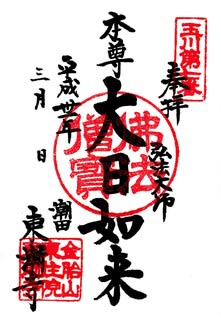
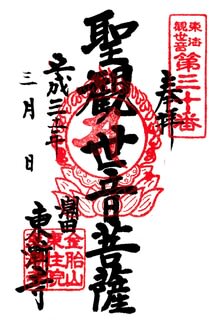
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第12番 愛宕山 寳蔵院
横浜市鶴見区馬場4-7-5
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第12番、武相二十八不動尊霊場第21番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
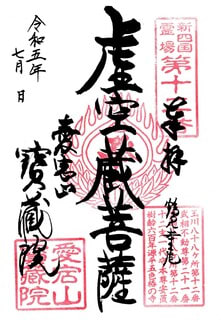
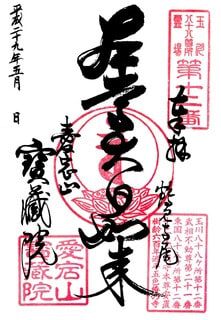
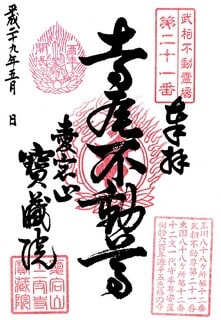
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
第13番 摩尼山 長松寺
横浜市鶴見区駒岡町3-4-22
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第81番、武相二十八不動尊霊場第17番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
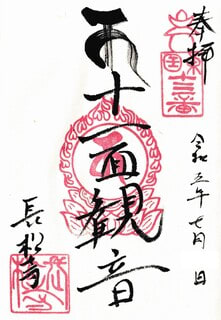
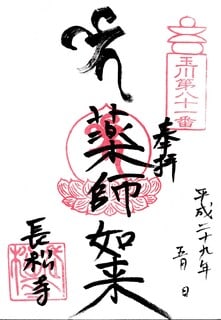

【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
第14番 子生山 東福寺
横浜市鶴見区鶴見1-3-5
真言宗智山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第10番、東海三十三観音霊場第14番、武相二十八不動尊霊場第20番、旧小机領三十三観音霊場第10番、鶴見七福神(毘沙門天)、武相四十八ヶ所不動尊霊場第29番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
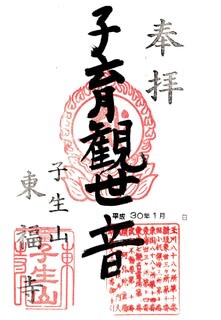
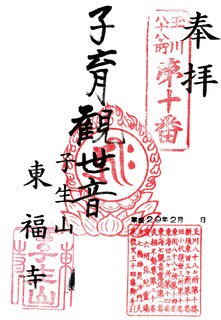
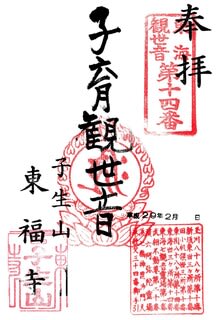
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
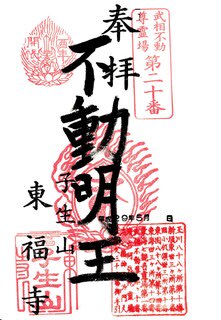
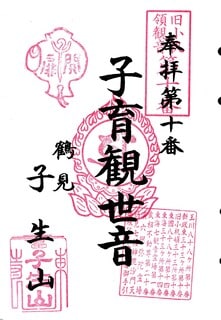
【写真 上(左)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 旧小机領三十三観音霊場の御朱印
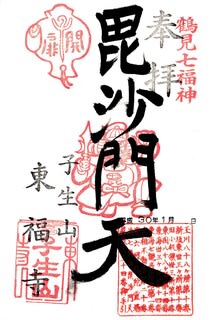
鶴見七福神(毘沙門天)の御朱印
第15番 生麦山 無動院 龍泉寺
横浜市鶴見区岸谷4-3-2
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:薬師如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第9番、東海三十三観音霊場第8番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第8番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
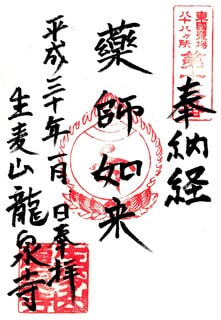

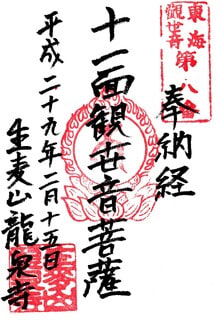
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第16番 密厳山 不動寺 遍照院
横浜市神奈川区子安通3-382
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

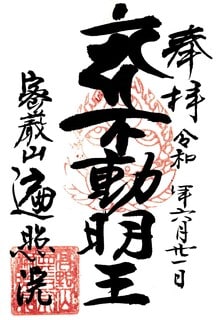
御本尊・不動明王の御朱印
第17番 医光山 薬王寺
横浜市神奈川区七島町6
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:武南十二薬師霊場第9番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
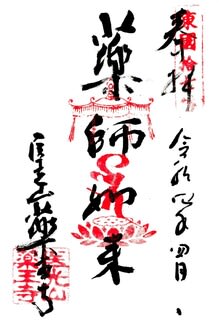
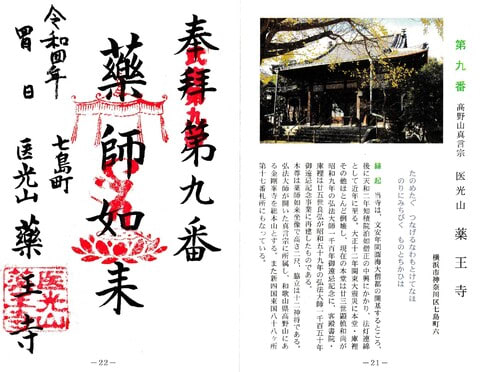
武南十二薬師霊場第9番の御朱印
第18番 海運山 満願院 能満寺
横浜市神奈川区東神奈川2-32-1
高野山真言宗
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:武南十二薬師霊場第10番
司元別当:笠䅣稲荷神社(神奈川区東神奈川)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
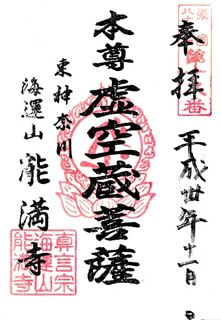
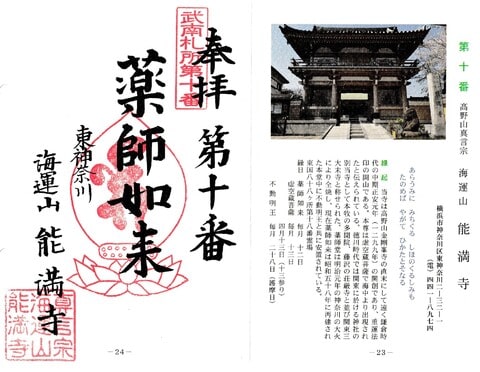
武南十二薬師霊場第10番の御朱印
第19番 平尾山 東光寺
横浜市神奈川区東神奈川2-37-6
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:武南十二薬師霊場第11番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
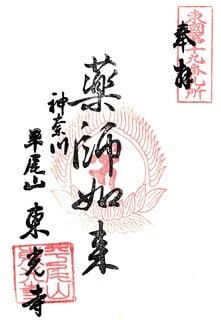
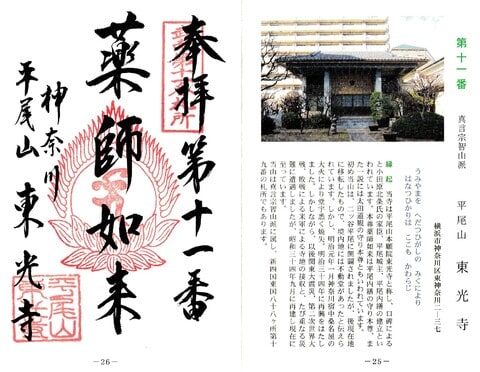
武南十二薬師霊場第11番の御朱印
第20番 神鏡山 東曼陀羅寺 金蔵院
横浜市神奈川区東神奈川1-4-3
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第3番
司元別当:(神奈川)熊野神社(神奈川区東神奈川)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
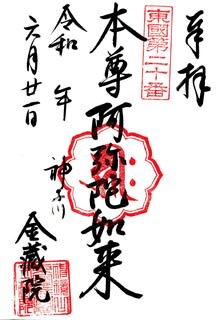

玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
第21番 洲崎山 功徳院 普門寺
横浜市神奈川区青木通3-18
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:
司元別当:洲崎大神(神奈川区青木町)、大綱金刀比羅神社(神奈川区台町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第22番 海浦山 新源院 吉祥寺
横浜市神奈川区白楽98
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:弘法大師
他札所:
司元別当:
授与所:第20番金蔵院
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
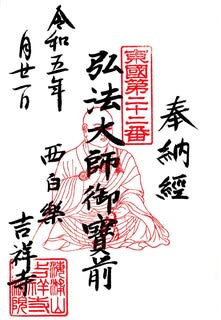
第23番 妙智山 歓成院
横浜市港北区大倉山2-8-7
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:薬師如来
他札所:旧小机領三十三観音霊場第12番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
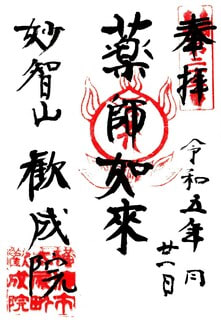
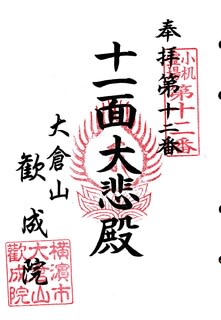
旧小机領三十三観音霊場の御朱印
第24番 八幡山 観音寺
横浜市港北区篠原町2777
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第82番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
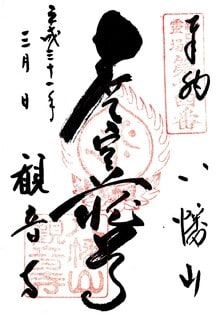

玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
第25番 瑞雲山 本覚院 三會寺
横浜市港北区鳥山町730
高野山真言宗
御本尊:弥勒菩薩
札所本尊:延命地蔵菩薩
他札所:武相二十八不動尊霊場第14番、旧小机領三十三観音霊場第2番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
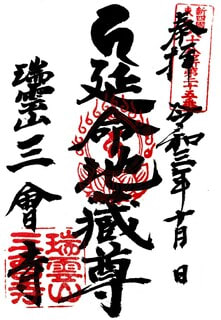


【写真 上(左)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 旧小机領三十三観音霊場の御朱印
第26番 普賢山 安楽寺 香象院
横浜市保土ヶ谷区岩間町2-153
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
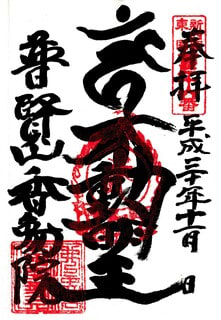
第27番 医王山 延壽院 遍照寺
横浜市保土ヶ谷区月見台291
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:
司元別当:牛頭天王社(保土ケ谷区天王町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
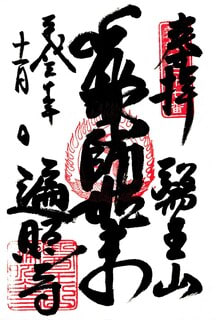
第28番 西方山 安樹院 大仙寺
横浜市保土ヶ谷区霞台14
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所本尊:金剛界大日如来
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第29番 羯摩山 密藏院 圓福寺
横浜市保土ヶ谷区西久保137
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第11番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
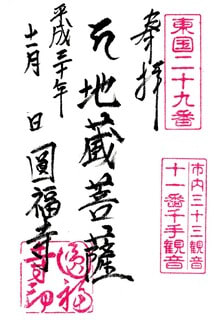
第30番 金巌山 櫻壽院 安楽寺
横浜市保土ヶ谷区西久保120
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
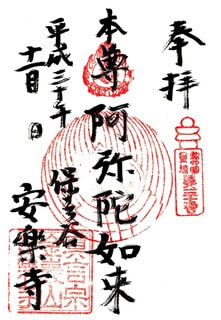
第31番 法亀山 地寿福院 願成寺
横浜市西区西戸部町3-290
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第12番、横浜市内二十一ヶ所霊場第3番
司元別当:(戸部)杉山神社(西区中央)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
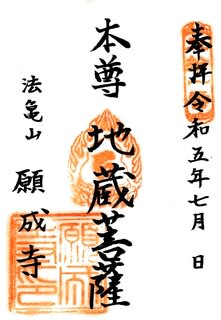
第32番 医王山 光明院 東光寺
横浜市南区三春台110
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第7番、横浜市内二十一ヶ所霊場第4番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第33番 東光山 医王寺 蓮華院
横浜市南区三春台19
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第5番、横浜市内二十一ヶ所霊場第8番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第34番 東医山 薬王寺
横浜市南区三春台7
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第4番、横浜市内二十一ヶ所霊場第7番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
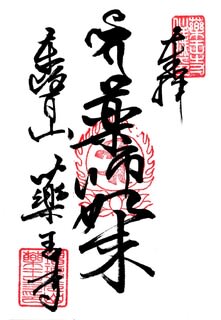
第35番 福智山 不動寺 普門院
横浜市南区西仲町1-2-6
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第3番、横浜市内二十一ヶ所霊場第6番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第36番 光明山 遍照院 東福寺
横浜市西区赤門町2-17
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:不動明王(波切不動尊)
他札所:横浜市内三十三観音霊場第2番、横浜市内二十一ヶ所霊場第5番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第37番 日明山 宝泉寺 大聖院
横浜市西区元久保5-20
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第1番、横浜市内二十一ヶ所霊場第1番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第38番 成田山 横浜別院 延命院
横浜市西区宮崎町30
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:関東三十六不動尊霊場第3番、横浜市内二十一ヶ所霊場第2番
司元別当:
授与所:授与所
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
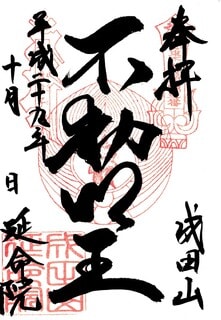
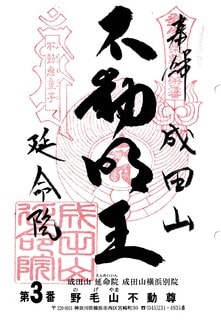
関東三十六不動尊霊場の御朱印
第39番 大慈山 瑠璃院 玉泉寺
横浜市南区中村町1-6-1
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第29番、横浜市内二十一ヶ所霊場第11番
司元別当:中村八幡宮(南区八幡町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
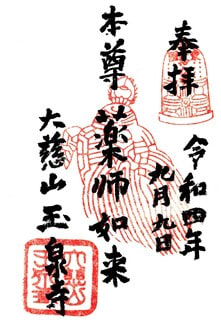
第40番 海龍山 本泉寺 増徳院
横浜市南区平楽103
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師(秘鍵大師)
他札所:横浜市内三十三観音霊場第16番、横浜市内二十一ヶ所霊場第21番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第23番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
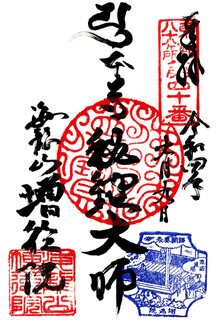
第41番 天沼山 威德院 東漸寺
横浜市中区大平町101
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第27番、横浜市内二十一ヶ所霊場第12番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
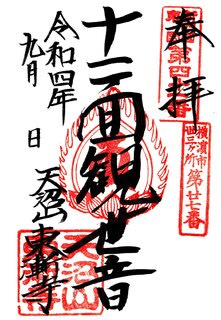
第42番 地福寺
横浜市南区平楽103 第40番増徳院内に移転
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:
司元別当:
授与所:第40番増徳院
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第43番 佛海山 宝光院 天徳寺
横浜市中区和田山1-1
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第17番、横浜市内二十一ヶ所霊場第20番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
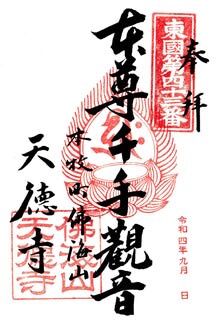
第44番 醫王山 成願寺 多聞院
横浜市中区本牧元町2-16
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:弘法大師
他札所:横浜市内三十三観音霊場第19番、横浜市内二十一ヶ所霊場第18番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
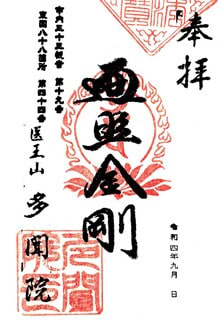
第45番 東光山 千蔵寺
横浜市中区本牧元町12-16
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第18番、横浜市内二十一ヶ所霊場第19番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
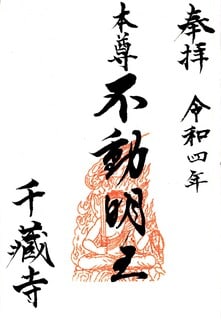
第46番 間門山 東福院
横浜市中区本牧荒井64
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如來
札所本尊:金剛界大日如來
他札所:横浜市内三十三観音霊場第17番、横浜市内二十一ヶ所霊場第20番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第47番 根岸山 覚王寺 大聖院
横浜市磯子区東町6-20
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第15番、横浜市内二十一ヶ所霊場第21番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
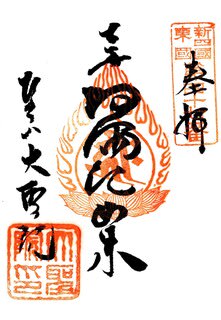
第48番 海向山 岩松寺 金蔵院
横浜市磯子区磯子4-3-6
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第22番、横浜磯子七福神(弁財天)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
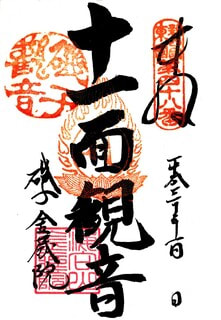
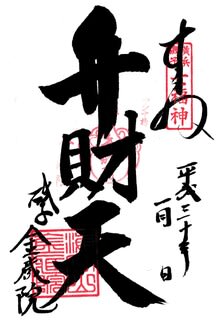
横浜磯子七福神(弁財天)の御朱印
第49番 禪馬山 不動院 真照寺
横浜市磯子区磯子8-14-12
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:横浜市内三十三観音霊場第23番、横浜磯子七福神(毘沙門天)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
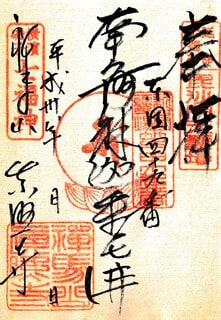
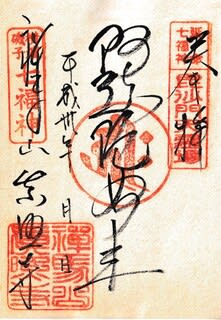
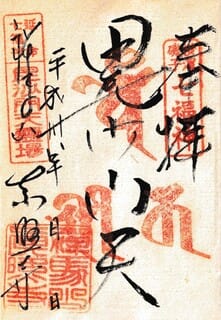
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 横浜磯子七福神(毘沙門天)の御朱印
第50番 龍頭山 明王寺 密蔵院
横浜市磯子区滝頭3-13-5
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第24番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第24番、横浜磯子七福神(布袋尊)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
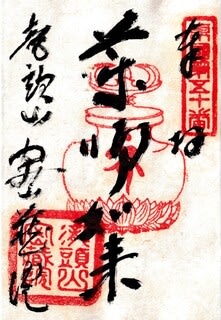


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 横浜磯子七福神(布袋尊)の御朱印
以下、■ 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印-2につづきます。
【 BGM 】
■ Just The Two Of Us - Grover Washington Jr. (feat. Bill Withers)
■ We Are One - MAZE feat. Frankie Beverly
■Remind Me (Remastered) - Patrice Rushen
こちらは鎌倉三十三観音霊場第16番の札所で、鎌倉観音霊場巡拝で訪れる人は少なくありません。
こちらは相州二十一ヶ所霊場第10番の札所でもあって、かなりマニアック(?)な霊場ですが、それでもある程度の巡拝者はいるかと思われます。
鎌倉三十三観音霊場の御朱印尊格は御本尊の十一面観世音菩薩。
相州二十一ヶ所霊場の御朱印尊格は「秘鍵大師」です。
ところがWeb検索でごく希に「千手観世音」の御朱印がヒットすることがあります。
これが新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印です。


【写真 上(左)】 補陀落寺の鎌倉観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 補陀落寺の相州二十一ヶ所の御朱印
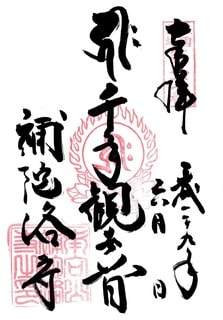
■ 補陀落寺の新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印
新四国東国八十八ヶ所霊場は川崎から横浜、そして逗子、鎌倉、藤沢と巡拝する神奈川県の弘法大師霊場(八十八ヶ所)です。
初番・発願は川崎大師(平間寺)、第88番の結願は鎌倉・手広の青蓮寺。
番外や掛所はなく、八十八の札所はすべて真言宗寺院です。
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
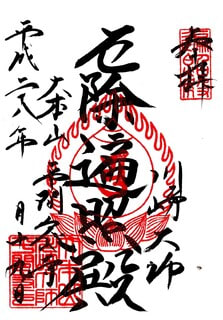
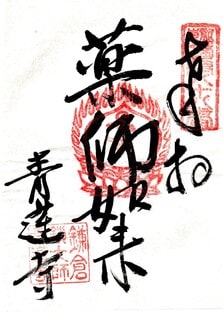
【写真 上(左)】 初番・発願の川崎大師(平間寺)の御朱印
【写真 下(右)】 第88番・結願の青蓮寺の御朱印
川崎エリアの札所は玉川八十八ヶ所との重複札所が多く、どうしても情報が多く専用納経帳も用意されている玉川八十八ヶ所霊場から巡拝することになります。
玉川八十八ヶ所霊場の初番・発願も川崎大師(平間寺)で、こちらは平間寺様がとりまとめを担われている模様。
一方、新四国東国霊場は現在、平間寺様はとりまとめにノータッチとみられ、新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印は授与されていません。
そんなこともあって新四国東国霊場の御朱印コンプリートは困難とあきらめていましたが、こつこつとまわっているうちに、意外に札所印つきの御朱印をいただけることに気づき、弘法大師御生誕1250年の今年の結願をもくろみ、数年がかりでようやく結願に漕ぎ着けました。
新四国東国霊場はすこぶる情報が少なく、ガイドブックはおろかリーフレットさえみたことがありません。
そのわりにしっかりとした札所標が設置されていたりして、どうもナゾの多い霊場です。
88の札所のうち御朱印を拝受できたのは87(残る1寺は七福神スタンプ)。その多くは札所印つきです。
お納めは概ね300円。専用納経帳がないので揮毫(書入れ)、印判捺、書置と授与形態は多彩です。
新四国東国霊場で面白いのは、ふつう弘法大師霊場では御本尊ないし弘法大師が札所本尊となりますが、新四国東国霊場では別尊や境内仏が札所本尊となる例がみられることです。
玉川八十八ヶ所霊場の札所本尊はおおむね御本尊なので、玉川、東国両札所兼任のお寺様ではそれぞれ異なる尊格の御朱印を拝受できる場合があります。
■ 上記の例/龍宿山 西明寺(川崎市中原区小杉御殿町/第9番)


【写真 上(左)】 玉川霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東国霊場の御朱印
↑ 玉川霊場は御本尊の金剛界大日如来、東国霊場は釈迦如来。
■ 坂東霊場と御朱印尊格が異なる例/瑞応山 弘明寺(横浜市南区弘明寺町/第60番)

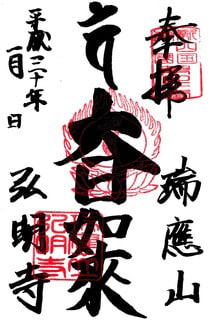
【写真 上(左)】 坂東霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東国霊場の御朱印
↑ 坂東霊場は御本尊の十一面観世音菩薩、東国霊場は金剛界大日如来。
実際、新四国東国霊場の札所本尊については情報が少ないため、拝所がよくわからず、先に御朱印をお願いすると同時に札所本尊についてお伺いするというかたちをとりました。(拝所が本堂ではない場合がある。)
札所の多くは他霊場との兼務で、新四国東国霊場は巡拝者が少ないため御朱印申告時は要注意です。
「八十八ヶ所」で申告すると玉川霊場、「弘法大師霊場」で申告すると相州二十一ヶ所と間違われる可能性があります。
実際、申告時に「東国霊場の御朱印ですね」と念を押されたケースが何度もありました。
しっかり「新四国東国霊場第●番でお願いします。」とお伝えすると間違いがないかと思います。
また、筆者は新四国東国霊場専用の御朱印帳をつくって巡拝したのですが、この場合はすべての御朱印がこの霊場なので間違いが少なくなると思います。
重複霊場としては、
川崎エリアで玉川八十八ヶ所霊場、東海三十三観音霊場、准秩父三十四観音霊場、准四国稲毛三十三観音霊場、武相二十八不動、川崎七福神。
横浜東部エリアで玉川八十八ヶ所霊場、准秩父三十四観音霊場、武相卯歳四十八観音霊場、旧小机領三十三観音霊場、横浜七福神。
横浜西南部エリアで坂東霊場、武州金沢三十四観音霊場、横浜磯子七福神、横浜金澤七福神。
逗子・鎌倉エリアで鎌倉三十三観音霊場、鎌倉二十四地蔵霊場、相州二十一ヶ所霊場、鎌倉十三仏霊場、相模国準四国八十八ヶ所霊場、小田急武相三十三観音霊場、関東八十八箇所霊場などがあります。
札所寺院は駅から離れたところがあり、札所範囲も広いため車での巡拝が有効です。
おおむね駐車場はありますが、入り組んだ路地や高低差のあるアプローチが多く、運転にはかなり気を使います。
見どころが多い札所もあるので、時間に余裕をもった巡拝をおすすめします。
それでは、順に御朱印をご紹介していきます。
新四国東国霊場の札所本尊は御本尊と異なるケースがあること、またエリア毎に兼務霊場が変わっていく様子もわかるので、拝受した御朱印はすべて掲載します。
第1番 金剛山 金乗院 平間寺(川崎大師)
川崎市川崎区大師町4-48
真言宗智山派
御本尊:弘法大師
札所本尊:
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第1番、関東八十八箇所霊場特別霊場、関東三十六不動尊霊場第7番、武相二十八不動尊霊場第1番、東海三十三観音霊場第33番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第1番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第15番
司元別当:大師稲荷神社(川崎区中瀬)
授与所:授与所
※平間寺様では、新四国東国霊場の御朱印は授与されていません。
〔 御本尊の御朱印 〕
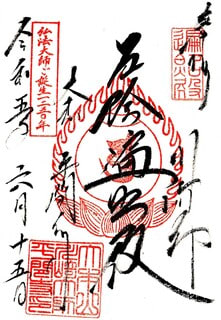
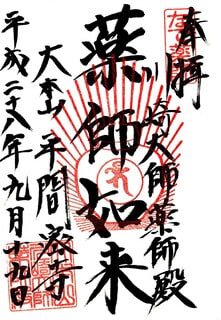
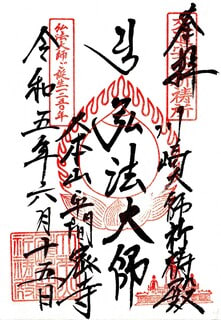
【写真 上(左)】 薬師殿の御朱印
【写真 下(右)】 自動車交通安全祈祷殿の御朱印
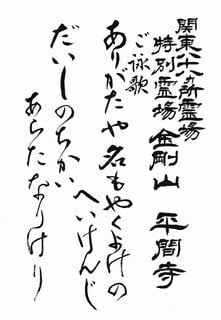
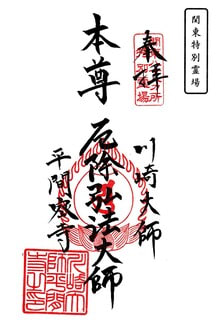
関東八十八箇所霊場の御朱印
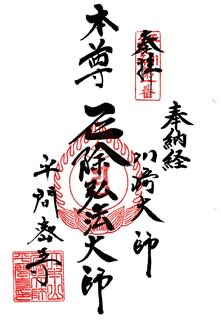
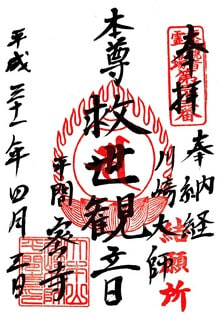
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
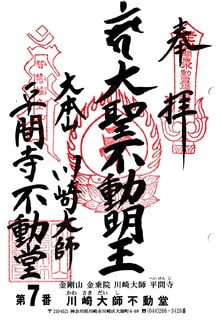
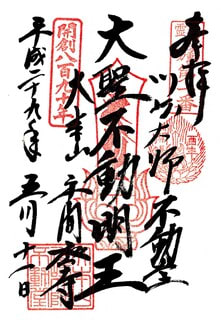
【写真 上(左)】 関東三十六不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
第2番 瑠璃光山 金剛院 真福寺
川崎市川崎区堀之内町11-7
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第13番、東海三十三観音霊場番外、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第11番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
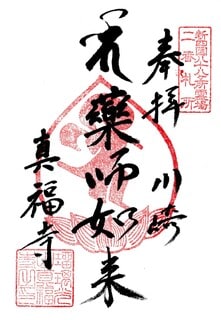

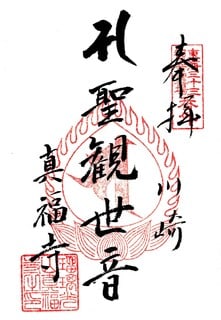
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第3番 大島山 般若院 真観寺
川崎市川崎区大島2-10-16
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第2番、東海三十三観音霊場第4番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第2番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

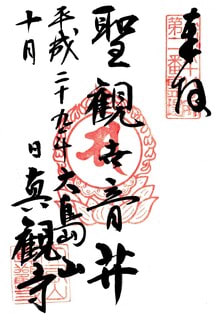
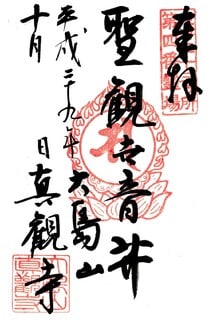
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第4番 明王山 聖無動寺 成就院
川崎市川崎区渡田3-8-1
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:大日如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第4番、東海三十三観音霊場第5番、武相二十八不動尊霊場第27番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第4番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕



【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
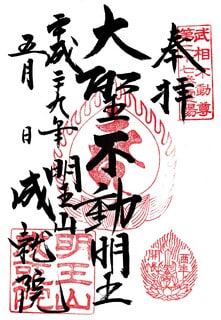
武相二十八不動尊霊場の御朱印
第5番 金澤山 福泉寺 圓能院
川崎市川崎区小田1-25-12
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:延命地蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第6番、東海三十三観音霊場第6番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第5番
司元別当:日枝大神社(川崎区小田)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
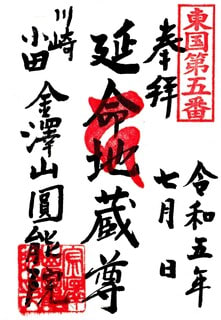
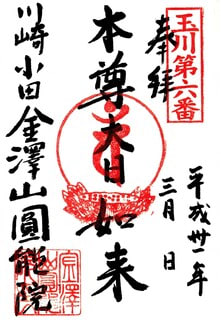
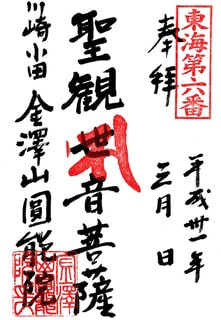
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第6番 圓明山 宝蔵院 延命寺
川崎市幸区都町4-2
真言宗智山派
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:薬師如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第14番、東海三十三観音霊場第15番
司元別当:女躰大神(幸区幸町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
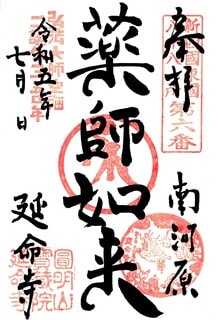
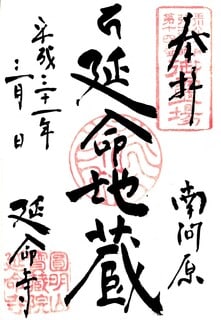
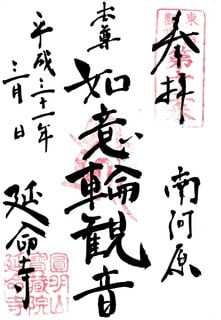
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第7番 瑠璃光山 長壽院 無量寺
川崎市中原区中丸子498
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第17番、川崎七福神(寿老神)、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第30番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

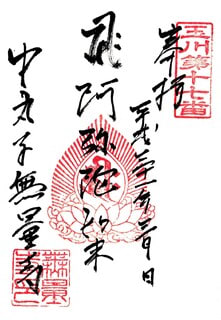
玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
第8番 西光山 東福寺
川崎市中原区市ノ坪45
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第21番、准秩父三十四観音霊場第10番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第32番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
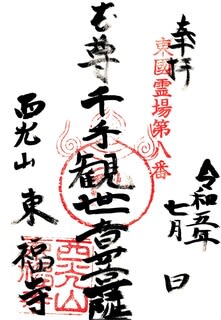

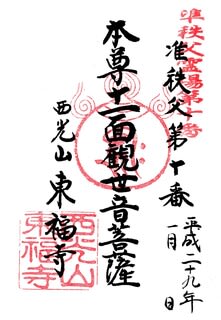
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 准秩父三十四観音霊場の御朱印
第9番 龍宿山 金剛院 西明寺
川崎市中原区小杉御殿町1-906
真言宗智山派
御本尊:金剛界大日如来
札所本尊:釈迦如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第20番、准四国稲毛三十三観音霊場第18番、川崎七福神(大黒天)、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第36番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕


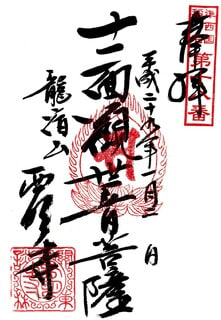
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 准四国稲毛三十三観音霊場の御朱印
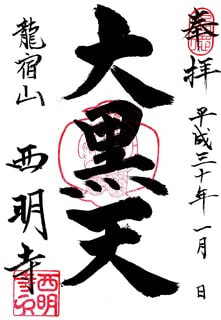
川崎七福神(大黒天)の御朱印
第10番 光明山 遍照院 金剛寺
横浜市鶴見区市場下町6-33
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第11番、東海三十三観音霊場第9番
司元別当:(鶴見)熊野神社
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
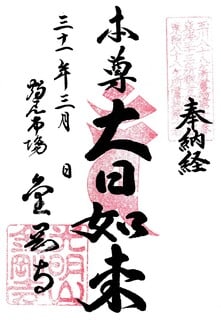
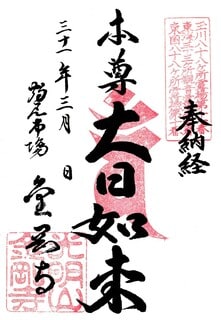
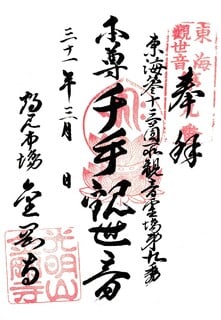
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第11番 金胎山 東住院 東漸寺
横浜市鶴見区潮田町3-144-2
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:薬師如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第7番、東海三十三観音霊場第30番
司元別当:潮田神社(鶴見区潮田町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
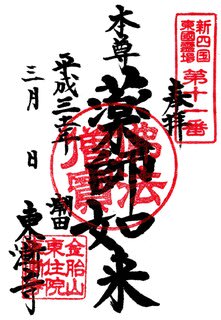
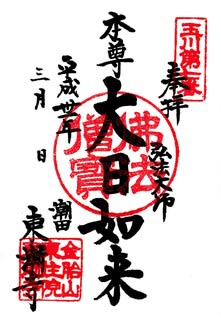
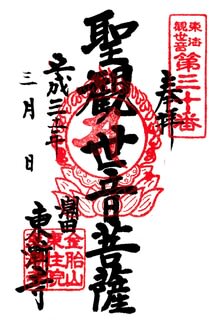
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第12番 愛宕山 寳蔵院
横浜市鶴見区馬場4-7-5
真言宗智山派
御本尊:大日如来
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第12番、武相二十八不動尊霊場第21番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
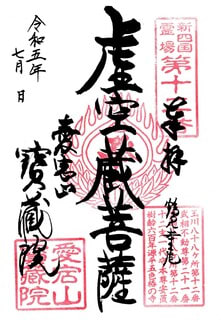
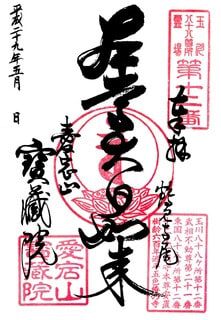
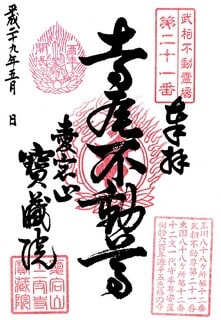
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
第13番 摩尼山 長松寺
横浜市鶴見区駒岡町3-4-22
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第81番、武相二十八不動尊霊場第17番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
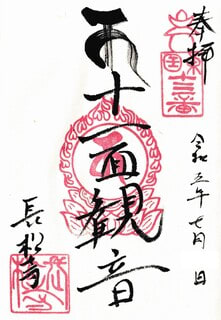
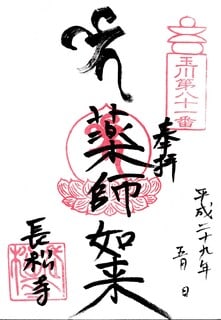

【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
第14番 子生山 東福寺
横浜市鶴見区鶴見1-3-5
真言宗智山派
御本尊:如意輪観世音菩薩
札所本尊:如意輪観世音菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第10番、東海三十三観音霊場第14番、武相二十八不動尊霊場第20番、旧小机領三十三観音霊場第10番、鶴見七福神(毘沙門天)、武相四十八ヶ所不動尊霊場第29番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
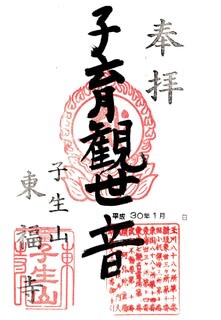
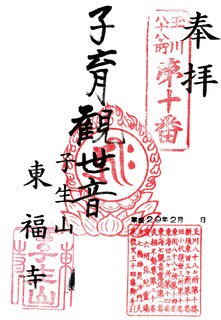
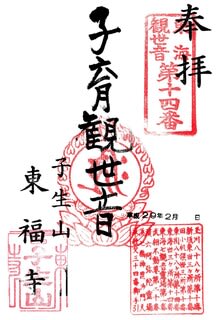
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
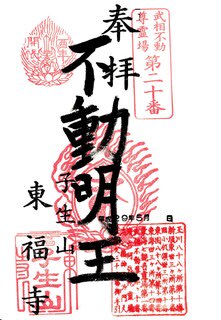
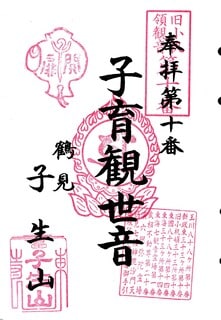
【写真 上(左)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 旧小机領三十三観音霊場の御朱印
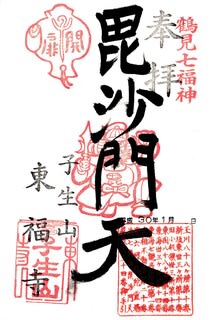
鶴見七福神(毘沙門天)の御朱印
第15番 生麦山 無動院 龍泉寺
横浜市鶴見区岸谷4-3-2
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:薬師如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第9番、東海三十三観音霊場第8番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第8番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
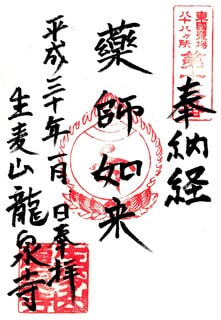

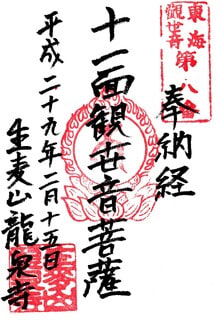
【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
第16番 密厳山 不動寺 遍照院
横浜市神奈川区子安通3-382
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

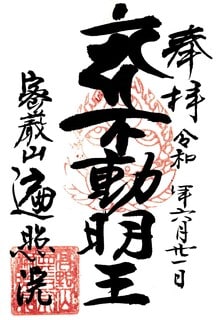
御本尊・不動明王の御朱印
第17番 医光山 薬王寺
横浜市神奈川区七島町6
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:武南十二薬師霊場第9番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
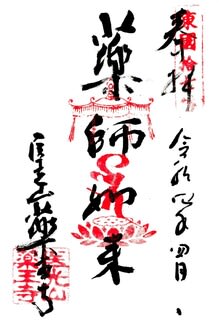
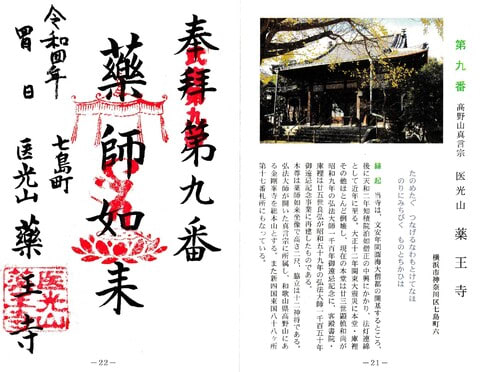
武南十二薬師霊場第9番の御朱印
第18番 海運山 満願院 能満寺
横浜市神奈川区東神奈川2-32-1
高野山真言宗
御本尊:虚空蔵菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:武南十二薬師霊場第10番
司元別当:笠䅣稲荷神社(神奈川区東神奈川)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
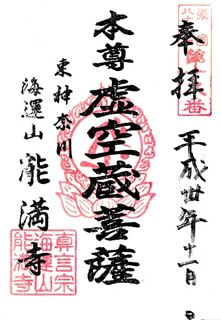
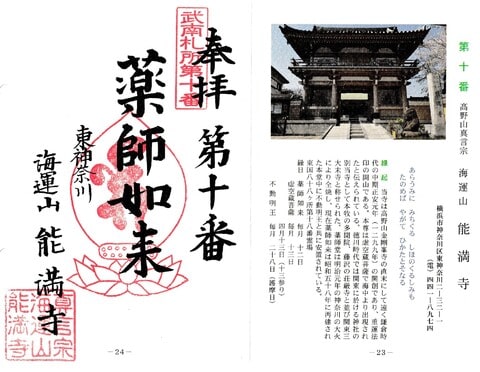
武南十二薬師霊場第10番の御朱印
第19番 平尾山 東光寺
横浜市神奈川区東神奈川2-37-6
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:武南十二薬師霊場第11番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
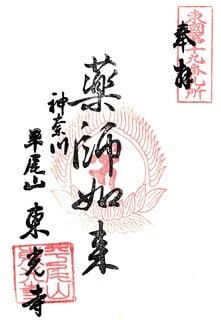
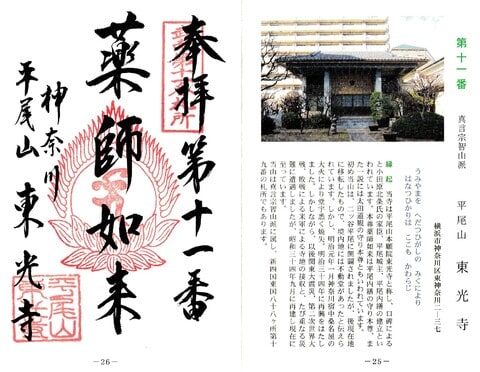
武南十二薬師霊場第11番の御朱印
第20番 神鏡山 東曼陀羅寺 金蔵院
横浜市神奈川区東神奈川1-4-3
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第3番
司元別当:(神奈川)熊野神社(神奈川区東神奈川)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
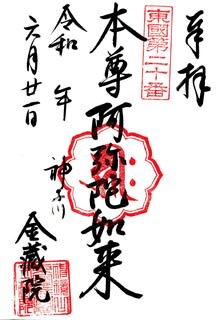

玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
第21番 洲崎山 功徳院 普門寺
横浜市神奈川区青木通3-18
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:聖観世音菩薩
他札所:
司元別当:洲崎大神(神奈川区青木町)、大綱金刀比羅神社(神奈川区台町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第22番 海浦山 新源院 吉祥寺
横浜市神奈川区白楽98
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:弘法大師
他札所:
司元別当:
授与所:第20番金蔵院
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
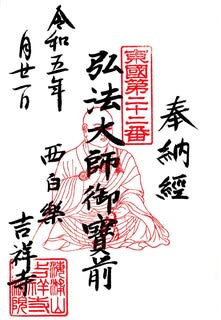
第23番 妙智山 歓成院
横浜市港北区大倉山2-8-7
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:薬師如来
他札所:旧小机領三十三観音霊場第12番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
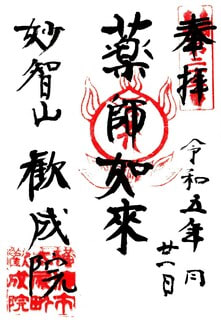
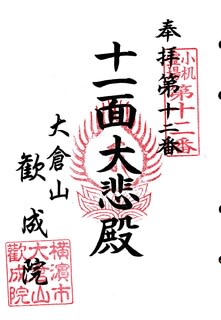
旧小机領三十三観音霊場の御朱印
第24番 八幡山 観音寺
横浜市港北区篠原町2777
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:虚空蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第82番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
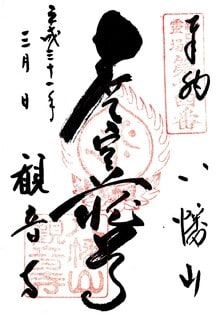

玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
第25番 瑞雲山 本覚院 三會寺
横浜市港北区鳥山町730
高野山真言宗
御本尊:弥勒菩薩
札所本尊:延命地蔵菩薩
他札所:武相二十八不動尊霊場第14番、旧小机領三十三観音霊場第2番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
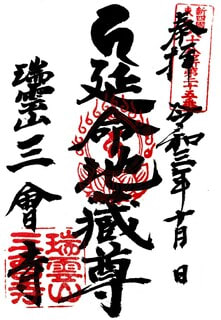


【写真 上(左)】 武相二十八不動尊霊場の御朱印
【写真 下(右)】 旧小机領三十三観音霊場の御朱印
第26番 普賢山 安楽寺 香象院
横浜市保土ヶ谷区岩間町2-153
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
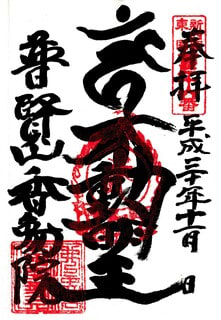
第27番 医王山 延壽院 遍照寺
横浜市保土ヶ谷区月見台291
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:
司元別当:牛頭天王社(保土ケ谷区天王町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
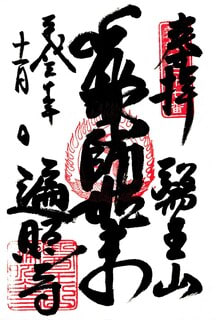
第28番 西方山 安樹院 大仙寺
横浜市保土ヶ谷区霞台14
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如来
札所本尊:金剛界大日如来
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第29番 羯摩山 密藏院 圓福寺
横浜市保土ヶ谷区西久保137
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第11番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
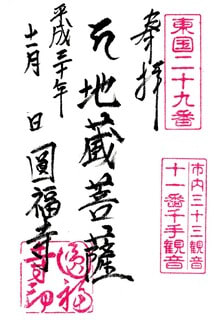
第30番 金巌山 櫻壽院 安楽寺
横浜市保土ヶ谷区西久保120
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
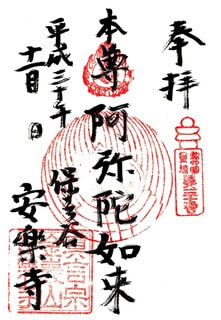
第31番 法亀山 地寿福院 願成寺
横浜市西区西戸部町3-290
高野山真言宗
御本尊:地蔵菩薩
札所本尊:地蔵菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第12番、横浜市内二十一ヶ所霊場第3番
司元別当:(戸部)杉山神社(西区中央)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
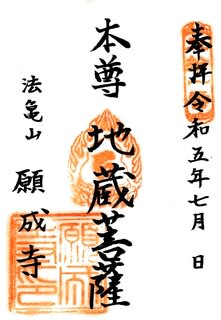
第32番 医王山 光明院 東光寺
横浜市南区三春台110
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第7番、横浜市内二十一ヶ所霊場第4番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第33番 東光山 医王寺 蓮華院
横浜市南区三春台19
高野山真言宗
御本尊:十一面観世音菩薩
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第5番、横浜市内二十一ヶ所霊場第8番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第34番 東医山 薬王寺
横浜市南区三春台7
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第4番、横浜市内二十一ヶ所霊場第7番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
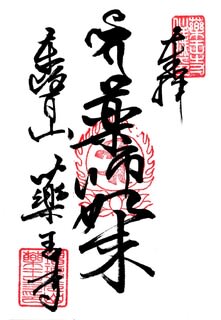
第35番 福智山 不動寺 普門院
横浜市南区西仲町1-2-6
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第3番、横浜市内二十一ヶ所霊場第6番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第36番 光明山 遍照院 東福寺
横浜市西区赤門町2-17
高野山真言宗
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:不動明王(波切不動尊)
他札所:横浜市内三十三観音霊場第2番、横浜市内二十一ヶ所霊場第5番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第37番 日明山 宝泉寺 大聖院
横浜市西区元久保5-20
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第1番、横浜市内二十一ヶ所霊場第1番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第38番 成田山 横浜別院 延命院
横浜市西区宮崎町30
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:関東三十六不動尊霊場第3番、横浜市内二十一ヶ所霊場第2番
司元別当:
授与所:授与所
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
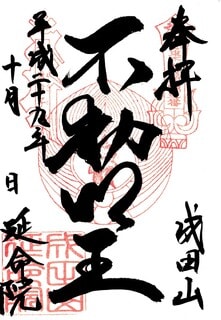
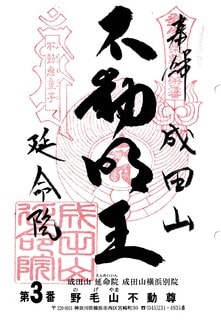
関東三十六不動尊霊場の御朱印
第39番 大慈山 瑠璃院 玉泉寺
横浜市南区中村町1-6-1
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第29番、横浜市内二十一ヶ所霊場第11番
司元別当:中村八幡宮(南区八幡町)
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
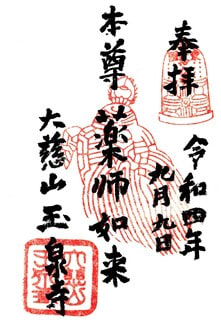
第40番 海龍山 本泉寺 増徳院
横浜市南区平楽103
高野山真言宗
御本尊:弘法大師
札所本尊:弘法大師(秘鍵大師)
他札所:横浜市内三十三観音霊場第16番、横浜市内二十一ヶ所霊場第21番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第23番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
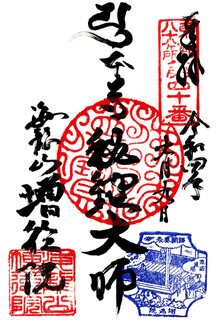
第41番 天沼山 威德院 東漸寺
横浜市中区大平町101
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第27番、横浜市内二十一ヶ所霊場第12番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
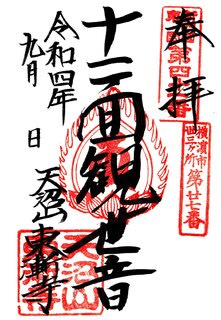
第42番 地福寺
横浜市南区平楽103 第40番増徳院内に移転
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:
司元別当:
授与所:第40番増徳院
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第43番 佛海山 宝光院 天徳寺
横浜市中区和田山1-1
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第17番、横浜市内二十一ヶ所霊場第20番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
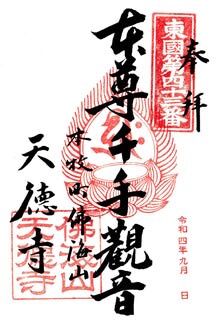
第44番 醫王山 成願寺 多聞院
横浜市中区本牧元町2-16
高野山真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:弘法大師
他札所:横浜市内三十三観音霊場第19番、横浜市内二十一ヶ所霊場第18番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
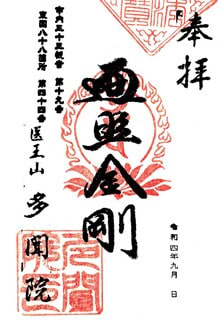
第45番 東光山 千蔵寺
横浜市中区本牧元町12-16
高野山真言宗
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:横浜市内三十三観音霊場第18番、横浜市内二十一ヶ所霊場第19番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
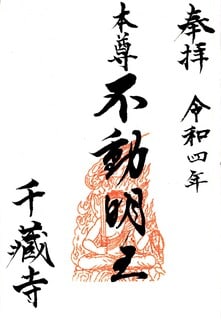
第46番 間門山 東福院
横浜市中区本牧荒井64
高野山真言宗
御本尊:金剛界大日如來
札所本尊:金剛界大日如來
他札所:横浜市内三十三観音霊場第17番、横浜市内二十一ヶ所霊場第20番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

第47番 根岸山 覚王寺 大聖院
横浜市磯子区東町6-20
高野山真言宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:阿弥陀如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第15番、横浜市内二十一ヶ所霊場第21番
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
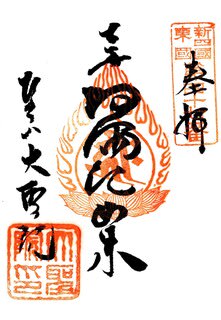
第48番 海向山 岩松寺 金蔵院
横浜市磯子区磯子4-3-6
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:十一面観世音菩薩
他札所:横浜市内三十三観音霊場第22番、横浜磯子七福神(弁財天)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
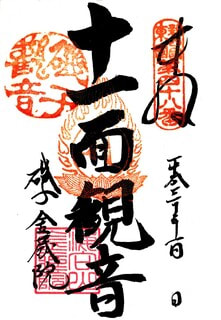
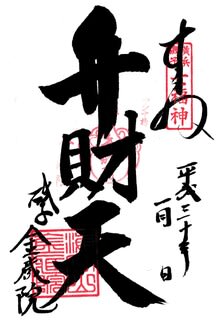
横浜磯子七福神(弁財天)の御朱印
第49番 禪馬山 不動院 真照寺
横浜市磯子区磯子8-14-12
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:釈迦牟尼佛
他札所:横浜市内三十三観音霊場第23番、横浜磯子七福神(毘沙門天)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
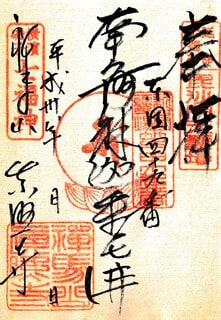
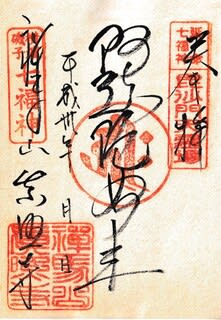
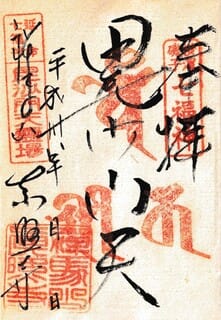
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 横浜磯子七福神(毘沙門天)の御朱印
第50番 龍頭山 明王寺 密蔵院
横浜市磯子区滝頭3-13-5
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:薬師如来
他札所:横浜市内三十三観音霊場第24番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第24番、横浜磯子七福神(布袋尊)
司元別当:
授与所:庫裡
〔 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印 〕
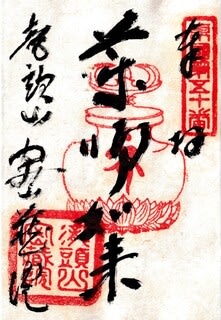


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 横浜磯子七福神(布袋尊)の御朱印
以下、■ 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印-2につづきます。
【 BGM 】
■ Just The Two Of Us - Grover Washington Jr. (feat. Bill Withers)
■ We Are One - MAZE feat. Frankie Beverly
■Remind Me (Remastered) - Patrice Rushen
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-8
Vol.-7からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第25番 六所山 長明院 長楽寺
(ちょうらくじ)
日野市程久保8-49-18
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
第25番札所の長楽寺は御府内霊場中ふたつある都区外の札所の一寺で、都下の日野市にあります。
第25番札所も複雑な変遷をたどっています。
現在の第25番札所は長楽寺ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では、四ッ谷小寺町の自然山 地福寺 和光院となっています。
「日野市観光協会Web」によると、長楽寺は元和六年(1620年)開山なので、御府内霊場開創の宝暦五年(1755年)にはすでに存在しています。
しかし明治初頭編纂の『御府内八十八ケ所道しるべ』では第25番札所は和光院なので、江戸期を通じて第25番札所は和光院であったとみられます。
(江戸八十八ヶ所霊場第25番も和光院。)
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第25番の和光院は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃されたのかもしれません。
和光院の札所本尊の一尊に将軍地蔵尊が定められていましたが、愛宕権現との習合色の強い将軍(勝軍)地蔵尊を祀る寺院が神仏分離で廃された例(愛宕・圓福寺など)があるため、当院もこの例に該当したのかも。
長楽寺は角筈(現・西新宿三丁目付近)の大寺院でしたが昭和20年5月の空襲で被災し、寺地への道路建設などもあって昭和35年に現在地に移転しています。
寺勢衰微した戦災後に御府内霊場札所になったとは考えにくいので、明治の和光院廃寺によって第25番札所を引き継ぎ、昭和35年の寺院移転とともに札所も移転したというのが自然な見方でしょうか。
「猫の足あと」様Webに掲載されている『日野市史』には以下の記載があるようです。
・総本山長谷寺の末(直末?)
・御本尊の不動明王像は唐よりの伝来と伝わる
・享和二年(1802年)以降、不動信仰により栄え門前市をなした
・明治中期より昭和11年にかけ諸伽藍を建立、大寺院の風格を備えた
・弘法大師像は厄除大師として知られていた
和光院は智積院末(現・智山派系)ですが、四ッ谷からほど近い角筈に不動尊霊場・厄除大師として知られる真言密寺の長楽寺があったため、こちらが第25番札所を承継されたのでは。
あるいは、明治中期から昭和11年にかけての諸伽藍整備の記念事業として、御府内霊場札所を受けられたのかもしれません。
今回は殊に推測が多くなりましたが、それだけ札所異動に関する情報がすくないということです。
-------------------------
【史料】
【長楽寺関連】
■ 日野市観光協会Web(要旨抜粋引用)
・元和六年(1620年)代官渡辺与兵衛が頼音和尚に帰依し、数千坪を寄進して開山したと伝わる。
・徳川四代将軍家綱公が将軍職に就く前、慶安三年(1650年)正月、武蔵国府中六所明神(現・大国魂神社)に参詣の折、当山に立ち寄られ、六所明神にちなんで真筆をもって六所山の山号を与えられたと伝わる。
・もとは新宿区西新宿3丁目にあり、大本堂・書院・庫裡・大師堂・地蔵堂・鐘楼・山門を備えた大寺院だった。
・昭和20年5月25日空襲に遭い、その後の都市計画道路建設により移転をよぎなくされ、昭和35年に多摩動物公園隣の現在地に移転した。
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(角筈村)長楽寺
同宗(新義真言宗)多磨郡中野村寶仙寺末 六所山長命院ト号ス 当寺モ多聞院ト同ク與兵衛ノ開基スル所ナリ 開山賴音 慶安三年(1650年)十二月寂 本尊不動ヲ置 寺傳ニ当山ヲ六所ト号セルハ 昔厳有院殿府中六所ヘ御参ノ時 タマ々々当寺ヘ成ラセ給ヒシヨリ名付シ由イヘト イト牽強ノ説と思ハル 元ヨリ拠トスヘキモノナケレト 其頃賜ヒシ御筆ナリトテ横物ノ掛軸ヲ寺宝トス
【和光院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
二十五番
四ッ谷小寺町
自然山 地福寺 和光院
智積院末 新義
本尊:不動明王 将軍地蔵尊 弘法大師
大師建立本尊地蔵ぼさつ 座像大師
■ 『寺社書上 [43] 四谷寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.38.』
四谷小寺町
京都智積院末
自然山 地福寺 和光院
新義真言宗
開山 法印泉秀 寛永十六年(1639年寂)
当寺開闢之年代相知不
古●麹町辺ニ●●処寛永年中(1624-1644年)(略)御用地(略)処●ニ立退●移●
本堂
本尊 不動明王
護摩堂
本尊 地蔵尊
不動尊 毘沙門天 両大師
鎮守 稲荷社

「和光院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
多摩都市モノレール・京王動物園線「多摩動物公園」駅徒歩2分と交通至便で、駐車場も完備しています。
多摩動物公園のすぐとなりで、休日は子連れファミリーの姿が目立ちます。


【写真 上(左)】 すぐ下にモノレールと駅
【写真 下(右)】 山内入口
丘陵を造成して建立した寺院なので、前面道路からかなりの急坂をのぼります。
参道沿いには石仏が並び、地蔵尊座像も御座します。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 参道の地蔵尊と石仏群
石仏は如意輪観世音菩薩と地蔵尊がメインで、江戸期の年号が刻まれているので、おそらく角筈の旧地から遷られた御像かと思います。
山内は郊外寺院にしてはコンパクトですが、急坂をのぼっただけに眺望よく明るい雰囲気。
小高い尾根上に尊像や堂宇が連なる構成です。


【写真 上(左)】 修行大師と鎮守神
【写真 下(右)】 修行大師像
手前から朱塗りの稲荷社。扁額には「当山鎮守」とみえます。
そちらの向かって左手には端正な修行大師像。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 山内
さらに、鐘楼、しあわせ小僧、釈迦如来佛足石、大師堂とつづきます。
大師堂には厄除弘法大師座像が御座され、台座には札番の銘板が置かれているのでこちらが御府内霊場の拝所であることがわかります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂の銘板


【写真 上(左)】 厄除弘法大師像
【写真 下(右)】 奥側の堂宇
札所本尊は不動明王で、たしか大師堂と相対する建物のなかに御座かと思いますが、なぜか記憶が定かでありません。
その奥に鉄柵があり「これより先檀家専用墓地に付 一般の方の立入はご遠慮下さい。」とあるので巡拝者の立入りはここまでです。
鉄柵の奥の大棟に鴟尾を置いた堂宇には「阿弥陀堂」の掲示がありました。
御朱印は庫裡?にて拝受しました。
なお、参詣時間は16時までで、月曜定休の掲示がありました。
出直し参拝はきびしい立地なので、事前の電話確認がベターかと思います。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

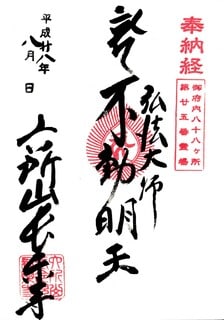
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「不動明王」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八ヶ所第廿五番霊場」の札所印。左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第26番 海賞山 地蔵院 来福寺
(らいふくじ)
公式Web
品川区東大井3-13-1
真言宗智山派
御本尊:延命地蔵菩薩
札所本尊:延命地蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第74番、東海三十三観音霊場第2番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第79番
司元別当:
授与所:事務所
第26番はふたたび都区内に戻ります。
鎌倉御家人や俳句とゆかりのふかい品川・大井の来福寺です。
縁起・沿革は公式Webに詳しいので、こちらと『新編武蔵風土記稿』を参考にまとめてみます。
当山の歴史は古く、正暦元年(990年)、智辨阿闍梨の開山といいますから、1030年以上もの法燈を伝承していることになります。
前九年の役、後三年の役などの戦禍を被るも法燈を堅持され、鎌倉時代には梶原一族が檀信徒となって栄之、景政、景時、景季等が寄進した「梶原松」「延命桜」があったと伝わります。
来福寺参道北側の路地には梶原稲荷神社がご鎮座です。
境内由緒書には「梶原平三景時(略)源頼朝ノ命ヲ奉ジテ武蔵國大井村鹿島谷ニ萬福寺ヲ建立シ、ソノ境内ニ守護神トシテ稲荷ヲ勧請シテ梶原稲荷ト尊称シタ。元応元年(1319年)、萬福寺ハ兵火ニヨリ焼失シ馬込村ニ移リタルニ依リ、焼ケ残リシ稲荷祠ハ梶原屋敷内ニ奉納サレテ、後、柴村来福寺ニ奉納サレ、ソノ追福ノタメ同寺ヘ松櫻ナドヲ植エ寄進シタ。コノ梶原塚ハ鎌倉源五郎景正ノ子梶原日向守 亦梶原助五郎一族ヲ祀ル古墳デアル。」とあります。
なお、現在梶原稲荷神社は地元の梶原稲荷講により維持管理されている模様です。

梶原稲荷神社
文亀元年(1501年)、源頼朝公の納経と伝わる経塚(現・大井1丁目経塚地蔵堂)の前を行脚していた梅巌(梅綾とも)和上が経塚のなかから読経の声を聞かれ、急ぎ掘り起こすと一躰の立派な地蔵菩薩像が出現しました。
不思議に思った梅巌和上がいろいろ調べてみると、この地蔵尊は行方不明となっていた来福寺の御本尊・延命地蔵尊で、弘法大師御作とも伝わる有り難いお像であることがわかりました。
以来このお地蔵さまは「経読(きょうよみ)地蔵尊」と呼ばれ、来福寺の御本尊として尊崇されるとともに、御分身は出現の地(経塚地蔵堂)および三つ叉地蔵堂(大井1丁目)に奉安され、ともに来福寺の境外佛堂として人々の信仰を集めています。
御本尊の経読地蔵尊は鎌倉権五郎景政の守り佛で梶原景季に伝わり、梶原氏との縁から当寺に収まられたといいます。
古来、地蔵尊には桜木を奉納する風習もあって、江戸時代には桜の名所として知られ、山内には「世の中は 三日見ぬ間に 桜かな」という雪中庵三世大島蓼太(芭蕉直系の旅俳人)の句碑があります。
古くは海上山、海照山と号し、境内に天満宮のお社があったので天神山とも呼ばれたといいます。
法系は往古は(馬込)長遠寺末、その後京都仁和寺末となり代々親王が住職を継承されました。
明治38年に川崎大師平間寺の法系となり今日に至っています。
寺伝もきれいに収まってそれではつぎの第27番・・・、となりそうですがそうはいきません。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には第26番札所に「四ッ谷南寺町 文殊院」とあるからです。
また、江戸八十八ヶ所霊場の第26番札所も文殊院となっています。
大井の地は御府内から外れており、この点からも江戸時代の札所は四ッ谷南寺町の文殊院であったとみられます。
20番代の札所は変遷が複雑で、いずれも一筋縄ではいきません。
第26番もこういう変遷があるので、文殊院についてたどっていきます。
文殊院は『御府内寺社備考』に掲載がなく、『寺社書上』と『御府内八十八ケ所道しるべ』を典拠とします。
文殊院は慶長十六年(1616年)、麹町九丁目横町に祐信上人が開山といいます。
寛永十一年(1633年)旧地を御用地として召し上げられ、四ツ谷南寺町に替地を拝領して移転したようです。
大塚護持院を本山とする新義真言宗寺院で、御本尊の阿弥陀児如来は秦氏ゆかりの尊像と伝わります。
秦河勝公は聖徳太子の同志として国造りに貢献したとされますが、河勝公九世孫の秦大蔵老ゆかりの伝承が伝わります。
漢文なので詳細まで読み取れません。すみませぬ。
太秦の名族の当主・秦大蔵老は年老いて子がなくこれを嘆いていたところ、一体の地蔵尊を得て子宝祈願に専念すると、妻が阿弥陀佛の霊夢をみるや女の子を授かりました。
父母の寵愛を一身に受け、聡明で花のように美しく育った姫でしたが、あるとき鷲にさらわれ(?)行方知れずとなってしまいました。
大蔵老は嘆き哀しみ、日夜姫の無事を尊佛に祈りました。
ここから先は記述が込み入って不詳ですが、紆余曲折ののち大蔵老は二寸余の阿弥陀佛像を得、以降、この尊像は「児如来」と尊称され崇められたという内容のようです。
『寺社書上』に「児如来と申阿弥陀木像(略)社僧秦氏代々乃家傳乃本尊」とあるので、こちらの児如来が御本尊として奉安され、札所本尊も児如来でありました。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊児如来ハ川勝の守(?)り佛なり」とあるので、秦河勝公の守り佛であったのかもしれません。
あるいは、河勝公ゆかりの川勝寺(現・京都市右京区西京極、廃寺)の奉安佛だったのかも。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には文殊尊の挿絵が載せられ、こちらが院号ゆかりの尊像とも思いますが、なぜか『寺社書上』には文殊尊についての記載はありません。

「文殊院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
↑ の挿絵には「阿ぶらげ坂」とみえます。
「阿ぶらげ坂」(油揚坂)とは「戒行寺坂」のことで、戒行寺が面していました。
『江戸切絵図』をみると文殊院は戒行寺の対面で、たしかに阿ぶらげ坂(戒行寺坂)に面していたことがわかります。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所霊場第26番の文殊院は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離時に廃された可能性があります。
第26番札所が四ッ谷の文殊院から大井の来福寺に承継された経緯については、手がかりが見当たらずまったくわかりません。
来福寺は長遠寺(新義智山派)末から仁和寺(古義)末となり、明治38年から川崎大師平間寺(新義智山派大本山)の法系に入っています。
一方、文殊院は大塚護持院末ですから長谷寺豊山派の流れで、本末関係など宗派的なつながりによる承継は考えにくいです。
四ッ谷から大井(品川)への遠距離移転もなんらかの事情があってのものでは?
確たる史料がみつからない以上、これ以上は掘り下げられないので、ナゾはナゾとして残しておきます。(と、逃げる(笑))
来福寺は東海三十三観音霊場との兼務札所です。
この観音霊場は東海道沿いの札所分布で、玉川八十八ヶ所霊場や新四国東国八十八ヶ所霊場との兼務札所はめずらしくないですが、御府内霊場との兼務はこちらだけで、それだけ南東(神奈川)寄りに飛んだ立地であることがわかります。
-------------------------
【史料】
【来福寺関連】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(大井村)来福寺
新義真言宗同郡馬込村八幡宮別当長遠寺ノ末ナリ 海賞山地蔵院ト号ス 正暦元年(990年)智瓣阿闍梨ノ草創ト云(略)本尊ハ弘法大師ノ彫刻ニテ延命経讀地蔵ト云ヘリ 寺傳ニヨレハ此像ハ鎌倉権五郎景政ノ守佛ナリシカ 数傳ノ後梶原景季ニ傳ハリ 終ニ當寺ヘ納タリトイヘト證トナスヘキモノアラサレハウケカヒカタシ
天神社 門ヲ入テ右ノ方小高キ処ニアリ
梶原塚 境内北ノ方ニアリ 景季ノ墳ト云 按ニ此辺梶原景時父子ノ舊蹟ト云モノ多シ(以下略)
梶原松 延命櫻 此二木ハ共ニ客殿ノ前ニアリ 梶原景季地蔵信仰ノ餘自ラ植シト云傳フ 今モコノ側にナラヒテ 地蔵尊信心ノ人ハ 櫻ノ木ヲ納ルコトヽナリタレハ 当寺ノ境内ニハ昔ヨリ櫻樹多カリシカ 猶近キ頃檀越ノ寄進ニテ再ヒ植増セシニヨリ 毎春花ノ頃ハ人コトニツトヒ来リテ賑ヘリ
■ 『江戸名所図会』(国立国会図書館)
砂水御林町にあり真言宗にて本尊は地蔵菩薩を安置す 弘法大師の作 御丈九寸八分なり
梶原氏の草創にてすなわち此地ハ其宅地なりしといふ
縁起云此本尊ハ梶浦氏代々其家の相伝人々尤霊威なり 然に元享の頃地辨と云沙門眼疾を患ひ此本尊に祈念して不日に本快を得たり 其後世の中大に乱る尓(しかり) 本尊の所在忘れさりしに 文亀年間梅巌阿闍梨当寺より四五町西の方経塚といふ地中よりこれを感得せしとなり(略)当寺境内櫻樹数株ありて悉く品を領てり 弥生の花盛にハ遠近薫を慕ひてし●ふ遊賞する人少ならす
納経塚
来福寺より六町ほど西にあり 相伝ふ此地に収ら●むといへり 来福寺本尊地蔵菩薩此所より出現したまひし頃土中にて夜なヽ読経したまひしとそ 故に来福寺本尊を世に経読地蔵尊と称せり

「来福寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[4],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836]. 国立国会図書館DC (保護期間満了)
【文殊院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
二十六番
四ッ谷南寺町
雲龍山 宝満寺 文殊院
大塚護持院末 新義
本尊:児如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [45] 四谷寺社書上 四』(国立国会図書館)
四ツ谷南寺町
護持院末
雲龍山 宝満寺 文殊院
新義真言宗
開山 祐信上人 寛永十三年(1636年)遷化
中興開基 紀州公御開基(略)年月日相知不候
本尊 阿弥陀児如来立像
本像山城國太秦(略)大蔵之作
児如来記
秦大蔵者乃秦川勝九世孫也(以下略)
護摩堂
本尊 立像不動木像 前立に二童子木像 座像地蔵木像
-------------------------
京急本線「立会川」駅から徒歩10分の住宅街にあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
東京湾にもほど近いですが、このあたりは武蔵野台地が海側にせり出しているところで地勢に起伏があり、石畳の参道も登り坂&階段です。


【写真 上(左)】 山門下
【写真 下(右)】 札所標


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の彫刻
山内入口に寺号標、山門手前に札所標があります。
参道階段の先に山門。来福門とも呼ばれ江戸末期の建立です。
入母屋屋根で桟瓦葺ながら大棟に青海波紋様を置き、降棟、隅棟とも整ってバランスのとれた意匠。水引虹梁両端の木鼻彫刻も見事です。
確信はもてないのですが、おそらく脇塀付の四脚門かと思います。


【写真 上(左)】 緑濃い山内
【写真 下(右)】 修行大師像と本堂
山門をくぐると緑濃い山内。京浜工業地帯にほど近い立地とはとても思えない落ち着いた空気はさすがに古刹。


【写真 上(左)】 地蔵堂の石標
【写真 下(右)】 天水鉢の「丸に並び矢」
本堂手前に修行大師像で、周囲はお砂踏み場となっています。
また、地蔵尊のお種子「カ」が刻まれた地蔵堂石標もみえます。
本堂の天水鉢には梶原氏の家紋「丸に並び矢」が彫られ、梶原氏とのゆかりを示しています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は近代建築で寄棟造桟瓦葺。向拝前三間は軒下に収まっています。
扁額はなく、向拝軒下に吊られた天蓋のようなもの(?)に寺号が刻まれています。


【写真 上(左)】 寺号入りの天蓋?
【写真 下(右)】 聖天堂参道
山内には聖天堂も御座します。
参道の朱塗りの山王鳥居が印象的で、江戸時代建立の堂宇(入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁付)の彫刻も見事です。
庭園に立つ立派な宝篋印塔は享保十九年(1734年)の銘で、右まわりに三回巡拝して願い事を祈願します。


【写真 上(左)】 宝篋印塔
【写真 下(右)】 安明閣
御府内霊場札所のうちでは緑の多い札所のひとつで、落ち着いた参拝ができます。
御朱印は本堂向かって右の寺務所兼休憩所の「安明閣」で拝受しました。
メジャー霊場3つの札所を兼務され、対応は手慣れておられます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊延命地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と地蔵菩薩のお種子「カ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「二十六番」の札所印。左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
■ 第27番 瑠璃山 正光院
(しょうこういん)
公式Web
港区元麻布3-2-20
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:江戸薬師如来霊場三十二ヶ所
司元別当:
授与所:庫裡
第27番札所は元麻布の正光院です。
公式Web および下記史料から縁起・沿革をたどってみます。
寛永七年(1630年)、紀州高野山学寮正智院末寺として麻布櫻田町に開創。
開基は黒田藩主筑前守忠之公、開山は正智院二十八世・検校法印宥専大和尚。
嘉永二年-文久二年(1849-1862年)刊の『江戸切絵図(麻布絵図)』にもしっかりその名がみられます。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』麻布絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
御本尊は弘法大師御作と伝わる薬師如来座像、脇立の日光・月光両菩薩も弘法大師の御作と伝わります。
御本尊は恵心僧都作で、一條帝御降誕の祈願佛という伝承もあるようです。
御本尊の薬師如来は霊験あらたかで「子安(易)薬師」として信仰を集めたといい、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所の札所(現在活動休止)となっています。
弘法大師の木座像も奉安。
別尊の不動尊は麻布大山不動、地蔵尊は子育鹽地蔵と称されていずれも庶民の信仰を集めていたとのこと。
地蔵尊は石佛で、もと霞山櫻田神社の別当・天台宗観明院境内にあったのを、同寺廃絶により当山に遷されたといいます。
開基は高野山真言宗の信仰篤いと伝わる、福岡藩二代藩主の黒田筑前守忠之公。
紀州高野山学寮正智院のおそらく直末で、「麻布高野山」とも呼ばれます。
弘法大師御作と伝わる薬師如来は「子安薬師」として信仰を集めているとあっては御府内霊場札所として申し分なく、今度こそはつぎの第28番へ・・・、となりそうですがやはりそうはいきません。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には第27番札所に「芝赤ばねばしいなり別当 圓明院」とあるからです。
また、江戸八十八ヶ所霊場の第27番札所も「(赤羽橋)三宝山 永護寺 円明院 廃寺」となっています。
しかし、圓明院は『寺社書上』『御府内寺社備考』ともに記載がなく、手がかりは『御府内八十八ケ所道しるべ』しかみつかりません。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には圓明院は「高野山宝性院(寶性院)末」とあります。
Wikipediaによると、宝性院は密教の学問(事相)を大成、宝門(而二門教学)と呼ばれる学派を生み出した宥快が院主となった高野山の寺院で、無量壽院とともに「門主寺」と呼ばれて高い格式を有しました。
大正2年に無量壽院と寳性院は合併、寳壽院を号して現在は高野山真言宗の大本山となっています。
圓明院はこのような高い格式の宝性院のおそらく直末ですから、もう少し記録が残っていてもよさそうですが、どうにも手がかりがありません。
頼みの『御府内八十八ケ所道しるべ』ですが、くずし字で読解不能の箇所があり、判然としません。
「当社の神体ハ大師一刀ごとに三礼して彫刻したまふ●駆三縁山の●山に有る年久しく当院の●●宥矢阿闍梨●●●三縁山の神祠(以下不詳) 土佐國安芸郡安●村竹林山神峯寺本尊十一面かん世をん菩薩像御丈(略)尊しの●る」
弘法大師ゆかりの尊格が御座され、三縁山(増上寺)となんらかの関係がありそうですが、よくわかりません。
国立国会図書館の「錦絵でたのしむ江戸の名所」には「(浄土宗大本山の増上寺は)空海の法弟である宗叡が武州豊島郡江戸貝塚(現在の千代田区紀尾井町付近)に建立した真言宗光明寺を前身とし、明徳4(1393)年聖聡が浄土宗に改宗、名も増上寺と改めた。」とあります。
(この記述は『江戸名所図会』等からひいたものかと思われます。)
赤羽橋といえば増上寺のお膝元ですが、この地に稲荷神の別当として真言密寺(圓明院)が置かれ、御府内霊場の札所とされたのは何らかの意味合いがあるのかもしれません。
弘法大師と稲荷神とのゆかりについてオフィシャルな資料はあまりみつからず、諸説あるようですが、川崎市川崎区の(川中島村)稲荷社(現・大師稲荷神社)は平間寺(川崎大師)が別当を司られた(新編武蔵風土記稿)とありますし、真言密寺の鎮守として稲荷神が祀られる例も少なくありません。
『江戸名所図会』には「(赤羽橋)此辺茶店多く河原の北に●毎朝肴市立て繁昌の地なり」とあり、その栄えている様子は挿絵からもうかがえます。
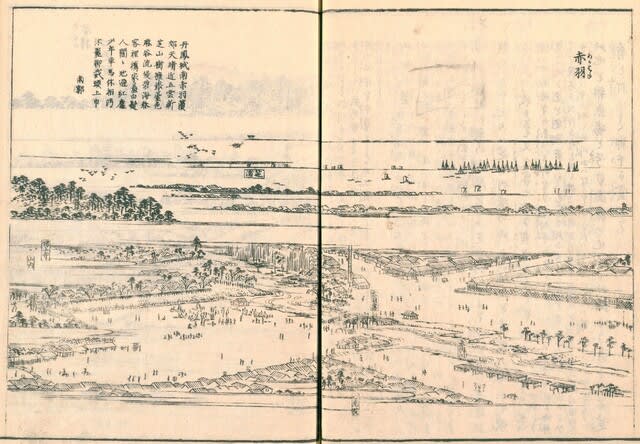
「赤羽」/出典:江戸名所図会 7巻 [3]松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[3],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836]. 国立国会図書館DC
「赤羽橋」駅から東京タワーに向かう谷間は緑ゆたかで「もみじ谷」と呼ばれる紅葉の名所で、この時代も行楽の名所として知られていたかもしれません。(絵図類は行楽地というより繁華地として描いている。)
稲荷神は商売繁昌の神様としても篤く信仰され繁華地に祀られる例も多かったので、赤羽橋に稲荷神が祀られ、別当として密寺が置かれたのも自然な流れだったのかもしれません。
また、現・宝珠院のあたりは弁天霊場、閻魔霊場として知られ、増上寺山内は浄土宗ながら神仏混淆の色彩が強かったとみられます。(→港区Web資料)
赤羽橋稲荷大明神、およびその別当の圓明院は、このような神仏混淆的な場の雰囲気に違和感なくなじんでいたと思われ、その様子は『御府内八十八ケ所道しるべ』の挿絵からもうかがえます。

「圓明院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
圓明院については情報がすこぶる少なく、宗教政策的な機微があるいはあるのかもしれず、不用意な推測は控えた方がいいようにも思えるので、ここまでにしておきます。
なお、赤羽稲荷大明神については現在、社殿は確認できません。
(Web上で跡地の情報がいくつかみつかります。圓明院の旧地は都営大江戸線「赤羽橋」駅のすぐ北側の、古川沿いであったとみられます。)
『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所異動表に「二十七番 赤羽橋 三宝山 圓明院 → 麻布櫻田町 瑠璃山 正光院」とあるので、おそらく明治初頭の神仏分離により芝赤羽橋の圓明院は廃され、第27番札所は麻布の正光院に承継されています。
圓明院はおそらく高野山寶性院(宝門)の直末、正光院は「学侶方宝門の筆頭寺院」(高野山正智院連歌資料集成)の高野山正智院の末でしたから、江戸の宝門寺院内で札所の承継がなされたとみられます。
-------------------------
【史料】
【正光院関連】
■ 『寺社書上 [20] 麻布寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.13.』
麻布櫻田町
紀州高野山学寮正智院末
瑠璃山 正光院
古義真言宗
開闢起立 寛永七年(1630年)
開山 高野山前南山寺務検校法印宥専大和尚 正智院二十八世、寛文十三年三月遷化
本堂
本尊 薬師如来座像
弘法大師木座像
薬師堂
薬師如来座像 脇立 日光菩薩 月光菩薩 以上弘法大師御作
幷 十二神
薬師尊幷二菩薩は祖師弘法大師乃作
聖天 不動尊 愛染明王
地蔵堂
地蔵尊石立像
■ 『麻布区史 P.878』(東京都立図書館デジタルアーカイブ)
瑠璃山正光院 櫻田町三五
古義真言宗高野派 紀伊高野山正智院末。寛永七年の起立で開基は筑前大守従四位黒田忠之、開山は高野山前南山寺務検校法印宥専大和尚(正智院第二十八世、寛文十三年三月二十八日寂)である。本尊薬師如来の坐像は恵心僧都作に係り、一條帝御降誕の祈願佛と傳へている。里俗子安薬師と呼び江戸時代はなかなか信仰されていた。愛染明王像と共に寛永十年黒田侯の寄進するところと傳ふ。
境内の大師堂は府内八十八ヶ所第二十七番霊場になつている。又、不動堂と地蔵堂がある。前者は麻布大山不動と云ひ後者は子育鹽地蔵と呼ばれ、曾て小民の信仰を集めていた。地蔵は石像で、もと霞山櫻田神社の別当、天台宗観明院境内にあったのを、同寺廢絶の為め此処に移したものである。
【圓明院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
二十七番
芝赤ばねばしいなり別当
三宝山 永護寺 圓明院
高野山宝性院末 古義
本尊:本地薬師瑠璃光如来 本社赤羽稲荷大明神 弘法大師
当社の神体ハ大師一刀ごとに三礼して彫刻したまふ●駆三縁山の●山に有る年久しく当院の●●宥矢阿闍梨●●●三縁山の神祠(以下不詳) 土佐國安芸郡安●村竹林山神峯寺本尊十一面かん世をん菩薩像御丈(略)尊しの●る
-------------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅徒歩10分。テレビ朝日通り、麻布税務署の前です。
駐車場はありますが、事前連絡要です。
六本木ヒルズにもほど近い、まさに都心のどまんなかの寺院です。
テレビ朝日通りに面した山内入口には、寺号標、札所標、そして「麻布高野山」の文字もみえます。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
山内は意外に緑が多く、よく整備されています。
正面の階段うえに本堂。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝-1


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
斜めや横に回れなかったので様式は不明ですが、屋根に宝珠を置いているので宝形造かもしれません。
手前に屋根付きの向拝、近代建築ながら水引虹梁も置いています。
向拝見上げには「瑠璃光」の扁額。
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙を貼込み)
中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」「不動明王」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ/ベイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「瑠璃光」印と「第廿七番」の揮毫。左下には「麻布高野山 正光院」の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-9)
【 BGM 】
■ far on the water - Kalafina
■ Erato - 志方あきこ
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO + JP & ROMAJI SUB
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第25番 六所山 長明院 長楽寺
(ちょうらくじ)
日野市程久保8-49-18
真言宗豊山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:
司元別当:
授与所:庫裡
第25番札所の長楽寺は御府内霊場中ふたつある都区外の札所の一寺で、都下の日野市にあります。
第25番札所も複雑な変遷をたどっています。
現在の第25番札所は長楽寺ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では、四ッ谷小寺町の自然山 地福寺 和光院となっています。
「日野市観光協会Web」によると、長楽寺は元和六年(1620年)開山なので、御府内霊場開創の宝暦五年(1755年)にはすでに存在しています。
しかし明治初頭編纂の『御府内八十八ケ所道しるべ』では第25番札所は和光院なので、江戸期を通じて第25番札所は和光院であったとみられます。
(江戸八十八ヶ所霊場第25番も和光院。)
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第25番の和光院は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃されたのかもしれません。
和光院の札所本尊の一尊に将軍地蔵尊が定められていましたが、愛宕権現との習合色の強い将軍(勝軍)地蔵尊を祀る寺院が神仏分離で廃された例(愛宕・圓福寺など)があるため、当院もこの例に該当したのかも。
長楽寺は角筈(現・西新宿三丁目付近)の大寺院でしたが昭和20年5月の空襲で被災し、寺地への道路建設などもあって昭和35年に現在地に移転しています。
寺勢衰微した戦災後に御府内霊場札所になったとは考えにくいので、明治の和光院廃寺によって第25番札所を引き継ぎ、昭和35年の寺院移転とともに札所も移転したというのが自然な見方でしょうか。
「猫の足あと」様Webに掲載されている『日野市史』には以下の記載があるようです。
・総本山長谷寺の末(直末?)
・御本尊の不動明王像は唐よりの伝来と伝わる
・享和二年(1802年)以降、不動信仰により栄え門前市をなした
・明治中期より昭和11年にかけ諸伽藍を建立、大寺院の風格を備えた
・弘法大師像は厄除大師として知られていた
和光院は智積院末(現・智山派系)ですが、四ッ谷からほど近い角筈に不動尊霊場・厄除大師として知られる真言密寺の長楽寺があったため、こちらが第25番札所を承継されたのでは。
あるいは、明治中期から昭和11年にかけての諸伽藍整備の記念事業として、御府内霊場札所を受けられたのかもしれません。
今回は殊に推測が多くなりましたが、それだけ札所異動に関する情報がすくないということです。
-------------------------
【史料】
【長楽寺関連】
■ 日野市観光協会Web(要旨抜粋引用)
・元和六年(1620年)代官渡辺与兵衛が頼音和尚に帰依し、数千坪を寄進して開山したと伝わる。
・徳川四代将軍家綱公が将軍職に就く前、慶安三年(1650年)正月、武蔵国府中六所明神(現・大国魂神社)に参詣の折、当山に立ち寄られ、六所明神にちなんで真筆をもって六所山の山号を与えられたと伝わる。
・もとは新宿区西新宿3丁目にあり、大本堂・書院・庫裡・大師堂・地蔵堂・鐘楼・山門を備えた大寺院だった。
・昭和20年5月25日空襲に遭い、その後の都市計画道路建設により移転をよぎなくされ、昭和35年に多摩動物公園隣の現在地に移転した。
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(角筈村)長楽寺
同宗(新義真言宗)多磨郡中野村寶仙寺末 六所山長命院ト号ス 当寺モ多聞院ト同ク與兵衛ノ開基スル所ナリ 開山賴音 慶安三年(1650年)十二月寂 本尊不動ヲ置 寺傳ニ当山ヲ六所ト号セルハ 昔厳有院殿府中六所ヘ御参ノ時 タマ々々当寺ヘ成ラセ給ヒシヨリ名付シ由イヘト イト牽強ノ説と思ハル 元ヨリ拠トスヘキモノナケレト 其頃賜ヒシ御筆ナリトテ横物ノ掛軸ヲ寺宝トス
【和光院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
二十五番
四ッ谷小寺町
自然山 地福寺 和光院
智積院末 新義
本尊:不動明王 将軍地蔵尊 弘法大師
大師建立本尊地蔵ぼさつ 座像大師
■ 『寺社書上 [43] 四谷寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.38.』
四谷小寺町
京都智積院末
自然山 地福寺 和光院
新義真言宗
開山 法印泉秀 寛永十六年(1639年寂)
当寺開闢之年代相知不
古●麹町辺ニ●●処寛永年中(1624-1644年)(略)御用地(略)処●ニ立退●移●
本堂
本尊 不動明王
護摩堂
本尊 地蔵尊
不動尊 毘沙門天 両大師
鎮守 稲荷社

「和光院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
多摩都市モノレール・京王動物園線「多摩動物公園」駅徒歩2分と交通至便で、駐車場も完備しています。
多摩動物公園のすぐとなりで、休日は子連れファミリーの姿が目立ちます。


【写真 上(左)】 すぐ下にモノレールと駅
【写真 下(右)】 山内入口
丘陵を造成して建立した寺院なので、前面道路からかなりの急坂をのぼります。
参道沿いには石仏が並び、地蔵尊座像も御座します。


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 参道の地蔵尊と石仏群
石仏は如意輪観世音菩薩と地蔵尊がメインで、江戸期の年号が刻まれているので、おそらく角筈の旧地から遷られた御像かと思います。
山内は郊外寺院にしてはコンパクトですが、急坂をのぼっただけに眺望よく明るい雰囲気。
小高い尾根上に尊像や堂宇が連なる構成です。


【写真 上(左)】 修行大師と鎮守神
【写真 下(右)】 修行大師像
手前から朱塗りの稲荷社。扁額には「当山鎮守」とみえます。
そちらの向かって左手には端正な修行大師像。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 山内
さらに、鐘楼、しあわせ小僧、釈迦如来佛足石、大師堂とつづきます。
大師堂には厄除弘法大師座像が御座され、台座には札番の銘板が置かれているのでこちらが御府内霊場の拝所であることがわかります。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂の銘板


【写真 上(左)】 厄除弘法大師像
【写真 下(右)】 奥側の堂宇
札所本尊は不動明王で、たしか大師堂と相対する建物のなかに御座かと思いますが、なぜか記憶が定かでありません。
その奥に鉄柵があり「これより先檀家専用墓地に付 一般の方の立入はご遠慮下さい。」とあるので巡拝者の立入りはここまでです。
鉄柵の奥の大棟に鴟尾を置いた堂宇には「阿弥陀堂」の掲示がありました。
御朱印は庫裡?にて拝受しました。
なお、参詣時間は16時までで、月曜定休の掲示がありました。
出直し参拝はきびしい立地なので、事前の電話確認がベターかと思います。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

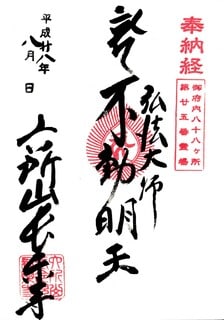
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「不動明王」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内八十八ヶ所第廿五番霊場」の札所印。左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第26番 海賞山 地蔵院 来福寺
(らいふくじ)
公式Web
品川区東大井3-13-1
真言宗智山派
御本尊:延命地蔵菩薩
札所本尊:延命地蔵菩薩
他札所:玉川八十八ヶ所霊場第74番、東海三十三観音霊場第2番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第79番
司元別当:
授与所:事務所
第26番はふたたび都区内に戻ります。
鎌倉御家人や俳句とゆかりのふかい品川・大井の来福寺です。
縁起・沿革は公式Webに詳しいので、こちらと『新編武蔵風土記稿』を参考にまとめてみます。
当山の歴史は古く、正暦元年(990年)、智辨阿闍梨の開山といいますから、1030年以上もの法燈を伝承していることになります。
前九年の役、後三年の役などの戦禍を被るも法燈を堅持され、鎌倉時代には梶原一族が檀信徒となって栄之、景政、景時、景季等が寄進した「梶原松」「延命桜」があったと伝わります。
来福寺参道北側の路地には梶原稲荷神社がご鎮座です。
境内由緒書には「梶原平三景時(略)源頼朝ノ命ヲ奉ジテ武蔵國大井村鹿島谷ニ萬福寺ヲ建立シ、ソノ境内ニ守護神トシテ稲荷ヲ勧請シテ梶原稲荷ト尊称シタ。元応元年(1319年)、萬福寺ハ兵火ニヨリ焼失シ馬込村ニ移リタルニ依リ、焼ケ残リシ稲荷祠ハ梶原屋敷内ニ奉納サレテ、後、柴村来福寺ニ奉納サレ、ソノ追福ノタメ同寺ヘ松櫻ナドヲ植エ寄進シタ。コノ梶原塚ハ鎌倉源五郎景正ノ子梶原日向守 亦梶原助五郎一族ヲ祀ル古墳デアル。」とあります。
なお、現在梶原稲荷神社は地元の梶原稲荷講により維持管理されている模様です。

梶原稲荷神社
文亀元年(1501年)、源頼朝公の納経と伝わる経塚(現・大井1丁目経塚地蔵堂)の前を行脚していた梅巌(梅綾とも)和上が経塚のなかから読経の声を聞かれ、急ぎ掘り起こすと一躰の立派な地蔵菩薩像が出現しました。
不思議に思った梅巌和上がいろいろ調べてみると、この地蔵尊は行方不明となっていた来福寺の御本尊・延命地蔵尊で、弘法大師御作とも伝わる有り難いお像であることがわかりました。
以来このお地蔵さまは「経読(きょうよみ)地蔵尊」と呼ばれ、来福寺の御本尊として尊崇されるとともに、御分身は出現の地(経塚地蔵堂)および三つ叉地蔵堂(大井1丁目)に奉安され、ともに来福寺の境外佛堂として人々の信仰を集めています。
御本尊の経読地蔵尊は鎌倉権五郎景政の守り佛で梶原景季に伝わり、梶原氏との縁から当寺に収まられたといいます。
古来、地蔵尊には桜木を奉納する風習もあって、江戸時代には桜の名所として知られ、山内には「世の中は 三日見ぬ間に 桜かな」という雪中庵三世大島蓼太(芭蕉直系の旅俳人)の句碑があります。
古くは海上山、海照山と号し、境内に天満宮のお社があったので天神山とも呼ばれたといいます。
法系は往古は(馬込)長遠寺末、その後京都仁和寺末となり代々親王が住職を継承されました。
明治38年に川崎大師平間寺の法系となり今日に至っています。
寺伝もきれいに収まってそれではつぎの第27番・・・、となりそうですがそうはいきません。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には第26番札所に「四ッ谷南寺町 文殊院」とあるからです。
また、江戸八十八ヶ所霊場の第26番札所も文殊院となっています。
大井の地は御府内から外れており、この点からも江戸時代の札所は四ッ谷南寺町の文殊院であったとみられます。
20番代の札所は変遷が複雑で、いずれも一筋縄ではいきません。
第26番もこういう変遷があるので、文殊院についてたどっていきます。
文殊院は『御府内寺社備考』に掲載がなく、『寺社書上』と『御府内八十八ケ所道しるべ』を典拠とします。
文殊院は慶長十六年(1616年)、麹町九丁目横町に祐信上人が開山といいます。
寛永十一年(1633年)旧地を御用地として召し上げられ、四ツ谷南寺町に替地を拝領して移転したようです。
大塚護持院を本山とする新義真言宗寺院で、御本尊の阿弥陀児如来は秦氏ゆかりの尊像と伝わります。
秦河勝公は聖徳太子の同志として国造りに貢献したとされますが、河勝公九世孫の秦大蔵老ゆかりの伝承が伝わります。
漢文なので詳細まで読み取れません。すみませぬ。
太秦の名族の当主・秦大蔵老は年老いて子がなくこれを嘆いていたところ、一体の地蔵尊を得て子宝祈願に専念すると、妻が阿弥陀佛の霊夢をみるや女の子を授かりました。
父母の寵愛を一身に受け、聡明で花のように美しく育った姫でしたが、あるとき鷲にさらわれ(?)行方知れずとなってしまいました。
大蔵老は嘆き哀しみ、日夜姫の無事を尊佛に祈りました。
ここから先は記述が込み入って不詳ですが、紆余曲折ののち大蔵老は二寸余の阿弥陀佛像を得、以降、この尊像は「児如来」と尊称され崇められたという内容のようです。
『寺社書上』に「児如来と申阿弥陀木像(略)社僧秦氏代々乃家傳乃本尊」とあるので、こちらの児如来が御本尊として奉安され、札所本尊も児如来でありました。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊児如来ハ川勝の守(?)り佛なり」とあるので、秦河勝公の守り佛であったのかもしれません。
あるいは、河勝公ゆかりの川勝寺(現・京都市右京区西京極、廃寺)の奉安佛だったのかも。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には文殊尊の挿絵が載せられ、こちらが院号ゆかりの尊像とも思いますが、なぜか『寺社書上』には文殊尊についての記載はありません。

「文殊院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
↑ の挿絵には「阿ぶらげ坂」とみえます。
「阿ぶらげ坂」(油揚坂)とは「戒行寺坂」のことで、戒行寺が面していました。
『江戸切絵図』をみると文殊院は戒行寺の対面で、たしかに阿ぶらげ坂(戒行寺坂)に面していたことがわかります。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC
「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所霊場第26番の文殊院は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離時に廃された可能性があります。
第26番札所が四ッ谷の文殊院から大井の来福寺に承継された経緯については、手がかりが見当たらずまったくわかりません。
来福寺は長遠寺(新義智山派)末から仁和寺(古義)末となり、明治38年から川崎大師平間寺(新義智山派大本山)の法系に入っています。
一方、文殊院は大塚護持院末ですから長谷寺豊山派の流れで、本末関係など宗派的なつながりによる承継は考えにくいです。
四ッ谷から大井(品川)への遠距離移転もなんらかの事情があってのものでは?
確たる史料がみつからない以上、これ以上は掘り下げられないので、ナゾはナゾとして残しておきます。(と、逃げる(笑))
来福寺は東海三十三観音霊場との兼務札所です。
この観音霊場は東海道沿いの札所分布で、玉川八十八ヶ所霊場や新四国東国八十八ヶ所霊場との兼務札所はめずらしくないですが、御府内霊場との兼務はこちらだけで、それだけ南東(神奈川)寄りに飛んだ立地であることがわかります。
-------------------------
【史料】
【来福寺関連】
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
(大井村)来福寺
新義真言宗同郡馬込村八幡宮別当長遠寺ノ末ナリ 海賞山地蔵院ト号ス 正暦元年(990年)智瓣阿闍梨ノ草創ト云(略)本尊ハ弘法大師ノ彫刻ニテ延命経讀地蔵ト云ヘリ 寺傳ニヨレハ此像ハ鎌倉権五郎景政ノ守佛ナリシカ 数傳ノ後梶原景季ニ傳ハリ 終ニ當寺ヘ納タリトイヘト證トナスヘキモノアラサレハウケカヒカタシ
天神社 門ヲ入テ右ノ方小高キ処ニアリ
梶原塚 境内北ノ方ニアリ 景季ノ墳ト云 按ニ此辺梶原景時父子ノ舊蹟ト云モノ多シ(以下略)
梶原松 延命櫻 此二木ハ共ニ客殿ノ前ニアリ 梶原景季地蔵信仰ノ餘自ラ植シト云傳フ 今モコノ側にナラヒテ 地蔵尊信心ノ人ハ 櫻ノ木ヲ納ルコトヽナリタレハ 当寺ノ境内ニハ昔ヨリ櫻樹多カリシカ 猶近キ頃檀越ノ寄進ニテ再ヒ植増セシニヨリ 毎春花ノ頃ハ人コトニツトヒ来リテ賑ヘリ
■ 『江戸名所図会』(国立国会図書館)
砂水御林町にあり真言宗にて本尊は地蔵菩薩を安置す 弘法大師の作 御丈九寸八分なり
梶原氏の草創にてすなわち此地ハ其宅地なりしといふ
縁起云此本尊ハ梶浦氏代々其家の相伝人々尤霊威なり 然に元享の頃地辨と云沙門眼疾を患ひ此本尊に祈念して不日に本快を得たり 其後世の中大に乱る尓(しかり) 本尊の所在忘れさりしに 文亀年間梅巌阿闍梨当寺より四五町西の方経塚といふ地中よりこれを感得せしとなり(略)当寺境内櫻樹数株ありて悉く品を領てり 弥生の花盛にハ遠近薫を慕ひてし●ふ遊賞する人少ならす
納経塚
来福寺より六町ほど西にあり 相伝ふ此地に収ら●むといへり 来福寺本尊地蔵菩薩此所より出現したまひし頃土中にて夜なヽ読経したまひしとそ 故に来福寺本尊を世に経読地蔵尊と称せり

「来福寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[4],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836]. 国立国会図書館DC (保護期間満了)
【文殊院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
二十六番
四ッ谷南寺町
雲龍山 宝満寺 文殊院
大塚護持院末 新義
本尊:児如来 不動明王 弘法大師
■ 『寺社書上 [45] 四谷寺社書上 四』(国立国会図書館)
四ツ谷南寺町
護持院末
雲龍山 宝満寺 文殊院
新義真言宗
開山 祐信上人 寛永十三年(1636年)遷化
中興開基 紀州公御開基(略)年月日相知不候
本尊 阿弥陀児如来立像
本像山城國太秦(略)大蔵之作
児如来記
秦大蔵者乃秦川勝九世孫也(以下略)
護摩堂
本尊 立像不動木像 前立に二童子木像 座像地蔵木像
-------------------------
京急本線「立会川」駅から徒歩10分の住宅街にあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
東京湾にもほど近いですが、このあたりは武蔵野台地が海側にせり出しているところで地勢に起伏があり、石畳の参道も登り坂&階段です。


【写真 上(左)】 山門下
【写真 下(右)】 札所標


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門の彫刻
山内入口に寺号標、山門手前に札所標があります。
参道階段の先に山門。来福門とも呼ばれ江戸末期の建立です。
入母屋屋根で桟瓦葺ながら大棟に青海波紋様を置き、降棟、隅棟とも整ってバランスのとれた意匠。水引虹梁両端の木鼻彫刻も見事です。
確信はもてないのですが、おそらく脇塀付の四脚門かと思います。


【写真 上(左)】 緑濃い山内
【写真 下(右)】 修行大師像と本堂
山門をくぐると緑濃い山内。京浜工業地帯にほど近い立地とはとても思えない落ち着いた空気はさすがに古刹。


【写真 上(左)】 地蔵堂の石標
【写真 下(右)】 天水鉢の「丸に並び矢」
本堂手前に修行大師像で、周囲はお砂踏み場となっています。
また、地蔵尊のお種子「カ」が刻まれた地蔵堂石標もみえます。
本堂の天水鉢には梶原氏の家紋「丸に並び矢」が彫られ、梶原氏とのゆかりを示しています。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は近代建築で寄棟造桟瓦葺。向拝前三間は軒下に収まっています。
扁額はなく、向拝軒下に吊られた天蓋のようなもの(?)に寺号が刻まれています。


【写真 上(左)】 寺号入りの天蓋?
【写真 下(右)】 聖天堂参道
山内には聖天堂も御座します。
参道の朱塗りの山王鳥居が印象的で、江戸時代建立の堂宇(入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁付)の彫刻も見事です。
庭園に立つ立派な宝篋印塔は享保十九年(1734年)の銘で、右まわりに三回巡拝して願い事を祈願します。


【写真 上(左)】 宝篋印塔
【写真 下(右)】 安明閣
御府内霊場札所のうちでは緑の多い札所のひとつで、落ち着いた参拝ができます。
御朱印は本堂向かって右の寺務所兼休憩所の「安明閣」で拝受しました。
メジャー霊場3つの札所を兼務され、対応は手慣れておられます。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊延命地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と地蔵菩薩のお種子「カ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「二十六番」の札所印。左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。


【写真 上(左)】 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 東海三十三観音霊場の御朱印
■ 第27番 瑠璃山 正光院
(しょうこういん)
公式Web
港区元麻布3-2-20
高野山真言宗
御本尊:薬師如来
札所本尊:薬師如来
他札所:江戸薬師如来霊場三十二ヶ所
司元別当:
授与所:庫裡
第27番札所は元麻布の正光院です。
公式Web および下記史料から縁起・沿革をたどってみます。
寛永七年(1630年)、紀州高野山学寮正智院末寺として麻布櫻田町に開創。
開基は黒田藩主筑前守忠之公、開山は正智院二十八世・検校法印宥専大和尚。
嘉永二年-文久二年(1849-1862年)刊の『江戸切絵図(麻布絵図)』にもしっかりその名がみられます。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』麻布絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
御本尊は弘法大師御作と伝わる薬師如来座像、脇立の日光・月光両菩薩も弘法大師の御作と伝わります。
御本尊は恵心僧都作で、一條帝御降誕の祈願佛という伝承もあるようです。
御本尊の薬師如来は霊験あらたかで「子安(易)薬師」として信仰を集めたといい、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所の札所(現在活動休止)となっています。
弘法大師の木座像も奉安。
別尊の不動尊は麻布大山不動、地蔵尊は子育鹽地蔵と称されていずれも庶民の信仰を集めていたとのこと。
地蔵尊は石佛で、もと霞山櫻田神社の別当・天台宗観明院境内にあったのを、同寺廃絶により当山に遷されたといいます。
開基は高野山真言宗の信仰篤いと伝わる、福岡藩二代藩主の黒田筑前守忠之公。
紀州高野山学寮正智院のおそらく直末で、「麻布高野山」とも呼ばれます。
弘法大師御作と伝わる薬師如来は「子安薬師」として信仰を集めているとあっては御府内霊場札所として申し分なく、今度こそはつぎの第28番へ・・・、となりそうですがやはりそうはいきません。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には第27番札所に「芝赤ばねばしいなり別当 圓明院」とあるからです。
また、江戸八十八ヶ所霊場の第27番札所も「(赤羽橋)三宝山 永護寺 円明院 廃寺」となっています。
しかし、圓明院は『寺社書上』『御府内寺社備考』ともに記載がなく、手がかりは『御府内八十八ケ所道しるべ』しかみつかりません。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には圓明院は「高野山宝性院(寶性院)末」とあります。
Wikipediaによると、宝性院は密教の学問(事相)を大成、宝門(而二門教学)と呼ばれる学派を生み出した宥快が院主となった高野山の寺院で、無量壽院とともに「門主寺」と呼ばれて高い格式を有しました。
大正2年に無量壽院と寳性院は合併、寳壽院を号して現在は高野山真言宗の大本山となっています。
圓明院はこのような高い格式の宝性院のおそらく直末ですから、もう少し記録が残っていてもよさそうですが、どうにも手がかりがありません。
頼みの『御府内八十八ケ所道しるべ』ですが、くずし字で読解不能の箇所があり、判然としません。
「当社の神体ハ大師一刀ごとに三礼して彫刻したまふ●駆三縁山の●山に有る年久しく当院の●●宥矢阿闍梨●●●三縁山の神祠(以下不詳) 土佐國安芸郡安●村竹林山神峯寺本尊十一面かん世をん菩薩像御丈(略)尊しの●る」
弘法大師ゆかりの尊格が御座され、三縁山(増上寺)となんらかの関係がありそうですが、よくわかりません。
国立国会図書館の「錦絵でたのしむ江戸の名所」には「(浄土宗大本山の増上寺は)空海の法弟である宗叡が武州豊島郡江戸貝塚(現在の千代田区紀尾井町付近)に建立した真言宗光明寺を前身とし、明徳4(1393)年聖聡が浄土宗に改宗、名も増上寺と改めた。」とあります。
(この記述は『江戸名所図会』等からひいたものかと思われます。)
赤羽橋といえば増上寺のお膝元ですが、この地に稲荷神の別当として真言密寺(圓明院)が置かれ、御府内霊場の札所とされたのは何らかの意味合いがあるのかもしれません。
弘法大師と稲荷神とのゆかりについてオフィシャルな資料はあまりみつからず、諸説あるようですが、川崎市川崎区の(川中島村)稲荷社(現・大師稲荷神社)は平間寺(川崎大師)が別当を司られた(新編武蔵風土記稿)とありますし、真言密寺の鎮守として稲荷神が祀られる例も少なくありません。
『江戸名所図会』には「(赤羽橋)此辺茶店多く河原の北に●毎朝肴市立て繁昌の地なり」とあり、その栄えている様子は挿絵からもうかがえます。
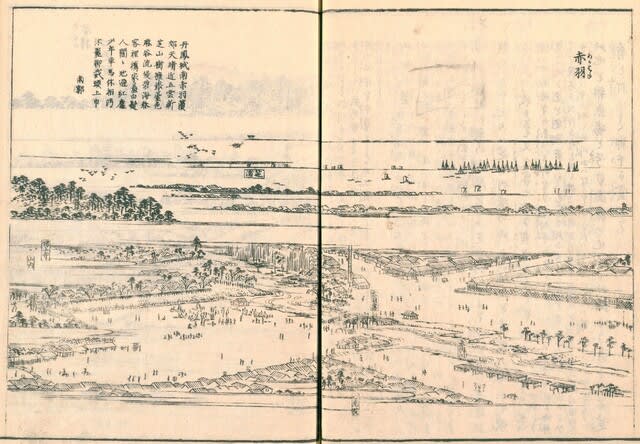
「赤羽」/出典:江戸名所図会 7巻 [3]松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[3],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836]. 国立国会図書館DC
「赤羽橋」駅から東京タワーに向かう谷間は緑ゆたかで「もみじ谷」と呼ばれる紅葉の名所で、この時代も行楽の名所として知られていたかもしれません。(絵図類は行楽地というより繁華地として描いている。)
稲荷神は商売繁昌の神様としても篤く信仰され繁華地に祀られる例も多かったので、赤羽橋に稲荷神が祀られ、別当として密寺が置かれたのも自然な流れだったのかもしれません。
また、現・宝珠院のあたりは弁天霊場、閻魔霊場として知られ、増上寺山内は浄土宗ながら神仏混淆の色彩が強かったとみられます。(→港区Web資料)
赤羽橋稲荷大明神、およびその別当の圓明院は、このような神仏混淆的な場の雰囲気に違和感なくなじんでいたと思われ、その様子は『御府内八十八ケ所道しるべ』の挿絵からもうかがえます。

「圓明院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
圓明院については情報がすこぶる少なく、宗教政策的な機微があるいはあるのかもしれず、不用意な推測は控えた方がいいようにも思えるので、ここまでにしておきます。
なお、赤羽稲荷大明神については現在、社殿は確認できません。
(Web上で跡地の情報がいくつかみつかります。圓明院の旧地は都営大江戸線「赤羽橋」駅のすぐ北側の、古川沿いであったとみられます。)
『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所異動表に「二十七番 赤羽橋 三宝山 圓明院 → 麻布櫻田町 瑠璃山 正光院」とあるので、おそらく明治初頭の神仏分離により芝赤羽橋の圓明院は廃され、第27番札所は麻布の正光院に承継されています。
圓明院はおそらく高野山寶性院(宝門)の直末、正光院は「学侶方宝門の筆頭寺院」(高野山正智院連歌資料集成)の高野山正智院の末でしたから、江戸の宝門寺院内で札所の承継がなされたとみられます。
-------------------------
【史料】
【正光院関連】
■ 『寺社書上 [20] 麻布寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.13.』
麻布櫻田町
紀州高野山学寮正智院末
瑠璃山 正光院
古義真言宗
開闢起立 寛永七年(1630年)
開山 高野山前南山寺務検校法印宥専大和尚 正智院二十八世、寛文十三年三月遷化
本堂
本尊 薬師如来座像
弘法大師木座像
薬師堂
薬師如来座像 脇立 日光菩薩 月光菩薩 以上弘法大師御作
幷 十二神
薬師尊幷二菩薩は祖師弘法大師乃作
聖天 不動尊 愛染明王
地蔵堂
地蔵尊石立像
■ 『麻布区史 P.878』(東京都立図書館デジタルアーカイブ)
瑠璃山正光院 櫻田町三五
古義真言宗高野派 紀伊高野山正智院末。寛永七年の起立で開基は筑前大守従四位黒田忠之、開山は高野山前南山寺務検校法印宥専大和尚(正智院第二十八世、寛文十三年三月二十八日寂)である。本尊薬師如来の坐像は恵心僧都作に係り、一條帝御降誕の祈願佛と傳へている。里俗子安薬師と呼び江戸時代はなかなか信仰されていた。愛染明王像と共に寛永十年黒田侯の寄進するところと傳ふ。
境内の大師堂は府内八十八ヶ所第二十七番霊場になつている。又、不動堂と地蔵堂がある。前者は麻布大山不動と云ひ後者は子育鹽地蔵と呼ばれ、曾て小民の信仰を集めていた。地蔵は石像で、もと霞山櫻田神社の別当、天台宗観明院境内にあったのを、同寺廢絶の為め此処に移したものである。
【圓明院関連】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)
二十七番
芝赤ばねばしいなり別当
三宝山 永護寺 圓明院
高野山宝性院末 古義
本尊:本地薬師瑠璃光如来 本社赤羽稲荷大明神 弘法大師
当社の神体ハ大師一刀ごとに三礼して彫刻したまふ●駆三縁山の●山に有る年久しく当院の●●宥矢阿闍梨●●●三縁山の神祠(以下不詳) 土佐國安芸郡安●村竹林山神峯寺本尊十一面かん世をん菩薩像御丈(略)尊しの●る
-------------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅徒歩10分。テレビ朝日通り、麻布税務署の前です。
駐車場はありますが、事前連絡要です。
六本木ヒルズにもほど近い、まさに都心のどまんなかの寺院です。
テレビ朝日通りに面した山内入口には、寺号標、札所標、そして「麻布高野山」の文字もみえます。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 山内
山内は意外に緑が多く、よく整備されています。
正面の階段うえに本堂。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝-1


【写真 上(左)】 向拝-2
【写真 下(右)】 扁額
斜めや横に回れなかったので様式は不明ですが、屋根に宝珠を置いているので宝形造かもしれません。
手前に屋根付きの向拝、近代建築ながら水引虹梁も置いています。
向拝見上げには「瑠璃光」の扁額。
御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙を貼込み)
中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」「不動明王」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ/ベイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「瑠璃光」印と「第廿七番」の揮毫。左下には「麻布高野山 正光院」の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-9)
【 BGM 】
■ far on the water - Kalafina
■ Erato - 志方あきこ
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO + JP & ROMAJI SUB
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-7
Vol.-6からのつづきです。
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第21番 寶珠山 東福院
(とうふくいん)
公式Web
新宿区若葉2-2-6
新義真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第21番、弁財天百社参り第34番
司元別当:
授与所:寺務所
第21番はふたたび四谷に飛びます。
公式Webによると、天正三年(1575年)に開基(開山)法印祐賢上人、外護者大沢孫右衛門尉によって麹町九丁目(横町)に創建。
寛永十一年(1634年)に現在地に移転といいます。
大沢氏は藤原北家持明院流とされ、本拠は遠州堀江城(浜松市西区)。
今川家家臣から徳川家に仕え、大沢基宿は最初の高家職を勤めたことで知られています。
高家は幕府の職制のひとつで、老中の管轄下で将軍の代参、勅使・院使の接待や饗応役の大名への儀典指南などの職務を果たしました。
ちなみに忠臣蔵の敵役、吉良上野介義央は高家で、赤穂事件の直前まで浅野内匠頭長矩に対して勅使饗応役の指南を行っていたといいます。
高家職に就けるのは「高家旗本」(「高家」の家格にある旗本)のみで、主に有力大名・守護系戦国大名の子孫や公家の分家など、「名門」の家柄で占められたといいます。
大沢氏は藤原北家持明院流という家格もあって、高家に任ぜられたのでは。
東福院は『御府内寺社備考』では「常陸国(筑波山)護持院末」とあり、もともとは筑波山知足院中禅寺(大御堂)の末寺だったようですが、いまは根来寺を祖廟(本山)とする新義真言宗寺院です。
なお、筑波山知足院中禅寺(大御堂)は、真言宗江戸触頭四箇寺および徳川将軍家祈祷寺と強い関係をもち、具体的には筑波知足院 → 江戸知足院 → 江戸護持院 → 音羽護国寺という流れがみられますが、これについては第87番護国寺でふれます。
(→『近世初期の知足院』坂本正仁氏/PDF』)
『御府内寺社備考』によると、御本尊は大日如来。
脇士に不動明王と毘沙門天を奉安し、両界八祖画像、弘法大師像を安ずる保守本流的な真言宗寺院であったようです。
江戸八十八ヶ所霊場も同番なので、開創当初からの札所とみられます。
弁天堂の御本尊辨財天(秘像)は弘法大師の御作と伝わり、お前立の辨財天座像も奉安、「出世辨天」として尊崇をあつめた弁財天百社参り第34番の札所本尊は、こちらの弁財天尊ではないでしょうか。
なお、『ルートガイド』によると地蔵堂の地蔵菩薩は「豆腐地蔵」と呼ばれ、由来の逸話を載せていますが、『寺社書上』『御府内寺社備考』にはこの縁起は記載されておらず、江戸後期以降の伝承かもしれません。
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.62』
四谷南寺町
本寺常陸国(筑波山)護持院末
阿祥山 宝壽寺 東福院
新義真言宗
起立慶長十六年辛亥(1611年)麹町九丁目横町
開山 法印祐賢
本尊 大日如来
脇士 不動尊 毘沙門天
両界八祖画像
弘法大師木像
弁天堂
本尊辨財天(秘像) 弘法大師作 前立辨財天座像
脇立 大黒天立像 毘沙門天
不動尊 十一面観音
地蔵堂
地蔵尊立像 疱瘡神 愛宕
稲荷社
神体無之 本地十一面観音立像 石地蔵尊
寺中 泉蔵院
■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
阿祥山寶壽寺東福院は大塚護持院末の新義眞言宗で、四谷南寺町今の寺町にある。境内は古跡拝領地で千九百三十四坪餘、慶長十六年辛亥(1611年)麹町九丁目横町に起立し、寛永十一年甲戌(1634年)此地に転じた。開山法印祐賢の示寂年月は明かでない。府内八十八箇所廿一番の札所である。猶寺には辨財天木像涅槃画像其他を蔵していて、中にも辨財天は出世辨天と称して有名である。(略)
-------------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号標
四谷寺町に立地し、寛永十一年(1634年)麹町九丁目横町から現在地に移転しているので、寛永年間(1624-1645年)家光公の治世に江戸城外堀工事のため四谷に移転させられた麹町の寺院のひとつとみられます。
第18番愛染院と東福院坂(天王坂)を挟んだほぼ対面にあります。

 【写真 上(左)】 根来寺の寺紋「三つ柏」
【写真 上(左)】 根来寺の寺紋「三つ柏」
【写真 下(右)】 参道
東福院坂の途中に山内入口。
根来寺を祖廟(本山)とする新義真言宗寺院は、御府内霊場では3箇寺(当山、自性院(谷中)、加納院(谷中))。
門扉には新義真言宗総本山根来寺の寺紋「三つ柏」が掲げられています。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 本堂
正面が近代建築の本堂。
参道右手に御府内霊場札所碑、子育?地蔵尊、聖観世音菩薩、地蔵堂と並びます。
地蔵堂は『ルートガイド』に載っているもので、堂内扁額には「豆腐地蔵尊」とありました。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 豆腐地蔵尊


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は寺務所を兼ねていて仏堂のイメージはうすいですが、正面に山号扁額が掲げられているので、こちらからの奉拝と思われます。
御朱印は寺務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印。
「豆腐地蔵」の印判も捺されています。
右上に「第二十一番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第22番 天谷山 龍福寺 南蔵院
(なんぞういん)
新宿区箪笥町42
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第22番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第27番、弁財天百社参り第40番
司元別当:
授与所:庫裡
御府内霊場には南蔵院と号する札所が練馬(第15番)、牛込(第22番)と高田(第29番)の3箇寺あり、それぞれ練馬南蔵院、牛込南蔵院、高田南蔵院と呼んで区別されます。
下記史料類と『ルートガイド』をもとに牛込南蔵院の縁起・由緒をたどってみます。
牛込南蔵院は、元和元年(1615年)、牛込城主の牛込勝重が正胤法印を請じて早稲田の地に吉祥山福正院と号して創建。
当初は弁財天二尊を上宮・下宮として祀っていたといいます。
延宝九年(1681年)、旧寺地が御用地として召上げられ、替地として現在地を拝領して移転し元号に改めました。
弁財天上宮は現在地に遷られ、下宮は弁天町の宗参寺(曹洞宗)にご遷座して奉祀といいます。
宗参寺も江戸三十三ヶ所弁財天霊場第26番、弁財天百社参り第41番の兼務札所ですから、こちらも代表的な弁財天霊場となっていたことがわかります。


【写真 上(左)】 宗参寺
【写真 下(右)】 宗参寺の御朱印
当山、宗参寺ともに牛込氏とのゆかりがふかい寺院です。
新宿区の新宿文化観光資源サイトでは宗参寺山内の牛込氏墓が紹介され、説明文には下記の内容が記されています。
・牛込氏は上野国勢多郡大胡(現・前橋市大胡町周辺)の領主・大胡氏の出で、15世紀末に武蔵国に進出して北条氏に従った。
・大永六年(1526年)には牛込に定住し、天文二十四年(1555年)北条氏康により牛込姓への改姓を認められ、牛込から日比谷あたりまで領有。
・その城館は現在の光照寺(袋町15番地)一帯の「牛込城跡」(新宿区登録史跡)に築かれ、「牛込家文書」は東京都指定有形文化財。
・天正十八年(1590年)の北条氏滅亡後は徳川氏に従い幕臣となった。
・宗参寺は天文十二年(1543年)に没した大胡重行(法名宗参)の墓所として子の勝行が創建した寺院で、以来牛込氏の菩提寺となっている。
また、Wikipediaには「徳川家康の江戸入城の後、館(牛込城)は廃止され、跡地に神田光照寺が移転してきたのは1645年のことであったとされる。」とあります。
『ルートガイド』によると、正胤法印は上総千葉一族とのこと。
たしかに千葉氏の通字は「胤」ですが、千葉氏は一族が多いので簡単には追い切れません。
『御府内寺社備考』をみると、南蔵寺は当初から弁財天とのゆかりがふかく、旧来は弁財天が御本尊であった可能性があります。
山内に宇賀神、十五童子立像も安置され、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第27番、弁財天百社参り第40番のふたつの弁財天霊場の札所でもありました。
現在の南蔵院の御本尊および御府内霊場の札所本尊は千手観世音菩薩です。
ところが、不思議なことに『御府内寺社備考』には千手観世音菩薩にかかわる記載がありません。
弘法大師については、寺中薬王院に弘法大師木坐像を奉安しており、御府内霊場札所の要件を満たしています。
江戸八十八ヶ所霊場も同番なので、開創当初からの札所とみられます。
東京都公文書館によると、『御府内寺社備考』は文政九年(1826年)から3年程度で作成されました。
御府内霊場の開創は宝暦五年(1755年)頃とみられるので、『御府内寺社備考』は御府内霊場開創後の作成です。
なので、当初の南蔵院の御府内霊場札所本尊は、弁財天と弘法大師であった可能性もあります。
弁財天と千手観世音菩薩の尊格的なつながりはよくわかりませんが、日本三大弁天のひとつ竹生島宝厳寺の千手千眼観世音菩薩は、西国三十三所第30番の札所本尊で当山御本尊の弁天様と同じく60年に一度の御開扉です。
また、江ノ島の岩屋内には弁財天とともに千手観世音菩薩が祀られています。
栃木県の大谷寺(坂東観音霊場第19番)にも千手観音と弁財天にまつわる伝承が伝わります。
その昔、この地に毒蛇が棲みつき、毒蛇が吐き出す毒水の害で人々が苦しみ、毒蛇の住処は「地獄谷」と呼ばれて畏れられていました。
東国を巡錫中の弘法大師がこの話を聞かれると、秘法をもってこの毒蛇を退治されました。
大師が去られた後に人々が地獄谷を訪れると、高い岩山には千手観音が光り輝き、その脇侍として不動明王と毘沙門天が彫られており、これが大谷寺開山の縁起とされます。
大谷寺には弁天堂があり、こちらの弁財天には、弘法大師の秘法により心を入れ替えた毒蛇がお仕えしているそうです。(同山パンフ記載の縁起より抜粋)
以上から、弁財天と千手観世音菩薩はなんらかの関係があるとも考えられ、その縁から千手観世音菩薩が御本尊となられたのかもしれません。
(かなり牽強附会的なこの見方は、あくまでも筆者の憶測です。)
弘法大師とのゆかりは強く、聖天堂の本地佛・十一面観世音菩薩は弘法大師作、寺宝の獨鈷杵は弘法大師が唐より招来されたもの、般若心経も弘法大師御筆と記されています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内寺社備考 P.35』
牛込御箪笥町
京都大佛智積院末
天谷山 竜福寺 南蔵院
当寺開闢之儀者元和の初年(1615年)下総國香取妙幢院正胤法印 武蔵國牛込之領主何某請ふより同國豊嶋郡早稲田の里●褐をとて●上宮下宮乃二宇を造立し辨財天二体を勧請し正胤法印上の宮を別当し吉祥山福正院といふ ●後第四世日胤代延宝九年(1681年)右地所御用地ニ付召上替地として南●之地所を拝領 仕以地名を蟇谷といへ(略)当所に称し天谷山南蔵院と改む。下の宮を●猶旧内地に安置●●弁天町●なり。
弁天木座像
十五童子木立像
唐●●●
右●宇賀神安置
薬師木座像
金毘羅木立像
獨鈷杵 弘法大師大唐より渡来開山正胤所持是什宝とす
般若心経 弘法大師筆
辨財天縁起 一巻
聖天堂
本尊観世音 黄金鋳像 秘佛
本地佛 十一面観世音 弘法大師作 木立像 水戸家御寄附宝暦六年(1756年)
歓喜天●尊● 一基
護摩堂
本尊不動明王木立像
阿弥陀堂
本尊阿弥陀如来 安阿弥作木坐像
稲荷社
寺中二軒
安養院 当時廃地
薬王院 本尊薬師如来 地蔵尊木立像 弘法大師木坐像
■ 『牛込区史』(国立国会図書館)
天谷山龍福寺南蔵院 智積院末
元和初年(1615年)、早稲田在辨財天上宮(今の辨天町でゝもあらう)の別當として、正胤法印開山、寺号を吉祥山福正院と云つたが、延寳九年箪笥町に移り、寺號を改めた。開山法印正胤寛永七年(1630年)二月廿九日遷化。(略)
本尊辨財天は弘法大師の作といひ伝ふ。
寺中 安養院
同上 薬王院
-------------------------


【写真 上(左)】 前面道路からの山内
【写真 下(右)】 山内入口
新宿区の牛込周辺はいまでも古い地名が住所として残っています。
箪笥町もそのひとつで、「箪笥」とは"武器"のことで、江戸時代に幕府の武器をつかさどる具足奉行・弓矢鑓奉行組同心の拝領屋敷があったことに由来するとのこと。(→東京都公文書館(江戸東京の町名)より)
かつては陸の孤島的だった牛込辺も、都営大江戸線の開通により俄然便利になりました。
南蔵院は、都営大江戸線「牛込神楽坂」駅直近にあります。
通りに面して門柱。門柱には院号の表札。
門柱右に「大聖歓喜天」の石標、門柱左には御府内霊場札所標。
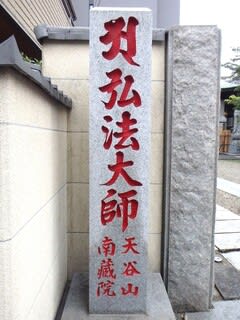

【写真 上(左)】 札所碑
【写真 下(右)】 山内
正面が本堂、向かって右手に聖天堂の伽藍配置です。
本堂はコンクリ造の近代建築ですが、切妻の妻の下に銅板葺の唐破風向拝を附設。
見た目の印象からすると入母屋造ないし切妻造の妻入りかもしれません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
唐破風鬼に経の巻獅子口。その上の妻部は格子仕上げで拝みに蕪(三つ花)懸魚と鬼板には真言宗の輪違い紋を掲げて本堂の風格を備えています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
がっしりとした向拝柱と見上げに院号扁額。
堂前向かって右の通常修行大師像が御座す場所には地蔵尊立像の安置なので、弘法大師御像は本堂内と思われます。


【写真 上(左)】 本堂(手前)と聖天堂(奥)
【写真 下(右)】 聖天堂
本堂向かって右手の堂宇は聖天堂。
おそらく入母屋造瓦葺の妻入りで、妻部に向拝を附設したかたちかと思います。
こちらは伝統的な寺院建築で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股などを備え、向拝上部に「歓喜天」の扁額を掲げています。
『御府内寺社備考』記載の「聖天堂」の系譜をひく堂宇かと思われます。
御朱印は本堂右手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

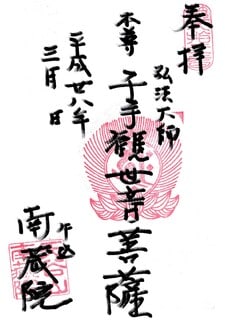
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)
中央に「本尊 千手観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と千手観世音菩薩のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第弐拾貳番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第23番 川崎大師 東京別院 薬研堀不動院
(やげんぼりふどういん)
公式Web
中央区東日本橋2-6-8
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:関東三十六不動尊霊場第21番、御府内二十八不動霊場第9番
司元別当:
授与所:本堂内
第23番札所は川崎大師東京別院の薬研堀不動院です。
公式Webには、薬研堀不動院は、古くから目黒(不動尊)、目白(不動尊)と並び江戸三大不動として知られ、『江戸名所図会』をはじめ多くの文献に紹介されているとの由。
公式Webおよび『ルートガイド』『関東三十六不動霊場公式ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
保延三年(1137年)、真言宗中興の祖・興教大師(覚鑁上人)は43歳の厄年を無事にすまされた御礼として一刀三礼で不動明王尊像を敬刻、紀州・根来寺に奉安されました。
天正十三年(1585年)、豊臣秀吉の根来攻めの兵火に遭った際、根来寺の大印僧都がこの尊像を守護して葛籠に納め、みずから背負われて東国へ下りました。
大印僧都は隅田川のほとりに有縁の霊地を定め、天正十九年(1591に)堂宇を建立されたのが薬研堀不動院のはじまりといいます。
こちらの不動尊の霊験まことにあらたかで、人々は「葛籠不動尊」と称し、目黒不動尊、目白不動尊とあわせて「江戸三大不動尊」と奉じて篤く尊崇したといいます。
とくに薬研堀不動尊の歳の市は、江戸の一年を締めくくる風物詩としてたいへん賑わったそうです。
(「歳の市」は12月14日の深川八幡に始まり、浅草観音、神田明神、愛宕神社、平河、湯島天神を巡って28日の薬研堀不動院で納めとなりました。)
山内の「収めの歳の市碑」(歳の市保存会)には、往年の歳の市の賑わいがつぎのとおり描写されています。
「戦前は何十軒もの羽子板屋が出店し 当時の千代田小学校の通りには『がさ市』が立ち 〆飾り 角松 竹 海老 こんぶ等が威勢よく売られ 身動き出来ぬ位の人出に下町情緒豊かな歳末風景がみられた」
また、当山は講談発祥の地という説があり、山内には「講談発祥之地碑」が建てられて、いまもご縁日の28日には講談が奉納されています。
明治二十五年(1892年)川崎大師平間寺の別院となり、都内有数の弘法大師霊場・不動尊霊場としていまに至っています。
江戸中期に変遷があったとみられ、「猫の足あと」様掲載の『中央区史』には「天保年中(1831-1845年)、本所弥勒寺中へ移され、維新後、有縁の旧地に移り咲いて仏殿を造営」とあります。
御府内霊場の開創は宝暦五年(1755年)頃とされるので、薬研堀不動院の弥勒寺中への移転(天保年中(1831-1845年))前です。
弥勒寺は御府内霊場開設当初からの札所(第50番)とみられるので、薬研堀不動院が当初からの札所(第23番)だとすると移転り際に弥勒寺の札所兼務問題がでてきます。
一方、江戸八十八ヶ所霊場の第23番は、市谷川田ヶ久保の稲荷山 薬王寺で、明治はじめの神仏分離で廃寺となっています。
『御府内八十八ケ所道しるべ』によると、御府内霊場第23番は明治のはじめまで市ヶ谷の薬王寺とあります。
よって薬研堀不動院は、明治二十五年(1892年)までに本所の弥勒寺内から旧地に移り咲き、御府内霊場第23番は川崎大師平間寺の別院となった薬研堀不動院に引き継がれたのではないでしょうか。
真言宗智山派の大本山・平間寺(川崎大師)の東京別院だけに、札所承継にあたり様々な動きがあったのかもしれませんが、詳細はわかりません。
薬王寺は大塚護國寺末だったので現在の真言宗豊山派系、平間寺は真言宗智山派の大本山ですから、札所の承継にやや疑問はありますが、なにぶん天保年中(1831-1845年)から明治初期までの薬研堀不動院の動静がほとんどたどれないので、下記史料類から薬王寺についてたどってみます。
薬王寺は室町時代、武将・太田道灌(1486年没)が築いた城の守護として京都稲荷山の神霊を勧請して市ヶ谷御門のあたりに草創と伝わります。
開山は法印澄覺(寛文三年(1663年)十月遷化)。
当初は愛染尊(明王)を安置し、愛染院と号していたようです。
元和の頃(1615-1624年)、稲荷社は当寺より二町ばかり北の方へ遷られたといいます、
中興開山は法印證覚(正(徳)三年(1713年)十月遷化)。
貞享年中(1684-1688年)に弘法大師御作の薬師如来像を奉安し、愛染院から薬王寺に号を改めたといいます。
『江戸名所図会』には「(稲荷社を)其後又此地へうつして当寺の護法神とせり。」とあるので、法印證覚の頃に稲荷社が当地に戻られて護法神となったのかもしれません。
史料類をみると、弘法大師御作の御本尊・薬師如来をはじめ、弘法大師の御自作像、(興)教大師御作の顧不動尊を奉安するなど、堂々たる新義真言宗寺院の内容を備え、弘法大師霊場札所としての資格も充分備えていたものとみられます。
桂昌院(5代将軍綱吉公の生母)、常憲院(徳川綱吉公)の帰依が篤かったらしく、仏像・仏画の寄附の記録が残ります。
このような由緒ある寺院が明治の神仏分離で廃寺となってしまったのは、いささか不思議な感じもしますが、いまは「市谷薬王寺町」の地名にその名を残すのみです。
なお、Wikipediaなど複数のWeb資料で「(薬王寺の)法灯は文京区大塚の護国寺に移された。」とあります。
護国寺は御府内霊場の第87番札所。
護国寺での重番を避けるとしても、豊山派系の寺院が承継すればよさそうですが、智山派大本山・平間寺(川崎大師)の東京別院が引き継いだ背景には、やはり特段の事情があったのかもしれません。
いずれにしても、平間寺(川崎大師)は東京別院を通じて御府内霊場の一画を占めることとなりました。

「薬研堀」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[1],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836]. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
※本所移転前の絵図と思われます。
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [38] 市谷寺社書上 三止』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.39』
市谷南寺町
大塚護國寺末
稲荷山 東光院 薬王寺
新義真言宗
開山 法印澄覺(寛文三年(1663年)十月遷化)
中興開山 法印證覚(正(徳)三年(癸巳)(1713年)十月遷化)
本尊 薬師如来 弘法大師作 石像秘佛
前立 薬師如来 木座像丈七寸
日光 月光 十二神将
・桂昌院様御寄附
正観世音 唐佛金之像 丈壱尺二寸
顧不動尊 (興)教大師作 木坐像丈九寸
幷両脇士
・桂昌院様ヨリ拝領
愛染尊 運慶作 木像 丈八寸
毘沙門天王 聖徳太子作 木像 丈三尺許
阿弥陀如来 行基菩薩作 木立像一尺二寸
地蔵尊
弘法大師御自作像 椅子座 丈ヶ壱尺壱寸
歓喜天 唐金鋳像秘佛
・寺寶
嵯峨帝御守本尊 佛眼佛母尊 天竺佛
・常憲院様ヨリ拝領
不動尊 一幅 弘法大師筆 二童子 倶利伽羅 後●院後持尊
涅槃像
(略)
稲荷社
稲荷大明神 神躰木立像
御本地佛 十一面観世音 鋳佛坐像
天神木坐像 辨才天木坐像
唐寺開闢之義 往古太田持資入道道灌 御城築●●為 城内乾●護 京都稲荷山●神霊を勧請し ●愛染尊を安置依●稲荷山愛染●と号し市ヶ谷御門之(略)貞享年中(1684-1688年)弘法大師彫刻之石像坐像●来安置と依て本院改号薬王寺とす
桂昌院様依●帰依薬師如来(略)寄附
■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
稲荷山 薬王寺
東光院と号す。同所より西方の方、河田ヶ窪にあり。新義の真言宗にして、大塚の護國寺に属せり。
開山を法印澄覺と号く。
本尊薬師如来の像は、弘法大師、天台四明の洞の霊石を得て、彫刻し給ひし霊像なりといふ。貞享(1684-1688年)の初、須田氏某、当寺に安置なし奉るとなり。
当寺昔は愛染院と称したりといふ。
稲荷祠
境内にあり。相傳ふ。太田道灌(1486年没)の勧請にして、むかしは今の市ヶ谷御門の辺にありしとなり。元和の頃(1615-1624年)当寺より二町ばかり北の方へ遷し、其後又此地へうつして当寺の護法神とせり。

「薬王寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------


【写真 上(左)】 街路にはためく幟-1
【写真 下(右)】 同-2
都営浅草線「東日本橋」駅徒歩約3分、都営新宿線「馬喰横山」駅徒歩約5分という交通至便の札所です。
あたりは完璧なビル街で、その道路沿いにお不動様の幟が並び立つさまはなかなか絵になります。


【写真 上(左)】 改修後の現山内
【写真 下(右)】 本堂
ビルに囲まれた一画に急な階段と、その上に重層八角堂的なお堂。
参道階段脇には幟がはためき、不動尊霊場の趣きがあります。
こちらは数年前にリニューアルされ、手前に数台分の駐車場ができました。
本堂内にあった納経所は、駐車場前に移されて全体に山内はすっきりとしています。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 向拝
階段をのぼった正面が向拝で五色幕が張り巡らされて華やかです。
「不動尊」の提灯のおくに「薬研堀不動院」の扁額。
以前は本堂内でお参りできましたが、現在は不明です。
正面お厨子のなかにお不動さまと向かって右に観世音菩薩像。
左手の尊像は金剛界大日如来でしょうか。
その両脇には弘法大師像と興教大師像という、真言宗寺院らしい堂内です。

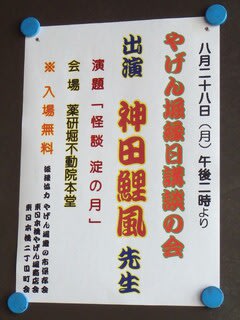
【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 講談の会の案内
公式Webで「不動院の鎮守」として紹介されている矢ノ庫稲荷神社は、「東日本橋」駅寄りの薬研堀不動院信徒会館のよこの角地に御鎮座で、薬研堀不動院納経所で御朱印を拝受できます。

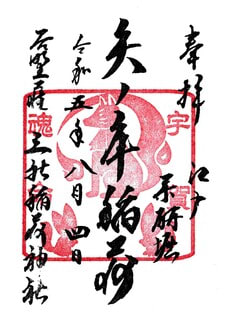
【写真 上(左)】 矢の庫稲荷
【写真 下(右)】 矢の庫稲荷の御朱印
境内の縁起書によると、かつて当地に隣接する日本橋一丁目あたりは谷野と呼ばれ、正保二年(1645年)幕府が米蔵を建て谷野蔵矢之倉と称されました。
米蔵の庭中に御蔵の鎮神として三社を合殿し三社稲荷神社を祀りました。
中央は谷野蔵稲荷、左に福富稲荷、右には新左衛門稲荷で、元禄十一年(1698年)に御蔵を鉄砲洲に移転した際に三社稲荷は一緒に御遷座されました。
御蔵跡周辺の人々は三社稲荷の名を惜しんで、新左衛門稲荷と福富稲荷を初音森神社に合祀、谷野蔵稲荷は変遷を経て現在地に御鎮座となり、社号も矢の庫稲荷と改められました。
経緯は明らかでないですが、薬研堀不動院公式Webには「不動院の鎮守」として矢の庫稲荷が紹介されています。
上記のとおり、旧第23番札所の稲荷山 薬王寺には太田道灌ゆかりの稲荷社が祀られていました。
三社稲荷のうち新左衛門稲荷と福富稲荷が合祀された初音森神社も太田道灌ゆかりの神社で、三社稲荷神社・太田道灌を介してなんらかの繋がりがあったのかもしれません。
ちなみに、初音森神社は墨田区千歳の御鎮座ですが、元地とされる東日本橋二丁目は薬研堀不動院(矢の庫稲荷)のそばで、昭和23年に旧跡地に初音森神社摂社(儀式殿)が創建されています。


【写真 上(左)】 やげん堀七味の奉納サンプル
【写真 下(右)】 聖徳太子碑
不動院に戻って、本堂向かって右手にはやげん堀七味の奉納サンプル、手水舎、聖徳太子碑など。


【写真 上(左)】 講談発祥記念之碑
【写真 下(右)】 遍路大師尊像


【写真 上(左)】 順天堂発祥之地碑
【写真 下(右)】 収めの歳の市碑
本堂向かって左手には講談発祥記念之碑、遍路大師尊像、順天堂発祥之地碑、収めの歳の市碑、梵字不動尊、子寶地蔵尊と並びます。


【写真 上(左)】 梵字不動尊
【写真 下(右)】 子寶地蔵尊
梵字不動尊は、薬研堀不動院開創四百十五年を記念して梵字書家により不動三尊として揮毫、石刻されたものです。
中央は不動明王のお種子「カンマーン」、向かって右は不動明王の左脇侍である矜羯羅童子のお種子「コンカラ」、向かって左は不動明王の右脇侍である制多迦童子のお種子「セイタカ」と思われます。


【写真 上(左)】 納経所
【写真 下(右)】 御朱印見本
御朱印は納経所にて拝受しました。
お不動様の御朱印は御本尊、御府内霊場、関東三十六不動尊霊場の3種です。
べつに矢ノ庫稲荷神社の御朱印も授与されています。
また、オリジナルの御朱印帳も廉価にて頒布されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「大聖不動明王」「川崎大師別院」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の揮毫と御寶印(火焔宝珠)。
右上に「御府内第廿三番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 御本尊の御朱印 〕

〔 関東三十六不動尊霊場の御朱印 〕
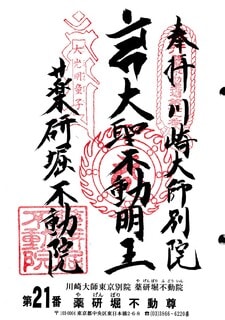
■ 第24番 高天山 大徳院 最勝寺
(さいしょうじ)
新宿区上落合3-4-12
真言宗豊山派
御本尊:釈迦牟尼如来
札所本尊:釈迦牟尼如来
他札所:
司元別当:中井御霊神社(新宿区中井)、東山藤稲荷神社(新宿区下落合)
授与所:庫裡
第24番札所は新宿区上落合に飛んで豊山派の最勝寺です。
上落合は府外で、『新編武蔵風土記稿』の範疇ですがごく簡単な記載しかありません。
これでは詳細のたどりようがないので、「猫の足あと」様記載の『新宿区の文化財』から抜粋引用させていただきます。
・創建時期や開基は不明だが、江戸時代には中井御霊神社、下落合東山藤稲荷神社の別当寺であった。
・最勝寺の塀際にある弘法大師の石標(御府内霊場道標/安政五年(1858年))には「弘法大師24番」「従是四谷北町和光院ニ11町」「従是新町多聞院ニ1町」とある。
・これは、内藤新宿の三光院にあったもので、明治初年に三光院が廃寺になった際、その大師堂が最勝寺に移された時、一緒に移ったと思われる。
『ルートガイド』には、開創・建立の詳細不明ながら鎌倉幕府第五代執権・北条時頼の開創と伝わり、中井御霊神社、下落合東山藤稲荷神社の別当であったこと、度々戦火や自然災害に遭ったことが記されています。
また、現地案内書にも「開創 鎌倉時代 北条時頼(西暦1250年代)」とあります。
かなりの大寺でありながら、戦火や災害により寺伝類を逸失してしまったようです。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には、第24番札所は内藤新宿の稲荷山 三光院とあり、同書の札所異動表によると、おそらく明治の初頭に三光院から四ッ谷寺町の愛染院に遷っています。
なので第24番札所は、三光院(内藤新宿)→愛染院(四ッ谷寺町)→最勝寺(上落合)の順に異動したとみられます。
まずは江戸期の札所である三光院から当たってみます。
三光院は明治初期に廃寺となっており、記録は多くありません。
『寺社書上』(国立国会図書館)には、内藤宿追分の稲荷社(現・花園神社)の項に「導師愛染院兼別当三光院」とあり、「別当所 ●御府内八十八ヶ所之内廿四番札所」とあります。
花園神社公式Webには「花園神社も真義真言宗豊山派愛染院の別院である三光院が合祀され、住職が別当(管理職)を兼ねる慣わしだったためであるといわれています。しかし、その三光院は明治元年(1868)3月に維新政府が祭政一致の方針に基づき神仏分離令を発布し、廃仏毀釈が進む中で花園神社と分離され、本尊は愛染院に納めて廃絶となりました。」とあります。
以上より、四谷(内藤新宿)追分の三光院が江戸期の御府内霊場第24番札所であったこと、三光院は内藤宿追分の稲荷社(現・花園神社)の別当であったことがわかります。
下記史料より、三光院の御本尊は現・花園神社の本地佛であった十一面観世音菩薩とみられ、こちらは明治初期の三光院廃絶を受けて本寺である四ッ谷愛染院に遷られています。
また、弘法大師御像も同時に遷られたとみられます。
第24番の札所本尊は十一面観世音菩薩・弘法大師であったので、第24番札所もおそらくこの際愛染院に異動しています。
しかし愛染院は御府内霊場第18番の札所なので、おそらく札所の重複がおこりました。
これを解消するために、上落合の最勝寺に第24番が異動したのでは。
愛染院、最勝寺とも新義豊山派なので、以前から両寺の交流があってこの異動が成立したものとも思われます。
最勝寺は落合エリアの有力寺院で、これは中井の御霊神社(落合村小名中井鎮守)、下落合の東山藤稲荷神社(東国源氏の氏神)の別当を司っていたことからも裏付けられます。


【写真 上(左)】 (中井)御霊神社
【写真 下(右)】 (中井)御霊神社の御朱印

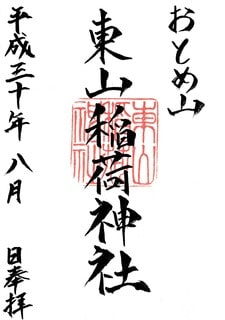
【写真 上(左)】 東山藤稲荷神社
【写真 下(右)】 東山藤稲荷神社の御朱印
明治に入ると”御府内”の意味合いがうすれ、御府内霊場札所も郊外に遷る例が増えてきますが最勝寺もその例かと思います。
せっかくなので、三光院が別当を司った花園神社の由緒・沿革を主に花園神社公式Webを参考として追ってみます。


【写真 上(左)】 (中井)花園神社
【写真 下(右)】 (中井)花園神社の御朱印
花園神社は、徳川家康公入府の天正十八年(1590年)より前に吉野山より勧請されたといい、江戸開府以前から新宿の総鎮守として重要な神社であったとみられています。
寛永年間(1624-1644年)までは現在より約250m南の現・伊勢丹付近にありましたが、
寛永年間、旗本・朝倉筑後守の下屋敷に囲い込まれてしまったため、幕府に訴えて現社地を拝領しました。
そこはもと尾張藩下屋敷の庭園で、花が咲き乱れていたため「花園稲荷神社」と号したと伝わります。
かつては四谷追分稲荷とも三光院稲荷とも呼ばれ、三光院が古くから別当を務めていたことがわかります。
明治に入って「稲荷神社」を号しましたが、江戸期から「花園社」として親しまれていたため、大正5年1月、東京府知事に改名を願い出て正式に「花園稲荷神社」となったそうです。
さらに昭和40年、末社の大鳥神社を本社に合祀した際に社号を「花園神社」に改めています。
花園稲荷社と弘法大師については、『寺社書上』に「弘法大師吉野(不明)吉野山●●●●花その稲荷と称す」とあり、吉野山からの稲荷神勧請にあたって弘法大師が関与されたことを示唆しています。
御神躰は正一位花園稲荷大明神。相殿に不動明王、愛染明王、随神二躰を奉安し、別当所(三光院)には稲荷大明神の本地佛として(十一面)観世音菩薩、弘法大師の木坐像も奉安して、神仏混淆色の強い境内であったとみられます。
現在の御祭神は倉稲魂命(花園神社)・日本武尊(大鳥神社)・受持神(雷電神社)。
旧社格は郷社。新宿の総鎮守として庶民の信仰篤く、とくに11月の「大酉祭 (新宿酉の市)」は多くの人出で賑わい浅草の鷲神社、府中の大國魂神社とともに「関東三大酉の市」に数えられます。
安永九年(1780年)と文化八年(1811年)には、大火で焼失した社殿を再建するため境内に劇場を設けて、見世物や演劇、踊りなどを興行して評判となりました。
場所柄、芸能関係者の信仰も篤いといい、とくに境内社の芸能浅間神社の敷地内には芸能人の奉納名が並びます。
もとより稲荷神信仰の色彩が強いですが、史料によっては創祀に弘法大師がかかわられたという伝承もあり、そのような流れもあって別当の三光院が御府内霊場札所となったのかもしれません。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
二十四番
内藤新宿上裏通り
稲荷山 三光院
四ッ谷愛染院末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 花園稲荷社 弘法大師
三光院→愛染院(札所異動表)
■ 『寺社書上 [46] 四谷寺社書上 五止』(国立国会図書館)
内藤宿追分
稲荷社
本社 文化十一年(1814年)再建
神躰 正一位花園稲荷大明神
弘法大師吉野(不明)吉野山●●●●花その稲荷と称す
相殿 不動明王
愛染明王
随神 二躰
奉 造営武蔵國豊嶋郡四谷追分稲荷社大明神本社幣殿拝殿
(略)
導師愛染院兼別当三光院 権大僧都法印栄住
境内末社
牛頭天王社 (千)葉稲荷社 福徳稲荷小祠 毘沙門天王 金比羅宮 第六天 疱瘡神 天満宮 稲荷大明神 秋葉宮 三峯
中興開山 寶盛? 本寺愛染院第二世 元和二?年(1616年)●●中興す
別当所 右後年焼失
観世音菩薩 右稲荷之本地佛
弘法大師 木坐像
●御府内八十八ヶ所之内廿四番札所
興教大師
歓喜天
文政十年(1827年)文月 三光院
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
最勝寺
同宗同末(新義真言宗多摩郡中野村宝仙寺末)西方山安養院と号す。本尊弥陀。
地蔵堂。

「三光院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
都営大江戸線「中井」駅徒歩2分、東京メトロ東西線「落合」駅徒歩4分、西武新宿線「中井」駅徒歩5分と交通至便で、山手通りに面して駐車場も完備しているのでアクセスは楽です。

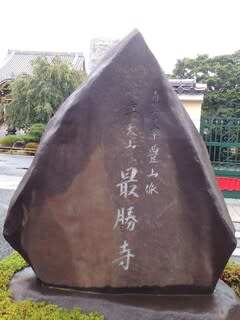
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
山内入口、山内とも広々としていて大寺のスケール感。往時は伽藍が建ち並んでいたのでは。

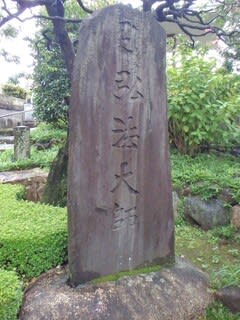
【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 弘法大師碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、正面に軒唐破風を構え、その下に二重の水引虹梁で両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えた整った意匠です。
向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 七福神
本堂前にはかわいい七福神像も。


【写真 上(左)】 本堂と堂宇
【写真 下(右)】 堂宇
本堂向かって左に宝形造本瓦葺の真新しい堂宇があります。
お砂踏み場があるので大師堂かとも思いましたが、御府内霊場の札所板は別の宝形造桟瓦葺のお堂に掲げられていたので、こちらが大師堂かと思われます。
ただし、こちらの堂前には聖観世音菩薩の立像が御前立的に御座され、観音堂の雰囲気もあります。


【写真 上(左)】 (おそらく)大師堂
【写真 下(右)】 札所板
二度も参拝し、当然堂宇についてもお伺いしているはずですが、なぜか記憶があいまいで申し訳ありませぬ。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「釋迦牟尼如来」「弘法大師」の揮毫と釈迦如来のお種子「バク」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第廿四番」の札所印。左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-8)
【 BGM 】
■ far on the water - Kalafina
■ Erato - 志方あきこ
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO + JP & ROMAJI SUB
※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。
■ 第21番 寶珠山 東福院
(とうふくいん)
公式Web
新宿区若葉2-2-6
新義真言宗
御本尊:大日如来
札所本尊:大日如来
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第21番、弁財天百社参り第34番
司元別当:
授与所:寺務所
第21番はふたたび四谷に飛びます。
公式Webによると、天正三年(1575年)に開基(開山)法印祐賢上人、外護者大沢孫右衛門尉によって麹町九丁目(横町)に創建。
寛永十一年(1634年)に現在地に移転といいます。
大沢氏は藤原北家持明院流とされ、本拠は遠州堀江城(浜松市西区)。
今川家家臣から徳川家に仕え、大沢基宿は最初の高家職を勤めたことで知られています。
高家は幕府の職制のひとつで、老中の管轄下で将軍の代参、勅使・院使の接待や饗応役の大名への儀典指南などの職務を果たしました。
ちなみに忠臣蔵の敵役、吉良上野介義央は高家で、赤穂事件の直前まで浅野内匠頭長矩に対して勅使饗応役の指南を行っていたといいます。
高家職に就けるのは「高家旗本」(「高家」の家格にある旗本)のみで、主に有力大名・守護系戦国大名の子孫や公家の分家など、「名門」の家柄で占められたといいます。
大沢氏は藤原北家持明院流という家格もあって、高家に任ぜられたのでは。
東福院は『御府内寺社備考』では「常陸国(筑波山)護持院末」とあり、もともとは筑波山知足院中禅寺(大御堂)の末寺だったようですが、いまは根来寺を祖廟(本山)とする新義真言宗寺院です。
なお、筑波山知足院中禅寺(大御堂)は、真言宗江戸触頭四箇寺および徳川将軍家祈祷寺と強い関係をもち、具体的には筑波知足院 → 江戸知足院 → 江戸護持院 → 音羽護国寺という流れがみられますが、これについては第87番護国寺でふれます。
(→『近世初期の知足院』坂本正仁氏/PDF』)
『御府内寺社備考』によると、御本尊は大日如来。
脇士に不動明王と毘沙門天を奉安し、両界八祖画像、弘法大師像を安ずる保守本流的な真言宗寺院であったようです。
江戸八十八ヶ所霊場も同番なので、開創当初からの札所とみられます。
弁天堂の御本尊辨財天(秘像)は弘法大師の御作と伝わり、お前立の辨財天座像も奉安、「出世辨天」として尊崇をあつめた弁財天百社参り第34番の札所本尊は、こちらの弁財天尊ではないでしょうか。
なお、『ルートガイド』によると地蔵堂の地蔵菩薩は「豆腐地蔵」と呼ばれ、由来の逸話を載せていますが、『寺社書上』『御府内寺社備考』にはこの縁起は記載されておらず、江戸後期以降の伝承かもしれません。
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.62』
四谷南寺町
本寺常陸国(筑波山)護持院末
阿祥山 宝壽寺 東福院
新義真言宗
起立慶長十六年辛亥(1611年)麹町九丁目横町
開山 法印祐賢
本尊 大日如来
脇士 不動尊 毘沙門天
両界八祖画像
弘法大師木像
弁天堂
本尊辨財天(秘像) 弘法大師作 前立辨財天座像
脇立 大黒天立像 毘沙門天
不動尊 十一面観音
地蔵堂
地蔵尊立像 疱瘡神 愛宕
稲荷社
神体無之 本地十一面観音立像 石地蔵尊
寺中 泉蔵院
■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)
阿祥山寶壽寺東福院は大塚護持院末の新義眞言宗で、四谷南寺町今の寺町にある。境内は古跡拝領地で千九百三十四坪餘、慶長十六年辛亥(1611年)麹町九丁目横町に起立し、寛永十一年甲戌(1634年)此地に転じた。開山法印祐賢の示寂年月は明かでない。府内八十八箇所廿一番の札所である。猶寺には辨財天木像涅槃画像其他を蔵していて、中にも辨財天は出世辨天と称して有名である。(略)
-------------------------


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 院号標
四谷寺町に立地し、寛永十一年(1634年)麹町九丁目横町から現在地に移転しているので、寛永年間(1624-1645年)家光公の治世に江戸城外堀工事のため四谷に移転させられた麹町の寺院のひとつとみられます。
第18番愛染院と東福院坂(天王坂)を挟んだほぼ対面にあります。

 【写真 上(左)】 根来寺の寺紋「三つ柏」
【写真 上(左)】 根来寺の寺紋「三つ柏」【写真 下(右)】 参道
東福院坂の途中に山内入口。
根来寺を祖廟(本山)とする新義真言宗寺院は、御府内霊場では3箇寺(当山、自性院(谷中)、加納院(谷中))。
門扉には新義真言宗総本山根来寺の寺紋「三つ柏」が掲げられています。


【写真 上(左)】 札所標
【写真 下(右)】 本堂
正面が近代建築の本堂。
参道右手に御府内霊場札所碑、子育?地蔵尊、聖観世音菩薩、地蔵堂と並びます。
地蔵堂は『ルートガイド』に載っているもので、堂内扁額には「豆腐地蔵尊」とありました。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 豆腐地蔵尊


【写真 上(左)】 本堂向拝
【写真 下(右)】 本堂扁額
本堂は寺務所を兼ねていて仏堂のイメージはうすいですが、正面に山号扁額が掲げられているので、こちらからの奉拝と思われます。
御朱印は寺務所にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印。
「豆腐地蔵」の印判も捺されています。
右上に「第二十一番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第22番 天谷山 龍福寺 南蔵院
(なんぞういん)
新宿区箪笥町42
真言宗豊山派
御本尊:千手観世音菩薩
札所本尊:千手観世音菩薩
他札所:江戸八十八ヶ所霊場第22番、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第27番、弁財天百社参り第40番
司元別当:
授与所:庫裡
御府内霊場には南蔵院と号する札所が練馬(第15番)、牛込(第22番)と高田(第29番)の3箇寺あり、それぞれ練馬南蔵院、牛込南蔵院、高田南蔵院と呼んで区別されます。
下記史料類と『ルートガイド』をもとに牛込南蔵院の縁起・由緒をたどってみます。
牛込南蔵院は、元和元年(1615年)、牛込城主の牛込勝重が正胤法印を請じて早稲田の地に吉祥山福正院と号して創建。
当初は弁財天二尊を上宮・下宮として祀っていたといいます。
延宝九年(1681年)、旧寺地が御用地として召上げられ、替地として現在地を拝領して移転し元号に改めました。
弁財天上宮は現在地に遷られ、下宮は弁天町の宗参寺(曹洞宗)にご遷座して奉祀といいます。
宗参寺も江戸三十三ヶ所弁財天霊場第26番、弁財天百社参り第41番の兼務札所ですから、こちらも代表的な弁財天霊場となっていたことがわかります。


【写真 上(左)】 宗参寺
【写真 下(右)】 宗参寺の御朱印
当山、宗参寺ともに牛込氏とのゆかりがふかい寺院です。
新宿区の新宿文化観光資源サイトでは宗参寺山内の牛込氏墓が紹介され、説明文には下記の内容が記されています。
・牛込氏は上野国勢多郡大胡(現・前橋市大胡町周辺)の領主・大胡氏の出で、15世紀末に武蔵国に進出して北条氏に従った。
・大永六年(1526年)には牛込に定住し、天文二十四年(1555年)北条氏康により牛込姓への改姓を認められ、牛込から日比谷あたりまで領有。
・その城館は現在の光照寺(袋町15番地)一帯の「牛込城跡」(新宿区登録史跡)に築かれ、「牛込家文書」は東京都指定有形文化財。
・天正十八年(1590年)の北条氏滅亡後は徳川氏に従い幕臣となった。
・宗参寺は天文十二年(1543年)に没した大胡重行(法名宗参)の墓所として子の勝行が創建した寺院で、以来牛込氏の菩提寺となっている。
また、Wikipediaには「徳川家康の江戸入城の後、館(牛込城)は廃止され、跡地に神田光照寺が移転してきたのは1645年のことであったとされる。」とあります。
『ルートガイド』によると、正胤法印は上総千葉一族とのこと。
たしかに千葉氏の通字は「胤」ですが、千葉氏は一族が多いので簡単には追い切れません。
『御府内寺社備考』をみると、南蔵寺は当初から弁財天とのゆかりがふかく、旧来は弁財天が御本尊であった可能性があります。
山内に宇賀神、十五童子立像も安置され、江戸三十三ヶ所弁財天霊場第27番、弁財天百社参り第40番のふたつの弁財天霊場の札所でもありました。
現在の南蔵院の御本尊および御府内霊場の札所本尊は千手観世音菩薩です。
ところが、不思議なことに『御府内寺社備考』には千手観世音菩薩にかかわる記載がありません。
弘法大師については、寺中薬王院に弘法大師木坐像を奉安しており、御府内霊場札所の要件を満たしています。
江戸八十八ヶ所霊場も同番なので、開創当初からの札所とみられます。
東京都公文書館によると、『御府内寺社備考』は文政九年(1826年)から3年程度で作成されました。
御府内霊場の開創は宝暦五年(1755年)頃とみられるので、『御府内寺社備考』は御府内霊場開創後の作成です。
なので、当初の南蔵院の御府内霊場札所本尊は、弁財天と弘法大師であった可能性もあります。
弁財天と千手観世音菩薩の尊格的なつながりはよくわかりませんが、日本三大弁天のひとつ竹生島宝厳寺の千手千眼観世音菩薩は、西国三十三所第30番の札所本尊で当山御本尊の弁天様と同じく60年に一度の御開扉です。
また、江ノ島の岩屋内には弁財天とともに千手観世音菩薩が祀られています。
栃木県の大谷寺(坂東観音霊場第19番)にも千手観音と弁財天にまつわる伝承が伝わります。
その昔、この地に毒蛇が棲みつき、毒蛇が吐き出す毒水の害で人々が苦しみ、毒蛇の住処は「地獄谷」と呼ばれて畏れられていました。
東国を巡錫中の弘法大師がこの話を聞かれると、秘法をもってこの毒蛇を退治されました。
大師が去られた後に人々が地獄谷を訪れると、高い岩山には千手観音が光り輝き、その脇侍として不動明王と毘沙門天が彫られており、これが大谷寺開山の縁起とされます。
大谷寺には弁天堂があり、こちらの弁財天には、弘法大師の秘法により心を入れ替えた毒蛇がお仕えしているそうです。(同山パンフ記載の縁起より抜粋)
以上から、弁財天と千手観世音菩薩はなんらかの関係があるとも考えられ、その縁から千手観世音菩薩が御本尊となられたのかもしれません。
(かなり牽強附会的なこの見方は、あくまでも筆者の憶測です。)
弘法大師とのゆかりは強く、聖天堂の本地佛・十一面観世音菩薩は弘法大師作、寺宝の獨鈷杵は弘法大師が唐より招来されたもの、般若心経も弘法大師御筆と記されています。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内寺社備考 P.35』
牛込御箪笥町
京都大佛智積院末
天谷山 竜福寺 南蔵院
当寺開闢之儀者元和の初年(1615年)下総國香取妙幢院正胤法印 武蔵國牛込之領主何某請ふより同國豊嶋郡早稲田の里●褐をとて●上宮下宮乃二宇を造立し辨財天二体を勧請し正胤法印上の宮を別当し吉祥山福正院といふ ●後第四世日胤代延宝九年(1681年)右地所御用地ニ付召上替地として南●之地所を拝領 仕以地名を蟇谷といへ(略)当所に称し天谷山南蔵院と改む。下の宮を●猶旧内地に安置●●弁天町●なり。
弁天木座像
十五童子木立像
唐●●●
右●宇賀神安置
薬師木座像
金毘羅木立像
獨鈷杵 弘法大師大唐より渡来開山正胤所持是什宝とす
般若心経 弘法大師筆
辨財天縁起 一巻
聖天堂
本尊観世音 黄金鋳像 秘佛
本地佛 十一面観世音 弘法大師作 木立像 水戸家御寄附宝暦六年(1756年)
歓喜天●尊● 一基
護摩堂
本尊不動明王木立像
阿弥陀堂
本尊阿弥陀如来 安阿弥作木坐像
稲荷社
寺中二軒
安養院 当時廃地
薬王院 本尊薬師如来 地蔵尊木立像 弘法大師木坐像
■ 『牛込区史』(国立国会図書館)
天谷山龍福寺南蔵院 智積院末
元和初年(1615年)、早稲田在辨財天上宮(今の辨天町でゝもあらう)の別當として、正胤法印開山、寺号を吉祥山福正院と云つたが、延寳九年箪笥町に移り、寺號を改めた。開山法印正胤寛永七年(1630年)二月廿九日遷化。(略)
本尊辨財天は弘法大師の作といひ伝ふ。
寺中 安養院
同上 薬王院
-------------------------


【写真 上(左)】 前面道路からの山内
【写真 下(右)】 山内入口
新宿区の牛込周辺はいまでも古い地名が住所として残っています。
箪笥町もそのひとつで、「箪笥」とは"武器"のことで、江戸時代に幕府の武器をつかさどる具足奉行・弓矢鑓奉行組同心の拝領屋敷があったことに由来するとのこと。(→東京都公文書館(江戸東京の町名)より)
かつては陸の孤島的だった牛込辺も、都営大江戸線の開通により俄然便利になりました。
南蔵院は、都営大江戸線「牛込神楽坂」駅直近にあります。
通りに面して門柱。門柱には院号の表札。
門柱右に「大聖歓喜天」の石標、門柱左には御府内霊場札所標。
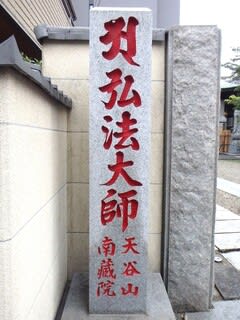

【写真 上(左)】 札所碑
【写真 下(右)】 山内
正面が本堂、向かって右手に聖天堂の伽藍配置です。
本堂はコンクリ造の近代建築ですが、切妻の妻の下に銅板葺の唐破風向拝を附設。
見た目の印象からすると入母屋造ないし切妻造の妻入りかもしれません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
唐破風鬼に経の巻獅子口。その上の妻部は格子仕上げで拝みに蕪(三つ花)懸魚と鬼板には真言宗の輪違い紋を掲げて本堂の風格を備えています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
がっしりとした向拝柱と見上げに院号扁額。
堂前向かって右の通常修行大師像が御座す場所には地蔵尊立像の安置なので、弘法大師御像は本堂内と思われます。


【写真 上(左)】 本堂(手前)と聖天堂(奥)
【写真 下(右)】 聖天堂
本堂向かって右手の堂宇は聖天堂。
おそらく入母屋造瓦葺の妻入りで、妻部に向拝を附設したかたちかと思います。
こちらは伝統的な寺院建築で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股などを備え、向拝上部に「歓喜天」の扁額を掲げています。
『御府内寺社備考』記載の「聖天堂」の系譜をひく堂宇かと思われます。
御朱印は本堂右手の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕

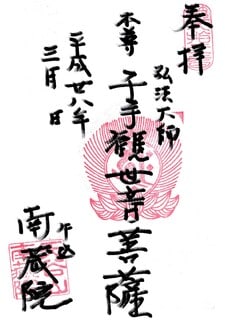
【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)
中央に「本尊 千手観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と千手観世音菩薩のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「第弐拾貳番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第23番 川崎大師 東京別院 薬研堀不動院
(やげんぼりふどういん)
公式Web
中央区東日本橋2-6-8
真言宗智山派
御本尊:不動明王
札所本尊:不動明王
他札所:関東三十六不動尊霊場第21番、御府内二十八不動霊場第9番
司元別当:
授与所:本堂内
第23番札所は川崎大師東京別院の薬研堀不動院です。
公式Webには、薬研堀不動院は、古くから目黒(不動尊)、目白(不動尊)と並び江戸三大不動として知られ、『江戸名所図会』をはじめ多くの文献に紹介されているとの由。
公式Webおよび『ルートガイド』『関東三十六不動霊場公式ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。
保延三年(1137年)、真言宗中興の祖・興教大師(覚鑁上人)は43歳の厄年を無事にすまされた御礼として一刀三礼で不動明王尊像を敬刻、紀州・根来寺に奉安されました。
天正十三年(1585年)、豊臣秀吉の根来攻めの兵火に遭った際、根来寺の大印僧都がこの尊像を守護して葛籠に納め、みずから背負われて東国へ下りました。
大印僧都は隅田川のほとりに有縁の霊地を定め、天正十九年(1591に)堂宇を建立されたのが薬研堀不動院のはじまりといいます。
こちらの不動尊の霊験まことにあらたかで、人々は「葛籠不動尊」と称し、目黒不動尊、目白不動尊とあわせて「江戸三大不動尊」と奉じて篤く尊崇したといいます。
とくに薬研堀不動尊の歳の市は、江戸の一年を締めくくる風物詩としてたいへん賑わったそうです。
(「歳の市」は12月14日の深川八幡に始まり、浅草観音、神田明神、愛宕神社、平河、湯島天神を巡って28日の薬研堀不動院で納めとなりました。)
山内の「収めの歳の市碑」(歳の市保存会)には、往年の歳の市の賑わいがつぎのとおり描写されています。
「戦前は何十軒もの羽子板屋が出店し 当時の千代田小学校の通りには『がさ市』が立ち 〆飾り 角松 竹 海老 こんぶ等が威勢よく売られ 身動き出来ぬ位の人出に下町情緒豊かな歳末風景がみられた」
また、当山は講談発祥の地という説があり、山内には「講談発祥之地碑」が建てられて、いまもご縁日の28日には講談が奉納されています。
明治二十五年(1892年)川崎大師平間寺の別院となり、都内有数の弘法大師霊場・不動尊霊場としていまに至っています。
江戸中期に変遷があったとみられ、「猫の足あと」様掲載の『中央区史』には「天保年中(1831-1845年)、本所弥勒寺中へ移され、維新後、有縁の旧地に移り咲いて仏殿を造営」とあります。
御府内霊場の開創は宝暦五年(1755年)頃とされるので、薬研堀不動院の弥勒寺中への移転(天保年中(1831-1845年))前です。
弥勒寺は御府内霊場開設当初からの札所(第50番)とみられるので、薬研堀不動院が当初からの札所(第23番)だとすると移転り際に弥勒寺の札所兼務問題がでてきます。
一方、江戸八十八ヶ所霊場の第23番は、市谷川田ヶ久保の稲荷山 薬王寺で、明治はじめの神仏分離で廃寺となっています。
『御府内八十八ケ所道しるべ』によると、御府内霊場第23番は明治のはじめまで市ヶ谷の薬王寺とあります。
よって薬研堀不動院は、明治二十五年(1892年)までに本所の弥勒寺内から旧地に移り咲き、御府内霊場第23番は川崎大師平間寺の別院となった薬研堀不動院に引き継がれたのではないでしょうか。
真言宗智山派の大本山・平間寺(川崎大師)の東京別院だけに、札所承継にあたり様々な動きがあったのかもしれませんが、詳細はわかりません。
薬王寺は大塚護國寺末だったので現在の真言宗豊山派系、平間寺は真言宗智山派の大本山ですから、札所の承継にやや疑問はありますが、なにぶん天保年中(1831-1845年)から明治初期までの薬研堀不動院の動静がほとんどたどれないので、下記史料類から薬王寺についてたどってみます。
薬王寺は室町時代、武将・太田道灌(1486年没)が築いた城の守護として京都稲荷山の神霊を勧請して市ヶ谷御門のあたりに草創と伝わります。
開山は法印澄覺(寛文三年(1663年)十月遷化)。
当初は愛染尊(明王)を安置し、愛染院と号していたようです。
元和の頃(1615-1624年)、稲荷社は当寺より二町ばかり北の方へ遷られたといいます、
中興開山は法印證覚(正(徳)三年(1713年)十月遷化)。
貞享年中(1684-1688年)に弘法大師御作の薬師如来像を奉安し、愛染院から薬王寺に号を改めたといいます。
『江戸名所図会』には「(稲荷社を)其後又此地へうつして当寺の護法神とせり。」とあるので、法印證覚の頃に稲荷社が当地に戻られて護法神となったのかもしれません。
史料類をみると、弘法大師御作の御本尊・薬師如来をはじめ、弘法大師の御自作像、(興)教大師御作の顧不動尊を奉安するなど、堂々たる新義真言宗寺院の内容を備え、弘法大師霊場札所としての資格も充分備えていたものとみられます。
桂昌院(5代将軍綱吉公の生母)、常憲院(徳川綱吉公)の帰依が篤かったらしく、仏像・仏画の寄附の記録が残ります。
このような由緒ある寺院が明治の神仏分離で廃寺となってしまったのは、いささか不思議な感じもしますが、いまは「市谷薬王寺町」の地名にその名を残すのみです。
なお、Wikipediaなど複数のWeb資料で「(薬王寺の)法灯は文京区大塚の護国寺に移された。」とあります。
護国寺は御府内霊場の第87番札所。
護国寺での重番を避けるとしても、豊山派系の寺院が承継すればよさそうですが、智山派大本山・平間寺(川崎大師)の東京別院が引き継いだ背景には、やはり特段の事情があったのかもしれません。
いずれにしても、平間寺(川崎大師)は東京別院を通じて御府内霊場の一画を占めることとなりました。

「薬研堀」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[1],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836]. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
※本所移転前の絵図と思われます。
-------------------------
【史料】
■ 『寺社書上 [38] 市谷寺社書上 三止』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.39』
市谷南寺町
大塚護國寺末
稲荷山 東光院 薬王寺
新義真言宗
開山 法印澄覺(寛文三年(1663年)十月遷化)
中興開山 法印證覚(正(徳)三年(癸巳)(1713年)十月遷化)
本尊 薬師如来 弘法大師作 石像秘佛
前立 薬師如来 木座像丈七寸
日光 月光 十二神将
・桂昌院様御寄附
正観世音 唐佛金之像 丈壱尺二寸
顧不動尊 (興)教大師作 木坐像丈九寸
幷両脇士
・桂昌院様ヨリ拝領
愛染尊 運慶作 木像 丈八寸
毘沙門天王 聖徳太子作 木像 丈三尺許
阿弥陀如来 行基菩薩作 木立像一尺二寸
地蔵尊
弘法大師御自作像 椅子座 丈ヶ壱尺壱寸
歓喜天 唐金鋳像秘佛
・寺寶
嵯峨帝御守本尊 佛眼佛母尊 天竺佛
・常憲院様ヨリ拝領
不動尊 一幅 弘法大師筆 二童子 倶利伽羅 後●院後持尊
涅槃像
(略)
稲荷社
稲荷大明神 神躰木立像
御本地佛 十一面観世音 鋳佛坐像
天神木坐像 辨才天木坐像
唐寺開闢之義 往古太田持資入道道灌 御城築●●為 城内乾●護 京都稲荷山●神霊を勧請し ●愛染尊を安置依●稲荷山愛染●と号し市ヶ谷御門之(略)貞享年中(1684-1688年)弘法大師彫刻之石像坐像●来安置と依て本院改号薬王寺とす
桂昌院様依●帰依薬師如来(略)寄附
■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)
稲荷山 薬王寺
東光院と号す。同所より西方の方、河田ヶ窪にあり。新義の真言宗にして、大塚の護國寺に属せり。
開山を法印澄覺と号く。
本尊薬師如来の像は、弘法大師、天台四明の洞の霊石を得て、彫刻し給ひし霊像なりといふ。貞享(1684-1688年)の初、須田氏某、当寺に安置なし奉るとなり。
当寺昔は愛染院と称したりといふ。
稲荷祠
境内にあり。相傳ふ。太田道灌(1486年没)の勧請にして、むかしは今の市ヶ谷御門の辺にありしとなり。元和の頃(1615-1624年)当寺より二町ばかり北の方へ遷し、其後又此地へうつして当寺の護法神とせり。

「薬王寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------


【写真 上(左)】 街路にはためく幟-1
【写真 下(右)】 同-2
都営浅草線「東日本橋」駅徒歩約3分、都営新宿線「馬喰横山」駅徒歩約5分という交通至便の札所です。
あたりは完璧なビル街で、その道路沿いにお不動様の幟が並び立つさまはなかなか絵になります。


【写真 上(左)】 改修後の現山内
【写真 下(右)】 本堂
ビルに囲まれた一画に急な階段と、その上に重層八角堂的なお堂。
参道階段脇には幟がはためき、不動尊霊場の趣きがあります。
こちらは数年前にリニューアルされ、手前に数台分の駐車場ができました。
本堂内にあった納経所は、駐車場前に移されて全体に山内はすっきりとしています。


【写真 上(左)】 参道階段
【写真 下(右)】 向拝
階段をのぼった正面が向拝で五色幕が張り巡らされて華やかです。
「不動尊」の提灯のおくに「薬研堀不動院」の扁額。
以前は本堂内でお参りできましたが、現在は不明です。
正面お厨子のなかにお不動さまと向かって右に観世音菩薩像。
左手の尊像は金剛界大日如来でしょうか。
その両脇には弘法大師像と興教大師像という、真言宗寺院らしい堂内です。

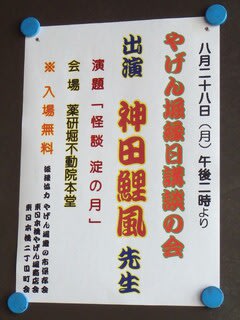
【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 講談の会の案内
公式Webで「不動院の鎮守」として紹介されている矢ノ庫稲荷神社は、「東日本橋」駅寄りの薬研堀不動院信徒会館のよこの角地に御鎮座で、薬研堀不動院納経所で御朱印を拝受できます。

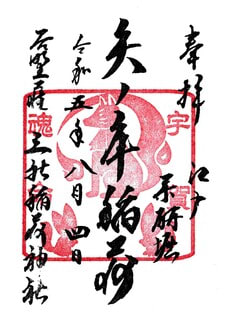
【写真 上(左)】 矢の庫稲荷
【写真 下(右)】 矢の庫稲荷の御朱印
境内の縁起書によると、かつて当地に隣接する日本橋一丁目あたりは谷野と呼ばれ、正保二年(1645年)幕府が米蔵を建て谷野蔵矢之倉と称されました。
米蔵の庭中に御蔵の鎮神として三社を合殿し三社稲荷神社を祀りました。
中央は谷野蔵稲荷、左に福富稲荷、右には新左衛門稲荷で、元禄十一年(1698年)に御蔵を鉄砲洲に移転した際に三社稲荷は一緒に御遷座されました。
御蔵跡周辺の人々は三社稲荷の名を惜しんで、新左衛門稲荷と福富稲荷を初音森神社に合祀、谷野蔵稲荷は変遷を経て現在地に御鎮座となり、社号も矢の庫稲荷と改められました。
経緯は明らかでないですが、薬研堀不動院公式Webには「不動院の鎮守」として矢の庫稲荷が紹介されています。
上記のとおり、旧第23番札所の稲荷山 薬王寺には太田道灌ゆかりの稲荷社が祀られていました。
三社稲荷のうち新左衛門稲荷と福富稲荷が合祀された初音森神社も太田道灌ゆかりの神社で、三社稲荷神社・太田道灌を介してなんらかの繋がりがあったのかもしれません。
ちなみに、初音森神社は墨田区千歳の御鎮座ですが、元地とされる東日本橋二丁目は薬研堀不動院(矢の庫稲荷)のそばで、昭和23年に旧跡地に初音森神社摂社(儀式殿)が創建されています。


【写真 上(左)】 やげん堀七味の奉納サンプル
【写真 下(右)】 聖徳太子碑
不動院に戻って、本堂向かって右手にはやげん堀七味の奉納サンプル、手水舎、聖徳太子碑など。


【写真 上(左)】 講談発祥記念之碑
【写真 下(右)】 遍路大師尊像


【写真 上(左)】 順天堂発祥之地碑
【写真 下(右)】 収めの歳の市碑
本堂向かって左手には講談発祥記念之碑、遍路大師尊像、順天堂発祥之地碑、収めの歳の市碑、梵字不動尊、子寶地蔵尊と並びます。


【写真 上(左)】 梵字不動尊
【写真 下(右)】 子寶地蔵尊
梵字不動尊は、薬研堀不動院開創四百十五年を記念して梵字書家により不動三尊として揮毫、石刻されたものです。
中央は不動明王のお種子「カンマーン」、向かって右は不動明王の左脇侍である矜羯羅童子のお種子「コンカラ」、向かって左は不動明王の右脇侍である制多迦童子のお種子「セイタカ」と思われます。


【写真 上(左)】 納経所
【写真 下(右)】 御朱印見本
御朱印は納経所にて拝受しました。
お不動様の御朱印は御本尊、御府内霊場、関東三十六不動尊霊場の3種です。
べつに矢ノ庫稲荷神社の御朱印も授与されています。
また、オリジナルの御朱印帳も廉価にて頒布されています。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「大聖不動明王」「川崎大師別院」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の揮毫と御寶印(火焔宝珠)。
右上に「御府内第廿三番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。
〔 御本尊の御朱印 〕

〔 関東三十六不動尊霊場の御朱印 〕
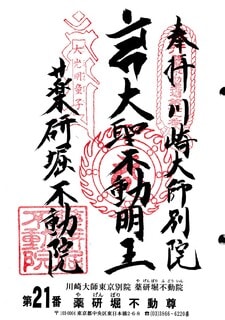
■ 第24番 高天山 大徳院 最勝寺
(さいしょうじ)
新宿区上落合3-4-12
真言宗豊山派
御本尊:釈迦牟尼如来
札所本尊:釈迦牟尼如来
他札所:
司元別当:中井御霊神社(新宿区中井)、東山藤稲荷神社(新宿区下落合)
授与所:庫裡
第24番札所は新宿区上落合に飛んで豊山派の最勝寺です。
上落合は府外で、『新編武蔵風土記稿』の範疇ですがごく簡単な記載しかありません。
これでは詳細のたどりようがないので、「猫の足あと」様記載の『新宿区の文化財』から抜粋引用させていただきます。
・創建時期や開基は不明だが、江戸時代には中井御霊神社、下落合東山藤稲荷神社の別当寺であった。
・最勝寺の塀際にある弘法大師の石標(御府内霊場道標/安政五年(1858年))には「弘法大師24番」「従是四谷北町和光院ニ11町」「従是新町多聞院ニ1町」とある。
・これは、内藤新宿の三光院にあったもので、明治初年に三光院が廃寺になった際、その大師堂が最勝寺に移された時、一緒に移ったと思われる。
『ルートガイド』には、開創・建立の詳細不明ながら鎌倉幕府第五代執権・北条時頼の開創と伝わり、中井御霊神社、下落合東山藤稲荷神社の別当であったこと、度々戦火や自然災害に遭ったことが記されています。
また、現地案内書にも「開創 鎌倉時代 北条時頼(西暦1250年代)」とあります。
かなりの大寺でありながら、戦火や災害により寺伝類を逸失してしまったようです。
『御府内八十八ケ所道しるべ』には、第24番札所は内藤新宿の稲荷山 三光院とあり、同書の札所異動表によると、おそらく明治の初頭に三光院から四ッ谷寺町の愛染院に遷っています。
なので第24番札所は、三光院(内藤新宿)→愛染院(四ッ谷寺町)→最勝寺(上落合)の順に異動したとみられます。
まずは江戸期の札所である三光院から当たってみます。
三光院は明治初期に廃寺となっており、記録は多くありません。
『寺社書上』(国立国会図書館)には、内藤宿追分の稲荷社(現・花園神社)の項に「導師愛染院兼別当三光院」とあり、「別当所 ●御府内八十八ヶ所之内廿四番札所」とあります。
花園神社公式Webには「花園神社も真義真言宗豊山派愛染院の別院である三光院が合祀され、住職が別当(管理職)を兼ねる慣わしだったためであるといわれています。しかし、その三光院は明治元年(1868)3月に維新政府が祭政一致の方針に基づき神仏分離令を発布し、廃仏毀釈が進む中で花園神社と分離され、本尊は愛染院に納めて廃絶となりました。」とあります。
以上より、四谷(内藤新宿)追分の三光院が江戸期の御府内霊場第24番札所であったこと、三光院は内藤宿追分の稲荷社(現・花園神社)の別当であったことがわかります。
下記史料より、三光院の御本尊は現・花園神社の本地佛であった十一面観世音菩薩とみられ、こちらは明治初期の三光院廃絶を受けて本寺である四ッ谷愛染院に遷られています。
また、弘法大師御像も同時に遷られたとみられます。
第24番の札所本尊は十一面観世音菩薩・弘法大師であったので、第24番札所もおそらくこの際愛染院に異動しています。
しかし愛染院は御府内霊場第18番の札所なので、おそらく札所の重複がおこりました。
これを解消するために、上落合の最勝寺に第24番が異動したのでは。
愛染院、最勝寺とも新義豊山派なので、以前から両寺の交流があってこの異動が成立したものとも思われます。
最勝寺は落合エリアの有力寺院で、これは中井の御霊神社(落合村小名中井鎮守)、下落合の東山藤稲荷神社(東国源氏の氏神)の別当を司っていたことからも裏付けられます。


【写真 上(左)】 (中井)御霊神社
【写真 下(右)】 (中井)御霊神社の御朱印

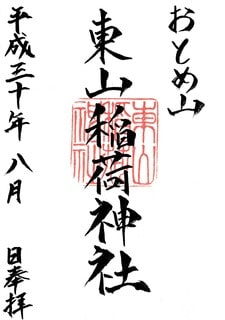
【写真 上(左)】 東山藤稲荷神社
【写真 下(右)】 東山藤稲荷神社の御朱印
明治に入ると”御府内”の意味合いがうすれ、御府内霊場札所も郊外に遷る例が増えてきますが最勝寺もその例かと思います。
せっかくなので、三光院が別当を司った花園神社の由緒・沿革を主に花園神社公式Webを参考として追ってみます。


【写真 上(左)】 (中井)花園神社
【写真 下(右)】 (中井)花園神社の御朱印
花園神社は、徳川家康公入府の天正十八年(1590年)より前に吉野山より勧請されたといい、江戸開府以前から新宿の総鎮守として重要な神社であったとみられています。
寛永年間(1624-1644年)までは現在より約250m南の現・伊勢丹付近にありましたが、
寛永年間、旗本・朝倉筑後守の下屋敷に囲い込まれてしまったため、幕府に訴えて現社地を拝領しました。
そこはもと尾張藩下屋敷の庭園で、花が咲き乱れていたため「花園稲荷神社」と号したと伝わります。
かつては四谷追分稲荷とも三光院稲荷とも呼ばれ、三光院が古くから別当を務めていたことがわかります。
明治に入って「稲荷神社」を号しましたが、江戸期から「花園社」として親しまれていたため、大正5年1月、東京府知事に改名を願い出て正式に「花園稲荷神社」となったそうです。
さらに昭和40年、末社の大鳥神社を本社に合祀した際に社号を「花園神社」に改めています。
花園稲荷社と弘法大師については、『寺社書上』に「弘法大師吉野(不明)吉野山●●●●花その稲荷と称す」とあり、吉野山からの稲荷神勧請にあたって弘法大師が関与されたことを示唆しています。
御神躰は正一位花園稲荷大明神。相殿に不動明王、愛染明王、随神二躰を奉安し、別当所(三光院)には稲荷大明神の本地佛として(十一面)観世音菩薩、弘法大師の木坐像も奉安して、神仏混淆色の強い境内であったとみられます。
現在の御祭神は倉稲魂命(花園神社)・日本武尊(大鳥神社)・受持神(雷電神社)。
旧社格は郷社。新宿の総鎮守として庶民の信仰篤く、とくに11月の「大酉祭 (新宿酉の市)」は多くの人出で賑わい浅草の鷲神社、府中の大國魂神社とともに「関東三大酉の市」に数えられます。
安永九年(1780年)と文化八年(1811年)には、大火で焼失した社殿を再建するため境内に劇場を設けて、見世物や演劇、踊りなどを興行して評判となりました。
場所柄、芸能関係者の信仰も篤いといい、とくに境内社の芸能浅間神社の敷地内には芸能人の奉納名が並びます。
もとより稲荷神信仰の色彩が強いですが、史料によっては創祀に弘法大師がかかわられたという伝承もあり、そのような流れもあって別当の三光院が御府内霊場札所となったのかもしれません。
-------------------------
【史料】
■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)
二十四番
内藤新宿上裏通り
稲荷山 三光院
四ッ谷愛染院末 新義
本尊:十一面観世音菩薩 花園稲荷社 弘法大師
三光院→愛染院(札所異動表)
■ 『寺社書上 [46] 四谷寺社書上 五止』(国立国会図書館)
内藤宿追分
稲荷社
本社 文化十一年(1814年)再建
神躰 正一位花園稲荷大明神
弘法大師吉野(不明)吉野山●●●●花その稲荷と称す
相殿 不動明王
愛染明王
随神 二躰
奉 造営武蔵國豊嶋郡四谷追分稲荷社大明神本社幣殿拝殿
(略)
導師愛染院兼別当三光院 権大僧都法印栄住
境内末社
牛頭天王社 (千)葉稲荷社 福徳稲荷小祠 毘沙門天王 金比羅宮 第六天 疱瘡神 天満宮 稲荷大明神 秋葉宮 三峯
中興開山 寶盛? 本寺愛染院第二世 元和二?年(1616年)●●中興す
別当所 右後年焼失
観世音菩薩 右稲荷之本地佛
弘法大師 木坐像
●御府内八十八ヶ所之内廿四番札所
興教大師
歓喜天
文政十年(1827年)文月 三光院
■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)
最勝寺
同宗同末(新義真言宗多摩郡中野村宝仙寺末)西方山安養院と号す。本尊弥陀。
地蔵堂。

「三光院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
都営大江戸線「中井」駅徒歩2分、東京メトロ東西線「落合」駅徒歩4分、西武新宿線「中井」駅徒歩5分と交通至便で、山手通りに面して駐車場も完備しているのでアクセスは楽です。

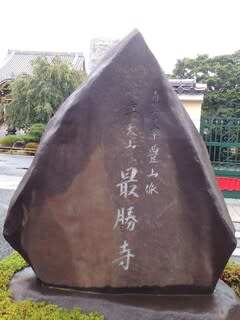
【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
山内入口、山内とも広々としていて大寺のスケール感。往時は伽藍が建ち並んでいたのでは。

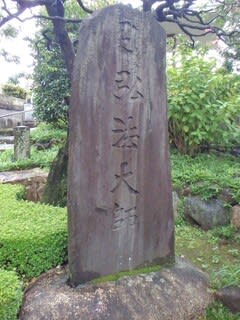
【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 弘法大師碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、正面に軒唐破風を構え、その下に二重の水引虹梁で両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えた整った意匠です。
向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 七福神
本堂前にはかわいい七福神像も。


【写真 上(左)】 本堂と堂宇
【写真 下(右)】 堂宇
本堂向かって左に宝形造本瓦葺の真新しい堂宇があります。
お砂踏み場があるので大師堂かとも思いましたが、御府内霊場の札所板は別の宝形造桟瓦葺のお堂に掲げられていたので、こちらが大師堂かと思われます。
ただし、こちらの堂前には聖観世音菩薩の立像が御前立的に御座され、観音堂の雰囲気もあります。


【写真 上(左)】 (おそらく)大師堂
【写真 下(右)】 札所板
二度も参拝し、当然堂宇についてもお伺いしているはずですが、なぜか記憶があいまいで申し訳ありませぬ。
御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。
〔 御府内霊場の御朱印 〕


【写真 上(左)】 専用集印帳
【写真 下(右)】 汎用御朱印帳
中央に「釋迦牟尼如来」「弘法大師」の揮毫と釈迦如来のお種子「バク」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
右上に「御府内第廿四番」の札所印。左下に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
以下、つづきます。
(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-8)
【 BGM 】
■ far on the water - Kalafina
■ Erato - 志方あきこ
■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO + JP & ROMAJI SUB
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




