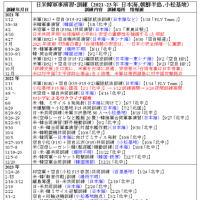橋下徹=「維新の会」が登場し、この党(運動)がファシズムか否かが問題になっている。そのために、ドイツナチズム(ヒトラー)の登場過程の検証が必要である。ヨアヒム・フェストの『ヒトラー』(河出書房新社1975年刊)上巻を紹介する。40年前の読書ノートだが、それほど的外れでもないだろう。
『ヒトラー(上巻)』(ヨアヒム・フェスト著)
<反ユダヤ主義>
オーストリア=ハンガリー帝国における資本主義の成長は古い封建的・農奴的生産関係を根底から破壊していった。とりわけ市民層は進歩によって、都市の成長によって、技術・大量生産、経済的集中によってひどく脅かされはじめていた。この小市民層の不安・動揺はその現実からの逃避を必要とし、民族主義的、人種論的な防衛イデオロギー・排外主義イデオロギーの中に見いだした。(オーストリア=ハンガリー帝国はロシアからギリシャまで含む10もの民族を内包する多民族国家だった)
1870年代に起きた経済危機は圧倒的少数民族であるユダヤ人に対する排外主義的・差別主義的感情を爆発せしめた。ユダヤ人はあらゆる地方で追い立てられた。ハプスブルク王家の首都ウィーンでの融和的・妥協的な影響によって、東方からユダヤ人が流れこんできた。1857~1910年にいたる50年間にウィーンのユダヤ人の占める割合は2%から8.5%にまでのぼり、近くのある町では3分の1を占めるところもあった。だがここでも安全ではなかった。
このような歴史的事情からユダヤ人はやむなく商業活動へと追いやられ、さらにアカデミックな領域へ、ジャーナリズムへ、銀行へ、工業の相当部分を占めるようになった。このことがさらに反ユダヤ主義を挑発し、これまでの人種的・宗教的な差別から、経済関係での憎悪を生み出し、さらに排外主義デマゴーグの手によって、政治的・社会的とりわけ社会ダーウィニズムによる生物学的な憎悪へとかきたてられている。(この辺の書き方には、著者自身の反ユダヤ主義的臭いがする)
当時の排外主義イデオローグとしてはゲオルグ・リッター・フォン・シェーネラー氏とヨカール・ルエガー博士であり、社会ダーウィニズムをもって反ユダヤ主義を構築した。シェーネラーは「宗教はどうでもいい、不潔は血の中にある」と絶叫した。
社会ダーウィニズムは19世紀後半の初めのうちは左翼の啓蒙の一要因だったが、やがて右旋回をはじめてデモクラシー、ヒューマニズムのイデーが自然に反していると言って、デモクラシーやヒューマニズム、自由主義、議会主義、平等の理念、国際主義否定の立証のために用いられた。
さらにチェンバレンはヨーロッパの歴史を人種闘争の歴史と解釈し、ローマ帝国の没落を「血の混合」に発する歴史的退廃過程のモデルケースと考え、オーストリア=ハンガリー帝国も同じ道をたどるのではないかとのデマゴギーを展開した。
この反ユダヤ主義はドイツにおいてのみ開花したのではなく、フランスにおいてもロシアにおいても、すなわち全ヨーロッパにおいて展開された。ヒトラーはこのような思想が蔓延する中で、南ドイツに生まれ、成長し、青年期はウィーンで過ごした。ヒトラー自身は貧困を単なる欠乏としてではなく、それよりもむしろ社会的地位低下の屈辱的な証拠と考える典型的な小ブル出身であった。ヒトラーの読むものと言えば、低俗な反ユダヤ主義の新聞であり、雑誌であった。ウィーンからミュンヘンに移ったヒトラーが好んで読んでいた新聞は『ドイツ民族新聞』であった。このようにしてヒトラーは反ユダヤ主義のゴリゴリになり、「ゲルマンの優位はユダヤ人を絶滅するところにある」と絶叫した。ちなみに、ミュンヘン時代のヒトラーの手紙には「今日のユダヤ人がドイツ国民にもたらす危険」について書かれている。ヒトラーは当時のドイツ社会の一般的な「ひとり」であった。
<ナチスの登場>
ナチス党の前身であるドイツ労働者党は1919年1月5日、ミュンヘンで、アントン・ドレクスラーによって25名を結集して結成された。「ドイツ人によって指導される社会主義の組織」と謳い、サロン的で閉鎖的な集団に過ぎなかった。1919年秋、ヒトラーが入党し、頭角を現した。ヒトラーの主張のもとに、これまでの閉鎖性を打ち破り、公開大衆集会を開催し、ヒトラーは2人目に登場して30分間アジり、大成功した。大衆へのアピールを有効にするために綱領を作成した。反資本主義・反マルクス主義・反議会主義・反ユダヤ主義を明確にし、第1次世界大戦の敗戦とその結果としてのワイマール共和国を断固として否定した。
2回目の集会は2000名を結集し、大成功をおさめた直後、国家社会主義ドイツ労働者党(NSDAP)に改称した。党旗は真っ赤で左翼の伝統を奪い、プロパガンダの方法も左翼から奪い、党名も社会主義を僭称し、綱領・スローガンも左翼と見まがうばかりのものにした。だが、軍・政府から公然と支持されており(バイエルン州首相は州議会の席上ヒトラーを賞賛した)、SA(突撃隊)やナチス官僚を維持するために必要な財政はブルジョアジーに頼っていた。ミュンヘンのブルジョアジーは戦後革命の嵐の中で、ドイツ共産党を日常的に殲滅しているナチスにみずからの未来をかけていた。
ヒトラーはナチスの前進に気をよくしていて、一揆を試みるが、もはや戦後革命の嵐も収まりかけ、安定への兆しを見せていたために、ブルジョアジーに見放されて失敗した。ヒトラーは裁判により5年の刑を言い渡され、1年後の1924年12月20日に釈放された。
ヒトラーは南ドイツの党再建に取りかかると同時に北ドイツで運動しているシュトラッサー兄弟、ゲッペルスと合流した。シュトラッサーのグループはヒトラーよりもはるかに社会主義的であった。シュトラッサーは「フランス軍国主義に対抗し、イギリス帝国主義に対抗し、ウオール街の資本主義に反対して、ソ連との同盟」を唱えていた。ゲッペルスは「我々は社会主義者である。我々は経済的弱者を搾取し、不当な報酬を生み出す今日の資本主義経済秩序に敵対する。我々はその不倶戴天の敵である。我々はいかなる事情があろうとも、この体制を撲滅する決意である。あのプチブルのアドルフ・ヒトラーがNSDAPから追放されるべきだ」と提案している。
旧諸侯の財政について、ヒトラーは戦術的配慮から旧諸侯や有産階層の側にたたざるを得ないだろうと考え、シュトラッサー、ゲッペルスは左翼諸政党と同じように旧諸侯の財産無償没収に賛成した。この対立の中で、ヒトラーは陰謀的に多数派になるように工作した上で、バンベルグ指導者会議を開き、シュトラッサーグループを粉砕した。シュトラッサーグループはやむなく独自で作成し配布していた社会主義的綱領案を回収した。これを機に弟のオットー・シュトラッサーが脱落した。
<ナチスの議会進出>
1928年 ナチスは初の国政選挙で12議席、1930年9月の選挙で107議席(第2党)を獲得したが、ドイツ共産党はまったく危機感を持たず、「9月選挙での唯一の勝利は共産党である」と有頂天になっていた。1932年7月31日、選挙でついにナチスは第1党(230議席)になる。だがこの選挙の内容はナチスの左翼への勝利を意味してはいなかった。すなわち中間政党とブルジョア政党に打撃を与えたが、中央党・社民党・共産党に食い込むことができなかった。ナチスはこれ以上伸びていくためには、プロレタリアートに手を伸ばすしかなかった。
国会で、グレゴール・シュトラッサー、ゴットフリート・フェーダーは「銀行と株式市場の頭目」の資産剥奪を求めていたが、ナチス党の財政危機克服のために大企業との関係をよくしなければならず、その要求を下ろさせた。ナチスはまさにジレンマの谷間にあった。
1932年11月6日、選挙の最中にベルリンで交通企業ストが起こった。これは共産主義者により、労働組合の決議に反して引き起こされたものだが、ナチス党員は直ちにこれに参加した。共産党とSA(突撃隊)は一緒になって5日にわたり、レールをはがし、ピケットを張った。この時点で、ナチスにとって他の選択は困難であった。もっとも、このためブルジョアジーをひどく怒らせ、ナチスの財政はまったく干上がってしまった。選挙は200万票と34の議席を失った。
<ナチス政権獲得>
だが政局は混沌としていた。①ボナパルチズム支配を構築しようとしているヒンデンブルク、②あくまでも形式民主主義にこだわる社民党、③左右からの破壊者、ドイツ共産党とナチス。結局権力はヒトラーの手に握られた(1933年、ヒトラーを首相に任命)。ブルジョアジーが決断したのである。ひとつはよりいっそう伸びつつある共産党の威力、もうひとつはナチス党内社会主義派のグレゴール・シュトラッサーの脱落によって、ほっと胸をなでおろしたのである。
なんといってもナチス党の弱点は「社会主義」を提起しながら、それを裏切らねばならず、ブルジョアジーに色目を使いながらプロレタリアートの支持を取り付けなければならないという二律背反にある。
ドイツ共産党がナチスへの攻撃をどのように展開していたのか。一番重要なことはイデオロギーの段階できちんとナチスをとらえきれなかったことにあろう。さらにナチスを反革命として位置づけたとき、猛然と内戦に突入しなければならなかったのである。しかし、ナチズムの成長以後、共産党とナチスの激突は数え切れないくらいあるが、これに勝利することができなかった。
『ヒトラー(上巻)』(ヨアヒム・フェスト著)
<反ユダヤ主義>
オーストリア=ハンガリー帝国における資本主義の成長は古い封建的・農奴的生産関係を根底から破壊していった。とりわけ市民層は進歩によって、都市の成長によって、技術・大量生産、経済的集中によってひどく脅かされはじめていた。この小市民層の不安・動揺はその現実からの逃避を必要とし、民族主義的、人種論的な防衛イデオロギー・排外主義イデオロギーの中に見いだした。(オーストリア=ハンガリー帝国はロシアからギリシャまで含む10もの民族を内包する多民族国家だった)
1870年代に起きた経済危機は圧倒的少数民族であるユダヤ人に対する排外主義的・差別主義的感情を爆発せしめた。ユダヤ人はあらゆる地方で追い立てられた。ハプスブルク王家の首都ウィーンでの融和的・妥協的な影響によって、東方からユダヤ人が流れこんできた。1857~1910年にいたる50年間にウィーンのユダヤ人の占める割合は2%から8.5%にまでのぼり、近くのある町では3分の1を占めるところもあった。だがここでも安全ではなかった。
このような歴史的事情からユダヤ人はやむなく商業活動へと追いやられ、さらにアカデミックな領域へ、ジャーナリズムへ、銀行へ、工業の相当部分を占めるようになった。このことがさらに反ユダヤ主義を挑発し、これまでの人種的・宗教的な差別から、経済関係での憎悪を生み出し、さらに排外主義デマゴーグの手によって、政治的・社会的とりわけ社会ダーウィニズムによる生物学的な憎悪へとかきたてられている。(この辺の書き方には、著者自身の反ユダヤ主義的臭いがする)
当時の排外主義イデオローグとしてはゲオルグ・リッター・フォン・シェーネラー氏とヨカール・ルエガー博士であり、社会ダーウィニズムをもって反ユダヤ主義を構築した。シェーネラーは「宗教はどうでもいい、不潔は血の中にある」と絶叫した。
社会ダーウィニズムは19世紀後半の初めのうちは左翼の啓蒙の一要因だったが、やがて右旋回をはじめてデモクラシー、ヒューマニズムのイデーが自然に反していると言って、デモクラシーやヒューマニズム、自由主義、議会主義、平等の理念、国際主義否定の立証のために用いられた。
さらにチェンバレンはヨーロッパの歴史を人種闘争の歴史と解釈し、ローマ帝国の没落を「血の混合」に発する歴史的退廃過程のモデルケースと考え、オーストリア=ハンガリー帝国も同じ道をたどるのではないかとのデマゴギーを展開した。
この反ユダヤ主義はドイツにおいてのみ開花したのではなく、フランスにおいてもロシアにおいても、すなわち全ヨーロッパにおいて展開された。ヒトラーはこのような思想が蔓延する中で、南ドイツに生まれ、成長し、青年期はウィーンで過ごした。ヒトラー自身は貧困を単なる欠乏としてではなく、それよりもむしろ社会的地位低下の屈辱的な証拠と考える典型的な小ブル出身であった。ヒトラーの読むものと言えば、低俗な反ユダヤ主義の新聞であり、雑誌であった。ウィーンからミュンヘンに移ったヒトラーが好んで読んでいた新聞は『ドイツ民族新聞』であった。このようにしてヒトラーは反ユダヤ主義のゴリゴリになり、「ゲルマンの優位はユダヤ人を絶滅するところにある」と絶叫した。ちなみに、ミュンヘン時代のヒトラーの手紙には「今日のユダヤ人がドイツ国民にもたらす危険」について書かれている。ヒトラーは当時のドイツ社会の一般的な「ひとり」であった。
<ナチスの登場>
ナチス党の前身であるドイツ労働者党は1919年1月5日、ミュンヘンで、アントン・ドレクスラーによって25名を結集して結成された。「ドイツ人によって指導される社会主義の組織」と謳い、サロン的で閉鎖的な集団に過ぎなかった。1919年秋、ヒトラーが入党し、頭角を現した。ヒトラーの主張のもとに、これまでの閉鎖性を打ち破り、公開大衆集会を開催し、ヒトラーは2人目に登場して30分間アジり、大成功した。大衆へのアピールを有効にするために綱領を作成した。反資本主義・反マルクス主義・反議会主義・反ユダヤ主義を明確にし、第1次世界大戦の敗戦とその結果としてのワイマール共和国を断固として否定した。
2回目の集会は2000名を結集し、大成功をおさめた直後、国家社会主義ドイツ労働者党(NSDAP)に改称した。党旗は真っ赤で左翼の伝統を奪い、プロパガンダの方法も左翼から奪い、党名も社会主義を僭称し、綱領・スローガンも左翼と見まがうばかりのものにした。だが、軍・政府から公然と支持されており(バイエルン州首相は州議会の席上ヒトラーを賞賛した)、SA(突撃隊)やナチス官僚を維持するために必要な財政はブルジョアジーに頼っていた。ミュンヘンのブルジョアジーは戦後革命の嵐の中で、ドイツ共産党を日常的に殲滅しているナチスにみずからの未来をかけていた。
ヒトラーはナチスの前進に気をよくしていて、一揆を試みるが、もはや戦後革命の嵐も収まりかけ、安定への兆しを見せていたために、ブルジョアジーに見放されて失敗した。ヒトラーは裁判により5年の刑を言い渡され、1年後の1924年12月20日に釈放された。
ヒトラーは南ドイツの党再建に取りかかると同時に北ドイツで運動しているシュトラッサー兄弟、ゲッペルスと合流した。シュトラッサーのグループはヒトラーよりもはるかに社会主義的であった。シュトラッサーは「フランス軍国主義に対抗し、イギリス帝国主義に対抗し、ウオール街の資本主義に反対して、ソ連との同盟」を唱えていた。ゲッペルスは「我々は社会主義者である。我々は経済的弱者を搾取し、不当な報酬を生み出す今日の資本主義経済秩序に敵対する。我々はその不倶戴天の敵である。我々はいかなる事情があろうとも、この体制を撲滅する決意である。あのプチブルのアドルフ・ヒトラーがNSDAPから追放されるべきだ」と提案している。
旧諸侯の財政について、ヒトラーは戦術的配慮から旧諸侯や有産階層の側にたたざるを得ないだろうと考え、シュトラッサー、ゲッペルスは左翼諸政党と同じように旧諸侯の財産無償没収に賛成した。この対立の中で、ヒトラーは陰謀的に多数派になるように工作した上で、バンベルグ指導者会議を開き、シュトラッサーグループを粉砕した。シュトラッサーグループはやむなく独自で作成し配布していた社会主義的綱領案を回収した。これを機に弟のオットー・シュトラッサーが脱落した。
<ナチスの議会進出>
1928年 ナチスは初の国政選挙で12議席、1930年9月の選挙で107議席(第2党)を獲得したが、ドイツ共産党はまったく危機感を持たず、「9月選挙での唯一の勝利は共産党である」と有頂天になっていた。1932年7月31日、選挙でついにナチスは第1党(230議席)になる。だがこの選挙の内容はナチスの左翼への勝利を意味してはいなかった。すなわち中間政党とブルジョア政党に打撃を与えたが、中央党・社民党・共産党に食い込むことができなかった。ナチスはこれ以上伸びていくためには、プロレタリアートに手を伸ばすしかなかった。
国会で、グレゴール・シュトラッサー、ゴットフリート・フェーダーは「銀行と株式市場の頭目」の資産剥奪を求めていたが、ナチス党の財政危機克服のために大企業との関係をよくしなければならず、その要求を下ろさせた。ナチスはまさにジレンマの谷間にあった。
1932年11月6日、選挙の最中にベルリンで交通企業ストが起こった。これは共産主義者により、労働組合の決議に反して引き起こされたものだが、ナチス党員は直ちにこれに参加した。共産党とSA(突撃隊)は一緒になって5日にわたり、レールをはがし、ピケットを張った。この時点で、ナチスにとって他の選択は困難であった。もっとも、このためブルジョアジーをひどく怒らせ、ナチスの財政はまったく干上がってしまった。選挙は200万票と34の議席を失った。
<ナチス政権獲得>
だが政局は混沌としていた。①ボナパルチズム支配を構築しようとしているヒンデンブルク、②あくまでも形式民主主義にこだわる社民党、③左右からの破壊者、ドイツ共産党とナチス。結局権力はヒトラーの手に握られた(1933年、ヒトラーを首相に任命)。ブルジョアジーが決断したのである。ひとつはよりいっそう伸びつつある共産党の威力、もうひとつはナチス党内社会主義派のグレゴール・シュトラッサーの脱落によって、ほっと胸をなでおろしたのである。
なんといってもナチス党の弱点は「社会主義」を提起しながら、それを裏切らねばならず、ブルジョアジーに色目を使いながらプロレタリアートの支持を取り付けなければならないという二律背反にある。
ドイツ共産党がナチスへの攻撃をどのように展開していたのか。一番重要なことはイデオロギーの段階できちんとナチスをとらえきれなかったことにあろう。さらにナチスを反革命として位置づけたとき、猛然と内戦に突入しなければならなかったのである。しかし、ナチズムの成長以後、共産党とナチスの激突は数え切れないくらいあるが、これに勝利することができなかった。