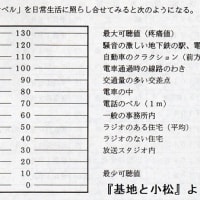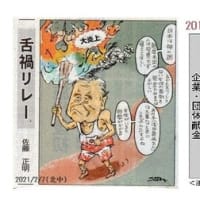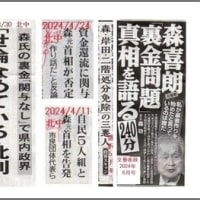論考「近代日本のナショナリズム」
ある機関誌(2020年8月)に投稿した原稿です。
目次:はじめに/【1】近代日本のナショナリズム(近代以前、明治初期~日清戦争、明治中期~日露戦争、日露戦争後~、昭和初期~15年戦争/【2】現代日本のナショナリズム(敗戦期、1960年代~、21世紀)/参考文献/用語について
はじめに
2019年日帝安倍政権とマスコミは、天皇代替わりを契機にして、天皇制賛美を洪水のようにたれ流し、天皇制に日本(人)のアイデンティティ(天皇の赤子)を求めるという、天皇制・天皇教ナショナリズムを煽り、加えて日本海(東海)大和堆のイカ漁問題、領土問題(独島・釣魚台)、軍隊慰安婦・徴用工問題などで国益主義・排外主義をあおり、スポーツ=オリンピックなどで日本民族の優秀さを賞讃し、21世紀の日本ナショナリズムを形成しようとしている。
ナショナリズムは近代的な国民国家の政治原理である。たとえば、王制を打倒したフランス革命の「自由・平等・友愛」、イギリスから独立したアメリカの「自由主義・共和主義」、ワイマール体制を打倒したドイツの「ナチズム」、明治維新後の「天皇制+国益・排外主義」、敗戦後の「象徴天皇制+9条平和主義」をナショナル・アイデンティティとして、近現代資本主義国家のもとに国民を繋ぎとめ、少数派(支配階級)が多数派(被支配階級)を支配・動員し、資本を増殖するためのイデオロギー装置として機能している。
日本では、江戸期のように、階級が厳格に固定化され、鎖国政策下の閉鎖された社会では、ナショナリズムは適合的な政治原理にはなりえず、明治期に入り(19世紀末~20世紀初頭)、対外関係が重要になった資本主義社会で発生した。日本ナショナリズムは天皇制・天皇教、対西欧コンプレックスの克服、国益・排外主義(特に対中国・朝鮮)などで構成されてきた。
統治機構が未確立な明治初期には、天皇・維新政府と対峙・対決する自由民権運動があったが、1882年(明治15年)、刑法第116条に大逆罪(天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス)が規定されて以降は、天皇制批判が封印され、対外戦争批判(天皇制批判を内包)が日本ナショナリズム批判の糸口とされた。したがって、日本ナショナリズムに対抗・対立する反ナショナリズムの存否は、「(天皇批判を内在化した)非戦・反戦」のあり方で確認することができる。
明治期に形成され、今日に至る日本のナショナリズムと反ナショナリズムの歴史をおさらいすることによって、21世紀の日本ナショナリズム批判への糸口としたい。
【1】近代日本のナショナリズム
(1)近代以前
古来、「すばらしい日本」、「美しい日本」、「稀有な日本」などのナショナルアイデンティティの創出がおこなわれてきた。推古天皇は「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙(つつが)無きや」と書いて、『国書』を中国(隋)に送り(607年)、北畠親房は、『神皇正統記』(1300年代)で、「大日本は神国なり。天祖はじめて基をひらき、日神ながく統を伝へ給ふ。我国のみ此事あり。異朝には其たぐひなし。此故に神国と云ふなり」と書いている。奈良時代の『風土記』や室町時代の『人国記』もナショナル・アイデンティティ捜しの書である。
江戸期には荷田春満→賀茂真淵→本居宣長(「古道論」)→平田篤胤(「復古神道」)らの「国学」が大和心(魂)を宣揚し、1823年には、佐藤信淵は『宇内混同秘策』で、「皇国御国は、大地の最初になれる国として、世界万国の根本なり」と、天皇こそ唯一の支配者であると「自民族至上主義」を主張した。水戸学者の会澤正志斎は日本を万世一系の皇統を軸とする祭政一致の国家体制と特徴づけ、天皇の存在を根拠に日本の対外優越性を説いた。吉田松陰は忠誠対象を天皇に一元化し、藩閥政府も政党も財界もすべて「私」にすぎず、天皇のみが公共性を代表すると考えていた。
幕末には、アメリカ、ロシアなどからの開国要求に、為す術もなく右往左往する江戸幕府に対抗する諸藩・武士階級によって、倒幕・尊王攘夷運動がはじまるが、天皇は倒幕に利用できる「玉」にすぎなかった。林子平はロシアの脅威への対抗から、朝鮮領有の必要性を説く『海国兵談』(1791年)を著し、侵略思想の萌芽が現れている。
江戸期に入って、度量衝や通貨の標準、商業の発達、教育(寺小屋)、出版が普遍化され、「単一国家」形成の基礎が形成されたが、300藩に分かれ、各藩の領民(武士、農民・商人)は所属する藩との関係性を結んでいたが、徳川幕府はもちろん天皇にも関心は薄く、「日本」という国家意識(ナショナリズム)を形成してはいなかった。
(2)明治初期~日清戦争
明治維新後、沖縄、北海道を包摂し、文化的・言語的共通性を確立(強制)し、国境が決められ、近代的単一国家が形成された。
維新政府にとっては、天皇は「玉」程度の扱いだったが、自由民権運動や資本主義生産関係の形成過程で、大逆罪(1882年)で批判派をねじ伏せ、軍人勅諭(1882年)、教育勅語(1890年)、決定的には日清戦争をとおして、天皇を核とした日本ナショナリズムを大衆レベルへと浸透させていった。
明治以降の日本ナショナリズムの第1の柱は天皇(制)にあり、例えば陸羯南(新聞『日本』1889年~)は「我が日本に在りて国民の本心は天皇を以て神と為し、臣民を以て宝と為す。神なり、故に侵すべからず。宝なり、故に軽んずべからず」と述べ、また中国を「善導」すべきとして、中国侵略を正当化する論をたてている。
第2の柱は、幕末の攘夷運動をひきつぎ、不平等条約の解消、西洋へのキャッチアップによる近代化(帝国主義化)である。徳富蘇峰は「皇室中心主義」を称えるとともに、ペリーによる強制開国を<強姦=屈辱>と捉え、<鎖国→開国>期を日本ナショナリズムの起点とし、『大日本膨張論』(1894年)では、中国の衝突に勝利しない限り、日本の発展はあり得ないと主張し、日清戦争の目的を<自尊心の回復、欧米による認知>に置いた。
第3の柱は周辺諸国への侵略による国益の追求に置いた。西郷隆盛は朝鮮半島の領有によって国内危機を解除する「征韓論」を称えた(1860年代)。杉田鶉山は明治政府の専制を批判し、アジアの人民解放を主張していたが、日本の近代化のためには中国・朝鮮の侵略が必要と、その主張を変えた(1880年代)。大井憲太郎は当初、韓国独立党を支援していたが、西欧諸列強への対抗手段として、大陸を領有すべきだと主張を変えた(1880年代)。
福沢諭吉は「日清戦争は文(明)野(蛮)の戦争」と主張し、台湾割奪(1895年)後、「(抵抗者は)兵民の区別を問はず、一人も残らず誅戮(ちゅうりく)して集類なからしめ」、「内国にて民権を主張するは、外国に対して国権を張らんが為なり」などと、<民権=侵略>論を主張し、日本ナショナリズムの第2、第3の柱確立に余念がなかった。
日露戦争時には幸徳秋水、堺利彦らとともに非戦論を主張した内村鑑三さえもが「支那(注:中国)は社交律の破壊者なり、人情の害敵なり、野蛮主義の保護者なり」と日清戦争を支持したように、この時期の日本ナショナリズムは<神権天皇制+欧化+周辺国侵略論>で構成されていた。
自由民権運動の変節
自由民権運動は1874年の国会開設請願からはじまり、「国会開設」「地租軽減」「条約改正」を目標にし、1890年の国会開設をもって終熄した。全国津々浦々で民権結社や学習運動が起こり、国会開設請願運動、憲法起草運動が起き、1884年の秩父困民党蜂起と加波山事件がその頂点にある。秩父蜂起は、人民の参加による人民のための政治をめざし、天皇制とは相容れない「社会的平等やコミューンの思想」を孕んでいた。しかし、福沢諭吉による「脱亜論」(1885年)の影響を受け、琉球、アイヌ、朝鮮、台湾への差別・蔑視へと繋がり、大陸侵略政策批判の根拠を失い、1884年の甲申事変(朝鮮における親日クーデターの失敗)後には、民権派は政府以上に好戦的な姿勢に転じたのである。
たとえば、筆者の義母の係累に加波山事件で投獄された横川省三がおり、1887年保安条例で「皇居3里以内接近禁止」の決定がおりた。その後の横川省三は、日露戦争開戦時(1904年)にロシア軍の東清鉄道を爆破するために満州に潜伏していたところを逮捕され、ハルピンで銃殺刑に処された。
このように、自由民権運動は挫折し、「脱亜論」に取り込まれ、官民一体で排外主義があおりたてられ、日本ナショナリズムが形成されていったのである。
日清戦争反対論
もともと自由民権運動には天皇制批判が孕まれており、1882年には、天皇(制)批判を封殺するために、「大逆罪(死刑)」、1885年には「爆発物取締罰則(死刑)」が施行された。秩父蜂起や加波山事件が鎮圧(1884年)され、軍人勅諭(1882年)、教育勅語(1890年)で天皇の「神聖不可侵性」が浸透し、日清戦争(1894年)を迎えるころには、天皇批判もアジア連帯論も姿を消し、戦争支持論が明治中期の社会意識となっていた。
日清戦争反対論について見てみると、1870年代の谷干城は征韓論(外征によって士族の不満を解消し国論統一を図る)に立っていたが、日清開戦を積極的に支持する民権派とは距離をおき、支持せず、戦争終結後の戦争賠償も過大な要求はすべきではないと主張し、遼東半島割奪の要求も批判している。
1894年、日清戦争中の勝海舟は時局談話『氷川清和』で、「日清戦争はおれは大反対だったよ。なぜかって、兄弟喧嘩だもの、…支那(注:中国)は昔時から日本の師ではないか。…今日になって兄弟喧嘩をして、支那(注:中国)の内輪をサラケ出して、欧米の乗ずるところとなるくらゐのものサ」と語っている。
また、当時の文学者泉鏡花は『予備兵』(1894年)、『海城発電』(1896年)、『琵琶伝』(1896年)、『凱旋祭』(1897年)で、日清戦争への不同意を明確に表現している。
日清戦争反対論はごく少数派であり、戦争が始まると、「絵にも唄にも、支那(注:中国)人に対する憎悪が反映してきた。私が学校で教えられた最初の日清戦争の唄は、討てや膺(こら)せや清国を、清は皇国(みくに)の仇なるぞ、討ちて正しき國とせよ。」(生方敏郎著『明治大正見聞史』)と書かれているように、排外主義があおりたてられた。
(3)明治中期~日露戦争
高山樗牛は日清戦争後の1897年の『太陽』誌上で、「日本国家共同体へ国民を思想的にも精神的にも強制動員し、国家的価値や国家的利益がすべてに優越する」、「西欧先進帝国主義国家との競合と対立に耐えうる強大な国家建設」(日本主義)などと主張した。この時期には、日清戦争に勝利した「大国民」としての日本民族を自画自讃し、諸列強との覇権争いに対応するための大陸侵略思想の形成と実践の段階に入っていった。
世論は日露開戦支持一色となり、民本主義を称える吉野作造は「朝鮮の独立と帝国の自尊のために、ロシアを挫かねばならない」と主張し、「忠君愛国」の天皇制ナショナリスト海老名弾正も「(朝鮮)合同説」を称えて、ともに日露戦争を支持した。
インターナショナリズム
日清戦争期には戦争批判がほとんどなかったが(泉鏡花による厭戦小説はあるが)、日露戦争開戦の危機が深まっている1903年、幸徳秋水・堺利彦らは安部磯雄、片山潜らの支持を得て、社会主義の立場から、『平民新聞』を発行し、非戦論を展開した。
1904年には、トルストイの『悔い改めよ』や『共産党宣言』が翻訳され、幸徳秋水はインターナショナリズム(国際主義)に大きな影響を受けている。幸徳秋水は『平民新聞』(1904年3月)の社説で、「社会主義者の眼中には人種の別なく地域の別なく、国籍の別なし、諸君と我等とは同志也、兄弟也、姉妹也、断じて闘うべきの理有るなし、諸君の敵は日本人に非ず、実に今の所謂愛国主義也、軍国主義也、然り愛国主義と軍国主義とは、諸君と我等と共通の敵也。」と提言している。ここで、幸徳は自国・日本の戦争に反対し、ロシア社会民主党は「敗戦」を歓迎し、両国人民のインターナショナリズムが交差したのである。
その後7月には、幸徳秋水は海老名弾正の「朝鮮民族の運命を観じて日韓合同説を奨説す」について、「保護国は不可也、属国は不可也」、「日本人が如何に韓人を軽蔑し虐待せるかは、心ある者の常に憤慨せるに非ずや」、「見よ、領土保全と称するも、合同と称するも、その結果は只ヨリ大なる日本帝国を作るに過ぎざることを」(論文「朝鮮併呑論を評す」)と、侵略(朝鮮併合)と排外主義とアジア蔑視を激しく批判した。
作家・徳田秋声は日露戦争真っただ中の1904年に、『春の月』で「此奴(息子)も又兵隊だ。其時分は、何所の国と戦をするだらう」と、厭戦的に書き、キリスト者・木下尚江も非戦論の立場から、1908年韓国併合の動きについて、「略奪は国家の本性だ」と痛烈に批判している。
(4)日露戦争後~
日露戦争に勝利した日帝は、大陸侵略思想の本格的な形成と、その実践としての朝鮮半島支配権の拡張に向かった。1906年山縣有朋は「国利国権の伸張は先づ清国に向かって企画せらるるものとす」「(中国侵略は)帝国の天賦の権利」、同年田中義一は「大陸国家構想(大陸に日本の活路を開く)」、1916年後藤新平の「日本膨張論」など、大陸侵攻論や大陸膨張論が日本社会を覆い尽くしていた。
このような情勢のなかで、1910年5月25日、明治天皇暗殺計画(信州明科爆裂弾事件)が発覚し、信州の社会主義者宮下太吉ら4人が逮捕された。この事件を口実として、非戦・反戦勢力を一掃するために、日帝は幸徳大逆事件をでっち上げ、数百人の社会主義者・無政府主義者を逮捕・検挙し、翌1911年24人に死刑判決、12人を処刑し、天皇(制)の凶暴性を示したのである。
社会主義者を一掃し、日本ナショナリズムを満展開し、韓国併合(1910年)、満蒙独立運動(1912年、15年)、第1次世界大戦参戦(1914年~)、山東出兵(1927、28年)、満州事変(1931年)へと突っ走るのである。
1911年に幸徳秋水が処刑された後、「大正デモクラシー」が開花する。労働組合(日本労友会など)が増加し、労働争議(八幡製鉄所の大争議など)の件数・参加人数とも増加、高止まりの状態で推移している(一覧表)。『マルクス伝』、『資本論』、『空想的及科学的社会主義』、『賃労働と資本』、『労賃・価格及利潤』、『国家と革命』、『帝国主義論』など共産主義文献が多数翻訳発行され、米騒動(1918年)が全国に波及し、小作争議も増加し、安田善次郎刺殺(1921年)、原敬首相刺殺(1921年)、虎の門事件(1923年)など左右のたたかいが火花を散らしていた時代である。
1912年から上杉慎吉と美濃部達吉の天皇機関説論争があり、美濃部達吉は「天皇は元首であるが、同時に憲法に従って政治(統治権)を行使する『機関』ともいえる。…したがって国家の『機関』である以上、天皇も『国家』意思に従わなければならない」と主張し、天皇主権=神権説を退け、1913年には機関説が勝利し、憲法は機関説で運用された。
1917年ロシア革命でソ連が誕生したことにより、国民のなかに共産主義思想が広まり(1922年日本共産党結成)、民衆のなかに権利意識が高揚し、普通選挙権獲得に関心が集まった。天皇制及び国家神道の動揺を懸念した政府は、普通選挙法制定(1925年)に抱き合わせて、治安維持法「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」を制定し、共産主義運動に致命的な規制をかけた。
この時代は、日本ナショナリズムにたいする批判が噴出し、大逆罪(死刑)と治安維持法による恫喝と言論封殺によって、辛うじて守られていたといえる。
(5)昭和初期~15年戦争
天皇機関説は大正から昭和の初めまで憲法学界の通説となったが、中国侵略戦争(1931年満州事変~)が始まる過程で、1935年美濃部達吉は不敬罪で告発され,『憲法撮要』など3著が発禁処分を受け、天皇機関説は政治的に葬られ、天皇主権説に逆戻りした。侵略戦争遂行のための天皇制ナショナリズムから不純物を取り除いたのである。
大逆罪(1982年)、爆発物取締罰則(1985年)に加えて、1925年に治安維持法(国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコト)が成立し、その本格的発動は1928年3・15弾圧(1568人検挙)であり、山本宣治刺殺(1929年)、小林多喜二(1933年)や鶴彬(1938年)を獄死させ、約7万人が送検され、拷問死90人を含め、少なくとも400人強が獄死している。
このように、日帝は弾圧と白色テロルによって人民の気孔をふさいだが、この時期(昭和初期)の労働争議は大正期よりも多発しており、1940年の産業報国会によって労働組合の活動が強制的に停止されるまで、人民の権利意識が広範かつ強固に存在していた。このような労働者人民の抵抗を内部から解体するために、文学者、画家、音楽家、宗教者、哲学者などを総動員して、日本ナショナリズムを強制したのである。
筆者の住む石川県でいえば、詩人・室生犀星は、1943年の詩集『美以久佐(みいくさ)』の序詩では、「みいくさは勝たせたまへ/つはものにつつがなかれ/みいくさは勝たせたまへ/もろ人はみないのりたまへ/みいくさは勝たせたまへ/食ふべくは芋はふとり/銃後ゆたかなれば/みいくさびとよ安らかなれ/みいくさは勝たせたまへ」と戦勝を祈念し、「マニラ陥落」では、軍靴がグアム、ウエーキ、香港、マレー、ボルネオ、シンガポール、マニラへと踏みにじっていくことに、犀星は快哉を叫んでいる。これらの戦争詩は劇場やラジオで朗読され、国民の戦意昂揚に資した。
真宗僧侶の暁烏敏(あけがらすはや)は1936年の説教で、「今日の日本臣民は子供をお国の役に立つように、天皇陛下の御用をつとめるように念願して育てにゃならんのであります。…日本の臣民は天皇陛下の家の子供として、天皇陛下の御用にたち、…百姓でも、町人でも、すべてその心得がなくてはならんのであります」、「天皇機関説を称える人の態度を見ますと、…頭の上がった態度であります。天皇は神聖にして侵すべからずという国体明徴の道は臣民の道であります。我々はこの臣民としての自覚がなければならんのであります」と、宗教界も率先して天皇への忠誠を要求している(『皇道・神道・仏道・臣道』)。
画家宮本三郎は1940年に中国に画家として従軍し、41年には「南苑攻撃図」、その翌年に「山下―パーシバル会見図」を描き、45年敗戦まで戦争画を多数描き続けている。
このような文学、宗教、絵画などの表現者がこぞって体制に順応していった裏には、革命党の不在、すなわち人民に開かれた非公然の出版・配布の経験的蓄積の未成熟があるのではないだろうか。しかし、上海では「大韓民国臨時政府」(1919年~)、タイでは「自由タイ」(1943年~)、フィリピンでは「抗日人民軍=フクバラハップ」(1942年~)、マレー半島では「マラヤ人民抗日軍」(1942年~)、ビルマでは「パサパラ(反ファシスト人民自由連盟)」(1944年~)が、日帝の暴力支配のもとで結成されたたかいぬいている。
このように1931年満州事変から始まった15年戦争によって、数千万のアジア人民の殺戮、310万人の日本人兵士・市民の死をもたらしたものこそ、日本ナショナリズム(天皇制+国益・排外主義)であり、とりわけ「東亜新秩序」(「諸民族の自主独立」、「民族の伝統尊重と創造性伸暢」、「互恵経済発展」、「欧米からの植民地解放」、「同祖同族論」、「家族国家観(家長=日本、家族=諸民族)」)にもとづく戦時ナショナリズム=大東亜共栄圏構想であり、主体的側面としては革命党不在の問題を挙げねばならないだろう。
とはいえ、「大東亜共栄圏構想」は実体を伴わず、アジア市場を狙う米帝の参戦が立ちはだかり、敗戦を迎え、戦時日本ナショナリズムは破綻したのである。
【2】現代日本のナショナリズム
(6)敗戦期
1945年に敗戦を迎えた日本で、破綻した日本ナショナリズムはどのように「変化・再編」されたのだろうか。『読売新聞』の世論調査(1948年8月15日発表)によれば、<天皇制存続=90.3%、天皇制廃止=4.0%>という結果がある。他方では、同年9月の日本世論調査研究所の文化人・議員・財界人1000人の「指導者層」を対象にしたアンケートでは、<退位賛成=約50%、退位反対=約44%>であった。ここから見えることは高学歴者のなかでは退位支持が多数を占めているものの、一般市民の天皇制支持は解体されず、天皇(制)ナショナリズムは戦後も人々の意識を支配していたことである。
日本軍に侵略され、大きな被害を被ったアジア諸国民は天皇制廃止を主張したが、このような国民意識を把握していた米占領軍は、「間接植民地統治方式」で日本を支配するために天皇制を残し、とりあえず日帝軍部の解体・無力化を図ったのである。
戦時期の苛酷な弾圧・投獄(前述)と転向によって、反体制組織も思想も壊滅状態であり、日帝敗北後、非転向政治犯3000人が釈放(岩波『近代日本総合年表』)されたものの、旧体制(天皇制)はもちろん、米占領軍を打倒すべき組織的主体は、あらかじめ解体されていた。他方植民地支配下の朝鮮では何万人もの活動家が亡命し、朝鮮本国に檄を発し、日帝敗北後に帰国し、民衆と共にたたかいぬいた歴史を持っている。
論壇の分裂
戦後期の論壇には、「アメリカの民主主義に降伏するのではない、皇室中心の民主主義である」(45年9月、『毎日新聞』)、「君民一如の民主政治」(45年12月、鳩山一郎)、「国民は天皇を愛する。愛するところに真の民主主義がある」(46年4月、津田左右吉)など、民主主義と天皇制の共存論が溢れていた。
他方では「天皇制は個人の自由を奪い、責任の観念を不可能にし、道徳を頽廃させる」(46年3月、加藤周一)、「天皇制の由来は…悠久なものではなく、…天皇制は明治維新以来70年来のもの」(46年3月、羽仁五郎)、「天皇制は明治以後はじめて出来た」(46年9月、井上清)、「天皇制が…日本人をして…半永久的な未成年段階にとどまらせる」「天皇制廃止を目標として国民的成長」(49年、中野好夫)、「(天皇制を)倒さなければ日本人の道徳的自立は完成しない」(52年、丸山真男)と、天皇(制)にたいする賛否が拮抗していたのである。
革命党の役割と試練
このように国論が真っ二つに分裂しているときにこそ、革命党の天皇制批判と行動が重要であった。共産党は1945年10月の「人民に訴う」のなかで、天皇制打倒・人民共和政府樹立を声明し、志賀義雄は「天皇こそ最大の戦争犯罪人」(11月)、宮本顕治は「専制君主(=天皇)の永続的支配はその民族の汚辱」(46年2月)と天皇制を批判したが、他方では野坂参三は「専制権をもたぬ天皇」(1945年4月延安で)の残存を容認し、「民主戦線によって祖国の危機を救え」(1946年1月)と祖国防衛論に陥いっていたのである。
戦後期を迎えた共産党には、「侵略戦争の敗北を革命に転化する」という思想的・運動的準備もなく、天皇制打倒のスローガンもおろし、米占領軍に恭順の意を示しながら(解放軍規定)、ついに1950年レッドパージで壊滅的な打撃を受けたのである。
すなわち、敗戦によって既成権力(天皇制と軍部)の権威が地に落ちた、千載一遇のチャンスに、占領軍に支えられた日帝ブルジョアジーは、戦前の<天皇制+軍部>による統治から、<象徴天皇制+民主主義+憲法9条>への転換を図って、生きのびたのである。ここに象徴天皇制という新たなナショナル・アイデンティティが形成されたのである。
(7)1960年代~
敗戦帝国主義・日帝は1965年日韓条約を転換点として、アジア再侵略(経済的)の道を歩み始めている。共産党は米帝従属論のもとで、「日韓条約」を反米民族闘争の課題と位置づけ、革共同は「日韓条約=再植民地化」として、「日韓(条約)の本質を日帝の(再)植民地支配としてとらえ、反植民地闘争の原則的立場を確立、…植民地支配にたいする帝国主義本国プロレタリアートの国際的任務」(1966年「第3回大会報告」)と位置づけてたたかっている。
それは、ベトナム反戦・大学闘争(帝国主義大学解体)に引き継がれ、1970年「7・7」告発によって、近代以降のアジア侵略への自己批判と現代日帝の再侵略阻止を、みずからに課したのである。
その後の日帝は帝国主義として、法改正を繰り返しおこない、繰り返し自衛隊を派兵し、建国記念日(紀元節)を設け、日の丸を国旗とし、君が代を国歌とし、教育基本法を改悪(愛国心)し、スポーツで祖国日本を讃美し、領土問題で対韓国・中国排外主義をあおり、戦前型の日本ナショナリズム(元首天皇制+国益・排外主義)へと国民を導こうとしている。
(8)21世紀の日本ナショナリズム
かつて、日本ナショナリズムは大逆罪、爆発物取締罰則、治安維持法によって保守・強制されていたが、「象徴天皇制+民主主義+憲法9条」を内容とする戦後の日本ナショナリズムは占領軍支配下で生まれ、爆発物取締罰則、破防法(1952年)、凶器準備集合罪(1958年)、共謀罪(2017年)などの弾圧法体制によって保守・強制されている。
その象徴天皇制は、戦後の統治システムの重要な一角を占め、日本ナショナリズムの重要な要素をなし、人民から自立心と主体性を奪ってきたが、しかし、21世紀の日帝にとって、「象徴天皇制+民主主義+憲法9条」という戦後の統治形態そのものが桎梏と化している。①解釈改憲で自衛隊を強大化し、海外に派遣してきたが、憲法9条の制約を取り払って、ストレートに対外軍事行動が出来る国への衝動に駆られている。②新型コロナウイルス問題を奇貨として、安倍政権は火事場泥棒のように、政府に権限を集中させ、国民の権利を制限する「非常事態条項」を憲法に潜り込ませようと画策している。
③さらに天皇を象徴から元首に変えることによって、戦後民主主義を根底から変質させ(立憲君主制へ)、内に向かっては従順な臣民へ、外に向かっては兇暴な侵略者へと変えようとしているのである。それは、まごう事なき天皇制・天皇教+国益・排外主義+戦争によって構成された戦前型日本ナショナリズムへの志向である。
その実践的手法として、「国際貢献論」「美しい国づくり」「戦後レジームからの脱却」「新しい生活様式」などと、歯の浮くようなスローガンを並べ立てて、21世紀日本ナショナリズムを再構成しようとしているが、これに対置すべき「1970・7・7」思想(連帯し内乱へ)を、2007年「7月テーゼ」で、革共同自身が否定・清算してしまったのである。「被差別・被抑圧人民のたたかいと労働者階級の自己解放闘争を並列的に扱う傾向」、「出身の共産主義者は、自己をまず労働者階級解放闘争をたたかう主体として確立」などと言いなして、差別・排外主義とのたたかいを後景に押しやり、二義的な課題とし、被差別人民とりわけアジア人民との連帯・共闘論を否定した(北陸では不二越強制連行訴訟支援からの逃亡)。
120年前の日露戦争時に、「愛国主義と軍国主義とは、諸君(ロシア社会民主党)と我等と共通の敵也」と呼びかけ、「朝鮮併呑論を評す」で、朝鮮併合を真っ向から批判した幸徳秋水の「革命的祖国敗北主義・侵略戦争を内乱へ」論をいまこそ継承し、21世紀をたたかいぬくために、早急に21世紀日本ナショナリズムを対象化するための諸論沸騰を期待したい。
参考資料
纐纈厚著『侵略戦争 歴史的事実と歴史認識』(1999年)/色川大吉著『自由民権』(1981年)/小熊英二著『<民主>と<愛国>』(2002年)/塩川伸明著『民族とネイション ナショナリズムという難問』(2008年)/植木和秀著『ナショナリズム入門』(2014年)/米原謙著『東アジアのナショナリズムと近代』(2011年)/原佑介論文「木下尚江の『大日本魂』批判」(2008年)/『大東亜聖戦大碑資料集(1)』(2001年)/『島田清次郎の実像』(2019年)/『上海爆弾事件後の尹奉吉』(2020年)/『石川県ゆかりの表現者と戦争』(2020年)/マルクス・エンゲルス著『共産党宣言』(1848年)/大澤真幸著『近代日本のナショナリズム』(2011年)/岩波『近代日本総合年表』(1968年)/山村信一論文「国民帝国とナショナル・アイデンティティの逆説」(2017年『ナショナル・アイデンティティを問い直す』所収)/『2007年7月テーゼ学習・討議資料』(前進社)/生方敏郎著『明治大正見聞史』(1979年)/「天皇制ボナパルティズム論」(1960年『本多延嘉著作選』)/泉鏡花著『予備兵』『『琵琶伝』『柳小島』など/室生犀星詩集『美以久佐(みいくさ)』(1943年)/暁烏敏著『皇道・神道・仏道・臣道』(1937年北安田パンフレット)/
ある機関誌(2020年8月)に投稿した原稿です。
目次:はじめに/【1】近代日本のナショナリズム(近代以前、明治初期~日清戦争、明治中期~日露戦争、日露戦争後~、昭和初期~15年戦争/【2】現代日本のナショナリズム(敗戦期、1960年代~、21世紀)/参考文献/用語について
はじめに
2019年日帝安倍政権とマスコミは、天皇代替わりを契機にして、天皇制賛美を洪水のようにたれ流し、天皇制に日本(人)のアイデンティティ(天皇の赤子)を求めるという、天皇制・天皇教ナショナリズムを煽り、加えて日本海(東海)大和堆のイカ漁問題、領土問題(独島・釣魚台)、軍隊慰安婦・徴用工問題などで国益主義・排外主義をあおり、スポーツ=オリンピックなどで日本民族の優秀さを賞讃し、21世紀の日本ナショナリズムを形成しようとしている。
ナショナリズムは近代的な国民国家の政治原理である。たとえば、王制を打倒したフランス革命の「自由・平等・友愛」、イギリスから独立したアメリカの「自由主義・共和主義」、ワイマール体制を打倒したドイツの「ナチズム」、明治維新後の「天皇制+国益・排外主義」、敗戦後の「象徴天皇制+9条平和主義」をナショナル・アイデンティティとして、近現代資本主義国家のもとに国民を繋ぎとめ、少数派(支配階級)が多数派(被支配階級)を支配・動員し、資本を増殖するためのイデオロギー装置として機能している。
日本では、江戸期のように、階級が厳格に固定化され、鎖国政策下の閉鎖された社会では、ナショナリズムは適合的な政治原理にはなりえず、明治期に入り(19世紀末~20世紀初頭)、対外関係が重要になった資本主義社会で発生した。日本ナショナリズムは天皇制・天皇教、対西欧コンプレックスの克服、国益・排外主義(特に対中国・朝鮮)などで構成されてきた。
統治機構が未確立な明治初期には、天皇・維新政府と対峙・対決する自由民権運動があったが、1882年(明治15年)、刑法第116条に大逆罪(天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス)が規定されて以降は、天皇制批判が封印され、対外戦争批判(天皇制批判を内包)が日本ナショナリズム批判の糸口とされた。したがって、日本ナショナリズムに対抗・対立する反ナショナリズムの存否は、「(天皇批判を内在化した)非戦・反戦」のあり方で確認することができる。
明治期に形成され、今日に至る日本のナショナリズムと反ナショナリズムの歴史をおさらいすることによって、21世紀の日本ナショナリズム批判への糸口としたい。
【1】近代日本のナショナリズム
(1)近代以前
古来、「すばらしい日本」、「美しい日本」、「稀有な日本」などのナショナルアイデンティティの創出がおこなわれてきた。推古天皇は「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙(つつが)無きや」と書いて、『国書』を中国(隋)に送り(607年)、北畠親房は、『神皇正統記』(1300年代)で、「大日本は神国なり。天祖はじめて基をひらき、日神ながく統を伝へ給ふ。我国のみ此事あり。異朝には其たぐひなし。此故に神国と云ふなり」と書いている。奈良時代の『風土記』や室町時代の『人国記』もナショナル・アイデンティティ捜しの書である。
江戸期には荷田春満→賀茂真淵→本居宣長(「古道論」)→平田篤胤(「復古神道」)らの「国学」が大和心(魂)を宣揚し、1823年には、佐藤信淵は『宇内混同秘策』で、「皇国御国は、大地の最初になれる国として、世界万国の根本なり」と、天皇こそ唯一の支配者であると「自民族至上主義」を主張した。水戸学者の会澤正志斎は日本を万世一系の皇統を軸とする祭政一致の国家体制と特徴づけ、天皇の存在を根拠に日本の対外優越性を説いた。吉田松陰は忠誠対象を天皇に一元化し、藩閥政府も政党も財界もすべて「私」にすぎず、天皇のみが公共性を代表すると考えていた。
幕末には、アメリカ、ロシアなどからの開国要求に、為す術もなく右往左往する江戸幕府に対抗する諸藩・武士階級によって、倒幕・尊王攘夷運動がはじまるが、天皇は倒幕に利用できる「玉」にすぎなかった。林子平はロシアの脅威への対抗から、朝鮮領有の必要性を説く『海国兵談』(1791年)を著し、侵略思想の萌芽が現れている。
江戸期に入って、度量衝や通貨の標準、商業の発達、教育(寺小屋)、出版が普遍化され、「単一国家」形成の基礎が形成されたが、300藩に分かれ、各藩の領民(武士、農民・商人)は所属する藩との関係性を結んでいたが、徳川幕府はもちろん天皇にも関心は薄く、「日本」という国家意識(ナショナリズム)を形成してはいなかった。
(2)明治初期~日清戦争
明治維新後、沖縄、北海道を包摂し、文化的・言語的共通性を確立(強制)し、国境が決められ、近代的単一国家が形成された。
維新政府にとっては、天皇は「玉」程度の扱いだったが、自由民権運動や資本主義生産関係の形成過程で、大逆罪(1882年)で批判派をねじ伏せ、軍人勅諭(1882年)、教育勅語(1890年)、決定的には日清戦争をとおして、天皇を核とした日本ナショナリズムを大衆レベルへと浸透させていった。
明治以降の日本ナショナリズムの第1の柱は天皇(制)にあり、例えば陸羯南(新聞『日本』1889年~)は「我が日本に在りて国民の本心は天皇を以て神と為し、臣民を以て宝と為す。神なり、故に侵すべからず。宝なり、故に軽んずべからず」と述べ、また中国を「善導」すべきとして、中国侵略を正当化する論をたてている。
第2の柱は、幕末の攘夷運動をひきつぎ、不平等条約の解消、西洋へのキャッチアップによる近代化(帝国主義化)である。徳富蘇峰は「皇室中心主義」を称えるとともに、ペリーによる強制開国を<強姦=屈辱>と捉え、<鎖国→開国>期を日本ナショナリズムの起点とし、『大日本膨張論』(1894年)では、中国の衝突に勝利しない限り、日本の発展はあり得ないと主張し、日清戦争の目的を<自尊心の回復、欧米による認知>に置いた。
第3の柱は周辺諸国への侵略による国益の追求に置いた。西郷隆盛は朝鮮半島の領有によって国内危機を解除する「征韓論」を称えた(1860年代)。杉田鶉山は明治政府の専制を批判し、アジアの人民解放を主張していたが、日本の近代化のためには中国・朝鮮の侵略が必要と、その主張を変えた(1880年代)。大井憲太郎は当初、韓国独立党を支援していたが、西欧諸列強への対抗手段として、大陸を領有すべきだと主張を変えた(1880年代)。
福沢諭吉は「日清戦争は文(明)野(蛮)の戦争」と主張し、台湾割奪(1895年)後、「(抵抗者は)兵民の区別を問はず、一人も残らず誅戮(ちゅうりく)して集類なからしめ」、「内国にて民権を主張するは、外国に対して国権を張らんが為なり」などと、<民権=侵略>論を主張し、日本ナショナリズムの第2、第3の柱確立に余念がなかった。
日露戦争時には幸徳秋水、堺利彦らとともに非戦論を主張した内村鑑三さえもが「支那(注:中国)は社交律の破壊者なり、人情の害敵なり、野蛮主義の保護者なり」と日清戦争を支持したように、この時期の日本ナショナリズムは<神権天皇制+欧化+周辺国侵略論>で構成されていた。
自由民権運動の変節
自由民権運動は1874年の国会開設請願からはじまり、「国会開設」「地租軽減」「条約改正」を目標にし、1890年の国会開設をもって終熄した。全国津々浦々で民権結社や学習運動が起こり、国会開設請願運動、憲法起草運動が起き、1884年の秩父困民党蜂起と加波山事件がその頂点にある。秩父蜂起は、人民の参加による人民のための政治をめざし、天皇制とは相容れない「社会的平等やコミューンの思想」を孕んでいた。しかし、福沢諭吉による「脱亜論」(1885年)の影響を受け、琉球、アイヌ、朝鮮、台湾への差別・蔑視へと繋がり、大陸侵略政策批判の根拠を失い、1884年の甲申事変(朝鮮における親日クーデターの失敗)後には、民権派は政府以上に好戦的な姿勢に転じたのである。
たとえば、筆者の義母の係累に加波山事件で投獄された横川省三がおり、1887年保安条例で「皇居3里以内接近禁止」の決定がおりた。その後の横川省三は、日露戦争開戦時(1904年)にロシア軍の東清鉄道を爆破するために満州に潜伏していたところを逮捕され、ハルピンで銃殺刑に処された。
このように、自由民権運動は挫折し、「脱亜論」に取り込まれ、官民一体で排外主義があおりたてられ、日本ナショナリズムが形成されていったのである。
日清戦争反対論
もともと自由民権運動には天皇制批判が孕まれており、1882年には、天皇(制)批判を封殺するために、「大逆罪(死刑)」、1885年には「爆発物取締罰則(死刑)」が施行された。秩父蜂起や加波山事件が鎮圧(1884年)され、軍人勅諭(1882年)、教育勅語(1890年)で天皇の「神聖不可侵性」が浸透し、日清戦争(1894年)を迎えるころには、天皇批判もアジア連帯論も姿を消し、戦争支持論が明治中期の社会意識となっていた。
日清戦争反対論について見てみると、1870年代の谷干城は征韓論(外征によって士族の不満を解消し国論統一を図る)に立っていたが、日清開戦を積極的に支持する民権派とは距離をおき、支持せず、戦争終結後の戦争賠償も過大な要求はすべきではないと主張し、遼東半島割奪の要求も批判している。
1894年、日清戦争中の勝海舟は時局談話『氷川清和』で、「日清戦争はおれは大反対だったよ。なぜかって、兄弟喧嘩だもの、…支那(注:中国)は昔時から日本の師ではないか。…今日になって兄弟喧嘩をして、支那(注:中国)の内輪をサラケ出して、欧米の乗ずるところとなるくらゐのものサ」と語っている。
また、当時の文学者泉鏡花は『予備兵』(1894年)、『海城発電』(1896年)、『琵琶伝』(1896年)、『凱旋祭』(1897年)で、日清戦争への不同意を明確に表現している。
日清戦争反対論はごく少数派であり、戦争が始まると、「絵にも唄にも、支那(注:中国)人に対する憎悪が反映してきた。私が学校で教えられた最初の日清戦争の唄は、討てや膺(こら)せや清国を、清は皇国(みくに)の仇なるぞ、討ちて正しき國とせよ。」(生方敏郎著『明治大正見聞史』)と書かれているように、排外主義があおりたてられた。
(3)明治中期~日露戦争
高山樗牛は日清戦争後の1897年の『太陽』誌上で、「日本国家共同体へ国民を思想的にも精神的にも強制動員し、国家的価値や国家的利益がすべてに優越する」、「西欧先進帝国主義国家との競合と対立に耐えうる強大な国家建設」(日本主義)などと主張した。この時期には、日清戦争に勝利した「大国民」としての日本民族を自画自讃し、諸列強との覇権争いに対応するための大陸侵略思想の形成と実践の段階に入っていった。
世論は日露開戦支持一色となり、民本主義を称える吉野作造は「朝鮮の独立と帝国の自尊のために、ロシアを挫かねばならない」と主張し、「忠君愛国」の天皇制ナショナリスト海老名弾正も「(朝鮮)合同説」を称えて、ともに日露戦争を支持した。
インターナショナリズム
日清戦争期には戦争批判がほとんどなかったが(泉鏡花による厭戦小説はあるが)、日露戦争開戦の危機が深まっている1903年、幸徳秋水・堺利彦らは安部磯雄、片山潜らの支持を得て、社会主義の立場から、『平民新聞』を発行し、非戦論を展開した。
1904年には、トルストイの『悔い改めよ』や『共産党宣言』が翻訳され、幸徳秋水はインターナショナリズム(国際主義)に大きな影響を受けている。幸徳秋水は『平民新聞』(1904年3月)の社説で、「社会主義者の眼中には人種の別なく地域の別なく、国籍の別なし、諸君と我等とは同志也、兄弟也、姉妹也、断じて闘うべきの理有るなし、諸君の敵は日本人に非ず、実に今の所謂愛国主義也、軍国主義也、然り愛国主義と軍国主義とは、諸君と我等と共通の敵也。」と提言している。ここで、幸徳は自国・日本の戦争に反対し、ロシア社会民主党は「敗戦」を歓迎し、両国人民のインターナショナリズムが交差したのである。
その後7月には、幸徳秋水は海老名弾正の「朝鮮民族の運命を観じて日韓合同説を奨説す」について、「保護国は不可也、属国は不可也」、「日本人が如何に韓人を軽蔑し虐待せるかは、心ある者の常に憤慨せるに非ずや」、「見よ、領土保全と称するも、合同と称するも、その結果は只ヨリ大なる日本帝国を作るに過ぎざることを」(論文「朝鮮併呑論を評す」)と、侵略(朝鮮併合)と排外主義とアジア蔑視を激しく批判した。
作家・徳田秋声は日露戦争真っただ中の1904年に、『春の月』で「此奴(息子)も又兵隊だ。其時分は、何所の国と戦をするだらう」と、厭戦的に書き、キリスト者・木下尚江も非戦論の立場から、1908年韓国併合の動きについて、「略奪は国家の本性だ」と痛烈に批判している。
(4)日露戦争後~
日露戦争に勝利した日帝は、大陸侵略思想の本格的な形成と、その実践としての朝鮮半島支配権の拡張に向かった。1906年山縣有朋は「国利国権の伸張は先づ清国に向かって企画せらるるものとす」「(中国侵略は)帝国の天賦の権利」、同年田中義一は「大陸国家構想(大陸に日本の活路を開く)」、1916年後藤新平の「日本膨張論」など、大陸侵攻論や大陸膨張論が日本社会を覆い尽くしていた。
このような情勢のなかで、1910年5月25日、明治天皇暗殺計画(信州明科爆裂弾事件)が発覚し、信州の社会主義者宮下太吉ら4人が逮捕された。この事件を口実として、非戦・反戦勢力を一掃するために、日帝は幸徳大逆事件をでっち上げ、数百人の社会主義者・無政府主義者を逮捕・検挙し、翌1911年24人に死刑判決、12人を処刑し、天皇(制)の凶暴性を示したのである。
社会主義者を一掃し、日本ナショナリズムを満展開し、韓国併合(1910年)、満蒙独立運動(1912年、15年)、第1次世界大戦参戦(1914年~)、山東出兵(1927、28年)、満州事変(1931年)へと突っ走るのである。
1911年に幸徳秋水が処刑された後、「大正デモクラシー」が開花する。労働組合(日本労友会など)が増加し、労働争議(八幡製鉄所の大争議など)の件数・参加人数とも増加、高止まりの状態で推移している(一覧表)。『マルクス伝』、『資本論』、『空想的及科学的社会主義』、『賃労働と資本』、『労賃・価格及利潤』、『国家と革命』、『帝国主義論』など共産主義文献が多数翻訳発行され、米騒動(1918年)が全国に波及し、小作争議も増加し、安田善次郎刺殺(1921年)、原敬首相刺殺(1921年)、虎の門事件(1923年)など左右のたたかいが火花を散らしていた時代である。
1912年から上杉慎吉と美濃部達吉の天皇機関説論争があり、美濃部達吉は「天皇は元首であるが、同時に憲法に従って政治(統治権)を行使する『機関』ともいえる。…したがって国家の『機関』である以上、天皇も『国家』意思に従わなければならない」と主張し、天皇主権=神権説を退け、1913年には機関説が勝利し、憲法は機関説で運用された。
1917年ロシア革命でソ連が誕生したことにより、国民のなかに共産主義思想が広まり(1922年日本共産党結成)、民衆のなかに権利意識が高揚し、普通選挙権獲得に関心が集まった。天皇制及び国家神道の動揺を懸念した政府は、普通選挙法制定(1925年)に抱き合わせて、治安維持法「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」を制定し、共産主義運動に致命的な規制をかけた。
この時代は、日本ナショナリズムにたいする批判が噴出し、大逆罪(死刑)と治安維持法による恫喝と言論封殺によって、辛うじて守られていたといえる。
(5)昭和初期~15年戦争
天皇機関説は大正から昭和の初めまで憲法学界の通説となったが、中国侵略戦争(1931年満州事変~)が始まる過程で、1935年美濃部達吉は不敬罪で告発され,『憲法撮要』など3著が発禁処分を受け、天皇機関説は政治的に葬られ、天皇主権説に逆戻りした。侵略戦争遂行のための天皇制ナショナリズムから不純物を取り除いたのである。
大逆罪(1982年)、爆発物取締罰則(1985年)に加えて、1925年に治安維持法(国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコト)が成立し、その本格的発動は1928年3・15弾圧(1568人検挙)であり、山本宣治刺殺(1929年)、小林多喜二(1933年)や鶴彬(1938年)を獄死させ、約7万人が送検され、拷問死90人を含め、少なくとも400人強が獄死している。
このように、日帝は弾圧と白色テロルによって人民の気孔をふさいだが、この時期(昭和初期)の労働争議は大正期よりも多発しており、1940年の産業報国会によって労働組合の活動が強制的に停止されるまで、人民の権利意識が広範かつ強固に存在していた。このような労働者人民の抵抗を内部から解体するために、文学者、画家、音楽家、宗教者、哲学者などを総動員して、日本ナショナリズムを強制したのである。
筆者の住む石川県でいえば、詩人・室生犀星は、1943年の詩集『美以久佐(みいくさ)』の序詩では、「みいくさは勝たせたまへ/つはものにつつがなかれ/みいくさは勝たせたまへ/もろ人はみないのりたまへ/みいくさは勝たせたまへ/食ふべくは芋はふとり/銃後ゆたかなれば/みいくさびとよ安らかなれ/みいくさは勝たせたまへ」と戦勝を祈念し、「マニラ陥落」では、軍靴がグアム、ウエーキ、香港、マレー、ボルネオ、シンガポール、マニラへと踏みにじっていくことに、犀星は快哉を叫んでいる。これらの戦争詩は劇場やラジオで朗読され、国民の戦意昂揚に資した。
真宗僧侶の暁烏敏(あけがらすはや)は1936年の説教で、「今日の日本臣民は子供をお国の役に立つように、天皇陛下の御用をつとめるように念願して育てにゃならんのであります。…日本の臣民は天皇陛下の家の子供として、天皇陛下の御用にたち、…百姓でも、町人でも、すべてその心得がなくてはならんのであります」、「天皇機関説を称える人の態度を見ますと、…頭の上がった態度であります。天皇は神聖にして侵すべからずという国体明徴の道は臣民の道であります。我々はこの臣民としての自覚がなければならんのであります」と、宗教界も率先して天皇への忠誠を要求している(『皇道・神道・仏道・臣道』)。
画家宮本三郎は1940年に中国に画家として従軍し、41年には「南苑攻撃図」、その翌年に「山下―パーシバル会見図」を描き、45年敗戦まで戦争画を多数描き続けている。
このような文学、宗教、絵画などの表現者がこぞって体制に順応していった裏には、革命党の不在、すなわち人民に開かれた非公然の出版・配布の経験的蓄積の未成熟があるのではないだろうか。しかし、上海では「大韓民国臨時政府」(1919年~)、タイでは「自由タイ」(1943年~)、フィリピンでは「抗日人民軍=フクバラハップ」(1942年~)、マレー半島では「マラヤ人民抗日軍」(1942年~)、ビルマでは「パサパラ(反ファシスト人民自由連盟)」(1944年~)が、日帝の暴力支配のもとで結成されたたかいぬいている。
このように1931年満州事変から始まった15年戦争によって、数千万のアジア人民の殺戮、310万人の日本人兵士・市民の死をもたらしたものこそ、日本ナショナリズム(天皇制+国益・排外主義)であり、とりわけ「東亜新秩序」(「諸民族の自主独立」、「民族の伝統尊重と創造性伸暢」、「互恵経済発展」、「欧米からの植民地解放」、「同祖同族論」、「家族国家観(家長=日本、家族=諸民族)」)にもとづく戦時ナショナリズム=大東亜共栄圏構想であり、主体的側面としては革命党不在の問題を挙げねばならないだろう。
とはいえ、「大東亜共栄圏構想」は実体を伴わず、アジア市場を狙う米帝の参戦が立ちはだかり、敗戦を迎え、戦時日本ナショナリズムは破綻したのである。
【2】現代日本のナショナリズム
(6)敗戦期
1945年に敗戦を迎えた日本で、破綻した日本ナショナリズムはどのように「変化・再編」されたのだろうか。『読売新聞』の世論調査(1948年8月15日発表)によれば、<天皇制存続=90.3%、天皇制廃止=4.0%>という結果がある。他方では、同年9月の日本世論調査研究所の文化人・議員・財界人1000人の「指導者層」を対象にしたアンケートでは、<退位賛成=約50%、退位反対=約44%>であった。ここから見えることは高学歴者のなかでは退位支持が多数を占めているものの、一般市民の天皇制支持は解体されず、天皇(制)ナショナリズムは戦後も人々の意識を支配していたことである。
日本軍に侵略され、大きな被害を被ったアジア諸国民は天皇制廃止を主張したが、このような国民意識を把握していた米占領軍は、「間接植民地統治方式」で日本を支配するために天皇制を残し、とりあえず日帝軍部の解体・無力化を図ったのである。
戦時期の苛酷な弾圧・投獄(前述)と転向によって、反体制組織も思想も壊滅状態であり、日帝敗北後、非転向政治犯3000人が釈放(岩波『近代日本総合年表』)されたものの、旧体制(天皇制)はもちろん、米占領軍を打倒すべき組織的主体は、あらかじめ解体されていた。他方植民地支配下の朝鮮では何万人もの活動家が亡命し、朝鮮本国に檄を発し、日帝敗北後に帰国し、民衆と共にたたかいぬいた歴史を持っている。
論壇の分裂
戦後期の論壇には、「アメリカの民主主義に降伏するのではない、皇室中心の民主主義である」(45年9月、『毎日新聞』)、「君民一如の民主政治」(45年12月、鳩山一郎)、「国民は天皇を愛する。愛するところに真の民主主義がある」(46年4月、津田左右吉)など、民主主義と天皇制の共存論が溢れていた。
他方では「天皇制は個人の自由を奪い、責任の観念を不可能にし、道徳を頽廃させる」(46年3月、加藤周一)、「天皇制の由来は…悠久なものではなく、…天皇制は明治維新以来70年来のもの」(46年3月、羽仁五郎)、「天皇制は明治以後はじめて出来た」(46年9月、井上清)、「天皇制が…日本人をして…半永久的な未成年段階にとどまらせる」「天皇制廃止を目標として国民的成長」(49年、中野好夫)、「(天皇制を)倒さなければ日本人の道徳的自立は完成しない」(52年、丸山真男)と、天皇(制)にたいする賛否が拮抗していたのである。
革命党の役割と試練
このように国論が真っ二つに分裂しているときにこそ、革命党の天皇制批判と行動が重要であった。共産党は1945年10月の「人民に訴う」のなかで、天皇制打倒・人民共和政府樹立を声明し、志賀義雄は「天皇こそ最大の戦争犯罪人」(11月)、宮本顕治は「専制君主(=天皇)の永続的支配はその民族の汚辱」(46年2月)と天皇制を批判したが、他方では野坂参三は「専制権をもたぬ天皇」(1945年4月延安で)の残存を容認し、「民主戦線によって祖国の危機を救え」(1946年1月)と祖国防衛論に陥いっていたのである。
戦後期を迎えた共産党には、「侵略戦争の敗北を革命に転化する」という思想的・運動的準備もなく、天皇制打倒のスローガンもおろし、米占領軍に恭順の意を示しながら(解放軍規定)、ついに1950年レッドパージで壊滅的な打撃を受けたのである。
すなわち、敗戦によって既成権力(天皇制と軍部)の権威が地に落ちた、千載一遇のチャンスに、占領軍に支えられた日帝ブルジョアジーは、戦前の<天皇制+軍部>による統治から、<象徴天皇制+民主主義+憲法9条>への転換を図って、生きのびたのである。ここに象徴天皇制という新たなナショナル・アイデンティティが形成されたのである。
(7)1960年代~
敗戦帝国主義・日帝は1965年日韓条約を転換点として、アジア再侵略(経済的)の道を歩み始めている。共産党は米帝従属論のもとで、「日韓条約」を反米民族闘争の課題と位置づけ、革共同は「日韓条約=再植民地化」として、「日韓(条約)の本質を日帝の(再)植民地支配としてとらえ、反植民地闘争の原則的立場を確立、…植民地支配にたいする帝国主義本国プロレタリアートの国際的任務」(1966年「第3回大会報告」)と位置づけてたたかっている。
それは、ベトナム反戦・大学闘争(帝国主義大学解体)に引き継がれ、1970年「7・7」告発によって、近代以降のアジア侵略への自己批判と現代日帝の再侵略阻止を、みずからに課したのである。
その後の日帝は帝国主義として、法改正を繰り返しおこない、繰り返し自衛隊を派兵し、建国記念日(紀元節)を設け、日の丸を国旗とし、君が代を国歌とし、教育基本法を改悪(愛国心)し、スポーツで祖国日本を讃美し、領土問題で対韓国・中国排外主義をあおり、戦前型の日本ナショナリズム(元首天皇制+国益・排外主義)へと国民を導こうとしている。
(8)21世紀の日本ナショナリズム
かつて、日本ナショナリズムは大逆罪、爆発物取締罰則、治安維持法によって保守・強制されていたが、「象徴天皇制+民主主義+憲法9条」を内容とする戦後の日本ナショナリズムは占領軍支配下で生まれ、爆発物取締罰則、破防法(1952年)、凶器準備集合罪(1958年)、共謀罪(2017年)などの弾圧法体制によって保守・強制されている。
その象徴天皇制は、戦後の統治システムの重要な一角を占め、日本ナショナリズムの重要な要素をなし、人民から自立心と主体性を奪ってきたが、しかし、21世紀の日帝にとって、「象徴天皇制+民主主義+憲法9条」という戦後の統治形態そのものが桎梏と化している。①解釈改憲で自衛隊を強大化し、海外に派遣してきたが、憲法9条の制約を取り払って、ストレートに対外軍事行動が出来る国への衝動に駆られている。②新型コロナウイルス問題を奇貨として、安倍政権は火事場泥棒のように、政府に権限を集中させ、国民の権利を制限する「非常事態条項」を憲法に潜り込ませようと画策している。
③さらに天皇を象徴から元首に変えることによって、戦後民主主義を根底から変質させ(立憲君主制へ)、内に向かっては従順な臣民へ、外に向かっては兇暴な侵略者へと変えようとしているのである。それは、まごう事なき天皇制・天皇教+国益・排外主義+戦争によって構成された戦前型日本ナショナリズムへの志向である。
その実践的手法として、「国際貢献論」「美しい国づくり」「戦後レジームからの脱却」「新しい生活様式」などと、歯の浮くようなスローガンを並べ立てて、21世紀日本ナショナリズムを再構成しようとしているが、これに対置すべき「1970・7・7」思想(連帯し内乱へ)を、2007年「7月テーゼ」で、革共同自身が否定・清算してしまったのである。「被差別・被抑圧人民のたたかいと労働者階級の自己解放闘争を並列的に扱う傾向」、「出身の共産主義者は、自己をまず労働者階級解放闘争をたたかう主体として確立」などと言いなして、差別・排外主義とのたたかいを後景に押しやり、二義的な課題とし、被差別人民とりわけアジア人民との連帯・共闘論を否定した(北陸では不二越強制連行訴訟支援からの逃亡)。
120年前の日露戦争時に、「愛国主義と軍国主義とは、諸君(ロシア社会民主党)と我等と共通の敵也」と呼びかけ、「朝鮮併呑論を評す」で、朝鮮併合を真っ向から批判した幸徳秋水の「革命的祖国敗北主義・侵略戦争を内乱へ」論をいまこそ継承し、21世紀をたたかいぬくために、早急に21世紀日本ナショナリズムを対象化するための諸論沸騰を期待したい。
参考資料
纐纈厚著『侵略戦争 歴史的事実と歴史認識』(1999年)/色川大吉著『自由民権』(1981年)/小熊英二著『<民主>と<愛国>』(2002年)/塩川伸明著『民族とネイション ナショナリズムという難問』(2008年)/植木和秀著『ナショナリズム入門』(2014年)/米原謙著『東アジアのナショナリズムと近代』(2011年)/原佑介論文「木下尚江の『大日本魂』批判」(2008年)/『大東亜聖戦大碑資料集(1)』(2001年)/『島田清次郎の実像』(2019年)/『上海爆弾事件後の尹奉吉』(2020年)/『石川県ゆかりの表現者と戦争』(2020年)/マルクス・エンゲルス著『共産党宣言』(1848年)/大澤真幸著『近代日本のナショナリズム』(2011年)/岩波『近代日本総合年表』(1968年)/山村信一論文「国民帝国とナショナル・アイデンティティの逆説」(2017年『ナショナル・アイデンティティを問い直す』所収)/『2007年7月テーゼ学習・討議資料』(前進社)/生方敏郎著『明治大正見聞史』(1979年)/「天皇制ボナパルティズム論」(1960年『本多延嘉著作選』)/泉鏡花著『予備兵』『『琵琶伝』『柳小島』など/室生犀星詩集『美以久佐(みいくさ)』(1943年)/暁烏敏著『皇道・神道・仏道・臣道』(1937年北安田パンフレット)/