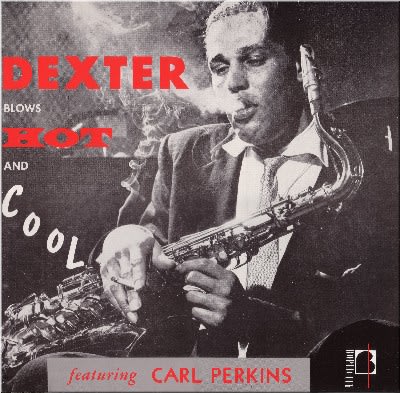先週の日曜日同様、今日も数日前の天気予報では「曇り後雨」で思わしくなった。しかし、当日が決てみると天気は良好であった。
朝の7時に家を出た時にすでに空気は暖かかった。念のためにサイクルジャージの背面ポケットに綺麗に畳んだウィンドブレーカーを入れていたが、それが使われることがないであろうことは朝少し走っただけで分かった。
この一週間は蓄積した疲労を軽減するため、週に3回行われるジムでのトレーニングは軽めのメニューで済ませていた。そのおかげか、体の疲労度は軽減され、幾分軽く感じられた。
Mt.富士ヒルクライムの本番まであと2週間・・・これから1週間はまたトレーニングの強度を上げる予定である。そして本番前1週間はまた緩める。その調整方法で、本番の6月14日において、調子がピークを迎えられるといいのであるが・・・
今日の参加者は7名であった。その参加者のロードバイクの内訳はRIDLEY3台、ORBEA2台、BH1台、そして私のKUOTA1台である。
脚の血管の手術で久しぶりに参加したメンバーがいたので、行き慣れた正丸峠に行くこととなった。往復距離は約100km。
今日も時折高ケイデンスデ走行を試した。相変わらずケイデンスが120を超えるとお尻がひょこひょこする。
多摩湖サイクリングロードを抜けて旧青梅街道を進んだ。昨日の土曜日も暑かったが、今日も暑くなりそうである。それにしてもまだ5月だというのに・・・ちょっと異常である。
異常といえば、気温が高いだけでなく、最近は地震や火山の噴火などが続いている。昨日の晩も体感的にはやや大きめと感じられた地震があった。「大震災」と名がつくような大きなものが来ないといいが・・・
岩蔵街道に入るとますます暑さはしっかりとしたものになった。岩蔵温泉郷を抜けてしばらく走った先のファミリーマートでいつものように休憩をとった。
「補給食は何にするか・・・」冷房が効いていて気持ちの良いファミリーマートの店内でしばし迷った。迷った結果「和風ツナマヨおにぎり」と「塩大福」に決まった。それらを冷たいほうじ茶で体内に流し込んでいった。
休憩後山伏峠の上り口を目指してリスタートした。短めのアップダウンを乗り越えていって、名栗川沿いに伸びる県道に達して左折した。
ここから緩やかな上りが続く。距離は10数キロ。信号も数えるほどしかなく、気持ち良く走れるエリアである。風は向かい風・・・
その向かい風を切り分けていって山伏峠の上り口に到着した。太陽は遮るものがいないことをいいことに、さんさんとその光を地上に降り注いでいた。
朝の7時に家を出た時にすでに空気は暖かかった。念のためにサイクルジャージの背面ポケットに綺麗に畳んだウィンドブレーカーを入れていたが、それが使われることがないであろうことは朝少し走っただけで分かった。
この一週間は蓄積した疲労を軽減するため、週に3回行われるジムでのトレーニングは軽めのメニューで済ませていた。そのおかげか、体の疲労度は軽減され、幾分軽く感じられた。
Mt.富士ヒルクライムの本番まであと2週間・・・これから1週間はまたトレーニングの強度を上げる予定である。そして本番前1週間はまた緩める。その調整方法で、本番の6月14日において、調子がピークを迎えられるといいのであるが・・・
今日の参加者は7名であった。その参加者のロードバイクの内訳はRIDLEY3台、ORBEA2台、BH1台、そして私のKUOTA1台である。
脚の血管の手術で久しぶりに参加したメンバーがいたので、行き慣れた正丸峠に行くこととなった。往復距離は約100km。
今日も時折高ケイデンスデ走行を試した。相変わらずケイデンスが120を超えるとお尻がひょこひょこする。
多摩湖サイクリングロードを抜けて旧青梅街道を進んだ。昨日の土曜日も暑かったが、今日も暑くなりそうである。それにしてもまだ5月だというのに・・・ちょっと異常である。
異常といえば、気温が高いだけでなく、最近は地震や火山の噴火などが続いている。昨日の晩も体感的にはやや大きめと感じられた地震があった。「大震災」と名がつくような大きなものが来ないといいが・・・
岩蔵街道に入るとますます暑さはしっかりとしたものになった。岩蔵温泉郷を抜けてしばらく走った先のファミリーマートでいつものように休憩をとった。
「補給食は何にするか・・・」冷房が効いていて気持ちの良いファミリーマートの店内でしばし迷った。迷った結果「和風ツナマヨおにぎり」と「塩大福」に決まった。それらを冷たいほうじ茶で体内に流し込んでいった。
休憩後山伏峠の上り口を目指してリスタートした。短めのアップダウンを乗り越えていって、名栗川沿いに伸びる県道に達して左折した。
ここから緩やかな上りが続く。距離は10数キロ。信号も数えるほどしかなく、気持ち良く走れるエリアである。風は向かい風・・・
その向かい風を切り分けていって山伏峠の上り口に到着した。太陽は遮るものがいないことをいいことに、さんさんとその光を地上に降り注いでいた。