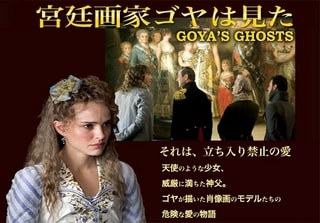
"GOYA'S GHOSTS"
2006年/米国・スペイン/114分
【監督】 ミロス・フォアマン
【製作】 ソウル・ゼインツ
【脚本】 ミロス・フォアマン ジャン=クロード・カリエール
【出演】 ハビエル・バルデム/ロレンソ神父
ナタリー・ポートマン/イネス・ビルバトゥア、アシリア
ステラン・スカルスガルド/フランシスコ・デ・ゴヤ
ランディ・クエイド/国王カルロス4世
ミシェル・ロンズデール/異端審問所長
ホセ・ルイス・ゴメス/トマス・ビルバトゥア
>>2008-11-23 青森松竹アムゼ
--------------------------------------------------------------------------------------
ゴヤの「裸のマハ」(1800年)。小さい頃に画集かなんかで見て、「見てはいけないものを見てしまった…」という気持ちにさせられたものです(アングルの「泉」も同様)。それ以来、私にとっては、「ゴヤ」といえばあの絵、でした。同じ構図で「着衣のマハ」(1801-03年)という作品もあることも知りましたが、やっぱり「裸」のインパクトには負ける。長じて、ゴヤの「5月3日」とか「わが子を食らうサトゥルヌス」(1821-23年)といった作品も知るようになりましたが、やっぱり小さいときの印象ってずっと残っているもので。

そんなゴヤの映画、しかも、「カッコーの巣の上で」、「アマデウス」の名匠ミロス・フォアマン監督作品とあっては、見逃すわけにはいかない。期待どおり、なかなか興味深い物語でした。ゴヤの作品そのものはそれほど出てくるわけではないのですが(エンドロールでこれでもかというくらい出てきますけど)、異端審問、ナポレオンによるスペイン征服など、歴史映画としても十分楽しめます。
それにしても、「家政婦は見た」じゃあるまいし、何でしょうかこの邦題は…。スペインを代表する画家の一人、フランシスコ・デ・ゴヤが、物語全体の生き証人としての役割を担っているわけですが、別に「のぞき見ていた」わけでもないのに。原題は"Goya's Ghost"。ま、確かに、直訳の「ゴヤの亡霊」じゃオカルトものと間違われそうではありますが。
もっとも、この映画の主役はゴヤにあらず。ハビエル・バルデムが演じるロレンソと、ナタリー・ポートマン演じるイネス。ハビエル・バルデムといえば、「ノー・カントリー」の不気味な殺人鬼役がやたらと印象的ですが、今回は、時代の奔流に流される野心たっぷりの男を見事にこなしています。あの顔はあまりにも印象が強くて忘れようにも忘れられないですなア。
かたや、ナタリー・ポートマン。私にとっては「ブーリン家の姉妹」に続いての御見参。美しいだけの女優じゃないことが、この映画でも証明されていますね。ふぅ~。
この2人の男女それぞれの肖像画を描いたのがゴヤ、というのがこの映画の設定。フランシスコ・ゴヤは、当時の国王カルロス4世(在位1788-1808)のもとで宮廷画家として活躍していました。イネスは裕福な商人の娘。その美しさにゴヤも惚れ込み、マドリードのサン・アントニオ・デ・ラ・フロリーダ教会の天井画に彼女の姿を描いたほど。肖像画を描いてもらうためにゴヤのアトリエにやってきたロレンソ神父は、そこで彼女の肖像画を見て心を奪われる。
映画のあとでゴヤの画集を見ていたら、映画で出てきたイネスの肖像画とそっくりな絵を見つけました。「サバーサ・ガルシア」(1806-11年)。映画では、ナタリー・ポートマンそのものの肖像画でしたが、ホンモノの方もかなり美しい女性です。ゴヤが実際に描いたフローリダ教会の天井画も画集に載っていました。教会のドームの内側に描かれたフレスコ画「パドヴァの聖アントニウスの奇跡」(1798年)。高さ9mもの天井に絵を描くのは相当な労力が必要だったことでしょう。むろん、かつてミケランジェロが描いたシスティナ礼拝堂の天井画「天地創造」に比べれば知名度は低いかもしれませんが、ゴヤの天井画も、だまし絵のような欄干の周囲に人物を配置し、中心に空を据えるといった構図、暖かく明るい色調などに思わず目を奪われてしまう。見事な作品だと思います。
さて、ロレンソ神父は、異端審問の厳格な執行を異端審問所長に進言します。ふだんから目を光らせていれば、異端はすぐしっぽを出すはずだと。こうして、とある居酒屋にも「異端探し」の網が張り巡らされる。そこにたまたま来ていたイネスが、「豚肉を口にしなかった」ことで、ユダヤ教徒ではないかと疑われる。イネスは異端審問所に召還され、ユダヤ教徒でないことを証明せよと命じられる。
誰しも、ここで、イネスが嫌いなはずの豚肉を我慢してでも食べて見せるのかなと思う。それで「無実」が証明されるのかなと。ところが、スペインの異端審問はそんな甘っちょろいものじゃない。イネスは、いきなり後ろ手に縛られ、天井から吊されて「自白」を強要されるのです。つまり、異端審問とは、「拷問」とほぼ同義ということ。その場面は出てきませんでしたが、イネスは、痛みに耐えかね、ユダヤ教徒であることを認めてしまったらしい。
イネスの父トマスは、ゴヤを通じてロレンソに助けを求める。ロレンソは、地下牢につながれたイネスを見て、それがあの肖像画の娘であることに気づく。思わず彼女を抱きしめるロレンソ。しかし、彼には彼女を救うだけの権限はない。業を煮やしたトマスは、ロレンソを夕食に招待すると見せかけて、彼を同じように天井から吊し、拷問するという強硬手段に打って出る。そして、ロレンソに「自分はチンパンジーとオランウータンの合いの子である」という文書にサインさせるのです。
「神への信仰は身体の痛みに打ち克つことができる」というロレンソの言葉を逆手に取ったわけです。ロレンソは、トマスから預かった多額の寄付金を審問所長に届けますが、いったん「自白」したものを所長といえども覆すわけにはいかない。イネス釈放の願いは退けられてしまう。
そこでトマスは、今度は国王に直言する。ロレンソのサインした文書を携えて。トマスは、ロレンソを陥れることが目的ではなく、拷問による自白がいかに信憑性のないものかを言いたかったのです。その文書は教会の上層部にまで届き、ロレンソは「異端」として追われる身となり、いずこかへ姿を消す。そして、イネスの安否は…?
それから15年の時が流れる。1804年にフランス皇帝となったナポレオンは、「自由と平等」を旗印にヨーロッパ各地を蹂躙していました。1808年、その刃はスペインにも向けられます。怒濤のように押し寄せてくるナポレオン軍の前に、スペインの国土は瞬く間に蹂躙されてしまいます。
さて、映画はここからが面白いところ。ロレンソはフランスに逃亡していたことが明らかになります。フランスで、革命の洗礼をどっぷり浴びた上に、ナポレオンの部下の一人として故郷に戻ってくる。ナポレオンは、自分の兄ジョゼフをスペイン王に据えると、古い制度を次々に破壊していきます。教会制度や異端審問もその一つ。異端審問所は廃止され、所長は裁判にかけられる。
15年間地下牢につながれていたイネスも釈放される。もうあの美しかった面影はなく、ひどい顔。覚束ない足取りで自分の家に戻る。ところが、既に家族の姿はなく、ナポレオン軍によって荒らされた家の中には死体が転がっている始末。イネスは次にゴヤのもとを訪れる。そして、ゴヤに驚くべき事実を告げるのです…。
さて、イネスの人生を大きく狂わせることになるのが「異端審問」です。
「宗教裁判」とも言われるこの制度は、カトリックの正統教義が確立した時に始まりました。「異端」は「正統」があるから存在する。カトリックすなわち「正統」教義に反する考えはすべて「異端」とみなすことは、ローマ教皇を頂点とするカトリック教会の発展に不可欠だったのです。
中世には何度か大規模な異端への弾圧が行われていますが、17世紀初頭、ルターによる宗教改革によって「プロテスタント」と呼ばれる新教各派が出現すると、彼らも当然「異端」とみなされることになりました。そうしたいわゆる「反宗教改革」と呼ばれるカトリックの巻き返し運動の拠点となったのがスペインでした。
もともとスペインという国は、8世紀以降イベリア半島にやってきたイスラム教徒との戦い(レ・コンキスタ=国土回復運動)の中で中央集権体制が整えられてきた国です。レ・コンキスタは、1492年をもって終了しますが、その中心にいたのは、教会関係者ではなく、世俗権力者つまり国王でした。したがって、スペインは、ローマにいる教皇よりも、国王が教会を支配する傾向が強かったのです。つまり異端審問は、国王の権力を示す絶好の機会でもありました。
加えて、スペインの異端審問の特徴は、キリスト教徒に改宗したイスラム教徒やユダヤ教徒も対象となっていたことがあります。カトリックを旗印に国内の統一を図ろうとする国王にとって、彼らは大きな不安材料だったのです。たとえ改宗したとしても、いったん押された「異端」の烙印はそう容易には消せるものではありませんでした。スペイン異端審問の犠牲者の数は、100万人にものぼると言われています。
この映画の中で、異端審問をかつてのように厳しく適用するべきだと主張するのがロレンソ。それは国王カルロス4世にうまく取り入って、自分の出世につなげようというねらいがあったものと思われます。皮肉にも、そのことで彼は自ら墓穴を掘ることになるのですが。
それにしても、豚肉を食べなかったというだけで「異端」の疑いをかけられるとは、何とも不合理な話です。しかも、「疑いをかけられる」ということは、ほとんど「有罪」に等しいわけですから。この時代のスペインの異端審問が、必ずしも、「あつい信仰心」に裏打ちされたものだけではなかったこと、宗教と政治がいかに表裏一体のものであったかということが、とてもよくわかります。
さて、後半では、ゴヤの生涯についてもざっと触れてみたいと思います。王家御用達の「宮廷画家」だけが、彼の顔ではなかったようです。
2006年/米国・スペイン/114分
【監督】 ミロス・フォアマン
【製作】 ソウル・ゼインツ
【脚本】 ミロス・フォアマン ジャン=クロード・カリエール
【出演】 ハビエル・バルデム/ロレンソ神父
ナタリー・ポートマン/イネス・ビルバトゥア、アシリア
ステラン・スカルスガルド/フランシスコ・デ・ゴヤ
ランディ・クエイド/国王カルロス4世
ミシェル・ロンズデール/異端審問所長
ホセ・ルイス・ゴメス/トマス・ビルバトゥア
>>2008-11-23 青森松竹アムゼ
--------------------------------------------------------------------------------------
ゴヤの「裸のマハ」(1800年)。小さい頃に画集かなんかで見て、「見てはいけないものを見てしまった…」という気持ちにさせられたものです(アングルの「泉」も同様)。それ以来、私にとっては、「ゴヤ」といえばあの絵、でした。同じ構図で「着衣のマハ」(1801-03年)という作品もあることも知りましたが、やっぱり「裸」のインパクトには負ける。長じて、ゴヤの「5月3日」とか「わが子を食らうサトゥルヌス」(1821-23年)といった作品も知るようになりましたが、やっぱり小さいときの印象ってずっと残っているもので。

そんなゴヤの映画、しかも、「カッコーの巣の上で」、「アマデウス」の名匠ミロス・フォアマン監督作品とあっては、見逃すわけにはいかない。期待どおり、なかなか興味深い物語でした。ゴヤの作品そのものはそれほど出てくるわけではないのですが(エンドロールでこれでもかというくらい出てきますけど)、異端審問、ナポレオンによるスペイン征服など、歴史映画としても十分楽しめます。
それにしても、「家政婦は見た」じゃあるまいし、何でしょうかこの邦題は…。スペインを代表する画家の一人、フランシスコ・デ・ゴヤが、物語全体の生き証人としての役割を担っているわけですが、別に「のぞき見ていた」わけでもないのに。原題は"Goya's Ghost"。ま、確かに、直訳の「ゴヤの亡霊」じゃオカルトものと間違われそうではありますが。
もっとも、この映画の主役はゴヤにあらず。ハビエル・バルデムが演じるロレンソと、ナタリー・ポートマン演じるイネス。ハビエル・バルデムといえば、「ノー・カントリー」の不気味な殺人鬼役がやたらと印象的ですが、今回は、時代の奔流に流される野心たっぷりの男を見事にこなしています。あの顔はあまりにも印象が強くて忘れようにも忘れられないですなア。
かたや、ナタリー・ポートマン。私にとっては「ブーリン家の姉妹」に続いての御見参。美しいだけの女優じゃないことが、この映画でも証明されていますね。ふぅ~。
この2人の男女それぞれの肖像画を描いたのがゴヤ、というのがこの映画の設定。フランシスコ・ゴヤは、当時の国王カルロス4世(在位1788-1808)のもとで宮廷画家として活躍していました。イネスは裕福な商人の娘。その美しさにゴヤも惚れ込み、マドリードのサン・アントニオ・デ・ラ・フロリーダ教会の天井画に彼女の姿を描いたほど。肖像画を描いてもらうためにゴヤのアトリエにやってきたロレンソ神父は、そこで彼女の肖像画を見て心を奪われる。
映画のあとでゴヤの画集を見ていたら、映画で出てきたイネスの肖像画とそっくりな絵を見つけました。「サバーサ・ガルシア」(1806-11年)。映画では、ナタリー・ポートマンそのものの肖像画でしたが、ホンモノの方もかなり美しい女性です。ゴヤが実際に描いたフローリダ教会の天井画も画集に載っていました。教会のドームの内側に描かれたフレスコ画「パドヴァの聖アントニウスの奇跡」(1798年)。高さ9mもの天井に絵を描くのは相当な労力が必要だったことでしょう。むろん、かつてミケランジェロが描いたシスティナ礼拝堂の天井画「天地創造」に比べれば知名度は低いかもしれませんが、ゴヤの天井画も、だまし絵のような欄干の周囲に人物を配置し、中心に空を据えるといった構図、暖かく明るい色調などに思わず目を奪われてしまう。見事な作品だと思います。
さて、ロレンソ神父は、異端審問の厳格な執行を異端審問所長に進言します。ふだんから目を光らせていれば、異端はすぐしっぽを出すはずだと。こうして、とある居酒屋にも「異端探し」の網が張り巡らされる。そこにたまたま来ていたイネスが、「豚肉を口にしなかった」ことで、ユダヤ教徒ではないかと疑われる。イネスは異端審問所に召還され、ユダヤ教徒でないことを証明せよと命じられる。
誰しも、ここで、イネスが嫌いなはずの豚肉を我慢してでも食べて見せるのかなと思う。それで「無実」が証明されるのかなと。ところが、スペインの異端審問はそんな甘っちょろいものじゃない。イネスは、いきなり後ろ手に縛られ、天井から吊されて「自白」を強要されるのです。つまり、異端審問とは、「拷問」とほぼ同義ということ。その場面は出てきませんでしたが、イネスは、痛みに耐えかね、ユダヤ教徒であることを認めてしまったらしい。
イネスの父トマスは、ゴヤを通じてロレンソに助けを求める。ロレンソは、地下牢につながれたイネスを見て、それがあの肖像画の娘であることに気づく。思わず彼女を抱きしめるロレンソ。しかし、彼には彼女を救うだけの権限はない。業を煮やしたトマスは、ロレンソを夕食に招待すると見せかけて、彼を同じように天井から吊し、拷問するという強硬手段に打って出る。そして、ロレンソに「自分はチンパンジーとオランウータンの合いの子である」という文書にサインさせるのです。
「神への信仰は身体の痛みに打ち克つことができる」というロレンソの言葉を逆手に取ったわけです。ロレンソは、トマスから預かった多額の寄付金を審問所長に届けますが、いったん「自白」したものを所長といえども覆すわけにはいかない。イネス釈放の願いは退けられてしまう。
そこでトマスは、今度は国王に直言する。ロレンソのサインした文書を携えて。トマスは、ロレンソを陥れることが目的ではなく、拷問による自白がいかに信憑性のないものかを言いたかったのです。その文書は教会の上層部にまで届き、ロレンソは「異端」として追われる身となり、いずこかへ姿を消す。そして、イネスの安否は…?
それから15年の時が流れる。1804年にフランス皇帝となったナポレオンは、「自由と平等」を旗印にヨーロッパ各地を蹂躙していました。1808年、その刃はスペインにも向けられます。怒濤のように押し寄せてくるナポレオン軍の前に、スペインの国土は瞬く間に蹂躙されてしまいます。
さて、映画はここからが面白いところ。ロレンソはフランスに逃亡していたことが明らかになります。フランスで、革命の洗礼をどっぷり浴びた上に、ナポレオンの部下の一人として故郷に戻ってくる。ナポレオンは、自分の兄ジョゼフをスペイン王に据えると、古い制度を次々に破壊していきます。教会制度や異端審問もその一つ。異端審問所は廃止され、所長は裁判にかけられる。
15年間地下牢につながれていたイネスも釈放される。もうあの美しかった面影はなく、ひどい顔。覚束ない足取りで自分の家に戻る。ところが、既に家族の姿はなく、ナポレオン軍によって荒らされた家の中には死体が転がっている始末。イネスは次にゴヤのもとを訪れる。そして、ゴヤに驚くべき事実を告げるのです…。
さて、イネスの人生を大きく狂わせることになるのが「異端審問」です。
「宗教裁判」とも言われるこの制度は、カトリックの正統教義が確立した時に始まりました。「異端」は「正統」があるから存在する。カトリックすなわち「正統」教義に反する考えはすべて「異端」とみなすことは、ローマ教皇を頂点とするカトリック教会の発展に不可欠だったのです。
中世には何度か大規模な異端への弾圧が行われていますが、17世紀初頭、ルターによる宗教改革によって「プロテスタント」と呼ばれる新教各派が出現すると、彼らも当然「異端」とみなされることになりました。そうしたいわゆる「反宗教改革」と呼ばれるカトリックの巻き返し運動の拠点となったのがスペインでした。
もともとスペインという国は、8世紀以降イベリア半島にやってきたイスラム教徒との戦い(レ・コンキスタ=国土回復運動)の中で中央集権体制が整えられてきた国です。レ・コンキスタは、1492年をもって終了しますが、その中心にいたのは、教会関係者ではなく、世俗権力者つまり国王でした。したがって、スペインは、ローマにいる教皇よりも、国王が教会を支配する傾向が強かったのです。つまり異端審問は、国王の権力を示す絶好の機会でもありました。
加えて、スペインの異端審問の特徴は、キリスト教徒に改宗したイスラム教徒やユダヤ教徒も対象となっていたことがあります。カトリックを旗印に国内の統一を図ろうとする国王にとって、彼らは大きな不安材料だったのです。たとえ改宗したとしても、いったん押された「異端」の烙印はそう容易には消せるものではありませんでした。スペイン異端審問の犠牲者の数は、100万人にものぼると言われています。
この映画の中で、異端審問をかつてのように厳しく適用するべきだと主張するのがロレンソ。それは国王カルロス4世にうまく取り入って、自分の出世につなげようというねらいがあったものと思われます。皮肉にも、そのことで彼は自ら墓穴を掘ることになるのですが。
それにしても、豚肉を食べなかったというだけで「異端」の疑いをかけられるとは、何とも不合理な話です。しかも、「疑いをかけられる」ということは、ほとんど「有罪」に等しいわけですから。この時代のスペインの異端審問が、必ずしも、「あつい信仰心」に裏打ちされたものだけではなかったこと、宗教と政治がいかに表裏一体のものであったかということが、とてもよくわかります。
さて、後半では、ゴヤの生涯についてもざっと触れてみたいと思います。王家御用達の「宮廷画家」だけが、彼の顔ではなかったようです。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます