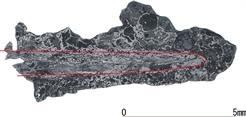ネアンデルタール人に続き、古い話で恐縮ですが、「世界最古の靴」が発見されたのだそうです(2010年6月10日付け各紙)。トルコ、イランの北、グルジアの南、カスピ海と黒海の間にあるアルメニアという国の洞窟から2年前に発見された革靴が、放射性炭素年代測定法による分析の結果、紀元前3,500年前のものと分かり、現在のところ、「世界最古」なのだとか。
片方しか見つかっていないそうですが、牛革製で24.5 . . . 本文を読む
モンゴルと聞いて思い浮かべる人物…といえば、かつてはチンギス・ハーン(ジンギス・カーン)で決まりでした。しかし、今や多くの日本人は、チンギス・ハーンより朝青龍の名を挙げることでしょう。
相撲は確かに超一流でした。だけど、それ以外の部分では…。ヒールを「演じている」というより、もともとそういう性質なのかもしれないなと思う。それにしても、朝青龍一人のせいで、モンゴルという国に対する日本人のイメージが . . . 本文を読む
ちょっとびっくりしたのですが、昨日、『「言葉」にとらわれないこと』で、行政や政治が市民に浸透させようとしている(?)言葉にはとらわれる必要はない、ということを書いたばかりなのですが、今日たまたま読んでいた『ガンジーの危険な平和憲法案』(C.ダグラス・ラミス著、集英社新書)という本に、こんなことが書かれていました。
言葉と思考方式には密接な関係がある。政府が、もし国の言葉を支配できるようになった . . . 本文を読む
約270字のお経、般若心経。その意図するところを一文字で表すとすれば、「空」に尽きると言われます。その「空」の精神を、日常生活の中で実践する具体的な方法が、「色即是空 空即是色」です。
『現代語訳 般若心経』(玄侑宗久著、ちくま新書)によれば、「色(しき)」とは、「五蘊(ごうん)」の一つ。五蘊とは、「私たちの身心を構成する五つの集まり、色、受、想、行、識を意味」するのだそうです。
・色…形ある . . . 本文を読む
来年の干支は虎ですね。
虎って、20世紀初頭には10万頭が生息していたのが、現在の個体数は、インド、東南アジアを中心として、多く見積もって5,000頭程度なんだそうです。これにはちょっとびっくりです。虎なんてもっとたくさんいるかと思ってました。ん…?…ということは、龍を除く十二支の中で、虎は最も個体数の少ない動物ということになりますね。
虎には、9亜種あるそうですが、そのうち、3種(ジャワト . . . 本文を読む
ハプスブルク家。
世界史を学んだことがある人なら、一度は聞いたことのある名前…ですよね? ヨーロッパの中世から近代史は、ハプスブルク家を避けては通れません。
あるいは、マリア・テレジアとかモーツァルトがらみでこのヨーロッパの名門に触れたことのある人も多いのかもしれません。
私の手元に、「歴史読本ワールド 総集編」『ハプスブルク家とウィーン大百科』(新人物往来社)という分厚いムック本があります . . . 本文を読む
古代史の大きなポイントの一つに、「鉄器」があります。正しくは、「鉄製武器の使用」か。これをフルに使った民族は、例外なく強大な国家を築いています。オリエントではヒッタイト人、アッシリア人、ギリシアではドーリア人。
人類の文化の発展は、道具の歴史と重なります。最初は石器や土器。人類が初めて使った金属は青銅でした。青銅器を使い、城壁を張り巡らした都市国家をつくり、意思の伝達に文字を用いる。この3つがそ . . . 本文を読む
約20年前の1989年夏、八戸市是川の風張遺跡で、女性作業員が掘り当てた縄文時代後期の土偶は、これまで見たことのない姿をしていました。
手のひらに乗るくらいの大きさ(高さ約20㎝)のその土偶は、両膝を立てた格好で座り、両手を正面で合わせていたのです。その姿から、のちに「合掌土偶」と呼ばれるようになるこの土偶が、先日、国宝に指定されることが内定しました。縄文時代の考古資料としては、全国で4例目 . . . 本文を読む
「どんなに壁が正しく、どんなに卵が間違っていても、私は卵の側に立つ」。
作家の村上春樹氏が、「イェルサレム賞」の授賞式の記念講演で語った言葉だそうです。『ノルウェーの森』、『海辺のカフカ』などの村上氏の作品は、ヘブライ語にも翻訳され、イスラエルでベストセラーになっているのだとか。イェルサレム賞は、イスラエル最高の文学賞で、アーサー・ミラー(米国)やホルヘ・ルイス・ボルヘス(アルゼンチン)など、歴 . . . 本文を読む
ルーブル美術館にある「サモトラケのニケ」は、以前、授業で使っていた自作の「世界史サブノート」の表紙に使ったことがあるくらい好きな彫刻ですが、「ニケ」というのは、ギリシア神話の勝利の女神。ローマ神話でいえば、「ヴィクトリア」に相当します。また、スポーツメーカーの「NIKE」もこの女神の名前に由来しています。
その「ニケ」と、「民衆」を意味する「ラーオス」が組み合わされて生まれたギリシア語の名前が「 . . . 本文を読む
バラク・オバマ氏が第44代米国大統領に決まりました。
「黒人初」とか「アフリカ系初」という形容詞が付けられるのは、いまだに米国が人種差別から抜け出せていないことの証でもありますね。日本でいえば明治維新の頃まで、米国には黒人奴隷制度が存在していました。「自由の国」という米国のイメージは、アングロサクソン系の白人が作りだしたものであり、黒人は蚊帳の外でした。しかも、奴隷制度そのものはなくなっても、黒 . . . 本文を読む
佐賀紀行の続きです。有田、伊万里で古今のやきものを堪能した我々は、一路北上、名護屋城跡に向かいました。
「夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡」
芭蕉が平泉・藤原三代の栄華をしのんで詠んだ句ですが、ここ名護屋城趾にも、この句はふさわしいと思いました。1590年に天下を統一した「太閤」豊臣秀吉が、次なるターゲットである朝鮮半島進出に向けて、前線基地としたのが名護屋城。それは、秀吉にとっては、ある . . . 本文を読む
おもしろい、おもしろくないはこの際別として、歴史の中で中学生や高校生が一番学んでおかなければならない部分は、もちろん「近現代史」でしょう。
社会人として世に出た若者が「第二次世界大戦」や「太平洋戦争」のことを知らないというのはどうなんだろう。「知らない」にもほどがあるというのはまさにこのことで、たとえば日本がかつて米国と戦争をしていたことさえ知らないというのは、どう考えてもぞっとしない。「原爆」 . . . 本文を読む
試しに7世紀あたりの世界地図を開いてみましょう。この世紀の初めに生まれたイスラム教の国、イスラム帝国(ウマイヤ朝)が西アジアからインド、中央アジア、北アフリカ、そしてヨーロッパのイベリア半島に至る広大な勢力を誇っているのがまず目を引きます。ヨーロッパにはまだイギリスもフランスもドイツもなく、そのルーツであるフランク王国という国があるだけ。もちろんバルカン半島から小アジアにかけては、かつてのローマ帝 . . . 本文を読む
インド・ムガル帝国のシャー・ジャハンが愛妃マハルの墓として建てたというタージ・マハル。白亜の大理石でできた左右対称の美しい霊廟。死ぬまでに一度は見てみたい建物です。
ところが、この「白亜の殿堂」が、完成から350年以上を経て、「白亜」でなくなっているという話は以前から聞いていました。その原因の一つは、最近とみに進む大気汚染なのだとか。急速に経済成長を遂げつつあるインドをある意味で象徴するような話 . . . 本文を読む