金欠ストレスによるものなのだろうか、先週から、背中の右肩甲骨の背骨側がかなり痛む。今朝もその痛みで4:00くらいに目が覚めてしまい、眠れなくなってしまった。しかたなく早々に起きだしたけれど、しかし眠い。朝食を食べてから、しばしまた寝ることになる。ところが背中が痛いので、寝ているのか、意識があるのかはっきりしない。途中、ウツラウツラと時計を見れば、そのたびに15分くらいは経過している。ということは、寝ているということなのだろう。
これまで家に置いていた本を会社に設置した書架に移動しているので、それを整理しないといけない。先日は、ヘンリー・ミラーの『北回帰線』(大久保康雄訳、新潮文庫)が出てきた。奥付は1989年31刷とあるので、これは、古書店で購入したものか、普通に書店で買ったものか、まったく判断ができない。それとも、友人から借りたまま返し忘れているとか。
中学生のとき、学校の図書館に河出書房新社だったかの世界文学全集が入っていて、その1冊が『南回帰線』だった。ある日、その本を手にしてペラペラ見てみたけれど、何が書いてあるのかさっぱりわからない。なにやら卑猥そうなことも書いてあるようだけれど、厨房の想像力ではそれがどう卑猥なのかもわからない。確か、ミラーに何某という男性の友人ができたら、それからケツの穴が痛くてしょうがなかったと書かれていたことは覚えている。ところが不覚にも、当方、当時は世間を知らない田舎の厨房だったので、それがどういう意味なのか理解もできなかったのだ。どうしてお尻が痛いのだろうと真剣に疑問に感じていたわけで、いま思い出せば、なんともかわいいガキであったものだ。
そんなこともあって、大学生のときに『北回帰線』を読んでみて、わかったようなわかんないような感じがし、それから数年して読み返してみて、またわかったようなわかんないような気がしたことは記憶している。しかしその間、『南回帰線』もまじめに読んだけれど、ジョージ・オーウェルが「ミラー自身は、その本質において一作かぎりの人間」と評したように、作品としては『北回帰線』が圧倒的に優れていた。つまり、『北回帰線』を読めば、ミラーはそれで充分だとも言える。
それで、今回改めてまた読み直してみて、結局、またしてもわかったようなわかんなかったような感慨に浸ったわけである。理由の一つは、小生が英語の苦手な人間で翻訳本として『北回帰線』を読む以上、どんなに素晴らしい翻訳であっても、元の英文の詩的なリズムを理解できるわけがないということが挙げられる。それと、キリスト教文化圏に生きている人間でもないので、ミラーがどんなに涜神的なことを述べてもそれほどショッキングでもないし(「ふぁっく・ゆう」なんて笑いでしかない)、聖書から字句の引用があっても原典からの意味を理解することはできない。『オーウェウル評論集3 鯨の腹の中で』(平凡社ライブラリー、川端康雄編)をたまたま読んでいたから、「鯨の腹の中」がどういうことなのかおぼろげな知識を持てたけれど、『北回帰線』の本文中に「鯨の腹の中」というフレーズが出てきても、その背景まで理解できるわけがないのだ。ところが、さっきから、その出てきた箇所を探しているのだけれど、それがなかなか見つからないのだ。
そこで例えば、本書の326~344Pにかけて、ミラーが滔々と述べている、宣言のような詩のような「文学の金本位制からの脱却」という部分は、小生にはなかなか理解しにくいという箇所なのだ(と、例を変えることにする)。結局、「われはすべて流れゆくものを愛する」というミルトンの句に行き着くのだろうけれど、そこまでに溢れ出てくる過剰なイメージを共有できている感じがまったくない。そこを共有できているであろうオーウェルは、(世の中のあらゆる悲惨なことを)「自分は受け入れる」態度なのだと論じている。ふ~ん、西洋ではそういうものなのか。「流れゆくものを愛する」ことと「現実を受け入れる」ことは、東洋的な精神態度においては異質のもののような気がするけれど、そんなことはどうでもいい。
つまり、上記したことのすべてが、この作品にとって本質的なことではない。極論してしまえば、本書を手にしてミラーに惹かれる人間は、惹かれたというその一点だけで特殊な精神的選民なのだ。しかし困ったことに、この選民はあくまでも「特殊」であって、社会的に立派であったり、優秀であったりするわけではまったくない。まともな社会生活を求めながらも、どこかそこに適応できず、ついつい混沌の世界に彷徨ってしまう人間。社会的な落伍者ということでもないし、上昇志向がないというわけでもないのだけれど、お上品にふるまうことよりも世界の根源を暴くことについつい熱中してしまう人間。自分自身に正直でありたいなんて言う奴を殴りたくなる人間。整然とした精神性に、整然性のゆえに嫌悪を感じてしまう人間。そういう人間が、ミラーに惹かれていくのだろう(と思う)し、多分、小生も(困ったことに)そういうタイプの人間なのだろう。
いま現在、ヘンリー・ミラーという作家が世界的にどの程度の人気があるのか知らないけれど、どんどん人気がなくなっていけばいい。選民は選民であることに存在意義があるのだ。選民は少数派でなければならない。そういえば昔、『ヘンリー&ジューン』という、ミラーを中心とした人間模様の映画があって、ミラーとアナイス・ニンとのハードな濡れ場が話題になって小生も観にいったけれど、全然面白くなかった。結局、ミラーのもつ混沌を、その人間関係に投影してもまったくしょうがないことなのだと理解したものだった。
これまで家に置いていた本を会社に設置した書架に移動しているので、それを整理しないといけない。先日は、ヘンリー・ミラーの『北回帰線』(大久保康雄訳、新潮文庫)が出てきた。奥付は1989年31刷とあるので、これは、古書店で購入したものか、普通に書店で買ったものか、まったく判断ができない。それとも、友人から借りたまま返し忘れているとか。
中学生のとき、学校の図書館に河出書房新社だったかの世界文学全集が入っていて、その1冊が『南回帰線』だった。ある日、その本を手にしてペラペラ見てみたけれど、何が書いてあるのかさっぱりわからない。なにやら卑猥そうなことも書いてあるようだけれど、厨房の想像力ではそれがどう卑猥なのかもわからない。確か、ミラーに何某という男性の友人ができたら、それからケツの穴が痛くてしょうがなかったと書かれていたことは覚えている。ところが不覚にも、当方、当時は世間を知らない田舎の厨房だったので、それがどういう意味なのか理解もできなかったのだ。どうしてお尻が痛いのだろうと真剣に疑問に感じていたわけで、いま思い出せば、なんともかわいいガキであったものだ。
そんなこともあって、大学生のときに『北回帰線』を読んでみて、わかったようなわかんないような感じがし、それから数年して読み返してみて、またわかったようなわかんないような気がしたことは記憶している。しかしその間、『南回帰線』もまじめに読んだけれど、ジョージ・オーウェルが「ミラー自身は、その本質において一作かぎりの人間」と評したように、作品としては『北回帰線』が圧倒的に優れていた。つまり、『北回帰線』を読めば、ミラーはそれで充分だとも言える。
それで、今回改めてまた読み直してみて、結局、またしてもわかったようなわかんなかったような感慨に浸ったわけである。理由の一つは、小生が英語の苦手な人間で翻訳本として『北回帰線』を読む以上、どんなに素晴らしい翻訳であっても、元の英文の詩的なリズムを理解できるわけがないということが挙げられる。それと、キリスト教文化圏に生きている人間でもないので、ミラーがどんなに涜神的なことを述べてもそれほどショッキングでもないし(「ふぁっく・ゆう」なんて笑いでしかない)、聖書から字句の引用があっても原典からの意味を理解することはできない。『オーウェウル評論集3 鯨の腹の中で』(平凡社ライブラリー、川端康雄編)をたまたま読んでいたから、「鯨の腹の中」がどういうことなのかおぼろげな知識を持てたけれど、『北回帰線』の本文中に「鯨の腹の中」というフレーズが出てきても、その背景まで理解できるわけがないのだ。ところが、さっきから、その出てきた箇所を探しているのだけれど、それがなかなか見つからないのだ。
そこで例えば、本書の326~344Pにかけて、ミラーが滔々と述べている、宣言のような詩のような「文学の金本位制からの脱却」という部分は、小生にはなかなか理解しにくいという箇所なのだ(と、例を変えることにする)。結局、「われはすべて流れゆくものを愛する」というミルトンの句に行き着くのだろうけれど、そこまでに溢れ出てくる過剰なイメージを共有できている感じがまったくない。そこを共有できているであろうオーウェルは、(世の中のあらゆる悲惨なことを)「自分は受け入れる」態度なのだと論じている。ふ~ん、西洋ではそういうものなのか。「流れゆくものを愛する」ことと「現実を受け入れる」ことは、東洋的な精神態度においては異質のもののような気がするけれど、そんなことはどうでもいい。
つまり、上記したことのすべてが、この作品にとって本質的なことではない。極論してしまえば、本書を手にしてミラーに惹かれる人間は、惹かれたというその一点だけで特殊な精神的選民なのだ。しかし困ったことに、この選民はあくまでも「特殊」であって、社会的に立派であったり、優秀であったりするわけではまったくない。まともな社会生活を求めながらも、どこかそこに適応できず、ついつい混沌の世界に彷徨ってしまう人間。社会的な落伍者ということでもないし、上昇志向がないというわけでもないのだけれど、お上品にふるまうことよりも世界の根源を暴くことについつい熱中してしまう人間。自分自身に正直でありたいなんて言う奴を殴りたくなる人間。整然とした精神性に、整然性のゆえに嫌悪を感じてしまう人間。そういう人間が、ミラーに惹かれていくのだろう(と思う)し、多分、小生も(困ったことに)そういうタイプの人間なのだろう。
いま現在、ヘンリー・ミラーという作家が世界的にどの程度の人気があるのか知らないけれど、どんどん人気がなくなっていけばいい。選民は選民であることに存在意義があるのだ。選民は少数派でなければならない。そういえば昔、『ヘンリー&ジューン』という、ミラーを中心とした人間模様の映画があって、ミラーとアナイス・ニンとのハードな濡れ場が話題になって小生も観にいったけれど、全然面白くなかった。結局、ミラーのもつ混沌を、その人間関係に投影してもまったくしょうがないことなのだと理解したものだった。















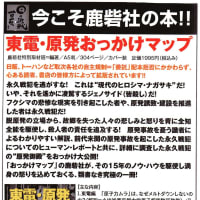




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます