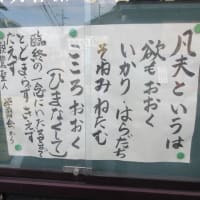前回の日記で敗戦直後に作られた、米軍による東京空爆により焼失した区域を示した「帝都近傍図」のことを書きました。
その中で、いわゆる「東京大空襲」から8日後の昭和20年(1945)の3月18日にお付きの者を引き連れて焼け跡の視察にやってきた昭和天皇の姿を目撃した作家の堀田善衛(1918~1998)が、そのとき目にした光景について一文を遺していると書きました。彼の代表作のひとつである「方丈記私記」に記されている一文です。この一文、前半部分で天皇の視察の様子を書いているのですが、その後半で、天皇が視察に来ていることに気づいた近くに居合わせた被災者たちの様子について書いています。この後半部分を以下に引用しておきます
東京大空襲天皇視察についての堀田氏の一文(筑摩書房、堀田善衛全集「方丈記私記」より)
《私が歩きながら考えていたことは、天皇自体についてではなかった。そうではなく廃墟でのこの奇妙な儀式のようなものが開始されたときに、あたりで焼け跡をほっくりかえしていた、まばらな人影がこそこそというふうに集まってきて、それが集まってみると実はかなりの人数になり・・・その人たちの口から出た言葉であった・・・・
私は方々に穴のあいたコンクリート塀の陰にしゃがんでいたのだが、これらの人々はほんとうに土下座して、涙を流しながら、陛下、私たちの努力が足りませんでしたので、むざむざと焼いてしまいました、まことに申訳ない次第でございます、命をささげまして、といったことを、口々に呟いていたのだ。
私はほんとうにおどろいてしまった。私はピカピカ光る小豆色の自動車と長靴とをちらちら眺めながら、こういうことになってしまった責任を、いったいどうしてとるものなのだろう、と考えていたのである。こいつらぜーんぶを海に放り込む方法はないものか、と考えていた。ところが責任は、原因を作った方にはなくて、結果を、つまり焼かれてしまい、身内の多くを殺されてしまった方にあることになる!そんな法外なことがどこにある!こういう奇怪な逆転がどうしていったい起こり得るのか!
ということが私の考えていたことの中枢であった。ただ一夜の空襲で十万人を超える死傷者を出しながら、それでいてなお生きる方のことを考えないで、死ぬことばかり考え、死の方へのみ傾いて行こうとするのは、これはいったいどういうことなのか・・・・なぜいったい、死が生の中軸でなければならないようなふうに政治は事を運ぶのか?
とはいうものの、実は私自身の内部においても、天皇に生命のすべてをささげて生きる、そのころのことばでいわゆる大義に生きることの、戦慄をともなった、ある種のさわやかさというものもまた、同じく私自身のなかにあったのであって、この二つのものが私自身のなかで戦っていた。せめぎ合っていたのである》
この光景を目にしたあと、堀田氏は近い将来日本が敗れることになることを覚悟して、日本を捨て上海へと向かいます・・・そのきとのことを「まるで梯子が外されることが分っていて二階に上るような心境であった」と彼は記しています
そして、東京大空襲から5か月後、終戦の日すなわち1945年8月15日、「終戦を告げる天皇のラジオ放送が流れて以降、人々が皇居前広場につめかけ、敗戦をわびた」「広場で13人が自害」(NHKのドキュメンタリーより)したとされています。堀田氏が焼け跡で目にした光景がそのまま繰り返されたのです・・・
この堀田氏の一文を読まれての感想はひとによって様々でありませう・・・なかなか重い、と申しますか、とりわけ最後の部分は・・・いろいろ考えさせる一文です。GGIがヘタクソな感想を述べるのは無駄というのもでありせう。それよりも、読み飛ばさないで、じっくりこの堀田氏の一文にじっくり向き合っていただければと思います・・・
今日の写真は軍服姿で部下の軍人たちを引きつれて焼跡を視察する昭和天皇の報道写真です。よろしければクリックしてご覧くださいませ
なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・
グッドナイト・グッドラック!
その中で、いわゆる「東京大空襲」から8日後の昭和20年(1945)の3月18日にお付きの者を引き連れて焼け跡の視察にやってきた昭和天皇の姿を目撃した作家の堀田善衛(1918~1998)が、そのとき目にした光景について一文を遺していると書きました。彼の代表作のひとつである「方丈記私記」に記されている一文です。この一文、前半部分で天皇の視察の様子を書いているのですが、その後半で、天皇が視察に来ていることに気づいた近くに居合わせた被災者たちの様子について書いています。この後半部分を以下に引用しておきます
東京大空襲天皇視察についての堀田氏の一文(筑摩書房、堀田善衛全集「方丈記私記」より)
《私が歩きながら考えていたことは、天皇自体についてではなかった。そうではなく廃墟でのこの奇妙な儀式のようなものが開始されたときに、あたりで焼け跡をほっくりかえしていた、まばらな人影がこそこそというふうに集まってきて、それが集まってみると実はかなりの人数になり・・・その人たちの口から出た言葉であった・・・・
私は方々に穴のあいたコンクリート塀の陰にしゃがんでいたのだが、これらの人々はほんとうに土下座して、涙を流しながら、陛下、私たちの努力が足りませんでしたので、むざむざと焼いてしまいました、まことに申訳ない次第でございます、命をささげまして、といったことを、口々に呟いていたのだ。
私はほんとうにおどろいてしまった。私はピカピカ光る小豆色の自動車と長靴とをちらちら眺めながら、こういうことになってしまった責任を、いったいどうしてとるものなのだろう、と考えていたのである。こいつらぜーんぶを海に放り込む方法はないものか、と考えていた。ところが責任は、原因を作った方にはなくて、結果を、つまり焼かれてしまい、身内の多くを殺されてしまった方にあることになる!そんな法外なことがどこにある!こういう奇怪な逆転がどうしていったい起こり得るのか!
ということが私の考えていたことの中枢であった。ただ一夜の空襲で十万人を超える死傷者を出しながら、それでいてなお生きる方のことを考えないで、死ぬことばかり考え、死の方へのみ傾いて行こうとするのは、これはいったいどういうことなのか・・・・なぜいったい、死が生の中軸でなければならないようなふうに政治は事を運ぶのか?
とはいうものの、実は私自身の内部においても、天皇に生命のすべてをささげて生きる、そのころのことばでいわゆる大義に生きることの、戦慄をともなった、ある種のさわやかさというものもまた、同じく私自身のなかにあったのであって、この二つのものが私自身のなかで戦っていた。せめぎ合っていたのである》
この光景を目にしたあと、堀田氏は近い将来日本が敗れることになることを覚悟して、日本を捨て上海へと向かいます・・・そのきとのことを「まるで梯子が外されることが分っていて二階に上るような心境であった」と彼は記しています
そして、東京大空襲から5か月後、終戦の日すなわち1945年8月15日、「終戦を告げる天皇のラジオ放送が流れて以降、人々が皇居前広場につめかけ、敗戦をわびた」「広場で13人が自害」(NHKのドキュメンタリーより)したとされています。堀田氏が焼け跡で目にした光景がそのまま繰り返されたのです・・・
この堀田氏の一文を読まれての感想はひとによって様々でありませう・・・なかなか重い、と申しますか、とりわけ最後の部分は・・・いろいろ考えさせる一文です。GGIがヘタクソな感想を述べるのは無駄というのもでありせう。それよりも、読み飛ばさないで、じっくりこの堀田氏の一文にじっくり向き合っていただければと思います・・・
今日の写真は軍服姿で部下の軍人たちを引きつれて焼跡を視察する昭和天皇の報道写真です。よろしければクリックしてご覧くださいませ
なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・
グッドナイト・グッドラック!