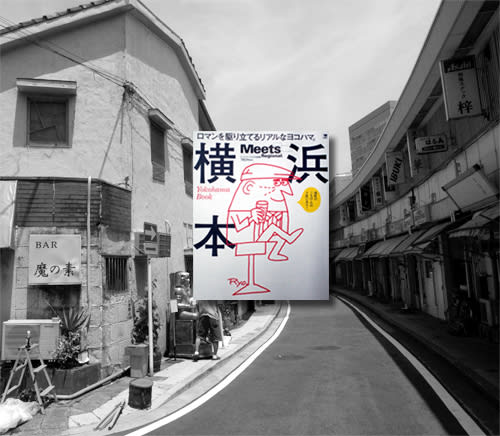まだ小学校に上がる前だったと思う。
買い物といえば、二俣川からカラシ色の車輌の相鉄で西横浜まで行き、そこから市電に乗って藤棚まで。そこで買い物を済ませると、また市電に乗って坂を上り、坂を下り伊勢佐木町へ。これがいつものコースだった。
市電に乗った記憶は、その頃で途切れる。あとは、和田町あたりから三ツ沢方面にトロリーバス(架線つきの電気モーターで走るバス)に何度か乗ったときに、かつてここは市電が走っていたルートだと教えられた。
先日、都電荒川線に揺られたこともあり、本屋の棚で見つけた文字に反応して読んでみた。
獅子文六著『ちんちん電車』(河出文庫720円+税)である。
名前は知っていたが、なにしろ書籍にお目にかかったことがない。1893年横浜生まれの小説家であり、劇作家・演出家としても活躍した方らしい(最近新聞の書評で偶然、牧村健一郎著朝日新聞出版社刊『獅子文六 二つの昭和』を見つけ、こちらも買ってある)。
氏が子供の頃に路線を延ばしていった東京のちんちん電車に、73歳(昭和41年)になって改めて乗り途中下車したり、回想する話(週刊朝日に連載したものをまとめた)。ちょうど、都電が廃止となるというのがきっかけだという※。
銀座の通り、神田のあのあたりなどの道路の真ん中を電車が走っていたのだということを、懐かしい描写とともに想像させてくれる。最初は、子供の頃はみんなが当たり前のように避けたものなのに、昭和41年当時は車に邪魔者扱いされていると嘆く。しかし、スピード感や眺める高さ、乗客に「金や権力をカサにきた、不愉快な人はいない。また、ヨタモンのような者も不思議と、都電に乗らない」ので、東京の乗り物の中で一番好きだと言っている。また「都電はいかに行儀のいい車であるかは、絶対に“割り込み”をしないということでもわかる」とも。
すっかりモータリゼーションの波に押し出されてしまった路面電車ではあるが、最近トラムという名で、世界的にも見直されている。混雑の緩和、省エネルギー、バリヤフリーなどの観点から、新たに導入しようとする動きもあるという。
車窓に映る東京の街の風景をのんびりと眺めながら、乗り換えながら、うまいものを食べ歩く日が来るかもしれない。やっぱり、食い物かい(笑)。いや、獅子文六さんも、あちこちで食べているので。これ、懐かしの東京を巡るグルメ本でもありますよ。
※都電が廃止されたのに、都電荒川線が生き残っているじゃんと思う方。残念ながら、軌道専用区間が多いので、路面走行がほとんどの路面電車には分類されないらしいですね。