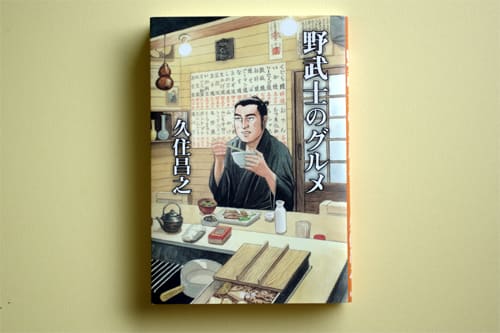藤沢の養豚農家の“こせがれ”宮地勇輔氏が書いた『湘南の風に吹かれて豚を売る』(かんき出版刊1400円+税)を読んだ。
テレビや雑誌をはじめメディアにもかなり露出しているので、ご存じの方も多いだろう。それまで単なる豚肉として出荷されていた、しかし実は父親がこだわりをもって独自の手法で精魂込めて育てた豚肉を、『
みやじ豚』というブランド商品に昇華させた青年の著である。
それは、農業を「きつい、汚い、かっこ悪いの3K産業」から「かっこよくて、感動があって、稼げるの3K産業」に変革しようという挑戦でもある。その発想や、それを実行していくプロセスがわかりやすく描かれていて面白い。ビジネス書としてとらえることもできるだろうが、やはり農業そのもの、これからの日本の食についても考えさせられる。
「あのイチゴよりおいしいイチゴに出会ったことがないんですよ」
年末に会った経理のK嬢に言われたのは、妻の実家のイチゴのことだ。ずいぶん前に会社に持っていったことがある。そのときの話を今でもするのだ。
会社以外でも「このあいだのイチゴはどこへ行ったら買えるの?」という質問をよく受ける。
答えは「海老名の実家」としか答えようがないのが現実。だって、いったん農協に出荷してしまえば「海老名いちご」というフィルムで覆われてはいるが、どこの店頭に並ぶのかは全くわからないからだ。しかも、市内で生産されたいちごには「海老名いちご」と表記されているが、妻の実家で作ったものかどうか判断するすべはない(4パック入った箱には生産者名が入っているが)。それは、消費者側にとっても「あのとき食べたあのイチゴ」を狙い買いできないということでもある。お店で「海老名いちご」を見つけたとしても、「あの時」と同じイチゴを食べられる可能性は高いとは言えないのである。
そんな従来の流通スタイルを打ち破る仕組みをカタチにしながら、農業の、そして日本の未来まで動かしていこうとしている、それが宮地勇輔氏という若者なのだ。
身近にもどかしいこうした例があったので、とても共感しながら読むことができた。
そして、これをいま一番伝えてあげたいのが、甥である。妻の実家を継ぐであろう高校3年生。ただし、内側からの視点だけでしか農業を見ていないので、逆に理解が難しいかもしれない。
もしも農業を“プロデュース”していくのであれば、宮地氏のようにいったん外で学ぶべきなのだろう。もちろん、その必要性も宮地氏は説いている。
帯にある『「働く」と「生きる」はきっとつながる!』というフレーズ。働く価値感をどこに求めるのか、どうしたら自分にとってやりがいのある仕事ができるのか、考えさせられる本である。