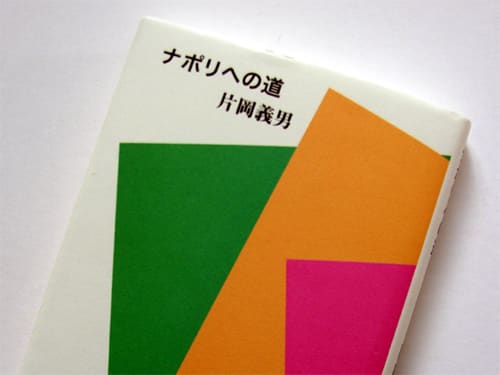もう何十年も前に人気を博したトレンディドラマのような仕立て。
ところが、イカした登場人物が見当たらない。湘南、ホテル、バーと、舞台は非日常っぽいのに、実はそれらがみんなフツーだったりするのだ。
『モーテル0467 鎌倉物語』(甘糟りり子著 マガジンハウス刊1500円+税)は、七里ヶ浜を見下ろすちょっと古ぼけたホテルと、腰越駅からも海からも歩いて1分の小さなバーにやってくる人々が織り成す優しいストーリーだ。
男性視点で描かれているが、女性作家だけあって表現が何とも柔らかい。男性読者の僕にとっては物足りない印象は拭えないが、テンポのゆっくりとした懐かしいドラマを見ているようで心地いいのは確か。知っている風景が出てきたり、お店の情報が収集できるのも嬉しい。
それから、バーでかかるノンジャンルの懐メロがいい。トレンディな曲のヒットパレード。いちいち口ずさまずにはいられない。トレンディドラマ風といい、作者の狙い通りといったところかな。
『湘南』を彷彿とさせる本にはすぐに飛びついてしまうほうで、この本も発売されて間もないうちに購入していた。ところが、カバーがかかったままどこかに埋もれてしまい、先日“発掘”されて、ようやく読んだ。よく見たら、2006年7月20日発売。偶然発掘されなかったら、この本自体が懐かしいものになるところだった(笑)。