1988年に農水省が企画立案して作られた「農道空港」という空港がある。全国に8ヶ所作られた。農産物の鮮度を落とさずに消費地へ運ぶのが目的である。時あたかも、バブルの絶頂期を終わろうかと言うときである。
お役人の作った事業には、何の間違いもなく世界がどのように変わろうとも、この事業は押し進められた。多くの人たちは疑問を持ったのは当然である。運送手段はセスナ機で、200キロがやっとである。片方で高速道路網を国は整備したおかげで、消費地にいち早く鮮度を落とさずに持ち込む優位性もそれほど高くはならなかった。
8空港の内、4空港が北海道にある。高価な運送代に見合う農産物など存在しない。ご多分に漏れずどの空港も、大赤字である。この事業が僅か9年でとん挫したのは救いだろう。
空港の規模は全て、幅が25メートルで長さが800メートルで、有視界飛行(VFR)のみ可能な空港である。農道を少し大きくしただけのと言うイメージから、農道空港と呼ばれるがそれなりの空港の規制がある。払い下げられた自治体はこの規制の中で、利用目的の範囲を広げるのに苦労している。
防災訓練や地域のイベントやラジコンの愛好者に利用されていると言っても、収入につながるわけではない。無用の施設であることには変わりはない。少なくとも、農産物の流通に使われている空港はない。
こうした得体の知れない構造物は、良く目を凝らしてみると農村には無数にある。殆ど人が通らない農道や、農家のいなくなったところに作られた配水施設や灌漑設備などは見ているだけでも腹が立つ。その多くが農業予算を用いているからである。
事業が地域に降りてくると、地域の業者は活気づくため、自治体もその関係者もとりあえず文句を言わない。僻地では何らかの意味で、誰もが関係者になるからである。民主党による政権交代は、こうしたことをやってくれるものだとばかり思っていたが、鳩山ボッチャマは変身したのか本音が頭角を現したかは解らないが、自民化しつつある。










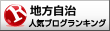
















これが昨年の総選挙の姿でした。
蓋を開けると、不安は見事に的中し政府や党の体制作りにばかり躍起になって政治主導の結果は大臣、政務三役ばかりが忙しく大多数の与党議員は政策論議すらする場所がない。
批判した者は更迭され、新人は多数決の時に数の論理で起立するだけが唯一の議員活動。
この際、事業仕分けでは国会議員の優遇措置も審議して貰いたい。
グリーン車無料だの、報酬以外の報奨費だの、議員食堂、宿舎など優遇されすぎである。膨大な資料の整った国立国会図書館さえもいったい何割の議員が利用しているのか?
今の日本は、多重債務者と何ら変わりはない。
国債の買い手が居なくなるだろう。つまり借金が出来なくなる事になり、破綻においこまれる。或いは、国民の金融資産が借金の埋め合わせでチャラになる。
金利の上昇とハイパーインフレの到来である。
総理自らが、危機的状況を訴えるべきである。