徐々に重い原子核が生成されて、天体の中心部には、より重くて複雑な原子核が蓄えられてく。
その天体内の構造は、みっしりと重い原子核が集まった中心部から、外にいくにしたがって軽くてシンプルなタイプのものになっていき、最外部がスカスカの水素原子核、って「タマネギ構造」。
外から一皮むくたびに、質量が重い層になってくわけだ。
そして、この核融合活動の最後の最後に生成されて、天体の芯になるのが、鉄。
鉄の原子核は非常に安定してるんで、ちっとやそっとのことでは壊れないんだ。
鉄ができて「打ち止め」となると、天体は核反応をしようにないんで、内からの膨張圧力が得られない。
つまり、自らの重さで収縮してく。
すると密度が高まり、さらに鉄が生成される。
だけど、あまり圧迫されすぎると、風船は破裂するよね。
それとおんなじで、天体の重い鉄芯が収縮圧に耐えきれなくなると、ついには大爆発を起こす。
「超新星」ってやつだ。
ピカーッ、一瞬で宇宙が光に満たされる、みたいなやつ。
その一瞬時で、天体はそれまでの生涯(数十億年)に放出しつづけたよりも大きなエネルギーをまき散らす。
この莫大なエネルギーは、さらに多様な原子核を、つまり鉄よりも重くて複雑なタイプのものを生成する。
簡単に言えば、天体の誕生と成長、そして最期という過程でつくられた新しい数々の原子核が、宇宙中にバラまかれる。
高温高圧のくびきから逃れて自由になった原子核は、プラズマ状態の中で生き別れになった電子を再びつかまえる。
プラスマイナスで相性のいい電子を、原子核内の陽子と同じ数だけつかまえて自分の周囲をめぐらせると、プラマイゼロとなり、晴れて安定した「原子」となる。
各種「物質」の種ができたわけだ。
これによって、ひろびろとした新世界がひらける。
ちょっと前のことを考えてもみてよ、なんたって宇宙空間には、ほとんど水素しかなかったんだから。
そこに、炭素や、酸素や、鉄やらが新たに加わったんだ。
それらの物質が、再び万有引力で引き合い、複雑な味わいのスープとなり、多様な天体を構成し、さらに混沌とした世界をつくりあげてくわけだ。
いつかにつづく。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園
その天体内の構造は、みっしりと重い原子核が集まった中心部から、外にいくにしたがって軽くてシンプルなタイプのものになっていき、最外部がスカスカの水素原子核、って「タマネギ構造」。
外から一皮むくたびに、質量が重い層になってくわけだ。
そして、この核融合活動の最後の最後に生成されて、天体の芯になるのが、鉄。
鉄の原子核は非常に安定してるんで、ちっとやそっとのことでは壊れないんだ。
鉄ができて「打ち止め」となると、天体は核反応をしようにないんで、内からの膨張圧力が得られない。
つまり、自らの重さで収縮してく。
すると密度が高まり、さらに鉄が生成される。
だけど、あまり圧迫されすぎると、風船は破裂するよね。
それとおんなじで、天体の重い鉄芯が収縮圧に耐えきれなくなると、ついには大爆発を起こす。
「超新星」ってやつだ。
ピカーッ、一瞬で宇宙が光に満たされる、みたいなやつ。
その一瞬時で、天体はそれまでの生涯(数十億年)に放出しつづけたよりも大きなエネルギーをまき散らす。
この莫大なエネルギーは、さらに多様な原子核を、つまり鉄よりも重くて複雑なタイプのものを生成する。
簡単に言えば、天体の誕生と成長、そして最期という過程でつくられた新しい数々の原子核が、宇宙中にバラまかれる。
高温高圧のくびきから逃れて自由になった原子核は、プラズマ状態の中で生き別れになった電子を再びつかまえる。
プラスマイナスで相性のいい電子を、原子核内の陽子と同じ数だけつかまえて自分の周囲をめぐらせると、プラマイゼロとなり、晴れて安定した「原子」となる。
各種「物質」の種ができたわけだ。
これによって、ひろびろとした新世界がひらける。
ちょっと前のことを考えてもみてよ、なんたって宇宙空間には、ほとんど水素しかなかったんだから。
そこに、炭素や、酸素や、鉄やらが新たに加わったんだ。
それらの物質が、再び万有引力で引き合い、複雑な味わいのスープとなり、多様な天体を構成し、さらに混沌とした世界をつくりあげてくわけだ。
いつかにつづく。
東京都練馬区・陶芸教室/森魚工房 in 大泉学園











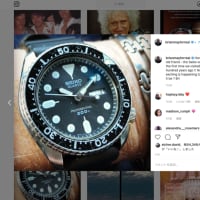
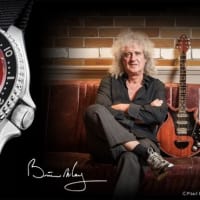













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます