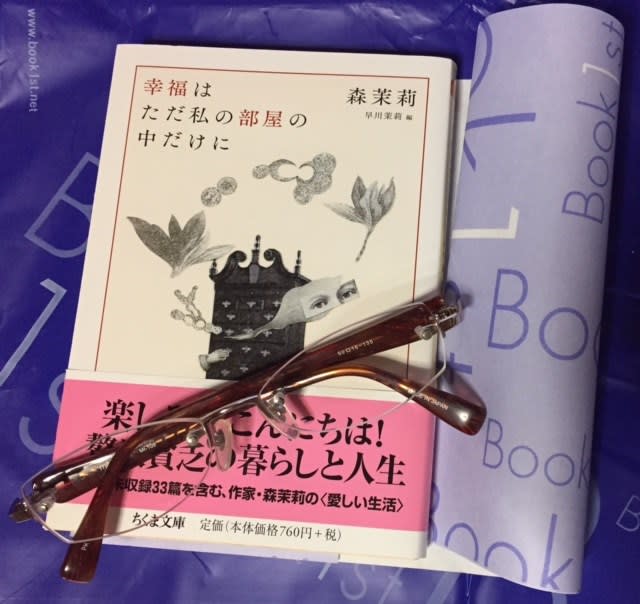深夜になって、雨が本降りに。
気温30℃湿度63%。蒸し暑い。
熱帯低気圧が、四国沖で、台風に昇格したようで、日本近海で、台風になるのは、わりと珍しい・・・とニュースは、伝えていた。
久しぶりに、小説を読んだ。
渡辺淳一の『天上紅蓮』。
氏には、珍しい?歴史小説・・・と言っていいのかもしれない。
鳥羽天皇の后・待賢門院璋子の生涯を描いた平安王朝絵巻・・・なのだろう・・・。
渡辺淳一の作品は、初期の頃の『花埋み』、『無影灯』などは、名作だと思う。
『花埋み』は、日本初(医師免許を取得した)女医、『無影灯』は、不治の病に侵された外科医の物語で、どちらもテレビドラマ化された作品だった。
初期の頃は・・・よかった。
いつからか・・・かなり際どいエロの世界の書き手となったようで、『失楽園』あたりから、だろうか?そのへんの変遷は、そのあたりの作品は、未読なので、何とも言い難いのだけれど。
『天上紅蓮』は、養父である白河法皇の愛人として、まさに掌中の珠として育てられ、その権力に守られた待賢門院璋子が、養父である法皇と夫である鳥羽天皇のふたりの間で、栄華を誇る暮らしから、権力者である白河法皇の死後、落日の如く、落ちていく物語なのだけれど、待賢門院璋子のセリフがほとんどなくて、ただいつも身悶えして
『法王さまぁ・・・。』
・・・と言っているだけの・・・小説であった(ような気がする)。
白河法皇と待賢門院璋子の・・・所謂、床の中の描写が、生々しいし、幼い頃から、白河法皇に、性技を仕込まれた待賢門院璋子の夫との閨での描写は、まさにエロス・・・なんだろうなぁ・・・。
まあ、それだけです。
同じ、待賢門院璋子の登場する『宮尾本・平家物語(宮尾登美子・著)』とは、一線を画すもの。
やはり、王朝絵巻とは、かなり離れた・・・天上紅蓮・・・だったように思う。