アンソニー・ホロヴィッツのホーソーン&ホロヴィッツ シリーズ第3作『殺しへのライン』(A Line to Kill、山田蘭訳、創元推理文庫、2021)をさっそく読んだ。ホロヴィッツはここ4年ほど毎年1作ずつ翻訳されて、すべて大評判になってきた。ここでもその都度書いてきたが、このシリーズの方だけ紹介すると『メインテーマは殺人』、『その裁きは死』である。元刑事ホーソーンの名推理を描くシリーズだが、作者が作中に出て来るなど独創的なミステリーになっている。特に第1作は傑作だった。

エンタメシリーズとして、この作品から読んでも可能になっているけど、登場人物には前からの経緯もあるから順番に読む方が面白いだろう。今回はもうすぐ第1作『メインテーマは殺人』が刊行される直前で、すでに第2作『その裁きは死』の事件も解決した後という時間設定である。宣伝のため、文芸フェスティバルに参加してはどうかということになる。探偵役のダニエル・ホーソーンは何しろヘンクツで、個人的なことはほとんど明かさない。だから文芸フェスなんか嫌がるかと思うと、場所がチャンネル諸島のオルダニー島だと聞いて参加に前向きになる。

 (チャンネル諸島、後の地図の赤いところがオルダニー島)
(チャンネル諸島、後の地図の赤いところがオルダニー島)
チャンネル諸島は上に掲載した地図にあるように、英仏海峡のほぼフランス寄りにある島々である。英国王室の私領という不思議な存在で、イギリスが外交・防衛を担うけれど独自の憲法があって行政は別になっているという。一番大きなジャージー島は人口10万を超えていて、「ジャージ」「ジャージー牛」の語源。オルダニー島なんてところは知らないし、いかにも的な地図が載ってるから、きっと架空かと思ったら実在していた。チャンネル諸島の中では北東に離れた人口2400人の小さな島である。チャンネル諸島は第二次大戦中にドイツに占領され、オルダニー島には強制収容所が作られている。そのことは小説の中にも出て来る。
 (オルダニー島)
(オルダニー島)
さて肝心の文芸フェスだが、今回が初開催ということで、主催者のジュディス・マシスンは張り切っているが参加者はパッとしない。児童文学者のアン・クリアリーは前にホロヴィッツも会ったことがあるが、他にはテレビで評判の料理人マーク・ベラミーとその助手キャスリン・ハリス、本が売れている盲目の霊能者エリザベス・ラヴェルとその夫シド、フランスの朗読詩人マイーサ・ラマルなどが参加している。ホロヴィッツは何しろ紹介するべき本が未刊行とあっては知名度も今ひとつ。
一方、島側では後援者である大金持ちのチャールズ・ル・メジュラーは、オンラインゲーム会社で大もうけして、島に「眺望館」という大邸宅を作った。今は彼も関わって、ノルマンディー半島から島を通ってイギリスに通じるケーブル設置計画があり、島を二分する争いになっている。ル・メジュラーは料理人マーク・ベラミーと同じ学校で、過去に因縁があったらしい。一方、彼の財務顧問をしているのがデレク・アボットという人物で、これがまたホーソーンと過去の因縁があったのである。どうやらホーソーンはアボットがオルダニー島にいることを知っていて、この文芸フェスに参加したかったらしい。
 (オルダニー島の強制収容所跡)
(オルダニー島の強制収容所跡)
しばらくは文芸フェスの様子が順を追って描かれる。そしてル・メジュラーは彼の大邸宅に関係者を集めて、マーク・ベラミーが料理を担当する大パーティを開くことになった。ル・メジュラーの妻、ヘレン・ル・メジュラーも島に帰ってきた。ミステリーなんだから殺人事件が起こるんだろうけど、いつ起こるんだという感じで進んで行き、450頁中の150頁ほどになって事件が起きる。島にはすぐ動ける警官がその時はいなくて、ガーンジー島から派遣されてくるが、ホーソーンも捜査への協力を依頼される。
ホロヴィッツは作中でミステリーでは意外な犯人が多いものだなどと言いながら、今回だけは違うかもしれない。それだと作品にまとめるのは苦労するなどとつぶやいている。英国本土から遠く、一種観光小説的な興趣で進んで行く。そのためスラスラ読んでしまうのだが、もちろん奸智にたけた作者だけに何も起こってないはずの文芸フェスの間にも様々な伏線が散りばめられている。
それが最後の最後になって、電撃的に真相が明かされて、自分は何を読んでいたんだろうと思う。まあ作りすぎ的な感じも否めないのだが、いかにもホロヴィッツ的なミステリーだ。読んで傑作だと思ったけど、どうにもホーソーンという謎がますます大きくなってくる。イギリスではすでに次回作“The Twist of a Knife” が発表されている由。来年の翻訳刊行が待ち遠しい。

エンタメシリーズとして、この作品から読んでも可能になっているけど、登場人物には前からの経緯もあるから順番に読む方が面白いだろう。今回はもうすぐ第1作『メインテーマは殺人』が刊行される直前で、すでに第2作『その裁きは死』の事件も解決した後という時間設定である。宣伝のため、文芸フェスティバルに参加してはどうかということになる。探偵役のダニエル・ホーソーンは何しろヘンクツで、個人的なことはほとんど明かさない。だから文芸フェスなんか嫌がるかと思うと、場所がチャンネル諸島のオルダニー島だと聞いて参加に前向きになる。

 (チャンネル諸島、後の地図の赤いところがオルダニー島)
(チャンネル諸島、後の地図の赤いところがオルダニー島)チャンネル諸島は上に掲載した地図にあるように、英仏海峡のほぼフランス寄りにある島々である。英国王室の私領という不思議な存在で、イギリスが外交・防衛を担うけれど独自の憲法があって行政は別になっているという。一番大きなジャージー島は人口10万を超えていて、「ジャージ」「ジャージー牛」の語源。オルダニー島なんてところは知らないし、いかにも的な地図が載ってるから、きっと架空かと思ったら実在していた。チャンネル諸島の中では北東に離れた人口2400人の小さな島である。チャンネル諸島は第二次大戦中にドイツに占領され、オルダニー島には強制収容所が作られている。そのことは小説の中にも出て来る。
 (オルダニー島)
(オルダニー島)さて肝心の文芸フェスだが、今回が初開催ということで、主催者のジュディス・マシスンは張り切っているが参加者はパッとしない。児童文学者のアン・クリアリーは前にホロヴィッツも会ったことがあるが、他にはテレビで評判の料理人マーク・ベラミーとその助手キャスリン・ハリス、本が売れている盲目の霊能者エリザベス・ラヴェルとその夫シド、フランスの朗読詩人マイーサ・ラマルなどが参加している。ホロヴィッツは何しろ紹介するべき本が未刊行とあっては知名度も今ひとつ。
一方、島側では後援者である大金持ちのチャールズ・ル・メジュラーは、オンラインゲーム会社で大もうけして、島に「眺望館」という大邸宅を作った。今は彼も関わって、ノルマンディー半島から島を通ってイギリスに通じるケーブル設置計画があり、島を二分する争いになっている。ル・メジュラーは料理人マーク・ベラミーと同じ学校で、過去に因縁があったらしい。一方、彼の財務顧問をしているのがデレク・アボットという人物で、これがまたホーソーンと過去の因縁があったのである。どうやらホーソーンはアボットがオルダニー島にいることを知っていて、この文芸フェスに参加したかったらしい。
 (オルダニー島の強制収容所跡)
(オルダニー島の強制収容所跡)しばらくは文芸フェスの様子が順を追って描かれる。そしてル・メジュラーは彼の大邸宅に関係者を集めて、マーク・ベラミーが料理を担当する大パーティを開くことになった。ル・メジュラーの妻、ヘレン・ル・メジュラーも島に帰ってきた。ミステリーなんだから殺人事件が起こるんだろうけど、いつ起こるんだという感じで進んで行き、450頁中の150頁ほどになって事件が起きる。島にはすぐ動ける警官がその時はいなくて、ガーンジー島から派遣されてくるが、ホーソーンも捜査への協力を依頼される。
ホロヴィッツは作中でミステリーでは意外な犯人が多いものだなどと言いながら、今回だけは違うかもしれない。それだと作品にまとめるのは苦労するなどとつぶやいている。英国本土から遠く、一種観光小説的な興趣で進んで行く。そのためスラスラ読んでしまうのだが、もちろん奸智にたけた作者だけに何も起こってないはずの文芸フェスの間にも様々な伏線が散りばめられている。
それが最後の最後になって、電撃的に真相が明かされて、自分は何を読んでいたんだろうと思う。まあ作りすぎ的な感じも否めないのだが、いかにもホロヴィッツ的なミステリーだ。読んで傑作だと思ったけど、どうにもホーソーンという謎がますます大きくなってくる。イギリスではすでに次回作“The Twist of a Knife” が発表されている由。来年の翻訳刊行が待ち遠しい。










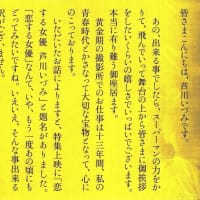
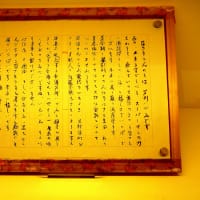








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます