毎月読んでる「戦争と文学」シリーズも6回目。我ながらよく読んでると思う。残り2冊だから、何とか頑張りたい。前回の「女性たちの戦争」は、女性を描く作品が少なく巻名と中身が違っていた。今度の「戦時下の青春」も青春を描くのは数編。永井荷風「勲章」とか野坂昭如「火垂るの墓」などは、どう拡大解釈しても「青春」ではないだろう。もっとも戦時下を描く名作だから落とせなかったのだろう。650頁にも及ぶ本を読んで一番思ったのは「空襲の恐怖」である。
 (表紙=手塚治虫「新・聊斎志異 女郎蜘蛛」
(表紙=手塚治虫「新・聊斎志異 女郎蜘蛛」
「戦時下の青春」にふさわしいのは、吉行淳之介「焔の中」、井上光晴「ガダルカナル戦詩集」ぐらいかと思う。どちらも読んでいたので、先の2作と合わせて4編が既読だった。でも「焔の中」はすっかり忘れていた。これは大変よく出来た短編で、吉行淳之介の確かな筆力に舌を巻いた。一度召集されて病気で帰された大学生という設定は、ほぼ作者自身である。作家の父は早世し、美容師の母と暮らす。この母がテレビドラマにもなった吉行あぐりだが、若い頃に読んだときは知らなかった。暮らしの中に若い娘が不思議な感じで登場し、そして空襲を迎える。
 (吉行淳之介)
(吉行淳之介)
井上光晴「ガダルカナル戦詩集」は長崎の青年たちが出征する友の壮行会に集まる話。表題の詩集は実際に戦時中に刊行されて評判になったもので、作中で登場人物が読んで感激する。この小説は戦時中の目で書かれているので、登場人物たちが何を心配し心に掛けているかが描かれる。そこが判りにくいところで、暗いムードが全編を覆っているし読みにくい。井上光晴はその後「明日」という小説を書いた。1945年8月8日の長崎を描き、映画化もされた。それを思い出すと、ここに出てくる登場人物の何人かは、8月9日の長崎にいたはずだなと今回思った。
この巻には有名な作家がずいぶん収録されている。すでに作家として世に出ていた人は、井伏鱒二、太宰治、内田百閒などは自身の体験を書いたものが入っている。池波正太郎「キリンと蟇(がま)」は「鬼平」などで有名な作家の現代小説で、こんな作品があったかとビックリした。証券会社員だった「キリン」が軍需工場に徴用されて、旋盤工になる。職場の先輩「蟇」に教えられて、何とかやっていく。戦後になって思わぬところで再会するが…。「株屋」が「職工」になれるのかをテーマにしながら、「徴用」という体験を後世に伝える小説にもなっている。
 (池波正太郎)
(池波正太郎)
今ではほとんど知られていない作家も収録されている。上田広「指導物語」は熊谷久虎監督によって戦時中に映画化された。蒸気機関車の運転を兵士に教える機関手の話で、鉄道ファンには知られているかもしれない。その原作があったのかという感じだが、非常に素直に進行する「教育小説」で、内容はほぼ映画と同じだった。上田広は火野葦平などと並ぶ兵隊作家だったらしいが、元々は鉄道省に勤めていたと出ている。戦後も鉄道に関する小説を書いている。顔写真は見つからなかったが、戦時中に出た「指導物語」の本があった。
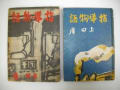 (「指導物語」)
(「指導物語」)
前田純敬(すみのり)の1949年の「夏草」は、芥川賞候補になったという。作家も作品も知ってる人はほとんどいないと思うけれど、鹿児島在住の14歳の少年が軍に召集されて海辺で「本土決戦」の訓練をさせられる。その間に鹿児島市は空襲され逃げ惑う。川内(せんだい)に避難するが、そこも空襲を受ける。奄美大島出身者への差別も描かれる。東京や大阪の空襲を書き残した記録は多いが、地方都市の空襲を描く小説は珍しい。これがまた恐怖に次ぐ恐怖で、都市空爆の恐ろしさをここまで描いた小説は少ないと思う。その後あまり活動しなかったようだが、非常に貴重な作品だ。2004年に亡くなったが、その年に「夏草」が刊行されている。
 (「夏草」)
(「夏草」)
結城信一という作家もほとんど知られていないだろう。1980年の「空の細道」が日本文学大賞を受賞していて、一応前の二人よりは文学史に名を残している。全3巻の全集もあるが、僕も今回「鶴の書」で初めて読んだが哀切な空襲小説だった。30過ぎた女学校の教師が不遇な女子生徒を引き取って暮らしている。辻潤と伊藤野枝みたいな例もあったけれど、今では書けない設定かもしれない。編者の浅田次郎はこの名品を埋もれさせてはならないと思って選んだと言っている。「鶴の書」の鶴の意味が判るとき、この小説は真に忘れがたくなる。
 (「鶴の書」)
(「鶴の書」)
一番最後にある井上靖「三ノ宮炎上」も異色の青春もので、戦時中の神戸・三ノ宮にたむろする「不良女子」を描く。「不良」と言ってもカワイイもんだが、戦時中にも「不良」がいたということが新鮮。江戸川乱歩「防空壕」、坂口安吾「アンゴウ」は空襲を題材にした独自のミステリー。小林勝「軍用露語教官」も面白かった。他にも中井英夫「見知らぬ旗」、三浦哲郎「乳房」、高橋和巳「あの花この花」、川崎長太郎「徴用行」、石川淳「名月珠」、高井有一「櫟(くぬぎ)の家」、古井由吉「赤牛」など多彩な作品があった。さすがに名の知られた作家はうまいもんだ。
 (表紙=手塚治虫「新・聊斎志異 女郎蜘蛛」
(表紙=手塚治虫「新・聊斎志異 女郎蜘蛛」「戦時下の青春」にふさわしいのは、吉行淳之介「焔の中」、井上光晴「ガダルカナル戦詩集」ぐらいかと思う。どちらも読んでいたので、先の2作と合わせて4編が既読だった。でも「焔の中」はすっかり忘れていた。これは大変よく出来た短編で、吉行淳之介の確かな筆力に舌を巻いた。一度召集されて病気で帰された大学生という設定は、ほぼ作者自身である。作家の父は早世し、美容師の母と暮らす。この母がテレビドラマにもなった吉行あぐりだが、若い頃に読んだときは知らなかった。暮らしの中に若い娘が不思議な感じで登場し、そして空襲を迎える。
 (吉行淳之介)
(吉行淳之介)井上光晴「ガダルカナル戦詩集」は長崎の青年たちが出征する友の壮行会に集まる話。表題の詩集は実際に戦時中に刊行されて評判になったもので、作中で登場人物が読んで感激する。この小説は戦時中の目で書かれているので、登場人物たちが何を心配し心に掛けているかが描かれる。そこが判りにくいところで、暗いムードが全編を覆っているし読みにくい。井上光晴はその後「明日」という小説を書いた。1945年8月8日の長崎を描き、映画化もされた。それを思い出すと、ここに出てくる登場人物の何人かは、8月9日の長崎にいたはずだなと今回思った。
この巻には有名な作家がずいぶん収録されている。すでに作家として世に出ていた人は、井伏鱒二、太宰治、内田百閒などは自身の体験を書いたものが入っている。池波正太郎「キリンと蟇(がま)」は「鬼平」などで有名な作家の現代小説で、こんな作品があったかとビックリした。証券会社員だった「キリン」が軍需工場に徴用されて、旋盤工になる。職場の先輩「蟇」に教えられて、何とかやっていく。戦後になって思わぬところで再会するが…。「株屋」が「職工」になれるのかをテーマにしながら、「徴用」という体験を後世に伝える小説にもなっている。
 (池波正太郎)
(池波正太郎)今ではほとんど知られていない作家も収録されている。上田広「指導物語」は熊谷久虎監督によって戦時中に映画化された。蒸気機関車の運転を兵士に教える機関手の話で、鉄道ファンには知られているかもしれない。その原作があったのかという感じだが、非常に素直に進行する「教育小説」で、内容はほぼ映画と同じだった。上田広は火野葦平などと並ぶ兵隊作家だったらしいが、元々は鉄道省に勤めていたと出ている。戦後も鉄道に関する小説を書いている。顔写真は見つからなかったが、戦時中に出た「指導物語」の本があった。
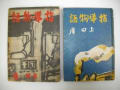 (「指導物語」)
(「指導物語」)前田純敬(すみのり)の1949年の「夏草」は、芥川賞候補になったという。作家も作品も知ってる人はほとんどいないと思うけれど、鹿児島在住の14歳の少年が軍に召集されて海辺で「本土決戦」の訓練をさせられる。その間に鹿児島市は空襲され逃げ惑う。川内(せんだい)に避難するが、そこも空襲を受ける。奄美大島出身者への差別も描かれる。東京や大阪の空襲を書き残した記録は多いが、地方都市の空襲を描く小説は珍しい。これがまた恐怖に次ぐ恐怖で、都市空爆の恐ろしさをここまで描いた小説は少ないと思う。その後あまり活動しなかったようだが、非常に貴重な作品だ。2004年に亡くなったが、その年に「夏草」が刊行されている。
 (「夏草」)
(「夏草」)結城信一という作家もほとんど知られていないだろう。1980年の「空の細道」が日本文学大賞を受賞していて、一応前の二人よりは文学史に名を残している。全3巻の全集もあるが、僕も今回「鶴の書」で初めて読んだが哀切な空襲小説だった。30過ぎた女学校の教師が不遇な女子生徒を引き取って暮らしている。辻潤と伊藤野枝みたいな例もあったけれど、今では書けない設定かもしれない。編者の浅田次郎はこの名品を埋もれさせてはならないと思って選んだと言っている。「鶴の書」の鶴の意味が判るとき、この小説は真に忘れがたくなる。
 (「鶴の書」)
(「鶴の書」)一番最後にある井上靖「三ノ宮炎上」も異色の青春もので、戦時中の神戸・三ノ宮にたむろする「不良女子」を描く。「不良」と言ってもカワイイもんだが、戦時中にも「不良」がいたということが新鮮。江戸川乱歩「防空壕」、坂口安吾「アンゴウ」は空襲を題材にした独自のミステリー。小林勝「軍用露語教官」も面白かった。他にも中井英夫「見知らぬ旗」、三浦哲郎「乳房」、高橋和巳「あの花この花」、川崎長太郎「徴用行」、石川淳「名月珠」、高井有一「櫟(くぬぎ)の家」、古井由吉「赤牛」など多彩な作品があった。さすがに名の知られた作家はうまいもんだ。















