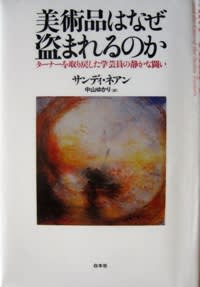【奈良県主催セミナーで、「孔子の聖人イメージも後につくられた!」】
「論語を読み直す」と題した講演会が14日、奈良県文化会館で開かれた。県主催の地域交流セミナーの初回で、講師は京都大学教授の小倉紀蔵氏。専門は朝鮮半島の思想・文化、東アジア哲学で、NHKテレビ・ラジオのハングル講座講師や「日韓文化交流会議」委員などを務めた。昨今の論語ブームもあって、当初予想の2倍の約400人が小ホールを埋め尽くした。
 講師の小倉紀蔵氏
講師の小倉紀蔵氏
孔子といえば聖人君子というイメージが強い。だが、小倉氏は講演の初めに「聖人のイメージは後につくられたもの」とまず否定した。「孔子は低い階層の出身で幼くして両親を亡くし、若い頃には正式な就職ができず3Kのアルバイトが続いた。勉学に励み自分を高めていったのは確かだが、孔子自身も『まだ君子にもなれない』と嘆いていた」。
孔子は「非常に感性が鋭い人だった。そこが大変頭が良かった孟子との大きな違い」という。「孔子が重視したのは見る・聞く・味わうといった感覚」。その例として論語の中の「郷党編」を紹介した。そこには季節外れのものや切り口が雑なものは食べない、食事中には話さない――といった食べ物や食べ方へのこだわりが記される。「論語は決して道徳的なことばかり書かれているわけではない」。
孔子は「仁」に重きを置いた。論語にも「仁」という言葉が数多く出てくる。「子曰く、荀(まこと)に仁に志せば、悪しきこと無し」(里仁編)、「子曰く、巧言令色、鮮(すく)なし仁」(学而編)――。では「仁」とは? 弟子たちもそれを知りたがったが、孔子は最愛の弟子、顔淵には「克己復礼」だといい、他の弟子には1人1人違う説明をした。小倉氏は「仁は人偏に数字の二と書く。仁は本来、定義できないが、あえて言うなら、人と人とのあいだに立ち現れる<いのち>であり、その<あいだのいのち>を立ち現すための意力である」という。
論語には「君子」とその反対の「小人」についても多く記す。「子曰く、君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」(子路編)、「子曰く、君子は義に喩(さと)り、小人は利に喩る」(里仁編)、「子曰く、君子は器ならず」(為政編)――。両者を大別すると、君子はアニミズム的教養の持ち主、共同体主義、生命尊重、文化主義的といった特徴を持つ。一方、小人はシャーマニズム的、グローバリズム、利益尊重、覇権主義的などの特徴を持つ。コミュニケーション能力に関しては、君子は朴訥としているのに対し、小人はペラペラと弁舌さわやかで「上から目線で説教して共同体を破壊する」という。
論語が誤読されてきた背景には「論語の世界観がアニミズムなのに、後世、それを汎神論的に読んでしまったことによる」と指摘する。孔子の死後、孟子は性善説を唱え孔子が最も重きを置いた「仁」に加え徳目義の思想を主張した。その孟子について、小倉氏は「孔子のいう小人の世界観と道家の汎神論的な世界観を併せ持っていた。その孟子によって孔子は聖人に祭り上げられた」と指摘する。
小倉氏は「孔子のアニミズム的な世界観が残っているのは(中国や朝鮮半島ではなく)むしろ日本ではないか。仁の解釈についても一番分かるのが日本人だと思う」と話す。その例証として俳句を挙げた。「同じ場面に立っても1人1人感じ方が違い、それをわずか17文字でそれぞれに表現する。それが孔子の言う仁であり、いのちでもある」。
最後に学而編の有名な一節「子曰く、学びて時に之を習う、また説(よろこ)ばしからずや。朋あり遠方より来る、また楽しからずや」に触れた。その中の「遠方」は論語が書かれた当時にそんな熟語はなく、「えんぽう」の読みは誤りという。「遠くより方に(まさに)来る」と読むべきで、会いたかった友が突然やって来て2人の間に立ち現れる「仁」そのものを表しているそうだ。