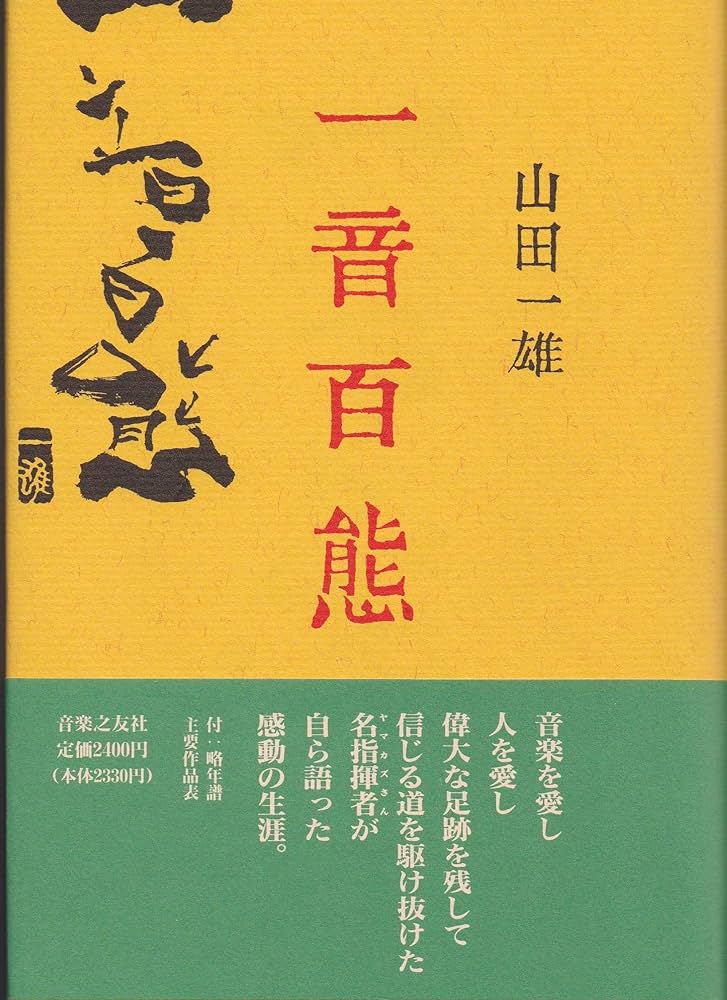読了。

非常に刺激的な内容だった。
音楽は好きだが、「音楽科教育はいかにあるべきか?」、「そもそも音楽科教育はなんのためにあるのか?」などということを考えたことは1mmたりともなかった(苦笑)
しかし、ここに書かれていることは全てそのまま私自身の音楽との関わりに関係してくる。
私はたまたまクラシック音楽や、その中でも特に吹奏楽に興味を持っているけれど、それは大凡「18C以降のヨーロッパ、乃至アメリカで生まれた音楽」に
過ぎない。
そして私が受けてきた音楽に関する授業や、吹奏楽部/Wオケで受けてきた薫陶もその枠の中のものでしかない。
しかし当たり前だが、音楽は西洋の、それも近代以降のものだけではない。
世界各地に様々な形態の、様々な特色を持った音楽が無数にあり、勿論それは日本にも当てはまる。
所謂ポピュラー・ミュージックに関しても全く同じだ。
筆者の主張をここで全ては代弁できないが、私が一番印象深かったのは、「西洋のクラッシック/ポピュラー音楽」の価値観(例えばメロディ/リズム/ハーモニーの要素、記譜法、機能和声、地域/時代に即した演奏技法等)に縛られずに、それ以外の音楽の価値観を認めるためにこそ音楽科の授業はあるべきだ、という点だった。
ああ、書いているとどんどん長くなってしまいそうなのでこの辺りで一旦止めるが(苦笑)、とにかく自分自身の音楽との向き合い方にとても大きな影響を受けた気がする。
筆者の長谷川亮さんは動画の配信などもされているそうなので、少しずつ学んでいきたいと思う。
再度おすすめです(^^)b!