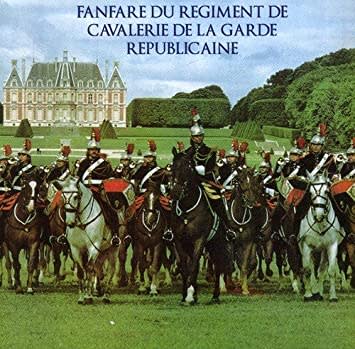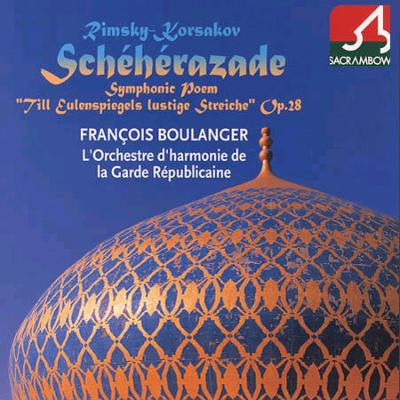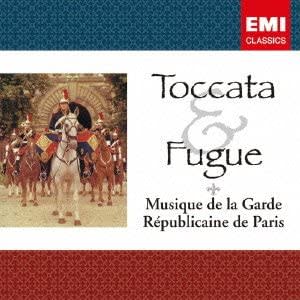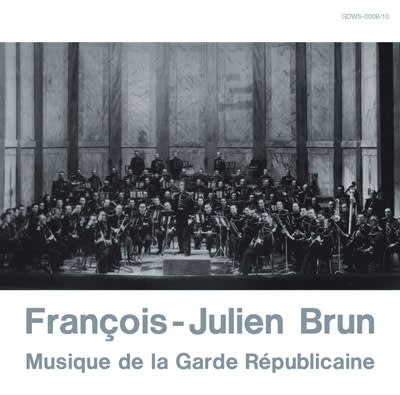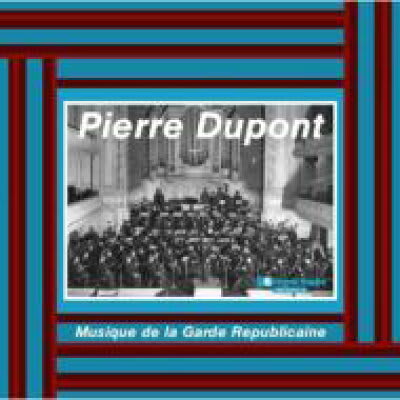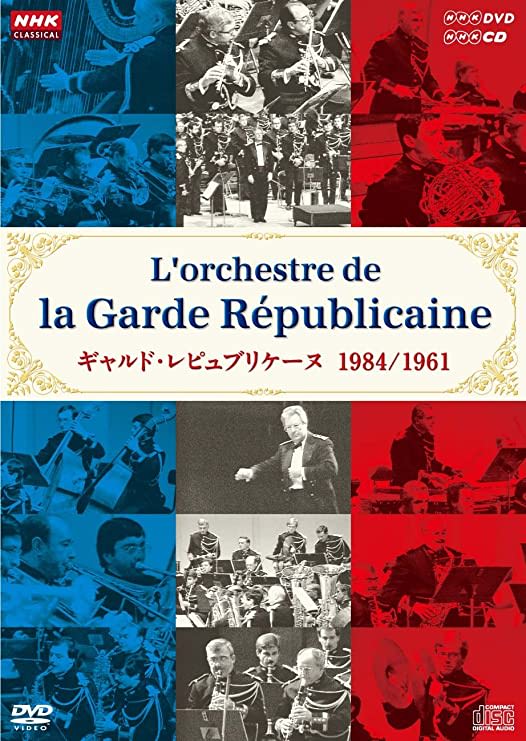本日届いた本↓

日本を代表するプロバンドの記念誌。
いわゆる「ニュー・サウンズ・イン・ブラス」シリーズから聴き始めたのだったと思う。
高校時代は『アフリカン・シンフォニー』とか『黒いジャガーのテーマ』とか、自分で指揮するようになってからは『テキーラ』とか『ディズニー・メドレー』とか、ずいぶん演奏したものだ。
鑑賞する対象としては、やはりフェネルが常任指揮者になってからだろう。
残念ながら生で鑑賞したことはなかったが、音源は沢山持っていて、特に「40周年記念演奏会」(2000年)のDVDは愛聴盤の一つ(^^)。

定期演奏会には都合7回お邪魔している。
■第52回(1993) 『ローマの祭り』他(指揮:山下一史)
■第57回(1995) 『無窮動』(尹伊桑)他(指揮:金洪才)
■第83回(2004) 『ガーデン・レイン』、室内協奏曲(武満徹)、『小さな三文音楽』(K.ヴァイル)他(指揮:岩城宏之)
■第116回(2013) 「ワーグナーの夕べ」(『ローエングリン』、『トリスタン』他)(指揮:飯森泰次郎)
■第135回(2017) 『この地球を神と崇める』(K.フサ)他(指揮:大井剛史)
■第144回(2018) 『シンフォニック・レクイエム』(V.ネリベル)他(指揮:大井剛史)
■第147回(2019) 交響曲代5番(DSCH)他(指揮:T.ザンデルリンク)
最後のザンデルリンクが2年前の2月15日、この日以来県外には遠征できていない・・・。
昨年秋の演奏会(150回)、メシアンの『われ死者たちの復活を待ち望む』を聴きに行けなかったのが、本当に悔やまれる(T_T)。
21Cに入ってからの演奏会はどれも素晴らしく、特にも飯森さんのワーグナーは強烈に思い出深い。
また、大井さんのフサとネリベルも忘れられない演奏。
世評によると、つい先日行われた原田慶太楼さん指揮の演奏会もずいぶん盛り上がったらしい。
聴いてみたかったなあ...。

一ファンとして言わせてもらうならば、プログラムがかなり保守的で、アレンジ作品が多いのが残念(>_<)。
ヨーロッパで大変個性的な活動を展開しているオランダ管楽アンサンブルやノルウェー管楽アンサンブルを聴き込んでいるせいもあろうが、
個人的にはもっともっと吹奏楽ならではの魅力を発揮できるプログラミングを希望したいものだ(苦笑)。
池袋の芸劇に足を運べる日が一でも早く戻ってきますようにm(__)m。
PS ということで、本日の職場でのBGMも吹奏楽w。

Live In Concert At Bozar-brussels Vol.2: Symphonic Band Of The Belgian Guides
CD 1 : DANCES
Danzon Nr 2 – Arturo Marquez
Dances of Galanta – Zoltan Kodally
Raga 1 – Wim Henderichx (Solist: Gert François)
Four Dances of Estancia – Alberto Ginastera
Los Trabajadores
Danza del Trigo
Los Peones de hacienda
Danza Final
CD 2 :1918
Behind the Lines: Estaminet au Carrefour – Cecil Coles
Berceuse héroïque – Claude Debussy
Le Carillon – Edward Elgar (Solist: Émilie De Voght)
In Flanders’ Fields – John Philip Sousa (Solist: Émilie De Voght)
Le Drapeau belge – Edward Elgar (Solist: Émilie De Voght)
Le Tombeau de Couperin – Maurice Ravel
Slava – Léonard Bernstein
On the Town: Three Dance Episodes – Léonard Bernstein
West Side Story – Symphonic Dances – Léonard Bernstein
CD 3 : GREAT CLASSICS
Ouverture Poète et Paysan – Franz von Suppé
La belle Hélène : Vers tes autels, Jupin – Jacques Offenbach *
Les Contes d’Hoffman : Barcarolle – Jacques Offenbach *
Ouverture Benvenuto Cellini – Hector Berlioz
Ouverture Les Vêpres Siciliennes – Giuseppe Verdi
Nabucco : Chœur des esclaves – Giuseppe Verdi *
La Traviata: Coro di zingarelle e mattadori – Giuseppe Verdi *
Aïda: Triomphmarch – Giuseppe Verdi *
こちらもヨーロッパを代表するバンドの一つ。
特に1枚目の舞曲集は躍動感に満ちあふれ、抜群に面白い!