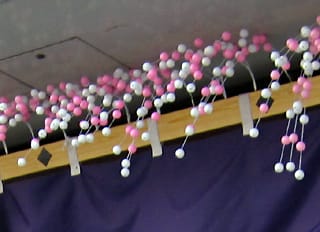「永井一郎氏が亡くなられたそうじゃ」
「永井一郎さんって…?」
「アニメ『サザエさん』(1969年~)で波平の声を担当された方、といえばわかるかの?」
アニメ「サザエさん」の磯野波平の声で知られる声優の永井一郎(ながい・いちろう)さんが27日未明、虚血性心疾患のため広島市内で死去した。82歳。
(「永井一郎さん死去 「サザエさん」波平の声」中国新聞 2014年1月28日)
「広島で亡くなられた?」
「テレビ番組のナレーションの仕事で、広島に来られとったそうじゃ」
「新聞の記事にも書いてあったけど、永井さんといえば波平さんの声、なんじゃろうね」
「波平さんといえば、「バカモ~ン!」」
「あのお父さんは、サザエさんやカツオを、よう叱りよっちゃた」
「親になってわかるのは、子どもを叱るのは難しい、ということかのう」
「「叱る」ことと「怒る」ことは違うもんね」
「叱ることは、子どものためになることを、愛情をもって言うことじゃ」
「子どもが納得できるように言い聞かせる必要もあるよ」
「感情的にならずに叱るのは、結構難しいしの」
「サザエさんやカツオを叱るのは、家族を見守る波平さんの、やさしさの裏返しじゃったんかもね」
「永井氏といえば、『宇宙戦艦ヤマト』(1974年)で、佐渡酒造(さど さけぞう)と徳川彦左衛門(とくがわ ひこざえもん)の2役を担当されとってんじゃ」
「見た目、正反対の2人を演じられとってんじゃね」
「劇場版が上映されて、ヤマトがブームになったころ、この事実を知って驚いたもんの」
「うちゃ、全部見とるわけじゃないけぇ、ようわからんけど、佐渡先生は沖田艦長の体調をサポートする役じゃったような気がするよ」
「永井さんも、同じようなことを言われとったのう」
佐渡は、容姿は三枚目のキャラですが精神的には二枚目なんですよ。
(『宇宙戦艦ヤマト PERFECT MANUAL 2』)
「精神的には2枚目か。なるほどね」
「佐渡先生は、容姿は3枚目じゃが、沖田艦長への献身的な態度は2枚目。で、その2枚目と3枚目のところを、うまくバランスをとりながら演じるのが難しかったそうじゃ」
「最後、地球に戻ってくる直前に沖田艦長が亡くなられたとき、佐渡先生がした敬礼は2枚目のところじゃろうね」
「ヤマトは、若者たちが成長する話。そんな若者たちを見守り、さりげなく助言するのが徳川さんの役回りでもあった。あと、『機動戦士ガンダム』(1969年)にも触れとかんにゃいけん」
「ガンダム?」
「永井氏はガンダムでナレーションを担当されとってんじゃ」
人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって、既に半世紀が過ぎていた。
地球の周りの巨大な人工都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み、育て、そして死んでいった。
宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。
この一ヶ月あまりの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。
人々はみずからの行為に恐怖した。
戦争は膠着状態に入り、八ヶ月あまりが過ぎた。
(『機動戦士ガンダム』第1話オープニングナレーションより)
「おぉー、この声も永井さんじゃったんか」
「次回予告の「君は生き延びる事ができるか?」も永井氏じゃ」
「へぇ」
「オープニングナレーションは、「神の視点から、すべてを見通しているような感じ」で収録した、と語られとったのを読んだ記憶があるのう」
「波平さんや徳川さん、佐渡先生が見守る役じゃとしたら、今度は天の上から見通しているような役じゃったんかね」
「ガンダムでは、ナレーションのほかにも、いろんなキャラの声も担当されとってんじゃ」
↓ガンダムで永井氏は何役演じているのか、についてはこちら↓
「アニメ機動戦士ガンダム(1年戦争)で声優の永井一郎さんが何役もやってますが、...」yahoo知恵袋
「ざっと20人!」
「これ以外にも、名前のないキャラも担当されとってじゃけぇ、一体何人になることやら」
「永井さんがおってんなかったら、ガンダムも成り立ってなかったともいえるわけじゃね」
「『サザエさん』『ヤマト』『ガンダム』と3作品を並べてみると、それぞれ45年前、40年前、35年前に放送が始まったことになるんじゃの」
「ありゃま、そんなむかしの話になるん?」
「わしらも歳を取るはずじゃ」
「今日は、先日亡くなられた声優の永井一郎さんについて話をさせてもらいました」
「永井氏のご冥福をお祈りします。ほいじゃあ、またの」
「永井一郎さんって…?」
「アニメ『サザエさん』(1969年~)で波平の声を担当された方、といえばわかるかの?」
アニメ「サザエさん」の磯野波平の声で知られる声優の永井一郎(ながい・いちろう)さんが27日未明、虚血性心疾患のため広島市内で死去した。82歳。
(「永井一郎さん死去 「サザエさん」波平の声」中国新聞 2014年1月28日)
「広島で亡くなられた?」
「テレビ番組のナレーションの仕事で、広島に来られとったそうじゃ」
「新聞の記事にも書いてあったけど、永井さんといえば波平さんの声、なんじゃろうね」
「波平さんといえば、「バカモ~ン!」」
「あのお父さんは、サザエさんやカツオを、よう叱りよっちゃた」
「親になってわかるのは、子どもを叱るのは難しい、ということかのう」
「「叱る」ことと「怒る」ことは違うもんね」
「叱ることは、子どものためになることを、愛情をもって言うことじゃ」
「子どもが納得できるように言い聞かせる必要もあるよ」
「感情的にならずに叱るのは、結構難しいしの」
「サザエさんやカツオを叱るのは、家族を見守る波平さんの、やさしさの裏返しじゃったんかもね」
「永井氏といえば、『宇宙戦艦ヤマト』(1974年)で、佐渡酒造(さど さけぞう)と徳川彦左衛門(とくがわ ひこざえもん)の2役を担当されとってんじゃ」
「見た目、正反対の2人を演じられとってんじゃね」
「劇場版が上映されて、ヤマトがブームになったころ、この事実を知って驚いたもんの」
「うちゃ、全部見とるわけじゃないけぇ、ようわからんけど、佐渡先生は沖田艦長の体調をサポートする役じゃったような気がするよ」
「永井さんも、同じようなことを言われとったのう」
佐渡は、容姿は三枚目のキャラですが精神的には二枚目なんですよ。
(『宇宙戦艦ヤマト PERFECT MANUAL 2』)
「精神的には2枚目か。なるほどね」
「佐渡先生は、容姿は3枚目じゃが、沖田艦長への献身的な態度は2枚目。で、その2枚目と3枚目のところを、うまくバランスをとりながら演じるのが難しかったそうじゃ」
「最後、地球に戻ってくる直前に沖田艦長が亡くなられたとき、佐渡先生がした敬礼は2枚目のところじゃろうね」
「ヤマトは、若者たちが成長する話。そんな若者たちを見守り、さりげなく助言するのが徳川さんの役回りでもあった。あと、『機動戦士ガンダム』(1969年)にも触れとかんにゃいけん」
「ガンダム?」
「永井氏はガンダムでナレーションを担当されとってんじゃ」
人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって、既に半世紀が過ぎていた。
地球の周りの巨大な人工都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み、育て、そして死んでいった。
宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。
この一ヶ月あまりの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。
人々はみずからの行為に恐怖した。
戦争は膠着状態に入り、八ヶ月あまりが過ぎた。
(『機動戦士ガンダム』第1話オープニングナレーションより)
「おぉー、この声も永井さんじゃったんか」
「次回予告の「君は生き延びる事ができるか?」も永井氏じゃ」
「へぇ」
「オープニングナレーションは、「神の視点から、すべてを見通しているような感じ」で収録した、と語られとったのを読んだ記憶があるのう」
「波平さんや徳川さん、佐渡先生が見守る役じゃとしたら、今度は天の上から見通しているような役じゃったんかね」
「ガンダムでは、ナレーションのほかにも、いろんなキャラの声も担当されとってんじゃ」
↓ガンダムで永井氏は何役演じているのか、についてはこちら↓
「アニメ機動戦士ガンダム(1年戦争)で声優の永井一郎さんが何役もやってますが、...」yahoo知恵袋
「ざっと20人!」
「これ以外にも、名前のないキャラも担当されとってじゃけぇ、一体何人になることやら」
「永井さんがおってんなかったら、ガンダムも成り立ってなかったともいえるわけじゃね」
「『サザエさん』『ヤマト』『ガンダム』と3作品を並べてみると、それぞれ45年前、40年前、35年前に放送が始まったことになるんじゃの」
「ありゃま、そんなむかしの話になるん?」
「わしらも歳を取るはずじゃ」
「今日は、先日亡くなられた声優の永井一郎さんについて話をさせてもらいました」
「永井氏のご冥福をお祈りします。ほいじゃあ、またの」