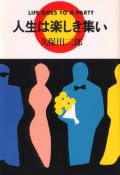ブログ友達の所で、小説の登場人物を対象とした人気ランキングをやっていて、見事チャンピオンに輝いたのが、京極夏彦の処女作「姑獲鳥の夏」(1994年)に出てくる京極堂こと、中禅寺秋彦。古本屋にして陰陽師。と言っても情けない話、この作家の作品を読んだのは初めて。大ベストセラーで数年前に映画化されDVDもあるんですね。興味が湧いたので、早速図書館で借りて読んでみました。
感想は、凄いの一言。まず作者のウンチク。日本古来の風習とか妖怪とかについての知識が豊富だし、それをこれでもかとぶつけてくるその根性はたいしたもの。業界用語が多過ぎて、さすがに途中からは、細かく理解しようとする意欲がなくなって。頭がふらふらしながらも、なんとか読了。終わってみると分厚いステーキを食べた後のような感覚。緻密な構成と因果が素晴らしい。
でもね、正直なところ後味悪いです、はい。ホラー系そのものが苦手だし、それに空想系や異次元系が入ると、もうダメ。それに輪をかけて苦手なのが、日本の伝統的陰湿陵辱SM系。なんかね、文庫本の表紙の挿絵からしてヤバイとは思っていたけど。
若かりし頃、日活ロマンポルノっていうアダルト映画があって、好きだった宇能鴻一郎モノをお目当てに観にいくと、3本立ての中の1本は、SMモノだったりして。薄暗い部屋、ローソク、赤い縄。もういけません。始まるとすぐに劇場から出たなあ。
それで面白い話を一つ。接待で赤坂にあるクラブに連れていかれたことがあって、そこでローソクプレイを初体験。するんじゃないですよ、される方。SじゃなくてM。あれってローソクと体との距離で温度調節するんですね。だから離してやると、見た目程熱くない。店を出る時、なんかイッパシのSM体験をした気になって、男の幅が拡がった気がしたのを憶えています。〈笑〉
文庫版 姑獲鳥の夏
感想は、凄いの一言。まず作者のウンチク。日本古来の風習とか妖怪とかについての知識が豊富だし、それをこれでもかとぶつけてくるその根性はたいしたもの。業界用語が多過ぎて、さすがに途中からは、細かく理解しようとする意欲がなくなって。頭がふらふらしながらも、なんとか読了。終わってみると分厚いステーキを食べた後のような感覚。緻密な構成と因果が素晴らしい。
でもね、正直なところ後味悪いです、はい。ホラー系そのものが苦手だし、それに空想系や異次元系が入ると、もうダメ。それに輪をかけて苦手なのが、日本の伝統的陰湿陵辱SM系。なんかね、文庫本の表紙の挿絵からしてヤバイとは思っていたけど。
若かりし頃、日活ロマンポルノっていうアダルト映画があって、好きだった宇能鴻一郎モノをお目当てに観にいくと、3本立ての中の1本は、SMモノだったりして。薄暗い部屋、ローソク、赤い縄。もういけません。始まるとすぐに劇場から出たなあ。
それで面白い話を一つ。接待で赤坂にあるクラブに連れていかれたことがあって、そこでローソクプレイを初体験。するんじゃないですよ、される方。SじゃなくてM。あれってローソクと体との距離で温度調節するんですね。だから離してやると、見た目程熱くない。店を出る時、なんかイッパシのSM体験をした気になって、男の幅が拡がった気がしたのを憶えています。〈笑〉
文庫版 姑獲鳥の夏