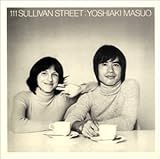だいぶ前に石井希尚(まれひさ)著の「この人と結婚していいの?」を紹介したけど、今日はその続編?で渡辺淳一のエッセイ集「懲りない男と反省しない女」(2005年)。婦人公論に連載された「男の錯覚 女の幻想」を再構成してまとめたもの。前者が分かり易い比喩を中心にして男と女の違いを論じているのに対し、後者はセックスが中心。なにせ渡辺淳一ですから。
読み終わった感想としては、“その通り”の一言。自分の感覚に非常に近かった。特に男については自分が書いてもこうなるだろうと思うぐらい同じ。自分は男の中でも特殊な部類だろうなと思っていたけど、ひょっとしてそうでもないかな、なんて感じて。それでしみじみ思うのは、男と女って顔は似ているけど違う動物なんだってこと。これはもう確信に近い域に到達しています。
「心を重視する女とセックスにこだわる男」、「結婚で愛を育みたい女と不倫でしか燃えない男」、「寝るまでが優しい男と寝てから深まる女」、「女が夢見る夫と男が望む妻」、「慣れて燃える女と慣れて醒める男」、「セックスレスでも愛のある夫とそれでは許せぬ妻」、「夫の浮気を許せない妻と浮気ぐらいと考えている夫」、というのがサブタイトル。うーん、ガチンコですね。
どうですか?大体内容想像できますよね?でも男の立場で物を言っているから、対談相手の女性には彼の言っていることは、ほとんど理解できていません。まあ所詮違う動物?だから、互いに理解できる方が不思議だと考えた方が自然なんだけど。思うに渡辺先生は、こういう男と女の違いを深く理解した上で、次々と素晴らしい恋愛小説を書いているわけで、そこが素晴らしい。まあ自分なりの解釈で言えば、いつまでもときめいていたいという気持ちだけは、男と女も同じってことだと思います。
写真はGWに東京藝大美術館へ行った時に展示してあった黒田清輝の裸婦画三部作「智・感・情」(1899年)。絵を見て女を感じるというのはあまりないことだけど、これは別格。明治時代にしてはモデルの女性のプロポーションが抜群だったなあ。
懲りない男と反省しない女
読み終わった感想としては、“その通り”の一言。自分の感覚に非常に近かった。特に男については自分が書いてもこうなるだろうと思うぐらい同じ。自分は男の中でも特殊な部類だろうなと思っていたけど、ひょっとしてそうでもないかな、なんて感じて。それでしみじみ思うのは、男と女って顔は似ているけど違う動物なんだってこと。これはもう確信に近い域に到達しています。
「心を重視する女とセックスにこだわる男」、「結婚で愛を育みたい女と不倫でしか燃えない男」、「寝るまでが優しい男と寝てから深まる女」、「女が夢見る夫と男が望む妻」、「慣れて燃える女と慣れて醒める男」、「セックスレスでも愛のある夫とそれでは許せぬ妻」、「夫の浮気を許せない妻と浮気ぐらいと考えている夫」、というのがサブタイトル。うーん、ガチンコですね。
どうですか?大体内容想像できますよね?でも男の立場で物を言っているから、対談相手の女性には彼の言っていることは、ほとんど理解できていません。まあ所詮違う動物?だから、互いに理解できる方が不思議だと考えた方が自然なんだけど。思うに渡辺先生は、こういう男と女の違いを深く理解した上で、次々と素晴らしい恋愛小説を書いているわけで、そこが素晴らしい。まあ自分なりの解釈で言えば、いつまでもときめいていたいという気持ちだけは、男と女も同じってことだと思います。
写真はGWに東京藝大美術館へ行った時に展示してあった黒田清輝の裸婦画三部作「智・感・情」(1899年)。絵を見て女を感じるというのはあまりないことだけど、これは別格。明治時代にしてはモデルの女性のプロポーションが抜群だったなあ。
懲りない男と反省しない女



















 ラピスラズリ
ラピスラズリ