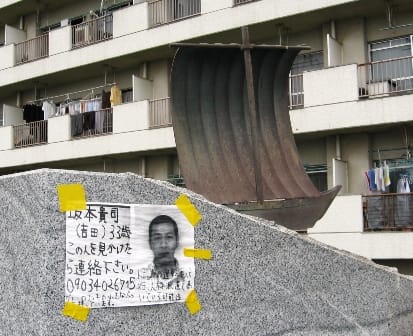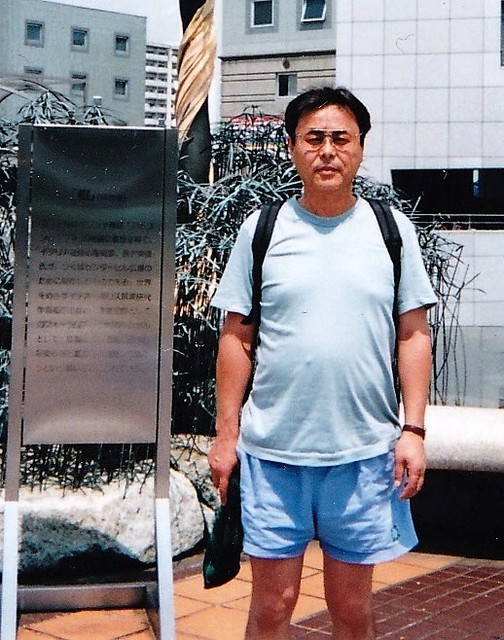水海道シリーズはお休みします。それで、わたくし一昨日の土曜日に“ひな祭り”に行ってきたのです。
ホントのところは、別の用件で土浦に行ったところ、偶々、市内で“ひな祭り”をやっていたのです。
ひな祭りのメイン会場は、亀城公園の近くにある「まちかど蔵」です。そのほか、50軒ほどの商店でお雛様を飾っているのです。
“まちかど蔵”の前には、“カブスカウト”の子供達が盛んに“呼び込み”をしています。普段とは異なり、それなりの“賑わい”です。
私も、“元気”で可愛い彼らから、「ひな祭りの会場案内マップ」と「ティッシュ」を受け取りました。

普段は薄暗い蔵ですが、この日は、赤い毛氈の雛壇、色とりどりのお雛様、桃の花に梅の花、いつもと違い華やいでいます。
雛壇下の孟宗竹の緑が全体を引き締めています。

このお雛様達の衣は、地元の名産「ハスの葉」等の植物の葉っぱだそうです。

こちらのお二人の衣装は“渋く”、タダの蓮の葉っぱとは思えません。

こちら、郷土色豊かに「レンコン」が飾られています。名産品ですから、まぁ、いいか。

この子供達の呼び込みは、元気過ぎ、“過熱気味”で、かなり煩くなってきました。2グループで競っているようです。

駅前を通ってこの会場に来たのですが、ひな祭りの開催を感じる雰囲気は何処にもありませんでした。
呼び込み、案内地図配りは、街の玄関である駅前でやった方が、ずっとずっと効果的だと思うのでした。
“雛人形製作関係”のおばさんが、「煩いはねぇー」と、小さな声で呟くのが聞こえました。
可愛い声も、何度も何度も繰り返し聞いていると、甲高くて、耳障りな騒音に聞こえてくるのです。
子供達は一生懸命なんですけどねぇ・・・・・・。指導者の方、やっぱり、駅前がいいですよ。
亀城公園の“垂れ梅”

ほぼ満開、甘い香りが漂います。

この日は、風もなく、暖かく、モォー!ホントに春!

この幟がある処に、お雛様が飾られています。こういう「ひな祭り」、各地でやるようになりました。

それほどお金もかからず、それなりに人が集まります。土浦のひな祭りは今年が始めてかも?
孟宗竹を使った花飾り、冬が終り春が来た気分になります。

何故か? このお人形屋さんは、祭りには不参加のようです。
商売人にとっては、“桃の節句”はもう終りのようです。
“端午の節句”に向かって動いているのです。

偶々行った土浦で、思い掛けずのひな祭りでした。
明日は、間違いなく、水海道シリーズです。
それでは、また明日。