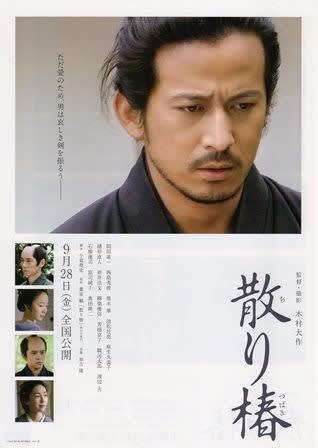この作品は、ロシア公開時に、ロシア正教会の信徒や過激派が上映中止運動や放火事件を起こすなどがあったが、本国だけで210万人が見た話題作といわれる。
古典的な純愛物語に過ぎないが、宮殿やバレエのシーンの豪華さは、ロシア映画の持つ底力を久しぶりに感じさせるものだ。
気鋭のロシアの監督、アレクセイ・ウチーチェリが、ロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世と、マリインスキー・バレエ団の伝説のプリマと謳われたマチルダ・クシェシンスカヤの、許されざる恋の実話を大胆かつ華麗に描き上げた。
1890年代のサントペテルブルグ・・・。
ロシアの王位継承者であるニコライ2世(ラース・アイディンガー)は、世界的に有名なバレリーナのマチルダ(ミハリナ・オルシャンスカ)を一目見た瞬間恋に落ちる。
二人は惹かれあうが、ニコライにはアリックス(ルイーゼ・ヴォルフラム)という婚約者がいた。
ニコライは、皇帝の座と真実の恋のはざまで揺れ動く。
燃え上がる彼らの恋は、ロシア国内で賛否両論を巻き起こし、国を揺るがすほどの一大ロマンスとなる。
父の死、王位継承、政略結婚、外国勢力の隆盛と、滅びゆくロシア帝国とともに、二人の情熱的な恋は引き裂かれようとしていた・・・。
当時、ニコライ2世といえば、国内では「聖人」として神格化されていた人物だ。
この作品をめぐって、皇帝の名誉を傷つけるとして賛否両論が飛び交うのはもちろん、ウチーチェリ監督を尊敬していたプーチン大統領が参戦したり、キリスト教過激派も登場し、俳優たちも安全上の理由でプレミア上映会を欠席するという事態にまで発展したのだった。
実話にもとずく物語だけに、ロシア全土を巻き込んだセンセーショナルな話題作となった。
エカテリーナ宮殿ももちろんだが、世界三大バレエ団であるマリインスキー・バレエ団の壮麗な舞台が再現され、圧倒的なスケールと豪華絢爛たる映像美は見逃せない。
総体的な軽やかな仕上がりで、恋愛映画としては小品(?)としてのまとまりもよく、片意地張らずに楽しめ作品となった。
ただし、皇帝ニコライの味付けが薄い。
あまり葛藤が感じられないのはどうしてか。
平民であるマチルダと皇族のアリックスの関係など魅力的に描かれているが、マチルダを選ぶということは帝位を譲ることになる。
この恋の試練は、ニコライの、帝位を継ぐのか放棄するのかという選択になる。
不倫の結果は、大体破滅に向かうというのがロシア文学では多いようだが、ニコライの悲劇はさてどうであったろうか。
この愛と官能の欲求を描いたロシア映画「マチルダ 禁断の恋」は、ヒロインの人生を自分で掴み取ろうという野心を一杯に感じさせて、結構面白く見せる。
[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)
この作品、関東一円での上映を終えており、現在近県から全国各地へと、上映館は順次静かに広がりつつあるようだ。
次回は日本映画「雪の華」をとりあげます。