後半戦が始まったものの、当初は90分を予定していたのに残りは60分しかない。しかし前半の印象からして、後半が60分では終わらないことだろう。時間の延長を画策することになる。われわれのあと、その場を使いそうな人や団体はいなさそうだから、勝手に延長して黙っておけばわからないかなとも考えるが、そういう心がけの悪い振る舞いは世間を狭くするだけである。
後半もどうせ人の話を聞くだけなのだが、前半はそれだけでも盛り上がったので、どんな話が飛び出すのやら期待しないわけにはいかない。そして20代のある女性に話が振られた。彼女曰く、「ある人のために一生懸命になる仲間がいるなんて、マンガのなかだけの話だと思っていました。ところが、本当にそういう仲間がいたので驚いてしまいましたし、私もその仲間の世界に少しでも入ることができてとてもうれしかったです」
これには、小生も含め会場全体が笑い出してしまった。彼女のイメージしているマンガというのは『ワンピース』あたりを指すのだろうか。ところが小生は、『ワンピース』ってきらいなんだよね。そもそも線が好きじゃないし、なにかあれば、仲間だ、友情だと騒ぎ立て、大声を上げれば力が倍増して窮地を脱することができる。世の中ってそんなものじゃないだろというわけだ。
しかし彼女の話を聞いて笑い転げつつ、いまの世の中ってそんなものなのか、とも感じた。つまり、特に若い人ほど人間関係が希薄になるよう制度設計がされているのだろう。そのうえSNSの時代である。ネット上での人間どうしの結びつきに、どうしてもウェートが置かれてしまうようになる。
安田浩一氏の『ネットと愛国』(講談社)でだったか、在日朝鮮・韓国人の方が通名を使うことを口汚くののしる在特会のメンバーが、リアルの場でも互いにハンドルネームで呼び合っているとあり、読んでいて大笑いしてしまったことがある。しかも、在特なんてネットにしか居場所のなかった連中がリアルの場で集まろうとした組織であるから、そのうち慣れないリアルでの活動に疲れてしまい脱落していくのが多いとあり、なるほどなあと思った次第である。
もちろん、一般の人が在特並みにうだつの上がらない連中であるはずがないのだけれど、小生を含めて在特的精神病理には多かれ少なかれ感染しているわけである。現在を生きるということは、そういうことだ。孤独をまぎらすためSNSを通して人付き合いを求めても、実際の人付き合いやSNS上での付き合いにはそのうち飽きてしまって嫌気がさす。この矛盾から生まれるフラストレーションは、そのうちどうなるのだろうか。
あれ?話がずいぶんとそれていってしまった。「ある人のために一生懸命になる仲間がいる」ということがリアルなものとして受け止められない感覚、それについて考えてみようとしていたのである。言うたら悪いけれど、小生なんてガキのころから人には恵まれている方なので、仲間感覚というのはそういうものだとばかり感じてきていた。仲間の一人が教員に殴られたら、小生に罪がないにしてもそいつと一緒に殴られるのはしょうがないという感覚である。それがリアルではなく、マンガの世界?なんやそりゃ?
見た感じ、発言した彼女は内向的で、積極的に他者と触れ合おうとするタイプではなさそうだ。それゆえに、これまで仲間と呼べる友人がいなかったのだろうか。そんなこともあるまい。やはり、いまの若い人々に通底するある種の感覚なのだろう。先ほど「制度設計」という言葉を使ったけれど、例えば幼いころにどうでもいいようなことで取っ組み合いのケンカになるなんて、小生には当たり前のことであった。そんなのいまでは、暴力反対の四文字熟語で当事者の内面で即座に却下されることだろう。
いやいや、暴力が正しいと述べているわけではない。人と人との付き合いには、ときには暴力も含まれるというだけのことだ。Oさんが以前話していたことで、小生は大笑いしてしまったことがあり、それは「80年代まで、議論していて相手に伝わらなければ、すぐに殴っていたよ」げな。どうもねえ、殺伐とした状況にこそ濃い人間関係が生まれるのだろうか。そんなわけもない。
つまり、だれかと付き合うということは、常に痛みをともなう可能性があるということなのだ。それがどういう痛みなのかはケース・バイ・ケースなので一般化しにくいけれど、その痛みを一緒に乗り越えたところで仲間意識が生まれる。ところが、最初からその痛みを忌避してしまったら、仲間意識にまで到達するわけがない。発言した彼女は、その痛みの共有すらも恐れてきたのではないのだろうか。おのれが精神的に傷つくことを恐れ、それゆえに他者を傷つけることを恐れという循環構造である。もちろんそれは、彼女固有の問題ではなく、現在に一般化しつつあることなのだろう。その当然の帰結として、だれとも本音で向き合うことができない、したがってだれかと仲間意識を共有することもできないということにつながる。
そうすると次の疑問として(ここまでの論述がそれなりに正当なものであるとして)、どうしてそんなに傷つくことがいやなのか、となる。傷つくとは、ケンカに負けたなんてレベルの単純なものではなく、極端な場合には自死にまでいたるものなのだろう。しかし、最近は若い人との付き合いが減ってきているから、ここでは疑問を提起するところまでしかできない。
後半もどうせ人の話を聞くだけなのだが、前半はそれだけでも盛り上がったので、どんな話が飛び出すのやら期待しないわけにはいかない。そして20代のある女性に話が振られた。彼女曰く、「ある人のために一生懸命になる仲間がいるなんて、マンガのなかだけの話だと思っていました。ところが、本当にそういう仲間がいたので驚いてしまいましたし、私もその仲間の世界に少しでも入ることができてとてもうれしかったです」
これには、小生も含め会場全体が笑い出してしまった。彼女のイメージしているマンガというのは『ワンピース』あたりを指すのだろうか。ところが小生は、『ワンピース』ってきらいなんだよね。そもそも線が好きじゃないし、なにかあれば、仲間だ、友情だと騒ぎ立て、大声を上げれば力が倍増して窮地を脱することができる。世の中ってそんなものじゃないだろというわけだ。
しかし彼女の話を聞いて笑い転げつつ、いまの世の中ってそんなものなのか、とも感じた。つまり、特に若い人ほど人間関係が希薄になるよう制度設計がされているのだろう。そのうえSNSの時代である。ネット上での人間どうしの結びつきに、どうしてもウェートが置かれてしまうようになる。
安田浩一氏の『ネットと愛国』(講談社)でだったか、在日朝鮮・韓国人の方が通名を使うことを口汚くののしる在特会のメンバーが、リアルの場でも互いにハンドルネームで呼び合っているとあり、読んでいて大笑いしてしまったことがある。しかも、在特なんてネットにしか居場所のなかった連中がリアルの場で集まろうとした組織であるから、そのうち慣れないリアルでの活動に疲れてしまい脱落していくのが多いとあり、なるほどなあと思った次第である。
もちろん、一般の人が在特並みにうだつの上がらない連中であるはずがないのだけれど、小生を含めて在特的精神病理には多かれ少なかれ感染しているわけである。現在を生きるということは、そういうことだ。孤独をまぎらすためSNSを通して人付き合いを求めても、実際の人付き合いやSNS上での付き合いにはそのうち飽きてしまって嫌気がさす。この矛盾から生まれるフラストレーションは、そのうちどうなるのだろうか。
あれ?話がずいぶんとそれていってしまった。「ある人のために一生懸命になる仲間がいる」ということがリアルなものとして受け止められない感覚、それについて考えてみようとしていたのである。言うたら悪いけれど、小生なんてガキのころから人には恵まれている方なので、仲間感覚というのはそういうものだとばかり感じてきていた。仲間の一人が教員に殴られたら、小生に罪がないにしてもそいつと一緒に殴られるのはしょうがないという感覚である。それがリアルではなく、マンガの世界?なんやそりゃ?
見た感じ、発言した彼女は内向的で、積極的に他者と触れ合おうとするタイプではなさそうだ。それゆえに、これまで仲間と呼べる友人がいなかったのだろうか。そんなこともあるまい。やはり、いまの若い人々に通底するある種の感覚なのだろう。先ほど「制度設計」という言葉を使ったけれど、例えば幼いころにどうでもいいようなことで取っ組み合いのケンカになるなんて、小生には当たり前のことであった。そんなのいまでは、暴力反対の四文字熟語で当事者の内面で即座に却下されることだろう。
いやいや、暴力が正しいと述べているわけではない。人と人との付き合いには、ときには暴力も含まれるというだけのことだ。Oさんが以前話していたことで、小生は大笑いしてしまったことがあり、それは「80年代まで、議論していて相手に伝わらなければ、すぐに殴っていたよ」げな。どうもねえ、殺伐とした状況にこそ濃い人間関係が生まれるのだろうか。そんなわけもない。
つまり、だれかと付き合うということは、常に痛みをともなう可能性があるということなのだ。それがどういう痛みなのかはケース・バイ・ケースなので一般化しにくいけれど、その痛みを一緒に乗り越えたところで仲間意識が生まれる。ところが、最初からその痛みを忌避してしまったら、仲間意識にまで到達するわけがない。発言した彼女は、その痛みの共有すらも恐れてきたのではないのだろうか。おのれが精神的に傷つくことを恐れ、それゆえに他者を傷つけることを恐れという循環構造である。もちろんそれは、彼女固有の問題ではなく、現在に一般化しつつあることなのだろう。その当然の帰結として、だれとも本音で向き合うことができない、したがってだれかと仲間意識を共有することもできないということにつながる。
そうすると次の疑問として(ここまでの論述がそれなりに正当なものであるとして)、どうしてそんなに傷つくことがいやなのか、となる。傷つくとは、ケンカに負けたなんてレベルの単純なものではなく、極端な場合には自死にまでいたるものなのだろう。しかし、最近は若い人との付き合いが減ってきているから、ここでは疑問を提起するところまでしかできない。















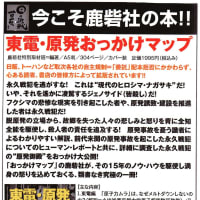




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます