猛烈な台風があちこちに傷跡を残せば、次は大地震。なにはともあれ、被害に遭われたかたにはお見舞い申し上げます。北海道の状況はまだ細部まで把握できていないだろうけれど、これからの復興は大変だと思う。幸いにも原発に異常がなくてよかった。どこかで地震が発生するたびに、原発は大丈夫かと不安がよぎってしまう。庶民が安心して暮らせる日々を目指すためにも、原発は即時廃炉にしてもらいたい。
しかしそこで、廃炉にしても出てきた核のゴミはどうなるのだろうか。結局はどこかに何万年もかけて保存するしかない。その、原発は人間と折り合いがつかない存在であることを示す難問を覆い隠すべく、再処理なんてバカげたことを為政者は主張してきたわけである。しかし、再処理なんてうまくいくわけがなく、「日本はプルトニウム持ちすぎ」とアメリカに嫌味を言われる始末だ。ドイツは、核のゴミをどのようにしたのだろうか。不勉強ゆえに知らない。
反原発の主張はまた別の機会とし、某日曜日、朝日新聞の歌壇を眺めていた。小生は短歌や俳句をたしなんだこともないし、自らやりたいと思うわけではないけれど、しかし、掲載されている歌句を眺めているのはなんとなく楽しいものである。しかも遅く起きた日曜の朝、寝ぼけまなこでボケーッと字面を追っていると、時おりハッと目を見開かされる歌句に出会うときがある。その日は、「うたをよむ」という中央の解説記事の欄に衝撃を受けた。ある俳人が、昨年5月に亡くなられたかたについて評を述べていたからだ。
要するに、その亡くなったかたの俳句はすごかったという内容で、それを「言葉から分枝する大樹を脳裏に茂らせ」なんていう、読んでいてこちらが赤面しそうないかにも俳人らしい表現を交えつつ述べている。そして最後に、亡くなったかたは「正真の俳人」であったと結んでいる。その語の意は、彼の句はイロモンじゃありませんよということなのだろう。その評者が彼の句を大いに持ち上げていることはよくわかるし、さらには彼自身に畏敬の念を持っていることも伝わってくる内容であった。
それでも、「正真」なる単語にはどこか違和感をかきたてる響きがある。先ほど述べたように、小生は俳句をたしなむわけではない。したがって、俳人なるものがどういう人なのかを知らない。もっといえば、俳人なるものの定義なんてものがあるわけがないのだ。これに似た話で、だれしもが作家を自称することができる。その意(こころ)は、「なにか有名な作品を書かれたんですか?」という質問に、「いま構想中です」と答えればいいというものだ。このエピソードと先ほどの評とでちがうのは、亡くなった彼はすでに多くの句を残し、多くの人に感動(などという安っぽい表現に収まらないもの)を与えてきた点である。つまり、すでに彼は俳人ではないかというのが、小生の第一印象であったということだ。それが「正真」かどうかなんてどうでもいいだろ、という気分になったのである。レーニン、トロツキーをはじめ、だれが正真のマルクス主義者かなんてことを言い出したら、それが制度的権威として作動してしまう。亡くなった彼は、それこそ忌避したかった状況にちがいない。
いや、ごめんなさい。酒を飲みながら駄文をベチャベチャ記していたら、少し興奮してきたようだ。まず、「うたをよむ」という欄に衝撃を受け、その内容に感動した。次に、そこで評されている人物はイロモンと見なされる可能性もあった。そこで評者は、決してそんなことはなく、彼の俳句はものすごく衝撃的で常に読者を刮目させてきたと述べているだけである。そこで小生は、なるほどいいことを述べるなあと思いつつも、そのいかにも俳人らしい表現についていけなかった、それだけのことである。しかし、「それだけ」のことをよくもまあ長く書くなあと、われながら感心してしまう。
その亡くなった彼に直接お会いしたことはない。文通したこともない。理由は、小生が東京に出てきたのが遅すぎたからだ。そして、彼から間接的に批判されたことはあるし、間接的な交流ならば間断なくあった。彼の自筆で句集をご恵投いただいたこともあるので、一応は小生の存在くらいは知っていたのだろうか(知らなくてもさして困ることもないのだけれども)。しかし、一度直接会いたかった人のうちのひとりであった。
彼の句に少し触れておきたい。2002年の句に「春の雷つはもの一人絶えにけり」というものがある(出典は明示しない)。その絶えた「つはもの」さんとは、小生と縁が深かった。それだけに、この句には違和感を抱いた。そもそも、彼は「つはもの」さんを直接には知らなかった。一方、小生はその「つはもの」さんとは日常的な付き合いがあった。それだけに、「つはもの」なる表現が、その人を表すのに適切ではないという印象を持ったのだ。
そこでまた考える。「つはもの」さんは過去に兵隊さんを目指したことがあった。そして「つはもの」さんは死ぬまで、兵隊さんになろうと決意した自分から抜け出すことができなかった。そうすると、「つはもの」という表現こそがぴったりではないのだろうか。「つはもの」さんのいろんな面を小生が知っているからといって、それが亡くなった彼の俳句表現以上の理解に到達していたのだろうか、という気もしてしまう。要するに、小生は「つはもの」さんのなにを知っていたのだろうかという、なんともいえぬ苦い思いがこみ上げてくるわけだ。小生よりも、「つはもの」さんと面識のなかった彼のほうがより本質を衝いていたのである。ウーム、まさに彼は正真の俳人であった。
しかしそこで、廃炉にしても出てきた核のゴミはどうなるのだろうか。結局はどこかに何万年もかけて保存するしかない。その、原発は人間と折り合いがつかない存在であることを示す難問を覆い隠すべく、再処理なんてバカげたことを為政者は主張してきたわけである。しかし、再処理なんてうまくいくわけがなく、「日本はプルトニウム持ちすぎ」とアメリカに嫌味を言われる始末だ。ドイツは、核のゴミをどのようにしたのだろうか。不勉強ゆえに知らない。
反原発の主張はまた別の機会とし、某日曜日、朝日新聞の歌壇を眺めていた。小生は短歌や俳句をたしなんだこともないし、自らやりたいと思うわけではないけれど、しかし、掲載されている歌句を眺めているのはなんとなく楽しいものである。しかも遅く起きた日曜の朝、寝ぼけまなこでボケーッと字面を追っていると、時おりハッと目を見開かされる歌句に出会うときがある。その日は、「うたをよむ」という中央の解説記事の欄に衝撃を受けた。ある俳人が、昨年5月に亡くなられたかたについて評を述べていたからだ。
要するに、その亡くなったかたの俳句はすごかったという内容で、それを「言葉から分枝する大樹を脳裏に茂らせ」なんていう、読んでいてこちらが赤面しそうないかにも俳人らしい表現を交えつつ述べている。そして最後に、亡くなったかたは「正真の俳人」であったと結んでいる。その語の意は、彼の句はイロモンじゃありませんよということなのだろう。その評者が彼の句を大いに持ち上げていることはよくわかるし、さらには彼自身に畏敬の念を持っていることも伝わってくる内容であった。
それでも、「正真」なる単語にはどこか違和感をかきたてる響きがある。先ほど述べたように、小生は俳句をたしなむわけではない。したがって、俳人なるものがどういう人なのかを知らない。もっといえば、俳人なるものの定義なんてものがあるわけがないのだ。これに似た話で、だれしもが作家を自称することができる。その意(こころ)は、「なにか有名な作品を書かれたんですか?」という質問に、「いま構想中です」と答えればいいというものだ。このエピソードと先ほどの評とでちがうのは、亡くなった彼はすでに多くの句を残し、多くの人に感動(などという安っぽい表現に収まらないもの)を与えてきた点である。つまり、すでに彼は俳人ではないかというのが、小生の第一印象であったということだ。それが「正真」かどうかなんてどうでもいいだろ、という気分になったのである。レーニン、トロツキーをはじめ、だれが正真のマルクス主義者かなんてことを言い出したら、それが制度的権威として作動してしまう。亡くなった彼は、それこそ忌避したかった状況にちがいない。
いや、ごめんなさい。酒を飲みながら駄文をベチャベチャ記していたら、少し興奮してきたようだ。まず、「うたをよむ」という欄に衝撃を受け、その内容に感動した。次に、そこで評されている人物はイロモンと見なされる可能性もあった。そこで評者は、決してそんなことはなく、彼の俳句はものすごく衝撃的で常に読者を刮目させてきたと述べているだけである。そこで小生は、なるほどいいことを述べるなあと思いつつも、そのいかにも俳人らしい表現についていけなかった、それだけのことである。しかし、「それだけ」のことをよくもまあ長く書くなあと、われながら感心してしまう。
その亡くなった彼に直接お会いしたことはない。文通したこともない。理由は、小生が東京に出てきたのが遅すぎたからだ。そして、彼から間接的に批判されたことはあるし、間接的な交流ならば間断なくあった。彼の自筆で句集をご恵投いただいたこともあるので、一応は小生の存在くらいは知っていたのだろうか(知らなくてもさして困ることもないのだけれども)。しかし、一度直接会いたかった人のうちのひとりであった。
彼の句に少し触れておきたい。2002年の句に「春の雷つはもの一人絶えにけり」というものがある(出典は明示しない)。その絶えた「つはもの」さんとは、小生と縁が深かった。それだけに、この句には違和感を抱いた。そもそも、彼は「つはもの」さんを直接には知らなかった。一方、小生はその「つはもの」さんとは日常的な付き合いがあった。それだけに、「つはもの」なる表現が、その人を表すのに適切ではないという印象を持ったのだ。
そこでまた考える。「つはもの」さんは過去に兵隊さんを目指したことがあった。そして「つはもの」さんは死ぬまで、兵隊さんになろうと決意した自分から抜け出すことができなかった。そうすると、「つはもの」という表現こそがぴったりではないのだろうか。「つはもの」さんのいろんな面を小生が知っているからといって、それが亡くなった彼の俳句表現以上の理解に到達していたのだろうか、という気もしてしまう。要するに、小生は「つはもの」さんのなにを知っていたのだろうかという、なんともいえぬ苦い思いがこみ上げてくるわけだ。小生よりも、「つはもの」さんと面識のなかった彼のほうがより本質を衝いていたのである。ウーム、まさに彼は正真の俳人であった。















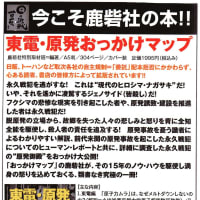




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます