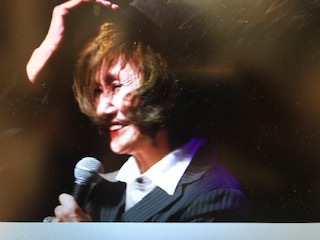今日は 震災で延び延びになっていた NHK文化センターの
8か月ぶりの講座でした。
吾妻鏡 全52巻中(うち一巻抜け) 今日から9巻目に入ります。
文治5年(1189年)正月3日 おう(土完 二字くっつける)飯例の
ごとし。 おう飯とは 当時一汁一菜に1.5合の酒、 調味料の乗った
経木の盆が 三枚出されること。 大盤振る舞い はここからきています。
これを供するには 厳格な順番があり 頼朝の信頼篤い者順です。
この年は 率いる兵は3百騎ながら(一万を越す兵を擁する者もいた)
旗揚げの第一人者、 頼朝が父とも仰いだ 千葉常胤でした。
続いて 御弓始です。 当時 武士とは 弓を使う人でした。
選ばれたのは 頼朝の異母弟範頼の部下で 武士の心意気を
頼朝に高く評価された 庄司行平です。 行平は9日の頼家の
弓始めでも 一番射手をつとめました。 この日の4番射手の控えに
海野小太郎幸氏が 選ばれています。 幸氏は 人質となった木曽義仲
の嫡男・義高についてきて 義高の影武者的存在でした。 義高亡き後も
弓の腕を買われ 頼朝に用いられました。
ところで 鎌倉武士の食卓は 経木をランチョンマットのように用いた
素焼きの器で 使い捨てでした。 庶民の食事は 木や塗の食器
だったそうです。 経木の上に素焼きの器がのったものが 沢山
出土したら それは五位以上の身分の高い武士の屋敷があったと
いうことらしい。
風呼 でした