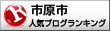高齢者が地域で集まって体操や茶話会などをして過ごす、住民主体の「通いの場」事業が、市原市のあちらこちらで立ち上がっています。
運営団体には補助金(立ち上げ支援10万円、基本額年間10万円など)が支給されることもあって、現在その数70カ所以上。行政の当初の予想を大幅に上回る勢いです。
そのうちの一つ、辰巳台にあるケアハウス辰巳彩風苑で開かれている「彩クラブ」の様子です。


補助金は主に筋トレの用の重りなどの備品購入に充てられています。

徐々に金属のウェイトを足していくのも励みになるそうです。全部つけると結構重い!
約2時間以上も様々なメニューがテンポよく進められていきますが、皆慣れた様子で手際よく道具を用意したり片付けたり、移動したり。
メニューはインストラクターが考えるのではなく、参加者がアイディアを出し合うのだそうです。

釣られるイカも釣り竿も、皆の手作り。頭も手も動かせて、一石二鳥!

私も一緒に「捕ったどー!」

彩クラブの場合、高齢者施設がご厚意で会場を貸してくださっていて、入居者も参加されています。施設の外の仲間との接点ができることが生き甲斐にも繋るので、施設側も歓迎しているとのこと。
市原市の「通いの場」は公民館や自治会館などを借りる場合が多いようですが、今後はこうした民間の協力がもっと増えると良いですね。
常に笑顔と笑い声が飛び交う「通いの場 彩クラブ」。私も人生の大先輩と楽しい時間を過ごさせていただきました(^^♪
運営団体には補助金(立ち上げ支援10万円、基本額年間10万円など)が支給されることもあって、現在その数70カ所以上。行政の当初の予想を大幅に上回る勢いです。
そのうちの一つ、辰巳台にあるケアハウス辰巳彩風苑で開かれている「彩クラブ」の様子です。


補助金は主に筋トレの用の重りなどの備品購入に充てられています。

徐々に金属のウェイトを足していくのも励みになるそうです。全部つけると結構重い!
約2時間以上も様々なメニューがテンポよく進められていきますが、皆慣れた様子で手際よく道具を用意したり片付けたり、移動したり。
メニューはインストラクターが考えるのではなく、参加者がアイディアを出し合うのだそうです。

釣られるイカも釣り竿も、皆の手作り。頭も手も動かせて、一石二鳥!

私も一緒に「捕ったどー!」

彩クラブの場合、高齢者施設がご厚意で会場を貸してくださっていて、入居者も参加されています。施設の外の仲間との接点ができることが生き甲斐にも繋るので、施設側も歓迎しているとのこと。
市原市の「通いの場」は公民館や自治会館などを借りる場合が多いようですが、今後はこうした民間の協力がもっと増えると良いですね。
常に笑顔と笑い声が飛び交う「通いの場 彩クラブ」。私も人生の大先輩と楽しい時間を過ごさせていただきました(^^♪