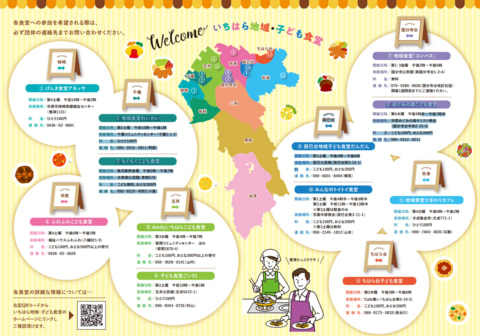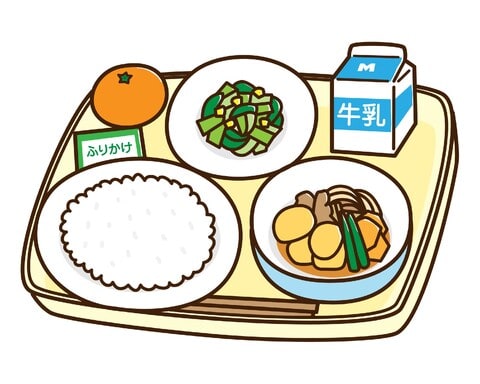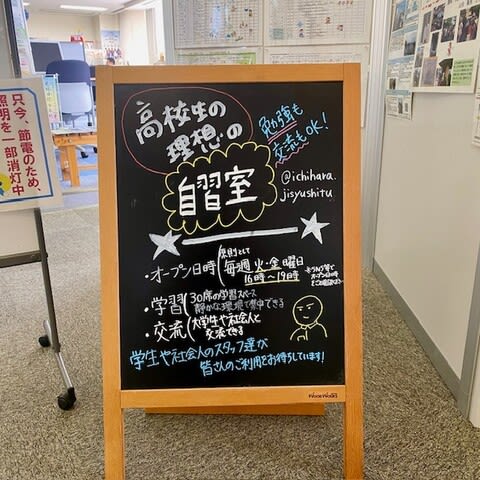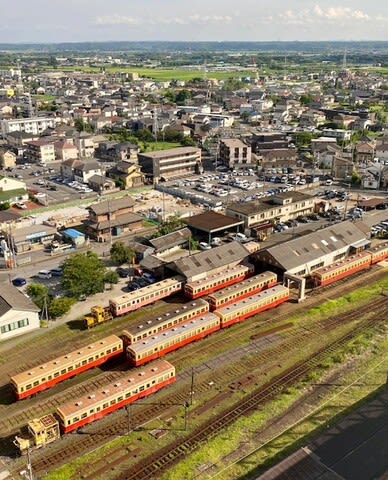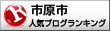先日、市原市を愛する若者たちが集まって活動をスタートさせた「いちはら部」の最終プレゼンが、サンプラザ市原で行われました。
驚くことに、市外・県外の若者支援の関係者も視察に訪れていました。

この夏の3日間、彼らは市原市が取り組む様々な施策に「ちょい足し」するというユニークな発想で、アイデアを練り上げてきました。
最終日のこの日は、市長や教育長をはじめ市職員も大勢駆けつけ、若者たちの発表に真剣に耳を傾けていました。
「国際交流をもっと身近に楽しみたい」
「若者向けに『エンジン03 in いちはら』の講座をデザインしたい」
「自信が持てる市原市にしたい」
彼らの純粋でまっすぐな言葉・・・いや~、眩しかった。。
プレゼンの後には、グループに分かれて市長たちと直接対話する時間も。
普段なかなか話す機会のない若者と行政が熱心に語り合う光景も感動的でした。



若者たちが自ら行動し、市原の未来を真剣に考える。
その熱い想いが、きっとこれからの市原市を動かす大きな力になるはずです。私たち大人は、それにちゃんと応えていかなければなりませんね。

「いちはら部」の活動はまだ始まったばかり。
ここから若者たちの手によって、どんな素敵なアクションが生まれていくのか、心から楽しみにしています!