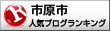今日は、市原市内の各地域で一斉に防災訓練が行われ、私は中央会場の辰巳台中学校へ足を運びました。


中学生の煙体験。

医療救護訓練。医師が運ばれてきた負傷者の重症度や緊急度によって優先度を決めていきます(トリアージ)。

接骨師による応急処置

こちら飲料メーカー伊藤園さんのブースでは、なぜか自動販売機の前に人だかりが・・・

電気がなくても、カギがなくても、無料で飲料が取り出せる「ライフライン・ベンダー」というタイプの自動販売機。
災害時に、このように手回しハンドルによる自家発電に切り替えることができます。私は今回初めて見ましたが、皆さんはご存知でしたか?

企業のCSR(社会貢献)の一環として、全国の公共施設などへの設置が進められているそうです。
そして災害救助犬の活躍、今年も見ることができました。

訓練後のワンちゃんに、お疲れさま!とナデナデ。

昨年は残暑が厳しい中で行われましたが、今年はむしろ肌寒いくらいでした。
訓練に参加した関係者や地域の皆さん、本当にお疲れ様でした!


中学生の煙体験。

医療救護訓練。医師が運ばれてきた負傷者の重症度や緊急度によって優先度を決めていきます(トリアージ)。

接骨師による応急処置

こちら飲料メーカー伊藤園さんのブースでは、なぜか自動販売機の前に人だかりが・・・

電気がなくても、カギがなくても、無料で飲料が取り出せる「ライフライン・ベンダー」というタイプの自動販売機。
災害時に、このように手回しハンドルによる自家発電に切り替えることができます。私は今回初めて見ましたが、皆さんはご存知でしたか?

企業のCSR(社会貢献)の一環として、全国の公共施設などへの設置が進められているそうです。
そして災害救助犬の活躍、今年も見ることができました。

訓練後のワンちゃんに、お疲れさま!とナデナデ。

昨年は残暑が厳しい中で行われましたが、今年はむしろ肌寒いくらいでした。
訓練に参加した関係者や地域の皆さん、本当にお疲れ様でした!