
All Photos by Chishima,J.
(コムクドリのオス2012年5月 以下アオバトを除きすべて 北海道中川郡池田町)
(NPO法人日本野鳥の会十勝支部報「十勝野鳥だより178号」(2012年9月発行)より転載 写真を追加)
開拓が入る前の十勝平野はカシワをはじめ、ミズナラ、センノキ、ハルニレ等の巨木に覆われていたらしい。しかし、今では帯広市街地の緑地面積が3%程度に過ぎないことからも察せられるよう、その大部分は失われてしまった。そんな往年の、巨木が生い茂る原野の片鱗を感じながら散策を楽しめるのが、池田町市街地に隣接する清見ヶ丘公園だ。
帯広から車で30分、またはJR池田駅から徒歩で20分の距離にある同公園は、池田市街地の東側に連なる丘陵地帯の一部で、公園内には樹齢300年を超えるというカシワの巨木が立ち並ぶ。両手を回してもとても抱きしめられない太さの幹と、その上部から力強く分岐する枝の数々からは、荘厳さと時の悠久さを十分実感できる。
同公園での探鳥は四季を通じて楽しむことができるが、一番のおすすめは初夏(5月中旬~6月上)。巨木が多いため、樹洞や木の割れ目も多いのであろう。コムクドリやキビタキ、ハリオアマツバメといった樹洞営巣性の鳥が多いのが特徴の一つだ。コムクドリを観察するのなら、葉が芽吹く以前の5月中・下旬が良い。黄金週間前後に夏鳥として渡来する本種は、渡来初期にはディスプレイや営巣場所をめぐる争い等のため活発に動き回る。「キュルキュルキュル…」という、ムクドリより高めの声を頼りに探せば、主に梢付近にその姿を見出すのはそう難しくない。ムクドリより一回り小さく、オスでは赤褐色や紫色が鮮やかな本種は意外にも気性が荒く、既に繁殖に入っているアカゲラと樹洞をめぐって争い、そこから追い出すことさえある。じっくり観察していれば、そんな場面に出くわすかもしれない。
ハリオアマツバメは、斜面の上にある駐車場付近が観察しやすい。「チルルルー…」というアマツバメよりやや低めの声と共に、鎌型の鳥体が高速で迫って来る。時には「シュッ」という羽音が耳を掠めることさえある。和名の由来となった、尾羽の先の針状の突起は高速で飛翔するので観察は難しいが、最近ではデジタルカメラの性能が大幅に向上したので、高速で撮影すれば画像で確認できることがある。本種は、私の生まれ育った関東地方平野部ではほとんど見られず、高山帯に赴いてようやく少数観察できる程度だったので、自宅付近で毎日のように観察できても、未だに有難味を感じてしまう。
虫を追いかけるハリオアマツバメ
2012年5月

留鳥の樹洞営巣種であるカラ類やゴジュウカラ、キツツキ類も勿論多く、6月下旬以降は巣立ったばかりのあどけない幼鳥を見ることも多い。年間を通してヤマガラを観察できるのも、ここならではだろう。南方系で照葉樹林を主たる生息地とし、十勝では少ない種だが夏にも少数が観察され、冬には分散個体も加わるのか、やや増えるようだ。ドングリを好む種なので、カシワの巨木が林立しているのが良いのかもしれない。繁殖期であればシジュウカラより更にテンポの遅い囀り、それ以外であれば「ニーニー」というハシブトガラより鼻にかかった地鳴きを意識して探すと良い。
ヤマガラ
2009年11月

樹洞の鳥といえば、ここはかつてフクロウで有名な場所であった。ここで撮影された雛や家族の写真を、今でもあちこちで見かける。しかし、近年では年に数回声が聞かれるだけで、繁殖の有無は不明である。多くのカメラマンが押し寄せ、巣立ち雛に張り付いて親鳥が給餌できない状況が何年も続いたらしい。中には昼間ほとんど動きのないフクロウの、動きのある写真を撮ろうと騒ぎ立てたり、花火(?)を焚いたりする輩までいたという。デジタルカメラの普及に伴って動物写真が簡単に撮れるようになり、動物への思いやりの欠片も抱けない人間が大手を振ってフィールドを闊歩してるのが、悲しいかな、昨今の現状である。どうか探鳥中に運良くフクロウに出会うようなことがあっても、深追いはしないで欲しい。
公園の北側に隣接して、池田清見温泉がある。ナトリウム‐塩化物強塩泉のしょっぱい温泉なのだが、おそらくそのためにここに飛来するのがアオバトだ。なぜか渡来初期の5月には見られないが、6月中旬以降、最大30羽ほどが温泉に隣接した公園内の沢に飛来する。葉が茂る時期なので直接確認できていないが、沢で飲水してナトリウムを摂取していると思われる。本種は海水を飲む行動が有名だが、鉱泉付近等での飲水も知られており、ナトリウムの摂取が生理的に必要と考えられている。葉が茂り、警戒心も強いため飲水を観察するのは難しいが、尺八のような声や上空を飛ぶ姿は8月頃まで楽しむことができる。
アオバトの飛翔(左がオス)
2011年7月 北海道白糠郡白糠町

公園はカラス類のねぐらにもなっており、8月中旬以降は数千羽のカラスがねぐら入りするのを日没前後に観察できる。冬にはカラス類に代わってトビがねぐらとして利用するようになり、冷え込んだ朝には午前9時を過ぎてもなお、多数のトビが巨木に群がる姿が見られる。
繁殖期は上で紹介した鳥にくわえて、ヒヨドリ、アカハラ、センダイムシクイ、コサメビタキ、アオジ、シメ、ニュウナイスズメ等を観察できる。公園で下草の手入れが行き届き林床が開けているためか、ウグイス、ヤブサメ、コルリ等は見られない。
秋から冬は葉が落ちるので留鳥のカラ類やキツツキ類が観察しやすくなり、キバシリやキクイタダキも姿を現す。清見温泉側の沢ではミソサザイもよく観察される。また、園内を走り回るエゾリスが目立つ季節でもある。
エゾリス
2009年11月

基本的には大樹を謳歌しながら身近な鳥を楽しむ、散策的バードウオッチングの場所であるが、ヤツガシラ、ヤマゲラ、シロハラ、ミヤマホオジロ等の記録もあるので油断は禁物だ。もっとも、そう書いている筆者もそれらを見た時は散歩中で、カメラを取って戻ってくるといなくなっていたというのが大半であるが…。
ヤツガシラ
2010年5月

アフターバードウオッチングの選択肢は多い。春秋にはガンカモ類や猛禽類で賑わう十勝川下流域は目と鼻の先であるし、渡り時期であれば十勝が丘展望台やまきばの家展望台で猛禽類や小鳥類を見るのも良いだろう。同公園内には児童公園やパークゴルフ場もあるのでファミリーでの探鳥にも向いており、その場合ワイン城や十勝エコロジーパーク等観光コースに繰り出すこともできる。池田町内には、もやしたっぷりのラーメンを堪能できる「再来」や、格安でカットステーキのランチを楽しめる「よねくら」等、飲食店も多い。清見温泉や十勝川温泉で湯に浸かるのもまた一興だ。
カシワの巨木茂る公園内
2008年12月

(2012年9月7日 千嶋 淳)










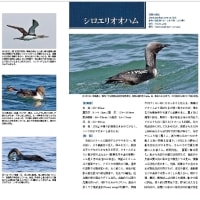
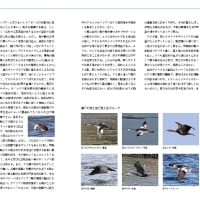
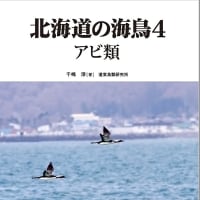







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます