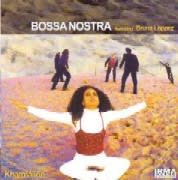一時期の大人気が嘘のように最近はすっかり身を潜めているイタリアのIrma Records。しかしやはり良いレコードというのは流行り廃りなんかと関係なく時を越えるもの、そんなわけでこの盤の紹介です。ブラジル生まれの女性ヴォーカリスト、Bruna Loppezを迎えて98年にリリースされた本作は彼らの2ndアルバム。ただ、この盤に関して言えば僕はむしろインストものの方が気に入っていて、たとえばイタリアからのアシッド・ジャズへの回答のようなA-3のLife辺りがツボだったりします。基本的にはクールなジャズ・ファンク~フュージョンなのだけれど、どことなくイタリアという土地特有のオシャレさなんかも伝わってきて、そこが僕にとってはUK産アシッド・ジャズにはない魅力かな?疾走感溢れるD-3のNastyもかなり好き。鮮烈なホーンがカッコよくて夜のドライブなんかにぴったりな気がします。さてさて、そんな本作で今もっとも旬だと思えるのがC-1のChico Desperado。こちらはBruna Loppezを迎えた歌モノですが、程よくオシャレでヨーロピアンなラテン・ジャズで、フロアの空気を一発で南国の香りを運んでくれそうな名曲です。ちなみに、Routine Jazzの最新作に収録された関係からか、安くてよくある盤のはずなのに最近都内ではあまり見ないような・・・。
いまだに店によっては多少高めに値段設定しているところもあるラッパーECDによる98年のクラブヒット。B-3のオリジナルもそこそこ悪くないのですが、何せこの盤でリミックスを務めるのは小西・須永の両レコード番長です。当然悪くなるはずはなく、どちらも共にOrgan b. SUITEに収録済。一瞬のアカペラの後に1,2,1,2,3,4!とPeddlersの声ネタ・サンプリングから始まるaudiomusica N°2 remixはSunaga t Experience名義の最初期ワークとしてはGemini IV Space Nova!と並び屈指の好ナンバー。ジャズボッサmeetsヒップホップと言った感じの軽快かつオシャレな曲に仕上がっています。中盤ではいるAsiana嬢のナレーションとも相まって極上のグルーヴを生み出しています。そしてメガミックス仕立てのthe Readymade All That Jazzは、Lester WilsonのLight My Fireをメインに持ってきつつ至るところに小ネタを散りばめた小西印のド派手チューン。桃井かおりやClementineと一緒にテープで聴いたのが懐かしくなります。文句なしに素晴らしい一枚。ちなみにこの曲はアナログが何枚か出ていますが一番本命なのはこの作品。まだ聴いたことない人やECDの存在を軽く見ている人は必聴です。もう古いかもしれないけれど、それでもオススメ盤。ただ高く買う必要がある盤ではないので1000円くらいで見つけたときに買いましょう。両ヴァージョンともインストでも充分使えます。
同じようなジャケットだらけで分かりにくいですが、レペゼン仙台GagleのトラックメーカーDJ Mitsu The Beatsによるシングルです。もともと彼の作る音はPlactice&Tactix(Soljazzmix)の頃から好きでしたが、ソロ作品出してからの人気は本当に凄いですね。ヒップホップ界に留まらずヨーロッパのジャズDJなんかにも受けているよう。さてさて、こちらはそのソロ・アルバムNew Awakeningのリミックス集から最近カットされた12インチで、僕にとっては本当に待望の1枚です。理由はA-2に独行Jazz道(SW Mix)が収録されているから。SWの名の通りサックスとドラムにSleep Walkerの面々が参加した完全生音一発録りによる最高のリミックスです。Sleep Walker勢ではありませんが、うねうねしたベース・ラインとメロウなエレピの音色も抜群。ハンガーによる独特のフロウも見事にマッチして素晴らしい一曲に仕上がっています。中盤でのエレピ・ソロからサックス・ソロも決まっていますね。これは文句なしにカッコいい。小林径氏による人気セレクトCDシリーズ、Routine Jazzの最新作にも収録されているようです。ヒップホップ好きよりもむしろクラブ・ジャズ好きに聴いてもらいたい渾身の一曲、アナログはいずれ完売してしまうと思うのでお早めにどうぞ。
少し紹介が遅れてしまったけれど、ブラジル繋がりで最近の新譜から。New World Records所属のヴォーカル&ギターのデュオ、Beretによる最新12インチ。これがなかなかに上々の仕上がり。A-1の「虹の迷路」は大人気Saigenjiとのデュエットで、瑞々しくもブラジリアン・フレーヴァー漂うポップス。ギターでFilo Machadoも参加しているそうです。そして注目はB-1のContrast(Samba De Froresta Remix)。リミックスを務めるのは須永辰緒氏です。しっとりブラジリアンで始まって徐々に加速、サビ前で一気にブレイクする展開は鳥肌モノ。相変わらず期待を裏切らない良い仕事してますね。太宰百合氏によるピアノも変わらず美しく繊細。この人の綺麗なピアノとこういう澄んだ女性ヴォーカルって本当によく似合います。それにしてもBeretってとても東京的なアーティストだと思うのは僕だけでしょうか?彼らと似たような雰囲気を持ったレーベル・メイトのOrange Pekoeなんかと比べても、より東京テイストが強く表れている気がします。それは歌詞にしろヴォーカルにしろ音作りにしろ、それこそ至るところにね。別にだからどうこうということもありませんが、少なくとも僕はオレペコよりもこちらの方が好み。都会っぽさを味わいたい人にオススメの一枚。売り切れる前に買いましょう。
大阪出身のバンド、アーガイルによる7インチ。たまたまD.M.R.で見かけて買ったので、このバンドのことはよく知らないですけど、曲聴く限り大阪のWack Wack Rhythm Bandみたいな感じなのでしょうか?A面ではタイトル曲=Swing Out Sisterの初期代表曲を激キャッチーかつポップにカヴァー。90年代初頭のピチカート・ファイブのような楽しくてオシャレな音作りが可愛いです。これだけでも満足なのですが、さらに素晴らしいのがB面に収録されたI Saw The Lightのカヴァー。このブログでも過去に紹介したトッド・ラングレンによるヴァージョンがオリジナルですが、東京では数年前にリリースされたReggae Disco Rockersによるラヴァーズ・カヴァーや、そのハウス・リミックスも大人気の定番曲。で、彼らのヴァージョンはと言うとフルートとピアノが美しく舞う爽快なジャズ・ボッサに仕上がっていてこれが文句なしに良いです。完全生音使様なので、ブラジルもののクラシックなんかと混ぜてかけても全く違和感がなさそう。原曲、R.D.R.ヴァージョンとはまた一味違う爽快なカヴァーで、僕の今の気分ではこれがベストかなと思います。少しクセのあるヴォーカルも良い感じだし、暑い夏に向けてたまにはこういう爽快な曲でクール・ダウンしましょう。
先ごろ再発されたRay Terraceによるヴァージョンがサバービア・クラシックスとして有名な曲の日本人アーティストによるカヴァー。元々は「君の瞳に恋してる」の作者として有名なFrankie Valliが2匹目の泥鰌を狙って作った曲だそうで、2曲とも本当によく似たメロディ・ラインなのですが、より込み上げるという点ではこちらの曲の方が上のような気がします。さてさてThe Fascinationsはヴァイブ奏者の渡辺雅美氏を中心としたジャズ・コンボ。実際にライブを見たこともあるのですが、本当に魔法のように上手くスティックを操ります。詳しいテクニック的なことは分からないですが超絶技巧の持ち主であることは確か。そんな彼のコンボがこの名曲をカヴァーするのですから悪いわけがないです。ソウルフルで美しい女性ヴォーカルを配することで、Ray Terraceヴァージョンよりもさらに込み上げ度と透明感が格段にアップ。フリーソウルという点ではこちらの方がよりイメージと近いかもしれません。あちらは基本的にかなり熱いラテンですからね。僕はラテンはあまり得意ではないのでRay Terraceは持っていないのですがこれは好きです。アナログでは7インチ限定なので、興味のある方はお早めにどうぞ。熱い夏を涼しく過ごしたい方にオススメ。
恵比寿のカフェTenemntのオーナーにしてフェンダー・ローズ奏者、猪野秀史氏による2ndシングル。Michael Jacksonのカヴァーでヒットした前作も悪くないけれど、個人的にはこちらに軍配が上がります。ここでカヴァーされてるユーゼフ・ラティーフのLove Theme From Spartacusはスピリチュアル・ジャズの古典として昔から知られている曲。個人的には数年前にイタリアのSchema RecordsからリリースされたQuartetto Modernoのヴァージョンが気に入っていますが、今回の猪野氏によるカヴァーもなかなかに秀逸な出来。若干テンポ早めのタフでヒップホップ的なビートの上に例の哀愁の主旋律がエレピで乗っかっています。これが程よく夜感漂うスモーキーな雰囲気でカッコいい。60年代のモーダルな雰囲気を現代風に解釈するとこうなると言った感じでしょうか?今作も前作同様ジャズ~アンダーグラウンド・ヒップホップとクロス・オーヴァーにヒットしそうな感じです。ちなみにカップリングのBlood Is Thicker Than Waterもなかなかの佳曲。さらにジャケットも洗練されていてかなり良い感じですね。おそらくまた完売となってしまうと思うので、興味があれば早めのお買い求めをオススメします。
この音楽に何て名前を付けよう?単なるジャズではないしテクノとも少し違う。クラブミュージックでないことは明らかだけれど、難解な現代音楽として片付けてしまうのも惜しい・・・。極端にエレクトロニクスを多用した無機質な曲があったかと思えば、完全にアコースティックでバップのマナーにのっとったオールド・ジャズもあったりして、その全てが違和感も完全になしで一枚のアルバムに収められていて、どことなくEsbjorn Svensson Trio辺りにも少し近い質感かもしれないです。クラブ・ジャズのシーンとは全く無関係に生まれてきた現在型のスピリチュアル・ジャズとでも言うのかな?バップっぽいM-4のSevensが特に気に入っているけれど、完璧に電子音楽で構成されたM-2のタイトル曲も捨て難いです。激パーカッシヴなM-5のCampbell Townもカッコいい。基本的にポップ志向はないので普通の人向けのアルバムとは言えないかもしれませんが、実験音楽なんかが好きな人は聴いてもいいかもしれないです。ちなみに未アナログ化でCDのみの音源となります。まぁこういうのはアナログのノイズなんかが入ってこないほうが成立しそうな音楽なので、それでも全然構わないですけどね。
久々に新譜系から。多分フィンランドのマルチ・プレーヤーだと思うのですがTeddy Rokが地元のマイナーレーベルに吹き込んだ一枚です。それを再発レーベルのWhat Musicがワールド・リリースしたみたい。ちょっと僕自身も情報が足りてないんで、この辺のことはうまく説明できないです。ごめんなさい。Five Corners QuintetやPovoを始めスカンジナビア半島周辺のジャズ・シーンは大変盛り上がっているのですが、まぁそのうちの一枚だと思ってもらえればいいです。ヴォーカルをフィーチャーしたA-2のFeelが新世紀のコズミック・ソウルという感じで素晴らしい。少しTwo Banks Of Four辺りを思わせるA-3のAskaa!という曲も気に入ってます。ヒップホップ的なアプローチを見せるB-1のDamn Straightもなかなかの佳曲。全体を覆うスピリチュアルで土着的なトーンの中に、ヨーロッパならではの気高さが隠れているような気がして捨て難い一枚。ソウル・ジャズ・ヒップホップと様々なジャンルのクロス・オーヴァー。Povoのアルバムよりはこちらの方が僕は好きかな。アルバム一枚繋がっているので通し聴きするのにも良いかと思います。最近のアルバムにありがちなLP2枚組でもないんで・・・。クラブプレイということを考えない場合、やっぱり一つのアルバムはLP1枚に収まっていた方が個人的には嬉しいです。
日本のみならず世界のクラブジャズ・シーンの原点とも呼べるべきUFOことUnited Future Organizationの1stアルバム。当時はアシッド・ジャズの括りで語られていたようですが、全体的に今聴いても全然古臭くない内容で、90年代初頭に既にこの音を完成していた彼らは紛れもない天才だと思います。少し調べてみたところ、これ以前に3枚の12インチからの寄せ集めアルバムみたいですが、普通にアルバム通して作品として成立しているのがまず凄い。そしてサンプリングという手法でここまでのアルバムを作り上げたというのも考えられないくらい凄い。特にMichel LegrandをサンプリングしたB-1のLoud Minorityのカッコ良さと言ったらこの上ないです。高速4ビートのジャズブレイクス。この曲に関してならばアシッドジャズっていうよりも初期Jazzanovaのようなフューチャージャズという形容の方がぴったり来る感じでしょうか?どことなくCaravelliなんかを連想させるし・・・。ひいき目に見てと言うことではなく、日本のクラブジャズのレベルというのはこの頃から既に世界でもトップレベルだったのですね。今のクラブでも全然通用しそうな内容です。レアな音源を捜すのもいいですが、こういう基本的な盤を聴いておくことも大切。そんなことを考えさせられます。ちなみに僕の持っているのは多分UKプレスのジャケ違い盤。今ならば安く買えるしオススメです。