
花見の風習は、奈良時代から平安時代にかけて、貴族たちの間で行われた花を見ながら歌を詠む会が「花見」の起源とされる。
今では、花といえば「桜」がもっともポピュラーだが、昔は、花といえば「梅」が人気だったとか。万葉集の時代、中国からの文化の影響で梅の花を主題に読んだ歌の方が、桜を読んだ歌よりも圧倒的に多かった。その後、中国からの遣唐使の廃止により、梅よりも日本固有の桜の花が好まれるようになった。
死生観とつながりそうな、あの桜の散る姿は、まさに日本人好みと言えるだろう。
今では、花といえば「桜」がもっともポピュラーだが、昔は、花といえば「梅」が人気だったとか。万葉集の時代、中国からの文化の影響で梅の花を主題に読んだ歌の方が、桜を読んだ歌よりも圧倒的に多かった。その後、中国からの遣唐使の廃止により、梅よりも日本固有の桜の花が好まれるようになった。
死生観とつながりそうな、あの桜の散る姿は、まさに日本人好みと言えるだろう。















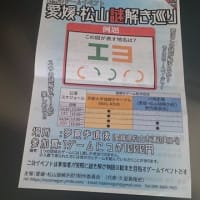



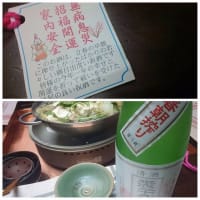
寒さから、段々と暖かくなり、そして、丁度いい気候の3月末から4月の初旬。
それにマッチしたのが桜というのではないかと思います。
人は、特に日本は、四季がはっきりしている国土。
この日本に生まれて幸せを感じることは多いと思います。
例えば、沖縄の宮古島では、2月に桜が咲いています。
そう考えると、季節がら、気候がいい時の花見は、最高ですね。
でも、基本的には、私は、きっと、花より団子なんでしょうけど・・。
東矢先生は、〇〇より、お酒でしょうか・・・。(笑)