「本光寺 お寺に咲く紫陽花」では紫陽花を中心としたフォトギャラリーだったので、今回は本光寺の像や建造物を中心にご紹介します。
本光寺は徳川と縁が深く、深溝(ふこうず)松平家の初代当主、松平忠定によって建立されました。
歴史を感じるものがたくさんあり興味深く見て歩きました。
-------------------- 本光寺 深溝松平の寺 --------------------

本光寺の山門にやってきました。

山門を通り右手を向くと、奥に階段が見えます。

三界万霊塔(さんかいばんれいとう)。
三界とは、無色界(むしきかい)、色界(しきかい)、欲界(よくかい)の三つを指します。
そしてこの塔は三つの世界、全ての精霊に対して供養することの大切さを示しています。

天妙院殿。
天妙院は島原藩主深溝松平家第9代当主、松平忠侯(ただこれ)の正室だった人で、近江彦根藩の第13代藩主、井伊直中(徳川家臣の名門、井伊家)の娘です。


階段を上っていきます。

門が見えてきました。

階段沿いに紫陽花もたくさん咲いています。


東御廟所(ひがしごびょうしょ)。
深溝松平家第6代~19代当主の墓所です。

深溝松平家は途中から島原藩(現在の長崎県)に移ったのですが、代々の藩主は亡くなると深溝松平家の菩提寺である本光寺に埋葬されました。
それぞれの墓所には家紋の「重ね扇」が印されています。



階段を下り、戻ります。

本光寺の本堂です。

梵鐘(ぼんしょう)。
「本光寺 お寺に咲く紫陽花」にも書きましたが徳川三代将軍家光公の勅命助成により、日本の平和、国民の厄難消除を願って、吉田城主松平忠利公が金、銀、銅を使って鋳造しました。
鐘には徳川家康公、家光公の名が記載されています。

深溝(ふこうず)松平家は松平一族の一つです。
徳川家康も元々は松平姓であり(家康は松平宗家)、深溝松平家はその分家となります。
先祖を遡ると徳川家康と共通の祖になります。

「感謝観音」。
「「ありがとう」という感謝の言葉が言えることは幸せなこと」とあり、たしかにそうだと思いました。
自分自身に対し、誰かが善意を向けてくれているということです。

肖影堂。

深溝松平家第5代当主、松平忠利の廟(びょう、墓所のこと)です。
忠利の忠は、徳川二代将軍、秀忠の前で元服した際に一字を貰っています。
忠利が吉田城主の間に家康は吉田城に5回宿泊、秀忠は4回宿泊、家光は3回宿泊していて、忠利がいかに将軍家から信用されていたかを示しています。



肖影堂の後ろに階段があります。

階段を上ると「願掛け亀」があります。
亀の襟首に賽銭が入ると願いが叶えられ、万年幸せになるとのことです。
賽銭を投げてみたら見事に襟首に入って嬉しかったです


深溝松平家7代当主、松平忠恕(ただひろ)の廟です。
歴代の藩主の中で最も多難だった人で、天災、地変、飢饉、凶作、普賢岳の噴火に見舞われ苦難の藩政だったとのことです。


御先祖堂。
西御廟所とも呼ばれていて、深溝松平家の礎を築いた初代~四代当主の墓所です。

初代は忠定、2代は好景(よしかげ)、3代は伊忠(これただ)、4代は家忠です。
案内板を見たら桶狭間の戦い(織田信長対今川義元)、三方ヶ原の戦い(徳川家康対武田信玄)、長篠の戦い(織田信長・徳川家康対武田勝頼)といった有名な合戦に参戦したことが書かれていました。
この人達が戦国時代に礎を築いてくれたおかげで深溝松平家は長く続いたということで、偉大な人達だと思います。
というわけで、本光寺を歩いたことによって深溝松平家のことを知りました。
徳川との深いつながりが分かり、梵鐘のように当時の将軍と直接関わるものまで見ることができて面白かったです
※フォトギャラリー館を見る方はこちらをどうぞ。
※横浜別館はこちらをどうぞ。
※3号館はこちらをどうぞ。
本光寺は徳川と縁が深く、深溝(ふこうず)松平家の初代当主、松平忠定によって建立されました。
歴史を感じるものがたくさんあり興味深く見て歩きました。
-------------------- 本光寺 深溝松平の寺 --------------------

本光寺の山門にやってきました。

山門を通り右手を向くと、奥に階段が見えます。

三界万霊塔(さんかいばんれいとう)。
三界とは、無色界(むしきかい)、色界(しきかい)、欲界(よくかい)の三つを指します。
そしてこの塔は三つの世界、全ての精霊に対して供養することの大切さを示しています。

天妙院殿。
天妙院は島原藩主深溝松平家第9代当主、松平忠侯(ただこれ)の正室だった人で、近江彦根藩の第13代藩主、井伊直中(徳川家臣の名門、井伊家)の娘です。


階段を上っていきます。

門が見えてきました。

階段沿いに紫陽花もたくさん咲いています。


東御廟所(ひがしごびょうしょ)。
深溝松平家第6代~19代当主の墓所です。

深溝松平家は途中から島原藩(現在の長崎県)に移ったのですが、代々の藩主は亡くなると深溝松平家の菩提寺である本光寺に埋葬されました。
それぞれの墓所には家紋の「重ね扇」が印されています。



階段を下り、戻ります。

本光寺の本堂です。

梵鐘(ぼんしょう)。
「本光寺 お寺に咲く紫陽花」にも書きましたが徳川三代将軍家光公の勅命助成により、日本の平和、国民の厄難消除を願って、吉田城主松平忠利公が金、銀、銅を使って鋳造しました。
鐘には徳川家康公、家光公の名が記載されています。

深溝(ふこうず)松平家は松平一族の一つです。
徳川家康も元々は松平姓であり(家康は松平宗家)、深溝松平家はその分家となります。
先祖を遡ると徳川家康と共通の祖になります。

「感謝観音」。
「「ありがとう」という感謝の言葉が言えることは幸せなこと」とあり、たしかにそうだと思いました。
自分自身に対し、誰かが善意を向けてくれているということです。

肖影堂。

深溝松平家第5代当主、松平忠利の廟(びょう、墓所のこと)です。
忠利の忠は、徳川二代将軍、秀忠の前で元服した際に一字を貰っています。
忠利が吉田城主の間に家康は吉田城に5回宿泊、秀忠は4回宿泊、家光は3回宿泊していて、忠利がいかに将軍家から信用されていたかを示しています。



肖影堂の後ろに階段があります。

階段を上ると「願掛け亀」があります。
亀の襟首に賽銭が入ると願いが叶えられ、万年幸せになるとのことです。
賽銭を投げてみたら見事に襟首に入って嬉しかったです



深溝松平家7代当主、松平忠恕(ただひろ)の廟です。
歴代の藩主の中で最も多難だった人で、天災、地変、飢饉、凶作、普賢岳の噴火に見舞われ苦難の藩政だったとのことです。


御先祖堂。
西御廟所とも呼ばれていて、深溝松平家の礎を築いた初代~四代当主の墓所です。

初代は忠定、2代は好景(よしかげ)、3代は伊忠(これただ)、4代は家忠です。
案内板を見たら桶狭間の戦い(織田信長対今川義元)、三方ヶ原の戦い(徳川家康対武田信玄)、長篠の戦い(織田信長・徳川家康対武田勝頼)といった有名な合戦に参戦したことが書かれていました。
この人達が戦国時代に礎を築いてくれたおかげで深溝松平家は長く続いたということで、偉大な人達だと思います。
というわけで、本光寺を歩いたことによって深溝松平家のことを知りました。
徳川との深いつながりが分かり、梵鐘のように当時の将軍と直接関わるものまで見ることができて面白かったです

※フォトギャラリー館を見る方はこちらをどうぞ。
※横浜別館はこちらをどうぞ。
※3号館はこちらをどうぞ。











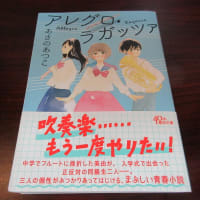








記事から話は少々ずれるけど、何か所かの立派な墓所を見て、確かに生きていらした形跡と言うものが伝わりました。
現代は、お墓問題が色々あり、お墓も多様化していて、持たないお家もあったりしますが、このように、ずっと形があるのは、すごい事だなと感じます。
お墓問題では、お墓自体がなく、手を合わせる場所に行くと亡くなった方の写真が自動的に出てくるというのが印象的です。
お墓を建てるにはかなりのお金が必要なので、段々とそんな家も増えていくのかも知れないです。