牛丼「価格戦争」に乗り遅れ 吉野家巻き返しへの遠い道のり
7月23日7時12分配信 J-CASTニュース
-------------------------------------------
牛丼チェーン各社が値下げ合戦を繰り返す中、吉野家も2010年7月下旬から牛丼を270円に値下げする。あくまで「期間限定」の価格というが、ゼンショー、松屋との「価格戦争」に乗り遅れ、後手後手が続いている。
2010年7月20日、吉野家が7月28日から8月3日までの期間、「夏の牛丼祭」を実施すると発表した。期間中、対象メニューが110円引きとなるキャンペーンで、牛丼並盛りの場合、通常380円が270円になる。沖縄県内の店舗など一部を除いて、全国の吉野家店舗で行う。
■ゼンショー、松屋は何度も値下げキャンペーン実施
牛丼チェーン業界では09年末から値下げ合戦が続いている。それまで大手牛丼チェーンの最安値はすき家の330円だったが、12月3日、松屋が320円に値下げ。その直後の7日には、すき家が更に安い280円に改訂した。
その後は、松屋とすき屋が散発的に値下げキャンペーンを実施。10年春から7月にかけて牛丼が250円になるキャンペーンを何度も繰り返してきた。
一方の吉野家はというと、4月に一度270円になるキャンペーンを実施したものの、基本的には静観、380円で売り続けてきた。10年春以降、すき家のゼンショーが既存店での売上が前年度比1~2割増、松屋が2~6%増を記録する中、吉野家は1~2割減と、「1人負け」の状態が続いていた。
今回の値下げキャンペーンについて、吉野家の広報担当者は、「他社との競争で値下げするのではない」と強調する。8月は一年の中でも客足が伸びる。その時期に吉野家で牛丼を食べ、「やっぱり牛丼は吉野家」だと再認識してもらいたいのだという。
「春のセールは新聞でも取り上げられ大きく盛り上がりました。前年度の売上は超えられませんでしたが、手応えは感じましたし、多少回復もしました。今回も盛り上がれば」
と話す。ただ、値下げといってもあくまで「期間限定」。キャンペーン終了後はもとの380円に戻るが、通常価格の値下げは「考えていません」としている。

■「客の流れが既にゼンショー、松屋の方にいっている」
吉野家の値下げキャンペーンについて、外食産業に詳しい経済ジャーナリストの中村芳平さんは「どれだけ離れた客を戻せるか。ゼンショーの安売りがボディブローのように効いてきている」と指摘する。客の流れが既にゼンショー、松屋の方にいっており、吉野家が取り戻そうとしても難しい、と見る。
「吉野家に固定ファンがいるのは確かですが、他と50~100円も違ったら行かなくなります。それに、最近はすき家も味が良くなっています。吉野家は、価格通りの価値があるから値下げはできないとしていますが、本当に吉野家の牛丼は優れているのか。固定ファンがいるからといって、それに甘えて殿様商売をしてはいけません」
吉野家HDは、10年2月期の連結決算で、過去最悪となる最終損益89億円の赤字を記録。7月8日に発表された3~5月期連結決算でも、最終赤字7億円だった。今後の業績によっては、4月から吉野家社長を兼任している、吉野家HDの安部修仁社長の責任問題に発展する可能性も指摘されている。
「今回の値下げにしても、後手後手な印象。長期的な戦略がなく、経営に迷いがあるように見えます。価格戦争に参加するならチマチマやるのではなく、とことんやればいいんです。今度も負けるようだと、株主も黙っていないかも知れません」
--------------------------------------------
完全に作戦負けですね。
予定変更を余儀なくされた、一か八かの苦し紛れの勝負手(¥380→¥270!)を放ったもののそれならこちらは¥250円と見事に反撃されて勝負手が宙に浮く。
¥270の勝負手も、多分、勝算はなかったのでは。
そして、消費者の称賛もなかったのでは。
後手後手。大局観の欠如。
判断力も直観力も足りなかった。
まだ投了には至ってないのだろうけど、
「他社との競争で値下げするのではない」
「やっぱり牛丼は吉野家」だと再認識してもらいたいのだという。
という理屈も説得力がない。
パイオニアでもあり、完璧な“吉牛”ブランドを築き上げていた老舗の実力者も、
ここにきて指し手に一貫性がない。
しかし、不況で消費が冷え込み、何でもかんでも低価格路線というのはわかるのだけど、
こういう争い、見ちゃいられない。
もちろん、安くなるのはありがたい、という側面は否定しないけれど、なんだかなあ、と思ってしまうし、皆で自分を貶めている、業界を疲弊させているだけのように思う。
そこまでやる必要が果たしてあるのか。
価格を主戦場にしないで、他の部分で戦えないのか。
価格ではなく、肉の質や味付けは絶対に負けないという作戦。
あのチェーンは、店員のサービスが他のチェーンとまるで違うという作戦。
企業イメージがいいので応援したい、という作戦。
まだまだいくらでもあるはず。
最近読んだこの本。
こんな一節があります。
------------------------------------------
資本主義だからしっかりもうけていい。
しかしもうけるだけではいけない。
資本主義はお金をまわすこと。お金を止めないことがルールだ。
お金だけをまわしていると、資本主義はギスギスしだす。冷たくなる。
だから、お金をまわすと同時に、あたたかさをまわす必要がある。
ウェットな資本主義のオキテはお金とあたたかさをまわし続けること。
これを守っていけば経済は元気になる。同時にあたたかな日本になる。
日本人でいることに誇りが持てるようになる。
--------------------------------------------
消費者だって本来の意味では求めていない低価格の争いに没頭して、
結果として、企業の体力もすり減らす。
つまり社員の生活もギスギスしだす。
ちゃんと将棋教室にでも通って、大局観とか判断力を養う必要があるんじゃないでしょうかね。
7月23日7時12分配信 J-CASTニュース
-------------------------------------------
牛丼チェーン各社が値下げ合戦を繰り返す中、吉野家も2010年7月下旬から牛丼を270円に値下げする。あくまで「期間限定」の価格というが、ゼンショー、松屋との「価格戦争」に乗り遅れ、後手後手が続いている。
2010年7月20日、吉野家が7月28日から8月3日までの期間、「夏の牛丼祭」を実施すると発表した。期間中、対象メニューが110円引きとなるキャンペーンで、牛丼並盛りの場合、通常380円が270円になる。沖縄県内の店舗など一部を除いて、全国の吉野家店舗で行う。
■ゼンショー、松屋は何度も値下げキャンペーン実施
牛丼チェーン業界では09年末から値下げ合戦が続いている。それまで大手牛丼チェーンの最安値はすき家の330円だったが、12月3日、松屋が320円に値下げ。その直後の7日には、すき家が更に安い280円に改訂した。
その後は、松屋とすき屋が散発的に値下げキャンペーンを実施。10年春から7月にかけて牛丼が250円になるキャンペーンを何度も繰り返してきた。
一方の吉野家はというと、4月に一度270円になるキャンペーンを実施したものの、基本的には静観、380円で売り続けてきた。10年春以降、すき家のゼンショーが既存店での売上が前年度比1~2割増、松屋が2~6%増を記録する中、吉野家は1~2割減と、「1人負け」の状態が続いていた。
今回の値下げキャンペーンについて、吉野家の広報担当者は、「他社との競争で値下げするのではない」と強調する。8月は一年の中でも客足が伸びる。その時期に吉野家で牛丼を食べ、「やっぱり牛丼は吉野家」だと再認識してもらいたいのだという。
「春のセールは新聞でも取り上げられ大きく盛り上がりました。前年度の売上は超えられませんでしたが、手応えは感じましたし、多少回復もしました。今回も盛り上がれば」
と話す。ただ、値下げといってもあくまで「期間限定」。キャンペーン終了後はもとの380円に戻るが、通常価格の値下げは「考えていません」としている。

■「客の流れが既にゼンショー、松屋の方にいっている」
吉野家の値下げキャンペーンについて、外食産業に詳しい経済ジャーナリストの中村芳平さんは「どれだけ離れた客を戻せるか。ゼンショーの安売りがボディブローのように効いてきている」と指摘する。客の流れが既にゼンショー、松屋の方にいっており、吉野家が取り戻そうとしても難しい、と見る。
「吉野家に固定ファンがいるのは確かですが、他と50~100円も違ったら行かなくなります。それに、最近はすき家も味が良くなっています。吉野家は、価格通りの価値があるから値下げはできないとしていますが、本当に吉野家の牛丼は優れているのか。固定ファンがいるからといって、それに甘えて殿様商売をしてはいけません」
吉野家HDは、10年2月期の連結決算で、過去最悪となる最終損益89億円の赤字を記録。7月8日に発表された3~5月期連結決算でも、最終赤字7億円だった。今後の業績によっては、4月から吉野家社長を兼任している、吉野家HDの安部修仁社長の責任問題に発展する可能性も指摘されている。
「今回の値下げにしても、後手後手な印象。長期的な戦略がなく、経営に迷いがあるように見えます。価格戦争に参加するならチマチマやるのではなく、とことんやればいいんです。今度も負けるようだと、株主も黙っていないかも知れません」
--------------------------------------------
完全に作戦負けですね。
予定変更を余儀なくされた、一か八かの苦し紛れの勝負手(¥380→¥270!)を放ったもののそれならこちらは¥250円と見事に反撃されて勝負手が宙に浮く。
¥270の勝負手も、多分、勝算はなかったのでは。
そして、消費者の称賛もなかったのでは。
後手後手。大局観の欠如。
判断力も直観力も足りなかった。
まだ投了には至ってないのだろうけど、
「他社との競争で値下げするのではない」
「やっぱり牛丼は吉野家」だと再認識してもらいたいのだという。
という理屈も説得力がない。
パイオニアでもあり、完璧な“吉牛”ブランドを築き上げていた老舗の実力者も、
ここにきて指し手に一貫性がない。
しかし、不況で消費が冷え込み、何でもかんでも低価格路線というのはわかるのだけど、
こういう争い、見ちゃいられない。
もちろん、安くなるのはありがたい、という側面は否定しないけれど、なんだかなあ、と思ってしまうし、皆で自分を貶めている、業界を疲弊させているだけのように思う。
そこまでやる必要が果たしてあるのか。
価格を主戦場にしないで、他の部分で戦えないのか。
価格ではなく、肉の質や味付けは絶対に負けないという作戦。
あのチェーンは、店員のサービスが他のチェーンとまるで違うという作戦。
企業イメージがいいので応援したい、という作戦。
まだまだいくらでもあるはず。
最近読んだこの本。
 | ウエットな資本主義(日経プレミアシリーズ)鎌田 實日本経済新聞出版社このアイテムの詳細を見る |
こんな一節があります。
------------------------------------------
資本主義だからしっかりもうけていい。
しかしもうけるだけではいけない。
資本主義はお金をまわすこと。お金を止めないことがルールだ。
お金だけをまわしていると、資本主義はギスギスしだす。冷たくなる。
だから、お金をまわすと同時に、あたたかさをまわす必要がある。
ウェットな資本主義のオキテはお金とあたたかさをまわし続けること。
これを守っていけば経済は元気になる。同時にあたたかな日本になる。
日本人でいることに誇りが持てるようになる。
--------------------------------------------
消費者だって本来の意味では求めていない低価格の争いに没頭して、
結果として、企業の体力もすり減らす。

つまり社員の生活もギスギスしだす。

ちゃんと将棋教室にでも通って、大局観とか判断力を養う必要があるんじゃないでしょうかね。











 線路は続く~よ、ど~こまでも~~
線路は続く~よ、ど~こまでも~~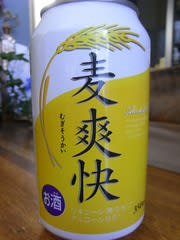


 小さいとき、オヤジの仕事が弁当屋だというのが恥ずかしくて言えなかった。
小さいとき、オヤジの仕事が弁当屋だというのが恥ずかしくて言えなかった。 上場してても、大きな会社でも、社員は皆暗く覇気がなく、つまらなそうにしている会社もある。
上場してても、大きな会社でも、社員は皆暗く覇気がなく、つまらなそうにしている会社もある。




 売り上げは気にしない。目先の数字を追っていては成長できない。
売り上げは気にしない。目先の数字を追っていては成長できない。


 独善的
独善的


 話を聞いてるだけで、刺激も十分、とっても晴れやかな気分になりました。
話を聞いてるだけで、刺激も十分、とっても晴れやかな気分になりました。





